DISC REVIEW
T
-

-
tacica
aranami
結成15周年を迎えたtacicaによる2020年のリリース第1弾は、TVアニメ"波よ聞いてくれ"のOPテーマ「aranami」と、8月17日に開催予定の結成15周年記念公演のテーマ曲とも言える「象牙の塔」の2曲を収録。アンセミックなロック・ナンバーの前者は誰もが感じていることを改めて言葉にしたような、ある意味tacicaらしからぬストレートなメッセージが意表を突きながら、最後の最後に溜飲が下がるパンチラインはやはり彼らならでは。一方、ホーンも使ったオーケストラルなアレンジが魅力の後者は、歌い始めのパンチラインでいきなりリスナーの気持ちを掴む。節目に謳う、そして、未来に繋げるバンドとしての所信表明。タイトルを含め、15年の活動に裏打ちされたバンドの矜持が窺える。
-

-
tacica
panta rhei
打ち鳴らすリズムとともに生命の躍動を謳い上げる7thアルバム。フル・アルバムとしては、『HEAD ROOMS』以来3年ぶりとなる。2018年にリリースした2枚の両A面シングルの4曲を含む全12曲を収録。80年代のUKロックや90年代のグランジ/オルタナを連想させるギター・ロックをバックグラウンドに、打ち込みのドラムやピアノも使って、引き続き新たなサウンドメイキングを追求しており、それが質実剛健、あるいはストイックという印象になるところが彼らならでは。そして、日々粛々と暮らす人々の気持ちを鼓舞する言葉は、安っぽい応援歌にはない思慮深さを持つ。アルバムを締めくくる「latersong」の"無い知恵 振り絞って行け"という一節が耳に残る。
-

-
tacica
煌々/ホワイトランド
『ordinary day/SUNNY』から5ヶ月ぶりにリリースする両A面シングル。打ち鳴らすリズムとアコースティック・ギターのリフがループするなかで生きる歓びを歌い上げる「煌々」は、バンド・サウンドにおける挑戦もさることながら、奇をてらわずにわかりやすい言葉で綴った歌詞も聴きどころ。"当たり前のことしか言ってない"と猪狩翔一(Vo/Gt)は言うが、その当たり前のことに気持ちを鼓舞される人は多いはず。轟音で鳴るギターがグランジ/オルタナを思わせる「ホワイトランド」も故郷の友人のために作ったという意味でtacicaらしからぬ(?)ストレートな歌詞が聴きどころとなっているが、「煌々」同様、何を歌っているかわかりやすいぶん、猪狩の言葉(の選び方)の強さを改めて印象づけるものになっている。
-

-
tacica
ordinary day/SUNNY
2017年8月にリリースしたミニ・アルバム『新しい森』同様、サポート・メンバーを迎え、4人編成のバンドとして、さらなる可能性を追求した2年ぶりのシングル。アコースティック・セットとバンド・セットの2部構成で行うツアーにインスパイアされたということで、音数を削ぎ落したバラードの「ordinary day」とロック・ナンバーの「SUNNY」を収録。命の炎が燃え盛る様を表現する、うねるようなドラマチックな演奏は、普通の日々がいかに尊いものかというストレートなメッセージであるとともに、バンドにとって大きな挑戦だったという。キラキラとした音色を纏った「SUNNY」は、ライヴ映え必至のアンセミックな曲調と、思考が絡み合うような歌詞のアンバランスさが、メンバーいわく"THE tacica"な1曲だ。
-

-
tacica
新しい森
1曲目の「mori」にその片鱗が窺えるように、強烈なビートが随所に散りばめられ研ぎ澄まされた楽曲たちを聴いて、新たにtacicaというバンドに興味を抱く人も多いだろう。前作『HEAD ROOMS』より1年5ヶ月ぶりのリリースとなるミニ・アルバムは、2017年3月から4月にかけて実施された2ndアルバム『jacaranda』再現東名阪ツアー[TIMELINE for "jacaranda"]のツアー・メンバーである野村陽一郎(Gt)が共同プロデュースを担当、ドラマー・中畑大樹(syrup16g)も参加しており、正式メンバーの猪狩翔一(Vo/Gt)、小西悠太(Ba)と共に"4人のtacica"で鮮やかに血を通わせた作品となっている。「YELLOW」、「youth」といったメッセージ・ソングがその分厚いサウンドに支えられてよりリアルに耳に飛び込んでくる。
-
-
tacica
HEAD ROOMS
彼らにとっては音楽を鳴らすことと自らの"生"と向き合うことはイコールなのだろう。tacicaというバンドは、人間が生きていく中で出会う光と影を一貫して歌い続けてきた。その本質は変わらないが、本作はいつになく晴れやかな表情をしている。その理由はまず、このバンドにしてはアッパー・チューンの多いアルバムだから。そして何より、結成11年目を迎えたバンドの風通しの良さを体現するように楽曲の自由度が増しているから、であろう。だから何よりも先に、サウンドに漲るプリミティヴな生への欲求が飛び込んでくる印象がある。自主企画ツアー"三 大博物館"のテーマ・ソング「サイロ」や、インディーズ期の楽曲「Butterfly Lock」も収録した6枚目のフル・アルバム。
-
-
tacica
newsong e.p.
tacicaの2012年第一声、再生ボタンを押し数秒待つ。そこから流れ出したのは、彼らの持ち味とも言える、3ピースという最小限の構成から無限の広がりを見せるバンド・アンサンブルではなかった。だがヴォーカル猪狩翔一の言葉とギター、そして叙情的なメロディが、間違いなくtacicaのものであると証明する。「wondermole」で非常に緩やかに幕を開け、今作の表題曲であり彼ら初のタイアップ曲である「newsong」で一気に加速する。彼らは決して綺麗な言葉の羅列で世界を彩ろうとはしない。今まで以上にシンプルで緻密に組み合わされた音の構成。そこに軽快なメロディを乗せ、焦燥感に満ちた言葉を歌い上げる。それは決して開き直りではなく、彼らの"決意"だ。
-
-
tacica
命の更新
昨年4月、ドラム・坂井俊彦の急病によりツアーの全公演を中止。9月に退院し、リハビリと制作活動を同時進行しながら活動していたtacicaが遂に本格始動。"tacica 復活"の言葉を掲げ届けられたのは、生きるという行為そのものに焦点を当てた一曲。随所で歌われるのは"体じゃ足りない位 生きて""両眼じゃ足りない位 夢を見ても足りない位 生きて"という強い想い。だが、こうも言う。しかし現実はどうだ、その想いとは裏腹に小さなことに囚われてばかり。人を、街を、悪を嫌い、結果自分が嫌いになって...自問自答と自己嫌悪の繰り返し。日々虚しい存在証明を繰り返すばかりだ。だが、そうやってそれでも生きていたいと、僕は僕を肯定したいと懇願することこそ生きるということなのだとtacicaは貴方を肯定してくれる。
-

-
TAHITI 80
Ballroom
来年デビュー15周年を迎えるフランスのポップ・マエストロ・バンドの前作から約3年半ぶり、通算6作目となる新作アルバム(日本先行リリース)。全編に亘りリバーブがかかり奥まった定位から聴こえてくるヴォーカル、Xavier Boyerの声は一聴すると女性のようにも聴こえるし、80年代のシンセ・ポップを彷彿とさせる音作りが懐かしくもあり新鮮でもある。ダークで妖しげなメロディの「The God Of The Horizon」、ゆったりと時が流れるようなドリーミー・ポップ「Solid Gold」など時代も性別も超越して理屈抜きで楽しめる、じっくり聴いてほしい極上のポップ・アルバム。2013年のFUJI ROCK FESTIVALで彼らを目撃したファンは必聴。
-

-
TAIJI at THE BONNET
ROCK STAR WARS
佐藤タイジ(Vo&Gt)、ウエノコウジ(B)、阿部耕作(Dr)、うつみようこ(Cho&Gt)、奥野真哉(Key)の5人から成るTAIJI at THE BONNETは、3月11日の震災から本格的に動き出し、ついにアルバムがリリースとなる。メンバーそれぞれのキャリアが長いこの5人が放つバンド・マジックは、驚くほど新鮮で瑞々しい。暴れだすギターとうねりをあげるベース……“ロック”というシンプルなキーワードから発するエネルギーの凄み。けれどどこまでもハッピーで自然と笑顔がこぼれるサウンド。大人が本気で“遊ぶ”とこんなにもカッコいいのだ。ロックとは何なのか、希望って何なのか……ストレートに芯の通ったロックがここにある。今届くべき音がギュッと詰まった1枚。
-

-
takekings
Case of takekings
FoZZtoneのギタリスト、竹尾典明が昨年秋に活動をスタートさせたソロ・プロジェクト、takekings。初の作品は、ソングライター/フロントマンとしての新たな魅力を放っているのはもちろん、ギタリストであるという情熱と誇りが音となって溢れ出た濃厚な、ロック"ギター"アルバムになった。エレクトリック/アコースティック・ギターを駆使して、歌やメロディの繊細な柔らかさを活かし、美しく煌びやかに縁どるプレイもあれば、ドライヴ感のあるリフと多彩なフレーズでダイナミックな音のタペストリーを紡ぎ上げてくる。心地良い緊張感で聴く者の時を掴んで奪っていく、そのパワーが圧巻。choro(Jeepta/Gt)、渡邉紘(プラナリア/HIGHGINTONIC006/Ba)、哲之(ジン/Dr)という布陣での、カロリー高めのアンサンブルも聴き応えあり。
-

-
THE TAKEOVER UK
Running With The Wasters
輸入盤のみで脅威の売り上げを記録した期待の新人ロックンロール・バンドTHE TAKEOVER UKの日本盤がいよいよ登場だ。ストレートなパワー・ポップ・サウンドにしゃがれた歌声に元気一杯の「シャラララ」コーラス。シングルである「Ah La La」は早くもインディ・アンセムの香りが漂う。思い出すのはデビュー当時のSUPERGRASSやTHE FRATELLIS。個人的には、この手のがむしゃら疾走系サウンドには滅法弱い。二人のソング・ライターが織りなすメロディは何処か懐かしさを感じさせ暖かい。新たな僕等バンドの登場です。
-

-
THE TALLEST MAN ON EARTH
The Wild Hunt
スウェーデン出身のSSWの2ndアルバム。初期のBob Dylanとも比較される事の多い彼の音楽はカントリー・フォーク・ギターと耳に残る特徴あるそのしゃがれた歌声ととてもシンプルなものだが、聴き流すという事が出来ないとても説得力のある音楽だ。何かをしながら聴く心地いいBGMとして機能する音楽もあるが、このアルバムにおいてはしっかりと向き合って聴くことをおススメしたい。さらっと流れる様な美しいアルペジオと繊細なメロディを奏でながらも、彼の楽曲からは聴くものに何か伝えようとする情熱や物語がこれでもかと溢れ出している。生まれながらにしてのシンガー・ソング・ライターというのは彼みたいな才能をもった人物のことを言うのだろう。
-
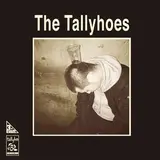
-
The Tallyhoes
Wake me up!
"ポップとロックンロール"を宿命に掲げるThe Tallyhoes。都内のライヴハウスを中心に活動してきた彼らが結成から3年半、ついに完成させた6曲入りの全国流通盤。ロックンロール・リヴァイヴァルに影響を受けているからって、決して頑固一徹なコワモテのバンドではない。メロディを重視しているというだけあって、ツイン・ヴォーカルやハーモニーを活かしたポップ・ソングの数々は、ロックンロ-ルを装いながら、その背後に幅広いバックグラウンドがあることが窺える。この3人組、なかなかのポップ/ロック・マニアらしい。ガレージ・ナンバーの「I'm OK!」から聴き始め、ソウルっぽいラストの「秘密のファンタジー」を聴き終わるときには、誰もがこのバンドに対する見方を改めるだろう。
-
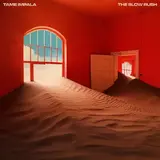
-
TAME IMPALA
The Slow Rush
奇才、Kevin Parker(Vo/Gt)率いるオーストラリアのサイケデリック・ロック・バンドがバレンタインデーに新アルバムをドロップ。数々のフェスでヘッドライナーを務めただけでなく、昨年は結婚し、公私共に充実していたKevinが、今作でもすべての楽器を演奏しているほか、ミックスやプロダクションも兼任している。細かいことはいろいろやっているのに、テクニカルな印象というよりは、80'sっぽいアナログなシンセ・サウンドの温かみや、自然と引きずり込まれるような根源的なリズムが印象的。才能が溢れ出すぎて怖いけど、それがちっとも嫌味じゃない、ナチュラルで我が道を行く雰囲気もすごい。TAME IMPALAの真骨頂とも言えるアートを超えたポップの世界をご堪能あれ。
-

-
TAMTAM
Strange Tomorrow
ダブ・バンドとしてのプライドを確固たるものにしながら、ダブ・バンドとしてできることを開拓してきたTAMTAM。フル・アルバムにはその軌跡が詰まっている。爆発の前のカオスと、新しい空気が吹き込んで覚醒するカタルシスとを猛スピードで繰り返すサウンドに引き入れられ、Kuroの歌うエモーショナルに、かつ自由に音の中で飛びまわったり、たゆたうようなヴォーカルに圧倒される。美しく、スケール感のあるサウンドながら、終始、ある種の緊張感・緊迫感を宿していて、その"何かが起こっている"感じにがっちりと心を掴まれ、揺さぶっていく、刺激的なアルバムだ。ディープで憂いのあるトーンながら、クリエイティヴィティや心の奥底の思いを活性していくかのような感覚が、湧き起こってくる、そんな重厚感がある。
-

-
TAMTAM
For Bored Dancers
洪水のようなギター音と前のめりに煽るビートではじまるTrack.1「クライマクス」。まずこの圧倒的な音でブラックホールのようにリスナーを引き込んでいくアルバムになっている。そして引っ張り込まれた先に広がるのは甘美な世界。ピアノの柔らかな音色を基軸にしたレゲエ・チューン「シューゲイズ」や、フリーキーで万華鏡的コラージュ感のあるダンス・ミュージック「フリー」など、様々なステップを踏むリズムが流れ、変わりゆく景色の中をたゆたうようにKuroのヴォーカルがのっていく。刻むビートは細やかで高揚感があり、しかしそのタイム感は午睡に溶け込んでいく時のような、心地好さがある。夢とうつつをシームレスに繋いで、音の揺りかごに乗せて揺さぶるアルバム。切なさと懐かしさを湛えた歌心がまたいい。
-

-
TANGO IN THE ATTIC
Sellotape
なるほど、スコットランドのVAMPIRE WEEKENDと称されるのも頷ける。カラフルでチャーミングな楽曲づくしのこのアルバムは、やはり全体を通してNYブルックリンあたりのインディー・ロック――特にANIMAL COLLECTIVE以降とでもいうべき、肉感的なビートを搭載したサウンドを聴かせてくれる。前作以上に幅が広がった作風で新しさはないけれど、瑞々しさや躍動感に満ちたトライバルなビートは、一時のブルックリンの盛り上がりに興奮した人なら、たまらないはず。シーンの隆盛が激しい今、時代を占うような作品ではないが、オモチャ箱をまさぐる様な音の戯れにウキウキして聴けてしまう作品だ。今年はアニコレ、GRIZZLY BEAR、MGMTなどかつてのトレンドを牽引したアーティストがリリースする。さて、インディー・ロックの今後はどうなるだろう?
-

-
The Taupe
セレンテラジン
"FUJI ROCK FESTIVAL '16"の"ROOKIE A GO-GO"に出演したこともあり、注目されている男女混合4人組オルタナティヴ・バンド初の全国流通盤となる1stフル・アルバム。自由な発想とそれを実現する音作りのアイディアが詰まった作品で、その表現力の豊かさは分け隔てなくジャンルに捉われないで音楽を聴いているであろうことが窺える。リード・トラック「GORILLA GORILLA GORILLA」では、もはや言語さえもリズムの一部と化している。曲ごとに凝ったアレンジのうえ、「テンプシーコーラ」や「テレサシティ」で聴ける男女ツイン・ヴォーカルも特徴的で、固定されたイメージを持たせないために飽きることがなく、ハマッたら何度も聴きたくなる底なし沼的な魅力のあるバンドだ。
-
-
Taylor Locke
Time Stands Still
元ROONEYのギター&ヴォーカル、Taylor Lockeの1stソロ・アルバム。2010年以降ROONEYの活動が休止状態になり、サイド・プロジェクトのTaylor Locke And The Roughs名義で2年間で3枚のアルバムをリリース。プロデュース業やエンジニアリング業を行いつつ、このアルバムの準備を進めてきた。もともとROONEYでも持ち前のポップ・センスを発揮していたが、このアルバムではさらに楽器それぞれの良さを活かす、温かさと一抹の切なさを匂わせるアコースティックな感触のバンド・サウンドで魅了する。アコギを爪弾く音は間近でその音を鳴らされているかのごとく鮮明で、音の響き方の細部までポリシーが貫かれているのがわかる。流行に左右されない音楽の普遍的な魅力を感じていただきたい。
-
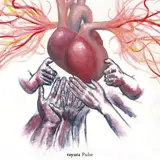
-
tayuta
Pulse
残響shop labelリリース第3弾は、2011年結成の大阪出身5ピース、tayutaのミニ・アルバム。彼らの音楽は残響所属バンドがお好きな方なら間違いなく刺さるポスト・ロック/マス・ロックだ。そんな彼らの個性のひとつはヴォーカル。この手の音だとヴォーカルがギターをかき鳴らして歌うイメージも強いが、このバンドのフロントマン、東 規行はヴォーカルだけに徹している。それゆえか、サウンドとヴォーカル・メロディは2本の虹のように美しい平行線を描く。これは東が体ひとつで音像の海に飛び込み、ヴォーカルに集中しているからこそ描ける線。4人の作る音を足場に、豊潤なファルセットを使いこなして歌い上げる彼の声の威力は大きい。各楽器のフレーズも挑戦的で、今後の動向が気になるバンドのひとつである。
-

-
te'
閾
これまで29文字を徹底していたタイトルが初めて1文字となったキャリア初のミニ・アルバム。"境界"、"敷居"という意味の"閾(しきみ)"と冠するところにはtachibana(Dr)の一時離脱で新体制となり、活動の区切りをつける想いが読み取れる。テクニカルなリフもなくコード・バッキングによる轟音が交差しグルーヴと化していくTrack.4を始め、過度なエフェクトやアレンジを排し、驚くほどタイトでオールドスクールなサウンドが詰まっている。昨年は彼らやtoe、BATTLESの新作リリースや、総括ディスク・ガイド本の出版を始め、ポスト・ロックというジャンルにとっても交通整理がなされ区切りがついた年となった。ここからポスト・ロック仕切り直し!と、シーンのど真ん中を闊歩するような頼もしい1枚だ。
-

-
te'
思想も共感もいらず、ただ幻聴を誘発する『起因』としての音楽。
メタル、ジャム、エレクトロニカなどを取り入れ、ポスト・ロックの可能性を更に拡張した5thフル・アルバムから約1年8ヶ月。te'が新作をライヴ会場、残響shop、残響オンラインストアにて限定リリースした。Track.1の電子音から荘厳に幕を開け、そのやわらかくも鋭いアンサンブルは、演者4人の指先にまで宿る集中力を感じさせる。未知の領域へ踏み込む好奇心や逞しさが崇高に瞬くTrack.2に対し、Track.3は憂いとひりついた緊張感が。複雑でテクニカルなリズムが楽曲の体幹を支え、2本のギターが語り掛けるように様々な情景を映し出す。真剣さが隅々に通った人間の熱量はこれほどまでに居心地の良い空間を作り上げるのか。ただがむしゃらなだけでは辿り着くことのできない、聖域とも言える音だ。
-
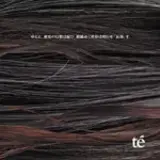
-
te'
ゆえに、密度の幻想は綻び、蹌踉めく世界は明日を『忘却』す。
昨年1月にベーシストmatsudaが加入し、新体制としては初となる、te’のフル・アルバム。メジャー・リリース作となった前作からは2年ぶりの5作目である。そもそもポスト・ロックとは“語る言葉”を持ち過ぎたロックに対する批評だったわけだが、te’はまさに、言葉を使わずして音と人間の感情を接続し、表現する。ギター、ベース、ドラムといった楽器によるアンサンブルが、まるで人間の五感や四肢の動きと直接リンクしているかのように、時に躍動し、時に沈黙する。te’の鳴らす、その1音1音が歓喜の笑い声であり、涙交じりの嗚咽であり、荒々しい怒号でもあるのだ。音楽と言う名の感情表現――いや、生命表現とでも言おうか。本作には、その臨界点のような凄まじさがある。
-

-
TEAM ME
To The Treetops
昨年リリースされたEPがここ日本でも話題となり、今作を非常に楽しみにしていた方も多かったと思う。期待していい。このアルバムには何かを始めようとする時の衝動やワクワクが、はちきれんばかりに詰まったとっても素敵なアルバムなのだから!ノルウェー出身のこの男女6人組は、元はバンドと偽ったソロ・プロジェクトで人気を獲得しつつあったMarius(Vo& Gt)がバンドお披露目の前日に、せっせと一晩のうちに友人に声をかけて結成。LOS CAMPESINOS!のキラキラ感、同じ北欧のLACROSSEが持つ抒情性を纏い、個々の感性を尊重しているこの若く民主的なバンドは、6人の持ってるおもちゃを使って何かしてやろうというピュアな気概と冒険心に満ちている。皆で楽しむ――この結束は何よりも固い。
-

-
TEAMS
Dxys Xff
マイアミのビート・メイカー/プロデューサーSean Bowieのソロ・プロジェクトTEAMS。2011年にマンチェスターのプロデューサーDarren WilliamsによるStar Slingerとのコラボ作品『Teams vs. Star Slinger』をリリースして話題となった。本作は同じく2011年にヴァイナルとデジタルのみでリリースされた作品の初CD化となる。全体的に心地の良いローファイなエレクトロ・サウンドがベースとなっており、そこまで斬新さはないがレトロ且つ面白いサウンドに仕上がっている。R&B、ファンク、ヒップ・ホップなどの要素を見事に融合しており、女性ヴォーカルをフィーチャーしたメロウな楽曲では心臓の鼓動を聴いているような切ないビートが突き刺さる。ビート・ミュージックのファンはもちろん、アンビエントやチルウェイヴのファンにもオススメの、聴き応えのある1枚。
-

-
Tearless Bring To Light
pieces
北海道の超新星4人組バンドによる初の全国流通ミニ・アルバム。闇を切り裂くようなサビの歌声から始まり、ド派手なギター・ソロが響き渡る「マイルドロット」。たっぷりとしたイントロで焦らしながら、サビでエモーションを爆発させる歌声が印象的な「Chain」。静かなユニゾンの中で英詞を丁寧に歌いこなすくらげに、様々なパターンの歌唱スキルが備わっていることを実感する「Skinny Sky」など、収録されている5曲どれもが、ニューカマーらしからぬ堂々たる存在感を誇っている。経歴を見ても、技巧派揃いのバンドであることは伝わってくるのだが、それだけではなく、4人の構築する美しい音の城の中で表現することが気持ち良くてたまらない! というような感情も、なみなみと溢れている。
-

-
TEDDY
20170607
今春メンバー全員が大学を卒業した神奈川発の4人組ギター・ロック・バンド TEDDYが、5ヶ月ぶりにリリースする2ndミニ・アルバム。前作『20170118』に続き日付をそのままタイトルにしてバンドの"いま"を刻むシリーズの第2弾となる。半年前といまとでは気持ち次第でガラリと違う自分になれるということを、言葉ではなく音楽で証明するような進化作。夢を諦めずに葛藤するTEDDYらしい等身大のナンバー「未来の手」もあるが、"通行人A"にはなりたくない少女の憂鬱を描いた「シュガーレスガール」やシリアスな曲調でロスト・ラヴを童話に喩えた「Actor」など、様々なサウンド・アプローチで綴られた全5曲はこれまで以上に表情豊か。情けない自分をありのままに歌うという素朴な性格のまま、ここからバンドは本格的に音楽家への道に踏み込んでいく。
-

-
TEDDY
20170118
決してヒーローにはなれない、ありのままの自分を歌うことで、同じようにどこかで涙を流す誰かに寄り添えるバンドになれたらいい。神奈川発の4人組ギター・ロック・バンド、TEDDYがリリースする初のミニ・アルバム『20170118』は、そんなバンドの決意を感じる作品だ。ポップで親しみやすいメロディと、その歌を最大限に活かすことを命題とした王道ギター・ロック。普遍的なアプローチの中で、フロントマン 長部 峻(Vo/Gt)が書く歌詞には、まるで伝えることを抑えられないとでもいうような熱さが滲み出ている。心のままに生きる難しさを知ればこそ、"モラルだとか魔法だとか 歪んだ言葉じゃなく 君は何を愛して生きるの"、そう問いかけるラスト・ソング「Dominant」が、鋭く胸に突き刺さる。
-

-
TEDDY
DETECT
2013年結成の4人組ギター・ロック・バンド TEDDYがTOWER RECORDS6店舗限定でリリースするニュー・シングル。"発見する"という意味を持つ表題曲「DETECT」には、劣等感に苛まれながらも、自分探しを続ける若者の姿がリアルに綴られている。これまでの爽やかなバンドのイメージを覆すアグレッシヴなロック・サウンドは、ここから未来を切り拓こうというバンドの強い決意を感じた。カップリングにはファンのTwitterから着想を得たバラード曲「ため息をついた少女の唄」、大人になりきれない宙ぶらりんな気持ちをノスタルジーと共に描いた「ハローグッバイ」を収録。ソングライター長部峻(Vo/Gt)がダメな自分を肯定して生み出す歌は、すべての弱虫たちに優しいエールを送ってくれる。
-

-
TEENAGE COOL KIDS
Foreign Lands
ネオアコ、はたまたUSオルタナを彷彿とさせるテキサス出身のギター・ロック・バンドTEENAGE COOL KIDS のセカンド・アルバムが登場。まずこんなにストレートなバンド名を聞いたのは久々。他に候補は無かったのかな、なんて思ったり。サウンドはGIRLSを引き合いに出したくなる様なシンプルでスカスカなサウンド。だけど10代の頃の甘酸っぱさを詰め込んだナンバーがあれば疾走感溢れるパンク・ナンバー、そしてシューゲイズ・サウンドと、とにかく曲ごとに新たな彼らの魅力が飛び出してくる。ここまでバラエティに富んだアイデアとポップな楽曲が並んでいるアルバムに出会えるなんてそうそうないかも。胸をくすぐる新たなインディ・バンドの登場だ。
-

-
TEENAGE FANCLUB
Here
グラスゴーを代表するインディー・ロック・バンドの重鎮が放つ6年ぶり10枚目。いつもどおりNorman Blake(Vo/Gt)、Raymond McGinley(Vo/Gt)、Gerard Love(Vo/Ba)が4曲ずつ持ち寄り、それぞれ自作曲でヴォーカルをとっている。新機軸や明確なコンセプトもなく、ただ機が熟したらセッションして曲作り。こんな"いつもどおり"にたまらなく耳を奪われ、説得力を感じるバンドなんてそういない。Track.1「I'm In Love」の甘酸っぱいメロディと突き抜けるコーラスが幕開けからメロウでうっとり。彼らも50代に突入し、楽曲のトーンも少しミドルエイジがかって三者三様の個性を発揮した幅広さはあるが、極めてバランスが良い。これも意図した仕上がりというよりは長年の活動による阿吽の呼吸だろう。新たな代表作の予感。
-

-
TEENAGE FANCLUB
Shadows
TEENAGE FANCLUBから5年ぶりとなる待望のニュー・アルバム『Shadows』がリリースされる。通算9作目となるこのアルバムは、どこか懐かしくて色褪せることのないメロディとポップで哀愁漂うギターのハーモニーが素晴らしい。5年ぶりだなんて忘れてしまうくらい期待を裏切らない仕上がりになっている。それにしてもこのバンドは90年にデビューして以来、ずっとみんなの心を打ち続けている。変わらないでいられるって意外に難しい。でも結局人は簡単に変わることなんて出来ないし、急に変われたとしてもそのまま満足していられるのだろうか?無理して変わることなんてしなくていい。そう、これは変わらない満足感が味わえるそんなアルバム。
-

-
THE TEENAGE KISSERS
VIRGIN FIELD
2012年のクリスマス・イブに誕生した4ピース・バンドTHE TEENAGE KISSERS。ソロとして活動していたNANA KITADEがフロント・ウーマンを務め、FOX LOCO PHANTOMなどでも活動するHIDEO NEKOTA(Ba)が曲を手掛ける。ルーツとなる90年代グランジ、オルタナティヴの、あの空気感、無邪気さも空虚感とが混じり合った香りをぷんぷんと漂わせるサウンドをこれでもかと食らわせる。HOLE、あるいはDAISY CHAINSAWなどを思わせるような、素っ頓狂なヴォーカルを活かしながら、歪んだギターと重たいベースやビートでぶっ飛ばしていく。ダークな雰囲気もあるけれど、その毒々しさを愛らしさも表するヴォーカルがポップに転化する。そんな狙いも込みで、ヒリッヒリにドライなギター・サウンドをやってるあたり確信犯的。
-

-
THE TEENAGE KISSERS
PERFECTLY DIRTY
北出菜奈(Vo)、猫田ヒデヲ(Ba)、仲田 翼(Gt)、小池麻衣(Dr)の男女混合4人からなるバンドのデビュー作となるミニ・アルバム。2012年12月結成のバンドとは信じられない程タイトな演奏だが、メンバー各々は様々なキャリアを積んだミュージシャンであり、特に仲田と猫田はGOLIATHのメンバーとしても活動しているだけに、既にバンドには確立されたグルーヴがある。ディレイ・ギターのリフレインと幾重にも重なったヴォーカルに圧倒されるダンサンブルな「VIOLENT LIPS」はバンドの魅力が詰まった曲。全体的に硬質でリヴァーブが効果的にかけられたドラムも心地よい。ジャケットやMVに見られるモノトーンを基調とした洒落たビジュアル・イメージも含め、ブレイクが期待されるバンドだが、それだけに"何を歌っているのか"が不明瞭な点に勿体なさを感じてしまう。
-

-
Teenagers in love
君とみた海
THE PAINS OF BEING PURE AT HEARTの楽曲タイトルから拝借した名を掲げて活動する、新潟のインディー・ポップ・バンドによる初の全国流通盤。10代から20代、子供から大人へと変化する少年少女の青春の1ページを1曲ずつ描いた、しかもアルバムを聴き進めるごとに主人公が歳を重ねていくという一貫性を持つ、非常にコンセプチュアルな1枚だ。"青春"と言っても、ここに記されているのは若々しくエネルギーに満ちたそれではなく、大人になっていくことへの寂しさ、葛藤、諦め、決意、幼さとの決別といった淡い感情。それをシューゲイズ/ポップ・サウンドが優しく包むという、儚い音像がなんとも切ない。男女それぞれの目線で綴られた歌詞に合わせ、ヴォーカルも男女で歌い分けており、思春期の心情をよりリアルに伝えてくれる。
-
-
TEENAGE WRIST
Chrome Neon Jesus
近年のEpitaph Recordsは派手さはないものの、若手、ベテラン共に渋めの実力派の作品を揃えている印象だ。そんな中でも、要チェックなのがこの3ピース・オルタナティヴ・ロック・バンド、TEENAGE WRIST。今作がデビュー作だが、その迫力あるサウンドと、どこか浮世離れした浮遊感のあるメロディは聴いていて病みつきになる。ハードコアの下地を感じさせるゴリっとしたベースに、ノイジーな轟音ギター。そこに柔らかなコーラスが伴うサウンドは、90年代エモやポスト・ロック、オルタナ好きにはたまらないはず。ひとつひとつの丁寧な音作りにも好感が持てる。Track.1に、なぜか日本語の台詞のようなものが入っているんだけど、日本語にゆかりがあるなら来日の期待もできるかな?
-

-
TEEN DAZE
Morning World
TYCHO、SUN GLITTERSなどのリミキサーとしても知られるカナダのJamison Dickによるソロ・プロジェクトであるTEEN DAZE、約2年ぶりのフル・アルバム。緊張感のあるストリングスに意表を突かれるオープニングから一転、静かに弾むドラム、陽光を乱反射させて揺れる波のようなギター&シンセ、柔らかなヴォーカル&コーラス・ワーク。生音主体のバンド・サウンドと聞き、従来のエレクトロ・サウンドをハイブリットに進化させたものを想像し たが、洗練さや生命力ではなく、人肌程度の温度と近さを印象づけられる生音だ。"Glacier"(=氷河)と名づけられた前作から大きく変化。聴き手を夢見心地にさせてくれる楽曲が揃った。
-

-
TEEN DAZE
All Of Us, Together
WASHED OUTやBLACKBIRD BLACKBIRDなど数多くのアーティストのリミックスを手掛けてきたことで知られるカナダ、バンクーバーのJamison DickによるTEEN DAZEが遂に待望のフル・アルバムを完成。再生スイッチを押した途端、身体が自然に動かずにはいられないほど、シンプルで小気味のよいリズミカルさ。そしてどこまでも優しい雰囲気のドリーミーなインスト曲が最初から最後までぎっしりと詰め込まれている。唯一インストではないM6 は女性ヴォーカルSTEFFALOOをフィーチャーし、もはや浮遊感、幻惑感は最高潮。まさにベスト・オブ・ドリーミーな1曲である。チルウェイヴ好きは勿論のこと、そうでなくとも見逃せない快作。
-

-
TEEN SUICIDE
It's The Big Joyous Celebration, Let's Stir The Honeypot
2013年より活動休止していたUSインディー・ロック・バンド、TEEN SUICIDE。バンド名からすでにナイスな香りしかしない彼らの4年ぶり2枚目となるアルバムが届いた。アナログ・レコードをそのまま録音したかのような雑なローファイ・サウンドを軸に、陽気な季節にピッタリな鼻歌テイスト且つグッド・メロディを散りばめている。さらに、ポップ、ロック、パンクな楽曲はもちろんアンビエントやエレクトロニカまで、美しいノイズを武器にして天才的なバランス感覚で切り刻むという、インディー・ロックの枠組みなどを取っ払った現代音楽のような若干の狂気さえも感じられる仕上がりとなっている。TEEN SUICIDEにしか表現できない前衛的な全26曲に要注目!


























