DISC REVIEW
D
-

-
DadaD
mission passion
Kate(Vo)とShige(Sound)によるポップ・デュオDadaD(ダーダーダー)の3rdアルバム。今作には夏にピッタリなオーガニックで哀愁漂うグッド・ミュージックが程よい尺と絶妙なバランスで凝縮されている。今すぐドライヴに出かけたくなるような高揚感を存分に堪能させてくれる「Ride Out」やドリーミングで熱帯夜のごとくムード満点のタイトル曲「mission passion」、そしてサンセット・ビーチで思い出に浸るような「Paradise」ある夏のはじまりから終わりまでのストーリーのなかへトリップできるような非常にクオリティの高い作品となっている。やみつきになりそうなKateのキュートでセクシーな歌声とDadaDの唯一無二な世界観を感じてもらいたい。
-

-
DadaD
Touch Touch Touch
“早起きは三文の徳”なんて昔の人はうまいこと言ったもんだ。そんな得をした日に、天気のいい日に出かけたくなるようなカラッと心地よいサウンドが爽快に響く。「Sing with me」がユニクロのCMソングに起用され注目を集めるデュオ・DadaD(ダーダーダー)。Shigeが作り出す心地よくも奇想天外かつ一筋縄ではいかないビートに英語・中国語・日本語の3ヶ国語を操るkate(Vo)の浮遊感ある声が乗ると気だるい雰囲気を纏いながらもポップに、そして爽やかに聴こえる。この組み合わせ、クセにならずにはいられないし、とんでもない化学反応を起こしている。部屋でのんびりしたり、料理をしたり、そんな日常の中に溶け込んでいく音楽。その一瞬一瞬を煌めかせてくれる。
-
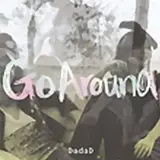
-
DadaD
Go Around
トラックメイク担当のShigeと、ヴォーカルと作詞を担当するKateによる男女デュオDadaD(ダーダーダー)の1stシングル。英語と日本語を交互に並べた歌詞すらも、風のように歌うヴォーカルに翻弄され、どこの国の言葉を口ずさんでいるのかなんて分からなくなってしまいそう。軽やかで滑らかに踊るKateの声はどこまでも瑞々しく、夏の日の噴水のようにキラキラと輝き、開放感と清涼感に満ちている。その後ろを時折チラつくのは、木漏れ日の中で揺れる影のような、Shigeの控えめなコーラス。極彩色の彩りと煌めきを添えるサウンドは、Kateの声をひき立てると同時に、全体に更なる立体感を与えている。彼らの音楽はアンビエントだが、心踊る。ほら、その足はもうステップを踏んでいるはず。
-

-
teto
正義ごっこ
ノイズ音から始まり、喉を壊すんじゃないかというくらいガナりっぱなしの「夜想曲」で荒々しくスタートし、こういう方向で来たか! と思ったら、続く「ラムレーズンの恋人」では、同じバンドとは思えないほどに軽やかで浮遊感のある音と優しいファルセットを聴かせる。そして、大切な人との別れを歌う春のナンバー「時代」に、アップテンポな中にはちきれそうなくらいの言葉数と想いを詰め込んだ「こたえあわせ」の4曲を収録。今年もフェスに引っ張りだこな彼らだが、これまで以上に直球の詞も含め、大きなステージで聴くと音源とはまた違った爽快感が味わえそうな曲が揃った。1stアルバム『手』も手掛けたカドワキリキによるアートワークも、キュートに見えつつ哀愁や陰を感じさせるのが彼ららしく、味わい深い。
-

-
DADA GAUGUIN
シーガルシーガル
大阪のひとりバンド DADA GAUGUINが4枚目の自主制作ミニ・アルバムをリリース。今作には、"変化"をテーマにした全4曲が収録されている。表題曲「シーガルシーガル」は、海で亡くなった水夫がカモメに生まれ変わるという都市伝説をもとに作られた、浮遊感のあるサウンドと頭から離れなくなるキャッチーなメロディが印象的な楽曲だ。他には"拍手もアンコールも/起こらず君が終わる"と、ただ過ぎていくだけのつまらない日常に棘を刺す「日々泡」、後悔や心の痛みをストレートに表現した「ムンク」、そして昔の自分に説教するため書いたという「進化論」と、その歌詞たちからは、情けない自分に対する毒を含みながらも、そんな自分から生まれ変わり、味気ない日々から抜け出そうという意志が窺える。
-

-
DADARAY
ガーラ
フル・アルバムとしては約4年ぶりで、リリース自体は約2年ぶり。その間に各々が様々なことを吸収したのだろう。"川谷絵音が手掛けるいちプロジェクト"という当初の印象から脱皮し、メンバー3人の個性がグッと表出するようになった。休日課長のレシピ本が原作のドラマ主題歌「Ordinary days」で新風を吹かせると、以降、えつこが中心となってアレンジを組み立てた八神純子カバー「黄昏のBAY CITY」、課長のベースが炸裂する「fake radio」など幅広く展開。REISのヴォーカルも曲ごとに違う表情を見せる。祝祭を意味する"ガーラ"というタイトルは、バンドの芽吹きを祝しているよう。初期曲「イキツクシ」のリアレンジが収録されているのも象徴的だ。
-

-
DADARAY
DADABABY
早くも4枚目のミニ・アルバム。川谷絵音のソングライターとしてのひとつのアウトプットでもあるDADARAY、今回は諦観、中毒性など恋愛における少し気怠げな異なるベクトルの曲を収録した印象だ。「刹那誰か」は比較的アップなジャズ・ファンク/レア・グルーヴで、生楽器で実験的なリフやフレーズを忍び込ませることで、ユニットの個性が光る。インディーR&B的な歌の符割りとビートを極力抑えた「singing i love you baby」、流れるようなピアノがまさに雨を想起させる「どうせなら雨が良かった」など、どの曲もアーバン・メロウなトレンドに限りなく近いようで、歌詞の切実さで刺してくる。1曲内容の毛色が違う「mother's piano」も含め、"本当は愛したい"という心情が核にある作品。
-

-
DADARAY
DADASTATION
ゲスの極み乙女。の休日課長(Ba)、ヴォーカリストのREISとえつこから成る3人組が、結成からわずか1年足らずというスピードでメジャー・デビュー。性質の異なる女声の絡み、洗練されたアンサンブル、ナイフを潜ませる川谷絵音(ゲスの極み乙女。/indigo la End/Vo/Gt)のソングライティング。全13曲が映し出すのは、疲弊し、虚無を抱える線の細い女性像。それが"大人な雰囲気を感じさせる上質なポップスを軸とする音楽を表現したい"と結成されたこのDADARAYのターゲット層そのものだということは言うまでもないだろう。バンドというよりプロジェクト、という印象があるのはその緻密な構築美から戦略めいたものが読み取れるから。だからこそ次にどう出るかが気になるところ。
-
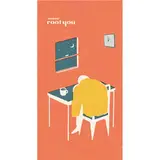
-
daisansei
root you
新体制初の新曲として2021年12月に配信リリースされた「ルートユー」を中心としたシングル。シンプルながらメンバーの顔が見えるアプローチにこだわったという温かいアンサンブルによるミディアム・ナンバーは、新生daisanseiを象徴する曲と言えるだろう。そんな「ルートユー」に加え、フルートやサックスの音色を取り入れたポップ・ソング「Yellow」、今回初収録の新曲「ビードロ」、「ルートユー」のリミックスと曲ごとに色は違うが、輝度や彩度を無理に上げようとせず、素朴だが良質なものを目指そうという姿勢が感じられるのは共通。ふわっと抑揚する音楽にひなたの道を散歩している感覚にさせられる今作が、懐かしの8cm CDでリリースされるのもしっくりくる。
-

-
daisansei
ドラマのデー
ベースにあるのは温かみのあるメロディ、ゆるりとした歌声。そこに重なるバンドの音は曲をポップにさせるが、基本一筋縄ではいかず、なかなか読めない。美しくも語りすぎない歌詞は、時におそろしいほど核心をつく。さらに突然ラップや朗読が始まる意外性、リード曲のテーマに合わせてカセットテープでリリースする遊び心も。次の瞬間何が飛び出すかわからない、異世界に連れ出されたみたいな楽しさと、ひたすらに誠実な筆致。両方を有する彼らの音楽からは、"大賛成"という単語に通ずる突き抜け具合、器の大きさを感じる。なお、本作は、本格始動から約1年半でリリースされる初のフル・アルバムで、今年は4ヶ月連続配信リリースもあった。アイディアが溢れている状況だけに次が楽しみだ。
-

-
DAISHI DANCE & MITOMI TOKOTO project.Limited Express
PARTY LINE
DAISHI DANCEの海外輸出名義プロジェクト“Limited Express”に、クラブ系ウェブサイト「CYBERJAPAN」のプロデューサーを始め多岐に渡る活動で知られるMITOMI TOKOTOが加わっての初音源!日本のクラブシーンを支え、それをさらにオーバー・グラウンドなシーンまで押し上げた立役者2人のサウンドとくれば、日本じゅうどこのクラブでも加熱しないわけがない。そして、武田真治のサックスとピアノの絡みがめちゃくちゃクールな「SAX@Arena」は、アッパーなムードの中に妖艶さがそこはかとなく漂う。「Tunnel」も、楽曲にアクセントを加える流麗な鍵盤の音色が印象的。振り返ってみれば、DAISHI DANCEの名作『theジブリ set』も高揚感と美が共存する作品だった。どう考えてもフロア仕様なサウンドに身を委ねるもよし、その中にある叙情性に胸を熱くするもよし!
-

-
Damian Jurado
Saint Bartlett
Damian Juradoは、その美しいメロディと天性の歌声で、聴く者の感情の機微に優しく触れながら、隣に寄り添ってみせるベテランのSSWだ。その音楽性の高さから、ミュージシャンからも多くの支持を集めている。Sub Popからも作品をリリースしてきたという経歴が示すように、彼はフォークという枠に留まらない音楽性を持っている。言うならば、オルタナティヴ、ローファイを通過した音響的なフォーク。フィールド・レコーディングで採取した音を散りばめた空間的な音像を持つ彼の歌は、柔らかなバンド・アンサンブルとコーラス・ワークとともに、聴く者をそっとスピリチュアルな世界へ誘ってくれる。Niel Young、WILCOから、SUPPER FURRY ANIMALSあたりが好きな人にもオススメ。
-

-
D.A.N.
D.A.N.
突然変異のニュー・ウェイヴか、はたまた異形のオルタナティヴか。このD.A.N.と名乗る3人の若者、とんでもない傑作を完成させてしまった。10年代のブラック感を血肉化した、洒脱なフロウの気だるげでマチュアなヴォーカルに、空虚な身体性を宿したデッドなリズム・セクション。黒人音楽と白人音楽を往来する耽美なサウンドをコンテンポラリーなセンスで鳴らす鋭敏な感性、さらに、はっぴいえんどから脈々と受け継がれる日本的叙情を掬い上げる風情も持ち合わせる。今作には、漆黒のトロピカルAORと言わんばかりの「Ghana」、東京の街の凍える孤独を踊り溶かすスモーキーなダンス・ナンバー「Native Dancer」など洗練の限りを尽くした珠玉の8曲が並ぶ。坂本慎太郎や中村弘二、THE XXの3人をまとめて踊らせる真夜中のダンスフロアで流れているのは、まさにこんなアルバムだろう。
-
-
Dana Buoy
Summer Bodies
AKRON/FAMILYでドラムやパーカッション等を担当しているDana JanssenがDana Buoy名義でリリースするソロ・アルバム。聴いた瞬間に南国をイメージするようなトロピカルな雰囲気がアルバム全体を通して貫かれている。Danaがほとんど1人でこなしたという様々な楽器に、アナログ・シンセサイザーやiPodのアプリ等を加えて完成させたという楽曲は、生楽器と機械音のバランスが絶妙でとても心地が良い。 ゆったりとしたフォーク・サウンドからスペイシーなシンセ・サウンドを経て、最後は賛美歌のような神秘的なポップ・サウンドにたどり着く。聴き終わると夏の終わりに思い出の写真を1枚ずつ眺めていたようで少し物悲しさが残る。Danaが自身のサウンドを“トロピコア”と呼んでいるらしいが、その名に相応しい夏にぴったりのドリーム・ポップ集だ。
-

-
DANGER MOUSE&Daniele Luppi
Rome
『Roma』なる架空のサウンド・トラックが届けられた。差出人はBROKEN BELLSとしての活動も記憶に新しいDANGER MOUSEから。おや? この壮大で荘厳なサウンド・スケープはなんだ!これまでの作品とは一線を画すものだ。まるで映画音楽の巨匠Ennio Morriconeへの挑戦状? DANGER MOUSEことBrian Burtonと、イタリア出身のコンポーザーDaniele Luppiが手を組んだこのプロジェクト。お互いイタリア映画音楽好きで、この分野で一緒に何かやろうと意気投合したのがきっかけのようだが、なるほど、マカロニ・ウェスタンの空気が満ちている。さらに驚くべきことに、ヴォーカルとして迎えたのはJack WhiteとNorah Jones!渋みと甘さが絶妙に絡む歌声を披露し、楽曲の味わい深さをより強めている。しかし、天才の名をほしいままにするBrianの動向は予想だにできない。彼の脳内はさながら小宇宙だろうか?
-

-
Daniel Johns
FutureNever
オーストラリアの人気オルタナティヴ・ロック・バンド、SILVERCHAIRのフロントマンとして知られるDaniel Johnsが2作目となるソロ・アルバムをリリース。全体的に、ソフト且つポップでありながら、どこか陰もあるサウンドがJohnsらしい。ロックにとらわれず、R&Bやシンセ・ポップなどのダンス・ミュージックにも手を伸ばした、境界線があいまいなファジーな世界観には、タイムレスな魅力がある。ピアノやストリングスに合わせ、自身の声帯さえ楽器のように自在に響かせるその表現力も、ソロになってさらに大きな武器となったのではないだろうか。早熟で評価され続けてきたDaniel Johnsが、キャリアを積んで名実共に熟してきたスキルを遺憾なく発揮した自由なアルバムだ。
-

-
DAN LE SAC VS SCROOBIUS PIP
The Logic of Chance
前作『汝、つねにキメるべし~ Thou Shalt Always Kill ~』で数々の超有名大物バンド達を「ただのバンド!」と言い放ったUK 問題児2人組から、2年ぶりの新作『The Logic Of Chance』が届いた。今作のアルバムのコンセプトについて「新しいことを試して自分の表現の幅を広げること」を目標に挙げたそうだ。前作の『Thou Shalt Always Kill』も斬新過ぎて思わず笑ったけど、同時に「こんな手法があったのか!」と気付かされ作品だった。そして今作は、社会・政治的なメッセージがさらにレベルアップし、エレクトロでヒップ・ホップでありながら、ポップとオルタナティヴが融合したサウンドのバランス感覚はお見事と言いたい。
-

-
Dannie May
Magic Shower
1曲目「マジックシャワー」が白眉の出来。音楽の力を信じ、言葉を曲に乗せ、リスナーと一緒に歌う意義を高らかに鳴らす様に目頭が熱くなる。これまでより素直な筆致が響くのは、彼等が重ねてきた経験が血となり肉となり、自信と説得力になっているから。「ふたりの暮らし」の"今んとこ夢は乾燥機"等、生活を捉えたフレーズも光る。だが一方で、先行配信で驚かせたミクスチャー・ロック「ダンシングマニア」ではダークな魅力も新展開。さらに、楽しくきゅんとするメロディでポップに振り切った「アストロビート」と10曲10様の心模様に寄り添う。大きな会場でのライヴやイベントのトリを任されるようになってきた彼等の気合がこもったネクスト・フェーズ。
-

-
Dannie May
五行
一度聴くとふとしたときに脳内再生してしまう中毒性の強いダーク・ポップ「玄ノ歌」から始まる物語。自然哲学"五行思想"のそれぞれの要素が持つ"5色"をテーマにした5曲を収めている。もちろんその意味を調べながら聴いて深みにハマるのも良し。だがフラットに再生してみても十分フックとなるナンバーが目白押しだ。血の通った温かな歌を響かせる「朱ノ歌」、田中タリラ(Vo/Key)がピアノ弾き語りで歌う珍しくシンプルなアレンジが染みる「木ノ歌」、Yuno(Cho/Kantoku)によるまろやかな言葉選びで愛を歌う「白ノ歌」、すでにライヴ定番曲の「黄ノ歌」と、沈んだ気持ちに寄り添いつつ、最後には前を向けるようにと作られた楽曲群。バンドの真心が一貫して伝わる、彼ら史上最も力を与えてくれる作品になった。
-

-
Dannie May
ホンネ
3人組コーラス系バンドによる、建前と本音がテーマの2作連続EP。その"ホンネ"のほうを冠した1枚が本作だ。それゆえ厭世的な部分や繊細な心の内が表現された曲が並ぶが、ただ言いたいことを直接的にぶちまけただけでもなさそうなのが、人間らしくて面白い。カオティックなシンセが引っ張る四つ打ちダンス・チューン「ええじゃないか」、シンガロングできるフレーズが配された「一生あなたと生きていくなら」はライヴ映えするだろうし、「小舟」はトラックを作り込むイメージの彼らがギター1本をバックに歌う初のアコースティック・ナンバーで、強力なフックになっている。他にもエッジィ且つ横ノリできるユニークな「負け戦」、リスナーを鼓舞しつつバンドの物語にも重なる「異郷の地に咲かせる花は」と、楽曲のレンジを一気に広げる。
-
-
DAN SAN
Shelter
ベルギー産インディー・フォーク最重要バンドと称される男女6人組のDAN SAN。カナダのシンガー・ソングライターFEISTがレコーディングしたことでも有名な築200年というマナー・ハウスにあるスタジオにてヴィンテージの機材で録音/制作した2ndアルバムは、前作を超える圧倒的に美しい世界観を堪能できる仕上がりに。フェード・インで厳かにスタートするTrack.1、爪弾くギターと優しい歌声にコーラスが重なるTrack.2などを始め、美しくも儚い幻想的なサウンドスケープが、やわらかく日常に溶け込んでくる音像を描く。前作をリリースしたあと、世界各国で120以上ものライヴを敢行した彼らは、確実に成長を遂げている。2ndアルバムにして重鎮のような存在感を放つDAN SANの極上の1枚に耳を傾けてほしい。
-

-
DAOKO
私的旅行
小林武史や中田ヤスタカ、中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES)、水野良樹(いきものがかり)、神山 羊ら豪華な面々が参加した、待望の3rdアルバム。ゲーム・アプリ"ドラガリアロスト™"の主題歌「終わらない世界で」と挿入歌「ぼくらのネットワーク」では、ゲームのストーリーに寄り添いながらも、彼女の特徴的な歌声と歌詞によりDAOKOの楽曲としての世界観も確立しているところはさすがだ。さらに、昨年大きな話題となった米津玄師とのコラボ曲「打上花火」のソロ・バージョンも収録。新しい世界への旅立ちを描いた「NICE TRIP」でラストを迎える本作を聴き終えた今、紅白初出場も決定したDAOKOが生み出すこれからの音楽にわくわくが止まらない。
-

-
DAOKO
打上花火
映画"打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?"の主題歌で米津玄師との共演が話題の弱冠20歳のラップ・シンガー、DAOKO。同映画を彩る楽曲「打上花火」は、切ないピアノの旋律と、ブレスの効いたきれいなウィスパー・ヴォイスで、夏の夜に咲く打上花火の美しく儚い様子が表現されている。また、挿入歌の「ForeverFriends」は、原作ドラマでも使用された楽曲のカバーで、彼女の聴き心地のよい声の魅力が満載の仕上がり。そして最後は、サカナクションの江島啓一(Dr)がアレンジした「Cinderella step」。ダンサブルでありながら、大人っぽさとあどけなさのシンクロ具合はさすがといったところ。少女と大人の女性の両方の魅力を併せ持つ彼女の今後の活躍が想像でき、ドキドキする1枚だ。
-

-
DARKSIDE
Psychic
クラブ・ミュージック・シーンの新星として一躍、脚光を浴びたNicolas Jaar。2011年発表の1stアルバム『Space Is Only Noise』が大歓迎された彼の新たな挑戦がジャズ畑のベーシスト、Dave Harringtonと組んだこのDARKSIDE。Harringtonをギタリストとして迎え、エレクトロニック・ミュージックはほぼ未経験という彼とセッションしながら曲を作り上げていったという。ヴォーカルを含め、メロディを際立たせることで、曲の輪郭がはっきりした前半の曲は、まさにその成果と言えそうだ。最大の収穫は熱い歌声を聴かせるブルース調のTrack.4「Paper Trails」とファンキーなリズムを打ち出したTrack.5「The Only Shrine I've Seen」。本作における最大のテーマだったに違いない、フィジカルな躍動感をアピールしている。
-

-
DARKSTAR
Foam Island
Warp Recordsへ移籍してリリースされた前作『NewsFrom Nowhere』以降、"FUJI ROCK FESTIVAL'13"への出演など、日本でも名を馳せるAiden Whalley、James Youngの2人によるエレクトロ・ユニットの約2年半ぶり3枚目のアルバム。言葉が飛び交い映画の一場面のような冒頭の「Basic Things」から「Inherent InThe Fibre」と幽玄なエレクトロ・サウンドが掴みどころのない印象を与えるが、「Stoke The Fire」のようなデカダンで都会的なダンス・トラックもありポップなエレクトロ・アルバムとなっている。MVが制作されている「PinSecure」の散らばったピースを集めて構築していくような音像が面白い。1枚のサントラ盤のつもりで通して聴いて欲しい。
-

-
DARLIA
Petals
イギリス・ブラックプールを拠点に活動する3人組ロック・バンド待望の日本デビュー・ミニ・アルバム。かねてから洋楽ロック・ファンの間では話題となっていた彼ら。OASIS、NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDSらのマネージメントを手掛けるIgnitionの秘蔵っ子と謳い文句にあるが、なるほどヴォーカルはLiam Gallagherそっくり。Track.1「Stars Are Aligned」からワクワクさせられる力強いバンド・アンサンブルとシンガロングできそうなメロディが飛び出してきて、思わず嬉しくなってしまった。歪んだギターと豪快で重たいリズム隊がNIRVANAを彷彿とさせる「Candyman」など、UKロックとUSインディーの魅力を併せ持ったサウンドは決して二番煎じの懐古バンドではない迫力。今後活躍がますます期待できそうだ。
-
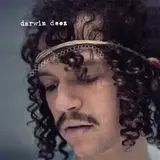
-
Darwin Deez
Darwin Deez
NYからこれまた一癖あるポップ・スター候補が登場というところか。これからファッション誌なんかにも取り上げられるであろうルックスのDarwin Deezは、THE STROKESとPHOENIXの間で、飄々としたポップ・ソングを鳴らす。エレクトロ・ポップを土台持ちつつ、基本はクールな佇まいのモダンなロックンロール。ちょっと甘くメロウなセンスは抜群に良いけれど、ちょっと突き抜け方が足りない気もする。PHOENIXのようなポップ・ソングを期待していたら、ちょっと肩透かしを食らうことになる。ただ、どちらかと言うと自覚的に突き抜けたポップさを避けているのだろう。ドリーミーで多幸感満載のエレクトロ・ポップ全盛の中、これはこれで最近あまりない感触だし、新鮮ではある。
-

-
DAS POP
The Game
“ポップ・ミュージックとは人生を変えるものさ!”と叫びベルギーから華麗に登場したのは、約2年前の出来事。その言葉通り、ありったけの幸福感を呼び起こすカラフルなポップ・ワールドを繰り広げ、新人とは思えぬポップ・マイスターっぷりには驚かされた。そして、彼らの次なる“Game”が完成した。前作ではその才能に惚れ込んだSOULWAXがプロデュースしていたが、今作はセルフ・プロデュースとなる。この変化は、本能の赴くままに筆を走らせたような軽やかさと大胆さが同居する、豊かなサウンド・ボキャブラリーに表れているだろう。HALL&OATESやWHAM!のような80’sサウンドを彷彿とさせ、あの輝かしくも享楽的な時代が甦るようなサウンドは、クラブ・シーンからお茶の間レベルまで浸透しそう。世代を超えて楽しんでもらいたいアルバムだ。
-

-
DAS POP
Das Pop
一時期はJUSTICEのMIX CDに納められた事で有名になった彼ら。それが昨年の頭だった事もあってようやくという印象を受ける日本デビュー・ アルバムの登場だ。あのJUSTICEが目をつけていた事も驚きだが、今回のアルバムのプロデューサーは同郷のSOULWAX。今でこそダンス・フィールドで語られる事が多いSOULWAXだがグラマラスなロック・バンドとしてデビューした彼らの事、ポップなロック・サウンドもお手の物だろう。モータウン・ビートのヒット・シングル「Underground」から始まる今作は、難しい事を考えずに楽しめる極上のポップ・ソングがズラリ。ベルギーで10年前に結成された彼らは「ポップ」というキーワードの中それぞれが曲を作っていきアルバムを完成させた。時間がたっても色あせない爽快なポップ・アルバム。
-

-
DATAROCK
Red
今年のSUMMER SONICに出演が決定している、ノルウェー出身のDATAROCK。セカンド・アルバムの今作は、彼らのトレードマークである“赤”がそのままアルバムタイトルとなった。ジャケットも、ブックレットも、盤も赤で統一という徹底っぷり。エレクトロニクスを駆使したダンサブルなポストパンクを基調に、ファンキーなサウンドでガツンと踊らせてくれる「Give It Up」は新たなフロアアンセムとなるか!?因みに、「True Story」の歌詞はTALKING HEADSの曲名が羅列されている。マイナーコードが主体で神経質さがぷんぷんと漂っているが、速いBPMとコンパクトにまとめられた曲群はとても聴きやすい。ギターのフレーズが覚えやすくセンスがいいのも好感色!ライブが楽しみ。
-

-
DATS
School
90年代への憧れが明快に綴られた「Time Machine」に象徴されるように、バンドとしてのパーソナルなルーツに目を向けたうえで、作品が目指す方向の純度が高まったのだろう。結成当時のダンサブルなインディー・ロックから、打ち込み主体に移行していった時期、そのうえでアップデートしたバンド・サウンドを鳴り響かせた近年まで、これまでの活動遍歴を詰め込んだ内容ではあるが、その奔放なミクスチャー・センスや、これまでにはなかった足取りの軽いポップ感、ソウルフルなメロディ、ガラッとイメージを変えた爽やかな色味のイラストを施したジャケットなどからは、何かが吹っ切れたことで手に入れた新機軸を感じ取ることができる。それはきっとあなたの生活にも新たな彩りを加えてくれるはずだ。
-

-
DATS
Game Over
"ダンサブルなロック"のイメージから、フロントマン MONJOEのトラックメイカーとしての打ち込みスキルを生かした音源にシフトし、ライヴではそれらのトラックを生音と融合させ、グルーヴを膨らませるスタイルを推し進めてきたバンドが、一連の流れを経たうえで、再びバンドで音源を作り上げることに舵を切ったEP『オドラサレテル』に続くシングルをリリース。もはや彼らを"生音"や"打ち込み"、"ロック"や"エレクトロ"といった縦割り構造に当てはめて語る必要はない。一貫して"ダンス・ミュージック"であることのうえに、この先どんな音が塗り重ねられていくのか。「Game Over」は、その可能性が無限大であることを示すとともに、日本中のお茶の間が踊る可能性を秘めた、一撃必殺のポップ・チューンだ。
-
-
THE DATSUNS
Death Rattle Boogie
2002年にデビュー。世界同時多発的に巻き起こったロックンロール・リヴァイヴァルの波の一端を担ったニュージーランドの4人組、THE DATSUNS。当時のバンドの中にはもはや表舞台から姿を消してしまったバンドも数多くいるが、彼らは本作が4枚目。着実に、自分たちのキャリアを築いている。そもそもがハード・ロック譲りの暴力的なまでにヘヴィなリフを武器に、当時の有象無象のバンドたちとは一線を画す個性を放っていたバンドだが、声変わりし損なった少年のような高音ヴォーカルと、疾走感するハードなギター・サウンドは相変わらず。随所に現れるねちっこいギター・ソロには、渋みと貫禄すら備えるようになった。たまには“牛丼特盛汁だく”みたいにハイ・カロリーなロックも聴きたくなるというあなたに、ぜひおススメ。
-

-
DAUGHTER
If You Leave
THE XXが、都市の暖かな暗闇に生きる若者たちの代弁者だとすれば、Daughterはそんな彼らの祈りを体現する巫女だ。ロンドン出身のElena Tonra(Vo/Gt.)を中心として結成された3人組の奏でる内省的なサウンドは、フォーク・ロックとも広義の意味でのシューゲイザーとも形容出来るような、ある種の神々しさを纏っている。Elenaのパーソナルな経験を元にした歌詞は時折、個人的な信仰体験を匂わせながら、普遍的な若さ故の痛みを歌う。音楽フェスSXSWで注目を集め、イギリスの名門レーベル“4AD”との契約後、ようやく待望のデビュー・アルバムを発表! という位置付けの今作であるが、期待を裏切らない。FUJI ROCK FESTIVAL '13への出演も決まっており、聴くなら今だ。
-
-
DAUGHTRY
Cage To Rattle
オーディション番組"アメリカン・アイドル"のセミ・ファイナリストで、圧倒的歌唱力を誇るフロントマン Chris Daughtry(Vo/Gt)率いるDAUGHTRY。アルバム総セールス800万枚を超える彼らの、ニュー・アルバムが完成した。前作では最先端のEDMを取り入れたり、逆にロックのルーツでもあるカントリーを取り入れたりと、冒険しつつもポップな方向に振り切っていたが、今作は彼らの根底にある、ワイルドなアメリカン・ロックの魂が全面に出た作品という印象だ。もちろん、ポップなメロディは今作でも健在だが、ブルースやゴスペルといった根源的な音楽に寄り沿うことで、より生々しいロックの魅力が際立っている。彼らのお家芸でもあるバラードも、哀愁たっぷり。これぞまさに大人のロックだ。
-

-
Dave Hause
Bury Me In Philly
Fat Wreck Chordsからアルバムをリリースしているパンク・バンド、THE LOVED ONESのフロントマンによる3作目のソロ・アルバム。Bob Dylanから連綿と続いているシンガー・ソングライターの流れの上で、自らのソングライティングを磨き上げることに挑戦という意味では、前2作の延長と言えるが、地元フィラデルフィアのヒーロー THE HOOTERSのEric Bazilianを共同プロデューサーに迎えたことで、これまで以上にBruce Springsteen、John Mellencampを始めとするアメリカン・ロックンロールに接近。"Bo Diddleyビート"を取り入れたり、ピアノやアコーディオンを使ったりしながら多彩なアレンジを加えたことで、いぶし銀と表現されてきた作風が広がりを見せたことは今回の一番の成果だ。
-

-
Dave Rowntree
RADIO SONGS
90年代に一世を風靡し、今も熱狂的なファンを世界中に持つBLUR。そのドラマーにして、パイロット、政治家、弁護士など多方面でその才能を発揮してきたDave Rowntreeが、満を持してソロ・デビュー・アルバムをリリース。ミュージシャンとしてもマルチ・プレイヤーであるだけでなく、バンド活動以外にも映画やドラマなどの劇伴を手掛け、作曲家としての評価も高い彼だけに、今作はその幅広い経験すべてが糧となって消化されたような作品となっている。ゆったりした大人な雰囲気のエレクトリック・サウンドをベースに、主張しすぎないオーケストレーションの巧みな演出、そしてBLURで培われたポップ・センス。Dave Rowntree自身の優し気なヴォーカルも楽曲に溶け込むようにマッチしていて魅力的だ。
-

-
DAY6
UNLOCK
アジア発の5人組によるJAPAN 1st アルバムは、生形真一(Nothing's Carved In Stone/ELLEGARDEN)がプロデュースを手掛けた「Stop The Rain」、「Falling」を含む全10曲入り。メンバー5人中4人がメイン・ヴォーカルを務める強味を生かし、エモーショナルなメロディや重厚なコーラスを押し出したロック・サウンドを鳴らしている。オープニングを飾る「Live Your Life」は大きな会場で映えそうなスケール感のある曲調で、シンガロング必至の歌メロに引き込まれる。他にテンポ良く進むポップな「Say Hello」、ドラマチックな起伏に富む「If ~また逢えたら~」、さらに生形が携わった「Stop The Rain」、「Falling」もアルバムの流れで聴くと、楽曲の魅力がよりいっそう際立って響いてくる。
-

-
DAY6
Stop The Rain
K-POPやロックなどのジャンルにとらわれない独自のスタイルを貫き、今年3月に日本デビューを果たした韓国の5人組ロック・バンドが、2ndシングルをリリース。今作は、なんとギタリストの生形真一(ELLEGARDEN/Nothing's Carved In Stone)によってプロデュースされた。重みのあるサウンドとギター・リフから生形の色がハッキリ見え、これまでよりもロック・テイストの強い作品となったが、メイン・ヴォーカル4人の歌声とメンバー作詞の歌詞によって、DAY6らしさもしっかりと表現されている。ダイナミックなサウンドに乗せて、大切な人を失った悲しみを歌う2曲でひとつのストーリーを作り上げた彼らは、アイドル色が強いと思われがちな韓国人アーティストのイメージをひっくり返す存在になるのでは。
-
-
DEAD CAN DANCE
Anastasis
なんと16年ぶりのリリースとなる通算9作目のフル・アルバム。かつてのダークで壮大な唯一無二の世界観は一層の高みへと昇華されており、あらためて音楽とは崇高な芸術なのだと気づかせてくれる。先行公開された「Amnesia」は幻想的で威厳を放つBrendan Perryのヴォーカルをピアノとストリングスが果てしないほどの哀愁を演出しながら包み込んでいく貫禄のサウンド。そしてLisa Gerrardが妖艶で美しいヴォーカルを務める「Anabasis」では中近東の民族音楽を取り入れており、彼らの真骨頂ともいえるジャンルや国境をも越えたオリジナリティを垣間見ることができる。ギリシャ語で復活を意味するというタイトル通り、今作で完全復活を遂げたDEAD CAN DANCE。新たなる伝説が、ここからはじまる。
LIVE INFO
- 2025.09.17
- 2025.09.18
- 2025.09.20
- 2025.09.21
- 2025.09.22
- 2025.09.23
- 2025.09.25
- 2025.09.27
- 2025.09.28
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号























