DISC REVIEW
J
-

-
先行シングルであるバレアレックなダンストラック「Tonight's Today」をあるクラブで聴いた時、これがまさかJACK PENATEの新曲だとは思いもよらなかった。本人曰く「前作と同じインディっぽいレコードを作ることも出来たけど、その
-

-
各種音楽メディアで高い評価を得た、前作『Smash』から約8年という月日を経て、満を持して今回、発表される『Glow』。DAFT PUNKやPHOENIXなどを擁するフレンチ・エレクトロ・シーンの肥沃な音楽的地表に育てられた、JACKSON
-

-
"FUJI ROCK FESTIVAL '22"にヘッドライナーとして出演したJack White。今年は、すでにアルバム『Fear Of The Dawn』を発表しており、今作は2022年2作目のアルバムになる。前作とは本来同時リリース予
-

-
Jack Whiteの新たな覚醒をアピールする3作目のソロ・アルバム。BeyoncéやA TRIBE CALLED QUESTとの共演がその前兆だったのか、大胆にヒップホップ、ファンク、ジャズに接近。そのうえでゴスペ
-

-
ジャズ、ブルース、R&B、フォーク、カントリーといったアメリカの大衆音楽をネタに思いっきり楽しんでいるという意味では全米No.1になった前作と同路線と言えよう。しかし、2年2ヶ月ぶりとなるソロ第2弾は、より自由に楽しんでいるという印象。Ja
-
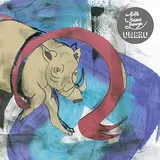
-
前作のフル・アルバムから1年を経て完成した新作はライヴ会場と配信限定リリースのミニ・アルバム。6曲中4曲が英語詞で歌われている。バラードはなく、冒頭の「freak me out」から、とにかくテンションが高い曲が続いて文句なしにカッコいい。
-

-
心機一転、札幌から東京に拠点を移した3ピース・ロック・バンド、Jake stone garageが放つ2ndフル・アルバムは、新作リリースとしては約3年半ぶりという、タメの効いた珠玉のロック・ナンバーが並ぶテンションの高い作品。Track.
-
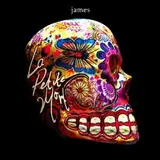
-
6年の活動休止を経て、2007年に復活してからも精力的に活動を続けている6人組、JAMESによる11作目のアルバム。U2、THE SMITHSに続くバンドとして、90年代に一時代を築いた彼らだが、ここではその頃を彷彿とさせるニュー・ウェイヴ
-

-
幼少期に両親の離婚を経験したというJames Arthurが荒んだ10代のエピソードと共にイギリス版"The X Factor"で優勝したのが2012年。1stアルバム『James Arthur』は全英2位を獲得するも、自身のSNS上での発
-

-
第58回グラミー賞の"最優秀新人賞"にノミネートされるなど、期待を集めるイギリス出身の新鋭シンガー・ソングライターの日本デビュー・アルバム。同作もすでに全英チャート1位を獲得、"最優秀ロック・アルバム"にもノミネートされているだけあって、さ
Warning: Undefined property: stdClass::$ItemsResult in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 34
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Warning: Attempt to read property "ItemInfo" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Warning: Attempt to read property "ProductInfo" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Warning: Attempt to read property "ReleaseDate" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Warning: Attempt to read property "DisplayValue" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 40
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 41
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 41
Warning: Attempt to read property "ItemInfo" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 41
Warning: Attempt to read property "ByLineInfo" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 41
Warning: Attempt to read property "Manufacturer" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 41
Warning: Attempt to read property "DisplayValue" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 41
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Attempt to read property "ItemInfo" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Attempt to read property "ExternalIds" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Attempt to read property "EANs" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Attempt to read property "DisplayValues" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 42
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 43
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 43
Warning: Attempt to read property "ItemInfo" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 43
Warning: Attempt to read property "Classifications" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 43
Warning: Attempt to read property "Binding" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 43
Warning: Attempt to read property "DisplayValue" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 43
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 45
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 45
Warning: Attempt to read property "Images" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 45
Warning: Attempt to read property "Primary" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 45
Warning: Attempt to read property "Large" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 45
Warning: Attempt to read property "URL" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 45
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 46
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 46
Warning: Attempt to read property "Images" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 46
Warning: Attempt to read property "Primary" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 46
Warning: Attempt to read property "Large" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 46
Warning: Attempt to read property "Height" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 46
Warning: Attempt to read property "Items" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 47
Warning: Trying to access array offset on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 47
Warning: Attempt to read property "Images" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 47
Warning: Attempt to read property "Primary" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 47
Warning: Attempt to read property "Large" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 47
Warning: Attempt to read property "Width" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-james_yuill.inc on line 47
-
昨年末の来日では素晴らしいライヴを観せてくれたJames Yuillから2ndアルバムが到着。胸を打つアコースティク・サウンドとエレクロ・ビートの融合は更なる進化をみせ、リード・トラックである「Crying For Hollywood」で見
-

-
メンバー・チェンジを経てリリースされる2nd EP。一貫してUKギター・ロックへのリスペクトを感じさせる、彼らのこれまでの楽曲の中でも異色なオルタナ・テイストの強い「KABUKI」を、1曲目にバーンと出してくるのが逆にJam Fuzz Ki
-

-
平均年齢21.8歳の東京の5人組が結成から2年でリリースする堂々の1stフル・アルバム。OASISをはじめとする90年代のUKロックをバックボーンに大音量で鳴らすロックンロールという意味では、前作(1st EP『Chased by the
-

-
現在のシーンに窮屈さを感じているのか、ここ数年の間に生まれたトレンドとは別のサウンドを求めるバンドが、増え始めた。この平均年齢20歳の5人組も、そのひと組。彼らが結成からわずか1年で大きな存在感をアピールし始めたのは、90年代のUKロックを
-

-
UKジャズで最も売れたアーティストとしても有名なJAIMIE CULLUMが4年振りに新作をリリース。ジャズという括りではまったく収まらない彼の魅力は今作でも溢れており、JEFF BECKとのライヴでの共演もあったようにアグレッシヴな側面も
-

-
前作『Jim』のポップでソウルフルな作風からまた一歩先へと踏み込んだ意欲作。特に今作はプロデューサーを務めたBECK とのコラボレーションを含めアコースティックな側面や実験的な側面を持つとてもパーソナルな作品だ。しかし、前作同様彼のエンター
-
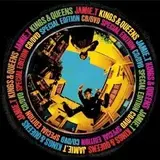
-
UK版BECKとも謳われるJAMIE Tのセカンド・アルバムがいよいよ日本発売となる。2007年に発表されたファースト・アルバムは天才誕生を予感させる傑作で、本国では賞賛を持って迎えられたが、残念ながら日本ではほとんど相手にされなかった。J
-
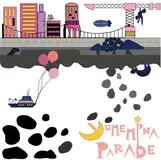
-
京都発3ピース・バンドの2ndミニ・アルバム。間にシングル、EPもリリースしているものの、ミニ・アルバムとしては前作『細胞ディスコリウム』からおよそ5年ぶり。「メランコリックサバイバー」を聴くと、昨今の四つ打ちダンス・ロック的なバンドがまた
Warning: Undefined property: stdClass::$ReleaseDate in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-japanese_breakfast.inc on line 40
Warning: Attempt to read property "DisplayValue" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-japanese_breakfast.inc on line 40
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-japanese_breakfast.inc on line 40
Warning: Undefined property: stdClass::$Manufacturer in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-japanese_breakfast.inc on line 41
Warning: Attempt to read property "DisplayValue" on null in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/inc/flat-japanese_breakfast.inc on line 41

-
フィラデルフィアを拠点として活動するインディー・ロック・バンド LITTLE BIG LEAGUEの紅一点にしてフロントウーマンであるMichelle Zaunerによるソロ・プロジェクト、JAPANESE BREAKFASTがUSレーベル
Warning: include(../calendar/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 141748
Warning: include(): Failed opening '../calendar/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 141748
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号









