DISC REVIEW
L
-

-
LACCO TOWER
青春
来年結成20周年を迎えるLACCO TOWERが放つ、"20年積み重ねた青春"を詰め込んだアルバム『青春』。しかし彼らが語る"青春"は、いわゆる"キラキラした青春"ではない。忘れたい過去も苦い思い出も今思い返してみれば青春だった、そんな"今だからこそ感じる青春"が表題曲では歌われている。歌謡曲的なメロディとロック・サウンドが融合した、ラッコらしさを前面に押し出す「化物」から、洗練されたアレンジでラッコの新しい音世界を見せる「雪」まで、20年の軌跡を辿るような楽曲群。きっと彼らは、"綺麗ではないから美しい"この青春を、ジャケットのドライフラワーのように美しいままこのアルバムに閉じ込め、それを胸にまた歩き出すのだろう。彼らの青春はまだまだ終わらない。
-

-
LACCO TOWER
闇夜に烏、雪に鷺
コロナ禍の中、メジャー・デビュー5周年を迎えたLACCO TOWERが世に問う完全生産限定の3枚組(2CD+DVD)。メジャー移籍後の5年の軌跡を振り返りながら、その間、発表してきた曲の中から全22曲を厳選し、曲が持つカラーから11曲ずつ黒盤と白盤に収録した。TV アニメ"ドラゴンボール超"のエンディング主題歌だった「薄紅」をはじめ、白盤にはアンセミックな曲が多めに選ばれてはいるものの、黒と白だから単純に動と静、暗と明とならないところが、LACCO TOWERの魅力であり、彼らがテーマにしてきた人の心の恐ろしさ。ラウドロックとエモと昭和歌謡が絶妙に入り混じる、唯一無二のサウンドとともに味わいたい。DVDには黒盤、白盤に選ばれていない曲も含め、MVを16曲収録。
-

-
LACCO TOWER
変現自在
現在のLACCO TOWERには迷いがこれっぽっちもないことを印象づける、メジャー5thアルバム。持ち味のひとつであるエキセントリックな魅力を抑えつつ、歌謡メロディとエモーショナルなロック・サウンドを掛け合わせた、LACCO TOWERらしさを粛々と追求した。その結果、アレンジの洗練と共に曲そのものの良さがこれまで以上に伝わる、ある意味聴きやすいアルバムになっている。その中で、長年のファンならば、ふんだんにフィーチャーしたコーラス・ワークや、「必殺技」のダンサブルなサウンド、得意の不倫ソング「不機嫌ノ果実」における第三者の視点の導入といった、新たな挑戦にも気づくはずだが、そんな変化が印象づけるのは、結成18年目を迎えたLACCO TOWERの新境地だ。
-
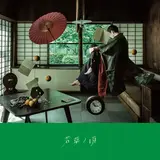
-
LACCO TOWER
若葉ノ頃
LACCO TOWERが持つ黒いイメージに振り切った『薔薇色ノ怪人』。そして、白いイメージに振り切った『遥』。その2枚を経て、「狂喜乱舞」のようなロック・ナンバーから「最果」のようなバラード、そして得意の不倫ソングの「薄荷飴」まで、黒と白のイメージがちょうどいい塩梅で溶け合うメジャー4thフル・アルバム。これまで搾り出すように作っていた彼らがこれは自分たちの中から滲み出てきたものだけで作ることができたという。メンバーたちは本当の意味で、これが自分たちの最高傑作と感じているようだが、そういう感じる理由は、そんな境地に達したことに加え、結成から16年経ってもなお成長していけると思えたことにもあるらしい。聴きながら、最高傑作を"若葉ノ頃"と名付けた理由をしっかりと噛みしめたい。
-

-
LACCO TOWER
遥
"ドラゴンボール超"のエンディング主題歌「遥」を含む、LACCO TOWERによるメジャー3rdアルバム。実は2017年3月にリリースしたミニ・アルバム『薔薇色ノ怪人』と制作がほぼ同時進行だったそうで、同作とは逆の方向性――彼らの曲を黒と白に分けるなら、白の方向に振り切った作品を目指したという。たしかにバラードとも言える「遥」がオープニングを飾っていることに加え、激しい曲がいつもよりも少なめということもあって、LACCO TOWERが持っていたエグさが薄まって、これまでよりも聴きやすい作品になっている。しかしそのぶん、1曲1曲に込めた思いはより深いものに。言い換えれば、音数が整理されたことで、歌詞に込めた生々しい感情がより際立った印象がある。物足りなさは全然ない。
-
-
LACCO TOWER
心臓文庫
前作『非幸福論』も、もちろんいいアルバムだった。しかし、それから1年ぶりにリリースする、このメジャー第2弾アルバムを聴いてしまうと、前作は若干、ストレートすぎたかも!? ラウドロック・バンドと共演しても引けを取らない演奏はさらにハード・ロック/ヘヴィ・メタル色を増す一方で、J-POPとしても十二分に勝負できるメランコリックな歌の魅力はさらに磨きがかけられている。エキセントリックなロック・ナンバーから哀愁のバラード・ナンバーまで、多彩な曲は"狂想演奏家"を名乗る彼らの面目躍如。そのうえで、LACCO TOWERらしさやクセを強調したアレンジが曲をより聴き応えあるものにしている。ストレートな彼らも、もちろんいい。しかし、"掘れば掘るほど面白い"とメンバー自らが主張する魅力なら断然こちらだ。
-
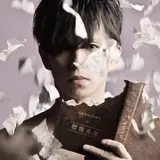
-
LACCO TOWER
非幸福論
日本のロックの伝統を受け継ぎながら、今の時代にふさわしい激情、熱情も持ち、場合によってはラウドロック勢にも負けないアグレッシヴな演奏をする5人組、LACCO TOWER。そこが、彼らが自ら"狂想演奏家"と名乗る所以。そんなLACCO TOWERらしさを前作以上に追求した5作目のアルバム。かつてTHE YELLOW MONKEYやTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTを輩出したTRIADレーベルからのメジャー・デビュー作――ということで、改めて自分たちらしさを打ち出してきた印象だ。激情あふれるロック・ナンバーに加え、バラード、昭和歌謡風......と、前作同様に多彩な曲を考えれば、ことさら激しい作品を作ろうとしたわけではないのだろう。それでも攻めているように感じられるのは、今の彼らに勢いがあるからだ。
-
-
LACCO TOWER
狂想演奏家
攻撃的なだけじゃない表現の追求がテーマの1つだったという。それにもかかわらず、音像は十二分にささくれだっている。それはやはり、バラードを歌ったとしても彼らはあくまでもロック・バンドだからだ。狂想演奏家を名乗る5人組による4作目のフル・アルバム。昭和歌謡を思わせる歌メロと日本語の歌詞、そして連打するピアノが存在のユニークさを印象づける激情ロックは彼等が掲げたテーマどおり、多彩なアプローチによってさらなる広がりをアピールしている。中にはポスト・パンク的なヒネリやニュー・ウェイヴ的な煌きを感じさせる曲もある。自主レーベルからリリースする初めてのアルバムということで、新たな出発という気持ちもあるにちがいない。幸せとは言えない現実を歌いながら、それでも自分たちは歌いつづけるというメッセージはバンドの新たな誓いにも聞こえる。こんな時代だからこそ、彼らの歌を必要としている人は多いはずだ。
-

-
LACCO TOWER
心枯論
今年バンド結成10周年を迎えるLACCO TOWER。メモリアル・イヤーに放たれるアルバムには、不思議なことに“総まとめ”や“安住”といった雰囲気が一切ない。より獰猛になった図太いバンド・サウンド、懐かしさや憂愁を纏ったメロディが走ったリ跳ねたり転げ回ったり……雑味なしの攻め100%盤だ。和心溢れるキーボードと絡まった絶唱混じりのヴォーカルが一気に加速していく「柘榴」、轟音リフとグルーヴ“これでもか!”な応酬「蛹」など、明日への意志を託したラスト・ナンバー「一夜」まで、一切合財聴きどころの金太郎飴状態。身を切りながら、いつでも心を枯らすほどの表現をしてきたこのバンドだからこそ掴めた“進化”がパンパンに詰め込まれた、唯一無二のロック・アルバム。
-

-
LADY GAGA
Harlequin
映画"ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ"で自身が演じるキャラクターにインスパイアを受け制作されたアルバム『Harlequin』は、ジャズを基調とした楽曲を中心に、ドリーミーな心地よさが感じられるTrack.4「World On A String」、サックスが絡み異国情緒漂うTrack.7「Smile」等、ミュージカルを鑑賞しているかのようなサウンド、楽曲構成が印象的な1枚。要所に収録されたゴスペルやフォークの名曲カバーは彼女の世界観をより深く覗かせるように、作品に立体感を与えている。世界のポップ・アイコンが"道化師"となって提供したエンターテイメントは圧巻だ。陽気な雰囲気のなか、本作では異質な不穏さが同居するTrack.8「The Joker」のサビにおける唯一無二のフロウには舌を巻く。
-

-
LAGITAGIDA
CartaMarina
2010年4月に結成し、今年はSXSWの出演も決定している攻撃型3ピース・インスト・ロック・バンドLAGITAGIDA(ラギタギダ)。昨年リリースされたミニ・アルバム『CaterpiRhythm』も耳を劈くような爆音と緊張感に身震いが止まらなかったが、今作はそこから更に進化している。目まぐるしくスピードを上げ暴れ回る3人の音像は強靭さを増し、その中に美しく輝くピアノとの相性も抜群。そのバランスが熱さをクール・ダウンさせるようでありながらも、尚スリリングに響くから不思議である。そしてそれが非常に心地良い。「Huntin'」では鮮やかなキーボードやハンズ・クラップを入れたりとキュートでポップなサウンド・アプローチも見せ、懐の広さを伺わせる。これぞアバンギャルドの真骨頂!
-

-
LAID BACK OCEAN
色+色
斬新な発想力と大胆不敵な行動力。そして、確固たるメッセージ性と縦横無人で自由な音楽性。LBOがそれらを武器にしながら駆け抜けてきたここまでの10年間は、決してなだらかなだけのものではなかった。だが、彼らはどんなときでも現在進行形であることを志し、常に未来に向かって歩み続けてきて今このときを迎えている。満を持してのベストとなる今作では過去曲たちの多くに、"色+色 ver."もしくは"色+色 mix"という形でアップデートが施されている点が、実に興味深い。新曲「COLOR COLOR」の仕上がりも秀逸な一方、特別BOX仕様 限定盤におけるDVD にはフロントマン YAFUMIの盟友、 UVERworldのTAKUYA∞(Vo)が手掛けているMV「YSC」も収録。全編がクライマックス!
-
-
LAID BACK OCEAN
DEFY
ゴボウのアク抜きや皮むきを推奨するレシピや料理家は、どうも好きになれない。ゴボウは、そのアクさえもうまく利用しながら調理してこそ、芳醇な香りや滋味深い旨味が得られるものだと個人的には信じて疑わないからである。似たようなことは音楽にも言えることが多々あり、例えばLBOは今作において、自らの醸し出す癖やアクを最上級の味わいへと導くことに成功したのではなかろうか。新ベーシスト、SHOUYAを交えることでキレ味を増したサウンドといい、フロントマン YAFUMIの紡ぐ強い意志に満ちた歌詞といい、ミックスをギタリスト、KAZUKIが手掛けている音像のあり方といい、ここにきてLBOは今まで以上に濃厚な逸品を仕上げたと言っていい。素材を丸ごと生かしたこの醍醐味をぜひご堪能あれ!
-

-
LAID BACK OCEAN
NEW MOON
暗い新月の夜。それが意味するものは、次へと向けた始まりなのではなかろうか。8年の活動歴を経ての1stフル・アルバムで、彼らはあえてベスト盤的な構成を避けたと言う。故に、どこか思わせぶりな「TOILET REVOLUTION」から始まる今作は、全編が安パイには寄らない積極的な攻めの姿勢にて描かれてゆく。例えば、リード・チューンである「Million」には日頃から実際に"走り続けている"YAFUMI(Vo)の経験と人生観が。バンド名の一部を曲題に織り込んだ「MOTHER OCEAN」では軽妙なウィットとある種の真実を。また、今作のために新録された「SHINE (NEW MOON ver.)」には、すべての生きる人たちへ向けた賛辞と救いまでが込められているのだ。KYOHEI(Ba)が手掛けたアートワークにも注目!
-

-
LAID BACK OCEAN
Bifröst
ピアノ・ロック・バンドLAID BACK OCEANの2ndアルバム。美しいピアノの旋律のイントロを聴けば、どこか夢をみているような不思議な心地になるだろう。そのまま身を委ねて、どっぷりと彼らの世界に浸かることをお勧めする。前作から7カ月という短いスパンでリリースされたにも関わらず、ノスタルジックな世界観はそのままに、以前よりも更に自由で伸びやかに鍵盤と弦楽器が共鳴している。バンドの成長の早さに、舌を巻かずにはいられない。ライヴで演奏されてきた楽曲を中心に構成された今作は、ソールド・アウトとなった日比谷野外音楽堂でのライヴ映像や今作のメイキング映像を収録したDVDとの(限定盤)。ライヴ・パフォーマンスに定評のある彼らの魅力も存分に楽しめるのではないだろうか。
-

-
la la larks
ハレルヤ
UKソウルっぽいとも言えるアダルト・オリエンテッドな表題曲のテイストが新境地とも言える、la la larks約1年ぶりのニュー・シングル。School Food Punishmentの内村友美(Vo)とStereo Fabrication of Youth他の江口 亮(Key)を中心にロック界の凄腕が集った5人組。そういう顔ぶれで大人っぽい洗練が感じられるポップスを演奏する意外性とエレクトロニカの要素も加えた曲調とは裏腹に、演奏そのものはかなりアグレッシヴというふたつ の意外性を楽しむことができる。坂本真綾に提供した「色彩」のセルフ・カバーが印象づけるのは、一見クールそうなこのバンドが持っている底力だ。それぞれに主張しあうプレイがせめぎあうさまは、まさにスリリングのひと言。
-

-
la la larks
ego-izm
内村友美(School Food Punishment)、江口 亮(Stereo Fabrication of Youth)、三井律郎(THE YOUTH)、クボタケイスケ(Sads)、ターキー(GO!GO!7188)という、様々なバンドでキャリアを積んできた5人によって2012年に結成されたla la larksが1stシングルをリリース。ピアノとストリングスとがドラマティックに絡み合い、内村のエモーショナルな歌とのハーモニーで壮大なロック・サウンドを生みだす表題曲、「end of refrain」ではモダンで晴れやかなエレクトロ、そして「earworm」はドリーミィな音響とノイズの波に美しいメロディがたゆたう。3曲3様で、バンドの音楽的な懐の深さを提示する内容となっている。いずれも構築的かつイマジネイティヴなサウンドで、高密度のドラマや映像的な高揚感がある。アルバムへの期待値が上がる1枚だ。
-

-
LAMA
New!
有名ミュージシャンが集まって結成されたスーパー・バンドといえば、今年Mick Jaggerを中心としたSUPERHEAVYが大きな話題をかっさらったが、我が国にはそう……LAMAがいる!そんな彼らの初となるアルバムが本作だ。ナカコーとフルカワがヴォーカルを担い、ロック / ダンス的な展開により後期スーパーカーの延長線上にある音楽になるのではという勘繰りもあったが、中核を成す田渕ひさ子のメタリックで切れ味抜群のギターと、3人とは最も出自の異なる牛尾憲輔の音像の巧みな効果の貢献度が高く、予想とはまた異なった化学反応の着地を見せている。このバンドの面白さは、4人の“らしさ”が全方位に向きながら、うまく成立しているところ。それを可能にしているのは、一重に彼らの度量の大きさか!
-

-
LAMA
Cupid/Fantasy
ナカコー、フルカワミキ、田渕ひさ子、牛尾憲輔と名前を聞いただけでもワクワクさせるメンツによるバンド・LAMA。今作はアニメ「UN-GO」エンディング・テーマとしてもオンエア中。4人の力が惜しみなく発揮され、ナカコーとフルカワの掛け合いは鮮やかにグラデーションしていくような華やかさがあり、フレッシュでキラキラしたサウンドを聴かせてくれる。M-2「Fantasy」はピアノの旋律が美しく、ナカコーの声がドリーミィに浮遊し、ソフトで繊細なサウンドを展開。往年のファンも新規で聴く人も、この切ない“甘酸っぱいドキドキ感”に胸を打ち抜かれてしまうだろう。消えてしまいそうな儚い煌きに酔いしれたい。11月30日には待望のアルバム『New!』をリリース!
-

-
LAMA
Spell
話題沸騰の新バンドLAMAの1stシングル。元SUPERCARのナカコー、フルカワミキに加えbloodthirsty butchersの田渕ひさ子、agraphの牛尾憲輔の四人が始めた新バンドという事で興奮を押さえられない音楽ファンは筆者だけじゃないはず。SUPERCAR、そしてNUMBER GIRLというバンドに胸を焦がした人にしてみれば期待するなという方が無理な話だ。ただ今作は、バンドを改めて結成したという4人の初々しい気持ちが詰まったフレッシュなダンス・ポップ。牛尾憲輔とナカコーが作り出す繊細なビートにフルカワミキの柔らかな歌声と切ないギター・フレーズが絡み合うフラットなダンス・ミュージック。ここからまたどのような化学反応が生まれて来るのか楽しみでならない。
-

-
LAMP IN TERREN
FRAGILE
"FRAGILE"というタイトル通り、傷つきやすくなった心に丁寧に触れるような、音や言葉のひとつひとつに誠を尽くした全10曲を収録。距離を置いた生活をしなければならない今、中でもまず胸に飛び込んでくるのが「宇宙船六畳間号」。星が瞬くようにキラキラと光るサウンドと浮遊感で、部屋の中から宇宙を描くこの曲。"気持ちと想像で君の形に触れる"、"僕ら確かに繋がっている"の詞に彼らの粋な実らしさが滲む。また、クワイアのスケール感が彼らとしては新しい「EYE」、アコギ片手に松本 大(Vo/Gt)の日常と本音を歌にした「いつものこと」など音像の幅も見せながら、すべてを総括するように、そんな人や世界の危うさと共生していく決意を示す、繊細且つ芯のある表題曲で締める流れも美しい。
-

-
LAMP IN TERREN
silver lining
長崎県で結成され、東京を中心に活動をしている3ピース・バンド、LAMP IN TERRENが"希望の光"という想いを込めたメジャー・デビュー・アルバムをリリースする。"この世の微かな光"という意味を持つバンド名を掲げた彼らは、思えばいつも光について大きな意味を持たせていた。全身を震わせて叫ぶような松本大の力強い声で歌われる歌詞には、どこか捨て鉢になっていながらも、決してすべてを諦めないという確かな意志や願いがある。それはまるで届かない光に向かって必死に手を伸ばすようにもどかしく、途方もない姿だが、本来人間はそういうものだ。ろうそくの様に小さくて温かい光がゆっくりと足元を照らしていくような、彼らにとって確かな指針になる作品。
-

-
LAMP IN TERREN
PORTAL HEART
長崎出身の3ピースによる1stミニ・アルバム。このLAMP IN TERRENというバンド名には"この世の微かな光"という意味が込められているという。そして、名は体を表すもので、その音楽もまさに"この世の微かな光"を照らし出すようなものだ。曲の主人公は常に"自分とは、心とは、命とは何なのか?"という自問自答を繰り返し、世界の大きさに震え、誰かのことを想い、時に孤独の雨に、時に希望の陽光に晒される。ある意味、人間ひとり分しかない、ちっぽけな歌だ。しかしながら、力強い歌声と荒々しく、しかし煌くようなメロディを奏でる演奏は、人ひとり、その身体にしか宿らない光を確かにその音に刻み込む。この世の広さに比べれば、苦しくなるほどに等身大な"人間"の歌。世界で最もくだらなく愛おしい賛美歌。
-

-
Lana Del Rey
Chemtrails Over The Country Club
郷愁と憂いの時を誘う歌声、気だるそうに問わず語りするようなヴォーカルは、虚ろであり同時に甘美な空気を纏う。そんな歌は今作でも健在だ。グラミー賞の最優秀アルバムにノミネートされた前作『Norman fucking Rockwell!』から1年半ぶりで、前作同様Jack Antonoff(FUN. etc.)とのタッグで作り上げた。Taylor Swiftなど女性アーティストの作品を多く手掛け、それぞれの独自性を引き出しつつヒット作品に結びつける手腕は大きく、LANA DEL REYもまた信頼を置いているのだろう。生楽器で丁寧に作り込まれて、必要最小限という趣だけれども彼女のムード、紡ぎ出す言葉の余韻となってその曲を深く色づけている。クラシカルだが、随所で効いた音の遊びが彼女のポップ性とマッチしている。
-

-
Lana Del Rey
Ultraviolence
David Lynch作品にも通じるデカダンを打ち出して、ノスタルジーは美しいものという幻想を破壊した前作『BornTo Die』から2年、"ギャングスタ界のNancy Sinatra"を謳い(Nancy Sinatraの「Summer Wine」のカヴァーは秀逸!)、ショウビズ界の堕天使を演じるLana Del Reyがリリースした2作目のアルバム。その世界観こそ変わらないものの、サウンド的に前作のトリップ・ホップ路線を改め、ストリングスやピアノも使いながら生音を意識したことで、R&Bの要素をはじめ、彼女が作る悲劇的なバラードの芯にある魅力がより剥き出しになった印象だ。プロデュースはこのところ、プロデューサーとして立てつづけにいい仕事をしているTHE BLACK KEYSのDan Auerbach。彼の代表作になることは間違いない。
-

-
LANY
gg bb xx
LAのシンセ・ポップ・バンド LANYが、前作からなんと11ヶ月という短いスパンで新作アルバムをリリース。もともと多作なバンドではあるが、今作に関してはより彼らをクリエイティヴにする状況があったのだろう。前作は、誰もが身近な人との絆の大切さを再確認したパンデミックのなか、自身の家族や育った環境にフォーカスしたアルバム。だが、今作はそういったテーマを設けず、自由に日常を切り取ったのだという。2017年の1stアルバムからヒット作をリリースし続け、大きく動いた日常を自身の中で整理するような意味もあったのかもしれない。そのためか、サウンドのアプローチにも自由度があって、思い出の写真をめくるようなワクワク感がある。魔法のようにカラフルなLANY流ポップをぜひ堪能してほしい。
-

-
LANY
Lany
全米ビルボードの新人アーティスト・チャートで1位を獲得、"SUMMER SONIC 2017"への初出演、初来日が決定と、注目を集めているLA発3ピース・バンドの1stアルバム。"世界で一番美しいセツナ・ポップ"というキャッチフレーズどおり、「The Breakup」を始めとする楽曲で聴かせるPaul Klein(Vo/Key/Gt)の儚げな歌声は言葉の壁を越えて胸に迫るものがあり、聴いているうちに徐々に引き込まれる魅力がある。「Super Far」、「Overtime」など、シンセを中心として作られているサウンドには80sのニュー・ウェーヴ、ニューロマンティックの匂いがあり、2014年結成の彼らが楽曲になぜこうしたアレンジを施すようになったのかが興味深い。途中、セリフだけの「Parents」を挟み、日本盤ボーナス・トラック6曲を含め全22曲という大ボリュームの1枚となっている。
-

-
Large House Satisfaction
Highway to Hellvalley
自主レーベル"小林田中時代"から初めてリリースするミニ・アルバム。天性のしゃがれ声を持つ小林要司(Vo/Gt)のヴォーカルは、これまでもバンドの名刺代わりとして異彩を放ってきたが、今作では"名刺程度では生温い"と言わんばかりの熱量が全楽曲から漏れ出している。タイトルからAC/DCへのオマージュを捧げ、冒頭「sHELLy」からは伝統的なジャパニーズR&Rを更新するギラついた殺気を纏っている。ブルージーな入りからTHE BEATLES「Hey Jude」を彷彿とさせる展開の「STAND」ではロックという音楽の寛容さを感じとれるだろう。音楽ジャンルとしてではなく"ロックンロール文化"そのものを高らかに掲げた彼らは、今作を機に"ロック・バンド"を背負う頼もしい存在となり得るかもしれない。
-

-
Large House Satisfaction
SHINE OR BUST
約1年振りとなるミニ・アルバムは、前作で試みたポップなメロディ、サウンド・アプローチをさらに明確にした作品。リード曲「Crazy Crazy」のシンプルで単純明快なギター・リフ、ストレートなリズム隊の演奏はメロディの良さを存分に活かしたもので、しゃがれ声を封印して歌う小林要司(Vo/Gt)のクリアで色気のあるヴォーカルもこれまでにない魅力を聴かせてくれる。一方で、SNSをテーマに怒りに満ちた歌と演奏で突っ走る「セイギノシシャ」、スケールの大きなサウンドを聴かせる「SHINE OR BUST」、矢継ぎ早に言葉が出てくる「Child Play」は観客の熱狂ぶりが浮かんでくるようなライヴ感満点の楽曲。これ以上ないカッコいい演奏といいメロディが詰まった、間違いなく彼らの代表作になるであろう傑作!
-

-
Large House Satisfaction
Sweet Doxy
賢司(Ba)と要司(Vo/Gt)の小林兄弟と田中秀作(Dr)からなる3人組が前作から1年3ヵ月ぶりにリリースするミニ・アルバム。ギミックに頼らない、今時珍しい正統派のロックは、そこに嗄れ声で吠えるように歌う要司のヴォーカルが加わることでキョーレツなインパクトを生んでいるが、その意味ではすでにライヴ・アンセムになっているTrack.1「トワイライト」よりもメロウなTrack.2「Jealous」や明るいTrack.3「Stand by you」のほうが聴きどころと言えそうだ。ガレージ・ロックからバラードまで、限られた編成の中で曲ごとに変化をつけるアレンジも見事だが、今回、初めて"女性"や"恋心"をテーマにしたことも曲調を広げるきっかけになったのかも。いろいろな意味で広がりが感じられる充実作だ。
-

-
Large House Satisfaction
HIGH VOLTEX
小林要司 (Vo/Gt)と賢司 (Ba)の兄弟と田中秀作 (Dr)からなるスリー・ピース・バンドLarge House Satisfactionのニュー・アルバム、この作品は新たな彼らの1stアルバムといっても過言ではないくらいの新鮮なパワーに溢れた作品だ。シングル『Traffic』で提示したシンプルかつキャッチーでありながら、ロックのダイナミズムと黒いグルーヴはそのままに更なる音楽的な広がりを見せている。今作のリード・トラックの「Phantom」からTrack.7のLHS流ダンス・ロックの「Jah」、メイン・ストリームへのアンチテーゼかのようなポップなアプローチなどTrack.10の「タテガミ」など、一気に駆け抜ける11曲。彼らの物語の新たな始まり、それにしてはあまりにも鮮烈なインパクトを残していく。
-

-
LA ROUX
La Roux
南ロンドンで結成された二人組ユニットLA ROUXのファースト・アルバム。近年DIY感覚を持った女性ヴォーカルの作品が流行しているが、ビートの強度で言えばこのLA ROUXが頭一つ飛び抜けている。まぁトラックを作っているBenの存在が大きいのだけれど。そういう意味ではTHUNDERHEISTと感覚が似ているのかな。80’sを彷彿とさせるニューウェーブとエレクトロ・サウンドを配合させ、時に声変わり前の少年の声をも彷彿とさせるEllie のハイトーンヴォーカルが巧妙に絡み合い、アンニュイな輝きを放っている。KITUNE所属アーティストだからといって、難しく考えなくていいんです。純粋に楽しいエレポップ・アルバム。
-

-
LA SERA
Hour Of The Dawn
今年、惜しくも解散してしまった2000年代後半のUSインディー・シーンを代表するガールズ・バンド、VIVIAN GIRLS。そのベーシストだったKaty Goodmanのソロ・ユニット、LA SERAの3rdアルバム。僕は取材で1度本人に会ったことがあるが、その凛とした美貌、そして何より"わたし、あんたに興味ないわ"というのをあまりにストレートに態度で表現してしまうそのクール・ビューティっぷりに、思わず"踏まれたい"と心の中で呟いたものである。本作はそんな彼女の才色兼備な魅力が過去最高に詰まった作品で、持ち前の60年代ポップス的メロディアスなソングライティングは更に磨き上げられ、それと同時に今までになかったヘヴィでハード・エッジなロック・チューンも目立つ。もはや"インディー・クイーン"の称号すら小さく見える傑作だ。
-

-
LA SERA
Sees The Light
昨年BLACK LIPSと共にカップリング・ツアーを行ったUSインディ界のアイドル・ガレージ・バンド、VIVIAN GIRLS。ここ日本でも刺激的かつチャーミングなパフォーマンスで多くの音楽ファンを魅了した彼女らだったが、そのルックスと佇まいでとりわけ男子をノック・アウトしたベーシストのKaty Goodmanがソロ・ユニットLA SERAとして、こんなに愛くるしい作品を作っていたとは!ニューヨークからカリフォルニアへと住まいを移したという点も制作に影響しているのか、レイド・バックした心地よいドリーミーさが漂い、VIVIAN GIRLSで聴けるメロディやコーラスの美しさを更にクリアーな形で全面に押し出したことによって、かなりポップでキュートな仕上がりに。たまりません。
-

-
THE LAST BANDOLEROS
The Last Bandoleros EP
メキシコとの国境に面したアメリカはテキサス州の4人組バンドのデビューEP。その堂々としたテクスメクスはまさに広大な土地からもたらされたアメリカンとメキシカンのいいとこ取り。ブルース、カントリー、ロカビリーと元は黒人文化が発祥となる音楽様式からの影響は、オープニング・ナンバーである「Maria」からしっかりと確認できる。一見単調に思われる流れに喜怒哀楽を与えているのは、ハーモニカやバンドネオンといったトライバルな楽器群、そしてそれらに豊かさをもたらす抜群のコーラス・ワークも聴きどころのひとつだ。そんな彼らを最も評価しているのがStingで、現在敢行中のワールド・ツアーにも帯同させるほど。そして6月に開催される武道館公演にてStingとともに来日も決定。そのスキルフルな演奏とダーティな佇まいに一目惚れすること間違いなし。
-

-
THE LAST DINNER PARTY
Prelude To Ecstasy
英国ロックの新たなスターとして世界から熱視線を浴びるロンドンの5人組ガールズ・バンド、THE LAST DINNER PARTYがついに待望の日本デビュー。本作は、本国ではすでに今年2024年の2月にリリースされているアルバムなので、すでにその存在は日本のロック・ファンからも認知されつつあるだろうが、せっかく国内盤が出るので、未聴の方はこの機会にぜひチェックしてほしい。これぞUKサウンドなアイロニーと退廃的な美意識を感じるロック・サウンド。これがデビュー作とは思えないほどの堂々たる"達観した"ロック・スタイル。攻撃的で刺激的な音楽でガンガンにテンションを上げるよりも、ダウナーで神秘的なサウンドにひとりで沈み込みたい、そんなときにおすすめな中毒性のあるアルバム。
-

-
LASTGASP
PLAYER
辿り着くべくして、今この機にLASTGASPは原点という名の初心に回帰したことになるのだろう。懲りすぎず、飾りすぎず、でもそれでいて貫くべきところは徹底的に貫く。そのスタンスをもって織り成されている音たちは、どの曲においても実に潔いほど凛としている。歌詞の面では日本語の機微を生かしたものが多いのも特徴で、「ワンルームデイドリーマー」での彼らいわく"中二病"感が絶妙に描かれた作風は特に秀逸。ゆえに、今作がLASTGASPにとって今後へ向けた重要な礎となっていくことは疑いようもない。無論、これらの楽曲たちは今後ライヴの場においても強い存在感を放っていくことになるはずで、その意味でも今作はLASTGASPにとっての近未来を明確に感じさせるものとなっているのだ。
-
-
LASTGASP
stair
劇場版アニメ"弱虫ペダル"の主題歌として起用された「Link」や、新機軸の曲が詰まったシングル『GO e.p.』など、LASTGASPの新たな試みを1枚にしたアルバム。アレンジャーを交えての楽曲制作を行い、バンドが追い求めたいサウンドを実現するためより大胆に、また細部にこだわって作り上げた曲が揃った。疾走感のあるサウンドと、自分自身を奮い立たせるメッセージを込めた歌を綴ってきた4人だが、今回はサウンドのレンジを広げ、様々な方法でその心模様を表現する。がむしゃらに走るばかりでない、どこかやるせなさも背負った気持ちをヘヴィなサウンドで表し、「羽根」では"羽根の無い僕らにも朝は来る"と少しずつたくましくなっていく過程を丁寧に歌い上げた。バンドで伝える楽しみを色濃くしたアルバムだ。
-

-
LASTGASP
GO e.p
ハンドクラップが似合う、ファンキーなイントロで始まるロックンロールな「GO」。これまで、アニメ"弱虫ペダル"主題歌となった「Determination」や「Days」のような疾走感のある曲や、切なくエモーショナルな曲を得意としていた4人だけれども、今回のシングルでは骨太なバンド感やワイルドさが強調されたサウンドとなった。曲作りの初期段階からアレンジャーを交え、通常のセッション的に作り上げる手法とは違った制作になったという。ライヴで映える曲、こんなライヴのシーンが見えるという曲を想像しながら具体的に音に落とし込み、ノリや躍動感を重視した。新しい試みのある制作で、その振り切った勢いがあったからか、歌に込めた思いも挑戦的に突き進む内容。バンドのこれからに向けたファンファーレ的な曲になった。
-

-
LASTGASP
the Last resort
もともとは、2015年7月にCDリリースしたLASTGASPの1stアルバム『the Last resort』が、この4月に改めて配信リリースされることになった。インディーズながら、人気アニメ"弱虫ペダル"の主題歌を手掛け、その主題歌を含む渾身のアルバムを経て、ツアーを敢行し、ここからまた大きくステップアップして行こうというタイミングで、全世界に向けての配信となる。メロディック・バンドの勢いやアンサンブルのスピード感、J-POPにも通用するキャッチーなメロディ、エモーショナルな歌、コブシを振るだけでなくじっくりと聴かせる曲など、得意な技と武器となるものをフルで使いながら曲を作り上げている4人。何かにぶつかって葛藤してヘコんでも、しっかりと立ち上がってまた走り出していく。そんな前向きでまっすぐな歌で、人生を大立ち回りしている汗臭さがいい。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























