DISC REVIEW
V
-
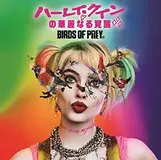
-
V.A.
Birds Of Prey: The Album
"スーサイド・スクワッド"でも屈指の人気を誇るスーパー・ヴィランを主役に据えた映画"ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY"のサントラは、ハーレイが作中で結成するガールズ・チームよろしく、個性豊かな女性ミュージシャンが集結。ド派手なアクション・シーンが目に浮かぶような、HALSEYによるヘヴィ・チューンのTrack.8を筆頭に、元FIFTH HARMONYのNORMANIが注目のラッパー MEGAN THEE STALLIONとコラボしたTrack.3、映画に登場する歌姫 ブラックキャナリーがJames BrownをカバーしたTrack.13など、次世代のアーティストが自由に躍動している。劇伴としてだけでなく、今の音楽シーンを知るうえでもおすすめ。
-

-
V.A.
TVアニメ「どろろ」音楽集-魂の鼓動-
50年ぶりの再アニメ化が大きな話題を呼んでいる手塚治虫による未完の傑作"どろろ"。その主題歌を担当するアーティストは発表されるたびに大きな話題になってきた。第1クールは女王蜂「火炎」とamazarashi「さよならごっこ」、第2クールはASIANKUNG-FU GENERATION「Dororo」とEve「闇夜」という世代を超えたラインナップだが、いずれも"どろろ"の時代背景や凄惨な世界観にリンクする傑作揃い。まさに"どろろ"という作品に出会わなければ、生まれなかったであろう、幸福なコラボレーションによって完成した楽曲たちだ。今作はそんな歴代主題歌をTVサイズで収録したDisc1のほか、全33曲70分を超える劇伴を収録したDisc2の2枚組になっている。
-

-
V.A.
Kitsune Maison Compilation 12
フランスの総合アート集団KITSUNEが送り出す人気シリーズの第12弾。一時期の勢いは衰えたものの、このシリーズは今日の音楽シーンを捉える意味でも、ブレイク間近の新人さんをチェックする意味でも重要な1枚。このコンピが優れているのはただの寄せ集めではなく、一枚を通してのバランスと統一感がいいというところ。センスの良さ含めこれだけ息の長いシリーズになったのはやはりKITSUNE独特のカラーがしっかりとアルバムを通して感じ取れるからだろう。今作はMark Ronsonの新曲を始め、LADY GAGAの「Born This Way」のプロデュースも務めたWHITE SHADOW等、しっかり旬所を押さえたセレクト。個人的なおススメは軽快なギター・リフと口笛が印象的なNEW NAVY。
-

-
V.A.
Kitsune Parisien
こんなに安心して聴けるコンピレーション・アルバムって他に存在するのだろうか?それほどまでに、揺るぎない地位を確立した『Kitsuné Maison』。そして早くもキツネから新しいコンピレーション『Kitsuné Parisien』が登場!キツネ・レーベルのボス、Gildasとパーティ番長のAndreが地元パリのニュー・カマーを厳選して収録。中でもTrack.8のBEATAUCUEというまだ若干20歳のテクノ・デュオの存在感には圧倒されてしまう。既に昨年キツネからデビュー・シングル(デジタル配信)も発売されており、今回収録された「Behold」は所謂現代のテクノなのだが、20歳でこのサウンドを生み出せるとは末恐ろしい。パリの音楽シーンの新時代到来の予感がする。
-

-
THE VACCINES
Pick-Up Full Of Pink Carnations
アルバム名は間違って記憶していたDon McLeanの「American Pie」の歌詞に由来するそうだが、喪失を歌った名曲をタイトルに用いたことは本作にとって最適だったと言える。創設メンバー Freddie Cowan(Gt)の脱退を経たTHE VACCINES通算6作目のアルバムは、ノスタルジックなギター・サウンドと切ないメロディで夢の終焉や失恋などの喪失感を描きながら、それらを乗り越え日々を生きていくための前向きさにも満ちた楽曲が並んでいる。キャッチーを発揮したTrack.4、甘酸っぱいメロディで失恋を歌うTrack.6、キーボードが哀愁を誘うTrack.9など、珠玉のポップ・ソングが満載で、これから訪れる出会いと別れの季節にも寄り添ってくれることだろう。
-

-
THE VACCINES
Back In Love City
2011年のデビュー以来日本でも人気を誇るロンドンの5人組ロック・バンド、THE VACCINESがオリジナル・アルバムとしては約3年半ぶりの新作を発表。前作では原点回帰と言うべき泥臭さを持ったギター・ロックを鳴らしていた彼ら。架空の都市をテーマに、RIHANNAなどを手掛けるDaniel Ledinskyをプロデューサーに迎えた今作は、基本姿勢を保ちつつ、80年代シティ・ポップを思わせるジャケットと同様ダンサブルな内容に。裏打ちのビートが夜のネオンとマッチする表題曲に始まり、サーフ・ロックとディスコ・サウンドを絡めたTrack.2、ラウドなギターを響かせるTrack.4、ラテンなメロディもチラつかせるTrack.6など、格段に自由度を広げた楽曲を収めている。
-

-
THE VACCINES
Combat Sports
前作のリリース後に脱退したPete Robertson(Dr)に替わってYoann Intontiが 加入、さらに前作のツアー・メンバーだったキーボーディストのTimothy Lanhamも加入し、5人の新体制となったTHE VACCINES。そんな彼らがリリースする約3年ぶ りの新作は、まさに原点回帰と言えるような、シンプルなギター・サウンドと、荒々し いガレージ・ロックを全面に押し出した痛快なアルバムだ。THE VACCINESの魅力は、30年前の若者が聴いてもなんの違和感もなくクールだと言うだろうし、おそらく 30年後の若者が聴いてもクールだと言うに違いない、そのタイムレスなキャッチーさだろう。今作には、そんな彼らの魅力と、色褪せないギター・ロックの未来が存分に詰まっている。
-

-
THE VACCINES
English Graffiti
前作から3年ぶりのリリースとなる3作目のアルバム。シンセやピアノも使って、ディスコ・ナンバーやピアノ・バラードにも挑戦しながら、ここで彼らが追求しているサウンドは、脱ギター・ロックというよりもむしろ、スタジオにおけるサウンド・メイキングをとことん試した結果と受け止めるべきかもしれない。ノスタルジックなロックンロール・ナンバーが持つ魅力は変わらない。しかし、THE FLAMING LIPSなどで知られるDave Fridmannと主にダンス・ミュージック畑で、いい仕事をしているCole M.G.N.をプロデューサーに迎え、彼らとレコーディングにおけるギミックを存分に使いながら作り上げた新しいサウンドはTHE VACCINESの音楽にロックンロールのひと言には収まりきらない深みを加えている。
-

-
THE VACCINES
The Vaccines Come Of Age
50'Sロックンロールや60'Sポップス、70'Sパンクなどを消化したラウド&ロマンティックなポップス集だった去年のファーストがプラチナを達成。ギター・ロック低迷が叫ばれる英国において救世主的な扱いを受けるTHE VACCINESだが、それがあくまで結果論であり、彼らが純粋に優れたポップ・ミュージックを求めているバンドであることが、このセカンドを聴けばわかる。全体的にまだ荒さも目立っていた前作に比べ、ソングライティングが格段に進化。音楽的参照点に大きな変化はないのだろうが、乱暴に言えばラウドなロックンロールとメロウなバラッドという2本柱によって成り立っていた以前と違い、1曲の中に様々な要素を取り入れ、より表現力豊かになった楽曲が並んでいる。期待を裏切らない充実のセカンドだ。
-

-
THE VACCINES
What Did You Expect From The Vaccines?
2010年6月結成のロンドンの4人組、THE VACCINESが結成の約1年半後の2011年3月にリリースしたデビュー・アルバム。フレーズらしいフレーズよりもむしろひずみ、残響、音の煌きといった音響を意識したギター・サウンドは現代におけるギター・ロックの在り方を象徴している。だが、それが50’sあるいは60’sを連想させるどこかノスタルジックなメロディーと見事に溶け合い、彼らならではと言える甘美な白昼夢の世界を作り出しているところが聴きどころだ。レコード・デビュー前にライヴを通してバズを作り上げていたとは言え、本作が大ヒットになった理由は威勢のいいサーフ・パンクからロマンチックなバラードまで、楽曲が粒揃いだったことも大きかったはず。普遍性を持った曲作りのセンスは大きな武器として、今後のキャリアにおいても活きてくるにちがいない。
-

-
THE VACCINES
What Did You Expect From The Vaccines?
vaccineとは“ワクチン”の意(ちなみに英語読みだと“ヴァクシーン”)。このバンド名、麻痺し切ったこの世の中を健全へと導く覚悟なのだろうか。“THE VACCINESに何を期待する?”というそこはかとなく挑発的なアルバム・タイトルからも彼らの自信が伺える。その自信はハッタリに非ず! 結成から1年にも満たないこのバンドは、デビュー・アルバムにして名盤を作り上げてしまった。瑞々しくダイナミックなサウンドは、UKロックの歴史を全て継承したようなスケール感と振り幅に溢れている。ドラムが炸裂した直後に美しいピアノで聴かせたかと思えば、ポップな音色を投下したりと、聴き手の心を常に揺さぶり続ける。正攻法の中に光る独特のセンスは、ギター・ロック・シーンの新たな希望と言って良いだろう。
-
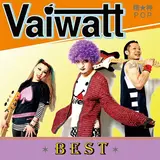
-
Vaiwatt
BEST
日々の生活で心が病んだ人たちを元気にする"精神ポップ"を掲げる3人組ロック・バンド、Vaiwatt(読み:バイワット)の初の全国流通盤。David Bowieの影響を受けた奇抜なメイクが目を惹くぴえろ拳(Vo/Rizm)を筆頭に、TAMA(Ba/Vo)とS タクロー(Gt/Shout)が集結して鳴らすのは、70年代のパンク/ニュー・ウェーブ色を強く滲ませた中毒性の高いロック・サウンド。今作は、問題イベント"東京アダルトチルドレン"を主催するなど、ライヴハウスを中心に活動してきたメンバーが、ライヴの人気曲を収録した、まさにベストな1枚。世界7ヶ国語で"つまんねぇ"を連呼する新曲「Babel Babel」を含む全8+1曲からは、アングラで危険な匂いもぷんぷん漂ってくる。
-

-
VALLEY
Lost In Translation
「Like 1999」がTikTokを中心に日本でもヒット、8月には初の来日公演を控えるカナダのオルタナ・ポップ・バンド、VALLEY。TikTokユーザーの心を掴んだ心地よいメロディや男女2声の柔らかなハーモニーはこの2ndアルバムでも堪能することができるが、ノリのいいポップ・ソングだけでなく、鳥のさえずりが聞こえるような落ち着いた楽曲も。不思議な浮遊感漂うサウンドや時折見せるヴォーカルの儚げな表情は、ポップさの中にノスタルジーを感じさせる。そして「Fishbowl」では、物語の終わりを告げ新たな世界へ誘うような壮大なストリングスが広がる。ロマンチックな愛の歌に前向きな失恋ソング、募る後悔を歌うナンバーまで、無邪気な青春を駆け抜け少し大人になった20代の心の機微を映す1枚。
-
-
VAMPIRE WEEKEND
Modern Vampires Of The City
3作目にふさわしい飛躍を印象づけるブルックリンの4人組の新作。求められるものの大きさを思えば、もっとややこしい作品になっても不思議ではなかった。それがこれほど天真爛漫な作品になったところにバンドの器の大きさが窺える。2013年を代表する1枚になることは必至の傑作。人懐こいメロディを持った軽快なロックンロールを、バロック、ダブ、ヒップホップ、アフロ・ポップの手法を使い、極めて現代的なポップスに作り上げるという意味では前2作の延長。そこにアンサンブルや音の響かせ方のおもしろさが加わり、バンド・サウンドが3D的にスケールアップした印象だ。アフロ・ポップの要素が後退したと言われているようだが、後半、その魅力をたっぷり楽しめるので、それを求めている読者はご安心を。
-

-
VAMPIRE WEEKEND
Contra
いや、もう名盤である。それでいいんじゃないかなと思ってしまう。アルバムの冒頭を飾る「Horchata」からラスト「I Think Ur Contra」での心地よいクールダウンまで、高揚感は途切れることなく上昇していく。引き締まったサウンド・プロダクションも特徴的だし、シンセ等のエレクトロ、はたまた弦楽器を取り入れてみたりとトピックは多い。ただ、それ以上にこの知的でクレイジーな音が、多幸感と高揚感の最果てまで肉体と意識をぶっ飛ばす為に鳴っていることこそが重要だ。トロピカルやアフロ、変則的なビート、そういう音を鳴らすことが目的化したようなバンドとはもう次元が違う。これはもう、一つの体験と言っていい。2010年、祝祭のど真ん中にいるのは、VAMPIRE WEEKENDだ。
-

-
THE VAMPS
Night & Day (Day Edition)
前作『Night & Day (Night Edition)』収録の「All Night With Matoma」は全世界でストリーミング再生回数4億回超えという、現代のポップ・スターぶりを遺憾なく発揮している彼ら。前作の続編となる本作でもEDM以降の世界基準のポップスがかゆいところに手が届くが如く、最強のバランスでアルバムとしてパッケージされている。R&Bもロックも消化したBrad Simpsonのヴォーカリゼーションの巧みさ、オーケストレーションとコーラスが生み出すスケールが心地よいTrack.1、洗練されたファンク・チューンのTrack.3など、現在のトレンドを20代半ばのメンバー自身の同世代クリエイターたちと作りあげているあたりも、単なるイケメン・バンドとは一線を画する所以。洋楽入門編としてもレコメンドしたい。
-

-
THE VAMPS
Wake Up
10代で、お互いにYouTubeで発表していたデモ音源を通して知り合い結成した、UK発の4ピース・バンド、THE VAMPSの2ndアルバムが完成。アイドル的なルックスと、デビュー前にしてTaylor SwiftやAustin Mahoneのオープニングを務め、MCFLYとツアーを回り、今作のタイトル曲でありシングルの「WakeUp」では、かのベッカムの息子であるブルックリンがMVに登場。そんなシンデレラ・ボーイっぷりも注目だが、今回のアルバムの楽曲もそれに負けずキラキラと華やかなポップ性や、アンセム感のあるロック・サウンドもありとパワフルになっている。モダンなアレンジが効いた、それでいて、どこか70年代、80年代の懐かしいポップスの香りを交えたフレンドリーな楽曲群は、SNS世代ならではの器用なトレンド・ミックスの成せる技か。
-

-
THE VASELINES
V For Vaselines
NIRVANAのKurt Cobainも愛したグラスゴー出身の男女デュオ、THE VASELINES。90年代に1度解散した彼らの、2008年の再結成後2作目となるフル・アルバム。何故、Kurtはこのデュオを愛したのか? その答えは、ピュアで、繊細で、下手っぴで、でも強い音楽愛に満ちたそのギター・ポップ・サウンドにすべて表れている。VASELINESはロックの"純潔"の象徴だった。衝動的に掻き鳴らされるギター、ラフでパンキッシュなサウンド、可愛らしいメロディ、柔らかなふたりの歌声―― そのすべてが、"俺を見ろ!"とのたまう男根主義的ロック・スターとも、ハリボテの煌びやかさを売りにする商業主義ポップスとも一線を画すものだった。本作でも、そんな彼らの本質は少しも変わらない。HomecomingsやJuvenile Juvenileあたりが好きな人は絶対に出会っておくこと。
-

-
THE VASELINES
Sex With An X
NIRVANAのKurt Cobainが生前敬愛していたことでも有名な、08年に再結成したスコットランドのガレージ・ポップ・バンドTHE VASELINESが、2枚目にして実に21年振りのアルバムをリリースする。絶妙なズレを保つEugene KellyとFrances McKeeのツイン・ヴォーカルから際立つのは、良い意味での“脱力感”。いつの間にか催眠状態に陥りそうな、不思議な中毒性を持っている。ポップなメロディに反して曲タイトルはシニカルで、ギターは轟音。ありふれた日常を気負わず自然体で歌いながら、いい笑顔で屈託なく舌を出すようなスカした空気感が心地良い。「Ruined」は1曲目に相応しく勢いがあり、新たなスタートへの決意が漲っている。
-

-
Vaundy
replica
メガヒットした単曲の間にアルバム曲を入れることを良しとしなかった結果、コンセプチュアルなDisc 1とヒット曲満載のDisc 2という凄まじいボリュームに着地した本作。大歓声のSEのなか鳴らされる骨太なロック「ZERO」に始まり、R&Rリバイバルやネオ・ソウル、モダンなサイケなどが展開。肌感覚や体感に肉薄するヴォーカルや歌詞表現、「NEO JAPAN」に象徴される現実認識を通過してタイトル・チューンの巨大な音像に辿り着くVaundy流ロック・オペラと呼べそうなDisc 1こそが実質的な2ndアルバムなのだろう。それだけにメガヒットが並ぶDisc 2収録曲の1曲に込めるアイディア、キャッチーさの確度にも舌を巻いてしまう。話題の「トドメの一撃 feat. Cory Wong」のリッチなサウンドは驚きの新境地。
-

-
VELTPUNCH
His Strange Fighting Pose
1997年に結成されたオルタナティヴ・ロック・バンドVELTPUNCHの通算7枚目のオリジナル・アルバム。新ドラマーにナオキ(ex.キウイロール)を迎えて制作された今作は、メロディアスでハードなサウンドは健在ながら、ポップ且つエネルギッシュなアルバムとなった。長沼&ナカジマの掛け合いによる男女ツイン・ヴォーカルとアンセミックなサビが印象的なオープニングナンバー「The sweetest」から、アグレッシヴで疾走感溢れるナンバーが並び、左右に振り分けられた美しいギター・アンサンブルや静と動と緩急をつけて進む一曲一曲の展開も見事。ラウドで振り切れた激しさもありながらも、作品全体として耳馴染みのいい心地いいサウンドに仕上がっている。
-

-
VELVET DAVENPORT
Warmy Girls
天才メロディメーカーと称されるParker Sproutを中心とする6人組バンドが今作で日本デビュー。フロントマンのParker SproutはARIEL PINK'S HAUNTED GRAFFITIに類まれなメロディセンスを見出された。そんな経緯もあってAriel Pinkのような心地良いローファイサウンドをしっかり受け継いでいる。60年代サイケデリックポップの香りを色濃く残したゆるゆるな音の断片が脳内を駆け巡り、絶妙なストレンジさが病みつきに。じわりじわりと体を蝕んでいくように時間をかけて脳内を侵食されていく感覚は愛おしい過去の記憶を画質の荒い映像で見ているみたいだ。力を抜いて気の合う仲間とビールでもどう? って気分になるこの1枚。白昼夢のような至福な時間に酔いしれたい。
-
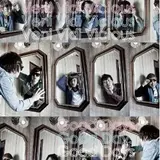
-
Veni Vidi Vicious
Good Days
Veni Vidi Viciousが息を吹き返した。そして覚静した。思えば、活動休止発表時、入江良介自身は解散の気持ちでいた。つまり、本当なら、VVVは1年半前に死んだも同然だった。そんな、事実上の死、そこを抜け出た先にあったものこそが、本作のタイトル・トラック「Good Days」。自分が死んだと仮定して妻と子供に書いたという、“僕が守る”ではなく愛する者の幸福をひたすらに願うこの曲は、彼が自らを殺すことで、初めて外界と繋がることが出来た曲でもある。そして、入江良介自身がTwitterでもって“届け!”と言い、拡散希望を、“繋がり”を求めたこの曲には、これまでのVVVでは持ち得なかったものがいくつも詰まっている。人生への、愛、希望。音楽への、愛、希望。ここには、命と希望、そしてバンドにとっての変化と発展がある。
-

-
Veni Vidi Vicious
9 stories
昨年1月の突然の活動休止から389日、静かに復活を遂げたVENI VIDI VICIOUS。復活後1作目となる本作は、過去2作と比べると、そのジャケットのごとく全体的に暗く煙ったい。だがこの煙は、ただただぼんやりと漂っているようでありながら、気付けばこの身にまとわりついて離れない。暴力や酒が飛び交う喧騒の真ん中で、それを斜に構えて見ているような、野暮ったい悲恋を描いたジム・ジャームッシュのような、ひどく寂しい映画の如く、どこか虚しくも愛おしさが募ってしまう世界のより深くまで誘われ、気付けばその深みにはまっている。“いつだって世界は嘘にまみれる”“願わない 信じない そうやって生きてきた”…言葉を拾おうとしたらきりがないほどに、切れ味鋭くも脆く不安定な刹那がいくつも詰まっている。
-

-
VENUS PETER
Nowhere EP
10年のブランクを経て、2006年に再結成を果たしてから、時折、思い出したように活動を始める5人組、VENUS PETERが8年ぶりに新作をリリースする。今回のリリースはメンバーである古閑裕(Ba)のレーベル、KOGA RECORDSの設立20周年記念ということらしい。90年代前半、フリッパーズ・ギターとともに渋谷系と名づけられたブームをリードしたバンドである。新曲3曲に過去のレパートリーの再録ナンバーとライヴ音源をそれぞれ3曲ずつ加えた計9曲を収録。ネオ・サイケなギター・ポップ路線を追求した新曲、ロックとダンスを融合したマンチェスター・ブームの申し子というバンドの出自を改めて印象づける再録ナンバーともに伝説として語られるバンドの姿を決して裏切らないものになっている。
-

-
VERY TRULY YOURS
Things You Used To Say
「ボトルに入った手紙を拾った少女は、その手紙を読みながら曲を作り、またそれをボトルに詰め込んで海に投げ入れた。“Very Truly Yours(親愛なるあなたへ)”と書き記した手紙と一緒に…」そんな愛らしい物語に由来する名前のバンドVERY TRULY YOURSのデビュー作。その音楽性については、TWEE GRRRLS CLUB編纂のコンピレーション『Grrrls Talk』に収録されたという情報だけで、分かる人には分かると思う。ガーリー・カルチャーを語る上で欠かせない映画監督Sofia Coppolaの出世作でもある映画『ヴァージン・スーサイズ』で描かれていたような、女の子の世界へのロマンチシズム溢れる、めいっぱいガーリーなインディ・ポップ。パステル・カラーで彩られたベッドルーム、フリルのワンピースを纏った女の子の笑い声がこだまする、秘密の花園へようこそ。
-

-
VESPERBELL
RUMBLING
「Noise in Silence」には、オカモトコウキ(Gt/OKAMOTO'S)、GOTO(Dr/礼賛/DALLJUB STEP CLUB/あらかじめ決められた恋人たちへ)、バンビ(Ba/アカシック)といった面々が集結。さらに「Bell Ringer」は、コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店)での活動でも話題を集めたDJ KSUKEの作曲であり、バックアップも固い。しかし何よりも輝いているのは2人の歌声だ。ラップも似合うハスキーでパワフルなヨミの歌声、老若男女の耳に馴染みやすい優しいカスカの歌声。溶け合うことなく、しかし2人で手を繋ぐように息ぴったりに響き合うハーモニーは聴き応えたっぷり。タフなロック・チューンを華麗に歌いこなす"強さ"から目が離せない。
-

-
VIB GYOR
We Are Not An Island
イギリスはリーズ出身の五人組、VIB GYOR。RADIOHEADやTRAVIS、COLDPLAYに続くバンドとして、高い注目を集める大型新人のデビュー・アルバム。虹の七色を記憶する為の造語(色の綴りの頭文字が並んでいる)をバンド名に冠するVIB GYOR。まさに前述のバンド達の系譜の上にあるUKらしい憂いを帯びたヴォーカルとメロディ、儚くも眩いサウンド・スケープを描き出す美しいアルバムだ。その完成度の高さとスケール感は新人とは思えないが、反対にデビュー・アルバムだからこその何かがないところは残念でもある。その実力は間違いないだけに、今後、クラシカルとも言えるそのスタイルにどこまで独自の色彩を加えることができるかは次作のお楽しみにしたい。
-

-
THE VICKERS
Ghosts
2006年にイタリアで結成された4人組、THE VICKERS。これまでは、THE STROKESやTHE LIBERTINESらに通じるソリッドなロックンロールを鳴らしていた彼らであったが、3作目となる今作で大胆な路線変更。Track.1「She's Lost」から60年代直系のサイケデリック・サウンドが爆発する。いったい彼らに何が起こったのだろうか。調べてみると、2012年11月にTHE BEATLESの「SheSaid She Said」のカバー音源を本国イタリアでリリースしていた。彼らのメロディ・センスとグルーヴ感は一朝一夕のものではなく、サイケデリックなサウンド・アプローチも決して付け焼刃のようなものではない。バンドの地力とセンスが光る1枚だ。
-

-
THE VICKERS
Fine For Now
イタリア発、06年結成の4人組THE VICKERSの、2ndアルバムにして日本デビュー作。GIRLSを聴いた時のような瑞々しいときめきを思い起こさせるのは、きっと全ての音がセンチメンタルを帯びた輝きに満ちているからだ。そして、その輝きの正体とは、VAMPIRE WEEKENDのようなトロピカルな音が寄せては返す波のごとく心地良く主張したりと、ちょっぴりサーフ・ロック寄りな穏やかさと爽やかさの中に、90年代のロックの衝撃を再び蘇らせたような“やんちゃさ”が全面に迸っているという点にある。膝小僧には絆創膏をした悪戯坊主が、兄ちゃんの部屋から勝手に持ち出したTHE STROESのCDを聴きながら走り回っているような、好奇心旺盛な少年の画が広がってきて、どうにもむずむずしてくるのだ。
-

-
VIDEO NASTIES
On All Fours
UK出身、本作がデビュー・アルバムとなるVIDEO NASTIES。こいつら、時代も流行も完全無視である。CAJUN DANCE PARTYが大絶賛なんて前情報から聴いた人は、ちょっとビックリするだろう。UK出身ということを疑ってしまうその音は、紛れもなく90年代US産オルタナ。フラストレーションとエモーションを爆音のギター・ディストーションに変換したあの音。抑えられない衝動と想像力を暴発させたあの音である。楽しく踊れるだけで、後には何も残らないような音楽とは対極にある、荒々しい熱量の固まりとしてのロックンロール。こういう音楽が今のUKから飛び出してくるから面白い。今、楽しいだけの音楽では物足りないと感じている人は、VIDEO NASTIESを聴けばいい。
-

-
THE VIEW
Exorcism Of Youth
昨年2022年に5年ぶりの再結成を果たしたTHE VIEWの、8年ぶりとなるフル・アルバム。3rdアルバム『Bread And Circuses』(2011年)を手掛けたYouthが再びプロデューサーとなっていることからも感じられるが、ファンキーだったりソウルフルだったり、ルーツを掘り下げるようなサウンドを意識していた前作からは一変、ブリティッシュ・ロックのピュアな魅力が前面に際立った作品だ。それでいながら、ヴォーカルひとつとってもかなり洗練された印象で、原点回帰というよりは、自分たちの強みを上手く進化させたサウンド。サウンドの変遷と、バンドとしての紆余曲折、世の中の移り変わり、すべてを通過して今がTHE VIEWにとってベストな時期、と感じさせるような説得力のあるアルバムだ。
-

-
THE VIEW
Ropewalk
00年代のロックンロール・リヴァイヴァルの波を追いかけるように現れ、デビュー・アルバムがいきなり全英No.1に輝いた4人組。今年、結成10周年を迎える彼らが3年ぶりにリリースする5作目のアルバム。曲の良さを、ギターをかき鳴らさずに伝えようとしたらソウル・ミュージックの影響が浮き彫りになってしまったなんていう前半から一転、後半はエキセントリックなアレンジのロック・ナンバーをたたみかけ、ぐいぐいと盛り上げる。その落差に驚かされながらブリティッシュ・ロックの伝統と胸を焦がすような感覚が随所に感じられるところは、やはり彼らならでは。そういう作品のプロデューサーがTHE STROKESのAlbert Hammond, Jr.とTHE STROKESのプロデューサー、Gus Obergというところも面白い。
-
-
THE VIEW
Seven Year Setlist
2007年発表の1stアルバムが全英No.1ヒットになり、シーンの最前線に躍り出た4人組、THE VIEW。5作目のアルバムは過去7年のキャリアから選曲したヒット曲の数々に新曲を加えたベスト盤と言っても差し支えない作品だ。英国情緒あふれるロックンロールをパンキッシュに、いや、クソガキらしい向こう意気とともに奏でてきた4人組の魅力をギュッと凝縮。曲の良さは同時に、しっかりと根っこを持ったバンドの力強さを思わせる。それぞれに異なる魅力をアピールしている新曲3曲も聴きどころだ。フォーク・ロック調の「Standard」は、THE LA’Sをちょっと連想させる。日本盤はAmy Winehouseのカヴァーを含む10曲を収録したボーナス・ディスクをカップリング。入門編としてこれを聴いておけば、まず間違いない。
-

-
THE VIEW
Bread And Circuses
あらあらこんなに大人になって! なんて、おばちゃんが久し振りに会った親戚の子に言ったりするが、そんな台詞を自分が、音楽を聴いて呟くなんて思ってもみなかった。そんな比喩がピッタリなTHE VIEWの3作目。元KILLING JOKEのYouthをプロデューサーに起用して1年の歳月を掛けて作られた今作は、今までの彼らの音をぎゅっと絞ってスマートにさせた見事なまでの洗練っぷり。1曲1曲のバリエーションも格段に広がり、キーボードやストリングスなどが大々的に取り入れられている。カラフルなサウンドが、瑞々しく美しいハーモニーの持つ力、声の持つあたたかみをとめどなく引き出してゆく。進化に対する彼らの粘り強さの賜物だろう。軽やかで力強いギター・ロック・サウンドに笑みが零れる。
-
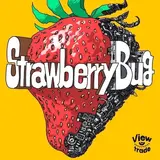
-
Viewtrade
Strawberry Bug
2020年6月に結成された、平均年齢19歳のオルタナティヴ・ロック&ポップ・バンド Viewtradeから、バンド史上初のデモ音源『Strawberry Bug』が届いた。会場/タワレコ一部店舗限定リリースとなった本作は、ロック・バンド然とした攻撃的なサウンドとJ-POP的なキャッチーさが融合した1枚に。池田凜哉(Gt/Vo)による文学的/哲学的な歌詞が刺さるファスト・チューン「路地裏のモーツァルト」、スピーディ且つテクニカルな演奏で畳み掛ける「チェイサーの最終戦」、そして他2曲とは異なる爽やかなポップ・センスが光る「サマータイム・メランコリー」と粒揃いの3曲が並ぶ。何より"ポップをナナメから視るバンド"というキャッチコピーを掲げる彼らなりの美学が貫かれているのが心地よい。
-

-
VILLAGERS
Darling Arithmetic
アイルランドはダブリン出身の青年、Conor O'Brien率いるVILLAGERSの3rdアルバム。サウンドの基調となるのはオーセンティックなフォークだが、そこにエレクトロニカやポスト・ロックを昇華したアレンジを塗すことで、深く己の内面世界に入り込んでいくような静謐なサウンドを産み出している。その内省的な音から想起したのは、デビュー当初のBRIGHT EYES。VILLAGERSには当時のBRIGHT EYESほどの荒々しさはないが、しかし、自らの心の奥底を見つめる、その眼差しの鋭さと熱さには通じるものがある。その後、BRIGHT EYESの視線は外側へ、社会へと向かった。VILLAGERSはどうだろう。内側か外側か――どちらにせよ、その眼差しに"変革"への意志が宿ったとき、化けるのではないだろうか。
-

-
VILLAGERS
{Awayland}
デビュー・アルバムがUKインディー・チャート及びアイルランドで1位を獲得し、海外メディアで絶賛されたアイルランド出身のConor J. O'Brienを中心としたバンド、VILLAGERSの2ndアルバムが完成。ギター・サウンドを中心としたシンガー・ソングライター風のサウンドが主体にはなっているが、本作は彼が影響を受けたというエレクトロニック・サウンドが要になっており、曲のダイナミズムが前作よりも増している。パーカッションの使い方が巧みで、ストリングスのアレンジと共に壮大なサウンド・スケープを描いている。シンプルでナチュラルなサウンドとリズミカルなビートを打つエレクトロニックなサウンドがどちらも主張しすぎず自然に融合しており、美しくも悲しげなこのアルバムの素晴らしさを物語っている。
-

-
THE VINES
Future Primitive
“生まれ変わった”、と言っても過言ではないのではないだろうか。それは変わってしまった、ということではなく、新たなパワーを吸収し我々の前に帰って来た、ということだ。オーストラリア発の4ピース・バンドTHE VINES、3年振りのリリースとなる5thアルバム。絶叫しガレージ・ロックをブチかましたかと思えば、切なく柔らかいフォーキーなサウンドを聴かせ、打ち込みのプログラミング・サウンドはどこまでも謎めいている。まるで泣いたり笑ったり、感情を全身で表現する赤子を見ているようで目が離せない。4分以上ある曲は無く、全13曲が走り抜けていくように目まぐるしく迫り来る。Craig Nichollsの幼さの残るヴォーカルはひたすらにピュアネス。それは音楽に命を捧げる覚悟を感じさせる気魄がある。
-

-
VITALIC
Rave Age
近年David GuettaやJUSTICEで盛り上がりを見せるフレンチ・エレクトロ・シーン。DAFT PUNKに続き、そのシーンを支え続けていたVITALICから、3年振りとなる3rdオリジナル・アルバムがリリースされる。自宅スタジオで地中海に思いを寄せながら制作し、パリでミキシングを行ったという同作は、アルバム・タイトルに相応しい非常に開放的で自由に満ちたサウンド。個性溢れる様々なヴォーカリストを招いた楽曲はポップでキャッチーなメロディが耳に優しく、ドラマティックな展開を見せるインスト・ナンバーはリズムとビートがリスナーの踊りたくなるツボを程よく刺激する。アラビアン・ミュージックを彷彿させる楽曲なども収録されるなど、様々なアイディアが詰め込まれた意欲作。
- 1
- 2
LIVE INFO
- 2025.11.29
- 2025.11.30
- 2025.12.09
- 2025.12.22
- 2025.12.27
- 2025.12.29
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























