DISC REVIEW
S
-

-
Saccharomyces cerevisiae
別れ
愛媛県松山発の4ピース・バンドによる1st EP。悲哀に美しさを見いだすこのバンドの在り方は、デビュー作の1曲目が"last scene"というタイトルであるあたりにもよく表れている。収録曲中、最も速いテンポと忙しないメロディ・ラインで心のざわめきを表現する「last scene」。1番は丸々弾き語り、そしてバンド・サウンドが重なるタイミングが非常に秀逸なバラード「備忘録」(Track.2)。リズムを後ろに引っ掛けるような進行の仕方が心地よい「白日の夢」(Track.3)。その名のとおり"別れ"をテーマにした全3曲は、聴き進めるほどに現世から遠ざかっていくような、不思議な浮遊感を持っている。聴く人の背中を叩くでもなく、腕を引っ張るでもなく、まるっと包んでしまう毛布みたいだ。
-

-
SADE
Soldier Of Love
これほど寡作でありながら、常に世界から愛され続けているバンドも珍しい。1984年から活動を続けながら、アルバムはたったの6枚しかない。Sade Aduという絶対的カリスマが率いるSADE、『Lovers Rock』以来10年ぶりとなる新作『Soldier Of Love』。相変わらずどこか謎めいた魅力を放つSADEの世界は10年前と何も変わらない。R&Bにレゲエをはじめとしたワールド・ミュージックを絶妙にブレンドして生み出される美しいサウンド・ジャーニーに乗せて、彼女は愛をせつせつと語りかけるように歌う。物悲しいギターとビートを軸にした生々しい音の上で世界を憂い、世界に向けて愛を語るAduの気丈な歌声が響く。真摯過ぎるほどに真摯な彼女の後姿に胸が熱くなる。
-
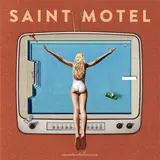
-
SAINT MOTEL
Saintmotelevision
2014年リリースの楽曲「My Type」が全米ビルボードのオルタナティヴ・ソングスTOP10にチャート・インし早耳リスナーの間で話題となったロサンゼルス発の4人組インディー・ポップ・バンド、SAINT MOTEL。前作より約4年ぶりとなる待望の2ndアルバムは、サックスやトランペットなどのホーン隊が前衛を守るとにかくファンキー且つポップなサウンドでご機嫌な幕開けとなるTrack.1や、ミドル・テンポで落ち着かせつつも後半のヴォーカルの掛け合いで高揚させるニクい演出を仕掛けてくるTrack.4。さらにTrack.7はそのタイトルどおり、さりげなく間奏にベートーヴェンの「エリーゼのために」をぶっ込んできて、そのオシャレ具合にはお手上げ。FOSTER THE PEOPLEやPHOENIX好きにはオススメしたい1枚だ。
-

-
saji(ex-phatmans after school)
ツバサ
phatmans after schoolというバンド名をsajiに改めて、再び歩き始めた彼らの改名後、初の音源。表題曲の「ツバサ」は、TVアニメ"あひるの空"のエンディング・テーマに起用されているが、ヴォーカルでありメイン・コンポーザーのヨシダがかねてより愛読していた作品なこともあり、原作の世界観をしっかりと楽曲に落とし込んでいる。それだけでなく、澄み切った青空が目に浮かぶ爽快感溢れるバンド・サウンドであり、そこに綴られている言葉は、新たな名前で走り出した今の彼らの姿を彷彿とさせるものに。また、甘酸っぱさのある「猫と花火」も、ビッグ・バンドな「まだ何者でもない君へ」も"夢"をテーマに掲げていて、心機一転の第一声に相応しい内容に仕上がっている。
-

-
phatmans after school
キミノバアイハ
直近の2枚のミニ・アルバムではアグレッシヴな作品を立て続けにリリースしてきたphatmans after schoolだったが、この最新アルバム『キミノバアイハ』はバンドの中核にある"歌"の魅力をフィーチャーした原点回帰の1枚となった。タイトルには2011年にリリースされたメジャー・デビュー作『ボクノバアイハ』のアンサーとしての意味合いを持たせているとおり、出会いや別れを繰り返す活動のなかで、変わってゆくこと、変わらないことのすべてを肯定するような曲たちが力強く鳴らされている。中でも、8曲目に収録された温かいミディアム・テンポ「kakemeguru」の"怖がらないで 一歩ずつ/君らしくいけばいいさ"というメッセージは、いまの彼らだからこそ歌える優しいエール・ソングだ。
-

-
phatmans after school
アンクロニクル
陽気なブラスがハピネスを運んでくる、ファンファーレのような「シリアル」で幕開ける2ndアルバム。"生命(僕たち)の年代記"を意味する造語をタイトルに掲げた今作のテーマは"原点回帰"で、住んでいる場所や年齢が違ってもみんな同じように抱える、同時代を生きる人々の葛藤や孤独など複雑な思いを繋ぐべく描かれた架空の物語が並ぶ。くよくよ悩む人を鼓舞するように、モヤモヤを蹴散らしていくパーティー・ナンバー「party holic」、ユーロビートを取り入れながら"倫理と本能の葛藤"というリアルな視点を綴った「FR/DAY NIGHT」、強力なフックを持った歌メロで主人公の心の声を叫ぶ「正常性バイアス」など、濃い味つけの楽曲が出し惜しみなく収められている。全13曲をキャッチーに仕上げるメロディ・センスもさすが。
-

-
phatmans after school
FR/DAY NIGHT/7日間.
2015年第1弾リリースとなる両A面シングル。「FR/DANIGHT」はユーロビートを軸にしたアップテンポのダンス・チューン。対して「7日間.」はアコースティック・ギターの音が効いたあたたかなミディアム・ナンバーだ。ライヴで観客が盛り上がる姿が目に浮かぶ前者と、聴き手ひとりひとりに寄り添うような後者。どちらも誰かに受け取られることを考えて作られた、表現のベクトルが外側を向いているからこそ生まれたであろう楽曲。にも関わらず、共通して人間の内側の葛藤――理性と本能、理想と現実の狭間で揺れる姿――を描いているのが面白い。秋には全国ツアー、さらに多くの人と対面することとなる日々のあとにはどんな曲が生まれるのだろうか。気が早いがそれも気になるところ。
-

-
phatmans after school
セカイノコトハ
2014年春、拠点を北海道から東京へ移し本格的にライヴを始動させた4ピース、phatmans after school。ミニ・アルバムやシングルで、キャッチーでキラキラとしたギター・サウンドを披露してきた彼らの1stアルバムは、四つ打ちチューン、ギターとシンセの音のシャワーが歌に降り注ぐフレッシュな曲から、打ち込み、じっくりと歌を聴かせる曲などやりたいことを詰め込んだエネルギッシュな1枚。そんな1stアルバムらしい天真爛漫なパワーがあるが、1曲1曲を紐解くと、細やかなディテールが積み重ねられたアレンジの妙がある。各々好みの音楽が幅広く、またJ-POPを聴きながら育ってきたゆえの、心地よい歌心とつい癖になって繰り返してしまうフックが織り込まれている。確信犯的なのか、天然なのか、これからが楽しみになる。
-
-
phatmans after school
メディアリテラシー
札幌在住、平均21歳の4人組バンドphatmans after school。2011年秋にメジャー・デビュー。メジャー1stミニ・アルバム『ボクノバアイハ』以来約1年5ヶ月振りのリリースとなる。若者特有の衝動と物憂げな空気が交錯するギター・ロック・ナンバー「メディアリテラシー」と、ティーンのモラトリアムな心情を綴ったキャッチーな「1○歳」、どちらも共通して歌われているのは"夢"だ。何が正しいかもわからなくなる現代。"それでも夢を追いたい"という彼らの純粋な思いはリスナーの心にまっすぐ飛び込んでくるだろう。インターネットを拠点に活動するy0c1eによる「無重力少年」のリミックスは、楽曲のサイバー感と憂いを抽出したソリッドなアレンジになっているのでこちらも必聴だ。
-

-
sajou no hana
ニューサンス
渡辺 翔、キタニタツヤ、sanaの3人で結成されたバンド sajou no hanaから約半年ぶりとなるニュー・シングルが届いた。迷惑事/厄介事を意味する"ニューサンス"(nuisance)をタイトルに据えた表題曲は"TVアニメ「スパイ教室」2nd season"EDテーマ。渡辺 翔が手掛けた歌詞は、欺瞞に満ちた現代における生きづらさが"見れない消えない汚れた生"、"ご立派に生きられて良かったね 優しさレイズ/幸せの強要今更苦しいだけ"などアイロニックな視点で綴られており、それを情感たっぷりに歌い上げるsanaのヴォーカルに終始圧倒される。曲調が二転三転するスリリングな展開、ダークな世界観を鮮烈に表現するソングライティングが痛快極まりない。
-

-
sajou no hana
切り傷
前作から約半年というスパンで到着した新作で、3人はまた新たな扉を開いた。タイトル曲は、TVアニメ"ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ 深章 厄災篇"のエンディング・テーマ。同シリーズとタッグを組んだシングルはこれで3枚目となるが、今回の表題曲はバンドにとって初となるスロー・バラードだ。ピアノやストリングスをフィーチャーした柔らかなサウンドと、儚くて繊細なsanaの歌声がなんとも映える美麗曲に仕上がった。一方「メーテルリンク」は、エモ/ポストロック的な雰囲気のあるバンド・サウンドを力強く押し出したアップテンポ・ナンバー。sajou no hanaの原点的な雰囲気を纏った楽曲を添えることで、バンドが持つ振り幅であり、可能性を改めて提示する快作になっている。
-

-
sajou no hana
青嵐のあとで
数々のヒット・ソングを手掛ける作曲/作詞家 渡辺 翔。作詞/作曲、ベーシスト、SSWと幅広く活動するキタニタツヤ。実力派ヴォーカリスト sanaを擁するsajou no hanaは、もはやバンドと言うよりクリエイター集団と言ったほうがしっくりくるかもしれない。青嵐とは、初夏に青葉を揺らす強い風のことだが、サウンドの輪郭を押し広げていく清涼で爽やかなギター・フレーズはまさに吹き抜ける青嵐そのもの。そしてc/wも含め、トラック内での各楽器の音の配置を大胆に振り分けたミックスが、立体的で臨場感のある音像を作り出し、目を閉じれば聴き手を取り囲んで音が鳴っているような感覚を生み出している。分析的な聴き方を好むリスナーならば、試しにイヤホンを片耳外してみるのも一興だ。
Warning: Undefined array key "$shopdata" in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/list/263415.php on line 27
-

-
SAKANAMON
liverally.ep
ストリングス入り編成に初挑戦した7thフル・アルバム『HAKKOH』、フィーチャリング・ゲストを迎えた配信シングル"PLUS ONE"シリーズを経て、今改めて放つ剥き身の3ピース・サウンド。歌や各楽器がかち合っては全力疾走しているほか、"どうしてそうなる?"的な捻りを効かせたワールド全開の展開も満載。リード曲の「おつかれさま」からは結成17年目を迎えた今だからこその温かい眼差しが感じられる曲で、総じて、現在進行形のバンドの魅力を真空パックしたような作品だ。お題があるからこそ自由になれる大喜利と同じ原理で、ライヴをテーマにした藤森元生(Vo/Gt)のソングライティングは抜群の仕上がり。15周年ツアー・ファイナルのライヴ音源も収録されている。
-

-
SAKANAMON
HAKKOH
今年2022年11月11日で結成15周年を迎えるSAKANAMONが、2年半ぶりとなるフル・アルバム『HAKKOH』をリリース。本作には、NHK「みんなのうた」名曲カバーにて参加した「南の島のハメハメハ大王」や、たかはしほのか(リーガルリリー)をゲスト・ヴォーカルに迎えた「1988」、宮崎市の魅力を発信する"宮崎食堂"へ書き下ろした楽曲「つつうららか」、インディーズ時代からファンの間で高い人気を誇る「妄想DRIVER」の2022年バージョンなど、結成15周年に掛けて全15曲が収められている。バンドの真骨頂とも言える洗練されたギター・ロック・サウンドを主軸としながら、初めてストリング編成に挑んだ楽曲も収録されるなど、3ピース・バンドとしての表現を拡張し続ける彼らの意欲作となった。
-

-
SAKANAMON
ことばとおんがく
1曲目に収録されている「ことばとおんがく」のイントロで、いろは歌のコーラスが左右から交互に聴こえた瞬間に、このアルバムに仕込まれている様々な仕掛けへの期待が高まった。ネクライトーキーのもっさ(Vo/Gt)が参加する「かっぽじれーしょん」では、軽快なメロディと共に展開される聴き間違いをテーマにした会話風の歌詞が、まるでコントのようで、思わずくすっと笑ってしまう。レの音が鳴ったら文字が入れ替わる「レ点」や、いろは歌のアナグラムになっている「いろはうた」など、各曲に異なった言葉遊びが展開され、日本語の面白さや美しさを再認識できるアルバムとなっている。遊び心たっぷりに繰り広げられる彼らの言葉と音楽の世界を、ぜひ歌詞カードを片手に堪能してほしい。
-

-
SAKANAMON
LANDER
5thミニ・アルバム『GUZMANIA』から半年で発表するアルバム。人の心を天体に見立て、遠く離れた人々の心に自分たちの音楽を届ける"着陸船"=LANDERというテーマのもと、人生の様々な場面を、ユーモアとペーソスを交えながら、あくまでもポジティヴに歌った全12曲が収録された。軸足をライヴに置いているバンドらしい硬派なバンド・サウンドと、90年代のJ-POPの影響――つまり、ロックの影響だけにとどまらないポップ・ソング作りのセンスおよびスキルが絶妙に、いや、過剰に入り混じる曲の幅広さは彼らならでは。「WOULD YOU LIKE A HENJIN」は初の完全打ち込み曲なんだそう。ダンサブルなリズム・アプローチに滲むブラック・ミュージックからの影響も聴きどころだ。
-
-
SAKANAMON
HOT ATE
非モテだ、オタクだ、一発でわかりやすいバンドでもない、そんなことはわかっちゃいるが、何が正解なんだ? そんな逡巡を抱えたまま、音楽体験としてのスリリングさで鬱屈を突破しようとするSAKANAMONらしさは不変の4thフル。00年代NYのポスト・パンクを彷彿とさせるTrack.1「UTAGE」の寛容さ、彼らがファンクを昇華したらこうなるというTrack.4「UMA」、ラウド/ミクスチャーの新鮮さだけじゃない、べらんめぇ調なのに抜群のフロウで言葉を当ててくる藤森のカンの良さにも驚くTrack.9「ラストボス」、そしてJ-POP風でもある親しみやすいメロに溢れる音楽愛の裏返しとも言える現実への焦燥と微かな期待が見える希少なシングルになった「PLAYER PRAYER」など、繰り返し聴きたい12曲。
-

-
Saku
Say Hello
表題曲は18歳のころから温め続けていた1曲。"新しい自分ってさ、/いつ出逢えるんだろう?"という言葉は思春期特有のアイデンティティの揺らぎによって導かれたものと思われるが、今歌えば、メジャー・デビューから2年半強を経た彼女の赤裸々な言葉として響く。それが今回リリースすることになった大きな理由であろう。迷いと決意の両方をまっすぐに歌い上げる同曲の直後だからこそ、「おつかれさん」の弾き語りが沁みる。聴く者の背中を押し、じんわりと心を温めてくれるようなこの2曲に救われる人は多くいるのでは? と思っていたら、ラストに待ち構えるのはどこか癖のある男性をパクチーに例える曲。しんみり終わらず最後には笑顔にさせるこの感じこそがSakuらしさなんだと改めて感じる。
-

-
Saku
ハローハロー
中高生を中心に支持を集めるシンガー・ソングライター Sakuが、前作『君色ラブソング』より約4ヶ月ぶりとなる4thシングル『ハローハロー』をリリース。今回は、"一歩踏み出したい女の子に贈る曲"をテーマに掲げ、Sakuの実体験をもとに制作。立ち止まってばかりじゃ何も始まらないし、痛みを知り大人になるために"新しい自分に出会いたい"、そんな人の背中を押してくれるTrack.1「ハローハロー」。大好きなダーリンにちょっとした文句をしたためた歌詞になっているTrack.2「NO WAY!!!」は、後半で"可愛いとこもあるから/やっぱり憎めない"と歌うツンデレ・ソングとなっている。恋をするときの楽しさやもどかしさ、儚さをうまく表現している1枚だ。
-

-
Saku
春色ラブソング
半年ぶりのリリースは片想いで悩んでいる女子中高校生にエールを送るラヴ・ソングが表題曲のシングル。作曲はSakuの同年代の作編曲家である中村瑛彦が担当し、作詞はSakuと中村と19歳の現役女子大学生兼作詞家の阿部伶香の3人で書き上げている。歌詞で描かれているリアリティ溢れる学生恋愛の風景は少女漫画さながら。今まさしくこのような状況の少女たちも少なくないのでは。Sakuの歌声もいつもよりあどけなく非常にスウィート。ストリングスや鍵盤などがきらきらと華やかに舞う、良質のJ-POPになっている。卒業シーズンにぴったりのラヴ・ソングだ。カップリングには作詞作曲をSakuが手掛ける純愛ソング、メジャー・デビュー曲のアコースティック・バージョンを収録。
-

-
Saku
Girls & Boys e.p.
現役タワレコ店員であるSSWのSakuがメジャー・デビューからわずか4ヶ月でリリースする新作EP。収録曲中3曲は夏がテーマになっており、季節の中では最も夏が好きという彼女の人間性が反映されている。パワー・ポップ的な力強さと清涼感と一抹のセンチメンタルが混ざり合ったTrack.1は、彼女の少ししゃがれたキュートでガーリーな歌声も鮮やか。ヴォーカルを楽器のように扱うコーラス・ワークも巧みだ。Track.2は夏の気だるさやきらめきが音で表現され、Track.3はシューゲイズ的な音像が幻想的。WEEZERの名曲をカバーしたTrack.4は、バンドならではのエモーショナルなグルーヴが原曲へのリスペクトを痛烈に物語る。彼女のバックグラウンドと、ポップ・アイコンとしての魅力が花開く作品だ。
-

-
Saku
FIGHT LIKE A GIRL
現役TOWER RECORDS店員の顔を併せ持つ、22歳のシンガー&ギタリストSakuの1stアルバム。新曲を中心に、THE CUREのカバー、既発のEP2作品から2曲を収録している。トータル・プロデューサーに吉田仁を迎え、カジヒデキ、堀江博久ほか"ネオ渋谷系"ともいえる豪華ミュージシャンが参加。渋谷系の精神に感銘を受けたSakuが繰り広げる、US/UKインディー要素をポップかつフレッシュに盛り込んだ2010年代の渋谷系ともいえる作品になった。ポップでキュートでスウィートの三拍子を引き立てているのは、インタビューでも彼女が語ってくれた"毒"の要素。ちょっとやそっとのことでは折れないサウンドへの強いポリシーや、陰の感情から生まれる涙があってこそ、彼女のハスキーで甘い歌声は映える。
-

-
Saku
START ME UP
映画"ビリギャル"の挿入歌に抜擢されたことで、急遽1stフル・アルバム『FIGHT LIKE A GIRL』と同時リリースされることが決定した初のメジャー盤。"ビリギャル"の書き下ろしとして制作された表題のTrack.1は、奔放なイメージの強い彼女には新機軸ともいえるストレートでエモーショナルな楽曲。居心地の良さを感じられる音楽を手探りしながら求めてきた彼女が歌う"あたらしいあたし好きですか 変わり続けてもいいですか"という言葉が切実に響く。バック・バンドもそんな彼女を抱え上げるようにシンプルで重厚なサウンドを展開し、その一体感は圧巻だ。一転Track.2はポップでガーリーなのに、歌の内容は男子に噛みつくという毒っ気のあるSakuらしい楽曲。この二面性も小気味よい。
-

-
The SALOVERS
青春の象徴 恋のすべて
「ニーチェに聞く」にて4人は声を揃えてこう歌う。"後悔だけは絶対に嫌で 全力疾走今日も続けてる"――2015年3月25日をもって無期限活動休止を宣言したThe SALOVERSの約2年半ぶりとなるフル・アルバム。10代限定フェス"閃光ライオット2014"の公式応援ソングとなった「喉が嗄れるまで」以外未発表の新曲だけを収録、メンバー4人だけで構想から完成までを手掛けたということから今作に対する彼らの全力っぷりが窺える。しかし、歌われる歌詞の一言一言がどうしても無期限活動休止という事実を脚色してしまうことが悲しくもあり悔しい。彼らが何年も歌い続けてきた自身の青春に終止符を打つ瞬間。最後までがむしゃらに全力で走り続けた彼らの姿を、あの青き日々が指標だったあなたの目に、耳に、胸に焼きつけて欲しい。
-

-
The SALOVERS
文学のススメ
The SALOVERSの3枚目となる3曲入りシングルはヴォーカル古館佑太郎の個性的な歌詞とカラフルなバンド・アレンジが定着したことを感じさせる1枚。表題曲「文学のススメ」では理想と現実に悩む文学青年を形どったレベル・ミュージック。"くそったれ"と連呼する様式美ハード・ロック的なメロディのサビが品性下劣な世の中に向けられているようでいて、世間を見下すことは己を見下げることにも繋がるという、インターネット・デフォルト世代ならではの批評性を感じさせる、というのは深読みしすぎ? Track.3のフジファブリックの名曲カバー「茜色の夕日」は、さながら「My Way」を歌うSid Viciousといった趣すら感じさせるほど荒っぽいが、せっかく骨っぽくもリリカルな演奏と、深読みしたくなる独特の歌詞を綴る感性を持っているのだから、もっとオリジナルで攻めてきてほしいと思う。The SALOVERS、期待しているのだ。
-

-
The SALOVERS
アンデスの街でこんな夜はHOT HOT HOT!
2013年4月に初の全国流通盤となる1stシングルをリリースした若手ロック・バンドの2ndシングル。収録曲を全部繋げたタイトルや、蒙古タンメン中本で撮影されたジャケットなどユーモアに溢れているが、その音楽は瑞々しくも骨っぽいギター・ロック。恋するが故に自分が自分でいられないような男の葛藤を"恋をしている 無理をしている"と歌う「HOT HOT HOT!」の、青いようでいて普遍的な感情の発露に超共感。ライヴでも感じたことだが、ストレートでいながら跳ねているリズム隊と曲ごとに表情豊かなリフを絡ませるGtのアンサンブルが絶妙で、そこに乗るVo古舘佑太郎の豊富なボキャブラリーがリズミカルなリリックを作り上げ、耳触りの良いロックとなっている。なにより明瞭でしっかり言葉が届く歌が素晴らしい。さらなる活躍に期待したくなるグッド・サウンド。
-
-
The SALOVERS
珍文完聞-Chin Bung Kan Bung-
その頭角を現したのは2010年、FUJI ROCK FESTIVAL“ROOKIE A GO-GO”に出演。その後も数々のイベントに出演し、オーディエンスを沸かせてきたThe SALOVERSがついにメジャー・デビュー! プレ・デビュー・アルバムにも収録された「オールド台湾」を含む渾身の11曲を詰め込んだ今作を一言で表すならば“初期衝動”。剥き出しで直線的。決して古くはないのだけれど、どこか懐かしいストレートなロックが突き刺さる。その半面、歌詞は文学的だ。多国籍な単語がところどころに散りばめられ、アジアの都市に見られるような極彩色のネオンのように楽曲を彩る。Vo/Gtの古舘が文学少年だったというのも頷ける。まだまだ荒削りだが、バンドの原点と勢いがそのまま楽しめるだろう。
-
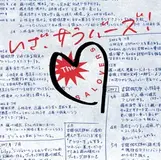
-
The SALOVERS
いざ、サラバーズ!
若手ギター・ロック・バンドの旗手として、常に名前が挙がり続けていたThe SALOVERSが遂にメジャー・デビュー。今作はプレ・デビュー・アルバムと位置づけられ、新曲が2曲とインディー時代の代表曲4曲が収録されている。メジャー・デビュー1作目というと肩に力の入りまくったド直球、ド王道の曲をぶつけてみたくなりそうなものだが彼らが持ってきた1曲目は「オールド台湾」。肩透かしをくらうタイトルではあるが、彼らの荒削りかつ甘酸っぱい焦燥感を携えた疾走感に溢れるギター・サウンド、そして古館 祐太郎(Vo&Gt)の力強い絶対的なヴォーカルは期待の新人というにはあまりにまぶしすぎる光を放つ。まずは名刺代わりのこの1枚から彼らの光を感じ取ってほしい。
-

-
salsa
VERY HARDCORE
都内を中心に活動する3ピース・バンドsalsaの、2枚目となる全国流通盤。3人の音はひたすら自由に、ぶつかり合いによって熱を生み出す。目の前でセッションが行われているような熱量が音源でもしっかりパッケージングされている。耳に残るリフや不可思議な曲調がクセになる曲も多いが、ミディアム・バラード「ブルー」やコーラスが印象的な「Doro」終盤で見せるメロディアスな面も必聴。サウンド面ではまだ粗さが残るもののテリトリーは広く、正直、このフル・アルバムの10曲を聴いてもまだ正体を掴みきれていない印象が否めない。ここからどう化けていくのかが想像できないからこそ、ここからどうにでも化けていける彼らの、次の一手が早くも気になる。
-

-
SALT CATHEDRAL
il abanico
レーベル契約前にNorthside FestivalやSXSWなどに出演し注目を集め、日本にて世界初流通となるデビューEPを昨年12月にリリースした、NYはブルックリンで活動するSALT CATHEDRAL。6月末からregaとの東名阪ツアーが決定している彼女たちが、初来日を記念してバンド初期のレア音源を急遽リリース。エレクトロニカ的なサウンドが際立つデビューEPに比べこの初期音源はインディー・ロック色が色濃く、そこに絡む南米の民族音楽的なリズムが肉体的に聴き手を突き動かす。透明感のあるソフトなJulianaのヴォーカルもその音に触発されるように感情的で、彼女たちの初期衝動を堪能できる。ちなみにアルバム・タイトルはバークリー大学での結成時のバンド名とのこと。
-
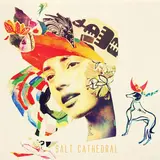
-
SALT CATHEDRAL
Salt Cathedral
レゲエ・ビートが軽やかな「Move Along」で幕を開けるSALT CATHEDRALのデビューEP。コロンビア出身の女性シンガー、Juliana Ronderosを擁するブルックリンの5人組は、すでに海外では話題の存在だという。フォークロアあるいはエキゾチシズムのニュー・ウェイヴ的な解釈とでも言えそうな音楽性は、同郷のDIRTY PROJECTORSや、さらに遡ってTALKING HEADSからの系譜を思わせるが、単にフォロワーとは言えない個性を印象づけているのがJulianaのハイトーン・ヴォイスだ。その奔放なヴォーカルは、早くもカリスマをアピール。リズムを執拗に刻みつづけるギターを軸とした緊張感あふれる演奏とともにヒプノティックな空間にリスナーを誘いこむ。全5曲収録。もっと聴きたい!
-

-
SALTY's
塩
よしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属する塩顔芸人のエア&生演奏グループが、結成4年で満を持してのメジャー・デビュー。配信シングルやライヴで披露されている既存曲に、Czecho No Republic武井優心(Vo/Ba)プロデュースの新曲「塩顔ジェネレーション」を加えた計14曲を収録している(※盛塩盤はライヴを再現したMC&コントも収録した計29トラック)。塩顔男子の苦悩や悲哀をユーモラスに描きながらもロマンチックな世界観に落とし込む歌詞、エッジの効いたピアノとドラムにムーディなサックスが重なるサウンドは、音楽的でハイ・レベル。ポップ・ソングながら、オルタナティヴなセンスを感じさせるアンサンブルをチョイスするところに、メンバーの音楽愛と本気度が伝わってくる。
-

-
SAME
Bloom
三重県出身4ピース・バンド SAME(読み:サメ)の2ndミニ・アルバム。平均年齢21歳の新星ロック・バンドと聞いてもっと粗削りのサウンドを想像していたが、それだけには留まらず。8ビートで駆け抜ける王道メロディック・パンク「アトリエ」(Track.1)に象徴されるような青春真っ盛り感はありつつも、橋田理(Ba/Vo)、橋本卓磨(Vo/Gt)、大橋武留(Gt/Cho)のフロント3人が紡ぐ歌を中心にしたサウンドは、一抹の切なさをもその手ですくい取る。どの曲の歌詞も日本語の響きを大切にしたものになっていて、丁寧に作られている印象だ。前作を引っ提げてのツアーでは地元の三重とファイナルの名古屋をソールド・アウトさせた彼ら。その名前が全国に広がる日も近いのでは。
-

-
SAN CISCO
Between You And Me
紅一点ドラマーも歌う男女ツイン・ヴォーカル・スタイルがナイスなオーストラリアの3人組が3年ぶりにリリースした4thアルバム。アルバム・チャートの3位を記録した本国のみならず、今回もまた、日本のインディー・ポップ・ファンの気持ちを鷲掴みにすることは必至。80年代のUKポップをバックボーンにネオアコからダンサブルなエレポップまで、曲ごとに趣向を凝らす彼らのサウンドは、これまで以上にR&B/ファンク由来の跳ねるリズムを強調したことで、昨今のシティ・ポップにもリンクしはじめると同時に、さらにユニークなものになってきた。中には「Messages」をはじめ、これまでのように80年代、UKというキーワードではくくれない曲も。ある意味、より日本人好みになったという印象もあり。
-

-
SANDAL TELEPHONE
SHUTDOWN→REBOOT
フル・アルバムから約1年4ヶ月で到着の2ndミニ・アルバム。キレ味の鋭いエレクトロ・ナンバー「SHUTDOWN→REBOOT」に始まり、ダークな空気を纏いながら疾走していく「Allegro」、デジタル・ファンクな「悲喜劇的アイロニー」といった、よりクールで、よりスタイリッシュなサウンドを提示しつつ、ポップに弾けるドラムンベースの「UnLucky」など、ライヴを熱く盛り上げる楽曲群も収録。中でも「Sparkle」は、彼女たちのグループ・コンセプトである"音楽で世界を笑わせたい、泣かせたい、踊らせたい"に相応しい、ハッピーながらもエモーショナルな空気が涙腺を刺激する仕上がり。アンニュイな歌声とキュートさもある電気グルーヴの「Shangri-La」カバーも収められている。
-

-
Sandy Beach Surf Coaster
BRAND NEW DAY
Track.1のイントロからライヴハウスで感じる音圧による突風と似た感触を感じる。このバンドで音を出せている喜びや、その感情が浮き動かす興奮がそのままパッケージングされているようだ。"LIFE MUSIC"を活動理念に掲げ、マイペースに活動を続けている愛知県の紅一点メロディック・パンク・バンド、Sandy Beach Surf Coasterの約5年振りとなるオリジナル作品。肉感のある瑞々しいギターと、メロコア直球ではないテクニカルさを併せ持つダイナミックなリズム隊、一抹の憂いを含む等身大のヴォーカル、包容力のある優しいメロディとそれを引き立てるコーラス・ワークと、サウンドからも4人の心が強固な結びつきを生んでいることが伝わる。作品タイトルに偽りなしの、希望に満ちた6曲。
-
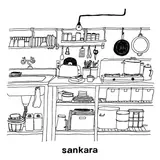
-
sankara
BUD
洗練とオーガニックなグルーヴを感じるトラックの上に乗る、柔らかなRyoのヴォーカルと硬い韻を踏む乾いたTossのラップ。どちらかが欠けても成り立たない人間の感情表現を分担しているようで、クセになる。ヒップホップをバックボーンに持つsankaraだが、縦に跳ねるビート感の「Slipping」など、ジャンルに縛られないトラックがポップ・ミュージックとしての幅を拡張。サーフ・ミュージックやレゲエのムードもある「Trip」は、スケールの大きなライヴで聴きたいイメージだ。現代的なトラックメイキングの中にエヴァーグリーンなソウルやR&B、ジャズのテイストもあり、日常に溶け込む音楽性と、聴き流すにはリアルな心情が吐露されたリリックという、オリジナルなバランスで成立しているのも聴きどころ。
-

-
SaToMansion
the garden
佐藤4兄弟からなるSaToMansionによる2ndアルバムは、前作"the room"から"the garden"というタイトルや、モノクロからカラーになったジャケットの変化にも表れているように、もっと多くの人に届けたいという想いが、歌詞やアレンジをこれまで以上に磨き上げることに繋がったという。身上としている歌謡ロックンロールというスタイルを、ブルース・ハープの導入など、新たな挑戦と共に追求しながら、雄大なバラードを含む多彩な全8曲を収録。それぞれに夢と現実というテーマを歌いながら、生きるうえで誰もが感じる哀愁が前作以上に滲み出てきた。希望も歌いながら、それだけで終わらない人間臭い歌詞も大きな魅力だ。すでに話題になっている中森明菜の「少女A」のカバーも違和感なく収まっている。
-

-
SaToMansion
the room
設定ではなく、正真正銘の佐藤4兄弟がそれぞれの活動を経て、2015年11月に結成したSaToMansionが結成からわずか9ヶ月でリリースする1stアルバム。三男のカズオ(Vo/Gt)と次男のオデキ(Dr)が以前やっていたバンド譲りのロックンロールに留まらない多彩な楽曲の数々は、ライヴハウスのお客さんだけではなく、より多くのリスナーに届けたいというこのバンドにかけるメンバーたちの思いが、歌謡曲とアグレッシヴなバンド・サウンドを掛け合わせたTrack.3「Call you」を中心に放射状に広がりながら実ったものだ。四つ打ちのダンス・ビートの導入など、現在のシーンをしっかりと見据えながら、彼らならではと言える芯が感じられるところがいい。コブシを効かせたカズオのヴォーカルも強烈な存在感をアピール。
-

-
THE MYNABIRDS
Lovers Know
DEATH CAB FOR CUTIEのBen Gibbardらによるエレポップ・デュオ、THE POSTAL SERVICEの再結成ツアーでのメンバーとして活動していたLaura Burhenn。彼女のソロ・プロジェクトがこのTHE MYNABIRDSだ。3作目となる今作は、どこかSSW然としていた、もしくは60年代のポップ・ミュージック的なエッセンスを多分に含んでいたこれまでの作風と異なり、10年代以降のモダンなシンセ・サウンドを機軸としたで質感で統一されている。例えば、アブストラクトなビートとアレンジの効いたTrack.2やブーミーなシンセ・ベースやメロディがどこか80'sリバイバル的なTrack.3など、新たなテイストでまとめ上げる。近年のUSインディー・シーンが才気溢れる人材の宝庫であることを改めて印象づける1枚。
LIVE INFO
- 2025.11.18
- 2025.11.19
- 2025.11.21
- 2025.11.22
- 2025.11.23
- 2025.11.29
- 2025.11.30
- 2025.12.09
- 2025.12.22
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























