DISC REVIEW
R
-

-
RADIOHEAD
A Moon Shaped Pool
あくまで直感なのだが、9.11以降の世界のパワー・バランスの崩壊を予見したような不気味な『Kid A』以降、RADIOHEADの不穏な通奏低音は変わらない。だが、この新作はそれでも人が人としてよりよくお互いを思いやり生きるための、何か心のチューニングを整える一歩前に出た印象がある。具体的には近年、フル・オーケストラやイスラエルのミュージシャンとの仕事も行うJonny Greenwoodと、ソロでDJ的な表現も行ったThom Yorke双方のアプローチが並列する「Burn The Witch」、久々にギターらしいギターが聴ける「The Numbers」、抑制されているものの、リズムがサンバであることに驚く「Present Tense」など、音楽があらゆる境界を溶かす静かで微かな希望が聴こえてくるというか、身を浸していると感じられる。
-

-
V.A.
Hostess presents NO SHIT! 2
2000年創立以来、旬なアーティストや海外でも評価の高いバンドを次々とリリースして来たホステス・エンターテインメントのレーベル・コンピ第2弾が登場。前作も充実の内容だったが今作はそれを上回る豪華さ。RADIOHEADやARCTIC MONKEYSの新作からはもちろん、2011年の年間ベストに軒並みランク・インしているBON IVERなどが収録されたDISC1は今年の洋楽シーンを手っ取り早く知る意味では最適の1枚。続くDISC2は話題沸騰のHOWLERを始めICEAGEなどこれからが期待される新人が並ぶ。ジャンルを横断しながら今の空気をしっかりと伝えるセレクト。個人的にはDISC2をしっかり聴き込んでほしい。とにかくお得なアルバムだ。
-
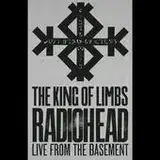
-
RADIOHEAD
King Of Limbs: Live From The Basement
現ロック・シーンの重要アイコンはどこへ向かうのか?RADIOHEADがスタジオ・ライヴ映像作品『Live From The Basement』をリリースする。本作のポイントは、最新作『The King Of Limbs』の8曲に加え「The Daily Mail」と「Staircase」の未発表音源&RECORD STORE DAYにて限定リリースされた12インチ・シングル「Supercollider」のライヴを収録。さらにサポート・ドラマーを含む新体制の6人編成でパフォーマンスを行なっている。また、最近のRADIOHEADはメディア露出が少なく、スタジオ舞台裏風景を収めた映像も貴重なものだろう。昨年リリースされたリミックス集から本作と多角的な考察を強いる『The King Of Limbs』だが、ブラッシュ・アップされたアンサンブル、細分化されたリズムにフィジカルなロックンロール回帰を促がしているように思えるが......その答えはあなたの眼で確かめてほしい。
-

-
RADIOHEAD
TKOL RMX 1 2 3 4 5 6 7
今年2月に発表されたRADIOHEADの8thアルバム『The King Of Limbs』。そのリミックス・シリーズが完全生産限定12インチ・アナログ・シングルでリリースされ、即完売していた。だが今回そんなリミックス・シリーズが、2枚組アルバムとしてリリースされることに急遽決定。Four Tet、CARIBOUなどクラブ・シーンで活躍する人物や、NATHAN FAKEやSBTRKTなど今日のミュージック・シーンを盛り上げるアーティストまで幅広いリミキサーが揃っている。「Bloom」は5種類のリミックスが収録されているが、原曲を生かしたアレンジ、原曲を一切無視し楽曲のとある箇所だけをフィーチャーしたアレンジなどなど、手掛ける人物によってまったく違う側面を切り出してくる。これぞリミックスの醍醐味だ。
-

-
RADWIMPS
記号として /'I' Novel
これまでバンドを支えてくれたファンに対する感謝の気持ちを込め、RADWIMPSがリリースしたメジャー・デビュー10周年記念の両A面シングル。持ち前のミクスチャー・ロック感覚を、とことんアグレッシヴ且つトリッキーに、そしてスピーディに表現した「記号として」とフォーキー且つメロディアスに、この10年間を振り返った「'I' Novel」。後者はヒップホップを生バンドで演奏したようなダンサブルな魅力もある。その2曲に加え、歌と演奏を同時に一発録りした「お風呂あがりの」も収録。マンドリンとウッドベースを使ったドラムレスの正調フォーク・ナンバー。そんなイレギュラーとも言える曲も含め、バンドの懐の深さを改めて印象づける3曲。こういう感謝の表現のしかたがファンには1番嬉しい。
-

-
RADWIMPS
ピクニック
1年8ヶ月ぶりのニュー・シングルは、バンドのフロントマンである野田洋次郎が主演を務める映画"トイレのピエタ"の主題歌。その1曲のみ収録したところにこの曲に対する誠実な想いがうかがえる。余命3ヶ月を宣告された主人公が死を目前にして、ついに感じることができた生きることへの想いを詩的に歌い上げたバラード。ギターの弾き語りと思わせ、想いを吐き出しながら高ぶっていく主人公の気持ちを表現するようにストリングス、ピアノが加わり、最後はバンドの演奏とひとつになってドラマチックに盛り上がる。それにもかかわらず、聴き終わったあと、深い感動とともに残るのは静謐という印象。生と死を歌った壮絶なバラード。アンビエントな音響を意識したと思しきサウンド・メイキングも聴きどころだ。
-

-
RADWIMPS
×と○と罪と
恋愛を歌い続けていた『RADWIMPS4~おかずのごはん~』までの4作品、よりバンドの音像を強度にし、人が目を逸らしがちな闇と向かい合い言葉を紡いだ『アルトコロニーの定理』と『絶体絶命』。その6つを経て作り上げられた『×と○と罪と』は、過去最高に切実で痛烈、そして何より素直で自由だ。自然体な音と言葉からは喜怒哀楽が生々しく滲み、ひとつひとつが心臓の中心を抉るように突き刺さる。その痛みの正体は"真実"。こんなことを言えば嫌われるかもしれない、気持ち悪がられてしまうかもしれない――綺麗な嘘の防御だらけの世の中で、彼らは傷つくことを恐れることなく"本音"を鳴らす。その勇敢な姿は美しく、偽りの世界に溺れる我々の救世主のようだ。RADWIMPSはまた新たな地を開拓した。
-

-
RADWIMPS
五月の蝿/ラストバージン
現在、アルバムに向け、新曲を作っているというRADWIMPSから届いた約7ヶ月ぶりとなる両A 面扱いのNEWシングル。ともにミッド・テンポのロック・ナンバーながら、激しい「五月の蝿」と穏やかな「ラストバージン」それぞれに正反対と言える曲調。究極のラブ・ソングらしい。愛の終わりと始まりを歌ったと考えれば、曲調の差も頷ける。「五月の蝿」の歌詞は、話題になっているように確かに衝撃的。気分が悪いという感想も理解できる。しかし恋愛っていうのは本来、これぐらい激しく感情が揺さぶられるものだろう。それを思えば、世の中にあふれている、きれいごとだらけのラブ・ソングのほうがよっぽど気持ちが悪い。歌詞を云々するよりもこれをメジャーからシングルとしてリリースする意味を考えるべきでは?
-

-
illion
UBU
日英独仏にてリリース、初ライヴはロンドンにて開催など、海外進出が大きなトピックとなっているRADWIMPS野田洋次郎のソロ・プロジェクト"illion"。初作品『UBU』は野田洋次郎というひとりのアーティストの音楽的才能がとめどなく溢れる荘厳なアルバムだ。生楽器と打ち込みは歌声と共に丁寧に音を編み込み、国やジャンル、理論や制約など、枠組みや既成概念を消してしまうように解き放たれてゆく。冷ややかでありながらぬくもりが滲み、哀しくも優しく、無機質でありながらも肉体的で、時に牙を剥いて襲い掛かり、時に人懐こく懐に潜り込む。そんな奔放さは捉え方によって様々な印象を得られるが、一貫しているのは揺るぎない自身の音楽への信念と挑戦。その姿勢はどこまでも勇敢で美しい。
-

-
RAGE AGAINST THE MACHINE
Rage Against The Machine 20th Anniversary Edition
衝撃的なジャケットと革新的な音楽性と直接的なメッセージで世界に強烈な印象を残し全世界で500万枚ものセールスを記録したRAGE AGAINST THE MACHINEの1992年のデビュー・アルバムが新たに20周年アニヴァーサリー・エディションとなって登場。今でも全く色褪せない衝撃と驚きを与えてくれるモンスター・アルバムだ。DISC2には貴重なデモ音源とDVDには当時のMVとライヴ映像が収録。初期のエネルギッシュなライヴ・パフォーマンスはファンならずとも圧倒されるだろう。彼らが創り出したメタリックなギター・リフとヒップホップとファンクの融合は、後のミクスチャー・ロック、オルタナティヴロックに多大な影響を与えた。血が煮えたぎる1枚。
-

-
Rain Drops
バイオグラフィ
8月に初のワンマンを成功させたVTuberユニット、Rain Dropsの初のフル・アルバム。異なる個性を持った6人の歌声が複雑に絡み合うオープニング・ナンバー「エンターテイナー」をはじめ、緑仙&三枝明那&ジョー・力一による不気味なラップ曲「ブギーマン」、える&童田明治&鈴木勝による透明感のあるミディアム・テンポ「Butterflies」など、ひとつのジャンルにとらわれない、ユニットの特性と組み合わせの妙を生かした多彩な楽曲を収録する。楽曲を手掛けたじん、堀江晶太(PENGUIN RESEARCH/Ba)、ヒトリエ、Q-MHzら実力派バンドからのメンバーはプレイヤーとしても参加。コアな音楽ファンにも訴求するロック・サウンドをバックに、ハイレベルに対峙する歌の存在感は唯一無二だ。
-

-
Rain Drops
オントロジー
タイトルの"オントロジー"とは、哲学用語で"存在論"と訳される言葉だという。生身の肉体を持たず、バーチャルな空間でVTuberとして音楽活動を始めたRain Dropsが、自らの存在意義を証明するために完成させたミニ・アルバムだ。緑仙、三枝明那、童田明治、鈴木勝、える、ジョー・力一という6人の歌声が個性豊かに交錯しながら描き上げる全7曲には、とても人間らしい感情の機微が描かれている。作家陣には前作に引き続きヒトリエのゆーまお(Dr)、ポルカドットスティングレイのウエムラユウキ(Ba)、cadodeのebaが参加したほか、インターネット・シーンで注目を集めるじん、柊キライやツミキたちが楽曲を提供。一部メンバーが初めて作詞にもチャレンジしたことで、クリエイティヴに深化を遂げる1枚になった。
-

-
RAMMELLS
Mirrors
新進気鋭のロック・バンド、RAMMELLSの2ndフル・アルバム。本作では、ロック、ブルース、ジャズなどのルーツ・ミュージックを軸としながら、そこに70年代から現在までのダンス・ミュージックの要素を取り入れた、"ネオ・ノスタルジー"とも呼べるサウンドを展開する。リード曲「真っ赤な太陽」から幕を開け、ロック色の強いギター・リフと浮遊感のある音像が夢と現実を往来するような「Surrealism」、ファンへ向けたラヴ・ソング「Over the purple」、ジャズ・ファンク調の「Echo」など、それぞれ個性が強く自由度の高い10曲が収録されている。クールでいながら、時に甘く気だるい色気を醸し出し、さらにキュートな一面も見せる、表情豊かな黒田秋子の歌声にも注目だ。
-

-
RAMMELLS
take the sensor
ビター・スウィートなミドル・チューン「Sensor」と、弾けたディスコ・フィーリングが印象的な2曲目「FINE」は、ちょっと捻った曲展開でサイケな世界を演出している。そして、これまでは使用していなかったシンセ・ベースも効いた「YOU」。ソウルとロックをふたつの軸として置きつつ、時代感や様々なジャンルを往来するオリジナルな折衷感覚と、メンバーそれぞれが作曲を手掛け音楽的なイニシアチブを持てるという、見方を変えれば、ひとりひとりが状況に応じて適材適所な役割を果たせる特性が、前半3曲でよくわかる。その強みが生むバリエーションは単純計算でも無限大だ。RAMMELLSという"バンド"だからこその可能性に溢れていて、早くも次作が楽しみになる1枚。
-

-
RAMONA LISA
Arcadia
NYはブルックリンのシンセ・ポップ・デュオCHAIRLIFTのヴォーカリスト、Caroline Polachekによるソロ名義=Ramona Lisaの1stアルバム。タイトルに関せられた"アルカディア"とは古代ギリシャから伝わる牧歌的な理想郷を意味するが、本作『Arcadia』は、まさにそんな理想郷=アルカディアを夢想させるに相応しい1枚だ。都会的なポップネスを持っているCHAIRLIFTとは異なり、Carolineの艶やかで幽玄なヴォーカル・ハーモニーと牧歌的なメロディ、そしてそこに何重にもレイヤーをかけた白昼夢のようなアレンジは、聴き手を"ここではないどこか"へと誘うような非現実味を帯びている。アルバム全体に流れるエレクトロニック・ビートは、まるで洞窟の奥深くへと案内する不穏な足音のようだ。このくだらない現実から一時離れるにはうってつけの甘美な作品。
-

-
Ran
無垢
福岡県出身のSSW、Ranによるデビュー・ミニ・アルバムは、"自身に向き合った嘘のないもの"をテーマとした6曲入り。冒頭のシューゲイザー風のギターからダークな一面が垣間見える「黒い息」、"今日も外面は笑っていて心の中では泣いていました"というストレートながらに本質的な思いが受け取れる「蘇生」、芯のあるバンド・サウンドに乗せて鬱憤とした感情を吐き出した「悲劇ごっこ」、届きそうで届かない想いを切なくピュアに描いた「靡かない」、軽快なサウンドの中に刺さる言葉を散りばめた「環」、未来への決意も窺える「ご飯の食べ方」と、くるくると変わる感情のひとつひとつをそれぞれ歌として昇華している。何より彼女の爽やかで一本筋の通った歌声は、聴く者の心をスッと軽くする力があると思う。
-

-
THE RAPTURE
In The Grace Of Your Love
THE RAPTUREより、実に5年ぶりの最新作が到着!メジャー・デビュー作にして多方面を騒がせた『Echoes』。DFA Recordsを離れ、自分たちだけで完成させた『Pieces Of The People We Love』。彼らが彼ら自身を紐解き、力量と秘めたる才能を見いだすことに成功した前作でみせた“会新のTHE RAPTURE”ともいうべき姿。至高の愛のかけらが煌めき飛び交う最高のダンス・ミュージックから5年、本作はその5年間を集約したような、大海を彷徨うような途方もないスケールを持ち合わせる。バンドと供に5年間という空白の時空を一気に越えていくような、雄大にして、優美な世界。今度の彼らは、“ダンス”だけじゃない。“酔いしれるように踊り”、“踊るように酔いしれる”。
-

-
RA RA RIOT
Need Your Light
ブルックリンのシーンの中でもある種の素朴さとスウィートなキャラクターがRA RA RIOTの作品の人懐こさにも繋がっているのは間違いない。特徴だった弦のパートが後退したのは前作『Beta Love』同様なのだが、VAMPIRE WEEKENDのRostam Batmanglij(Key/Vo)と共作した「Water」の民族性とマンチェ・ビートが融合したような印象的なミディアム・テンポ感や、同じくRostamと共作した「I Need Your Light」での朗らかさとホーリー感が自然と同居する感覚は彼ららしさを残しつつの新機軸。今や常道になった生音とシンセの配分も、彼らの手にかかるとどこか手作り感溢れるものになる。洗練されすぎず、でも今の感覚でポジティヴな感覚を残してくれる、日常への親和性の高い良作。
-

-
RA RA RIOT
The Rhumb Line
良質な作品はどんなに時が経とうと色褪せない魔力が宿っているもの。08年にリリースされたRA RA RIOTのデビュー・アルバムにはそれがある。チェロとヴァイオリンを活かした作風はARCADE FIREに通じる気品があり、ポスト・パンク的なビートやアフロ・ポップなノリにはVAMPIRE WEEKEND の姿がチラチラと浮かび上がる、チェンバー・ポップな世界観。贅沢(というかありえない!)な邂逅を想像してしまったが、全体をほのかに包み込むダークな印象には、やはり最愛のメンバーであるドラマーの死去が影響しているからだろう。だからこそ力強く吐き出される「Ghost Under Rocks」や意味深な「Dying Is Fine」、鎮魂歌のような「Winter' 05」は感動的に魂を揺さぶる。魔力とは、この想いの強さなのだ。今夏には2nd アルバムもリリース予定なので、そちらもチェック!
-

-
RAY
Camellia
"『アイドル×????』による異分野融合"と"圧倒的ソロ性"を掲げるアイドル・グループ RAYによる、現体制からの楽曲のみで構成された3rdアルバム。本作では、グループの代名詞とも言えるシューゲイズに変拍子を取り入れた「読書日記」や、初のシューゲイズ・バラード「ため息をさがして」などで、これまでのRAYの世界観をさらに深化させている。その一方で、ダンサブルなエレクトロの「フロンティア」、青木ロビン(downy/zezeco)が制作し、中尾憲太郎(Crypt City/勃殺戒洞/ex-NUMBER GIRL)、BOBO、ケンゴマツモト(THE NOVEMBERS)という豪華な演奏陣を迎えたオルタナティヴ・ロックの「火曜日の雨」ほかで新境地も見せた。音楽好きに長く愛されていきそうな名盤の誕生だ。
-

-
RAZORLIGHT
Olympus Sleeping
フロントマン Johnny Borrellが"ロックンロールへのラヴ・レター"だと語る10年ぶりのニュー・アルバムは、FAT WHITE FAMILYやSHAME、DREAM WIFEら新鋭の登場で盛り上がりを見せるロンドンのインディー・ロック・シーンにとっても、愛のメッセージであるに違いない。THE LIBERTINESに続くアイコンとして人気を博したRAZORLIGHTのデビュー当時も同じく、ガレージ・ロック・リバイバル・ムーヴメントによるUKロック再興の最中であった。そんな彼らの復活作は、原点回帰とも言える色彩豊かな疾走感溢れるガレージ・ロック、ロックンロールを展開。青春時代を切り取ったような瑞々しい1枚に、先述の若手バンドたちも心揺さぶられるだろう。
-

-
reading note
人間味
2016年10月には再び3人から4人体制に戻り、自主レーベルを立ち上げたreading noteだが、ミニ・アルバムは前作『19200』以来約2年4ヶ月ぶり。この間、おそらくバンドは苦しい経験もしてきたのだろう。しかし本作では、昨年末リリースのシングル『花』に引き続きレコーディング・エンジニアに池田 洋(never young beach、Yogee New Wavesらを担当)を招いたり、デジタル・サウンドを取り入れることに挑戦していたり、メジャー・コードの明るい響きをした曲が増えていたりと、逆境をチャンスと捉え、サウンド面の刷新を試みるバンドの前のめりな姿勢がよく表れている。"人間味"を文字どおりひとつの味(あじ)として捉えるユーモアの効いた歌詞の世界観も良いスパイスに。
-

-
reading note
19200
自分を変えてくれるのは、繰り返される日々に意味を見つけてくれるのはいつだって周りの人々や環境の変化であって欲しい。"五月病バンド"と称される大阪発の4人組バンド、reading noteはストレートなギター・ロックにそういった諦めや憤り、そこから生まれるため息まですべて音に込める。生々しい感情で綴られた歌詞はゆっくりと心を蝕んでいくようだ。はっぴぃえんどや高田渡などを輩出し、日本のフォーク・ロック創世記を作ったBellwood Recordsの新レーベル、ROCKBELL recordsよりリリースされるこの2ndミニ・アルバム。リアリティがあり自己を見つめる歌詞を中心としたロックを放つこのレーベルから、reading noteはあなたに赤裸々な心情を投げかける。
-

-
ЯeaL
ライトアップアンビバレンツ
2017年に"銀魂"OPとなったシングル「カゲロウ」や、1stアルバム『19.』を発表してから3年。1stアルバムのツアー後3人体制となって、シングルのリリースやツアーを重ねながらバンドを強靭に叩き上げてきたЯeaL。待望の2ndアルバムはバンド・サウンドやアレンジが洗練された。もともとソングライター、Ryoko(Vo/Gt)による膨大な音の情報量を詰め込んだ曲を、爆発的なアンサンブルとハイパーな歌で駆け抜けていく痛快さが、"THE ЯeaL"というサウンドであり武器だったが、その魅力を削ぐことなくアレンジが整理され曲が鋭さと華やかさを増した。単純な引き算でなく、思いの質量はぐんと上がっている。バンド・サウンド、ギター・サウンドにこだわり磨き上げてきた賜物的な作品だ。
-

-
ЯeaL
強がりLOSER
"銀魂."や"ポケットモンスター サン&ムーン"の主題歌に続き、"BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS"のEDテーマを書き上げたЯeaL。アニメとの相性もいい、ポップで疾走感たっぷりの爽快なロック・ナンバーは、彼女たちの十八番といったところだ。厚みのあるギター・サウンドで畳み掛けるパワフルな表現や、"Fight again‼"というキーワードとともに紡がれるシンプルなメッセージは、同世代のみならず、アニメを観る多くの子供たちの心をも掴むだろう。c/wにも、明治ザバス×バスケ日本代表の動画タイアップ・ソングになっているキャッチーな応援ソング「go!!」や、グルーヴ感もありつつアッパーな「エンドロール」といった楽曲が揃う充実した内容。
-
-
ЯeaL
未来コネクション
1stアルバム『19.』以来、1年ぶりとなるЯeaLの新作は、TVアニメ"ポケットモンスター サン&ムーン"のOPテーマ曲としてオンエア中の「未来コネクション」。ポジティヴにポンと背中を押すような曲となった。ЯeaLといえば、スピーディでキメと展開が多い、弾けた勢いのある曲が十八番だが、この「未来コネクション」は走ったり、止まったり、少し寄り道をしたりしながら足を進める、誰かに並走するようなテンポで歌を歌う。ソリッドなバンド・サウンドと、高揚感のあるサビのメロディ、キラキラとした音色とワイワイとしたコーラスはとてもキャッチー。このアニメを観て育った子供たちが、あとになって何か思い出とともにこの曲のエネルギーや力を思い起こせるような、鮮やかな煌めきがある。
-

-
ЯeaL
19.
大半の曲が、高校2、3年生のときに書かれたという、10代の集大成であり、リアリティが詰まった1stアルバム。10代の多感でエネルギー過多な感覚と、一方で冷静な観察者として同年代の言動、心の内をつぶさに、ソングライター Ryoko(Vo/Gt)は描く。加えて、J-POPやロックを研究して、"キャッチーさ"へと昇華したサウンドはとてもカラフル。曲構成がテクニカルだが、頭でっかちではない、キラキラとした感性と衝動感が詰まっていて、今でしか描けない瞬間を封じ込めたものだとわかる。観察者として毒づくシーンもあるけれど、皮肉をも、4人の演奏でポップなちょっと笑える曲に変換するパワーが、リスナーがフレンドリーで共感を覚えるところなんだろう。彼女たちの、上手さと曲の旨味とが濃厚に味わえる1stアルバムだ。
-

-
ЯeaL
カゲロウ
デビュー・シングル『秒速エモーション』から、10代らしからぬ卓越したアンサンブルを聴かせるガールズ・バンド、ЯeaLの3rdシングル曲「カゲロウ」は人気アニメ"銀魂."のオープニング・テーマに決定。2周目には一緒に口ずさめる、キャッチーでインパクトの高いメロディに磨きがかかり、リスナーの間口を広げそうな1曲だ。ЯeaL節とも言える、リズム・チェンジや猫の目のようなサウンド展開やギミックは控えめで、シンプルな構成の曲で惹きつける上手さが光る。カップリング「ひらり舞う」は春の別れと出発の季節に似合うドラマチックなロック・チューンで、もう1曲の「満月の夜に」はRyoko(Vo/Gt)のハイトーンが冴える、ウルトラ・ポップな高速チューン。振り切った幅広い曲調を、さらっと聴かせてしまうから恐るべし。
-

-
ЯeaL
仮面ミーハー女子
シングル『秒速エモーション』でデビューしたティーンズ・ガールズ・バンド、ЯeaLの2ndシングル表題曲「仮面ミーハー女子」は、コミュニケーション・ツールとしてSNSが当たり前にある10代の彼女たちならではの、本音と建前をリアルに綴った1曲。スピード感のあるビートと、フックたっぷりのギター・リフによるキャッチーなサウンドで、本音の毒を含んだ歌もポップに響かせる爽快さがある。負けん気の強さと、貪欲さの表われなのか、これは面白いというものをどんどん取り込んで咀嚼して、吐き出してと、凄まじいスピードで新陳代謝を繰り返していくような、情報量も自由度も高いサウンドとなっているのも面白い。勢いよく、歪に積み上げた感もあるのに、それだけじゃない。有無を言わさぬ説得力があるのは、自分たちの音楽への自負と愛があるゆえか。
-

-
REAL ESTATE
In Mind
懐かしい――ニュージャージー州出身のREAL ESTATEの音に耳を傾けるたび、場所や時間を問わず、ノスタルジックな気持ちにさせられる。ソフト・ロックを追求し続け、普通と普遍を掛け合わせたポピュラー・ミュージックには、そんな人の記憶にアクセスする作用があるのかもしれない。昨年、結成時からのメンバーであったリード・ギターのMatt Mondanileが脱退。新たにJulian Lynch(Gt)を迎え入れレコーディングされた4作目は、本来バンドにとって新章を告げる作品となると思われた。しかし、全体を通して感じる音色はどこまでも流麗で、奇をてらうような仕掛けもない。すべてをフラットに受け止める彼らの音楽はただひたすらに優しい。疲弊した現代に、急かされるように生きる日本人のような人種にこそ、彼らの音が必要だ。
-
-
REAL ESTATE
Days
瞼の裏に浮かぶは、澄んだ空気に満ちた森の中でのジャム・セッション。キラキラとした木漏れ日はまるでライティングのように照らされ、気心知れたメンバーのアンサンブルは上品で優しく、かつ甘酸っぱい蒼さもあり、親密に奏でる楽しさに溢れている――そんなイメージを抱かせたのはデビュー・アルバム『Real Estate』だった。"USインディの良心"と謳われ、一躍シーンの最前線に躍り出た3ピースから待望の新作が届けられた。ディストーション皆無なクリア・トーンで貫かれたサウンド、浮遊感ある囁き声は前作の系譜にあるが、さらに磨きをかけ軽やかにしたような仕上がりだ。一見シンプル過ぎて平凡に感じるかもしれないが、耳をすましてこのメロディに泳いで欲しい。微睡むほどの心地良さがクセになるだろう。
-
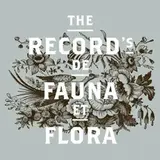
-
THE RECORD’S
De Fauna Et Flora
イタリアの超ド級スリー・ピース・ポップ・バンドが遂に日本デビュー。THE BEATLESやTHE BEACH BOYSなどの影響が如実に表れた楽曲もあれば、ジャワイアン的なトロピカル要素も見え隠れ。時代と国を股に掛けたポップ・チューンを堪能出来る。若干クリアではない音質との相性が極上だ。3曲目「I Love My Family」はギターが効果的で奇声も混じる酔っ払い並のハジケっぷり。だが4曲目「Panama Hat」は一転、オールディーズへの敬意に溢れたカントリー・ミュージック。これ本当に同一人物?と呆気に取られてしまった。このギャップも彼ら流のポップ・アプローチなのだろう。のどかさとキャッチーさが際立つ中で、さり気なく風味を効かすマニアックな音色や美メロもニクい。
-

-
The Recreations
Swing Together EP
昨年、一部の専門店でヒットを記録したThe RecreationsによるEPがついに全国流通されることに。The Recreationsは、作詞作曲とすべての楽器演奏をセルフ・プロデュースで行う南葉洋平のソロ・プロジェクト。初の音源集となるこのEPも、もともとはSoundCloud上で発表した楽曲を再録および再ミックスしたものに未発表曲を加えたものだ。パワー・ポップを基調としながら、90'sなオルタナ・サウンドや80'sニュー・ウェーヴのエッセンスも取り入れた曲の数々を聴けば、早耳のポップ・マニアたちが狂喜したのも頷ける。さらには往年の渋谷系に通じるスウィンギンなピアノ・ナンバーやシティ・ポップスも加え、稀有なポップ・センスを存分にアピール。ELO的な奇矯さに思わずニヤリ。
-

-
RED EARTH
RED EARTH 0
総勢9人の"フォークソングパーティ"、RED EARTHが1stアルバム『RED EARTH I』と2ndアルバム『RED EARTH Ⅱ』に続く、シングル『RED EARTH 0』をリリース。シングルと謳ってはいるものの、新曲4曲に加え、これまで広く流通させてはいなかった過去曲6曲を収録した、全10曲というボリューム。メロディアスなポップ色が強い前者と、激しいガレージ・サウンドが前面に出た後者は、ある意味対象的とも言えるのだが、両者の間に不思議と違和感はない。彼らが最初からその音楽性を"フォークソング"と形容していたように、持ち前の歌心が、異なるスタイルを1本の線で繋ぐ。そんなRED EARTHというパーティの本質を突き、自らの音楽に自ら新たな光を当てた1枚となっている。
-

-
RED EARTH
RED EARTH II
大阪を拠点に活動する"22世紀型爆音フォークソングパーティ"の2ndアルバム。基本はベースレスの変則的な楽器編成で、レギュラー・メンバー以外にもメンバーが存在するためライヴごとにメンバー構成が異なるとのことだが、今作はアコースティック&エレキ・ギター、ドラム、サックスで作られているようだ。寺澤尚史(Vo/Gt)の巻き舌気味のヴォーカルに煽動されるようにハイテンションで突き進む「22 century folk boy」、女言葉でひたすら詰め寄ってくる迫力に思わず笑ってしまう「YURUSANAI」、スカ・パンクっぽい「飛び出せシンドバッド」など、ギター・ロックにサックスが加わってダンディ且つユーモラスな楽曲が並んでいる。怒られそうな(!?)オマージュ・ジャケットも含めて掴みどころのないエンタメ感がある。
-

-
RED HOT CHILI PEPPERS
Unlimited Love
6年ぶりの新作にして、2019年に復帰したJohn Frusciante(Gt)が約16年ぶりに制作へ参加したアルバム。17曲(+ボーナス・トラック)に及ぶ収録曲は、4人が再会の喜びを分かち合い、ああだこうだ言いながら放浪の旅を楽しんでいるような、互いへのリスペクトと愛に溢れたサウンドだ。10thアルバム『I'm With You』以来のコラボとなった長年のプロデューサー、Rick Rubinによる生々しい音像もメンバー同士の一体感を増強している。一聴してのキャッチーさは少ないかもしれないが、スムースに流れるトラックの中で随所にほとばしるケミストリーが、聴くたびに新たな発見をもたらしてくれる。紆余曲折を経てたどり着いた、今のレッチリをありのままに詰め込んだようなアルバムだ。
-

-
RED HOT CHILI PEPPERS
I'm With You
2枚組という大ヴォリュームでリリースされた『Stadium Arcadium』以来、約5年振りの待望のオリジナル・アルバムがとうとうお目見え! Josh Klinghoffer(Gt)が加入して初のリリースとなる本作は、10thアルバムという節目に相応しいユーモアと愛に溢れた作品に仕上がった。未知なる世界を手探りしながら追究し、それを心の底から楽しんでいるような好奇心。そんなやんちゃさと素直さ、大人になったからこそ感じることが出来る様々な想いが、ドラマティックな空間を作り出す。美しいコーラス・ワーク、予測不可能な曲展開、ピアノ等を大胆に取り入れたりと、遊び心はとどまることを知らない。"キャッチー"や"ポップ"という言葉だけでは片付けられない、非常に深みのあるアルバム。名作!
-

-
redmarker
redmarker (the red album)
メンバー全員が20代になったばかりの3ピース、redmarker。10代のときに作った曲の再録や20代になって作った新曲、全10曲を収録した初のアルバムが完成した。先行リリースした「i'm happy i was born.」は、NIRVANAをオマージュしたグランジ/オルタナ・サウンドで、アルバムもその雰囲気かと思いきや、WEEZERやTHE RENTALSを思わせるキャッチーな曲から現代的なポップ・パンク、憂いのあるミディアムなギター・ロックなど、そのサウンドは幅広い。やりたいことを形にする無邪気さや大胆不敵さは、1stアルバムだからこそだろう。熱量は高く、しかしどこかひねくれてもいる。暑苦しいままではきっと伝わらないから、と3人は言う。ポップさやひとひねりの遊び、時に漂う気だるさがいいエッセンスになっている。
-

-
rega
Rega
結成10周年を迎えたRegaの新作は、1stミニ・アルバム『RONDORINA』、1stアルバム『Million』、配信限定楽曲など初期曲の現メンバーでの再録を中心に、新曲やリミックスを交えた全12曲入り。その表現力と描写力、デリケートさやメリハリが、既出の曲を今の曲として甦らせているのも印象深い。かつてのやんちゃさを現在ならではの手腕を用いて再録された各楽曲は、現ギタリスト 四本 晶の加入以前の曲を、今の4人ならではのサウンド、表現がなされているものばかり。彼らの特性をアラカルト的に抽出し凝縮された新曲「Wreck」の秀逸さもさることながら、デリケートさとダイナミズムにおける表現力のアップも著しい「JOG」など、中心となった既出各曲も新しい息吹を受けて新鮮に聴けるのも特徴的だ。
-

-
rega
Among the flow
昨年リリースされたミニ・アルバム『DISCUSS』に続きメンバーそれぞれが1曲ずつイニシアチブを取るという"1人1曲"がテーマとなった2部作の後編。前回は"議論"という少々緊張感漂うタイトルだったが、今回は"流れの中で"という、非常にregaらしいナチュラルなスタイルが反映されていることを物語る。メンバーいわく"非常にパーソナルな作品になった"とのことなのだが、個人それぞれを反映したどの曲でもすべての楽器が爽快に響くのは、バンドが健康だという何よりの証だ。ギターの掛け合いとそこに入り込むリズム隊が遊び心たっぷりのTrack.4、夏からライヴでも披露され既にアンセム化しているTrack.2など、口元をほころばせながら音を奏でる4人の姿が容易に想像できる。
LIVE INFO
- 2025.11.29
- 2025.11.30
- 2025.12.09
- 2025.12.22
- 2025.12.27
- 2025.12.29
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























