DISC REVIEW
W
-

-
THE WALKMEN
Lisbon
2002 年にNY のガレージ・シーンに登場してからTHE STROKES やVAMPIRE WEEKEND などに影響を与え、前作『You & Me』が英紙ザ・ガーディアンで満点を獲得して世界中から絶賛を浴びたバンド、THE WALKMEN。Frank Sinatra のような硬質でソウルフルな歌声を持つHamilton Leithauser が、エフェクトが強くかかりはち切れんばかりになっているがどこか温かみもあるギターと、深いリヴァーブで曇ったオルガンに乗せて歌う捻くれたソウル・ソングは決して他人には見せようとしない純粋&壮大なロマンチシズムを持ち、基本的に何を考えてるのか分からないクールな男を想像させる。全体的にミドル・テンポな曲が多く、どこか夢想的な雰囲気に満ちているのもこのクールな魅力に拍車をかけている。渋い・・・。
-
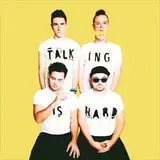
-
WALK THE MOON
Talking Is Hard
アメリカ、オハイオ州出身の4人組シンセ・ポップ・バンド、WALK THE MOONが自身2枚目となる今作『Talking Is Hard』で日本デビューを果たす。バンド名は、THE POLICEの名曲「Walking On The Moon」にヒントを得たというだけあって、高揚感のあるシンセ・サウンドやバウンシーなビート、突き抜けるほどにキャッチーなヴォーカルやどこかヘンテコさのあるメロディなど全編を通して80年代のポップ・ミュージックのエッセンスを感じさせる。スマッシュ・ヒットを記録した完全無欠のポップ・チューンTrack.3はもちろん、爆発するようにハード・ロッキンなパートが差し込まれるTrack.4、80'sソウル的な甘美なメロウさのあるTrack.12など、非の打ちどころのないアッパー且つダンサブルなポップ・アンセム集。
-

-
WALLOWS
Nothing Happens
俳優としても活動するDylan Minnette(Vo/Gt)を中心とした、南カリフォルニア出身の3人組インディー・ロック・バンド、WALLOWS。2017年にリリースしたシングルがバイラル・チャートでヒットし、注目を集めていた彼らが、待望の1stアルバムを完成させた。ポスト・パンクの影響が垣間見えるビートに、気だるげな歌声とドリーミーなシンセ、そして青春の甘酸っぱさを具現化したような衝動と混沌がミックスされたサウンドは、独特の雰囲気がある。女性SSWのCLAIROをフィーチャーしたTrack.4、歌うようなベース・ラインが際立つTrack.9、壮大なサウンドスケープを描くTrack.11と引き出しの多さも感じられ、これからの活躍にも期待が持てそうだ。
-

-
MONGOL800×WANIMA
愛彌々
以前より親交があり、イベントなどでの共演もあったモンパチとWANIMA。昨年のラジオ番組でキヨサク(Ba/Vo)とKENTA(Vo/Ba)が対談した際の、"いつかコラボレーションしよう"が実現した。タイトル曲は両者のコラボ曲、その他互いが曲を提供し合った曲と、互いのカバー曲という全5曲で構成した濃密な1枚になった。言葉の向こう、音楽の向こうに誰かの顔が見える、フレンドリーな歌を届ける両者だけに「愛彌々」はポップで強力なサウンドで、またいつでもこの歌のもとに集まれるような明るく、おおらかなメロディが冴える曲となった。リスペクトとともに、こんな曲を歌ってほしい願望も込められたのだろう。提供をし合った曲では両者新しい面が垣間見える。発展的な1枚であるところにバンドの姿勢が窺える。
-

-
WANIMA
Chilly Chili Sauce
昨年リリースされたミニ・アルバム『Cheddar Flavor』を引っ提げた全国ツアーがいよいよ4月28日からキックオフ。というタイミングで、さらに新曲4曲を詰め込み、ライヴへの気分を高めてくれるようなWANIMAの6thシングル。『Cheddar Flavor』で掲げていた"誰かに歌うな 自分に歌え"というテーマを踏襲するという今作は、パンクで遊び心溢れる表題曲「Chilly Chili Sauce」から、ドラマチックなアレンジにバンドが存在する理由そのものを刻んだ「ネガウコト」までライヴ映えする曲が並んだ。積み重ねた時間のなかで潰えた夢、変わり果てた姿を憂い歌う「月の傍で」など、KENTA(Vo/Ba)が絞り出す言葉はキャリアを重ねるごとに説得力を増していく。
-

-
WANIMA
COMINATCHA!!
"三ツ矢サイダー2019"のCMソング「夏のどこかへ」、劇場版"ONE PIECE STAMPEDE"主題歌「GONG」など、お馴染みの強力キラーチューンを多数収録した1年9ヶ月ぶりの待望の2ndアルバム。勢い良く"開会"を告げる高速2ビート「JOY」に始まり、「宝物」や「シャララ」といった新たなサウンド・アプローチを取り入れた楽曲を経て、笑顔の再会を約束する「GET DOWN」まで、彼らのライヴを体感するような全15曲は、ライヴという空間を何よりも大切にするWANIMAらしい構成だ。珠玉は、"生きて 生きて 生き抜いてやれ"と力強く歌い上げるバラード「りんどう」。これまでバンドが歌い続けてきた揺るぎないメッセージは、今作でより鋭く、強く浮き彫りになっている。
-

-
WANIMA
Everybody!!
誰もが奥歯を噛みしめながら、笑顔になりたくて生きている。そのことを眉間にしわを寄せて訴えるのではなく、笑顔で顔をしわくちゃにしながら心を込めて祈る、そんな包容力と強さを持ったWANIMAのメジャー1stフル・アルバム。この音楽が誰かの"お守り"であればと歌う「CHARM」、大海原で旅立つ"キミ"の船出に優しく背中を押す「ANCHOR」、すべての過去を肯定して"生きる"選択を誇る「ともに」、悲しみのなかで初めて"愛してる"という言葉を綴ったバラード「SNOW」。楽しすぎるライヴ・アンセムもあれば、少しエッチな曲もある。だが難しい言い回しはゼロ。伝えたい想いだけがストレートに刻まれるのは、彼らは本当に大切なものが何かをよく知っているからだ。
-

-
WANIMA
Gotta Go!!
ワーナーミュージック内のレーベル"unBORDE"とタッグを組み、シングル『Gotta Go!!』をリリースするWANIMA。今やパンク・シーンの中でも1番と言ってもいい勢いで、大手のCM曲に抜擢されたり、本人たちが登場する状況だ。キャッチーなキャラとサウンド、シリアスに郷愁をかき立てつつ、笑えるエロスもあって、聴けば笑顔になる。そのWANIMA節を3曲揃えた。「CHARM」は上京から10年経った今の彼らが伝えられる、新生活へのお守り(=CHARM)となる、大合唱必至の熱いアンセム。またCM曲となった「ララバイ」と、「これだけは」は3人の決意表明と言えそうな歌で、ブライトなメロディが冴える。音楽への姿勢は変わらず、もっとパワフルに暴れ回っていこうという1枚だ。
-

-
warbear
warbear
"「warbear」という名前は、THE WAR ON DRUGS×GRIZZLY BEARってこと?"なんて冗談も言いたくなるような、素晴らしい作品。Phil EkやBrian McTearといったUSインディーの要人をエンジニアに迎え、音数は削ぎ落としつつ、モダンに仕上げた音像が、尾崎の歌を引き立てている。その起点は『Sea and The Darkness』(Galileo Galilei)のラスト・ナンバー「Sea and The Darkness II (TotallyBlack)」であり、随所にサックスがフィーチャーされているのも、尾崎の趣向がはっきりと表れている。歌詞はよりパーソナルになり、基本的には内省的で、曲によっては死生観が強く表れつつも、どこか風通しの良さが感じられる。自らと深く向き合ったソウル・ミュージックで、第2章のスタートが切られた。
-

-
WARHAUS
Ha Ha Heartbreak
ベルギーの国民的インディー・ロック・バンド BALTHAZARのフロントマン、Maarten Devoldereによるソロ・プロジェクトが約5年ぶりの新作となる3枚目のアルバムを発表した。Leonard CohenやTom Waitsからの影響を公言するとおり、アルバム全編にわたってダンディな低音ヴォイスを生かしたスムースでスウィートなポップ/ソウルが展開され、しなやかなストリングスと、官能的なコーラスが彩りと、時には緊張感を与えている。ファルセットというよりシャウトを交え失恋を嘆くTrack.6、カッティングが耳を惹くTrack.9など、実験性を増した後半も魅力的。ARCTIC MONKEYSの『The Car』を聴いてアダルトなサウンドに興味が湧いた、という人にもおすすめ。
-

-
THE WAR ON DRUGS
I Don't Live Here Anymore
USインディー・ロック・シーンの実力派、THE WAR ON DRUGSの4年ぶり5作目のフル・アルバムとなる今作は、約3年という時間をかけてじっくりと楽曲を練り、ADELEの最新作も手掛けたShawn Everettを共同プロデューサーとして迎えて制作された。今作でも、ソングライティングの要を務めるフロントマン Adam Granducielのセンスが光る。派手さのないシンセ使いや、ゆったりとした時間の流れを感じさせるリズム・ライン、そしてAdam特有の力の抜けたヴォーカルも心地よい。そんなどこか懐かしくもあり、タイムレスな魅力を持ったサウンドメイキング、そして普遍的なメロディという、素朴だが奥深い様式美を感じる楽曲の数々は、聴く者を選ばず幅広く愛される作品となるだろう。
-

-
THE WAR ON DRUGS
Slave Ambient
現在はソロ・アーティストとして活躍中のKurt Vileが在籍していたことでも知られている、フィラデルフィア出身のインディー・ロック・バンドの2ndアルバム。幾度のメンバー・チェンジを経て現在は4人編成となっているが、フロントマンであるAdam Granducielの存在感がずば抜けているため、シンガー・ソングライター+バック・バンドとも取れなくはない。実際このアルバムを聴いているとBruce SpringsteenやBob Dylanが思い浮かぶように、彼の声、奏でる音が繊細かつ大胆に響き、強烈なインパクトを残す。フォーク・ロックやシンセ・ポップ等の様々なサウンドが融合されていて、聴くたびに新たな発見があるのも魅力的だ。壮大なインストから流れ込む「Come To The City」がアルバムのラストではなく中盤にするという事実も、本作の素晴らしさを象徴している。
-

-
WARPAINT
Heads Up
デビュー作が世界各国メディアの年間ベスト・アルバム上位にランクインした実績を持つ、ロサンゼルスの女性4人組による3作目。Jenny Lee Lindberg(Ba)がソロ作を発表、Stella Mozgawa(Dr)がJamie xx やKurt Vileのアルバムに参加するなど、メンバー個々で力を蓄えた昨年。その成果を発揮するかのように4人のアイディアが盛り込まれた今作は、バンドのネクスト・フェーズを感じさせる仕上がりだ。ダークで物悲しい雰囲気を纏いながらアートさながらに構築していく音像はより洗練されたうえに、ダンサブルなビートを前面に押し出したTrack.3、耽美的な冒頭から急ぎ足で駆け抜ける曲と声の重なりとの絡みが絶妙で心地よいTrack.9を筆頭に、全編新鮮に楽しめる。メランコリックを極めたTrack.11で最後に胸を締めつけて終わる、その余韻も素晴らしい。
-
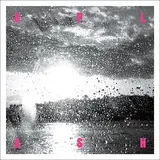
-
wash?
SPLASH
a flood of circle、クリープハイプなどのプロデュースや、様々なアーティストのサポート・ギタリストとしても活躍している奥村大(Vo/Gt)が2002年に結成した轟音オルタナ・ロック・バンド、wash?。彼らが前作から1年4ヶ月ぶりにリリースする8thアルバムは、誰彼構わずケンカを売っていたような前作から一転、奥村いわく"歌うアルバム"となった。パワー・ポップのTrack.3「ガールフレンド」を始め、やるせないムードも漂わせながら、シンプルなロックンロールの数々が持ち前のポップなメロディの魅力をアピール。Track.4「baby baby」はwash?流のバラードと言ってみたい。そして、ラストのTrack.7「ナイトミュージック」では、心機一転、前に進んでいこうというエネルギーをリスナーと共有する。
-

-
wash?
PURE CURE SURE
轟音で唸るギターを聴けば、90'sグランジ/オルタナがバンドのバックボーンであることは明らかだが、それだけじゃないと思わせる多彩な7曲が収録されている。ギタリスト、プロデューサーとしても活躍している奥村大(Vo/Gt)が率いる3人組が前作から1年ぶりに完成させた新作。作品全体にあふれる苛立ちやヒリヒリとしたムードは奥村のパーソナリティによるところが大きいようだが、曲の作り方はもちろん、それだけで終わらせないさまざまなアイディアが随所に散りばめられ、それが前述したように世界観の広がりを感じさせる「Dusk」を始め、幅広い曲に実っている。メロディからこぼれる言葉の多さは、それだけ言いたいことがあるということだろう。多めに加えられたメンバーによるハーモニーもいい感じだ。
-

-
wash?
love me
様々なバンドのサポートや故・上田現(ex.LA-PPISCH)のELEへの参加など、独自の道を歩んできた奥村大を中心とするWash? の5枚目のフル・アルバム。グランジ/ オルタナティヴ・ロックの影響を感じさせるバンド・アンサンブルはエモーショナルな歌とともに、静と動を繰り返す。その醒めた怒りや焦燥を詰め込んだ歌詞世界もあいまって、Wash?の攻撃的なロックンロールには、独特の求心力がある。それはきっと奥村大が救われてきた音楽から手に入れてきたものと同じ感触だろう。苛立ちながらも、捨てることができないわずかな希望に対する絶対的な信念。それは例えば、「ビリーバー」で誰彼かまわず毒づきながらも最後に発する「持て余したら/ 歌でも歌おう」とはき捨てるように歌うフレーズに詰まっている。
-

-
WAVVES
Afraid of Heights
プロデューサーにM.I.A.、Rihannaを手掛けたJohn Hillを起用という意外性や先行シングルがPitchforkのベスト・ニュー・トラック獲得など、リリース前から話題のローファイ・パンク・バンド、WAVVES 3年振りの4thアルバム。冒頭の「Sail To The Sun」からドリーミーなキラキラ・サウンドが飛び出したかと思いきやすぐさまそれを“冗談、冗談”と笑い飛ばすパンキッシュなベース・ラインが炸裂。淡々と頭の中を引っ掻くようなアコギが印象的な「Dog」、“わからない”と連呼する「Paranoid」、警官殺しをテーマとした「Cop」など、情緒不安定な歌詞と開き直った演奏の対比が面白い。アレンジに凝りながらもローファイな質感は変わらず、最後まで飽きさせずに聴かせる良作。
-

-
WAVVES
King Of The Beach
極私的な解釈でスイマセン!このアルバムを聴いてるとバンド組みたくなるんです。テクもギミックもいらねぇよ!とにかく勢いで突っ走ってしまえ!ってヤンチャなノリ。でも根幹はピュアな音楽愛に満ちている感じ。わかる?古くはRAMONESとか、最近ではVIVIAN GIRLSとか、日本ではBLUE HEARTSとか。ちょっとでも理解してくれたら連絡ちょうだい!バンドやろうぜ!はいごめんなさい、本線に戻します。海外メディアも大絶賛のWAVVES登場です。ローファイ&ガレージな荒々しさが持ち味だが、なんと言っても一度耳にしたら忘れられない強烈なフックを持ったメロディが最高!ヴォーカルNathanくんの恋人はBEST COASTのBethanyちゃんらしいので、ともに日本デビューを祝したカップリング・ツアーでの来日なんか実現しないかなぁ……切望します!
-

-
THE WAYBARK
マイ・ジェネレイション
青森出身の4ピースバンドTHE WAYBARKの1stアルバム。揃いのスーツに身を包んだ出で立ち、かと思えばメンバーそれぞれがてんでばらばらな名前だったりするので(だいち69(Vo)、Johnny(Gt)、おっくん(Ba)、ブラック斉藤(Dr))、正統派なのか、ふざけているのかと疑問に思ったが、失礼致しました。こいつら大真面目です。激アツなロックンロール野郎です。オールディーズからゼロ年代まで多くの音楽を消化した上で、音楽偏差値の高い曲を作る見た目も草食系な若いバンドが多い中、彼らはその間逆をいっている。とにかく熱血漢だ。だいち69は猪木イズムの継承者(早い話がプロレスファン)とのことだが、それで納得。これは闘魂注入ビンタのようなものじゃないか、一発おみまいしてやるぜという気合いだ。THE WAYBARK流闘魂注入後は、とにかく清々しいので、是非お試しあれ。
-

-
waybee
BRAND NEW WAVE.
藤村佑樹(Vo/Gt)の歌声がとてもいい。ナチュラルで素朴な響きの中に、何か歌わずにはいられない凛とした衝動を感じるからだ。2008年に結成した関西発の4人組バンド、waybee(読み:ウェイビー)。初の全国流通盤となる『BRAND NEW WAVE.』には、ロック、ヒップホップ、ポップスを渡り歩き、ジャンルを超えてオリジナルのロックを鳴らそうとする4人の決意が詰め込まれている。青春の甘酸っぱいフレーバーを感じる「Shampoo」、スタイリッシュなダンス・ナンバー「NIGHT CRUISING」など、カラーの違う全12曲がwaybeeの過去と未来を繋いでいく。バンド名の由来は"WAVE"。彼らが起こすビッグ・ウェーヴに乗り遅れるな。
-

-
WE ARE SCIENTISTS
Barbara
ニューウェイヴを研究し続けるマッドでポップな科学者達が新たな研究の成果を携えて帰ってきた。ニューウェイヴ、ポストパンク・リバイバルの中で登場し、着実に人気を獲得してきた彼らだが、今作からは元RAZORLIGHTのドラマー、Andy Burrowsが加入。その効果もあって、リズムに新たな躍動感が生まれているところが、新作の最大のポイントだろう。彼らの持ち味でもあるミニマルな曲作りと高揚感のあるメロディは健在で、これまで以上にキラキラとしたポップなフィーリングとグルーヴを生み出すことに成功している。個人的にも彼らの作品の中で最も楽しめるし、インディ・キッズからライト・リスナーまで、幅広い層にアピールできそうな好感度大なポップ・アルバム。先生、よい実験をされましたね。
-

-
WE ARE STANDARD
We Are Standard
昨年からフロアを中心に急上昇中のDEROLIANと同じスペインから登場したディスコ・パンク・バンド。縦でも横でもないディスコ・パンク独特の四つ打ちと、マッドチェスターのヘロヘロ・グルーヴを掛け合わせたような、ありそうでなかったサウンド。気だるそうなヴォーカルやキックは、まるでTHE RAPTUREとHAPPY MONDAYSの遺伝子を等しく分け合ったロクデナシのそれだ。何食わぬ顔で誰彼構わず、手をつけては「俺が他の女とキスをしながら、お前に会いたいと思っているなんて知らないだろ」なんて平然と言ってのける傲慢なロマンに溢れた歌詞もいい。HARD FIの登場を思い出すね。社会不適合者の為の、新たなスタンダードとなるか。
-
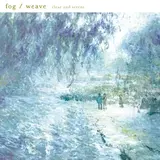
-
fog × weave
clear and serene
横須賀発の4人組weaveと京都の新鋭fogの2組によるスプリット・アルバム。fogにとってはこれが初の全国流通盤となるとのことで、気合も一入だろう。どちらのバンドも未発表曲を3曲ずつ持ち寄ってリリースされる今作は、一貫してエモーショナルなサウンドが印象的だ。weaveの"静"と"動"で編み込まれた緻密なサウンドに対して、fogは日本語詞によるギター・ロックで直球を投げてくる。似ているようで似ていない、近いようで遠いような両者だからこそ、まとまりを持ちながらも楽曲の個性が際立ったスプリット・アルバムに仕上がったのだろう。五月蝿いぐらいに詰め込まれた感情的なサウンドで、シーンの扉を開けていく彼らの勇士が見えるようだ。希望と期待に満ちている。
-
-
weave
The Sound
"何でもあり"も大歓迎。しかし、スクリーモ以降、それが行き過ぎてしまったため、何が何だかわからなくなってしまったエモの原点や本質を、横須賀の4人組weaveの1stアルバムに見出すリスナーは少なくないはずだ。静から動へ、動から静へという起伏を作り出しながらもほぼミッドテンポで押し通した全11曲。"何でもあり"ではないところに自分たちの表現に対する自信と確信が窺える。叫ぶわけでも唸るわけでもない。過剰な泣きがあるわけでもない。アクロバティックな演奏で驚かせるわけでもない。とことん研ぎ澄ました演奏はストイックの一言に尽きるが、作り手の情熱、美学、哲学をしっかりと伝えている。ビューティフル・エモなんて言葉も思い浮かべたが、考えてみればエモとは元々、美しい音楽ではなかったか。彼らのアルバムを聴き、そんなことも思い出したのである。
-

-
weave
the way to your heart
横須賀発の4人組エモ・ハードコア・バンドweaveが1stアルバムと昨年4月に発表した2ndシングルのリイシュー盤を同時リリース。その後者である本作は挨拶代わりの1作と言えるだろう。クリーンなギター・アルペジオに、強靭なリズム隊、激しく深く歪むギター、男気溢れるヴォーカル。しっとりと奏でられるタイトル・チューンを始め、インスト曲であるTrack.2「dawn」は、その優しい音色にじっくりと聴き入ってしまうし、Track.3「mineral pitch」は、爆音の中でグッと拳を突き上げシンガロングしたくなる衝動にかられる。彼らの熱とスピリットが凝縮された、ライヴを体感してみたくなる3曲だ。
-

-
WEEZER
SZNZ: Winter
2022年にWEEZERが1年を通して手掛けたプロジェクト"SZNZ"が、ついに完結。ヴィヴァルディの「四季」からインスピレーションを受けたという4枚のEPのラストを飾るこちらの『SZNZ: Winter』は、管弦楽器を用いて壮大に仕上げつつ、WEEZERらしい親しみやすさのあるグッド・メロディが心に沁みる作品となっている。さながらギター協奏曲とも言えるコンセプチュアルな展開で物語を紡いだ本作。ドラマチックに盛り上げる「I Want A Dog」に始まり、テルミンやストリングスを大胆に用いた「Sheraton Commander」で大きく展開、再び訪れる春へと希望を残すように、軽快なロック・ナンバー「The Deep And Dreamless Sleep」で締めくくられている。
-

-
WEEZER
SZNZ: Summer
四季の節目に合わせた4枚のEPシリーズ"SZNZ"の第2弾が到着。今回は夏がテーマだが、夏と聞いてパッと頭に浮かぶ陽気さや開放感からは対極とも言える、ヘヴィ且つハードな作品だ。ヴィヴァルディを引用しながら大仰なイントロダクションを奏でるTrack.1に始まり、RIHANNAやNIRVANAの名を挙げながら脳内で鳴り止まない音楽への愛を叫ぶTrack.2、ポップとダークを併せ持ったTrack.5、WEEZER版ロック・オペラと言うべき多彩な展開を見せるTrack.7など、パワー・ポップにいくつもひねりを加えたサウンドは今のWEEZERならでは。まるで青春時代の衝動を大人になってふと思い出したかのような、エモーショナルで情熱的な楽曲は、やっぱり夏に相応しい。
-

-
WEEZER
SZNZ: Spring
コロナ禍でも精力的な作品リリースを続けるWEEZERが、四季の節目に合わせた4枚のEPシリーズ"SZNZ"を始動。その第1弾である"Spring"は、柔らかで優しいロック・サウンドで、春のそよ風やうららかな日差しをイメージさせるにはもってこいの作品に仕上がっている。ファンタジー映画の音楽のようにフォーキーでオーガニックな楽器と、ほど良く歪んだギターが織りなすメロディは懐かしくも心地よく、実にキャッチー。ヴィヴァルディを引用したTrack.1や、ソフトな出だしから広がりを持って展開していくTrack.3、童謡とハード・ロックのヴァイブをブレンドしたTrack.6など、粒ぞろいの楽曲を収録。夏、秋、冬と続く"SZNZ"の続編にも必然と期待を持ってしまう作品だ。
-

-
WEEZER
Van Weezer
Rivers Cuomo(Vo/Gt)をはじめ、メンバーが影響を受けた'80sヘヴィ・メタルにオマージュを捧げた15thアルバム。VAN HALENやOzzy Osbourneの曲から拝借した超有名ギター・フレーズなど、デビュー作から表れていたメタルの影響をいつも以上に際立たせたところ、バンドが持つギター・オリエンテッドなロックの魅力を今一度アピールする作品になったところがメタル云々以上に一番の聴きどころになっている。デビュー作や"ザ・グリーン・アルバム"を連想させる曲の数々はある意味、原点回帰と言ってもいいかもしれない。故Eddie Van Halen(VAN HALEN/Gt)と共に、その2枚をプロデュースした故Ric Ocasekに本作が捧げられていることも大いに頷ける。
-

-
WEEZER
Weezer (Black Album)
思いついたら形にせずにいられない多産なバンド、WEEZERが13枚目となるアルバム(6枚目のセルフ・タイトル!)をリリースした。WEEZERと言えば、なぜか同じくセルフ・タイトルにしてしまったカバー・アルバムを発表したばかり。全体的にネタ元だけでなく、サウンドもノスタルジックな印象だったカバー作と比べると、こちらは冒頭の「Can't Knock The Hustle」、「Zombie Bastards」の流れで一瞬にして現代に引き戻される感じだ。R&Bも取り入れたダンサブルなポップ・ソングが目を引くが、ただところどころにはサウンドメイキングなどにノスタルジックな香りを残してある。Rivers Cuomo(Vo/Gt)の今の気分なんだろうな。
-

-
WEEZER
Pacific Daydream
WEEZERが作った小粋なポップ・アルバム、そんな印象の11作目。前作『Weezer(White Album)』は、現在のメインストリームにおけるポップ・ソング作りのマナーを意識した作品だったが、今回は多分にインディー風。そこを小粋という言葉で表現してみたい。デビューから20余年でさらにひと皮剥けた印象を与えることは、現在進行形のアーティストとしては称賛に値するものだ。特に、前作で急接近したR&Bの影響を消化したうえで、レゲエやディスコ・ビートをさりげなく取り入れたリズム・アプローチはさすがのひと言。ただし、ファンがそういう変化を求めているかどうかはまた別の問題。少なくとも歪ませたギターをギャーンと鳴らして、泣きを含んだポップ・メロディを歌うWEEZERはここにはもういない。
-

-
WEEZER
Weezer(White Album)
4作目のセルフ・タイトルとなる10thアルバム。"White Album"は例によって、便宜上の邦題。セルフ・タイトル作を4枚もリリースするバンドも珍しい。しかし、これはセルフ・タイトルが相応しい。例えば、"Red Album"なんかよりも断然。それもそのはずで、かつてWEEZERのコピー・バンドをやっていた本作のプロデューサー、Jake Sinclair(FALL OUT BOY他)とRivers Cuomo(Vo/Gt)は日本でも未だに人気が高い"Blue Album"と『Pinkerton』を目指したんだそうだ。その狙いは見事、成功。そこにTHE BEACH BOYS風のTrack.4「(Girl We Got A)Good Thing」やR&B風のピアノ・ポップのTrack.9「Jacked Up」が加えられ、バンドのサウンドをアップデート。これを否定できるファンはまずいない。
-
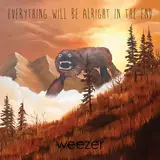
-
WEEZER
Everything Will Be Alright In The End
デビュー20周年を迎え、改めて原点に立ち返り、本来のWEEZERらしさを追求したんじゃないかと思わせる4年ぶりのニュー・アルバム。3パートからなる組曲に加え、新境地を思わせる絶妙な転調やデイスコ・サウンドやトラッド・フォークといった新機軸を取り入れながらも、1枚目と3枚目を思い出させるという意味で、これほどWEEZERらしいと思えるアルバムを作ったのは、たぶん10年ぶり?! ファンはきっとこういう作品を待っていたはずだ。たぶん1枚目と3枚目を手がけたプロデューサー、Ric Ocasekを三たび起用したことも大きかったに違いない。全体的に抑え気味ながらも聴きごたえはあり。Rivers Cuomo(Vo / Gt)も本来のメタル愛をストレートに表現。随所でメタルふうのリフやソロを披露している。
-

-
V.A.
ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN COMPILATION 2011
アジカン企画&主催の夏フェス"NANO-MUGEN FES."も今回で9回目(ツアー形式だった「NANO-MUGEN CIRCUIT2010」を含めると10回目)。WEEZERやMANIC STREET PREACHERSをヘッドライナーに、BOOM BOOM SATELLITES、the HIATUS、若手注目バンドねごと、モーモールルギャバンなど、洋邦共に相変わらずの豪華ラインナップ。出演バンドの楽曲が1曲ずつ収録されているコンピレーション・アルバムは、今作で5作目。そして、今回収録されているアジカンの新曲は2曲。チャットモンチーの橋本絵莉子(Vo&Gt)を迎えた「All right part2」は、後藤と橋本の気だるい歌い方と熱が迸る歌詞のコントラストが鮮やかで、高揚感に溢れたギター・リフとメロディも力強く鳴り響く。ユーモラスなあいうえお作文、男性の言葉で歌う橋本の艶とレア感も思わずニヤついてしまう。東日本大震災時の東京を描いた「ひかり」は、人間の醜い部分や絶望感にも目を逸らさず、物語が淡々と綴られている。言葉をなぞる後藤の歌に込められた優しさと強さは、当時の東京を克明に呼び起こしてゆく。生きることが困難な時もあるだろう。だが"オーライ"と口ずさめば、ほんの少し救われる気がする。音楽の持つ力を信じたい――改めて強くそう思った。
-
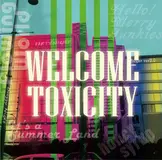
-
Welcome Toxicity
WELCOME TOXICITY
ポップ・アイコンmoemoe、サウンド・クラフトマン河上"puppy"誠、パーティー・ガイ辻川"wildmozet"郷という強烈な個性を放つ3人による滋賀県発のエレクトロ・ダンス・ポップ・バンドWelcome Toxicity。"RO69JACK 12/13"に入賞し注目を集める彼らの1stミニ・アルバムは、これでもかというほどにハイ・テンション。アッパー・チューンのリード・トラック「It's a Summer Land」を聴けば彼らがライヴのことを"PARTY"と呼んでいるのも納得がいく。アルバムに詰め込まれた、エレクトロ、ダンス・ポップ、レゲエなどの多彩なジャンルの楽曲たちを、オープニング・トラックのドキドキするような高揚感と、寂しさを感じさせるエンディング・トラックの収束感が、バランス良くまとめている。ヴォーカルに僅かな不安定さはあるが、まだまだ成長できそうな伸びしろを感じる。
-

-
THE WELLINGTONS
In Transit
もし友人が答えの出ない悩みにモヤモヤしてたら、ぼくは迷わずこのCDを差し出すよ。「黙って身を委ねろ!」って。この煌びやかなメロディ、男女混声ヴォーカルの爽快なハーモニー、そしてどこまでも突き抜けるエモーショナルが解決してくれるから。え?そんなに物事は単純じゃない?夢見たこと言うなって?うんうん、確かにそうだね。でも夢見たっていいじゃん、だってこれは純度120%のパワー・ポップなんだから!幸福なイマジネーションが溢れてしょうがない!もう本年度のパワポ・グランプリはこの1枚じゃない?メルボルン出身、メンバー・チェンジを経た新生WELLINGTONSから待望の新作が到着。全曲ハイライトで駆け抜けるこの気持ち良さに言葉はいらない。聴き終わった後、心はポジティヴに漂白されている。
-

-
WE'LL MAKE IT RIGHT
We'll Right It Make
オランダのDox Recordsに所属するポップの才人Benny Singsを中心としたRoos Jonker、Dean Tippet、Bart Suer、Extraa、Les Frogsの総勢6名のミュージシャン、プロデューサー、アーティストによるプロジェクト。再び“心を落ち着かせる音楽”を制作することをテーマに集結! 2010 年の秋にベルギーのアルデンヌの森に集まって作られた今作もリラックスした温かな雰囲気の楽曲揃い。「Maite」の無邪気な子供のあどけない声を聞いた途端、ふっと肩の力が抜けて、日常の喧騒を忘れられるに違いない。あとは優しい歌声に導かれるままに最後の「Mr & Mrs Woodman」まで、ソファに座って珈琲でも飲みながらゆったりと楽しんでいただきたい。
-

-
WE NEED SECRETS
Melancholy & The Archive
カナダ東部に位置するノバスコシア州出身のChad Peckによるソロ・プロジェクトWE NEED SECRETS。"ひとりマイブラ"と称される彼の、デビュー・アルバムにあたる今作は、4年もの歳月をかけて作られた渾身の一作。ソロ・プロジェクトでここまで深く、丁寧にシューゲイザー・サウンドを作りこめるのは、Chadのシューゲイザーへの愛ゆえだろうか。Track.4「Melancholy」ではひずんだギター・サウンドの中にポップなメロディが乗せられ、このプロジェクトのふり幅の大きさを感じさせてくれる。更にRINGO DEATHSTARRのフロントマンElliott Frazier(Gt/Vo)が客演、録音で参加しており、マスタリングにはSHELLACのBob Weston(Vo/Ba)が担当という、まさに"轟音"な布陣で固めている。
-

-
WHITE ASH
Quest
最初、YouTube"アニメ モンスターストライク"のタイアップ楽曲からなるミニ・アルバムって? それをバンドのオリジナル・ミニ・アルバムとしてリリースするってどういうこと? と疑問符だらけだったのだが、曲を聴けば大いに腑に落ちる。モンストというお題が功を奏したファストな8ビートやメジャー・キーに抜けていくサビが新鮮な「Strike」、跳ねる16ビートがWHITE ASH節とも言える「Drop」、R&Rバンドのファンクネスを感じる「Mad T.Party(1865-2016)」、そして"モンストグランプリ2016 チャンピオンシップ"大会イメージ・ソングとして多くの新しいリスナーを獲得しそうな「Monster」。何かに向かってチャレンジする気持ちを最高にホットなクールネスで煽る、彼ららしい着地点を見る。
-

-
WHITE ASH
SPADE 3
トランプの"大富豪"でジョーカー単枚切りに勝てる"スペードの3"に由来しているタイトル。その対象はあらゆるライバルや人生で出会う困難を指しているんじゃないだろうか。00年代海外インディー・ロックの影響下から、さらにあらゆる時代のロックを吸収/消化してオリジナルに表現するWHITE ASHのサウンドに対するセンスと、それを実現できる4人のスキルは狭義のバンド・シーンを本作で完全に飛び越えた。アップデートしたマンチェ・ビート的なイントロから2分に満たないクールさで駆け抜ける表題曲、重く乾いたビートのTrack.4、5、メランコリックでスローなTrack.6、遅いBPMなのにジワジワ攻めてくるTrack.8、トドメはエヴァーグリーンなラスト。今回、特に剛(Dr)の進化に圧倒される。


























