DISC REVIEW
G
-

-
Gacharic Spin
Gacharic Spin
初のセルフ・プロデュースで挑んだメジャー5thオリジナル・アルバム。今作からはなとアンジェリーナ1/3(Mic Performer)のツインVo体制となり、曲によってはアンジェリーナ1/3がメインVoを担当。そこには新たなGacharic Spin像が強烈に打ち出されており、驚く人も多いだろう。常に変化して進化し続ける彼女たちの姿にエネルギーを注入されるよう。また、スペイン語と日本語を織り交ぜた「ミライ論争」、メルヘンちっくな雰囲気と攻撃的インスト・パートを盛り込んだ「マジックアンブレラガール」、バラード調の「Days」、童謡風味の合唱コーラスが映え渡る「365日」などバラエティに富んだ楽曲が勢揃い。明暗の感情を吐き出したリアルな歌詞にも注目。
-

-
Gacharic Spin
Gold Dash
昨年、アンジェリーナ1/3(Mic Performer)とyuri(Dr)の加入により、はながVo/Gtに変更し、新6人体制(第5期)で挑んだ初のアルバム。驚くのはツイン・ギター編成になったことで、ロック度が強化されている点だろう。また、大村孝佳が作曲アレンジを担当した「起死回生 Forever」、THE BACK HORNの菅波栄純(Gt)が作詞作曲を手掛けた「超えてゆけ」、スウェディッシュ・ソングライティング・チームの提供曲「永久 No mission」の3曲はガチャピンの新たな魅力を引き出しており、作品の振れ幅をグッと広げている。スラップ・ベースが火を吹くヘヴィな「FRUSTRATION」もかっこ良く、ライヴで一段と映えそうな楽曲が収録された好盤と言っていい。
-

-
Gacharic Spin
ガチャっ10BEST
結成10周年を祝したベスト・アルバムは入門編、中級編、上級編の3タイプでリリース。入門編は新メンバー アンジェリーナ1/3(MC)を含む新5人体制で作り上げた新曲「逆境ヒーロー」に加え、メジャー時代の楽曲を収録している。中級編には入門編にプラスして、インディーズ時代の楽曲やライヴ音源を追加。上級編は前述の音源をすべて網羅しつつ、メジャー・デビュー以降のMVが13曲と、これまでリクエストが多かった["ライバー大宴祭"The Movie]収録のBlu-rayも付属。全曲リマスタリングが施され、ファンにはたまらない内容になっている。その中でも注目は「逆境ヒーロー」だろう。彼女たちの熱い意志が漲る楽曲で、聴く者を鼓舞する歌詞に多くの人が勇気づけられるに違いない。ジャケも秀逸。
-

-
GALACTIC
Other Side of Midnight:Live in New O
今年1月に来日を果たしたP-FUNKの創始者George Clintonとも共演した事のあるニューオリンズのジャム・ファンク・バンドGALACTICのライヴ盤が到着。昨年はスタジオ・アルバム『Ya-Ka-May』のリリースそしてジャパン・ツアーと精力的に活動を進めて来た彼ら。今作は彼らのホームでもありニューオリンズ音楽の聖地でもある名物ライヴ・ハウス“Tipitina’s”での最新パフォーマンスを収録。歓声やコール&レスポンス含め熱量がそのままパッケージングされたような素晴らしいライヴ盤だ。エネルギッシュ且つパーティ感満載な今作だが、ファンキーさの中に光るクールなベース・ラインにやられる。馬鹿騒ぎの中にも大人の落ち着きがあるような。来日が待ち遠しくなる好盤。
-

-
Galileo Galilei
Baby, It's Cold Outside
"ルーツを感じさせる音楽を作りたい"とフロントマンの尾崎雄貴が以前語ってくれた。だがそれはとても難しいことで、影響を出し過ぎると、既存の音楽の焼き増しになってしまう。だがその"自らの根源"ほどきらきらした純粋な思いが込められたものはないだろう。前作『PORTAL』は、Galileo Galileiの音楽愛が爆発した非常にピュアな作品だった。今作はそこから一歩先に行き、流れを汲みながらも独自の音楽性や精神性を深めている。ギター、ベース、ドラム、シンセ、それぞれの楽器の音も際立つアレンジになっており、より洗練されたギター・ロック・サウンドへと昇華。前作から9ヶ月でその成果が出ているのは、バンドのポテンシャルが高い証だ。彼らの音楽への冒険心は、ここから更に燃え上がるに違いない。
-

-
Galileo Galilei
PORTAL
北海道出身の5人組Galileo Galileiのメジャー2ndアルバムは、彼らが彼ららしくいるための挑戦だ。彼らは今年3月に拠点を東京から札幌に移し、メンバー全員で共同生活をしながら自作スタジオで曲作り、レコーディング、ミックスをセルフ・プロデュースで行っている。プログラミングやシンセなどを大胆に使ったアレンジに溶けるバンド・サウンド。淡い水彩画のように透明感に溢れた音は、そっと寄り添うようにあたたかく優しい。だがそれと同時に物悲しくもあり、心に眠る焦燥感を静かに煽る。架空の街をモチーフにした14曲のストーリーに誘われ、ゆっくりと溺れていくような不思議な感覚に陥った。新たな入口の扉を開けた5人。この先にはどんな出来事が待ち受け、彼らはどんな物語を描いてゆくのだろうか――。
-

-
G-Ampere
Rainbow Rainbow
来年で結成10周年を迎えるG-Ampereから、自ら集大成と語るニュー・アルバムが届けられた。2000年に大学のサークルで結成された彼らのサウンドはUSオルタナの影響を受けたと語る通りノイジーなギターと男女のツイン・ヴォーカルが絡み合い実験的ながら透明感に溢れ、聴いているもの達を暖かい気持ちにしてくれる。その間に挟み込まれるエレクトロニカの影響を受けただろうと思われる楽曲も素晴らしい。アルバムの最後に納められた「Yuko Can Walk On The Rainbow」は病気と闘う友人に捧げるために作られた9 分にも及ぶ大作。ハンドクラップから始まるこの曲はめまぐるしく展開を変えながら、「最高の瞬間」も「どうしようもない瞬間」も希望に変えていこうと歌う。
-

-
GANG GANG DANCE
Kazuashita
ANIMAL COLLECTIVEやLCD SOUNDSYSTEMら先鋭的なアーティストを生んだ00年代NYの傑出した音楽集団が7年の沈黙を破り新作をリリース。エイリアンが登場しそうなオーバーチュアに始まり、エレクトロとシューゲイズ・サウンドがエキゾチックに融合したアルバムでもハイライトとなる「J-TREE」や、どこか東洋的な神秘性を感じる「Lotus」など、エッジーなのに深い癒しも感じる楽曲が揃う。巫女的なLizzi Bougatsosの生身の人間離れしたヴォーカルも、その効果を増幅する。気楽に忘我の境地に浸るのもいいだろう。なお10月にはDEERHUNTERとともにレーベル"4AD"のオムニバス・ライヴ"Revue"での来日も決定しており、音楽とアートが溶け合うエクスペリメントな空間に期待したい。
-

-
GANG PARADE
Peace☆超パニック/一夏
両A面のメジャー6thシングル。「Peace☆超パニック」は、キュートな歌声で魅了するキラキラ王道アイドル系チームと、デス・ヴォイスも飛び出すラウドロック・チームのパートが入り乱れる尖った1曲だ。情報量が多く、ワチャワチャ感もあるあたりが彼女たちにピッタリ。逆に「一夏」では大人っぽい落ち着いたダンス・チューンでまた新たなギャンパレ像を見せているところも評価できる。さらに本作には、アイドル活動10年目を迎えたヤママチミキ&ユメノユアによるユニット曲「トーナリティ」を収録。こちらは、それぞれのパーソナリティをジャジーな要素とロックな要素を融合しながら表現した印象だ。三者三様で、シングルとは思えない聴き応え。
-

-
GANG PARADE
パショギラ / 躍動 / ROCKを止めるな!!
ギャンパレのメジャー5thシングル。そのリード曲「パショギラ」はKEYTALKとのコラボ曲だ。ロック・フェス常連のKEYTALKらしい陽のパワーが溢れたダンス・ロックと"みんなの遊び場"をコンセプトにするギャンパレは、ビールと唐揚げばりに相性抜群。キャッチーなメロディと四つ打ちサウンドで、一聴しただけで踊りたくなる1曲に仕上がった。カップリングはKOTONOHOUSE提供の和×EDMナンバーで新境地を見せる「躍動」、そしてTHE イナズマ戦隊プロデュースで、いい意味での泥臭い歌唱が胸を熱くする「ROCKを止めるな!!」の2曲。ジャンルの異なる3曲だが、いずれの曲もライヴで映えること間違いなし。今年のギャンパレは音楽フェスを大いに盛り上げてくれる存在になりそうだ。
-

-
GANG PARADE
The Night Park E.P.
新たなクリエイター陣を起用した"夜"をテーマとするコンセプトEP。本作では様々な夜の表情を切り取ったエレクトロやダンス・ミュージックを主軸とした楽曲が、近年でロックを主とした作品を世に送り出してきたギャンパレのイメージをいい意味で壊している。それだけでも十分に意欲作だと言えるが、13人のメンバーそれぞれが作詞作曲に携わり自作のパートを歌唱した「Gangsta Vibes」や、前作に引き続きユニット曲も収録され、聴きどころ満載。作品を丸ごと楽しめることは当然として、今夜の気分に合った曲をセレクトして楽しむのもいいだろう。音楽的には最先端ながらも、ジャンル感としてはPOP(前身グループ)時代からのファンには懐かしさを感じるところもあり、そこがまた良き。
-

-
GANG PARADE
OUR PARADE
"どんな困難があったとしても/楽しもう"と歌うオープニング・トラック「ENJOY OUR PARADE」は、今の彼女たちのテーマ・ソングとも言える1曲で、ここに至るまでたくさんの壁にぶつかってきた彼女たちが歌うからこそグッと来る。メンバーが"今の13人体制のギャンパレですごく大事な曲になっている"と語る「INVOKE」では、前身グループ POPからのメンバーであるヤママチミキとユメノユアによる共作の歌詞と、エモーショナルなサビメロが相まって、聴いているだけで目頭が熱くなった。そんな熱く滾る要素もあれば、頭を空っぽにして楽しめるパーティー・ソングもあり、新たな試みであるユニット編成曲も収録。ギャンパレらしい部分と新たなチャレンジが同居するアルバムに仕上がった。
-

-
GANG PARADE
Priority
13人体制となったGANG PARADEのメジャー4thシングル。表題曲「Priority」は、ギャンパレの現在地点を、飾らず、濁さず、まっすぐな言葉で綴った1曲だ。松隈ケンタ節が利いたメロディはメンバーの感情を見事に引き出していて、とりわけサビメロがエモくグッとくる。内省的な楽曲ではあるけれど、今まさに目標に向けて走り出したい、行かなくちゃいけない誰かにとっては、背中を押してくれる応援歌になってくれるはずだ。カップリングの「MELT」は、動きの多いベース・ラインに複数本のギターと、耳が賑やかになるモダンなロック・ナンバー。メンバーのキャ・ノンが担当した歌詞は、表題曲とは対照的に抽象的で個性的な言葉が使われていて、楽曲の世界観の想像をかき立ててくれる。
-

-
GANG PARADE
PARADE GOES ON
待ってました! 2020年3月からGO TO THE BEDSとPARADISESに分裂していたGANG PARADEが、待望――いや、切望されていた再始動を果たしてメジャー2ndシングルをリリース。表題曲「PARADE GOES ON」は、今回の再始動に込められた想いをストレートに歌うロック・ナンバーで、"ただいまだとか/おかえりだとか/ありきたりな言葉じゃ/あらわせないや"という歌い出しから、グッと来る言葉と歌唱のオンパレードだ。一方、c/wの「Period」は四つ打ちのエレクトロ・サウンドで、音楽的には表題曲とは対照的な仕上がりに。ただ、こちらも遊び人(※ファン)なら胸を締めつけられるようなフレーズばかりで涙腺崩壊は必至。パレエドよ、いつまでも続け。
-
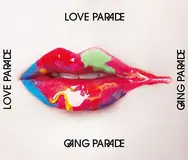
-
GANG PARADE
LOVE PARADE
新メンバーのナルハワールドが加入し10人体制になったギャンパレのメジャー初アルバム。これまであまり愛については歌ってこなかったイメージのある彼女たちだが、本作では、まっすぐな愛を表現した「らびゅ」、ユメノユアが日常で感じた歪んだ愛を歌詞にしたという「ALONE」、南国情緒溢れるサウンドで陽気な愛を感じさせる「LOVE COMMUNICATION」と、"LOVE PARADE"のタイトル通り、実に様々な愛が歌われている。王道なテーマとも言えるが、ひとりひとりの個性が強いギャンパレが歌うからこそ、多様な愛の形を表現した曲の説得力がより高まった印象だ。多くのリスナーに届きそうな題材を扱うことで、遊び人(※ファンの総称)がさらに増加する起爆剤になるであろう1枚。
-

-
GANG PARADE
ブランニューパレード
"苦労人"ギャンパレが満を持して世に送り出すメジャー・デビュー作品。彼女たちの門出を祝うようなイントロから始まる表題曲「ブランニューパレード」は、野外フェスや5月に行う東阪野音のステージが似合いそうなストレートなロック・チューンで、ギャンパレのアイドルとしての姿勢や歴史を語るような自己紹介ソングに仕上がっている。表題曲とは対照的にダークな音世界で魅せているc/wの「Dreamer」は、テラシマユウカによる作詞。音の響きを意識しつつも意味があり、さらに文字の見た目としてのカッコ良さも考えているという秀逸な歌詞なので、ぜひ歌詞カードを片手に堪能してほしい。ギャンパレが持つふたつの魅力を知ることができる、メジャーへの挨拶代わりの1枚だ。
-

-
GANG PARADE
LAST GANG PARADE
現9人体制初のアルバム。オープニング・トラックの「LAST」は、決して順調なことばかりではなかったグループの歴史がフラッシュバックするような歌詞で、傷つきながらも前に進もうとする強い意志を感じる1曲だ。そのほかの新曲はメンバーが作詞を手掛けており、振り切りすぎている「HERETIC」、「正しい答えが見つからなくて」や、皮肉を込めた歌詞をノリノリな曲に乗せる「Jealousy Marionnette」、温かくてほっこりする「Message」、冷たくも美しい「BOND」、そしてハルナ・バッ・チーンが作曲したグループ初の和テイストな1曲「夜暗い夢」といった、メンバーの個性が弾けるカラフルな曲が揃う。いずれもアンセムとなっているシングル3曲も収録され、文句なしの名盤に仕上がった。
-

-
GANG PARADE
CAN'T STOP
GANG PARADEの現体制2作目のシングル。「CAN'T STOP」はそのタイトルどおり、シーンを立ち止まることなく走り続ける彼女たち自身を歌う歌でもあり、一方で、優しい歌詞とリラックスした歌声で聴き手にそっと寄り添うような1曲でもある。表題曲としては珍しいミドル・テンポの曲だが、そんな"らしくなさ"も、個性の塊のようなメンバーの歌声が入ることでしっかりとGANG PARADEのカラーに染め上げた。c/wの「RATE SHOW」は、危険な香り漂う街で夜遊びをするかのようなドキドキ感と高揚感を生む、まさかのミュージカル風ナンバーだ。セリフ調のパートや、癖の強い歌い方など、遊び心溢れるギミックもあり、そのエンタメ性の高さは"みんなの遊び場"をコンセプトとする彼女たちらしい。
-

-
GANG PARADE
GANG 2
新9人体制で初となるシングル。今作は大きな会場が似合いそうなスケール感のある楽曲が揃っている。表題曲はイントロから荘厳な鍵盤が響き、ストリングスを効果的に用いた美しくも躍動感に溢れた曲調。"ウォーウォーウォー!"という合唱ポイントもあり、ライヴでの一体感を高める強力ソングと言っていい。いばらの道を突き進みながら、高みを目指そうとするリアルな心情が綴られた歌詞も共感を誘う。特に"はみ出た分だけ 新たな続きが 溢れ出すの"というフレーズがドラマチックに響いた。新たな代表曲になりそうな名曲だ。c/wの「来了(読み:ライラ)」はヤママチミキが作詞を手掛け、中国風味のオリエンタルな歌詞とサウンドが特徴的。癖の強い歌い回しも中毒性が高く、こちらもライヴで抜群の威力を発揮しそう。
-
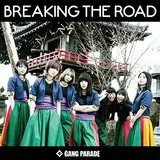
-
GANG PARADE
BREAKING THE ROAD
2018年の幕開けを告げるニュー・シングルは、なんでも乗りこなすGANG PARADEの音楽的振れ幅を象徴する、熱さと遊び心を兼ね備えた内容に仕上がった。表題曲はギャンパレ初のツー・ビートを用いたパンキッシュなナンバーで、道を壊して未来に突き進むんだ! という想いと見事にシンクロした曲調。コール&レスポンスできるパートもあり、ライヴでは観客を巻き込んでシンガロングの嵐を巻き起こすアンセム曲になるだろう。楽曲と歌詞を照らし合わせることで、より一層エモーショナルに響いてくる。c/w「とろいくらうに食べたい」は表題曲とは対照的にクール且つダンサブルなサウンドが心地よい。歌詞と曲調とのギャップに心を奪われつつ、一度聴いたらヤミツキになる中毒性がある。濃厚なシングルだ。
-

-
GARBAGE
Strange Little Birds
2012年リリースの『Not Your Kind Of People』以来となる、通算6枚目のニュー・アルバムは、Shirley Manson(Vo)いわく1stアルバム『Garbage』(1995年リリース)に近い感覚があるという。セルフ・プロデュースで、自らのレーベルからのリリースとなり、なんの制約もなく好きなものを思うままに制作できたことがその理由で、ピュアな衝動や音への欲求が詰まっている。エレクトロ・サウンドとポエトリーなヴォーカルがシックで、その行間から大人の雰囲気や、色気のあるダークネスが香っている。シンプルで、音数も少ないながらも、さりげない音の歪みやノイズ、奥行き感や、細やかな音の強弱やレイヤーでファンタスティックな世界観に聴き手を閉じ込める。インダストリアル感のある曲やポップな曲をアクセントに、全体に憂いある物語が流れていて美しい。
-

-
GARBAGE
Not Your Kind Of People
USの紅一点ポップ・ロック・バンドGARBAGEから7年振り5作目となる待望のオリジナル・アルバムが到着。活動休止中、ドラムスのButch VigはMUSE、GREEN DAY、FOO FIGHTERSなどのプロデュースを手掛けるなど精力的な活動を行なっていたとのこと。メンバーそれぞれが新たな英気を養いバンドへと戻ってきた今作、とにかくエネルギッシュである。ポップ、ヒップホップ、エレクトロニカ、ロックなどのバラエティに富んだ楽曲が感情を抑えきれないとばかりにはち切れる。そこに美しく輝くのがShirley Mansonのヴォーカル。服を着替えるように、曲ごとに違う魅力的な表情を見せてくれる。多彩なキャリアとバンド活動18年にして尚もこの実験性、チャレンジ精神に感服!
-

-
GARDA
Die Technique Die!
まるでノイズ・ジャンク・バンドBASTROから、優美で幻想的なGASTR DEL SOLへ移行していったシカゴ音響派の開祖DAVID GRUBBSの世界観のような。もしくは、元THE SMASHING PUMPKINSのギタリストJames Ihaがソロ作でみせた、フォークに宿したあまりにも優しく暖かみに溢れた音楽愛のような。どちらにせよ、ここにある静謐で透明な世界は、“その先に見つけた音響”なのかもしれない。ノイズ・バンドを出自にしたKai Lehmannを中心に結成された不定形ユニット、GARDAのデビュー・アルバム。大人数のユニットらしく、シンプルな弾き語りから壮大な歌ものまで、あらゆる創作意識の具現化を細部にまで拘るアレンジの手腕が光っている。変幻自在ながら、徹底した美しさは微睡みさえも促すもの。もしあなたが内省的な世界に溺れたいのなら、迷わず「Chest」を聴いてもらいたい。
-

-
GARI
Colorful Talk
これまでのGARIというと、ミクスチャー/エレクトロ色の強い、ラウドロック的なバンドという印象があった。しかしこの最新作は、従来の激しさを少し抑え、よりエレクトロ色を濃くし、踊りやすく、歌いやすく、更に幅広い層のリスナーにアプローチする作品となっている。「OVER THE SUNRISE」を聴いた瞬間、今までのファンは少し驚くかもしれないが、これはセルアウトではない。メンバー4 人で表現し得る限界にまで挑んだ、非常に進歩的で革新的な作品なのだ。同時に、JUSTICE を筆頭としたエレクトロ勢からインスパイアされた作品でもあるということで、そこかしこに現代流行のロッキンエレクトロ的なニュアンスが漂いつつも、そこを超越して更に凝ったトラックメイキングになっている点は、さすが長い歴史を持つバンドである。
-

-
GARNiDELiA
Duality Code
メンバーそれぞれのソロ活動を経て、待望の5thアルバムがついに完成。儚くてセンチメンタルなダンス・ナンバーから、ほっこりとするクリスマス・ソングまで、実に多彩な全12曲を収録。どれも聴き手の心に滑り込んでいく親しみやすさはありつつも、ハードで重厚感のあるサウンドと、再始動の幕開けに相応しい情熱迸る言葉を畳み掛ける「Live On!」や、"距離"から生まれた様々な想いを閉じ込めた「Uncertainty」など、ふたりの心境が色濃く表れた楽曲も。ユニットが掲げ続けているライヴ・タイトルを冠したtoku歌唱の「stellacage」、MARiAが自身の歌う理由を刻みつけた「Reason」と、自分たちの"場所"に関して歌った2曲で締めくくるのが、とにかくエモーショナルで熱い!
-

-
toku
bouquet
音楽ユニット、GARNiDELiAのサウンド・プロデューサーであり、とくPとしてボカロ曲も発表してきたtokuのソロ作。10人の女性アーティスト/声優をゲストに迎え、10人それぞれの世界観を引き立て、またそれぞれの曲で花をモチーフに1枚のアルバムとしてブーケのように束ねた。神田沙也加のエモーショナルなVoを生かした「ずるいよ、桜」の儚くポエティックなポップ・サウンドに、中島 愛参加の「Acacia」ではフューチャリスティックな物語性を引き立てるサウンド、やなぎなぎが歌う「Coreopsis」は実験的なサウンドが、ピュアな歌声とマッチ。また一青窈の「萌芽」は歌詞をスガシカオが手掛けており、3人の個性をぶつけ合う曲になった。架空の物語のサウンドトラックのように味わえる作品だ。
-

-
GAROAD
夜明け待つ君への贈唄
千葉県船橋市で結成し、都内のライヴハウスを中心に活動するGAROAD。田伏ユージ(Vo/Gt)、吉田マコト(Ba/Cho)で前身バンドからスタートし、GAROADとして来年で10周年となる今回、初の全国流通盤をリリース。エモーショナルな田伏の歌声と、前向きに駆け出そうとする誰かの背中を押す言葉が映えるギター・ロック「ギブ ユー」を筆頭に、タイトル同様誰かへのエールとなる"贈唄"が並ぶ。迷ったり、毎日に流されて焦りを感じたりする心にスポットライトを当てて、僕はここにいるよと温かに語り掛ける「place」やラヴ・ソング「素晴らしい日々」、また「マテリアル」ではヘヴィなリフやスラップ・ベースを用いて自らを奮い立たせる言葉を放つ。てらいのないまっすぐさが詰まった1st EP。
-

-
Gary Numan
Splinter (Songs From A Broken Mind)
35年に及ぶキャリアを誇るベテランながら、00年代に入ってから目覚ましい活躍を見せるGary Numanが新作をリリース。アグレッシヴという言葉がふさわしい現在の活動は、NINE INCH NAILSのTrent ReznorやMarilyn Mansonが彼からの影響を表明したことによるところも大きいわけだが、パンクの時代、シンセ・オリエンテッドな近未来ロックを奏で、その後のテクノ、エレポップ、サイバー・パンクの先駆けとなったNumanがシンセのみならず、ヘヴィなギター・サウンドも使い、エレクトロニックかつインダストリアルなロック・サウンドを奏でたこの新作。往年のファンのみならず、NINやM.Mansonのファンからも歓迎されるにちがいない。思いきって、Crossfaithのファンにもすすめてみたい。
-

-
Gauche.
メトリックモジュレーション
ピアノ、ベース、ドラム編成によるインスト・バンド、Gauche.の1stミニ・アルバム。リリカルなフレーズを紡ぎ、また感情過多でパーカッシヴなタッチで鍵盤を叩き、リスナーを予測不能な感情のジェットコースターに乗せて揺さぶるピアノと、そのうねりをアシストするだけでなく、土砂降りの雨を降らせるようなドラミングや、激しいベース・ラインなど、それぞれの音がせめぎ合う怒濤のアンサンブルを聴かせるバンドである。今作では、その3人の生々しい息吹と迸る感情とをリアルに収録した。言葉がなくとも歌うことができる心の有り様をあぶり出すような曲であり、インスト・サウンドだからこそできる歌がないぶんの余白で想像させる力を、とことん追求した内容だ。
-
-
geek sleep sheep
nightporter
yukihiro(L'Arc~en~Ciel)、kazuhiro momo(MO'SOME TONEBENDER)、345(凛として時雨)という、ちょっと意外と思わせる組み合わせでスタートしたバンドgeek sleep sheepによる1stアルバム。きっかけはyukihiroのソロ・プロジェクトacid androidの作品にmomoが参加したのが始まりだったという。それぞれのバンドでのアウトプットの仕方こそ違えど、80年代、90年代と同じ音楽体験や音楽的カルチャーショックも受けた同士。このバンドでは各々が好きに衝動を形にしている。本体のバンドやソロの看板を背負うことなく、その時の気分だったり、何となく試してみたかったこともできる自由な空間なんだろう。色とりどり、夢のように脈絡がなかったり、辻褄の合わないこともありになるようなアルバムに仕上がっている。
-

-
GENERAL FIASCO
Buildings
情緒不安定な10代の特効薬となる青い衝動、そんな瑞々しくも疾走感溢れるアグレッシヴさがパねぇ!北アイルランド出身の3ピース、GENERAL FIASCO。THE TEMPER TRAP擁するイギリスの有力レーベルInfectiousが激プッシュするニュー・カマーだ。なんだか同郷のASHがデビュー時に描いた世界観を想起するが、こちらはもっと内省的に踏み込んだナイーヴさがある。歌われている内容に、酒に溺れ向上心のかけらもない人間を目の当たりにした環境が反映されているというが、その嘆きの繊細さと反動の力強さで描く日常感が素晴らしいのだ。瞬時に虜とするキャッチーな美メロあり、なんと3人ともイケメンというウワサもあり……世界中でブレイク間違いなしか!?その真相を確かめに、サマソニでのパフォーマンスを見に行きましょう!
-

-
GENSHOU -現象-
我慢
みなさん、踊る準備はできていますか?キュウソネコカミを輩出し、いったんぶやギャーギャーズらが所属するEXXENTRIC RECORDSよりGENSHOU-現象-が、聴けば騒がずにはいられない2ndミニ・アルバムをリリース。彼らの真骨頂とも言うべき、鋭く、エモーショナルなジャパニーズ・ダンス・ロック・サウンドを見事に表現したアグレッシヴな1枚だ。オリエンタルなメロディとグルーヴ感にはどこか懐かしさが漂いつつ、疾走感やキレのある演奏は若手バンドとしての衝動や勢いで満ち溢れている。パワフルで爆発的な"和"のダンス・ビートに、祭囃子が植えつけられた大和魂が黙っちゃいない。同じ阿呆なら踊らにゃ損、損。
-

-
GEORGIA
Seeking Thrills
新世代のエレクトロ/シンセ・ポップ・クイーンとして注目を浴びているGEORGIAが、ニュー・アルバムをリリース。「Started Out」や「About Work The Dancefloor」といった先行シングルなど、ここ日本でもすでにシンセ・ポップ好きの中では話題となっている楽曲をはじめ、ポップでレトロ感のある楽曲は妙に中毒性がある。アナログ・シンセなどの機材にもこだわった80年代風のビートや、ダンス・フロアを意識したアンセミックな曲調も、マニアックなのに親しみやすい。彼女自身がもともとドラマーということもあって、様々なリズムをナチュラルに乗りこなし、都会的なビートから野性的なビートまで、自分色の浮遊感のあるお洒落サウンドに完成させるセンスはさすが。
-

-
THE GET UP KIDS
There Are Rules
"エモ"シーン、その全てのファンがこの名前を見れば心ときめくはず!あまりにも甘酸っぱいメロディとともに疾走する彼らの楽曲は、"感情"を刺激するまさしく"エモ"の代名詞的存在だった。一度は解散したもののシーンにカムバックしてくれた彼らの復帰作は、往年のファンには大きな驚きを与えるかもしれない。まず、音割れしそうなヴォルテージで響き渡る1曲目「Tithe」。"青春"な香りが漂うかつての彼らの音色から打って変わった攻撃性で幕を開け、続くエレクトリック・サウンドをフィーチャーした楽曲が二重三重のインパクトをぶつけてくる。過去の遺産にしがみつくことなく、現在の自分が信じるものを表現しようとする彼らの気概が表れているような作品だ。
-
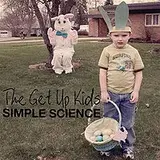
-
THE GET UP KIDS
Simple Science
長嶋茂雄の名言をなぞり、「わがエモは永久に不滅です!」と言っているように聴こえる。もちろん誤訳ですが、そんなエモーショナルなのだ。大盛況に終わった再結成来日公演も記憶に新しいTHE GET UP KIDSから、世界限定ハンド・ナンバリング入り10,000枚のEPが届けられた。スタジオ作としては4th アルバム『Guilt Show』以来約6年ぶりとなる新作だが、不変の泣きメロは健在!ちょっぴり涙腺をくすぐる切なさと軽やかにアゲる疾走感は、最早職人レベルの域です。メンバー自ら立ち上げたFLYOVER RECORDSから第1弾リリースであり、エモ・シーンの立役者として若手に喝を入れるべく(大沢親分イズム)、気概に満ちた叫びが詰まっています。この存在感は、まさにエモ終身名誉監督な佇まい!と、強引に野球ネタを絡めお伝えしました。
-
-
GHEEE
QUAD
前作から3年。ライヴで練り上げてきた8曲と、書き下ろしの4曲(しかもレコーディングの現場でぶっつけ本番で合わせていったという)は、いずれもが、ステージの熱や4人がせり出してくるような音圧や迸るパワーをそのまま封じ込めた臨場感だ。がっちりと絡み合ったアンサンブルであって、なお且つ、プレイヤーの個も色濃く冴えている。3分間のなかで、歪なそれぞれの音の個性を殺すことも抑えることもなく、活かし合い、時に凌ぎ合うように高密度のサウンドを生みだしているのが面白い。90'Sオルタナティヴ・ロックの香りも漂わせ、ヒリヒリに乾いたギター音が肌を擦っていく感覚はスリリングであるし、また絶妙にヴォーカルが入れ替わり、かけ合うことで、曲のスピードが加速するのも体感する。四の五の言わさず聴き手を巻き込むワザが詰まったアルバムだ。
-

-
Ghost like girlfriend
WINDNESS
Ghost like girlfriendの新作はエッジの効いた「shut it up」で幕を開ける。まず耳に入ってくるのは、"描け、狙え、したら行け"という言葉のループ。その後スピード・アップするドラムと効果音をバックに、不自然に区切られた文章がラップっぽく紡がれたのち、突然のびのびと歌声が響きわたる。歌詞のみならず、構成からも"周りを気にするな"というメッセージを感じさせる1曲だ。同曲をリードに据えた今作は、2019年3月の初ライヴを意識して制作された。それゆえ、空間を音楽で埋める意識が感じられる曲が詰まっている。「cruise」の手数の多いドラミングも心地よく、また聴けば聴くほど泣き出してしまいそうになる、リアルで、五感に寄り添った言葉選びも秀逸だ。
-

-
Ghost like girlfriend
WITNESS
作詞作曲/トラックメイクのすべてを手掛ける淡路島出身の新世代SSW、岡林健勝のソロ・プロジェクト Ghost like girlfriendが、デビュー作から約1年を経てミニ・アルバム『WITNESS』をリリース。日常に溢れている小さな幸せや葛藤、些細な喧嘩......ありふれた日常を切り取った歌は数多く存在するが、こんなにもありのままに切なさや弱さも綴りながらも、ずっと聴いていたいと思わせるものはほとんどないだろう。"君は正しい幸せを生きてよ"と願いながら"それでも君と居たかった"(「髪の花」)なんてずるすぎる。感情や景色が丁寧に描かれた歌詞と、ダンス・ミュージックのなかでギターをかき鳴らす絶妙な違和感が心地いい。ひと言で表現しがたい新しい音楽に、一度聴けば虜になってしまうこと間違いなし。
-
-
GHOST TOWN
The After Party
EDM×スクリーモと謳われるハリウッドの4人組、GHOST TOWNによる2作目のアルバム。EDMとはいえ、そこはFueled By Ramen所属のバンド。エレクトロニックなサウンドやダンス・ビートとともにパーティ感覚(ホラー風味を考えれば、ハロウィン・パーティか)を前面に押し出しながら、歌そのものからはFALL OUT BOY以降のR&Bの影響も窺えるし、バラードも含め、じっくりと聴かせる曲もこのタイプのバンドにしてはちょっと多めかもしれない。ピコリーモ以降の、いわゆるアゲアゲのサウンドを期待しすぎると、スクリームの度合いも含め、やや物足りないかも。そこが評価の分かれ目か。しかし、あくまでも歌で勝負するバンドという意味ではやはりFueled By Ramenらしい。
-

-
ジュースごくごく倶楽部
ぎろりエンタイトル
吉本興業所属の芸人6名によるバンド、ジュースごくごく倶楽部の2ndアルバム。どの曲もオーセンティックなロック・サウンドを軸に、賑やかなホーン・セクションがハッピーに曲を彩る「小悪魔なんてもんじゃない」、タイトルの元ネタになっている楽曲と同じく、モータウン・ビートで弾ませる「マジでタク乗る5秒前」、ジンジャエール阪本が男の悲哀を叫び倒す「わし今どんな感じ」、愛コーラの伸びやかなアカペラで幕を開ける「インフィールドスパゲッティフライ」など、全13曲を収録。楽曲制作もバンド内で行い、要所で耳に飛び込んでくる各パートのソロ・フレーズも多数ありと、メンバーが音楽と向き合っている本気度の高さはもちろん、楽しみながらバンドをしていることがありありと伝わってくる良曲揃い!
LIVE INFO
- 2025.11.18
- 2025.11.19
- 2025.11.21
- 2025.11.22
- 2025.11.23
- 2025.11.29
- 2025.11.30
- 2025.12.09
- 2025.12.22
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























