DISC REVIEW
Overseas
-

-
MICE PARADE
What It Means To Be Left-Handed
あるサイトのインタビューでMICE PARADEことAdam Pierceは、あなたにとって“美しい”とは何ですか?と質問され、“その質問の答えを僕は知らないと思う”と答えていた。とするとこの不定形ユニットが世界中の音楽をボーダレスに取り入れ続ける意図は、そんな答えを探索しているようだが、すでにAdamは答えを見つけているようだ。通算8枚目、3年ぶりの新作に溢れる美麗な世界観を堪能したらなおのこと確信してしまう。アフリカ、ブラジル、スペイン、イギリス……あらゆる要素を無国籍感覚で纏めたMICE PARADE節の高揚感たるや!パーカッシヴなフラメンコ・ギターやフィードバック・ノイズの美しさはさることながら、儚い歌声が独自の美を集約している。LEMONHEADSのカヴァーやクラムボンの3人が参加している「Tokyo Late Night」も注目だ。
-

-
NO AGE
Everything In Between
前作『Nouns』はなんとあのグラミー賞にノミネートされたNO AGE("Best Recording Package"。アートワーク系の賞ですね)。その『Nouns』と比べると疾走系ナンバーが増加しているせいか、攻撃性はさらに際立った感あり!ときに無慈悲にループ、かと思えば爆裂するリズム、暴力的に響くファズギター......。ノイジーな音色には鼓膜をかきむしられる感覚さえ覚えるのと同時に、雄大な奥行きで広がる音色はその痛みを癒してくれるかのよう。激しいけれど野蛮じゃない、知性や美をほのかに感じさせる世界観が素晴らしい。ちなみに彼ら、9月は本国でPAVEMENTやSONIC YOUTHらと対バンしているよう(観たい!そのメンツで来日希望!)。その両者を始めとする先人が切り拓いたオルタナティブ精神を、確実に受け継いでいるバンドだと思う。
-

-
THE MAGIC NUMBERS
The Runaway
兄弟2組という珍しい構成のバンドTHE MAGIC NUMBERSの3rdアルバム。FRANZ FERDINANDの日本武道館公演ではオープニング・アクトを務めるなどして、その知名度を高めた彼ら。本作は、Björkのサウンドクリエイターとして長年コラボしているValgeir Sigurdssonがプロデュースを手掛けたことも話題となっている。淡く流麗なサイケデリアをより際立たせるのは、どれが主旋律なのかすら分からなくなる男女のヴォーカル同士の絡み合い。コーラスであったはずの女性ヴォーカルが気づけば男性ヴォーカルと一体化し、両者の切れ目が分からなくなる。かと思えば、ふと気づくと、いつの間にか女性ヴォーカルは姿を消していたり。2種の声が、細胞分裂と結合を繰り返すような妖しい美しさがありながらも、その外形はとても軽やかでポップなサイケデリック・ナンバーとなっている。
-

-
THE RECORD’S
De Fauna Et Flora
イタリアの超ド級スリー・ピース・ポップ・バンドが遂に日本デビュー。THE BEATLESやTHE BEACH BOYSなどの影響が如実に表れた楽曲もあれば、ジャワイアン的なトロピカル要素も見え隠れ。時代と国を股に掛けたポップ・チューンを堪能出来る。若干クリアではない音質との相性が極上だ。3曲目「I Love My Family」はギターが効果的で奇声も混じる酔っ払い並のハジケっぷり。だが4曲目「Panama Hat」は一転、オールディーズへの敬意に溢れたカントリー・ミュージック。これ本当に同一人物?と呆気に取られてしまった。このギャップも彼ら流のポップ・アプローチなのだろう。のどかさとキャッチーさが際立つ中で、さり気なく風味を効かすマニアックな音色や美メロもニクい。
-

-
EVERYONE EVERYWHERE
Everyone Everywhere
フィラデルフィアを中心に活動する23歳の4人組 Everyone Everywhereのデビュー・アルバム。この音楽がみせてくれたのは、“憧れの時代”への時間旅行。私は彼らとほぼ同い年なのだが、90年代ロックというのは当時小学生だった私たちには、手が届きそうで届かなかった距離感であるからこその特別な想いがある。それは、当時は知り得ないはずの音楽へのノスタルジーという妙な感覚。例えば、彼らもフェイバリットに挙げたバンド、DINOSAUR JR の『GREEN MIND』を初めて聴いた時、そのスカスカの手ごたえとノイズと共に溢れるエモーショナルにかき立てられ涙した。この瞬間というのは、リリース当時にタイムスリップしている。もちろん当時はDINOSAUR JRなんて聴いたこともないのに…。ここには00年代に青春期を過ごした世代の、“間に合わなかった時代” への憧れがめいっぱい詰まっているのだ。
-

-
YOUNG HERETICS
We Are The Lost Lovers
憂いを帯びた美しいピアノ、双子のようにお互いに寄り添うKittyとMattのツイン・ヴォーカル、歪んだギター、冷たく響く硬質なビート。デビュー作でありながら、ジャンルを語るのが馬鹿らしくなるほど卓越した表現力は脅威的だ。“破滅的ポップ”とはまさしく彼らの音楽を表現するど真ん中の言葉である。物心ついた頃から共作を行っている2人。共に大人になって見えてきたこと、大人になっても絶対に捨てたくないもの。彼らの音楽にはこの2つが葛藤している。9曲目のタイトルである「010100110100111101010011」は沈没船から送られるモールスコードで“SOS”の意。大切なものたちが無下に扱われる悲しい現実。無邪気で純粋な心は涙を流しながら、大切なもののために戦い続ける。
-

-
SUPERCHUNK
Majesty Shredding
昨年EPをリリースし来日公演も行ったSUPERCHUNKから実に9年振りのアルバムが登場。Jim O' Rurkeプロデュース元作られた前作から、メンバーの育児休暇や別ユニットの活動などで休業状態が続いた彼らだが、昨年復活を果たし今年も夏のフェスへの参加が発表されるなど本格的に再始動。そして届けられた本作は一曲目の「Digging For Something」から力強いパワーポップを聴かせてくれる。とにかく瑞々しくストレートな作品だ。初期のノイジーな感じというよりは抜群のメロディ・ラインを全面に押し出したシンプルなサウンドは彼らの復活を心待ちにしていたファンの期待にバッチリと答えるものだろう。胸躍る素晴らしいギター・ポップ・アルバム。
-

-
THE VASELINES
Sex With An X
NIRVANAのKurt Cobainが生前敬愛していたことでも有名な、08年に再結成したスコットランドのガレージ・ポップ・バンドTHE VASELINESが、2枚目にして実に21年振りのアルバムをリリースする。絶妙なズレを保つEugene KellyとFrances McKeeのツイン・ヴォーカルから際立つのは、良い意味での“脱力感”。いつの間にか催眠状態に陥りそうな、不思議な中毒性を持っている。ポップなメロディに反して曲タイトルはシニカルで、ギターは轟音。ありふれた日常を気負わず自然体で歌いながら、いい笑顔で屈託なく舌を出すようなスカした空気感が心地良い。「Ruined」は1曲目に相応しく勢いがあり、新たなスタートへの決意が漲っている。
-

-
Philip Selway
Familial
"1、2、3、4" ――再生ボタンを押してまず聴こえた彼の囁き声のカウント。魔法が掛かったように、その瞬間から彼の音に落ちていった。RADIOHEADのドラマーであるPhilip Selwayのソロ・デビュー・アルバム。あの巨大バンドを離れて彼が作り上げた世界は、生身の彼をそのまま感じられるまさしく"等身大"。アコースティックでシンプルなアレンジは、柔らかく純粋で、ちょっぴりセンチメンタルな空気を作り出す。その音は心の深い所へゆっくりとあたたかく沁み渡ってゆく。そして感動すべき点は何と言っても彼の歌声である。優しく囁くようにやわらかく丁寧に紡がれる彼の言葉ひとつひとつが、誇り高い輝きを放つ。その光に、悲しみも怒りも浄化されていくようだ。東京大阪で開催される単独来日公演も要注目!
-

-
I AM KLOOT
Sky At Night
マンチェスター出身の3ピースバンドI AM KLOOTが5枚目となるアルバムをリリース。ミュージックビデオに人気俳優を起用し話題になったシングル曲であり、1曲目に収録されている「Northm Skies」はオーガニックでゆるやかな楽曲に仕上がっていて、このアルバムの壮大な音楽の旅の幕開けを予感させる。哀愁漂う「Fingerprints」、泣きのメロディにアコギが響く「Proof」、大人なスロウナンバー「It's Just The Night」と全体的に静かなロードムービーのように押し付けがましくない優しさが広がっている。ブレずに独自のロックを突き詰め、さらに高められた美しいメロディには感服するばかり。ソングライティングを手がけるJohnが“UKロック最大の詩人”と賞賛される理由がわかった。
-
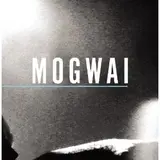
-
MOGWAI
Special Moves / Burning
ライヴに非常に定評がある彼らが満を持して単独ライヴCD+DVDを初リリース。2009年にニューヨークのブルックリンにあるMusic Hall Of Williamsburgで行なわれた3公演から厳選された楽曲と映像を収録している。MOGWAIを語る上で必要不可欠な"轟音"と"静寂"。MOGWAIが創り出す静と動に浸れば浸るほど、音に取りつかれて何も出来なくなってしまった。人は本当に美しいものに触れると、意識も力もどんどん抜けてゆくことを痛感した。極限まで洗練された硬質で繊細な音像のスケール感は、まさしくポスト・ロック第一人者の風格だ。フランスの気鋭映像監督Vincent MoonとNathanaël Le Scouarnecが手掛ける臨場感溢れるライヴDVD も必見。
-

-
THE CORAL
Butterfly House
THE CORALは60年代のロックを飲み込んで、今風にも聴こえるアレンジで絶妙な"古くささ"を醸し出し、独自のスタイルを確立。そしてギタリスト、Bill Ryder-Jonesの脱退を経て、3年ぶりの新作が到着した。"レコードは自分だけの世界を作り上げるマジカルで秘密の場所" というアイディアを楽曲に落とし込んだという今作は、何かが吹っ切れたかのように開放的に音が鳴らされているように思う。美しいコーラスに酔いしれるのも良し、ギターのメロディラインに聴き入るのも良し。何度もリピートしたくなる名曲揃いだ。どうやらメンバーも最高傑作と太鼓判を押している様子。その思い充分に伝わりました! いくつもの謎が残る「1000Years」のミュージックビデオもなんだか意味深。
-

-
THE BITE
ポケットにブルース
良い意味で時代錯誤なサウンドを奏でる4人組、THE BITE。ラジオ風疑似ライヴ盤など、ユニークな作品で話題を集めてきた彼らが遂にファースト・アルバムをリリースする。彼らがかき鳴らす60~70'sを彷彿させる重厚なロックンロールはどこまでもストレートでエネルギッシュ。と、こう書くとどこまでもワイルドで泥臭い作品に仕上がっているようであるが、音の基盤になっているのはあくまでポップ。懐かしさが混じるキャッチーなメロディは、“頼れる兄貴”的な安心感を与えてくれる。そんなハイテンションな楽曲の中で異彩を放つのは「雨の中」。ミディアムテンポの音に乗る酒井大明のしゃがれ声が、物悲しいながらに力強く歌を刻む。この渋さこそ日本男子の持つ色気、哀愁漂うハーモニカにも思わずくらり。
-

-
THE BLACK CROWES
Croweology
年を重ねるごとに味わいを増す上質なワインのように、奥深きロックンロールのロマンを奏で続けるTHE BLACK CROWES。本作はデビュー20周年を迎えたメモリアル・アルバムであり、そのキャリアを網羅し人気曲で纏めた、全編アコースティック・リメイク作となっている。セット・リストを眺めるだけでもファン悶絶のチョイスだが、今年いっぱいで無期限活動休止を宣言した彼らからの、ささやかだが愛情をいっぱいに詰め込んだアルバムだ。グルーヴィでソウルフルな楽曲がアコースティック作として浮き彫りになるのは、ロックンロールに対する真摯、というか良い意味での頑固な姿勢。それは純粋と表裏一体だが、紆余曲折を経た半生を噛み締めるようで感動的である。最後にこんなプレゼントを贈るなんて、かっこよすぎるよ。
-

-
EMERALDS
Does It Look Like I'm Here?
06年に結成されたアメリカのオハイオ発スリー・ピース・バンドの通産3枚目のアルバム。メンバーは全員20代前半。だがその作り込まれた音の構成は非常に成熟しており、研究に研究を重ねたベテラン科学者の発明品さながらの緻密さを誇る。煌びやかな70年代風アナログ・シンセ・サウンドと一癖あるギターが絡み合って作られる抒情的なメロディとノイズ、そのスケール感に拍車をかける重厚なベース音。洗練された電子音がひたすら頭の中を旋回し、どんどん思考能力は奪われてゆく。計算し尽くされた巧妙な精密機械の中を覗いていくとどんどんその中へ迷い込んでしまうような、はたまた宇宙の奥の奥に広がる未知なる世界に侵されてしまうような――異次元に連れ去られること必至の1枚。
-

-
KNIGHT SCHOOL
Revenger
いまや、“ブルックリン”という地名を聞いただけで、“おっ!”と反応する音楽ファンは相当数に昇るかも(笑)。そんな世界随一のミュージック・シティから、面白い素材がまたひとつ登場だ。今年のサマソニにも参戦するTHE DRUMS の「Let's Go Surfing」を、ローファイ感たっぷりにリミックスした2 人組、KNIGHT SCHOOL。Kevin AlvirとChris Ballaのデュオが鳴らすサウンドは、インディー・スピリットをビシビシ感じるザラついた質感。そして、ときにはシューゲイズな感覚もほのかに漂う轟音の中から響くメロディは、たまらなくスウィート!ユラユラと揺れるように響く声は、聴いているこっちの頭も自然とユラユラ揺れて、心地よく酩酊状態に……。夏の夕暮れに、ビール片手に聴いたら最高ですね(笑)。
-

-
GRASS WIDOW
Past Time
サンフランシスコの女性トリオ、GRASS WIDOWの初のフル・アルバム。デビューEPがVIVIAN GIRLSに絶賛され、7月にはSONIC YOUTHのサポート・アクトとして、ブルックリンのプロスペクト・パークでの野外イべントにも出演が決定するなど、既にその注目度は高い。一部では、今年最強の新人バンドとまで言われちゃっている女の子3人組は、そんなことはおかまいなしに低血気味なコーラスで淡々と歌う。その心地良いコーラスは、張り詰めた空気の中の、唯一の癒しとなっている。人肌の温もりのような居心地の良さ、静かなる声の共鳴、そこにまた酔ってしまいそうだ。この音はスカスカなのか重厚なのか、それすらあやふやな、つかみどころのなさも魅力的だ。徐々に高ぶってくるこの感じ、ローファイなんてとんでもない、グルーヴィに思えるのは私だけだろうか?
-

-
LOCAL NATIVES
Gorilla Manor
LA出身のニューカマー。FUJI ROCK FESTIVALにも出演が決定し、某レコードショップでも猛プッシュされていたのでご存知の方も多いかも。海外では今年2月にリリースされ、全米ビルボードでニューアーティスト・チャート3位にランクインするなど海外メディアでも大注目の彼ら。スウィート・アコースティック・サウンドと呼ばれる様にフォーキーな音色と美しいコーラス・ワークが彼らの魅力。ヴォーカルが3人もいてライヴでは4人で迫力ある歌声を響かせる。今作はアフロ・ビートも取り入れ軽快で爽快感溢れるナンバーもあり、しっかりとトレンドを押さえた内容。透明感あるメロディもさることながら、切れのあるドラムも聴き所だ。
-

-
ARIEL PINK'S HAUNTED GRAFFITI
Before Today
USインディのカルト・アイドルと言われるARIEL PINK。かつては知る人ぞ知る存在であった彼がGIRLSやANIMAL COLLECTIVEに認められついに今作でUKの名門レーベル4AD と契約を結びデビュー。ローファイ・サウンドと基本としながらもARIEL PINKを中心に結成された彼らのサウンドは明らかにそのカテゴリーをはみ出していて、とにかく摩訶不思議。ディスコやAOR風の楽曲もあれば、普通にシンプルなポップナンバーもあったり。ただ曲の展開は読めず。「L'estat」という楽曲はポップながら捉え所のない空間を漂うような曲で初めて聴いた時は度肝抜かされた。ただこの散漫と捉えられてしまうかもしれないこの作品のドラマティックさにはとても惹き付けられる。
-

-
HERE WE GO MAGIC
Pigeons
アメリカ、ブルックリン発のサイケデリック・ポップ・バンドが待望の日本デビュー盤をリリース。飄々としたギターと、柔らかくあたたかいキーボード。その中に芯を通すようにリズムを刻むベースとドラム。その音にぽっかり浮かぶ、ちょっと風が吹けばどっかに飛んでいってしまいそうな頼りなさげなヴォーカル。思わずうたた寝をしてしまいそうな心地良さだ。『Pigeons』という物語を進めれば進めるほど、夢なのか現実なのか分からなくなってゆく。だがどんどん彼らの世界が曖昧になれば曖昧になるほどどんどん鮮やかになっていくから不思議である。それこそ彼らが巧みに操る“マジック” なのかもしれない。催眠効果を伴う圧倒的な浮遊感とノスタルジック。気だるい夏の暑さと共に、夢と現実の狭間へ落ちていくのも悪くない。
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号








