DISC REVIEW
M
-
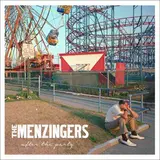
-
THE MENZINGERS
After The Party
3年ぶりのリリースとなるこの5作目は、作品を重ねるごとに音楽性を広げてきたTHE MENZINGERSの印象をまた若干変えるかもしれない。2006年結成のペンシルベニア州フィラデルフィアの4人組。THE CLASHを連想させるストリート・パンクの要素も持つポップ・パンクという本質のところは変わらないものの、フォークやオールディーズといったアメリカン・ロックのルーツに回帰するような曲がある一方で、80年代のUKロックを彷彿させる煌きを纏った曲もあるのは、メンバーそれぞれのバックグラウンドをこれまでよりも自由に反映させた結果なのか。ともあれ、それらがしっかりと彼ららしい曲になっているのは、10年のキャリアの中で培った独特なグルーヴと歌声のユニークさによるところが大きいのだろう。
-
-
MERCHANDISE
After The End
米フロリダ州タンパ発の5ピース、MERCHANDISEが通算4作目で、4ADからは初となるアルバムをリリース。フロリダというと個人的にはエモやハードコア勢の強いイメージの地で、彼らもまた遠からずというか、ノイジーで実験的なサウンドを生みだしていたと思うが、今作では劇的に変化。80年代ポップスのセクシーさ、シンセ・ポップも取り込んだ。わかりやすくシンセをキーにした曲よりも、深みを増した匂い立つようなギター・サウンドの曲が圧倒的にいいのだけど、ここにCarson Coxの低音が横たわるとさらにロマンティックに。DEPECHE MODEやINTERPOL、GRIZZLY BEAR作品を手掛けるGareth Jonesをミキサーに迎えて、音作りからバンドの意思を明解に伝えたアルバムは、THE CUREなども思い浮かぶ繊細なメランコリーが美しい。
-
-
MERCURY REV
The Light In You
MERCURY REVといえば、世界一のプロデューサーと言っても過言ではない名匠Dave Fridmannがレコーディング・メンバーとして籍を置くことでも知られるロック・バンド。しかし、7年のインターバルを挟みリリースされた今作『TheLight In You』に、Daveはスケジュールの都合で不参加。そういった背景でJonathan DonahueとGrasshopperのみで制作された今作からは、より密な空気感と円熟したヴァイヴが感じ取れる。作品は冒頭の「The Queen OfSwans」から穏やかに立ち上がり、全体を通してユーフォリックな祝祭感とソフトにロックする甘美なサイケデリアが横溢する。安穏とした流れに差し込まれる「Sunflower」のホット・グルーヴィンな異物感もいいスパイスに。聴き疲れも飽きも少ない末長く愛聴できる秀作だ。
-

-
Mernote
接触
バンド"のの"のギター&ヴォーカル、長谷川海音のソロ・プロジェクト"Mernote"による初のフル・アルバム。ひと言で言うなら、細胞分裂を現在進行形で繰り返しているような......。メロディの進め方、曲の展開のさせ方、楽器の入れ方、どこに注目してみても読み取ることができるのは、典型的な表現を避けようとする姿勢。自由自在な発想をもとにした、"こういうジャンルです"とは一概に言えない10曲が揃っている。ギター・リフを起点とした文字通りダンサブルなナンバー「dance」、ストリングスを大胆に取り入れた「untouchable」、ピアノ弾き語り曲「時の川」、社会を捉えた「香港」などを収録。バンドでは歌とギターをメインに演奏している人物だが、リズムへのこだわりが強く感じられるのが興味深い。
-

-
METRIC
Art Of Doubt
カナダのシンセ・ポップ/ロック・バンド、METRICの7thアルバム。冒頭の「Dark Saturday」は、夜の都会の路地裏が情景として浮かぶ1曲で、ダーク且つ耳馴染みがいい音の上に、気怠そうながら色気のあるEmily Hainesの歌声が乗ることで生まれるスリリングな空気感が、本作の世界へ聴き手を引き込む。表題曲「Art Of Doubt」は、感情の起伏の激しいヴォーカルとそれに呼応するように展開していくディープなサウンドが文句なしにカッコいい。また壮大なミドル・チューン、「Underline The Black」では美しいメロディにうっとりさせられる。懐かしさを感じさせるニュー・ウェーヴ的なサウンドながらも、決して古さは感じさせない円熟味のある1枚。
-

-
METRONOMY
Love Letters
素晴らしい。前々作『Nights Out』では脱臼エレポップで一晩の夜遊びを描き、続く『The English Riviera』では70年代AORをも消化し、優雅な箱庭ポップを展開。そんな己が道を突き進むMETRONOMYの新作は、『Nights Out』や『The English Riviera』にあった煌びやかさは薄れ、全体的にメランコリックな印象を聴き手に与える、今までで最もパーソナルな質感を持った作品に仕上がっている。アルバム全体を、まるでアンビエント・テクノのように繊細なアトモスフィアが覆っている上に、単音で奏でられるメロディはどれも切なく、曲によっては爪弾かれるギターの音色が哀愁を誘う。『Love Letters』というタイトル通り、まるで古い友人から1通の手紙を受け取ったかのような親密さを感じさせるアルバム。誰もが抱える心の孤独にそっと寄り添う傑作だ。
-

-
METZ
II
トロント出身のポスト・パンク・バンドの2ndアルバム。首尾一貫、ローファイな音が鳴り続けるいかにもSUB POPなグランジ・アルバム。NIRVANA以降もグランジのみならずBAND OF HORSESやCSSなど、多様なアーティストを輩出してきたSUB POPの先祖返り的なサウンドで、今時こんなアルバムができるのかとちょっぴり懐かしさすら覚えてしまう。イギリスの鬼才エンジニア/プロデューサーJoe Meekの仕事のような小曲「Zzyzx」に続く爆裂パンク「IOU」、「Landfill」、ラストの「Kicking A Can Of Worms」まで、とにかくやかましくてたまらない音楽が好きな方にはおすすめの1枚。できればデカい音量でかけられるシチュエーションで聴いて欲しい。ヘッドフォンで聴くと耳が悪くなりそうだから!
-

-
METZ
Metz
西村賢太の『苦役列車』を読んだ時、"この感じ、久しぶりだな"と思った。自堕落な主人公と、自堕落な生活。悪意と自嘲。正論より本音を描かんとする覚悟と優しさ。私小説。学生時代に読んでいた太宰や安吾を思い出したりもした。で、このSUB POPのニュー・カマー、METZの1stアルバムを初めて聴いた時の感覚は、そんな『苦役列車』の後読感に近かった。暴力的にノイジーなギター。硬質なビート。喉から血が出そうなほどの咆哮。「Headache」や「Negative Space」といった曲名から感じ取れる内省的な世界観。グランジ。かつてのNIRVANAがそうであったような、本音で世界と渡り合おうとする、あまりに愚かで愛おしい衝動がここにはある。"正しい音"はいらない。"本当の音"を鳴らす新世代グランジの傑作。
-

-
MEW
Visuals
前作から2年という、バンド史上最も短い期間でリリースされる完全セルフ・プロデュース/レコーディングによる7枚目のアルバム。2015年にBo Madsen(Gt)の脱退という大きな変化に立ち止まることなく、むしろその変化や直感が素直に閉じ込められた作品だ。時間をたっぷりかけ創り上げるという彼らの従来の制作スタイルを打ち破ることに挑戦した本作は、ツアーでのエネルギーや閃きが、ギター・サウンドやより開放的になった歌詞にストレートに表れている。彼ららしさを失わないまま、「Carry Me To Safety」に代表される、エネルギッシュなのに繊細、それでいて以前より壮大になった印象を与える楽曲ばかり。永遠に続くものなどない――変化が目まぐるしい現代だからこそ、長い期間を空けずに彼らが届けたかった思いが感じられる1枚だ。
-

-
MEW
Eggs Are Funny
FLAMING LIPSとの来日公演も記憶に新しいMEWからクリスマス・プレゼントが。結成から14年、バンドの歴史を網羅したベスト盤『Eggs Are Funny』である。代表曲はもちろん、メジャー・デビュー以前のレア音源や先日の公演で披露され話題となった新曲「Do You Love It?」も収録。さらには歴代のビデオ・クリップをコンパイルしたDVD付きというから、もう最強盤である。愛らしくも透徹な歌声、壮大な構築美、北欧の冷気漂う叙情性、アーティスティックな映像と、オリジナリティ溢れる世界観はいかにして描き出したのか?そんな進化/深化の過程を辿るように聴くとおもしろい。「Repeaterbeater」を音源では収めなかったのは彼ららしいひねくれセンスだろう。そろそろ“デンマークの至宝”という枕詞から、“デンマークの世界遺産”に認定しては?
-

-
MEW
No more stories Are told today I'm sorry They washed away No more stories The world is grey I'm Tired Let's Wash Away
ベーシストの脱退というアクシデントもあり、何と4年ぶりのリリースとなるMEW の5枚目のアルバム。まず何よりも、ブラッシュアップされたリズム隊が叩き出す多彩なビートに驚かされる。これまでのMEWにはなかった軽快なリズムの上をカラフルでドリーミーな音世界が広がっていく。特に、ダンサブルなM-9 ~M-11の3曲は、MEWの新境地とも言える出来。基本的にループするように連なって行くメロディは、螺旋を描きながら、さらに高みへと聴く者を誘っていく。アルバム全体を通してどこか醒めた質感の前作から一転、本作では温かみのあるサイケデリアを描き出している。ニューゲイザー、エレクトロ・シューゲイズ勢ともシンクロする極上のドリーミー・ポップ。
-

-
MGMT
Loss Of Life
MGMTが、約6年ぶり5枚目となる新作を発表した。原点回帰を果たした前作『Little Dark Age』は表題曲がTikTokで人気を集め、新たな層からの支持も得つつある彼らだが、本作では新たなフェーズのポップへの探求へと歩み出したようだ。前半ではOASISを彷彿させるギター・ロックのTrack.2、女性Voとのハーモニーが美しいTrack.3など、バンド・サウンドを軸に普遍的なポップネスを展開。後半ではエクスペリメンタルな側面が顔を覗かせていて、サイケの海に沈みゆくようなTrack.8、グリッチ・サウンドの中で幽玄なヴォーカルが漂うTrack.10と、摩訶不思議だが温かみのある世界へと変化していく様が心地よい。大衆性と実験性を高次元で両立させた意欲作だ。
-

-
MGMT
Mgmt
「Your Life Is A Lie」のMVが先行配信された際に感じた遊び心、かつてスタイリッシュ代表だった時期とは違うユルさが感じられるジャケを見た際の驚き。それはあながち内容とも無関係じゃなかった。前作『Congratulations』ほど内向的ではない。ふるいにかけられた10曲は似たものはなく、おのおの彼らが今感じていることをあの独特なフェティシズム、サイケデリア、悪夢的なイメージに沿う音と音の組み合わせで表現しきっているのだと思う。これまで同様、夢と現の境界線はボンヤリしているのだけど、不穏と甘美を奏でるエレクトロニクスのレイヤーにやられる「A Good Sadness」などはかなりの大作。不安の中にも喜びや煌めきを発見したり、逆もまた然り。現実世界を映す鏡のような作品だ。
-

-
MGMT
Congratulations
自転車で思い切り勢いをつけた後、ペダルを漕がないでいる時間って気持ちいいですよね。自由だし。そんな感じでしょうか。『Oracular Spectacular』で世界に衝撃を与えたMGMTだが、新作への期待もどこ吹く風という感じで、1967年のサンフランシスコにトリップしてしまった。プロデューサーにSonic Boomを迎えた今作は、音の質感といい、メロディといい、コーラスといい、そのまんまサマー・オブ・ラヴ。このレイドバックしたトリッピー感は、今の空気を象徴しているのかも。よくも悪くも、人間なんてそんなに変わらない。牛耳るか、諦めるか、それとも反抗するか。立場の違いだけ。2010年、時代の波を自在に乗りこなしながらMGMTが放つカウンター・ミュージック。
-
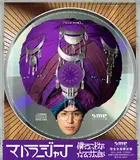
-
MHRJ
僕のスピな☆ムン太郎
スーツにターバン姿という強烈なヴィジュアルから放たれる洗練されたサウンドが話題のマハラージャンが、ついにメジャー1stアルバムをリリース。今まで作詞、作曲、編曲、演奏すべてを自身で手掛けてきたその圧倒的な楽曲センスはそのままに、本作ではハマ・オカモト(OKAMOTO'S/Ba)や石若 駿など豪華ミュージシャンが参加しさらにパワーアップ。会社員時代の経験をもとにしたシニカルな歌詞と、グルーヴィでダンサブルな楽曲に乗せて、社会人の"あるある"をポップに笑い飛ばす心地よさがクセになる。また「セーラ☆ムン太郎」ではEric Claptonの「Layla」をオマージュするなど、スパイスの効いた遊び心も。そんな彼が描く"デカいビジョン"に確実に近づく大きな一歩となる作品だ。
-

-
M.I.A.
MAYA
「Born Free」のPV、NYタイムズとのあまりに強烈なバトル。このアルバムを前にM.I.A. が振りまいた論争の渦は、とてつもなく大きかった。そんな中で世に出る本作は、多様な音楽性と感情が混在、交錯している。DIPLOやSWITCHを始めとしたプロデューサー陣とともに多種多様なビートをM.I.A. 流に乗りこなす不穏で攻撃的な曲も強烈なインパクトがあるが、それ以上に彼女の女性の部分が出た柔らかくポップな楽曲の秀逸さが目を引く。きっと母親になったことも大きいのだろう。自らの名前を冠した本作には、M.I.A.という特異なキャラクターが獲得した母性の強さを感じずにはいられない。だからこそ「Born Free」はあれ程の怒りに満ちているし、だからこそこのアルバムはとても優しく温かい。
-
-
MICE PARADE
Candela
数々の客演でも知られるAdam Pierceによるポスト・ロック・バンドMICE PARADEのニュ−・アルバムが到着した。日本でもクラムボンとの共演やFUJI ROCK FESTIVALなど数々の来日を果たしているため人気も高い彼らだが、前作から2年振りとなる今作は“今までとはまったく違う、はるかにいいものになる”と本人が言ったように、よりコンパクトにまとめられメロディを重視した耳馴染みのいいとても心地いい仕上がりだ。持ち味であるパーカッシヴでスリリングなアンサンブルも健在で、複雑なリズムと暖かいギターと柔らかな女性ヴォーカルが胸を打つ。特にタイトル・トラック「Candela」から後半の流れが特に素晴らしく、美しい景色を眺めているようなそんな気分に陥るアルバムだ。
-
-
MICE PARADE
What It Means To Be Left-Handed
あるサイトのインタビューでMICE PARADEことAdam Pierceは、あなたにとって“美しい”とは何ですか?と質問され、“その質問の答えを僕は知らないと思う”と答えていた。とするとこの不定形ユニットが世界中の音楽をボーダレスに取り入れ続ける意図は、そんな答えを探索しているようだが、すでにAdamは答えを見つけているようだ。通算8枚目、3年ぶりの新作に溢れる美麗な世界観を堪能したらなおのこと確信してしまう。アフリカ、ブラジル、スペイン、イギリス……あらゆる要素を無国籍感覚で纏めたMICE PARADE節の高揚感たるや!パーカッシヴなフラメンコ・ギターやフィードバック・ノイズの美しさはさることながら、儚い歌声が独自の美を集約している。LEMONHEADSのカヴァーやクラムボンの3人が参加している「Tokyo Late Night」も注目だ。
-

-
MIGMA SHELTER
OZ three
ミミミユが卒業し7人組になったMIGMA SHELTER。彼女たちによる"オズの魔法使い"×"サイケデリック・トランス"の3部作シングルが本作で完結した。「Brave」はバキバキに攻めたパートとじっくり聴かせるパートの緩急が印象的な1曲。オズで"Brave"="勇気"というと臆病なライオンをイメージさせるが、本楽曲はライオンをフィルターとしてMIGMA SHELTER自身のことを歌っているようにも思える。真偽のほどは定かではないが、いろいろと考察できる楽曲には間違いない。「Any Colours」はめまぐるしい展開に合わせて歌唱、ラップ、語りと様々な声の表現が盛り込まれているところが個性的。3部作の完結に相応しく、ドロシーと物語を総括するような歌詞も注目ポイントだ。
-

-
MIGMA SHELTER
OZ two
新メンバー3名が加入し、さらなる新体制となったMIGMA SHELTERによる"オズの魔法使い"を題材にした3部作シングルの第2弾『OZ two』。壮大でファンタジックな世界観から幕を開ける1曲目の「Be alive」は、主人公のドロシーと、カカシ、ブリキの木こり、ライオンの旅路を想起させる楽曲だ。曲が進行していくにつれて、徐々に雲行きが怪しく不穏になっていく展開は中毒性が高い。2曲目は「A land switched by a witch」。こちらは魔女によって変えられてしまったオズの国に佇むカカシに焦点を当てたと思われる1曲で、ミシェルらしい踊れるサウンドと共に歌詞の言葉遊びも堪能できた。次作でミシェルなりの"オズの魔法使い"がどう完結するのか、期待が高まる。
-

-
MIGMA SHELTER
OZ one
新メンバーのワニャ+、ユイノンを加えて6人組になった"サイケデリックトランスでアタマぶっ壊れるまで踊る"MIGMA SHELTER。彼女たちの新体制初リリース作品が、"オズの魔法使い"を題材にした3部作シングルの第1弾『OZ one』だ。1曲目は、物語の序章として竜巻や魔女をテーマにした「Tornado」。脳を揺らすサイケデリック・トランスと不穏でとげとげしい空気感の融合がクールで、強風が吹き荒れるようなドロップは作品への没入感を高めている。2曲目の「Emerald」は、オズ王国にたどり着いた主人公のドロシーが仲間と出会いながら向かったエメラルドシティについて楽曲化。3部作全体で今後どのような"ミシェルなりの「オズの魔法使い」"の世界が創造されていくのか、期待が高まる。
-
-
MIGMA SHELTER
ALICE
サイケデリック・トランスで踊り狂うアイドル・グループ MIGMA SHELTERが、クラウドファンディング目標400パーセント超えとなる約1,200万の支援を経てアルバム『ALICE』を完成させた。本作のコンセプトは"不思議の国のアリス"。過去にも様々なフォーマットで題材とされてきた誰もが知る名作だが、時として狂気を感じさせる"不思議の国のアリス"とサイケデリック・トランスとの掛け合わせは、ある意味で危険なまでの相性の良さを見せている。作品の没入感はものすごく、非現実的な世界、それこそ不思議の国に迷い込んだような感覚に1枚を通して包まれた。アルバム単体として楽しめるのはもちろん、原作のストーリーを頭に入れたうえで少女の物語を辿るのもいいだろう。怪作にして傑作。
-

-
mihoro*
May you be happy
ミニ・アルバム『love is alive』から約3年ぶりのフル・アルバム。過去曲でもサポートしていた雲丹亀卓人(ex-Sawagi)との「愛していた、これは本当」、YUKIやいきものがかり他を手掛ける湯浅 篤との「アネモネ」など初のコライト曲や、バンド・サウンドが基調となったなか、アレンジ面ではESME MORIとのタッグでmihoro*としては初めてメロウなトラックで歌う曲もありと試みのある作品になった。20代半ばの現在地から見える、変わらないものと変わりゆくもの、大人になっていくことやそこで生じる心の機微を、どちらも大事に歌に落とし込んだ。とてもリアルな体温が宿った曲が並ぶ。10代の頃からあった繊細さ、ちょっとした頑固さも、時を経てチャーミングに描かれている。柔らかな声と飾らない等身大の歌がフレンドリーな1枚だ。
-

-
mihoro*
love is alive
昨年秋、初の全国流通盤『Re:』をリリースしたSSW、mihoro*が今作『love is alive』でメジャー・デビュー。10代から活動を始めて、等身大のリアルな思いや恋愛の曲を多く描いてきた彼女が今作に詰め込んだのは、タイトルにもある愛のストーリーだ。うまく思いが通じ合わないもどかしさや、自分だけがいっぱいいっぱいでから回っている惨めさが滲む瞬間、「馬鹿な女」では自嘲気味に"貴方を好きな私が嫌いだった"とも歌う。自身の体験がもとになっているわけではないというが、そこで描かれる主人公たちの気分、眼に映る情景はとてもリアルで、そんなところが共感を呼んでいる。今の私、いつかの私が見つけられる曲だろう。現在放送中のドラマ・エンディング・テーマ「ミヤコワスレ」も収録。
-

-
mihoro*
Re:
今年20歳になったSSW、mihoro*の初流通盤となるミニ・アルバム。新曲や高校時代の曲、MVが100万回再生を超え、同世代を中心に反響を得ている「遊んでたの、知ってるよ。」など全8曲が収録された。白昼夢的な、気だるい痺れに浸るような「ナチュラルハイ」、普段は押し殺している感情が堰を切って溢れ早口でまくしたてる「ルサンチマン」の攻撃性、大人へと変わりゆく年月のスピードと心の速度がちぐはぐなリアルを描く「コドモノママデ(20)」など、心の機微や身に起こる出来事を素直な言葉で歌っている。ソリッドなギター弾き語りや、雲丹亀卓人(ex-Sawagi)とアレンジを施した多彩なバンド・サウンドもありと、各曲キャラクターが立っていて、聴き手が自分を投影できる曲が見つけられそうだ。
-

-
MIIKE SNOW
Miike Snow
カラフルでメロディアスなポップ職人、MIIKE SNOWがいよいよ日本デビュー。その正体は、Britney Spears「Toxic」など、世界的ヒット・ソングを数多く手がけたスウェーデンのプロデューサー・デュオが結成したバンドである。様々なアーティストに楽曲を提供しながら、バンドを続けてきた彼ら。PASSION PITやMIKA、PETER BJORN AND JOHNといった現代のポップ職人達と並ぶ、どこか切なさも携えた眩いポップ・ソング。エレクトロから、R&B、60's なポップまでを丁寧に現代にアップデートした彼らの音楽には、決して打算的なプロダクションはない。自らのイマジネーションの赴くままに産み落とされた、心踊る楽曲のクオリティの高さに驚かされるばかりだ。
-

-
MIKA MIKO
We Be Xuxa
NO AGE等とともに、LAのDIYシーンの代表的存在として高い注目を集めているMIKA MIKOのセカンド・アルバム。SLITSを思わせるヴォーカル、THE DAMMEDなどの初期パンクからDEVO、THE B-52's等の影響も伺えるパンク・サウンドが特徴的だが、いい具合にスカスカとしたガレージ・サウンドが、まさに今の音として鳴っている。そして、つんのめり過ぎず、軽快に跳ねるビートが全体を引き締める。冒頭を飾る「Blues Not Speed」や「JohnsonR. Cool」のような疾走感溢れるパンク・ナンバーもよいが、リヴァーヴの効いたコーラスとベース・ラインが特徴的な「Totion」、不穏なホーンが入り乱れる「Keep on Calling」など、タメの効いたビートの楽曲が、特にカッコイイ。
-

-
Miles Kane
Colour Of The Trap
一日が終わりを迎え、始まりに切り替わる瞬間はいつだろう。夜明けは終わりでもあり、始まりでもある。Miles Kaneは、そんな時間や空間の連続性の中に自分自身を見出している。血が湧き踊るビートとタイトで熟成されたサウンドは、密度が濃い。時間軸を思わせる楽曲は、圧倒的な完成度を誇る一日を記した日記、大きくはMiles Kane個人の歴史のようでもある。最終的には「Morning Comes」と歌い、終わりから始まりのシフトを予感させる。歴史の最後に終わりが訪れない、それこそがMiles Kaneが仕掛ける“罠”なのだ。オールディーズを踏襲した正統さの中に見え隠れする、狡猾さと貪欲ささえも心地よい。THE LAST SHADOW PUPPETS、THE RASCALES、THE LITTLE FLAMES――彼がこれまでに刻んだキャリアは、みんな忘れてしまえ。純粋培養の美意識の前では、冠言葉ほど無用なものはない。
-

-
MAN WITH A MISSION × milet
絆ノ奇跡 / コイコガレ
アニメ"「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編"のOP主題歌として、MAN WITH A MISSIONとmiletという異色タッグが実現した「絆ノ奇跡」。「コイコガレ」は同アニメのED主題歌であり、こちらは"鬼滅の刃"で「炎」(LiSA)や劇判などを手掛けてきた梶浦由記が作詞作曲を手掛け、マンウィズと共に編曲をしたスペシャルなタッグになっている。アニメの世界観を意識し和楽器のエッセンスを用いるなど、miletのヴォーカルとの掛け合いがドラマチックな「絆ノ奇跡」が迸るバンド・サウンドが軸になっているのに対して、「コイコガレ」の梶浦×マンウィズ×miletの掛け算は新鮮。ストリングスが先頭を走り、そこにギターやそれぞれのヴォーカルが有機的に絡む。エモーショナルでいて、先の読めない緊張感も並走するヒリヒリする爆発感が妙味だ。
-

-
milet
Who I Am
穏やかなメロディから重厚なバンド・サウンドのサビへ向かうアレンジと、声の変化に自分の存在意義を確認する様を体感できる表題曲。スケールの大きさや転調などワンオクToru(Gt)のプロデュースも聴きどころだ。対照的に話すニュアンスに近いハスキーなAメロから、駆け上がっていくダイナミズムを感じられるバラード「The Hardest」、アトモスフェリックなエレクトロ・サウンドと、軽快且つテクニカルなVoが楽しい「One Touch」、共作者 Mick Cooganとの語りの掛け合いが映画的なニュアンスを添える「Ashes」、マンウィズのBa/Cho Kamikaze Boy提供「Grab the air」の、BOOM BOOM SATELLITES中野雅之リミックスまでレンジの広さを堪能できる。
-

-
milet
Prover / Tell me
ハスキーで海外のR&B系ヴォーカリストのような存在感を持つ声で異彩を放つmilet。桑田佳祐がデビュー曲を2019年邦楽シングルの1位に選出したほどだ。早くも5作目のEPである今回。"証明者"を意味する「Prover」は力強いピアノ・リフが刻まれ、神聖な空気を醸すエレクトロニックなサウンドも相まってアンセム的な説得力がある。ここでも硬質でいて柔軟という両面を兼ね備えた声の力が際立っている。一方の「Tell me」は一転、光を感じるメロディやサウンドのテクスチャーで、少し甘く鼻にかかる声の魅力にとらわれる。c/wは「Your Light」のエレクトロ/R&Bのクールさ、「レッドネオン」のスケールのあるフォーキーさなどレンジは広いが、伝える意志に満ちた毅然とした歌が1本の筋を通す。
-

-
milet
inside you EP
2018年から本格的に音楽活動を始め、『inside you EP』でデビューを果たす、彗星の如く現れた新人シンガー・ソングライター、milet。デビュー作にもかかわらず、竹内結子主演ドラマ"スキャンダル専門弁護士 QUEEN"OPテーマなど、収録曲のほとんどがタイアップ曲であることからも彼女への注目度の高さが窺える。表情豊かなハスキーで厚みのある歌声に、ドラマを観ていて心を奪われた人も多いはず。さらに、思春期をカナダで過ごした彼女の流暢な英語詞を織り交ぜた歌詞や、一度聴いたら頭から離れなくなるメロディなど、ソングライティングの才も抜群。未だヴェールに包まれている部分が多いmiletだが、聴けば聴くほど彼女について知りたくなる、圧倒的な存在感を放つ楽曲が揃っている。
-

-
DUTCH UNCLES
O Shudder
マンチェスター出身の5人組、DUTCH UNCLESの4作目。彼らと同じく2009年にアルバム・デビューしたBOMBAY BICYCLE CLUB同様、ポスト・ロック~エレクトロニカ以降の皮膚感覚で、叙情的かつ構築的なハイブリッド・ポップスを奏でている。が、彼らがBOMBAY BICYCLE CLUBと違う点は、XTCやTALKING HEADS、SCRITTI POLITTIといった80年代ニュー・ウェーヴ勢からの影響があっけらかんと出てくるところ。リズムに対する冒険心と和音やメロディに対する美意識が拮抗するヒリヒリとした感触が、あの時代のバンドに似ているのだ。常に肉体的かつ歪でありながら、息をのむほどの美しさも持っている。そして、そのすべての要素がとても生々しい。そこがいい。
-

-
Milkey Milton
STARLIGHT
音楽系の専門学校で出会ったメンバーで結成された3人組ガールズ・バンド、Milkey Miltonによる初の全国流通盤ミニ・アルバム。メンバー全員が作詞を手掛け、それぞれに個性を生かした楽曲が収録された今作は、力強くも切ないピアノ・ロックに乗せて、全5曲に女の子のリアルな気持ちが綴られている。chika.(Key)による作詞作曲で、昨年7月に渋谷Guiltyで開催した初ワンマンでも披露された疾走感溢れる「八月十二日」をはじめ、"君"と歩いてゆく未来に向けての葛藤を刻んだ、ume(Gt)による作詞作曲「現在と未来」、最終列車で繰り広げられる別れのシーンが目に浮かぶような、mana(Vo)作詞作曲の「最後の『またね。』」まで。毒も悲しみも内包するミルミルの楽曲にロックの響きがよく似合っている。
-
-
MINA
愛楼
次世代アーティスト MINAが1st EP『愛楼(読み:めろう)』を発表した。2016年にGIRLFRIENDのベーシストとしてメジャー・デビューし、現在はベース・ヴォーカル動画などでSNSを中心に活動する彼女。初のCD作品となる本作は、そんな彼女の真骨頂であるスラップ奏法が炸裂するデビュー曲「天上天下唯我独尊」で勢い良く幕開け。ちなみに本人による"弾いてみた"動画がYouTubeにて公開されているのでこちらも要チェック。ほかにも、SNS上の投稿を巡る"狂愛"を描いた「君がいいねした」など、ベーシストならではのグルーヴ感で聴かせる全5曲を収録。様々な形の"愛"を注いだ作品とのことで、かわいらしい曲調も相まって多くのティーンエイジャーに刺さりそう。
-
-
MINI MANSIONS
Mini Mansions
穏やかなピアノとギターの音色、土に染み込んでいく水のように清いコーラス・ワーク。なのに何故こんなにも、無性に胸を掻き毟るのだろう。米ハード・ロック・バンドQUEENS OF THE STONE AGEのベーシスト、Michael Shumanが中心となって結成されたスリー・ピース・バンドのデビュー・アルバム。美しく繊細な不協和音は懐かしくもあり、まだ見ぬ森の奥を感じさせるような絶妙な不穏感も持ち合わせている。何ともシュールなサイケデリアは非常に高い中毒性があり、ぼんやりしていると飲みこまれそうになってくる。バロックやゴシックを感じさせるオルガンも、純粋なのにどことなく悲しげだ。黄金色に光る西日の中にぽつりとひとり残されたような、ぬくもりと切なさを醸し出す。
-

-
MINIMUMS
YMO vs minimums
マリンバ2台とパーカッションからなる女性3組ユニットのMINIMUMS のYMOカバー集。都内のワンマン・ライヴでは常に満員状態という人気を誇るこのユニットは国立音楽大学を卒業後、数々の音楽コンクールで賞を受賞後、NHKの朝のテレビ小説の音楽の演奏を担当するまでの急成長をとげ注目を集める。さて、今回のアルバムはタイトルが示す様にYMOの楽曲を3人がじっくりと取り組みMINIMUMS色に染め上げた、まるで風が吹き抜ける様に爽やかなアルバム。クラシカルな音楽性なだけに、ムード・ミュージックになりかねない所を、笛を取り入れたりと斬新なアレンジで、より取っ付きやすくキャッチーに仕上げその枠の中では収まらないとても魅力的な作品になっている。
-

-
MINT JULEP
Save Your Season
GOLD MUND/HELIOSとして人気のKeith Kenniffとなんと彼の奥さんのHollie Kenniffによるユニット MINT JULEP。しかしKeith Kenniffの才能たるや恐ろしい。彼のもつ独創的な世界とHollieのヴォーカルが溶け合うエレクトロ・シューゲイズ・サウンドは眼を閉じてもカラフルな世界に包まれるが如く広がっていく。フィードバック・ノイズもKeithの真骨頂と言える浮遊感のあるシンセも、Hollieの歌をまるで祝福するが如く優しく寄り添う。夫婦が故に作り出すことが出来る空気感というのもあるのだろう、緻密に作りこまれた音であるのに緊張感を伴うどころか非常にリラックスした響きを見せる。日本盤のみMOGWAI、Ulrich Schnauss、そしてHELIOSの豪華リミックスが収録されておりこれもまた三者三様の味付けがされており秀逸。歌ものシューゲイズ・サウンドに食傷気味の方も是非手にとっていただきたい作品。
-

-
The Mirraz
ぼなぺてぃっ!!!
『マジか。と つーか、E.P.』(2015年)以降、EDMサウンドを取り入れ始めたThe Mirraz。なぜ彼らがそこまでEDMに傾倒するのか正直理解できずにいたが、バンドの生々しさが前面に出た本作を聴いて何だか腑に落ちた。おそらく彼らは、快楽を上塗りし続ける人々の様子に、欲望の氾濫を観たのだろう。そしてその部分はこのバンドの核である渇望感と共鳴する。"ここじゃ死ねねぇ"という野望も、社会の枠の中で生き永らえることへの怒りも、"もっと愛してほしい"という女々しさも。ありとあらゆる欲望を原液のまま使用する全12曲はどれもむせかえるほどの高濃度。美醜もろとも"召し上がれ"と差し出すバンドの姿は、ポップでダークで、笑えるほどクールだ。
-

-
The Mirraz
しるぶぷれっ!!!
The Mirrazがメジャー・レーベルを離れ、自主レーベルからリリースする初のフル・アルバム。自主レーベルからの第1弾リリースとなった『マジか。と つーか、E.P.』でアプローチしたEDMとバンド・サウンドの融合をさらに追求した曲の数々は、海外のロック・シーンの最新トレンドを確信犯的に取り入れてきたThe Mirrazならでは。とはいえ、耳を傾けるべきはEDM云々よりもインパクトの大きなダンス・ビートとシンセ・サウンドを使い、彼らが表現しようとしているアグレッシヴなメンタリティ。リリックを迸らせる畠山承平(Vo/Gt)の舌鋒はますます鋭いものになってきた。切れ味鋭いカッティングを閃かせるギターも聴き逃せない。畠山によるリミックス・バージョン6曲を含む全18曲の大作だ。
LIVE INFO
- 2025.04.04
- 2025.04.05
- 2025.04.06
- 2025.04.07
- 2025.04.08
- 2025.04.09
- 2025.04.10
- 2025.04.11
- 2025.04.12
RELEASE INFO
- 2025.04.09
- 2025.04.15
- 2025.04.16
- 2025.04.23
- 2025.04.25
- 2025.04.26
- 2025.05.14
- 2025.05.16
- 2025.06.18
- 2025.06.25
- 2025.07.08
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号























