DISC REVIEW
ヤ
-

-
諭吉佳作/men
からだポータブル
中学生の頃に"未確認フェスティバル"で審査員特別賞を受賞、でんぱ組.incへの曲提供でも注目された2003年生まれの新世代音楽家が、本作と『放るアソート』の2作品でCDデビュー。転がるピアノの上をクリアな歌が生き物の如く跳ねる「ムーヴ」から、逆再生しているような笛の音色と掴みどころのないメロディに翻弄される「まま」で、冒頭から聴き手を没入させる。そうして無機質さと躍動感が行き来するサウンドに浸っていると、「この星にされる」では大人びた歌声に変化し、色香のある詞と共に現実味のある世界へ転換。坂元裕二の朗読劇"忘れえぬ 忘れえぬ"主題歌「はなしかたのなか」も、Corneliusからの影響が窺える、想像力を喚起させる曲で存在感充分だ。新感覚且つ心地いい音を求める貪欲なリスナーに薦めたい。
-
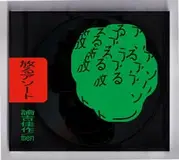
-
諭吉佳作/men
放るアソート
『からだポータブル』と同時発表する本作には、同じく10代の崎山蒼志との共作「むげん・」をはじめコラボ曲をパッケージ。2019年に公開された同曲は、都会的な雰囲気を纏いつつ一筋縄ではいかないピアノの旋律に、時折歪むギターを重ねた両者らしいサウンドと、対照的な歌声が不思議と溶け合ったナンバーだ。さらに、AFRO PARKERや、abelestとのコラボではヒップホップとの親和性にも気づかせてくれるし、長谷川白紙との1曲ではアグレッシヴな一面が、根本 凪(でんぱ組.inc/虹のコンキスタドール)や、音遊びが楽しいトラックメーカー Kabanaguとの楽曲では、天真爛漫なポップさの中に入り混じる狂気が溢れる。全曲で飛び出しまくりの諭吉佳作/menの潜在能力は、まるで底が見えない。
-

-
ユタ州
スルメ盤
結成10周年を迎える青春パンク・バンド、ユタ州の2ndフル・アルバム。Track.1「今日から俺は」で"使い古されたコードを鳴らせ/ありきたりでも言葉を絞りだせ"と歌っているように、たしかにこのバンドが鳴らす音楽には突飛な発明や目立つような飛び道具があるわけでもない。移り行く流行や真新しさに惑わされることなくバンドの芯を守り続けてきた日々の賜物だとも言えるが、どちらかというと、結局自分の感情だけをまっすぐ鳴らすことしかできなかった人たちなんじゃないかとも思う。そうやって不器用な性格を不器用なまま鳴らしている感じが良い。大多数が1等賞を獲れない世の中で、"特別じゃない自分"の存在をそのまま曝す歌に勇気づけられる人、少なくはないと思う。
-

-
ユナイテッドモンモンサン
SOS
女子を構成する"かわいい"とは結局"矛盾"のことだと思うのだが、そのリアルな"矛盾"をコミカルでポップでちょっぴり切実に描くのがこのバンドはうまい。"わからないようにわからしたい/わざとらしくなく近づきたい/聞こえないように聞こえて欲しいの"と歌うTrack.3「Base Ball Girl」に頷きたくなる女子も多いのでは? 共感できない場合も、この"もう、結局どっちだよ!"と言いたくなる感じがどうしても憎めなかったりするものだ。このバンドがそうして愛されていく未来すらも想像できる。アルバム・タイトルは"SOS"。とはいえ助けを求められたって、男子諸君は有用性あるアドバイスなど切り出さないように。結局は、親身になって寄り添ってくれるあなたが欲しいだけなのです。
-

-
ユナイテッドモンモンサン
フォスフォレッセンス
浪速発男女ツイン・ヴォーカル4人組バンド、ユナイテッドモンモンサンがレーベルを移籍し2ndミニ・アルバムをリリース。今作は全曲松岡恭子(Vo/Key/Gt)が作詞作曲を務め、並んだタイトルは「ロンリーナイトHYPER」「少女漫画シンドローム」「干物 woman no cry」……となかなか自虐的なものも。“こうだったらいいのに! きっといつかは!”“いやいや、現実はそううまくいくもんか”なんて、理想と現実で悶々としてしまう女子の等身大の気持ちを、キャッチーなメロディと人懐こいキーボード、パンク畑で培ったパワフルなサウンドがポップに弾ける。「恋のファンタジー」「KISS/KISS/KISS」は自虐とは真逆に、恥ずかしくなるほど恋する気持ちが爆発。リアルな乙女心がぎゅっと詰まった7曲だ。
-

-
ユニコーン
勤労ロードショー~ LIVE IN JAPAN ~
再結成がこんなに盛り上がったバンドもそうそういないだろう。僕は好運な事に今年の夏フェスでユニコーンを2回観ることができた。2回ともかなりの盛り上がりであったが、ニュー・アルバム・リリースもあり再結成ライヴによくある懐かしさだけで胸一杯になる事もなく、とても清々しいものであった。個人的に09年の夏の思い出の1曲を挙げろと言われたら「Hello」になるかもしれない。このアルバムはその夏の素敵なドキュメント作品だ。ユニコーンツアー2009蘇える勤労から夏フェス、そして最新の大阪城ホールのライヴまでをCD2枚で網羅。やはり奥田民生の存在感は飛び抜けているが、メンバー全員が揃った時のライヴ感をこのアルバムではしっかりと感じる事が出来る。まだまだユニコーンを未体験という方はこのアルバムから入ってみてはいかが。
-

-
ユニコーン
半世紀少年
いやあ、元気過ぎですよ、ユニコーン。精力的に動き回った2009年のユニコーンから届いた川西幸一生誕50周年記念のニュー・シングル「半世紀少年」。タイトルからしてユニコーン節炸裂だが、タイトルそのまんまの弾けっぷり。ブリブリのビートも、川西幸一本人のラップも、ベートーベンをサンプリングしたサビも、微妙に広島弁で韻を踏んでいるところも、何をやってもやっぱり、ユニコーン色。カップリングの「川西五○数え唄」に至っては、もう「この人達には敵わんなー」と苦笑するしかない。悪ふざけと言えばそれまでだけど、大人にしか(いや、ユニコーンにしか)できないふざけ方だし、これがアリになってしまうのも、ユニコーンならでは。こういうふざけ方を楽しめる50歳になりたいです、先輩。
-

-
ユニコーン
シャンブル
あまりにも唐突に、しかも、何事もなかったかのように、16年ぶりの再結成、新作発表をしてしまったユニコーン。等身大の苛立ちや感情を、包み隠さず、独自のユーモアで笑い飛ばす、無力で無敵なエンターテイメント。ユニコーンのロックンロールは、つまりそういうものだった。そんな当時のユニコーンを求めるファンには、今作に物足りなさを覚える人もいるだろう。ユニコーンらしい勢いを感じさせる曲は、シングル「WAO!」や「BLACKTIGER」など、数えるほど。だが、この人達は今も等身大だ。歳を重ね、おっさんになった。息も続かねえ。でも、彼らはそうした事実すら、楽しんでいる。そして、楽しんでもらおうとしている。ユニコーンは、今もロックンロール馬鹿のままだ。良くも悪くも、それでOKだと個人的には思う。この人達が無理して頑張ったりしたら、そっちの方が嘘くさい。
-

-
ユビキタス
ジレンマとカタルシス
"夜"をテーマにした前作から約2ヶ月半というインターバルでリリースされる4thミニ・アルバムは"昼"をテーマに制作。メンバー3人の出す音とメロディで魅せる楽曲が多く、これまで以上に彼らのルーツが色濃く出ている。制作期間中のヤスキ(Vo/Gt)の辿ったメンタリティが素直に反映されているのも特徴的で、楽曲が生まれた順と曲順はほぼ同じ。ラストの「カタルシス」はサウンドにも歌詞にも新しい気づきを得た多幸感や力強さが漲った曲になった。「R」の詞にあるように"今日から何か変わりそう"という予感を十二分に感じられる。1年間で2枚のミニ・アルバムを制作したことで、バンドがひと回りもふた回りも骨太になったのでは。ジレンマからカタルシスへ移りゆくリアル・ドラマを堪能してほしい。
-

-
ユビキタス
孤独な夜とシンフォニー
独りの夜に――余計なことを考えてしまったり、心の奥にしまい込んでいた気持ちがこみ上げてしまったり。どうにも感情がコントロールできないなんて経験は、きっと誰にだってあるはず。今作は、そのとき対峙する様々な自己や感情によって、人は構成されている="シンフォニー"だと、人のどんな面も肯定する1枚だ。エッジー且つ重心低めのサウンドに乗せ、渦巻く葛藤を吐き出していく「サカナ」、静かな夜に聞こえる雨音や時計の秒針音を思い出させる最小限の演奏とともに、タイトルそのままの時間に溢れる思いをトレースした「眠れない夜に」など、喜怒哀楽さながらの表情を見せる全7曲。頭から駆け抜けるタッピング・ギターが、めまぐるしく展開するパレードのような世界へと連れていくラスト「ハッピーエンド」を聴けば、どんな夜も笑って許したくなるはず。
-

-
ユビキタス
記憶の中と三秒の選択
5月と7月のシングル連続リリースを経て完成した初のフル・アルバム。シングルにも収録された4曲も然ることながら、今回新録された6曲の勢いが非常に瑞々しい。リード・トラック「ヒーローのつくり方」のコードを力強いストロークで刻むTHEギター・ロックな音像は逆境をも覆すヒーロー像と重なる。展開の激しい楽曲、ストリングスが優しく壮大に響くミディアム・ナンバー、リフレインを取り入れた縦ノリのダンス・ロック、ファンクの匂いがあるポップ・ソングなど、好奇心の赴くままに様々な音楽性を楽しんでいるようだ。ベースとドラムも骨が太くなり、バンドへの想いが率直に綴られた歌詞をまっすぐ歌うヴォーカルも頼もしい。新しい面と懐かしい面が収録された全10曲、すべてに共通するのは音楽に対する純粋な感情だ。
-

-
ユビキタス
透明人間
今年5月のシングル『空の距離、消えた声』に続いてリリースされる、ユビキタスのTOWER RECORDS限定3曲入りワンコイン・シングル。フロントマンの黒田保輝曰くバンドが"結成したときのモードに戻ってきた"とのことで、その言葉の通り音が隅々まで澄み渡っている。だが彼らは全国デビューしてからの約1年半でミニ・アルバム2枚とシングル1枚を制作するという逞しさを持つバンド。音の空白を効果的に使ったアンサンブルや、1音1音丁寧に鳴らされるフレーズなど、積み重ねてきた経験があってこそのサウンドとメロディと歌詞だ。表題曲はファルセットで歌われるサビの抜けが心地良く、ロックに攻めるTrack.2、爽やかなアップテンポ曲Track.3と、全曲でバンドのネクスト・ステージを感じられる。
-

-
ユビキタス
空の距離、消えた声
順調にリリースとライヴを重ね、じわじわと人気を伸ばしている大阪の3人組ロック・バンドが2作連続でリリースするTOWER RECORDS限定シングルの第1弾。切なさが感じられる3曲は、どれもユビキタスらしいと思えるものの、2月のツアー・ファイナルで披露した表題曲のストレート且つシンプルなアレンジにちょっとびっくり。より多くの人に届けたい、いや、届けられるという自信があるからこその直球勝負。その他、ダンサブルなリズムを忍ばせたミッドテンポの「ガタンゴトン」、ライヴの人気曲「足跡」の再録バージョンを収録。その「足跡」は3人それぞれに個性を主張しあう熱度満点のアンサンブルが聴きどころ。ライヴの盛り上がりが頭の中で想像できるような仕上がりになっているところがいい。
-

-
ユビキタス
奇跡に触れる2つの約束
前作から9ヶ月でリリースする2ndミニ・アルバム。楽曲そのものは人と人との繋がりや、繋がることで起こるあれこれを歌った等身大のギター・ロックながら、ひねりをきかせたクセのある演奏がこの大阪の3人組の個性を際立たせている。ダンサブルなところもあるプッシュ曲の「パラレルワード」など、歌ものといえる曲がある一方で、ライヴ・バンドとしての緊張感をアピールする「アマノジャク」のような曲もあれば、グルーヴや跳ねるリズムを意識した「飛行機雲」「拝啓、日曜日」という新境地を思わせる曲もあって、曲調はなかなか幅広い。ポップな作品をイメージしながら、"ポップなだけでは終わらさんぞ"と思ったメンバーの意欲をいろいろな形で感じられるところが今回の1番の聴きどころだ。
-

-
ユビキタス
リアクタンスの法則
2012年10月に結成という若いバンドでありながら、DIRTY OLD MENやBLUE ENCOUNTなどとの競演も果たす、大阪を拠点に活動中の3ピース・ロック・バンド、ユビキタス初の全国流通盤。シンプルでソリッドとキャッチーが同居する歌ものバンド・サウンドに、等身大の心情吐露とリアリティのある歌詞――典型的なギター・ロック・バンドとも言える。そんな彼らの光るセンスとは、歌詞世界とアレンジが密接なところ。10年代の主流となりつつあるラウド寄りなキメが盛り込まれたサウンド・メイクの「SNS」、情景がドラマティックに移り変わる「この世とあの世」、J-POP的な展開を見せるミディアム・ナンバー「再生」など、歌を汲んだアレンジはリスナーへ明快かつユーモラスにイメージを運ぶ。
-

-
指先ノハク
フルレンジ
2ndミニ・アルバムとなる本作は、サウンド・プロデュースを坂本夏樹(ex-チリヌルヲワカ / She Her Her Hers)が担当し、エンジニアとしてASIAN KUNG-FU GENERATIONや空想委員会などを手掛けた古賀健一が参加。それもあってか前作よりもかなり聴きやすい仕上がりになっており、わざと捻りを効かせているのではなく、天然で"出ちゃっている"ような印象。自称"変態"によるオルタナ精神はもはやバンドのスタンダードになりつつあるのだということが窺える。構築美を逸脱しながら新たな価値を探しもがくことこそがアイデンティティだと定義したのは、さらなる段階に進むための伏線なのでは? とも感じたため、気が早いが次回作にも期待したい。
-

-
指先ノハク
肴~SAKANA~
ちょっと捩れたメロディを歌い上げる凛としたヴォーカル、エフェクティヴで浮遊感のあるギター、ゴリッとしてスラップも織り交ぜる攻め気なベース、タイトで無駄がなく表情豊かなドラム。指先ノハクの4人の演奏スキルはとても高く、特に木村順子(Gt/Cho)の奇抜さスレスレの脱構築的なフレージングからは天性のオルタナ根性を感じ取ることができる。そしてそれこそがこのバンドの核となる要素だろう。とはいえ、コアでクローズな音楽に堕するのではなく、ポップを志向するバランス感覚も持ち合わせ、全編通して歌モノとして成立するキャッチーな魅力を備える。Track.1やTrack.4ではありそうでなかったひりついたポップ感とオルタナティヴさを提示し、Track.2では彼女らの掲げる変態性が結実するストレンジ・ポップを聴かせる。
-

-
ユプシロン
シニフィエ
歌声から始まる「ダイアル」は、ダイアルで喜怒哀楽を選んで"僕だけの歪なストーリー"を作り上げる興味深いナンバー。やり切れない感情が煮えたぎっているものの、ダイアルの音など遊び心も取り入れられており、メロディも開放的だ。他にも、"言葉の難しさ"という共感性の高いテーマを、様々な仕掛けを交えながら文学的に昇華した「白夜」、奔放なほど自由な「サイレントトリープ」、限界に挑戦するようなハイトーン&スピード感と"赤"というモチーフが調和した「RED」、ナチュラルな歌声で距離感が近く聴こえる「scar;prayer」と、歌詞からも曲からも進化が感じられる5曲。聴いているうちに、自分自身も"生きること"と向き合えるはずだ。全曲のインストも収録。
-

-
ユプシロン
ガタカ
少年のような少女のような、独特の歌声を持つユプシロン。さらに、その歌声を歌詞にリンクさせた繊細な表現にもこだわっている。そして、その歌詞にも様々な学問や芸術、時代からの影響が覗く。ギュッと歌詞を詰め込んで忙しなく疾走するユプシロン節が光る中で、ドラマチックで壮大な「祭壇」や、"今日は きっと記憶にも残らない/よくある一日だね"と素朴な今を慈しむような「ユビキタス」といった、違った魅力も乱反射している。トラックもバラエティに富んでおり、様々なルーツが見えてくる。バーチャル・シンガーでありながら、誰よりもリアルなシンガー・ソングライターであることを世に知らしめる1枚。
-

-
夢みるアドレセンス
メロンソーダ
新メンバーが加入し、7人体制となって2作目のシングル表題曲「メロンソーダ」は、夢アド史上最も王道と言っても過言でない、THEアイドル・チューンとなった。楽曲提供をしたのは、ハンブレッダーズのムツムロアキラ(Vo/Gt)。"ネバーエンディング思春期"を謳うハンブレッダーズと、夢みる"アドレセンス=思春期"というマッチングで、アイドルの前にひとりの女の子である7人の、甘酸っぱい青春や初々しい恋心を描いた曲だ。今回センターに抜擢されたのは、新加入の最年少メンバー、現在16歳の山下彩耶。曲に登場する女の子にもぴったりで、等身大の女子の気持ちを(ムツムロによる男子目線の妄想シチュエーションも込みで)可憐に歌っている。初のドラマ仕立てとなった、山下の本気の照れ満載のMVも必見。
-

-
夢みるアドレセンス
桜
季節としてもグループとしても"始まりの春"を迎えてリリースされる『桜』......でありながら、ほんわかした曲調でも、しみじみした歌詞でもないあたりが夢アドらしい。"くるくる回って回って回る"と聴き手を巻き込むフレーズや、"白"と"赤"というメンバー・カラーが織り交ぜられたラップなど、歌詞、曲、アレンジ、振付、意味合いが幾重にも重なる複雑な構造。それでも、あくまで聴き心地がポップなのは、百戦錬磨の夢アドのセンスと、それを楽曲制作者のNAOTO(ORANGE RANGE/Gt)が理解していたが故だと思う。カップリングは、ねごとの蒼山幸子(Vo/Key)が作詞作曲を務めた「プラスチックガール」。キュートでアンニュイな曲調から、タフな夢アド像がリアルに浮かび上がってくる。
-
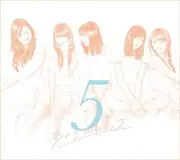
-
夢みるアドレセンス
5
首藤義勝(KEYTALK)、川谷絵音、大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、こやまたくや(ヤバイTシャツ屋さん)、オカモトショウ(OKAMOTO'S)、志磨遼平(ドレスコーズ)、真心ブラザーズ、MINMI、......まずは、楽曲提供した面々の名前に圧倒される。新進気鋭のロック・バンドのメンバーから実力派のアーティストまで、幅広く楽曲を提供してもらっているアイドルは、そうそういないのではないだろうか。そしてさらに面白いのは、これだけ個性の強い楽曲が揃っているにもかかわらず、どれも彼女たちが"夢アド色"に染め上げていること。ベスト・アルバムということで、これまでのリリースが総括されているが、それと同時に今作は、彼女たちの"ベスト"が尽くされた1枚だと思う。
-

-
優利香
Newestrong
関西で人気の朝の情報番組"おは朝(おはよう朝日です)"のテーマ・ソングに大抜擢された、神戸出身のシンガー・ソングライター 優利香、初の全国流通ミニ・アルバム。新しい1日の始まりを、清涼感溢れるサウンドで彩る"おは朝"テーマ・ソング「眩しい朝日」をはじめ、心のままに生きられない苛立ちをぶつけるギター・ロック「ハートレス人間」、柔らかな歌唱であの頃に想いを馳せる懐かしいポップ・ソング「ノスタルジーラムネ」など、楽曲ごとにまったく異なる世界を描くバラエティ豊かな全5曲を収録する。タイトルの"Newestrong"とは、"Newest(最新)"と、"Strong(強さ)"を合わせた造語。昨日よりほんの少しでも強い自分になれたら。そんな想いが通底する楽曲たちは優利香という人間そのものを表す。
-

-
ゆるふわリムーブ
綻び
"ネガティヴ・ポップ"を掲げて、広島を拠点に活動する4人組ギター・ロック・バンドの2ndミニ・アルバム。昨年6月にリリースした初の全国流通盤『芽生』が"第10回CDショップ大賞2018"の"中国ブロック賞"を受賞するなど、着実に支持層を拡大。そして今作では、王道ギター・ロックだった前作から一変、より幅広いサウンド・アプローチを取り入れた意欲作となった。テレビ新広島が企画する"全力応援プロジェクト"のために書き下ろしたリード曲「明日を鳴らせ」の他、打ち込みで制作した楽曲も収録。ふとしたことで綻ぶ人間関係を繊細な筆致で捉える「ウソヲツク」や「ブルースター」の悲しいドラマを経て、ラスト・ソング「愛の花束」が温かな余韻を残してくれる。
-

-
ゆるふわリムーブ
芽生
バンド名の由来は、"Twitterのタイムラインにたまたま流れてきたバンド名診断で出てきたものをそのまま使った"という嘘みたいな理由の広島発4ピース・バンドが、シングル表題曲3曲と過去曲の再録1曲含む全7曲入りとなる初の全国流通ミニ・アルバムをリリース。ヴォーカルはソフトでありつつも内に秘めた熱が散見し、初夏の風や緑のように清々しいサウンドはひりついたエッジーな側面も持つという、各メンバーがスタンダードなギター・ロックからはみ出した存在感を放つ。疾走感があってアッパーな楽曲もミディアム・テンポの楽曲も、感傷性が高く情熱的。ループ・ミュージック的なアプローチもアルバム内でアクセントになっており、まだまだ才能を秘めていることを予感させる、まさしく"芽生え"の作品だ。
-

-
ユレニワ
ピースの報せ
"こっちおいで"と、いきなりシンガロングへと巻き込み、"僕らは革命児"と宣言する「革命児」が1曲目という時点で、圧倒的な勝利を証明するユレニワの1stアルバム。"神も仏も殺してやる"と歌いながらも楽しいハンド・クラップが似合う「遺書」で戸惑わせたかと思いきや、緩やかに伸びやかに"ベランダに広がるネバーランドへ"と明言する「Lilac」が続く。ザクザクと響くオルタナ・サウンドには懐かしさもあるが、平均年齢21歳の彼らにとっては新鮮なのだろう。だからこそ、"ボニーとクライドになって"(「Cherie」)なんて、いくつものロック・バンドが使ってきた言葉を、狂おしいほどみずみずしく歌うことができるのだと思う。照れるほどの愛にあふれた終盤もたまらない。
-

-
あれくん
呼吸
切ない恋心を透き通った声で描き、10代を中心に話題のネット発SSW、あれくんのメジャー初アルバム。「好きにさせた癖に」は965万回、「ばーか。」は749万回と好調な再生回数を誇るが、それらすでに公開済みの楽曲は、すべてガラッとアップデートされている。チルなビート且つミニマムだけど一音一音が際立つ、トレンドを採り入れたポップ・サウンドにリアレンジされていて、海外アーティストを意識したようなあれくんのフェイクも含め、既発のバージョンを知っているとその進化に驚かされるはず。また、半数を占める新曲たちに綴られているのは、これまでの彼の代名詞=ラヴ・ソングの枠を超え、人生の葛藤に向き合った言葉たち。メジャー初作品にして現時点での集大成にとどまらず、新たな自分を切り拓いている。
-

-
夜韻-Yoin-
青く冷たく
アコースティックにポップスを奏でるネット発SSW あれくんが、オルタナティヴ・ロック・バンドのギタリスト、クラシックに出自をもつピアニストと出会い、結成した夜韻-Yoin-。そのメジャー1stミニ・アルバムは、愛する人とのすれ違いの物語を描いたノンストップ・ミックス作品だ。全編を通して相手を想う気持ちや命の儚さ、美しさが貫かれたコンセプチュアルな1枚だが、各曲のカラーは絶妙なグラデーションを描いていて、3人の素養に基づく音作りが楽しめるし、環境音も取り入れた立体的なサウンドはストーリーへの没入感も得られる。そして何より、あれくんの抜けのいい歌声は聴く者を肯定してくれる。MVや歌詞カードなど、トータルで演出された世界観に浸ってみれば、自ずと見えてくるものがあるかもしれない。
-

-
吉澤嘉代子
女優姉妹
ロックンロールやファンク、ニューミュージックにフォークなど、様々なサウンドに乗って少女たちが描く奔放な世界。2015年の1stアルバム『箒星図鑑』は、ティーンの輝きが凄まじい独創性とともに惜しげもなく放たれた衝撃作だった。あれから約3年8ヶ月。吉澤嘉代子が4枚目となるアルバムに設けたテーマは"性"、ひいては"女性"。生々しい性衝動、少女のように無邪気な大人、人間関係のわずらわしさなどが描かれた10の物語は、『箒星図鑑』さながらのサウンドやメロディのバリエーションが魅力的でありながら、明らかに、これまでの作品にはなかった色や艶やユーモアを感じ取ることができる。より豊かに、そして深みを増した吉澤ワールドをじっくり堪能してもらいたい。
-

-
吉澤嘉代子
ミューズ
ロング・セールスを続けている2ndシングル『残ってる』を絶賛した蔦谷好位置をプロデューサーに迎えた、シンガー・ソングライター 吉澤嘉代子の3rdシングル。"人生の傷跡を肯定するような歌"という「ミューズ」は、これまでにないメッセージ性と解き放たれたようなポップな魅力が新境地を思わせるものに。ストリングスやピアノを使いながら、ダンサブルなリズムや歪ませたギターを加え、意表を突くアレンジも聴きどころだが、ある意味、ウェルメイドなアレンジがそこに収まり切らない歌声の力量、魅力を改めて際立たせているところに耳を傾けたい。カップリングの「おとぎ話のように」は南波志帆に提供した曲のセルフ・カバー。グルーヴィな演奏とともに「ミューズ」以上に奔放な歌声の魅力を味わえる。
-

-
吉田健児
forthemorningafter
久しぶりにシンガー・ソングライターのロック・アルバムを聴いた、そんなざっくりした印象を持つアルバム。ルーツにカントリー・ブルースやフォークを持ちながら、90年代オルタナティヴ的な質感が加えられたのは、プロデューサーの西原誠(ex-GRAPEVINE)のセンスによるところが大きいのだろう。一見、社会や現実に対して疑問を呈しているように聞こえるTrack.1も、実は雑多な街を見下ろして、自分が知らない人のために涙を流せるのか? と静かに気持ちを反芻しているようだし、Track.4やTrack.5はとても寂しがり屋な側面が情景とともに立ち上がったりする。つまり音がロックでも感覚としてとても柔らかいのだ。独特なギターで映像喚起力を高める西川弘剛(GRAPEVINE)のアレンジのセンスも味わえる。
-

-
吉田ヨウヘイgroup
paradise lost, it begins
管楽器と女声コーラスを巧みに取り入れ、"和製DIRTY PROJECTORS"と評される男女6人組、"吉田ヨウヘイgroup"。傑作と呼ぶに相応しい前作『Smart Citizen』で見せたポップネスはその純度を保ったままに、ジャズ、ソウル、ファンク、エクスペリメンタル、オルタナティヴなど様々な音楽を取り込み、超高密度に"吉田ヨウヘイgroupの音"として音像化することが今作では試みられている。そういった意味では、極めて実験的/冒険的と言えるし、リズムやグルーヴの面では肉体性が増した"ロック的"な作品と位置づけることもできるだろう。そして移り気な現在の音楽シーンにおいても、単に消費されるだけに甘んじない圧倒的な強度と存在感を放つ。何度聴いてもその全容を掴みきれない、音楽的好奇心をくすぐられる1枚。
-

-
ヨソハヨソ
neandertharloid
2008年から活動する、ツイン・ギター&ツイン・ドラム、ベースの5人編成による東京発インスト・ロック・バンド、ヨソハヨソの1stミニ・アルバムがついに完成。LITEなどプログレッシヴでテクニカルなポスト・ロック・バンドの匂いを持ちつつも、随所で変態臭を撒き散らし、31GやIPECAC RECORDINGSあたりのバンドに通じる平然とバカをやる感覚は、奇天烈轟音好きにはたまらないものがあるだろう。が、そんなニッチな音楽偏愛に寄せているというわけでも、それを狙っているわけでもなく、この小節にどれだけ面白いものを詰め込めるか、1曲をどう面白く、飽きさせずに展開するか、そして瞬発力や閃きで生まれた高い熱量をどう運転していくか、という細かなディテールを丁寧に織り上げたゆえの、ピュアなエネルギーを感じる。
-

-
米津玄師
STRAY SHEEP
アルバムとしては実に2年9ヶ月ぶりとなる『STRAY SHEEP』。破格の大ヒットを記録した「Lemon」をはじめ、既発シングル「Flamingo」、「馬と鹿」や、楽曲提供でも話題になった「パプリカ」、「まちがいさがし」のセルフ・カバーを含む全15曲を収録。小中学生ユニット Foorinの天真爛漫な歌声が印象的な「パプリカ」だが、歌い手が変われば当然思い描く情景もガラリと変わり、そのことは楽曲の持つ多面的な魅力を何より表している。また、軽妙なサウンドとビートに刹那的で危うい雰囲気を同居させた新曲「感電」は彼の真骨頂。それらをひとつにパッケージした今作は、近年いかに米津玄師がポップ・カルチャーのど真ん中にいたかという事実と、その所以を改めて体験できる超大作だ。
-

-
米津玄師
orion
自分と相手を星座になぞらえ、切れない関係を願う「orion」は紛れもなく闘いの歌だ。落ち着いたテンポのなか決められた拍に鳴るピアノの和音やフィンガー・スナップ、その上に乗る伸びやかな歌声は、あたたかな場所を離れ戦地へ赴く人の凛とした意思そのもの。TVアニメ"3月のライオン"EDテーマの同曲は主人公のプロ棋士少年・桐山 零とリンクしているが、孤高のクリエイターである米津自身も零と似た闇を抱えているのでは。"痛みも孤独も全て お前になんかやるもんか"と敗北の女神へ吐き捨てる「ララバイさよなら」、険しい旅路をとことん軽やかに描く「翡翠の狼」も含む3曲を貫くのは、人は結局ひとりだが独りきりでは生きられない、だからこそ強くなることができる、という真理だ。
-

-
米津玄師
Flowerwall
人気ボカロP"ハチ"こと......なんて飾り言葉も不要なほど、米津玄師という名義も定着してきた。昨年、初のワンマン・ライヴを開催し、新境地へと踏み出した彼の3rdシングルは、壮大なサウンドスケープ広がる幻想的なナンバー。独特な言葉選びのセンスはそのままに、登場人物の感情がより鮮明に描き出され、"僕"と"君"が共に手を取り前へ進もうとする様子が目に浮かぶ。"フラワーウォール"="色とりどりの花でできた壁"―― 目の前に立ちふさがる壁がそう見えるのは"君"とふたりだからだろう。目の前にどんな困難があろうとも"君"と一緒なら笑いあえる、そんな希望に満ちた楽曲だ。フォーク・ロックの要素を含んだ「懺悔の街」、ダウン・ビートに乗せて虚無感を歌った「ペトリコール」と、カップリング2曲もそれぞれ米津ワールド全開。
-

-
米津玄師
diorama
正直に自分のスタンスを表すると、VOCALOIDは門外漢だ。そのコミュニティで盛り上がるニコニコもmixiもアカウントは持っていない。まぁ、頭の固いおっさんなわけで......。あ、オタク嫌悪はないので。それでも"初音ミク"なんて言葉は自然と聞こえてくる時代だし、動画の総再生回数が2000万回を超えるなんて、純粋にすごいことだなぁ、と。そこでこの人気ボカロP"ハチ"こと米津玄師のアルバム『diorama』だ。真新しさはないが、ロック・テイストで丹念に練られたメロディ・ラインに言葉遊び的語呂の良さはキャッチーで、多くの支持は納得できる。しかし現状のネット発という注目は挨拶として、彼のブログから引用すると"疑心と矜持を携えて何処かへ行きたい"という世界を見てみたい。願わくば、既存の価値観を壊した場所へ。
-

-
余命百年
二十二世紀からの手紙
ディスクユニオンおよびライヴ会場限定で発売された同名アルバムに、新録曲を追加して全国リリース。"余命百年"というバンド名にしろ、"二十二世紀からの手紙"というタイトルにしろ、永遠と儚さ、過去と未来が混在しているが、浮遊感のあるサウンドにも同様の印象が。聴き進めるほど方向感覚が失われていくような感覚。密かな昂揚感。フォーク・ミュージックからニュー・ウェイヴ、サイケ・ポップなど多数のジャンルが、時間軸も国籍の境界も関係なくゆったりと溶け合うサウンドこそ、不思議な魅力の根源であろう。正直8曲だけではこのバンドの内側に広がる宇宙を暴ききれていない。それでも未知だからこそ何だか気になるし、面白いバンドが現れたのだということだけはハッキリわかった。
-

-
ヨルシカ
創作
『エルマ』以降、日記帳や小説付きの大作が続いたヨルシカだが、2021年第1弾リリースとなる『創作』は初となる5曲入りEP。全体を通してアコースティックな手触りを大切にした温かなアプローチが印象的だ。季節の移ろいを風流に描いた「春泥棒」、鳥がさえずるインスト曲「創作」からつなぎ、打ち込みと牧歌的なサウンドが溶け合うミディアム・テンポ「風を食む」、カントリー調のアプローチも取り入れ、幻想的な夜を描いた「嘘月」など、新境地と言える楽曲が並ぶ。ヨルシカと言えば、夏の曲が多いイメージも強いが、今作は春の曲ばかり。それも春の終わり際の儚さに主眼を置いた。これはいいことも悪いことにも、必ず終わりが訪れるという、ひとつの暗喩だろうか。彼らの音楽はいつも深読みをしてしまう。
-

-
ヨルシカ
だから僕は音楽を辞めた
これまで緻密に作り込んだ2枚のミニ・アルバムで、リスナーを"ここではないどこかの物語"へと誘ってきたヨルシカが、"音楽を辞めた青年"を主人公にした初のフル・アルバム『だから僕は音楽を辞めた』を完成させた。できれば、今作は初回生産限定盤を手に取ってほしい。音楽を辞めることを決意した青年が"エルマ"に宛てた全14曲の楽曲に加えて、オスカー・ワイルド、ヘンリー・ダーガー、松尾芭蕉ら、偉大な芸術家たちの言葉を引き合いに出して綴られる"手紙"が今作への理解を深めてくれる。"音楽を辞めた"というセンセーショナルなモチーフをテーマにすることで、コンポーザー n-bunaが抱く思想や哲学を徹底的に炙り出し、ひいては"音楽をやる理由"が浮き彫りになる構造が秀逸。
LIVE INFO
- 2025.04.04
- 2025.04.05
- 2025.04.06
- 2025.04.07
- 2025.04.08
- 2025.04.09
- 2025.04.10
- 2025.04.11
- 2025.04.12
RELEASE INFO
- 2025.04.09
- 2025.04.15
- 2025.04.16
- 2025.04.23
- 2025.04.25
- 2025.04.26
- 2025.05.14
- 2025.05.16
- 2025.06.18
- 2025.06.25
- 2025.07.08
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号























