DISC REVIEW
-

-
X AMBASSADORS
Townie
1stアルバム『VHS』がヒットし、近年ではKYGOとのコラボやハリウッド映画への楽曲提供など精力的に活動するX AMBASSADORSの4thアルバム。フロントマンSam Harrisの故郷であるニューヨーク州イサカでの日々を愛とともに振り返る作品で、通底するアコースティックを主体とした素朴なサウンドが郷愁を誘う。街外れのガソリンスタンドでの複雑な想いを描いた「Sunoco」、亡き恩師がくれた言葉を嚙みしめるように歌い上げる「Your Town」、兄と家族の絆をエモーショナルに綴る「Follow The Sound Of My Voice」などパーソナルな内容だが、Samの誠実な歌声はリスナーの故郷に想いを馳せたくなるような共感を生むことだろう。現在のバンド像への橋渡しとなる「No Strings」の爽快感も見事。
-

-
JUSTICE
Hyperdrama
フレンチ・ハウスの革命児、JUSTICEが前作『Woman』(2016年)から約8年の歳月を経て本格的にシーンにカムバック。今作は、TAME IMPALAやTHUNDERCAT、MIGUELなど、幅広いアーティストをフィーチャーし、多彩な音楽表現に挑戦した意欲作。クラシカルなディスコ風のプリミティヴな楽曲が目立った前作とは一変して、今作はよりモダンで重厚感のあるサウンド、曲調はエモーショナル、それでいてファンキーという、より自由度の高い作品となった。3年前にGaspard Augéがソロ作をリリースしていることもあり、この数年の間、JUSTICEが停滞していたのではなく、本作に向けて様々な挑戦と成熟の期間が持たれていたということだろう。改めて彼らの創造性に驚かされるアルバムだ。
-

-
Liam Gallagher & John Squire
Liam Gallagher & John Squire
元OASISのヴォーカリストと元THE STONE ROSESのギタリストというUKロック好きならずともロック・レジェンドふたりのコラボにときめきを禁じ得ない音楽ファンは多いだろう。が、それ以上にやはりティーンエイジャーの頃、THE STONE ROSESの音楽に刺激を受けたLiamがJohnのソングライトを自分なりに解釈して歌っている原点回帰のムードがいい。仕上がりもラフなセッション・レコーディングっぽいし、且つ音数を絞ったモダンな聴感で、どこか時代を超越している。サイケデリックで中期のTHE BEATLESを彷彿させる「Just Another Rainbow」、コードやリフはどブルースでありつつ、削ぎ落とした音像の「I'm A Wheel」、ブギーなギター・リフや音色にJohnの色気が自ずと漏れる「Mars To Liverpool」など、聴くほどに味わいを増す1枚。
Warning: Undefined array key "$shopdata" in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/list/266265.php on line 27
-
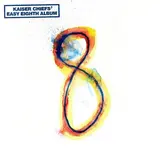
-
KAISER CHIEFS
Kaiser Chiefs' Easy Eighth Album
20年を超えるキャリアを持ちつつ軽快に新しいサウンドにチャレンジするあたりにアフター・ブリットポップのバンドの中でもユニークな色を見てしまうこのバンド。約5年ぶりのアルバムはNile Rodgersと共作したオープナー「Feeling Alright」や「How 2 Dance」にバンドのオリジンと、Nileのファンキーなカッティングが同居して違和感なし。また、本作はSam Smith、Ed Sheeran、CHARLI XCXらを手掛けるAmir Amorがプロデューサーを務めており、「The Job Centre Shuffle」は初期のニュアンスとシンセ・サウンドの出会いが楽しいし、ディスコ・ファンクとディスコ・パンクの中間点っぽい「Sentimental Love Songs」、哀愁メロもキャッチーな「Noel Groove」もいい。いい意味で重鎮化しないUKロックのひとつのモデル。
-

-
THE LIBERTINES
All Quiet On The Eastern Esplanade
THE STROKESやTHE WHITE STRIPESらと共に2000年代初頭のガレージ・ロック・リヴァイヴァル・ムーヴメントを支えた最重要バンドのひとつであり、2000年代UKロックのアイコンとしてロック史に名を残してきたTHE LIBERTINES。デビュー当時はかなり尖った印象だった彼らも20年の歳月を経て"なんだか少し丸くなったなぁ"と感慨深くなる作品だ。壊れそうな何かを内包した危うい魅力は落ち着いてしまったが、やはりこのバンドには他にないカリスマ性がある。王道なギター・ロックでありながら詩的で繊細なサウンドで、Peter DohertyとCarl Barâtふたりのフロントマンによるヴォーカルも楽曲ごとに違った顔を覗かせ、ファンを喜ばせてくれる。彼らがまだまだやれると証明した作品。
-

-
THE SNUTS
Millennials
今最も勢いのあるUKロック・バンドのひとつ、THE SNUTS。昨年の"サマソニ"での来日公演も好評だった彼らが、再び帰ってくる。この3rdアルバムを引っ提げての単独来日公演は、チケット発売から間もなく東京公演が即ソールド・アウトというのだから、ほんとに強い。本作は、そんなTHE SNUTSの人気を裏づける、彼らの魅力がギュッと凝縮されたようなアルバムだ。ほんのりノスタルジックな響きを持ったポップ・サウンドは、タイトル通りまさに"ミレニアル世代"を象徴する、ローテクとデジタル・ネイティヴの中間を浮遊する絶妙なセンスの良さを見せつけてくれる。そして、これまでよりも青春のキラキラした部分だけを掬い取ったように甘酸っぱく、不可侵な純粋さをリスナーに味わわせてくれる作品となった。
-

-
BLEACHERS
Bleachers
FUN.のギタリストで、近年はTaylor Swiftなどの作品を手掛け、グラミー賞計10度の受賞経歴を持つソングライター/プロデューサーとしても活動するJack Antonoff。彼のソロ・プロジェクト BLEACHERSが、Dirty Hit移籍作として発表したのが本アルバムだ。同郷のBruce Springsteenへの敬慕を忍ばせつつ、切なくも明るくソウルフルにまとめ上げられたサウンドは彼の過去/現在/未来を反映しており、セルフタイトルを掲げるに相応しい仕上がりに。LANA DEL REY、CLAIROなどのゲストも深みを与えている。出演が決定している"SUMMER SONIC 2024"でも、本作の楽曲が観客と一体となる瞬間を生み出してくれそうだ。
-

-
THE VACCINES
Pick-Up Full Of Pink Carnations
アルバム名は間違って記憶していたDon McLeanの「American Pie」の歌詞に由来するそうだが、喪失を歌った名曲をタイトルに用いたことは本作にとって最適だったと言える。創設メンバー Freddie Cowan(Gt)の脱退を経たTHE VACCINES通算6作目のアルバムは、ノスタルジックなギター・サウンドと切ないメロディで夢の終焉や失恋などの喪失感を描きながら、それらを乗り越え日々を生きていくための前向きさにも満ちた楽曲が並んでいる。キャッチーを発揮したTrack.4、甘酸っぱいメロディで失恋を歌うTrack.6、キーボードが哀愁を誘うTrack.9など、珠玉のポップ・ソングが満載で、これから訪れる出会いと別れの季節にも寄り添ってくれることだろう。
-

-
BOYGENIUS
The Record
グラミー賞3部門を受賞したBOYGENIUSのデビュー・アルバム。それぞれソロでも活躍するJulien Baker、Phoebe Bridgers、Lucy Dacusという才能豊かな女性アーティストが集結し、見事な化学反応を起こした今作は、デビュー・アルバムながらある種の落ち着きや完成度を感じさせる、しなやかで強固な意志の集合体だ。親しみやすいソフトなインディ・ロックから、90年代初期エモのような内に秘めた激しさを感じる楽曲まで、多彩なアプローチでそれぞれの個性的な世界観を生かしつつ、楽曲ごとに浮いた感じもしないという絶妙な仕上がりを見せてくれている。メッセージ性の強いファッションを披露したかと思えば、少女のような素朴さも見せる不思議なこの3人組からまだしばらくは目が離せない。
-

-
DEAD POET SOCIETY
Fission
デビュー・アルバム『-!-』(2021年)が高く評価されたオルタナティヴ・ロック・バンドの2ndアルバム。名門バークリー音楽大学在学中に結成し、今はロサンゼルスを拠点に活躍している彼らは、"死せる詩人の会"というバンド名がしっくりくる、詩的でインテリジェントな魅力を持ったバンドだ。激しいサウンドを鳴らしながらも緻密で芸術性の高い音作りを感じる曲の数々。荒々しいギターと、高音のファルセットも用いた繊細なヴォーカルの対比も心地よい。本作はインダストリアル・ロックやガレージ・ロック・テイストのダークな響きを持った楽曲もあれば、COLDPLAYのようなスタジアム・ロックの爽やかなスケール感を持った楽曲もあり、才能豊かなバンドの有り余る表現欲を浴びるように楽しめるアルバム。
-

-
KULA SHAKER
Natural Magick
今作は、再結成時に参加できなかったオリジナル・メンバー Jay Darlington(Org/Key)の、実に25年ぶりの復帰作ということで話題となっているが、注目したいのはなんと言ってもそのエネルギッシュなサウンドだ。ライヴ・パフォーマンスを意識したキャッチーな踊れるサウンド、ボリウッドのノリとサイケ・ロックのグルーヴ感、アーティスティックでユーモアのあるスパイス的要素、シンプルにやりたいことが凝縮されたコンパクトな仕上がり、そのすべてが絶妙に調和している。青春時代を一緒に過ごして、人生と音楽経験を共に積み上げてきたメンバーたちが、その再会を喜び合うように共鳴し作り上げられたサウンド。感動すら覚える、この祝福されたサウンドはぜひライヴでも体感すべきだろう。
-

-
MGMT
Loss Of Life
MGMTが、約6年ぶり5枚目となる新作を発表した。原点回帰を果たした前作『Little Dark Age』は表題曲がTikTokで人気を集め、新たな層からの支持も得つつある彼らだが、本作では新たなフェーズのポップへの探求へと歩み出したようだ。前半ではOASISを彷彿させるギター・ロックのTrack.2、女性Voとのハーモニーが美しいTrack.3など、バンド・サウンドを軸に普遍的なポップネスを展開。後半ではエクスペリメンタルな側面が顔を覗かせていて、サイケの海に沈みゆくようなTrack.8、グリッチ・サウンドの中で幽玄なヴォーカルが漂うTrack.10と、摩訶不思議だが温かみのある世界へと変化していく様が心地よい。大衆性と実験性を高次元で両立させた意欲作だ。
-

-
THE KILLERS
Rebel Diamonds
THE KILLERSのデビュー作『Hot Fuss』からなんと今年で20年。日本でもクラブ・ヒットした「Mr. Brightside」や「Somebody Told Me」など、すこぶるキャッチーな名曲を収録した同作を聴いて、彼らが一発屋になるんじゃないかと心配した方も多いんじゃなかろうか。ところが彼らはその後20年近く、順調に質を落とさぬポップさと、玄人好みのインディー感も併せ持った不思議な魅力でヒットを飛ばし続けた。このベスト盤は、そんな彼らのすべてのアルバムから、それぞれの作品を代表する粒揃いのダイヤモンドのように煌びやかな楽曲を集めた、美しいジュエリー・ボックスのような1枚。新曲3曲も、懐かしさのあるシンセと伸びやかなメロディが響く、新たなフェス・アンセムとして定着しそうな、これまた名曲だ。
-

-
POP MARSHAL
Rejoice!
2022年、その活動にひと区切りをつけたHEADSPARKS。来日ツアーを行うなど、ここ日本でもUKメロディック・ファンの間で愛されていたそのバンドのメンバーが、POP MARSHALとして再始動。メンバーを変えると、長年愛されたバンドから印象を変えることを目指すバンドも多いが、彼らはあくまで自分たちが積み上げてきたものを上手く生かし、ファンの期待に応えるものを作り上げた。特に、中心メンバーのAndy Barnardは、90年代から様々なバンドでシーンを支えてきた実力派だけあって、安定したメロディメーカーとしての才能を存分に発揮している。耳に残るギター・フレーズ、口ずさみやすいメロディ、ワクワクするようなテンションのリズム、これぞ愛すべきメロディック・パンクだ。
-

-
TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS
Ballad Of A Misspent Youth
70年代のグラマラスなロックを継承した"遅れて来たロック・スター"ことTuk Smith率いるTUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS。MÖTLEY CRÜEとDEF LEPPARDのツアー・オープニング・アクトに抜擢(コロナ禍で開催は実現せず)されるなど、結成当初から注目の実力派だ。男臭いハード・ロックではなく、青春してる爽やかさがあって、聴く人を選ばない。懐古主義的ノスタルジックな魅力だけでなく、エネルギッシュなロックの魅力に気づいたMÅNESKIN以降の若いロック・リスナーにもリーチするフレッシュなサウンドは、ライヴハウスでもスタジアムでも輝きそうな柔軟性がある。日本盤のレトロ萌えポイントは、なんと言っても懐かしい邦題("しくじった青春のバラッド")。盤で買う特別感があっていい。
-

-
PLAIN WHITE T'S
Plain White T's
2000年代エモ・シーンの重要バンド、PLAIN WHITE T'S。結成25年を超え、コンスタントにリリースも続ける彼らが、満を持してセルフ・タイトルのアルバムをリリースした。ポップ・パンク/エモ界隈からデビューしたバンドの中でも早い段階から、音楽性をそこまで変えないままポップ・シーンに順応したロックに上手くシフト・チェンジし、息の長い活動を続けてきた彼ら。今作は、そんなバンドの芯の部分が綺麗に磨かれた粒揃いのポップな楽曲が詰まったアルバムだ。エモのキュンとする切なさや、ソフト・ロックの温かなタッチ、ところどころに散りばめられたダンス・ロックの軽やかさ、それらがバランス良く作品としてまとまった、派手さはなくとも飽きが来ないという彼らの強みがとても良くわかる良作。
-

-
HEARSCAPE
Transient
フランスの女性リード・ヴォーカル&キーボード Léa Berthouxが率いるプログレッシヴ・ロック・バンド HEARSCAPEのデビュー・アルバム。RADIOHEADやMUSEといったイギリスのバンドから影響を受けているとのことで、歌詞は英語、かき鳴らす感じのギター、そしてプログレッシヴな曲調と、そのあたりのバンドのファンならばニヤニヤが止まらないようなそれっぽい雰囲気を纏っている。だが、それだけにとどまらないような、ヨーロッパっぽい不思議なおしゃれ感もあり、それに拍車を掛ける女性ヴォーカルの少々クセのある歌唱が堪らない。ピアノを効果的に使った音作りも、楽曲のドラマ性を演出していて引き込まれる要素のひとつだろう。アルバム終盤まで出し惜しみして効果的に用いられるフランス語の歌唱もセクシーでいい。
-

-
Ed Sheeran
Autumn Variations
秋をテーマに14人の物語を歌った14曲。恋に落ちる瞬間を描写しながらも哀愁漂うサウンドの「Magical」、小気味良いリズムとは裏腹に重く沈んだ心を映す歌詞が胸に迫る「Plastic Bag」、微笑ましいふたりの些細な幸せを切り取った「American Town」、別れを受け入れられず行き場を失った愛をエモーショナルに歌い上げる「Punchline」、ひとりで過ごす誕生日を切なくも軽やかなメロディに乗せ描いた「The Day I Was Born」など14のリアルなストーリーが、少し感傷的な秋の空気感を纏いパッケージされた。随所に深い悲しみを覗かせる歌詞は前作から通ずるところだが、綴られた美しい言葉たちはより文学的に。ぜひ歌詞カードを片手に聴いてほしい1枚だ。
-

-
THE NATIONAL
Laugh Track
前作『First Two Pages Of Frankenstein』と同セッション時に制作された"もうひとつの最新アルバム"。曲を作れなくなっていたというMatt Berninger(Vo)の心を壊れかけの車に喩えた、昨年リリースの「Weird Goodbyes Feat. Bon Iver」は待望のアルバム収録となった。またPhoebe Bridgersと再共演、さらにRosanne Cashが参加するなど今作もコラボが聴きどころに。「Space Invader」の後半、静寂から約3分かけてじっくりとボルテージを上げていく楽器陣のライヴ感も堪らない。そしてラストを飾るのは、8分近くに及ぶ「Smoke Detector」。キャリアを重ね、より自由に奏でられた至極のインディー・ロックを堪能してほしい。
Warning: Undefined array key "$shopdata" in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/list/259370.php on line 27
-

-
RIVAL SONS
Lightbringer
サイケでバリシブなブルース・ロックを奏でるカリフォルニアの4人組 RIVAL SONSの新作は、今年6月にリリースされた前作『Darkfighter』と対をなす1枚。今作も、彼らの過去作すべてを手掛け、彼らのサウンドを熟知したDave Cobbをプロデューサーに迎え、6曲というコンパクトな構成ながら聴き応えのあるアルバムに仕上げている。冒頭を飾る約9分という長尺のTrack.1は、バンドのルーツを掘り下げ様々な冒険に挑んだ1曲。静かなオープニングから一気に活気づく展開や、中盤の聴かせどころであるギター・ソロなど、1曲の中にもドラマがある。そのほかにもグルーヴィで重厚感のあるハード・ロッキンな楽曲、温もりを感じるメロディアスな楽曲など、一気に聴けてしまう上質なアルバム。
-

-
WILCO
Cousin
来年3月に来日公演が決定しているアメリカン・ロックを代表するバンド、WILCOから通算13作目となるスタジオ・アルバム『Cousin』が届いた。本アルバムは英ウェールズのミュージシャン Cate Le Bonをプロデューサーに迎えて制作。彼らが外部プロデューサーと組むのは6thアルバム『Sky Blue Sky』(2007年)以来とのこと。キャリアを通じて一貫された実験的な姿勢は今作でも健在で、オルタナ・カントリー・テイストのリード曲「Evicted」で見せるシンプルな音像ながらも繊細で奥深い表現力には舌を巻くばかり。Le Bonが"WILCOのすごいところは、彼らが何にでもなれること"と語っているように、WILCOというバンドの柔軟性と懐の深さを再認識させられてしまう1枚。
-

-
ANIMAL COLLECTIVE
Isn't It Now?
USインディーの中でも特に個性の塊といったサウンドを発信し続けるANIMAL COLLECTIVEが、水を得た魚のようにクリエイティヴィティを開放したニュー・アルバム。前作『Time Skiffs』は、コロナ禍もあってリモートでのレコーディングとなり、ある意味パッケージとしてきれいにまとまった感のある作品になっていたが、今作はその間くすぶっていたアイディアが一気に放出されたのだろう、64分(※輸入盤)という大作でありながらたった12日で完成したというのだから驚きだ。トロピカルでポップな楽曲と、対照的にアンビエントで実験的要素が満載の楽曲があったり、聴く者をザワつかせるニクい演出も彼ららしい。さらに約22分という長さに驚かされる「Defeat」が、意外にも聴きやすいというのも意外性だらけで面白い。
-

-
ASHNIKKO
Weedkiller
ヴィヴィットなブルー・ヘアーに、過激なリリックやダーク・ファンタジーなアートワーク、グロテスクなMVと、強烈なインパクトを放つエキセントリックな魅力で注目を集める新世代のポップ・アイコン ASHNIKKO。性的差別や男性優位な世の中への怒りを音楽を通しぶつけてきた彼女が、"環境破壊とテクノロジー"をテーマにデビュー・アルバムをリリースした。"Weedkiller(除草剤)"というワードはこのテーマを直接的に表しながらも、一方的に傷つけられた心が枯れ果てていくようなイメージも含ませ、彼女のパーソナルな怒りの根源を同時に表現。多くのゲストも参加しジャンルの枠にとどまらない自由さはあるが、荒廃した世界を想起させるダークな世界観は一貫され、作品全体でひとつの物語、ディストピアを描いている。
-

-
Liam Gallagher
Knebworth 22
ロック史に名を遺したOASISの伝説的野外ライヴ"Knebworth 1996"。その会場であるネブワース・パークを舞台に2022年に開催されたLiam Gallagherのライヴが"Knebworth 22"だ。今作は、その2日間にわたるライヴの音源をまとめた作品。昨年リリースした新作の楽曲やソロでの人気曲を中心に、OASISの名曲も織り交ぜた豪華なセットリストには、往年のファンでなくとも感動を覚えたはず。そんなオーディエンスの熱狂の歓声や大合唱が収録されているのもライヴ・アルバムである今作の楽しみのひとつ。Liamの独特な立ち姿が伝わってくるタイトル・コールや、ちょっとした煽りのセリフなど、ライヴの追体験ができるので、"サマソニ"関連の来日公演を逃した方にもおすすめ。
LIVE INFO
- 2025.10.18
- 2025.10.19
- 2025.10.24
- 2025.10.25
- 2025.10.26
- 2025.10.27
- 2025.10.28
- 2025.10.29
- 2025.10.30
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号
























