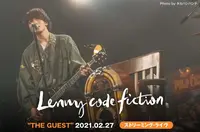LIVE REPORT
Japanese
KAKASHI presents "灯火祭2017"
Skream! マガジン 2017年10月号掲載

2017.10.28 @高崎clubFLEEZ / 高崎clubFLEEZ-Asile / 群馬SUNBURST
Writer 沖 さやこ
時代を作るのはフェスだろうか。メディアだろうか。SNSだろうか。否、時代を作るのはライヴハウスであると提言したい。時代はいまこの瞬間もライヴハウス、中でもその土地に根づいた小さいキャパシティのライヴハウスで確実に動いている。第一線で活躍するあのバンドも、世代を超えて愛されているあのバンドも、もともとはバンドにとって身近な小さなライヴハウスから始まった。もちろんライヴハウス以外にも、インターネットや路上ライヴなどからムーヴメントが起こることもある。だが、ライヴハウスは演者、観客、スタッフなど、音楽を愛するものが一堂に会する場所。狭くて暗い箱の中で音楽や想いを全身で発信し吸収し交換する、その純度や濃度の高さは抜きん出ていると言ってもいい。
"灯火祭"は群馬県前橋市出身の4人組バンド、KAKASHIが主催するサーキット・イベントで、2016年に始動した。初年度は高崎clubFLEEZと高崎clubFLEEZ-Asileで17組の熱演が繰り広げられ、2回目となる今年はさらに規模を拡大。群馬SUNBURSTを加えた全3会場に、総勢28組が出演した。
彼らは開催のきっかけを"群馬のライヴハウスのスケジュールを見て地元バンド、ツアー・バンドが減ったと感じ、このままでは群馬のライヴハウスの灯りが消えてしまうのではと思ってしまった"と話す。結成から2年ほどで拠点を東京に移し、思い入れのある地元を客観的に見ることができた若者ならではの発想だろう。群馬を離れ東京で揉まれてきたアマチュア・バンドの彼らが、群馬以外の場所で出会い、信頼関係を築いた同世代のバンドや尊敬する先輩バンドを率いて帰郷する――並々ならぬ覚悟が必要だったことは想像に難くない。
 当日午前11時30分、高崎clubFLEEZ。すでに建物の前には出演するバンドマンや、若い観客が男女多数集まっていた。会場整理をしていた人物に受付を問うと、KAKASHIのメンバーがやってきて直々に応対してくれた。灯火祭は企画、運営などすべてがKAKASHIメンバーによるDIY。メンバー全員で業務を手分けしながら当日を取り仕切っていた。
オープニング・アクトとして登場したのはハザマリツシ。ex-寸止海峡のフロントマンで、KAKASHIの堀越颯太(Vo/Gt)、中屋敷智裕(Ba/Cho)、齊藤雅弘(Gt)の専門学校の同級生でもある。オケを流して歌とラップを披露するスタイルで、フロアの真ん中に入ってパフォーマンスをしたり、フリップを使ってKAKASHIをいじりまくり、スタッフに背中を叩かれながら歌い人力オートチューンを披露するなど、たった10分に真面目におバカなステージを凝縮。観客からも笑いが絶えず、KAKASHIのメンバーもその様子をステージ袖や舞台端から微笑ましく見守っていた。そのあとの主催挨拶では中屋敷が"灯火祭は1年の集大成"と語り、齊藤は"今日来てくださったみなさんが楽しんで帰ってくれたら嬉しい"と続ける。ふたりの"灯火祭、始まります!"の掛け声とともにトップバッター・KOTORIのライヴがスタートし、とうとう灯火祭の幕が開けた。
当日午前11時30分、高崎clubFLEEZ。すでに建物の前には出演するバンドマンや、若い観客が男女多数集まっていた。会場整理をしていた人物に受付を問うと、KAKASHIのメンバーがやってきて直々に応対してくれた。灯火祭は企画、運営などすべてがKAKASHIメンバーによるDIY。メンバー全員で業務を手分けしながら当日を取り仕切っていた。
オープニング・アクトとして登場したのはハザマリツシ。ex-寸止海峡のフロントマンで、KAKASHIの堀越颯太(Vo/Gt)、中屋敷智裕(Ba/Cho)、齊藤雅弘(Gt)の専門学校の同級生でもある。オケを流して歌とラップを披露するスタイルで、フロアの真ん中に入ってパフォーマンスをしたり、フリップを使ってKAKASHIをいじりまくり、スタッフに背中を叩かれながら歌い人力オートチューンを披露するなど、たった10分に真面目におバカなステージを凝縮。観客からも笑いが絶えず、KAKASHIのメンバーもその様子をステージ袖や舞台端から微笑ましく見守っていた。そのあとの主催挨拶では中屋敷が"灯火祭は1年の集大成"と語り、齊藤は"今日来てくださったみなさんが楽しんで帰ってくれたら嬉しい"と続ける。ふたりの"灯火祭、始まります!"の掛け声とともにトップバッター・KOTORIのライヴがスタートし、とうとう灯火祭の幕が開けた。
 灯火祭は出演者すべてがKAKASHIと縁の深いアーティストたちだ。2016年に"MASH FIGHT!vol.5"のグランプリを獲得し、今年5月に初の全国流通盤をリリースしたSaucy Dogは"仲間が作るイベントは自然と気合が入る"と話す。25分で計5曲を演奏し、素朴ながらにドラマ性の高い曲展開と音作り、曲の情景を繊細に描くヴォーカルで観客を魅了した。
灯火祭は出演者すべてがKAKASHIと縁の深いアーティストたちだ。2016年に"MASH FIGHT!vol.5"のグランプリを獲得し、今年5月に初の全国流通盤をリリースしたSaucy Dogは"仲間が作るイベントは自然と気合が入る"と話す。25分で計5曲を演奏し、素朴ながらにドラマ性の高い曲展開と音作り、曲の情景を繊細に描くヴォーカルで観客を魅了した。
 そのあとすぐSUNBURSTに移動しkoboreを観に行くもすでに会場は満員で、観客はフロアの外の階段まで溢れていた。できる限り近づいてみるも入り口前までが限界。ただ音漏れを聴くだけでも夏よりもバンドの骨太度は上がっていて、スケールも大きくなっていた。伝えたいことを楽曲とMCでもってしっかりとストーリーにしたうえでハートをぶつけていく。注目度の高さに比例し、バンドも脂が乗っているようだ。
そのあとすぐSUNBURSTに移動しkoboreを観に行くもすでに会場は満員で、観客はフロアの外の階段まで溢れていた。できる限り近づいてみるも入り口前までが限界。ただ音漏れを聴くだけでも夏よりもバンドの骨太度は上がっていて、スケールも大きくなっていた。伝えたいことを楽曲とMCでもってしっかりとストーリーにしたうえでハートをぶつけていく。注目度の高さに比例し、バンドも脂が乗っているようだ。
 the ironyはリハから本番さながらの演奏。本編でも曲を颯爽と着こなすようにスマートなライヴを展開する。シンガロング、クラップ、テンポのいい曲運びと、全方位のツボを押さえたパフォーマンス。ダンス・ロック好きにも歌モノ好きにも、聴き入りたい人にも盛り上がりたい人にも対応した、まさにライヴ・シーンの盛り上がりが生んだバンドと言ってもいいだろう。華やかなステージングに観客も見惚れていた。
the ironyはリハから本番さながらの演奏。本編でも曲を颯爽と着こなすようにスマートなライヴを展開する。シンガロング、クラップ、テンポのいい曲運びと、全方位のツボを押さえたパフォーマンス。ダンス・ロック好きにも歌モノ好きにも、聴き入りたい人にも盛り上がりたい人にも対応した、まさにライヴ・シーンの盛り上がりが生んだバンドと言ってもいいだろう。華やかなステージングに観客も見惚れていた。
 再びFLEEZに戻ると、ステージにはircle。河内健悟(Vo/Gt)がしゃがれ声で"KAKASHIにもっと火つけるぞ!"と叫び、「呼吸を忘れて」、「セブンティーン」を畳み掛ける。牙を剥いて掴みかかるような彼らのパワーの源は、この先も音楽に人生を捧げる覚悟だろう。そんな彼らのステージは観客ひとりひとりに"お前はどう生きていく?"と問い掛けるようだ。生き様をぶつけるライヴは、先輩から後輩に捧げる最大のリスペクトだった。
再びFLEEZに戻ると、ステージにはircle。河内健悟(Vo/Gt)がしゃがれ声で"KAKASHIにもっと火つけるぞ!"と叫び、「呼吸を忘れて」、「セブンティーン」を畳み掛ける。牙を剥いて掴みかかるような彼らのパワーの源は、この先も音楽に人生を捧げる覚悟だろう。そんな彼らのステージは観客ひとりひとりに"お前はどう生きていく?"と問い掛けるようだ。生き様をぶつけるライヴは、先輩から後輩に捧げる最大のリスペクトだった。
 リハでライヴの定番曲「ドア」と「唄う」を演奏したWOMCADOLEは、未発表の新曲「絶望を撃て」、「月」を交えたセット・リストで攻める。この日はフロントマン/ソングライターの樋口侑希(Vo/Gt)の人間力が楽曲と演奏の核となるライヴだった。それは、トラブルで黒野滉大(Ba)の音が止まり観客の視線が彼に集中したとき、咄嗟に"そっち(※ベース側)見んじゃねぇ、俺を見ろよ!"と叫んだ樋口の言葉にも明確に表れていたと思う。喉を枯らし叫び、身体を振り絞り歌う彼も、懸命に音を鳴らし続ける楽器隊も、刹那的な美しさを放っていた。
リハでライヴの定番曲「ドア」と「唄う」を演奏したWOMCADOLEは、未発表の新曲「絶望を撃て」、「月」を交えたセット・リストで攻める。この日はフロントマン/ソングライターの樋口侑希(Vo/Gt)の人間力が楽曲と演奏の核となるライヴだった。それは、トラブルで黒野滉大(Ba)の音が止まり観客の視線が彼に集中したとき、咄嗟に"そっち(※ベース側)見んじゃねぇ、俺を見ろよ!"と叫んだ樋口の言葉にも明確に表れていたと思う。喉を枯らし叫び、身体を振り絞り歌う彼も、懸命に音を鳴らし続ける楽器隊も、刹那的な美しさを放っていた。
 FLEEZに隣接するAsileでは千葉県佐倉市出身の月がさのアクト。爆音とともに男気を叩きつける硬派なステージかと思いきや、手拍子を求めるというキャッチーな一面も持ち合わせる。"俺らの火を灯しに参りました"という言葉のとおり、同世代の仲間の祭りを最大限に盛り上げた。そして月がさと同じく佐倉市出身のHalo at 四畳半もKAKASHIの盟友。大トリのKAKASHIの前にFLEEZのステージに登場した彼らは、KAKASHIへの想いを嘘偽りなく、誤魔化さずまっすぐに語る。「シャロン」、「ステラ・ノヴァ」、「ユーフォリア」、「モールス」と、輝きを帯びた楽曲たちもこの日はさらに煌めいていた。
FLEEZに隣接するAsileでは千葉県佐倉市出身の月がさのアクト。爆音とともに男気を叩きつける硬派なステージかと思いきや、手拍子を求めるというキャッチーな一面も持ち合わせる。"俺らの火を灯しに参りました"という言葉のとおり、同世代の仲間の祭りを最大限に盛り上げた。そして月がさと同じく佐倉市出身のHalo at 四畳半もKAKASHIの盟友。大トリのKAKASHIの前にFLEEZのステージに登場した彼らは、KAKASHIへの想いを嘘偽りなく、誤魔化さずまっすぐに語る。「シャロン」、「ステラ・ノヴァ」、「ユーフォリア」、「モールス」と、輝きを帯びた楽曲たちもこの日はさらに煌めいていた。

27組のライヴが終わり、20時を過ぎとうとうKAKASHIの出番がやってきた。"新しい時代を作りにきました、全速力でやろうぜ!"と堀越が叫び、溜め込んだ力を放出させるように「失くせないから」、「流星の中で」を届ける。KAKASHIは4人が一丸となって音を発するバンド。中でも関 佑介のパンキッシュなドラミングは弦楽器隊の発射隊のようだ。両脇の舞台袖からは出演者たちが彼らに熱視線を向けていた。「灯京」は堀越が歌詞を噛みしめて歌い、そこに想いを重ねるように3人が音を重ねていく。群馬随一のライヴハウスであるFLEEZで聴く「灯京」は、東京で音楽を続けていくという強さや決意はもちろん、東京で得たものをホームに持ち帰るような優しさとあたたかさが垣間見られた。
 Halo at 四畳半のMCを受けて堀越は、仲間がどんどん成功していくことを喜ばしく思うと同時に心の底から悔しかったと話す。"だけどここで止まったら何もかも終わっちまうから、腐らず、投げ出さず、折れずに、今日まで走ってきました。その先にこんな日があるなら、いままでの悔しさや、先に行く背中を見送る気持ちも悪くねぇと思った。でも現状を自分の力で変えられない自分が不甲斐なくて情けない。でも言っても始まらないから歌うんだよ"と言い「違うんじゃないか」を歌い出した。すると袖で見ていたバンドマンがステージからフロアに飛び込む。サビやアウトロで次々とバンドマンたちがダイヴし、ステージの上には笑顔を浮かべた出演者たちで溢れる――堀越は"こんな景色が見られると思ってなかった"と言っていたが、KAKASHIの"悔しい"と"音楽を諦めたくない"という人間臭い正直さが観客や同志たちを刺激し、純粋で本能的な空間を作り上げたのだろう。本編ラストの「ドラマチック」はこの日のために作られたようなお誂え向きの曲。様々な仲間の背中を見送ってきたKAKASHIが、いまは仲間たちに背中を見守られ演奏することに加え、彼らの目の前にはその音を受け取る大勢の観客がいる。それはとてもあたたかく幸せな光景であり、未来へ繋がる大きな扉を開くようなエネルギーが漲っていた。
Halo at 四畳半のMCを受けて堀越は、仲間がどんどん成功していくことを喜ばしく思うと同時に心の底から悔しかったと話す。"だけどここで止まったら何もかも終わっちまうから、腐らず、投げ出さず、折れずに、今日まで走ってきました。その先にこんな日があるなら、いままでの悔しさや、先に行く背中を見送る気持ちも悪くねぇと思った。でも現状を自分の力で変えられない自分が不甲斐なくて情けない。でも言っても始まらないから歌うんだよ"と言い「違うんじゃないか」を歌い出した。すると袖で見ていたバンドマンがステージからフロアに飛び込む。サビやアウトロで次々とバンドマンたちがダイヴし、ステージの上には笑顔を浮かべた出演者たちで溢れる――堀越は"こんな景色が見られると思ってなかった"と言っていたが、KAKASHIの"悔しい"と"音楽を諦めたくない"という人間臭い正直さが観客や同志たちを刺激し、純粋で本能的な空間を作り上げたのだろう。本編ラストの「ドラマチック」はこの日のために作られたようなお誂え向きの曲。様々な仲間の背中を見送ってきたKAKASHIが、いまは仲間たちに背中を見守られ演奏することに加え、彼らの目の前にはその音を受け取る大勢の観客がいる。それはとてもあたたかく幸せな光景であり、未来へ繋がる大きな扉を開くようなエネルギーが漲っていた。
アンコールで堀越が初の全国流通盤『ONE BY ONE』を来年1月にリリースすることを発表する。"結成から全国流通盤リリースまで5年かかった。長かった。まじで長かった、めちゃくちゃ長かったよ"と涙ぐむ彼に、しばらく拍手が鳴りやまない。"この曲を持って全国を走り回って全国制覇します"と言い、同作から「本当の事」を演奏。堀越がまっすぐ前に向かって拳を突き出すと、観客が一斉に拳を掲げた瞬間は、この日のシンボルと言っていいほどの圧巻のシーンだった。急遽決定したダブル・アンコールの「風を纏って」は出演者たちが次々とフロアにダイヴ。晴れやかな演奏で最後を華々しく飾った。
ステージを去るとき、メンバーは穏やかな表情で客席をゆっくりと見渡した。5年間という過去を振り返ったときよりも、未来への野望を語ったときよりも、いまこの瞬間を噛みしめていたあの表情が、最も柔らかくあたたかかったことが印象に残っている。この日、彼らの歴史に新しい火が灯った。この火は間違いなく、これからも続く彼らの道を照らすものになるだろう。

- 1
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/livereport/2017/12/tomoshibisai.php on line 832
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/livereport/2017/12/tomoshibisai.php on line 832
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号