DISC REVIEW
B
-

-
OKAMOTO'S
VXV
CDデビュー5周年を迎え、1月に5thアルバムをリリースしたばかりのOKAMOTO'Sによる"5.5th"アルバムは5組のアーティストとのコラボレーション作品。RIP SLYMEとはAEROSMITH & RUN-D.M.Cばりのオールド・スクールな王道ヒップホップとハード・ロック・サウンドの融合を聴かせ、スカパラとは大編成イケイケ音楽部隊と化し、Wilson PickettばりにシャウトするROYとはクロさ全開で渡り合う。タイトルと曲調から"民生愛"がビンビン感じられる「答えはMaybe」と、いずれもOKAMOTO'Sならではの、この企画を実現できる実力と各アーティストへの敬意を感じさせる内容。中でもラストの黒猫チェルシーとのデュエット「Family Song」が出色で、2組の友情を感じさせる感動的な楽曲となっている。
-

-
THE BAWDIES
LEMONADE
小さい頃から音楽が大好きで、英国や米国のリズム&ブルースやロックンロールを聴き続けてきたのだろう。彼らの楽曲を聴いたらそう思わない人はいないのではないか。それ程トラディショナルなロックンロールを追求し続け、今作もそこからは一瞬たりともぶれてはいない。シンプルでパワフルなサウンド、渋いヴォーカル、全部英語の歌詞。しかし、ただの模倣とは違うのである。古き良き音楽を昇華することにより純度を高め、現代に再構築したのが彼らだ。そして、ファンキー・ビートなTrack.2には驚かされる。ROYの歌声が日本人離れした稀有なものであることを改めて感じずにはいられない。また、Etta Jamesへの愛と尊敬の念に溢れた「TOUGH LOVER」は彼女を知らない人でも楽しめる1曲に仕上がっている。
-

-
THE BAWDIES
LOVE YOU NEED YOU feat. AI
異色コラボ? いやいや寧ろ合いすぎちゃってどうしましょう! THE BAWDIESのトレード・マークとも言えるスーツを脱いで臨んだ、ソウル・シンガーAIとのコラボ曲「LOVE YOU NEED YOU」はハンズ・クラップやメロディアスなギター・リフなどがモダンな空気を醸し出す伝統的なロックンロール。ROYとAIのパワフルなツイン・ヴォーカルは息ピッタリ。5人がのびのびと楽しんで音を出しているのが伝わってくるので、聴いてるこっちもウキウキでスキップでもしたくなってくる。Ray Charlesの名曲「HIT THE ROAD JACK」のカヴァーも秀逸。THE BAWDIESの持つエンタテインメント性、AIのシンガーとしての力量をこれでもかと見せ付ける、エネルギッシュなシングルだ。
-

-
THE BAWDIES
JUST BE COOL
THE BAWDIESの勢いは留まることを知らない。現在バンドは怒涛のツアー中、にもかかわらずまさかのニューシングルのリリース。さらにHOT、HOTと言って来たバンドがまさかの"JUST BE COOL"というタイトル。いったいどうなっているんだ!?と思いながら音源を聴いてみると、なるほど納得。ソウル・ミュージックのループ感をTHE BAWDIES流に解釈した素晴らしい楽曲に仕上がっていた。Track.2には7月5日下北沢SHELTERで行われた「THERE'S NO TURNING BACK」TOUR FINALのプレミア音源を収録。これがまたベスト盤か!?というようなTHE BAWDIESの代表曲が収録されている。どちらにせよ、内容、ヴォリュームともに申し分のない一枚。
-

-
THE BAWDIES
THERE'S NO TURNIN' BACK
前作『THIS IS MY STORY』でTHE BAWDIESがただのルーツ・バンドなどではないと提示した後で、彼らがどう進むのかと思っていたが、ここまで幅広い音楽性をパッケージしたアルバムになるとは思っていなかった。痛快なシングル「HOT DOG」のようなロックンロールから、「I WANT YOU TO THANK YOU」といった驚くほどのポップ・ソングまで、これまでのTHE BAWDIESとは違う振れ幅を披露している。しかし、インタビューでも語ってくれたように、そこには変な力みなどなく、あくまで自然体で楽しんだ結果生まれたフレッシュな感覚が詰まっている。ROY のシャウトも凄まじく、これまでのTHE BAWDIESのロックンロールというイメージをさらに強固に塗り替える一枚。
-

-
THE BAWDIES
IT'S TOO LATE
『THIS IS MY STORY』で、それまでのルーツ・ミュージックからさらに前進したTHE BAWDIES 独自のサウンドを鳴らした彼等が、メジャー・ファーストシングルとなる『IT'S TOO LATE』をリリースする。音の質感は『THIS IS MY STORY』と同じくモダンなもの。その音は、うねりをあげるギター・フレーズが印象的な痛快なロックンロール。まさに、インタビューでも語られる通り、ルーツ・ミュージックの枠組みでは説明することのできない、独自のスタイルを獲得したことをはっきりと示す楽曲だ。カップリングは、今年のツアー・ファイナルの模様を収録したライヴ・ヴァージョン。そのエネルギッシュなライヴを疑似体験できる内容となっている。
-
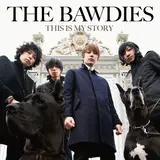
-
THE BAWDIES
This Is My Story
50~60'sのロックンロールへの憧れだけでは到底太刀打ちできない、「本物」のグルーヴに満ちたTHE BAWDIESの登場は、黒船来航さながらだった。当時のレコードから飛び出してきたかのような、ソウルフルなヴォーカルや跳ね回るリズムは、海外からスタイルだけを拝借するような日本のバンドが持つ、ある種のカッコ悪さを炙り出した。 真の意味での1stアルバムだ、とメンバーが口を揃えて語る本作は、ルーツ・ミュージックの飽くなき探求を進めてきたTHE BAWDIESが、いよいよ本格的にオリジナリティーを開拓した傑作である。モータウン的だったりモダンR&B的だったり、多様さを増した楽曲の中に見え隠れするのは、THE BAWDIESならではのポップ感覚。懐古主義なんて言葉から遠く離れた未来のポップ・シーンに、この音は鳴っている。
-

-
BBHF
Family
エレクトロやR&B、ヒップホップの影響を感じさせる配信限定EP『Mirror Mirror』と対になる、バンドのフィジカル面を打ち出した作品とも言えるが、完全に対照的でもないところが面白い。9月に先行配信した「なにもしらない」で窺えた、震えるような表現する自由や音楽に懸けて生きるしぶといほどの痛快さが、BBHFならではのジャンルのハイブリッドを生んでいることに感動する。アフリカン・リズムに乗せ生楽器のフレージングを研ぎ澄ました「花のように」にしろ、静謐且つ力強いサウンドスケープを描くなかで"水面を叩け 骨が砕けるくらい"と歌う「水面を叩け」にしろ、生きている細胞が躍動する歓喜に満ちている。しかも彼ららしい透徹した音像は世界でも無二だ。
-

-
Bird Bear Hare and Fish
Moon Boots
Kanye Westらに関わるAndrew Dawsonと、PARAMOREらを手掛けるBrian Phillipsというふたりのエンジニアの起用が象徴しているように、プログラミングと生演奏が独自のバランスで融合し、幅広い曲調の12曲へと結実。特に印象的なのは前者がミックスを担当した楽曲で、リズムマシンやサンプラーを駆使し、現代的なヒップホップやエレクトロ・ポップとリンクしながらも、最終的には日本語の歌モノに落とし込むという、このバランス感はなかなかお目にかかれるものではない。ギターのサンプリングでウォール・オブ・サウンドを作り出した「ウクライナ」と、TR-808によるトラップ風のリズム・アプローチを取り入れた「Work」が1枚のアルバムに共存するという、このクロスオーバー感は、今を生きるバンドの証明だ。
-

-
Bird Bear Hare and Fish
ライカ
尾崎雄貴(Vo/Gt)は「ライカ」について、"他とは違うギター・ロック"と語っていたが、"ギター・ロック"という言葉が、狭義のジャンルを指すことの多い現状において、僕はストレートに"ロック"と言い切りたい。アトモスフェリックな音像は現代的であり、ギターという楽器にまだまだ可能性があることを示しているものの、この躍動感はわざわざ"ギター"と冠するまでもなく、"ロック"そのものだ。一方、カップリングの「ロックフェス」にも要注目。フェスに留まらず、SNSやストリーミングなど、音楽との接し方が変化していくなかでの違和感をユーモアに包みながら表現したこの曲は、彼らがもはや閉じた世界の住人ではなく、現実と対峙する強さを身につけたことを示す意味で、重要な1曲と言える。
-

-
Bird Bear Hare and Fish
ページ/次の火
まずは元Galileo Galileiのメンバーがこうして新たな旅立ちの一歩を記したことを素直に祝福したい。尾崎雄貴(Vo/Gt)はwarbearとしてのインタビューで、以前のバンド時代について、"勝手に何かに縛られていると思い込んでいた"、"自分のキャパ以上のことをやろうとしちゃってた"と振り返っていたが、そういったプレッシャーから解放され、warbearとして自由な気持ちで音楽へと向かった結果、それと同じ気持ちで再びバンドに向かうことができるようになったのだろう。よって、この初のシングルからも気負いのようなものは一切感じられない。フレッシュなバンド・サウンドを部屋鳴りも含めたアンビエンスとともに閉じ込めた「ページ」、ゴスペルチックなコーラスがエモーションを喚起する「次の火」ともに秀逸で、早くも次のアクションが気になってしまう。
-

-
THE BEACHES
Hi Heel
元JERRY LEE PHANTOMのメンバーで構成されているものの、改名すると共に、第三国に息付くビートを取り入れながらロックとクロスオーバーさせ、カラっと乾いた南国風サウンドで、いくつものフロア・アンセムを産み出してきたTHE BEACHES。「もっとミダラに。もっとフラチに。」というキャッチフレーズが付けられた『Hi Heel』は、それまでのTHE BEACHESサウンドから明らかな変化が起きている。初期の日本の歌謡曲を彷彿とさせる妖しいメロディと不穏な音階表現が目立ち、跳ねるリズムのアッパーな縦ビートから、腰に纏わりつくような横ビートへ。THE BEACHES は常に時代の先の先を見据えているバンドだが、またしても私達の想像を遙かに超えた素晴らしい作品を届けてくれたのだ。今、日本で一番愛してやまないバンド。
-

-
BEACH HOUSE
Thank Your Lucky Stars
前作『Depression Cherry』からたった2ヶ月で届けられたボルチモア出身のドリーム・ポップ・デュオによる6枚目。スパンの短さは決してサプライズ的ではなく、創作の泉が湧き続けたゆえで、いつだって彼らは自然体だ。この2枚で無理にアプローチを変えたり、対となる要素を持たせることもなく、まるで同じ方向を向いている。ただ新たな創作の刺激となったのはVictoria Legrandが数曲ベースやギターを弾いていることだろう。前々作『Bloom』までのシンメトリーで幾何学的な美しさを持つメロディと規則正しいサウンドが、彼女の絶妙な拙さによって歪み、グルーヴが引き出されることで新たな心地良さを生む。彼らの航路は少しずつだが着実に舵を切っている。
-

-
BEACH HOUSE
Bloom
2010年の年間ベストの呼び声高い『Teen Dream』から約2年、またしてもVictoriaとAlexによるポップ・デュオBEACH HOUSEは傑作を創り上げた。儚いイマジネーションが開花した時に得られる一時の美しさを『Bloom』......花にモチーフを与え、制作された今作は、前作ほど"逃避"の様相は薄れ、だがしかし甘美で深遠ゆえの危うさの漂う、喪失感を伴った叙情性溢れる音楽。ギターのアルペジオとオルガン・ピアノが絡み合い飛翔していくかのような官能性と、Victoriaの中性的でイノセントなヴォーカルが手を組んで新たなユーフォリアを演出する。これは前作を聴いたときにも感じたことだが、黄昏時に聴くには、これ以上ないBGMなんじゃないかと思う。今作のテーマは"旅"なのだという。
-
-
BEACH HOUSE
Teen Dream
あのFLEET FOXESやGRIZZLY BEARも絶賛するボルティモア出身のドリーム・ポップ・デュオBEACH HOUSEから3rdアルバムが届けられた。本人達も自分達のクラシックが作れたと語る本作は、深くそして穏やかで、まるで森の中の優しい雨のように心が洗われる作品だ。前作リリース以降、地元ボルティモアを離れNYの教会を改造したスタジオで作った今作は完成度が高く、1つの世界観で統一されている。スライド・ギターとオルガンとフランス映画音楽の巨匠Michel Legrandの姪であるVictoriaの存在感抜群のヴォーカル。彼らはこの組み合わせだけで幻想的な世界へ僕らをどこまでも連れて行ってくれる。しかしそれは自分の中に閉じこもる様な世界ではなく、とても開放的なものだ。
-

-
BEADY EYE
Be
デビュー・アルバムとなった前作『Different Gear, Still Speeding』から約2年半、BEADY EYEから待望の2ndアルバムが届いた。TV ON THE RADIOのマルチ・プレイヤー、Dave Sitekをプロデューサーに招いた今作はどの曲も非常に音の抜けが良い。シングル曲の「Flick Of The Finger」も「Second Bite Of The Apple」も大々的にホーン・セクションが導入されているが、まったく違うキャラクターになっているところはさすがの手腕。どの曲も様々な表情でリスナーを歓迎してくれる。Noel Gallagherについて歌われている「Don't Brother Me」(訳:兄貴面するな)は愛とユーモアが込められた穏やかでキュートなナンバー。どうやらOASIS再結成を待っているのは、リスナーだけではないのかも。
-

-
BEADY EYE
Different Gear Still Speeding
2009年のNoel GallagherのOASIS脱退劇そして活動休止発表から約一年半、早くもBEADY EYEのデビュー・アルバムが届いた。「もう世界一のバンドじゃないし」その言葉が象徴するかの様に世界のあらゆるOASISファンの期待をひらりとかわしながら、またその上を行く様なフレッシュで力強いアルバムだ。60年代のブリティッシュ・ビートを基本としながら生々しいサウンドが印象的。Liam Gallagher のヴォーカルも今まで以上に深みがあり暖かい。疾走感たっぷりの攻撃的なナンバー「Four Letter Word」からの冒頭3曲で、気が付けばBEADY EYEに夢中になっている。新たにお気に入りのバンドを見つけた時の爽快感、極上のロックンロール・アルバム!
-

-
BEARINGS
Hello, It's You
カナダ発のポップ・パンク・バンド、BEARINGSの2年ぶり2枚目となるアルバム。GOOD CHARLOTTEや5 SECONDS OF SUMMERなどを手掛けたCourtney Ballardをプロデューサーに迎えた今作は、前作で披露した切なさと耳馴染みの良さを併せ持つメロディを引き継ぎながら、グッとメジャー感の増したサウンドに。イントロからポジティヴなヴァイブスを漂わせるTrack.1に始まり、80s風なシンセで甘酸っぱいフレーズを奏でるTrack.3、トラップ・ビートにアコギを絡ませたTrack.8と、挑戦的なアレンジもハマっている。ストレートに感情を乗せたラスト2曲も素晴らしく、ポップ・パンク直撃世代からエモ/オルタナ系のリスナーまでおすすめしたい1枚だ。
-

-
BEASTIE BOYS
Hot Sauce Committee Part 2
極上のラフ・ミックスみたいな仕上がり――。インタビューでメンバーが語った言葉は思いっきり頷ける。MCAの病気治療によるインターバルを経てついにリリースされる新作は、他の音源からのサンプリングで楽曲が構築されることも多いヒップホップというジャンルの中で、生音ならではのグルーヴ嗜好も色濃いビースティの真骨頂を感じる。全編で展開するサウンドの質感は、ある意味荒削り。しかし、だからこそ一聴からインパクトはもの凄い。そして、“これで踊らなかったら何で踊るの?”なんて言いたくなってしまう“どファンキー”なナンバーが並ぶ中で、「Lee Majors Come Again」はハードコア・パンク色が濃かった初期をちょっと思い出させたり……。ビースティはやっぱりビースティ、そのやんちゃ小僧っぷりは不変!
-

-
BEAT CONNECTION
The Palace Garden
THE DRUMSやHOT CHIPを送り出したことでも知られるMoshi Moshiから放たれるシアトルの強力な新人。新人といっても昨年にはEPが輸入盤で話題になっていたので知っている方も多いかもしれない。(今回の日本盤はそのEPもボーナス・トラックとして収録)。VAMPIRE WEEKENDラインの最新型といってもいいだろう。トロピカルなサウンドと華やかなシンセ・フレーズとダンス・ビート。リード・トラックで疾走感溢れる「The Palace Garden, 4am」はこれからのアンセムのひとつと成り得るだろう。ひとつひとつ耳に残るフックが満載。元々魅力的なバンドではあったがEPから一気に化けた印象。ダンス・フィールドからロック・サイドへ様々なリスナーへ届くであろう名盤。今の季節にぴったりそのままで。
-

-
BECK
Colors
3年半ぶりの新作は、グラミー賞の3部門を受賞した『Morning Phase』から一転、売れっ子プロデューサー、Greg Kurstinとともに完成させた極上のポップ・アルバム。いわゆるブルー・アイド・ソウルを、80'sっぽいきらびやかなシンセで飾り、現代的なグルーヴでバウンシーに聴かせるサウンドは、まさにモダン・ポップ職人Kurstinと組んだ成果。Bruno Marsとはまた違った形で、最新のポップスの在り方を提示することに挑んだ1枚と言ってみたい。しかし、それだけで終わらないのがBECK。ガレージ・ロックっぽいギターが鳴る「I'm So Free」、ブギウギ・ピアノが跳ねるTHE BEATLES風ポップ・ナンバー「DearLife」、ヒップホップの「Wow」といった変化球を加え、BECK印をしっかり刻み込む。
-
-
bed
ON OFF
“たいして意味無いこともあるだろう” ― そういってbedは物語を語り始めた。特徴的なツイン・ボーカルとツイン・ギターが鳴り響くサウンドの中、等身大の世界が次第にジワジワと広がりを見せる。LOATAGEやOGRE YOU ASSHOLE など、昨今非常に盛り上がりを見せている邦楽ロック・シーンにおいても、bedは特異なまでに愚直だ。情緒的に盛り上がりを見せる語り口調には、Vincent Galloに影響を受けたというのも頷ける。聴き込むほどに全身に馴染む楽曲は、大げさな装飾はなく、確実に一歩一歩踏みしめるように鳴らされている。そこには、ストイックなまでに徹底した“リアル”の追及があるのだ。様々な思いが入り乱れ、記憶が交錯する現実を堅実に語り紡ぐことで、彼らは自分と世界との繋がりを確固たらしめているのだ。
-

-
BELLE AND SEBASTIAN
Late Developers
今作は、昨年リリースされた前作『A Bit Of Previous』制作時に同時にレコーディングされていたということで、2作品は対をなすような位置づけになっているとのこと。2枚組ではなく、あえて時間を空けてリリースしたのにはいろいろ事情があるのかもしれないが、ファンにとっては嬉しいサプライズ・プレゼントとなった。地元グラスゴーでのレコーディングということで、全体的にリラックスしたトーンで描かれ、バンドが本当にやりたい音楽を詰め込んだというようなワクワク感もある。多彩な楽器の音色とお洒落なレトロ感、国際的で雑多な不思議かわいい雑貨屋さんを覗いたようなハッピーな気持ち。人生の悲哀を歌いながらもそんな人生を否定しない、聴く者の心に寄り添う姿勢が独特のポップネスとなっている。
-

-
BELLE AND SEBASTIAN
Girls In Peacetime Want To Dance
2月に行われるHostess Club Weekender出演が決定したグラスゴーの至宝BELLE AND SEBASTIANのニュー・アルバムが日本先行でリリース。オリジナルのアルバムとしては『Write About Love』以来の作品となる。うっとりと酔いしれ、また力強いアンセムとして心に深く刺さって、揺さぶっていくメロディ、歌、歌の物語を豊かに押し広げていくサウンドで、どっぷりとその世界に浸らせてくれる。そして、自分が見えているようで見てはいなかったものや、漠とした思いといったものにストーリーをもたらす。示唆に富んだその内容に、郷愁感や心強さと同じくらい感情的な痛みがぶり返すことも多いけれど、改めて青くも深みあるベルセバならではの上質なポップ・ミュージックが詰まっていて、時を忘れてしまう。
-
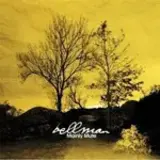
-
BELLMAN
Mainly Mute
ノルウェーのシンガー・ソングライターArne-Johan RauanのプロジェクトBELLMAN。中国や韓国のフェスティバルへの出演も決定しており、アジア圏全土で注目されている彼のデビュー・アルバムが、日本でもようやくリリースされる。北欧ならではの透明感溢れる空気が全編を通して漂っており、叙情的且つメランコリックなポップ・サウンドを主体に、時折クラシック・ロックの影響も感じさせる。すべての楽曲がどこまでも続く大自然を進んでいくようなスケール感を持っており、静かな前半から徐々に高まり後半にかけてどんどんドラマティックに展開していく様はエモーショナルで、美しい歌声も相まってとても幻想的。SIGUR ROSやMUM、KYTE等のファンは一聴の価値あり。
-

-
BENEE
Hey U X
ニュージーランド出身、Z世代の新星シンガー・ソングライター BENEEが初のアルバムをリリースした。TikTokでダンス・チャレンジ動画が投稿され世界的ブレイクのきっかけになったTrack.4は、華やかなディスコ・トラックに乗せて(失恋の)孤独を楽しく嘆く楽曲で、ロックダウン下の人々に刺さったのも納得のキラーチューン。かねてよりファンだったというGRIMESとコラボしたレイヴィなTrack.3、自粛期間中に観察していたカタツムリから着想を得たラップ・ナンバーのTrack.5、ダウナーなロック・サウンドにファルセットが心地よいTrack.8など、自由度の高い歌唱スタイルと楽曲でオルタナティヴなポップ・ワールドを展開。自身の恋愛経験に基づいた、赤裸々なリリックにも注目だ。
-

-
Ben Frost
Aurora
ここまでミニマムでクールな音のレイヤーで生々しい緊迫感を表現するインストゥルメンタリストもそうそう存在しないのではないか。再評価著しいSWANSの前作「The Seer」への参加や、Brian Enoからの依頼で映画"惑星ソラリス"に触発されたエクスペリメンタル・ミュージックを制作、またBjorkの「Desire Constellation」のリミックスなどでも知られる彼。MVも好評な「Flex」は感覚としては映画"ゼロ・グラヴィディ"劇伴の静かに迫り来る危機感を音楽へ昇華した感覚に近いが、この人の場合、どこか精神性としてインダストリアルやシューゲイズといったロックを宿している気がしてならない。中盤の1分半の暴力的なまでの轟音トラック「Secant」以外などは特に。恐怖と快楽は紙一重的な体感。
-

-
Benjamin Gibbard
Former Lives
言わずと知れたDEATH CAB FOR CUTIEのフロントマンでありソングライター、そしてPOSTALSERVICEとしても活躍するBen Gibbardの初のソロ・アルバム。今まで書き溜めていた曲を作品。前述の2つのプロジェクトとは一線を画した、牧歌的とも言えるほどに装飾を取り払ったアレンジにより“Ben”のソングライティングの能力の高さが非常に浮き彫りになっている。旧知の仲であるというEARLIMARTのAaronのスタジオで録音された本作は、全編非常にリラックスしたムードが音にもそこはかとなく漂い、聴く場所を選ばず常に寄り添える作品になっている。バンドとしての活動も楽しみだが、今後もソロとして音源の発表、そして来日を望みます!
-

-
Ben Watt
Fever Dream
1983年ネオアコの大名盤『North Marine Drive』から前作『Hendra』まで31年もの間隔があったことを思うと調子の良さがうかがえる2年ぶりのソロ3作目。前作に引き続き元SUEDEのBernard Butlerを右腕に据えている。良質なフォーク・ロック作品だがそこに留まるのはもったいない。Track.1の重苦しさから、共演にアシッド・フォーク・シンガーMarissa Nadlerを迎えたラストのTrack.10にかけて、雲の裂け目が広がるような、えも言えぬグラデーションがじんわり染み入る。EVERYTHING BUT THE GIRLでの成功、一時は死の淵までいった長い闘病生活、レーベル"Buzzin' Fly"の運営やDJ活動も経て、彼の年輪が刻み込まれた老成円熟の説得力だ。
-

-
berry meet
昼下がりの星、続く旅路
2022年結成のスリーピース・バンド berry meetが2ndミニ・アルバムをリリース。鮮やかなメロディが颯爽と駆けるサマー・チューン「青の魔法」、ソリッドなベースの歪みが鼓膜を揺らす「紬」と勢いある2曲で幕を開けるが、以降のボルテージは一変、等身大のソングライティングで紡がれるバラードを中心に構成される。恋の断片的な記憶を手繰り寄せるように、切なくも温かいコーラスが聴き手をうっとりさせるだろう。中でもポエティックな詞に思わず耳を傾けてしまうチルアウトな「星になりたい」は、詩集盤のリリースにも箔を付けるよう。終盤に収録される、100万回再生超えのMVが話題の「溺愛」も必聴だ。サビの合いの手にはギュッと胸を掴まれる。
-

-
BEST COAST
Crazy For You
BEST COAST!そう、西海岸最高なのである。ANIMAL COLLECTIVEのブレイク以降続々と個性的なアーティストが登場しているNYブルックリン・シーン同様、こちらはNO AGE以降だろうか、青い海と真っ赤な太陽を浴び自由に育ったアーティストで活況を呈しているL.A.シーン。なかでも今年のサマー・チューンとして刺激的な季節を彩ったのはこの1枚だったのでは?SONIC YOUTHのThurston MooreやBill Murrayまでもファンを公言している要注目デュオ、待望の日本デビューです。BEACH BOYSを夢見た女の子がひとり自室にこもり安い機材で作ってしまった、みたいなローファイ感覚が印象的だが、気だるいエコーを纏った甘いメロディから滴るノスタルジーが心を惹きつける。ジャケもご覧の通り、猫萌えユルユルさでファニー。でもこの飾らなさはバンドの魅力を象徴しているかもね。
-

-
betcover!!
告白
ヤナセジロウのソロ・プロジェクト、betcover!!による2ndアルバム。"2020年の今に望まれたロック・アルバム"と謳われる今作は、"愛"と"悲しみ"の表裏を淡々と歌い上げ、ノスタルジックで情緒溢れるサウンドスケープを描き、独自の感性を叙情詩のように表現した全10曲が収録されている。今作の鍵となるであろう「Love and Destroy」は、新たな試みとしてプロデューサーに小袋成彬を迎えて制作された楽曲。繊細で、しっとりと心に触れるものがあると同時に、"僕の体が道路に落ちても/心はそれを見ているだけ"などの言葉にハッとさせられ、聴き終えてからしばらく考えさせられるような感覚になる。純度の高い彼の音楽は、まさしく彼にしか作れないものだと思う。
-

-
betcover!!
high school !! ep.
"RO69JACK"優勝の18歳、ヤナセジロウのプロジェクト"betcover!!"。リード曲「COSMO」は、リバーブの効いた懐かしく温かな、心地よい横揺れのギター・ロック。だが、楽曲を聴き進めるうちに彼の音楽の旨みは他にもあるのではと気づく。ギター、キーボードなどの主張が、互いを"引き立てる"という考えは皆無なのではと思うほど、激しく、そこに気だるげな歌声と日本語の響きが乗るという不思議なバランス。そして独特の展開が持ち味だ。またアルバムを通して香るディスコチックな黒い匂いも、彼自身幼いころからEARTH, WIND & FIREを聴いて育ったというのだから納得。奇妙で絶妙な兼ね合いで音のスパイスを調合して作り上げたクセになる1枚。この生意気な曲者感、かなりいい。
-

-
BETH JEANS HOUGHTON AND THE HOOVES OF DESTINY
Yours Truly, Cellophane Nose
派手なヘア・スタイルに奇抜なメイク。ヴィジュアルから個人的に真っ先に連想したのはGwen Stefaniである。だが、聴こえてきた1曲目の「Sweet Tooth Bird」のイントロはTHE BEATLESを思い出すような正統派サウンド。更に聴き進めていけば、まぎれもないブリティッシュ・フォーク・ソングでヴィジュアルのイメージから想像したR&B等の要素は全くないのである。このギャップは流石に度肝を抜いた。更に21歳とは思えないほど甘さとセクシーさを兼ね備えた声は蠱惑的である。しかも、BLURやDEPECHE MODEを手掛けたBen Hillierがプロデュースを担当したというのだから、デビュー・アルバムから大物感の漂う1枚である。
-

-
THE BETHS
Jump Rope Gazers
女性ヴォーカル擁するニュージーランドはオークランド出身のバンド、THE BETHSの2ndアルバム。2018年のデビュー・アルバム『Future Me Hates Me』で得た成功への葛藤から生まれたという本作は、前作で見せた躍動感溢れるキュートで軽快なポップ・ロックだけでなく、少しセンチメンタルでアンニュイなムードも併せ持っている。インディー・ロック調のメロウなアレンジが冴える表題曲や、90年代オルタナのような重さとキャッチーさを感じさせる「Acrid」、「Don't Go Away」、しっとりとしたフォーク・サウンドの「Do You Want Me Now」など、ヒネりのきいたコーラスやメロディも含めてバンドとしての着実な成長が詰め込まれている1枚だ。
-

-
Bettye LaVette
ブリティッシュ・ロック解釈
グラミー賞ノミネート・アーティストBettye LaVetteが13曲の名曲を歌いあげる。これって、いわゆるヴォーカル力に定評のあるアーティストが人気ナンバーをカヴァーするっていう、日本にもよくあるヤツでしょ?と思ったあなた。そういった解釈はお門違いです。これは単に名曲を聴き、その余韻に浸るためのアイテムではない。タイトルの通り、各々の中にあるブリティッシュ・ロックの解釈を見直し、再考させるものである。60年代アメリカのリズム&ブルース、ソウル、ブルースのサウンドに影響を受け、それをイギリスで自らのスタイルへと作り変えていったミュージシャン達。Bettyeというソウル・ディーヴァにより、新たに息を吹き込まれた楽曲には、当時彼らが魅了されたブルースやソウルがある。それが“ルーツ・ミュージックへの再考”を喚起させるのだ。
-

-
BETWEEN YOU & ME
Armageddon
ポップ・パンクの明るく爽やかなサウンドが前面に押し出されたBETWEEN YOU & MEの2ndアルバム。甘酸っぱい恋心や、SNS時代特有の虚栄心などをテーマに、自分、他人、世界と向き合う現代の若者らしい青さが楽曲の勢いを加速させるが、ラストを飾る「Armageddon」で、本アルバム、そして本楽曲のタイトルが"最終戦争"であることを思い出すことになる。ここまでの9曲とは対照的にゆったりとしたリズム、聴かせるギター・ソロが、現代社会の分断が導く"最終戦争"からの"終末"を見つめるこの曲の儚さ、切なさを引き立たせる。もしいつか"終末"が訪れるなら、この1枚を聴いて、人間関係や見栄に悩んでいたあのころを思い出すのも悪くないだろう。
-

-
BIBIO
A Mineral Love
"Warp Records"所属のプロデューサーによる、3年ぶり7作目となるアルバム。サンプリングを一切排した今作は、オーガニックとエレクトロを自在に行き来する、言わば"人力フォークトロニカ"。制作においては"多様性"が重要なカギとなっただけあり、チルウェイヴからAOR、もしくはラウンジ・ミュージックといった様々なスタイルの音楽を喚起させるも、雑多な印象はなく、抜群の聴き心地で聴く者をあたたかく包みこむ。SSW然としたポップ・ソングのTrack.4、GOTYEをフィーチャーした幽玄なバラードのTrack.6、シンプル&ミニマルなエレクトロ・チューンのTrack.7など佳曲が揃い、日々のサウンドトラックとしても楽しめる。ディスコやブギーの再興という近年のトレンドに目を配らせつつも、時の洗礼にも耐えうる普遍性を帯びた秀作。
-
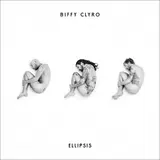
-
BIFFY CLYRO
Ellipsis
2013年以来の"FUJI ROCK FESTIVAL"出演も決まっているBIFFY CLYROから最高のタイミングで7枚目のアルバムが到着。先行シングル「Wolves Of Winter」で聴けたマイナー~メジャーを行き来するドラマチックなエモ感や音圧はあるが、どこまでも無駄を削ぎ落としたシェイプを聴かせる音像がストイックだ。今年の"Reading and Leeds Festivals"のヘッドライナーを務めるスタジアム・ロック・バンドでありつつ、日本では過小評価されている印象は拭えないが、いい意味でUSのエモやラウドロックのコードをメインで押す力技や突き抜けた明るさとは違う魅力がある。ピアノやアコギが効果的に配された繊細なバラード、スリリングなギター・リフとドラムの抜き差しの曲など、豪快に展開する曲が形成する起伏がカタルシスを生む。
-

-
BIFFY CLYRO
Opposites
UKを代表するモンスター・バンドは世界のモダン・ロックを代表するバンドになった。約3年ぶりの新作は、タイトルから察するに"対"になる世界観を持ったキャリア初のダブル・アルバム。作品全体を貫く物語の詳細は不明だが、深遠なムードのイントロダクションにタフなビートや力強いオーケストレーションが重なり、怒涛のスケール感へと昇華するカタルシスはさすがBIFFY節。加えて単にラテン的と括りがたい独特の変拍子や、バイオリンと聴き間違えそうなユニークな音色のギター、コードで塗りつぶすことなくスリリングに展開するアンサンブルなど、シンプルだが聴くほどに発見が。the HIATUSや9mm好きにもお勧めする。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























