DISC REVIEW
B
-

-
BURNOUT SYNDROMES
世界一美しい世界一美しい世界
大阪出身3ピース・バンドの初の全国流通盤となる1stアルバム。13歳からバンドを始め来年で早くも10周年を迎えるという彼らだが、決して早熟なわけではなく中学から仲間と1番楽しいことをしていたらこうなった、というバンドマンとして最も幸福な道程を歩んできているような気がする。全曲の作詞・作曲を手掛ける熊谷和海(Gt/Vo)が歌う内容はひたすら心の襞を描くような個人的なものだが、それを完全に理解・共有している石川大裕(Ba/Cho)廣瀬拓哉(Dr/Cho)と一体になることで観客が涙を流すほどの共鳴を生んでいるのだろう。Track.8「東名高速道路清水JCTを時速二〇〇キロメートル超で駆け抜けるのさ」は、まるでこのアルバムですべて終わってもいいというくらいに魂を削るような歌が胸に迫る。
-
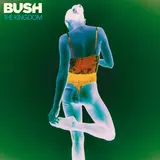
-
BUSH
The Kingdom
90年代のポスト・グランジ・シーンで人気を博し、2010年の再結成以降もコンスタントに活動を続ける、Gavin Rossdale(Vo/Gt)率いるBUSHの8作目。ザラついたギターに物憂げな歌声を乗せた基本スタイルは変わらずだが、プロデューサーに映画音楽を多く手掛けるTyler Batesや、ラウドロック界隈で活躍するErik Ronを迎えたことで、作品全体がソリッドでヒリついた空気感に。重々しいビートを叩きつけるTrack.2、緊迫感のあるギター・リフが刺さるTrack.6から、ピュアなバラードのTrack.8まで、円熟の境地に達したサウンドを堪能できる。グランジからヘヴィ・ロック、オルタナ・メタルまで、重めなサウンドが好きという人にハマるであろう1枚。
-

-
BUSH
Black And White Rainbows
1990年代から活躍、累計1,000万枚以上のセールスを誇るUKの大御所ロック・バンド、BUSHの3年ぶり7枚目のアルバム。2010年のバンド再結成以降、『The Sea Of Memories』(2011年)、『Man On The Run』(2014年)とコンスタントに作品をリリースしてきたバンドの充実度が伝わってくる15曲を収録。「Mad Love」の陰鬱なギター・リフから始まり、ミディアム・テンポでじっくり聴かせる楽曲が並んでおり、グランジ/オルタナティヴ・ムーヴメントを経てよりポップさを手に入れたベテラン・バンドの歌モノ作品といった印象。「Sky Turns Day Glo」、「All The Worlds Within You」などで聴かせるGavin Rossdale(Vo/Gt)の歌声は渋みと透明感の両方を感じさせるもの。「The Edge Of Love」、「People At War」と続く幻想的なサウンドで締めくくられる心地よいアルバム。
-

-
KLANGSTOF
Close Eyes To Exit
オランダのインディーズ・バンド MOSSの元メンバーで、アムステルダムを拠点に活動するノルウェー人アーティスト Koen Van De Wardtによるソロ・プロジェクト"KLANGSTOF"のデビュー・アルバム。10代のころにRADIOHEADの『OK Computer』に影響を受けて音楽を始めたのだという。「Hostage」の序盤は単純なリズム・トラックとゆるやかに流れるシンセで作られたアンビエントな音像から時間をかけて構築していき、終盤でノイジーに迫ってくるサウンドは壮大で圧倒的なクオリティ。ヴォーカルも表現力豊かで、ファルセットのハミングが印象的な「Seasons」、美しいアコースティック・ギターに乗せた歌い出しから感動的な展開となる「We Are Your Receiver」が聴きどころ。
-

-
butter butter
どこにでもあること
5作目のミニ・アルバムとなる今作は"教室"をテーマに、憂鬱な日々を過ごす1人の男子高校生が少しずつ成長していく姿を、アルバムの収録曲順を授業の時間割に見立てて収録したバンド初のコンセプト・アルバム。中高生のいじめ・自殺問題等のニュースを見かねたVo/Gtの鈴木貴之が子供の頃のいじめ体験を元に、子供たちの孤独な心に呼びかけるような内容となっており、Track.1の「1時限目:数学」から目の前で語りかけているかのように近い声にハッとさせられる。テーマからしてかなり重いアルバムではあるが、歌詞の内容のみならず、卓越した演奏力と細部にこだわったアレンジ、アンサンブルも聴きどころ。特にギターのセンシティヴなプレイはキッズに耳コピ意欲を沸かせそう。こうしたコンセプトでアルバム1枚を貫く意思と勇気は尊敬に値するだけに、1人でも多くこの音楽を必要としている子供たちの耳に届くことを願いたい。
-

-
butterfly inthe stomach
じたばたストーリー
ザ・チャレンジではチャレンジオノマックとして活躍する小野雄一郎(Vo/Gt)と、中江太郎(Dr)によるバンド、通称"バタスト"の初の全国流通音源。ポップな2ピース・サウンドに乗って歌われるのは、最初から最後まで"君"へのアツい好意。全曲通して、ただひたすらに。音読なんてされた日には聞いてるこっちが恥ずかしさで全身がむず痒くなるくらいのどストレートな想いの数々が音楽に乗ると平然と成立してしまう―― そんな音楽のマジカルな力を、ワイワイ楽しみながら活用しまくるポップ確信犯というべきだろうか。ちなみにバンド名の由来と思われる"butterflies in one's stomach"とは"そわそわする"の意。バンドが今後どう転がっていくのかも気になるところ。
-

-
the butterfly nine cord
MAJESTIC
3ピース・バンド、the butterfly nine cordの初流通音源となる2ndフル・アルバム。ZEPPET STOREのギタリスト、五味誠のプロデュースによる今作は"Art Of Waste-クズの芸術-"を謳った通り、雑然とし退廃的な世界観の中に独特の美意識を感じさせる楽曲が並んでいる。ストレートで硬質なリズム・セクションに乗ったギターは毛羽立ったノイズが中心だが「In the sun」で聴けるディレイを利かせたイントロから徐々に重厚な音が楽曲にふくらみを与えて行く様はお見事。続く「jellyfish」でも感じさせる繊細な音使いと、後半で畳み掛けるガレージ・サウンドがこのバンドの魅力だ。荒くれていても何故かスタイリッシュにすら感じるほど泥臭さのない研ぎ澄まされた作品。
-

-
BUZZ THE BEARS
THE GREAT ORDINARY TIMES
フル・アルバムとしては約5年ぶり。10年の活動をまとめたベスト盤を経た、新しいページをスタートさせる作品だが、その音楽とバンドへの姿勢や、歌に託した想いは不変だ。平坦ではない道を、人知れず涙や汗を流し、また立ち止まったりしながらも、すべてひっくるめて音にして抱きしめる。聴いていると、自然と背中にその手の温かさを感じる音楽がここに詰まっている。メロディックをルーツとした爽快な疾走感と、英語詞と日本語詞とが交じっていつつも、言葉がまっすぐに胸に響くキャッチーなメロディで、陽性のファスト・チューンからドライヴ感のあるロック、じっくり歌い上げるドラマチックな曲まで、幅広いサウンドを揃えた。このままセットリストでも最高な、ライヴ・バンドとしての自負も映る作品。
-

-
BUZZ THE BEARS
Q
BUZZ THE BEARS、7作目のミニ・アルバム。タイトルの"Q"には、制作中にバンドにとってよい曲とは何かという "問い=Question"があったこと、そして今年結成9年を迎えることもかけあわせている。BUZZ THE BEARSの歌の中心にある、聴く者の背中をガンガン押す熱いメッセージを肝にしつつ、「絵日記」では大事な人がいる日常のほっこりするようなシーンが綴られたり、「B・A・N・D」ではフェスでのあるあるな光景を毒も交えたアッパーな歌詞で歌い上げられる。この歌詞の緩急のバランスがいい塩梅で、彼らのフレンドリーな魅力が伝わるものになっている。だからこそ、檄を飛ばす曲はよりストレートに、スピードを上げて突き進んでいく。冒頭のパンク・チューン「Hurry Up!!」から最高の瞬間をパッケージした、高い熱量のアルバムだ。
-

-
BUZZ THE BEARS
L
自身のメッセージが聴き手の生活(Life)に根差し、ライヴハウスに気軽に(Light)足を運んでもらいたいという願いと、新作のテーマでもあるライヴ(Live)、それぞれの頭文字を取ったタイトルを掲げたミニ・アルバム。聴いてまず驚いたのが"Wow wow~"や"Yeah Yeah~"、明快な言葉などが並び、観客がシンガロングできる箇所がたくさん盛り込まれていること。歌を大事にしたメロコアやロックを奏で続けている彼らだが、意外にもこれまでにそういう曲は少ない。そんな新機軸に交わる、差し引きの効いた無駄な力みのないフランクなサウンドも心地よく、聴いてるこちらも自然体で楽しめる。タイトルに込めたテーマを実現させた頼もしい作品だ。より聴き手との距離が縮まるライヴの場景が目に浮かぶ。
-

-
BUZZ THE BEARS
GOLDCAGE
全13曲が閃光のようにあっという間に駆け抜ける、BUZZ THE BEARSのフル・アルバムとしては3年半振りの作品となる『GOLDCAGE』。まさにどの曲も黄金色に輝く強靭なパワーを放つ。“泣きのメロディック・パンク”と形容されることも多い彼らだが、その涙と切っても切れないのは“笑顔”だ。マイナー・コードを多く含んだコードとメロディも、ひたすら果敢に突き抜けながらもふとした瞬間に優しいアルペジオを鳴らすギターも、スピード感のあるリズム隊も、しっかりと人の目を鳴らされていることがわかる非常に真摯な音。彼らの心意気がそのまま楽器を伝って届けられている。メロディックだとか、ロックだとか、バラードだとか、そういう概念をすっ飛ばすほどの強い意思と熱いハートを存分に感じてほしい。
-
-
BUZZ THE BEARS
声
今年3月にキャリア初のシングル『ダーリン』をリリースしたBUZZ THE BEARSから2ndシングルがリリース。表題曲「声」は越智健太の歌声とギターが鮮やかに響き渡るロック・ナンバー。どこまでも突き抜ける青空と爽やかな風を彷彿させるキャッチーなサウンドはメロディック・パンクの枠を飛び越え、ロック・リスナーのみならずJ-POPリスナーの心も打つに違いない。信号機視点で歌われる「シグナル」のダイナミックなドラミングは、楽曲のスピード感をより生々しく印象付ける。ライヴを取り巻く日常をテーマにした「シンデレラキッズ」は否が応でも笑顔にならざるを得ないほどのアゲ曲。BUZZ THE BEARSのサウンドは、熱いハートがそのまま音に封じ込まれている。嘘や綺麗事などは一切存在しない、純な美しさに胸が焦がれる。
-

-
BUZZ THE BEARS
ダーリン
大阪出身、メロディック・パンクをベースにしたキャッチーかつ疾走感のあるサウンドと誰もが共感し、心を揺さぶる歌詞を武器にファンを増やしてきたBUZZ THE BEARS。彼らがシングルとしては初となる作品をリリース。表題曲である「ダーリン」はマイナー調のメロディと自分の弱さを認めながら"曲げることはできない"という強い気持ちを歌った非常にエモい仕上がり。Track.2「サウンド」はライヴでダイブとシンガロング必至の全英詞の爽快なパンク・チューン。そしてTrack.3の「ふたり」はミディアム・テンポのBUZZ流"卒業ソング"。この3曲はBUZZを今まで好きだったファンには彼ららしさをそのままに進化を感じることができるし、今作で彼らを知る方には名刺代わりの1枚になるはず。
-

-
Bye-Bye-Handの方程式
すくーぷ
初の全国流通ミニ・アルバムとなった前作から、約10ヶ月ぶりに到着したニュー・ミニ・アルバム『すくーぷ』。疾走感溢れる「midnight parade」がアルバムの1曲目を華やかに飾り、「ぷらねたりゅーむ」では少年が大人になる過程で抱く葛藤を歌う。同曲をはじめ、切なさの中に大切なものをそっと包み込むような温度を持って展開されていくのが、彼らの音楽の特徴ではないかと感じる。そんな彼らの多面性が表れた、ミドル・テンポの「ふたりのはなし」、洒落ていてジャジーな「雨恋」、イントロのギター・ソロが冴え渡る「ジュウブンノサン」などカラフルな1枚が完成。そしてラストには「FRIDAY」が据えられ、刺激的な恋に憧れる心情を歌うのだが、"あぁ、この曲のためのアルバム・タイトルだったのか"と深く頷ける。
-
-
Bye-Bye-Handの方程式
ろまんす快速特急
フォーリミ、reGretGirlらを擁するロック・レーベル、No Big Deal Recordsに所属する4人組バンド、初の全国流通ミニ・アルバム。あの子が好きという気持ちが暴走するロックンロール「最終トレインあの子の街へ」を皮切りに、70年代ポップスへのオマージュを込めた「甘い記憶」、ギターバンジョーをメイン楽器に使った素朴な味わいの小曲「夢送り競走曲」、桜の季節と共に訪れる別れを切なく綴ったバラード「春散る日々さ」など、その楽曲たちはノスタルジーと衝動が絶妙なバランスで溶け合う。全曲のソングライティングを手掛けるのはヴォーカル、汐田泰輝。銀河鉄道が駆ける星空に憧れ、二度と戻れないあの日へと想いを馳せるギター・ロックが、目を閉じて見える世界のロマンを教えてくれる。
-
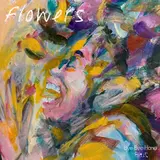
-
Bye-Bye-Handの方程式
Flowers
"ハイブリッド・ロック・バンド"を謳う大阪発の4人組、Bye-Bye-Handの方程式の3rdミニ・アルバムは、オーディションで所属を勝ち取ったNo Big Deal Recordsからの初リリースとなる意欲作 であり、5月に脱退したベーシストへのはなむけ的な意味 も込めた作品。これまで独特 の質感で 失恋を 吐露 する楽曲が印象 的だった彼らだが、今作は書き溜めていた曲の中から、 前向 きな楽曲だけを集めたというだけあって、言葉の取り合わせが懐かしい 思春期 の感覚を想起させる「あの子と宇宙 に夢中 な僕ら」をはじめ、"グッバイラブ ユー"のコーラスが切なくも温かい「ラブユー・シーユー」など、どの曲も自然と爽やかな背景が浮かぶ、フレッシュでエネルギッシュな1枚に仕上がった。
-

-
BYEE the ROUND
バイザラウンド
2003年結成、下北沢等を中心に活動する4ピース・バンドBYEE the ROUNDの1st フル・アルバム 。演奏とメロディで“攻め込み”、言葉では“責め込む”。苦しみもがく様を男臭く詩的に表現した、実に健全なギター・ロックだ。切情や熱情を帯びた熱く真っ直ぐな力強いヴォーカルに、遠慮なしに思い切り鳴らされる雄々しいギターとドラム、ヴォーカルをしっかりと支える重低音を響かせるベース。全てがダイナミックで全てが清々しい、正統派・ジャパニーズ・ギター・ロックとしての臭いを漂わせているのも逆に新鮮。ブルースの哀愁やガレージ・ロックのシンプルな衝動を含みながらも、全てがメロディックであり、全曲シングル・カットできそうな程に、真っ直ぐにロックしているパワフルな作品だ。


























