DISC REVIEW
B
-

-
Bob is Sick
sokokala
"押しつけがましかったり、痛かったりするくらいじゃないと、言葉は残しにくい"とフロントマンの久世悠喜は言う。それは人を傷つけるためではなく、人を奮い立たせるための衝撃と刺激だ。底にいた自分がスタート・ラインに立つために書いた言葉でもって、彼はリスナーを叩き起こそうとしている。SAKAE SP-RINGの主催でも知られるラジオ局、ZIP-FMが擁するレーベル"ZIP NEXT"からデビューするBob is Sick。2000年代ギター・ロックの系譜を辿る誠実なアプローチに、時折垣間見られるジャズの影響、ポスト・ロック的なドラミングが奥行きを作り出す。周りがどうこう言おうと、自分自身が動かなければ何も始まらないし変わらない。だから彼らは"いつか必ず君の夢を形にしろよ"と、あなた自身のことをあなたに委ねて歌う。
-

-
BODY/HEAD
No Waves
SONIC YOUTHのKim GordonとBill Naceによるエクスペリメンタル・デュオのライヴ・アルバム。音源でもかなり即興性の高いアヴァンギャルドな作品を聴かせるふたりだが、さらにライヴではKimのヴォーカルとギターも、Billのギターも"音楽以前"の感情やインスピレーションを原始的に表出させた演奏を担っていて、どちらかと言えば2本のギターによるアート、もしくは音のインスタレーションといった印象が強い。しかもノイジーで規則性のないそれは、予測不可能という意味で音のアクシデント、もしくは交信の途絶えた宇宙の彼方で鳴らされる絶望的で、でも人間が発するシグナルとしては最強に切実なものだ。ライヴ・パフォーマンスが少ないという意味では貴重だが、やはり生で観てこそ響くものがある気もする。
-

-
THE BOHEMIANS
ultimate confirmation
幕開けの「the earnest」のイントロ、陽性のオルガンとギター・リフや軽やかに高鳴るキックから、今作が心躍る最高の旅になることを約束してくれる。このキャッチーで高揚感たっぷりのロックンロールに続く「火薬!火薬!火薬!」は爆裂なアンサンブルが炸裂! さらに「ロックンロールジェントルメン」ではスピード感に溢れながらも洒脱な香りを纏ったロックンロールが、甘美な世界へと誘う。酸いも甘いも噛み分けた大人の余裕が漂い、毒っ気や皮肉をよりポップに、スマートに練り込んだそのサウンドは、噛む程に刺激や味わいが濃いものとなった。前作から約3年の時を経て、いい大人の尖りや遊び方を身に付けたバンドの最新形が詰まっている。
-

-
THE BOHEMIANS
BUM
今年1月、the pillowsの山中さわおが主宰するDELICIOUS LABELに加わった現代のグラム・ロック5人組が山中のプロデュースの下、完成させた4枚目のアルバム。60年代のブリティッシュ・ロックをただ再現するだけでは飽き足 らず、絶妙なデジャブ感とともにヒネリを加えたロックンロールが彼らの持ち味。その人を食ったようなセンスは好き嫌いが分かれそうだが、それこそがロックンロールが持つ諧謔と表裏一体のクリシティシズム。その点、ややクールすぎるきらいはあるものの、アーリー・ジャズ調のTrack.6「shyboy」、ピアノが転がるロックンロールのTrack.11「SUPER THUNDER ELEGANT SECRET BIG MACHINE」といった若干異色とも言える曲が流れにいい感じでデコボコを作っている。
-
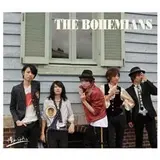
-
THE BOHEMIANS
憧れられたい
さすがはメジャー・デビュー作! 全てがスケール・アップしている。まず、タイトルからして素晴らしい。“ロックン・ロールはアイドルから始まる”、“スターになる前に、アイドルになりたい。”という心意のもと冠されたこの言葉は、ギラギラとした成功願望すらもセンセーショナルなキャッチ・フレーズとして作用させている。思えば、THE BOHEMIANSというバンドはインディーズ時代から、“ロック・バンド”という要素を、アイドル的にアイコン化して表現することに長けていた。そして、本作は、メジャー・デビューというステップすらも一つのコマーシャルとして、作品のスケール・アップの一端を担う要素として取り込んでしまったわけだ。インディーズという地下を飛び出し、更にモダンに、セクシーに。高揚感の嵐が吹き荒れる!
-

-
THE BOHEMIANS
I WAS JAPANESE KINKS
どぎついアイメイク、カラフルで奇抜だがどこかモダンなファッション、まるでキッチュなグラム・ロックのようなルックスのアーティスト写真がやけに印象的だったのだが、良い意味で、全てがそのビジュアル通りであった。軽快なブリティッシュ・ビートに胸をきゅんとさせるスウィートなメロディ。どことなく懐古的な臭いを漂わせるのはリズム&ブルースのこぶしも効いているからだろうか。舌ったらずで、けだるく、時に甘えたようにも聴こえるボーカルは、曲に“パンチラ”的なポップでキュートな色気を与えている。楽曲のみで、アートワーク的な部分も堪能したような印象を受けたのは、詳細なアーティスト情報もまだない彼らだが、既に徹底した独自の美学を持っているからだろう。バンドの個性と主張をたっぷりと詰め込んだ、まさにファーストアルバムにふさわしい作品。
-

-
BOK BOK
Your Charizmatic Self
ロンドンのアンダーグラウンド・ダンス・ミュージック・シーンでファッションやカルチャー方面からも熱い注目を集めるクリエイター集団"Night Slugs"の首領BOK BOKことAlex Sushon。彼が日本限定盤としてボーナス・トラックを追加収録したニューEPをリリースする。ファンクをグライム、エレクトロ・ミュージックへと昇華させたBOK BOK流とも言うべき音楽は、新世代UKのアンダーグラウンド・サウンドを魅せてくれる。「Melba'sCall」には、BBC Sound of 2014にもノミネートされ、センセーショナルなデビューを飾ったKelelaをフィーチャー。ソウルフルな彼女の歌声とBOK BOKのエレクトロ・サウンドのコラボにはうっとりと酔いしれてしまう。
-

-
B.O.L.T
Weather
移り変わる天気のように様々な感情が表現された1st EP。その作家陣には、どついたるねん、KNOCK OUT MONKEY、BACK LIFT、POT(※五十音順)といった強力なロック・バンドが名を連ねた。メロコア、ポップ・パンクを中心とした楽曲の数々は、提供アーティストの個性が発揮され、それぞれのカラーを持っているにもかかわらず作品としてのまとまりを感じさせる。それは、このEPのテーマ性だけでなく、メンバー4人の声が立ってきたことで、歌声で作品をひとつに束ねられるようになったからだろう。リード曲はHold Out Hope提供の「BY MY SIDE」。現行のUSポップ・パンクのテイストを取り込んだサウンドに乗せる、複雑な恋心を繊細なタッチで表現した歌唱に注目したい。
-

-
B.O.L.T
B.O.L.T "THE LIVE PACKAGE" 2021
自身初のツアー"#BOLT関東デマス ~初ライブツアーの巻~"のツアー・ファイナルと、恵比寿LIQUIDROOMで行われた"B.O.L.T ONE MAN LIVE 「Voyage」"の2本立てという豪華な映像作品。前者は、初のツアーでの経験を経て成長した4人の姿と、パフォーマンスの充実っぷりが見どころ。2ndアルバム『Attitude』を引っ提げてのツアーということもあり、同作の全曲が収録されているので、CDと共に楽しみたい。後者は、高井千帆のラスト・ティーン・ライヴというメモリアル公演。高井自身が考案した、四季をモチーフにパート分けが施されたコンセプチュアルなセットリストで、"Voyage"のタイトル通りに、メンバーと共に季節を旅する気分を味わうことができる。
-

-
B.O.L.T
More Fantastic
表題曲「More Fantastic」は、桜井日奈子主演のBSテレ東 真夜中ドラマ"ごほうびごはん"OP主題歌に起用され、SILENT SIRENのサウンド・プロデューサーとして知られるクボナオキが提供。B.O.L.Tらしい疾走感溢れるロック・ナンバーで、料理用語を巧みに取り入れながら恋愛に絡めた歌詞が目を引く、キャッチーでエネルギッシュな1曲だ。"空想よりも現実のほうがファンタスティックだ"という根底にあるテーマも深い。秋田のバンド Hold Out Hopeが提供したカップリングの「Reborn」は、B.O.L.Tが主軸とするポップ・パンクの中でもよりヘヴィなイージーコアをベースに、エレクトロニックな上物が映える。つい口ずさんでしまうエモーショナルなメロディは秀逸だ。
-

-
B.O.L.T
Attitude
各曲に身体のパーツや動きがテーマとして割り振られた2ndアルバム。Misaki(SpecialThanks)提供の「スマイルフラワー」、SHANKの松崎兵太は「まわりみち」、「未完成呼吸」の2曲、TOTALFATからShunとJoseがそれぞれ1曲ずつなど、楽曲を提供したアーティストには強力なライヴ・バンドの面々が名を連ねた。中学生になったばかりの青山菜花と白浜あや、20歳付近で大人になった内藤るなと高井千帆、双方の歌声が絡み合い、各作家の個性が発揮された曲を歌い上げる。今の彼女たちにしか作れない作品と言えるだろう。タイトル"Attitude"は"姿勢"などの意味を持つが、本作を経た4人がアーティストとしてどんな姿勢を見せてくれるのか、彼女たちの今後も楽しみだ。
-

-
B.O.L.T
スマイルフラワー
B.O.L.Tの2ndシングル表題曲「スマイルフラワー」を提供したのは、SpecialThanksだ。ミドル・テンポの歌い出しから徐々に疾走感と力強さを帯びていくこの曲は、コロナ禍でマスク着用が当たり前になり、日常で見る機会が減ってしまった"笑顔の大切さ"を伝えてくれる。B.O.L.TメンバーとMisaki(SpecialThanks/Vo/Gt)が持つ優しさを共鳴させたかのような歌声とサウンドで、ライヴハウスには笑顔の花が咲きこぼれるだろう。音楽性としても人間性としても、抜群の相性を見せた1曲だと言える。c/wは「OUR COLOR」。イントロからアウトロまで終始エモーショナルに駆け抜けていき(特にサビのユニゾンがエモエモ!)、こちらもライヴで威力を発揮しそうだ。
-

-
B.O.L.T
Don't Blink
今年アルバム『POP』でメジャー・デビューを果たしたB.O.L.Tの初シングル。BSテレ東のドラマ"どんぶり委員長"主題歌に起用されている表題曲「Don't Blink」は、TOTALFATが提供しており、TOTALFAT節全開のメロコア・サウンドに踊れる要素も加えたアッパー・チューンに仕上がった。"どんぶり"→"Don't Blink"→"瞬きしないでずっと見つめていて"と、ラブコメの主題歌に相応しく恋心と遊び心も詰まった歌詞にも注目。c/wにはバンド・サウンドに切ない想いを乗せた「淡い空」、1stアルバムから「SLEEPY BUSTERS」と「わたし色のトビラ」のリミックス音源も収められ、この1枚でB.O.L.Tの歌唱とサウンドの様々な顔を知ることができる。
-

-
B.O.L.T
POP
ももいろクローバーZや私立恵比寿中学が所属する"スターダストプラネット"の4人組アイドル、B.O.L.Tのメジャー・デビュー・アルバム。本作は、メロコア、パンクを始めとした生バンドによる本格ロック・サウンドが聴き応えたっぷりで、且つメロディをポップに仕上げることにより、タイトル通りにB.O.L.T流のポップを体現している1枚だ。同じ歌詞でも歌うメンバーによって意味が変わって聴こえてくるのは、年の離れたメンバー構成の賜物だろう。単曲配信が主流になりつつある時代に、アルバムを通して24時間を表現している点も意義深い。1枚を通して時間の流れを感じながら聴くも良し、今の時間帯に合った曲を聴くも良し。聴き方のバリエーションも楽しむことができる。
-
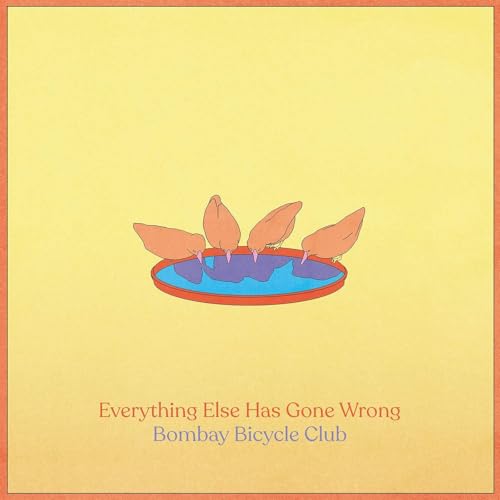
-
BOMBAY BICYCLE CLUB
Everything Else Has Gone Wrong
3年間の活動休止を経て2019年にシーンへ復帰したロンドン北部出身の4人組インディー・ロック・バンドが、約6年ぶり5枚目となるアルバムをリリースした。ポスト・パンクの影響を受けたギター・ロックに端を発し、静謐なフォークからきらびやかなエレクトロまで、アルバムごとに大胆な変化を見せてきた彼らだが、今回はバンド独自のキャラクターを確立し、全英1位を獲得した前作『So Long, See You Tomorrow』の流れを汲みつつ、より洗練させた音楽性の、まさに復帰作に相応しい内容に。エレクトロニクスとバンド・アンサンブルを巧みに折り重ねた色彩豊かなサウンドと、美メロを紡ぐドリーミーな歌声が生み出すソフトでポップな世界は、何度でも訪れたくなるほどの心地よさだ。
-

-
BOMBAY BICYCLE CLUB
So Long, See You Tomorrow
UKの天才バンドによる4枚目。デビュー時より何よりも特徴的であった、ヒップホップやR&Bからの影響を色濃く反映したビート感は、エレクトロニクスとバンド・サウンドの融合を見事に果たした前作『A Different Kind Of Fix』を経て、よりヴァリエーション豊かな表情を見せている。シンセやサンプリングを多用した上音も、時に静謐に、時にパワフルに、鮮やかな色彩を描く。とにかく細かな音作りをしているが、すべての音がナチュラルに、グラデーションを描くように重なり合っていく様は、耳にとって最高の快楽。肉体感と浮遊感を同時に鳴らすバランス感覚も絶妙。音の隙間から滴り落ちるメランコリーもたまらない。もう、すべてが圧倒的。THE HORRORSやFRIENDLY FIRESと並んで、今のUKになくてはならないバンドに成長したと思う。大傑作。
-

-
BOMBAY BICYCLE CLUB
I Had The Blues But I Shook Them Loose
平均年齢19歳、CAJUN DANCE PARTYに続く才能として注目を集めるBOMBAY BICYCLE CLUB。THE STROKESもVAMPIRE WEEKENDも通過したまさに今の音であると同時に、THE PIXESやSMASHING PUMPKINS等の90年代USオルタナの影響もハッキリと。多彩なギターの音色、印象的なパターンを刻むドラム、憂いを帯びたメロディ。どれか一つが突出することなく、全体が絶妙のバランス感覚を保っている。音を詰め込みすぎず、隙間を大事にしたアレンジも素晴らしい。いい湯加減のドリーミーさ、レイドバック感も心地よいギター・ロック。個性的なバンドがひしめくUSインディに対する、UKからの一発回答。12月には来日も決定、2009年後半の主役はこいつらか!?
-

-
BOMI
ビューティフォーEP
“全力の真っ直ぐ”は何にも屈しない強さがある。人の心を感動させるのは、小細工の一切ない熱い思いなのだ。表題曲「ビューティフォー」の突き抜けるハイトーン・ヴォイス、胸を高揚させる力強いリズム隊、太陽光線にも負けないくらいの眩しさを放つギターとピアノの音色が、そんなことを改めてわたしに教えてくれた。前作のフル・アルバム『メニー・ア・マール』から約8ヶ月。bómiが2013年初作品としてリリースするのは精鋭5曲を収録したミニ・アルバムだ。ポップと言うにはロックで、ロックと言うにはキュートすぎるbómiワールドは、今作も我々の日常にちょっとした魔法とスパイスを与えてくれる。ヴォーカル・アプローチもスケール・アップし、より彼女の魅力が輝く作品になった。
-

-
BOMI
キーゼルバッファ
アメリカ生まれ大阪育ちで両親は韓国人という生い立ちから既に興味を惹かれるbomi(ボーミ)のメジャー・デビュー・ミニ・アルバム。甘くキュートな歌声とモデルとしても活躍する恵まれたルックスは早くも各メディアがブレイク必至と大注目。そんなbomiの魅力を存分に楽しめる今作は本格的ロック・サウンドとダンス・チューンが網羅され、一気に最後まで聴ける高い完成度。平凡な日常への不満や女の子目線での純粋な恋愛感情をストレートなようで少し捻った言い回しで綴るユニークな歌詞と、リード曲「キューティクル・ガール」のエレクトロでキラキラな疾走感溢れるサウンド、そしてバラード曲「Someday」での切なくも伸びやかな歌声。bomiの豊かな表現力とポテンシャルの高さに胸ときめく良作。
-
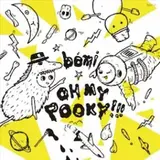
-
BOMI
OH MY POOKY!!!
アメリカ生まれ、大阪育ちのネクスト・ポップ・ロック・アイコンbómiの1stミニ・アルバムがTOWER RECORDS限定でリリース。ポップ、ロック、ダンスとジャンルがどんどんボーダーレスになっている昨今の音楽シーン、それを象徴するかのように縦横無尽に様々な色をbómiというフィルターを通してカラフルに見せてくれる。エレクトロなポップ・チューンの「iYO-YO」、スペイシーなニュー・ウェーヴ感溢れるテクノ・ポップの「PPP...」、中盤から終盤にかけての高揚感が心地よい四つ打ちダンス・トラックの「Mu-Zi-Q」。中毒性という名のポップ・マジックを飛び越した、完成度というよりはそれをあっさりと消化できてしまう飛び抜けた感度の良さが随所に感じ取れる。“可愛い新人の誕生”とか言ってると、気付いたときには周回遅れになってるかもしれないですよ?
-

-
BONES UK
Bones UK
あの天才ギタリスト Jeff Beckが認めたシンデレラ・ガールズということで、大注目の女性オルタナティヴ・ロック・デュオ BONES UKがデビュー作となるフル・アルバムをリリースした。世の中のトレンドなどまったく眼中にないような、我が道を行くスタイルで、ヘヴィでダークなインダストリアル・ロックをかき鳴らす。ポップな要素もあるが、エッジの効いたブルージーなギターやRosie Bonesの気だるい歌声など、泥臭いロックンロールが色濃く出ているため、打ち込みのビートをふんだんに使っていても、彼女たちはエレクトロ・デュオではなく、ロック・バンドなんだなと納得できる。中性的でロック・スターっぽい、尖ったファッションや佇まいも、堂々としていてクールだ。
-

-
Bo Ningen
III
イギリス・ロンドンを拠点とする日本人4人組バンド、Bo Ningenの1年半ぶりとなる3rdアルバム。レコーディング、ミックスにはPRIMAL SCREAMやASIAN DUB FOUNDATIONを手掛けるMax Hayesを迎えて、サイケデリックで、重量感のあるサウンド空間をより濃く作り上げている。ものすごい勢いで異空間へと放りだされ無防備になったところに、Taigen Kawabe(Vo/Ba)による日本語詞が響きわたる。こんがらがった思考をリセットするかのようなパワーがあり、爆音とアヴァンギャルドなバンド・アンサンブルで陶酔の彼方へとリスナーを吹っ飛ばす。Jehnny Beth(SAVAGES)や、詩人でもあるRoger Robinson(KING MIDAS SOUND)をゲストに迎えた日本語詞と英語詞がパラレルで流れる不可思議な感覚もまた、面白い。
-

-
bonobos
HYPER FOLK
メンバーの脱退を経て完成した前作の『ULTRA』以来2年3ヶ月ぶり6枚目のアルバム。自主レーベル"ORANGE LINE TRAXXX"を立ち上げる等、独自の活動をおこなう彼らの音楽はエレクトロ、レゲエ、スカと多彩で、一種の音楽研究所的な印象も受ける。タイトルに『HYPER FOLK』とあるように、楽曲の原型はフォーク・ギター1本でどこへでも出かけて演奏できるようなものなのだろうが、それをこうした色彩豊かな作品群にまとめ上げるメンバーの才能は特筆もの。カントリー・タッチの「春のもえがら」からインスト曲「virgo steps」への流れなどは映画音楽のようだ。器用すぎるきらいも感じるのだが、何度でも楽しめそうな作品。
-

-
bonobos
Ultra
レゲエ / ダブ、サンバやカリプソ……多彩な音楽表現を得意とする彼らだが、初期のエレクトロニカ的なサウンドは徐々に鳴りを潜め、管弦楽を取り入れ、壮大かつ、より温かみのある音楽へと移行。本作では、bonobosの祝祭的っぷりが完全に華開いた内容に!随所に煌めくサウンドを織り込み、春の訪れを印象させる様な自然賛歌の数々。SIGUR ROS……というよりは、Jonsiを彷彿とさせる色彩豊かなチェンバー・ポップか。特に「虹」、「O’Death」、「Wanderlust」の感動的な展開や童謡のような「あなたは太陽」の蔡忠浩の歌声といったら……。今年で活動10周年と相成った彼らだが、多幸感に満ちた本作は、集大成というよりも “新生bonobos誕生”というに相応しい。
-

-
bonobos
Go Symphony!
9枚目のシングルはDE DE MOUSEが手掛けたリミックス、震災後に無料配信されていた「PRAY for」の新録など全5曲がパッケージされた豪華盤。表題曲は自然も人間も世界もすべてを包み込む壮大な賛歌。ヴァイオリン、トロンボーン、フルート、子供の声......たくさんの音が集合して作り上げる圧倒的な世界は、まさ幻想的なシンフォニー!刻まれるビートが命の鼓動のように包み込み、ミュージック・ビデオではメンバーが不思議なダンスを披露。 bonobosは今年、結成10周年を迎える。今までメンバーの脱退などもあったが、アニバーサリー・イヤーにこんな新作を届けてくれたことを祝福したい。内から湧き出る歓びがあふれ出たような今作、ライヴだと感動倍増は確実。
-

-
bookman
ピアニシモ・ハートビート
pianissimo="極めて弱く"を冠したタイトル。全編を通して感じられる、心臓の拍動を思わせる温かなリズム。そして、時に凛と、時に柔らかく響く木囃子の歌声が儚くも力強い命の物語を目の前に浮き上がらせる。浮遊感を湛えた1曲目「Pianissimo Heartbeat(inst)」から、バンドらしい疾走感あるナンバー「夜をかかえて」、「遅咲きの花」まで、バンド・サウンドに縛られない多彩な楽曲たちの根底に常にあるのは、生と死の循環、そしてそれに向けられるどこまでも優しいまなざしだ。器用に生きられなかろうと、暗闇の中に身を潜めていようと、弱々しくとも懸命に生きる命の物語を真摯に描く"bookman"の歌は、彼の歌を必要とする人々の心の叫びを丁寧に、確実に掬い上げてくれるはずだ。
-

-
bookman
farewell note.
"孤高"と呼ぶに相応しいシンガー・ソングライター、コバヤシによるソロ・プロジェクト"bookman"。矛盾と不平等に満ち溢れた世界に対する彼の視界≒心の痛みや絶望を言語化し、ロック・サウンドに乗せて聴き手に訴え掛ける手法はamazarashiを彷彿とさせる。その世界観を貫きつつ、鬼気迫るポエトリー・リーディングを聴かせる「優シイ人ノ詩」、全英語詞のミクスチャー・ナンバー「escaper」、ピアノをフィーチャーしたミディアム・バラード「涙彩画」といったように、サウンド面での表現は非常に豊か。当たり前の日常生活の中に潜む、目を背けたくなるような感情や事実を容赦なく羅列した歌詞には心がややしんどくなるかもしれない。しかし、毎日に生きにくさを感じている人にこそ聴いてほしいと思うのは、彼の歌が本当は希望に手を伸ばしているからだ。
-
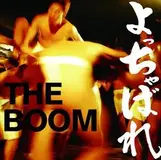
-
THE BOOM
よっちゃばれ
民謡、フォーク、ロック……いつだってジャンルの垣根をぶっ壊してきたのは彼らだった。今作は演歌の女王・石川さゆり、GO!GO!7188のユウをフィーチャリングした楽曲も収録し、盆踊りや島歌などの和テイストをふんだんに落とし込んだ印象。気になるアルバム・タイトル『よっちゃばれ』は“集まって”“寄ってきて”という意味を表す、宮沢和史(Vo)の故郷・山梨県の方言。音楽は孤独な心に手を差し伸べてくれるものでもあるけれど、みんな集まって音楽を共有し合うことは最高に楽しいものだと再確認させられる1枚だ。本来は3月30日のリリースが震災の影響で11月となったが、ラストに収録されているピアノと豊かな歌声が壮大に響く「ゆっくりおいで」が世界を優しく包み込んでいくようで、今の時代にとても沁みる。
-

-
THE BOOM
四重奏
今年は大物バンドの20周年が多いですね。このレビューの中にも幾つか20年を迎えたアーティストが。そして、このTHE BOOMも今年で結成20周年を迎え、シングル2枚、トリビュート・アルバム、そして3年ぶりのワンマン開催と精力的な活動を繰り広げている。そんなTHE BOOMが、20周年記念のオリジナル・アルバムをリリースする。沖縄民謡やラテン、ワールド・ミュージックにまで広がるポップを歌い続けてきたTHE BOOM。今作は、シングル「夢から醒めて」「All Of Everything」「My Sweet Home」を始め、宮沢のソウルフルな歌声が優しく響く、温かいグルーヴとメロウネスに満ちた大人のポップ・ミュージック集とも言うべき内容だ。
-

-
BOOM BIP
Zig Zaj
プロデューサー、アーティスト――Bryan Charles Hollonの仕事として最も印象に残るのは、やはりSUPER FURRY ANIMALSのGruff RhysとのユニットNEON NEONだろう。そうした活動を経て、ソロのBOOM BIP名義では6年ぶりの新作となるから待望だ。FRANZ FERDINANDOのAlex Kapranos、EMPIRE OF THE SUNのLuke Steele、RED HOT CHILI PEPPERSのJosh Klinghofferなどの豪華ゲスト参加に関心が向きがちだが、特筆すべきはサンプリングにおもねることなく、マルチ・プレイヤーとし「Pele」や「Tumtum」を作り上げる彼のセンス! 単に広いだけでなく深い音楽性を備えた、猥雑ギリギリの“折衷美”をお楽しみ頂きたい。
-
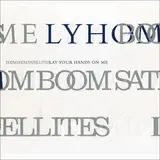
-
BOOM BOOM SATELLITES
LAY YOUR HANDS ON ME
多言は無用だろう。これがBOOM BOOM SATELLITESの最後の作品だ。その事実はどうしても切り離して考えられないが、ここまでポップで突き抜けていて美しいエレクトロニック・サウンドに昇華できたのは中野雅之(Ba/Prog)が探求に探求を重ねたからだろうし、逆に川島道行(Vo/Gt)の歌と言葉は、希望も絶望も共にある彼の心から自然に浮上したように聞こえる。タイトル曲の中で川島が"Lay your hands on me(ずっとその手で触れていてくれ)"と歌い、"I fly(僕は飛ぶ)"と歌う時間は聴き手が存在する限り永遠に思える。全4曲の後半2曲はもう歌ではなく川島の"声=意志"の力に寄り添うようにメロディ、サウンドが吟味され尽くしているのだが、そのことが何かに機能するために作られた音楽の一切を凌駕する。鳴っている音すべてが美しく、0.01秒の残響も聴き逃したくない。
-

-
BOOM BOOM SATELLITES
EMBRACE
オリジナルとしては『TO THE LOVELESS』以来、約3年ぶりとなる8枚目。ギター・サウンドやヴォーカル・ワークのオリジナリティに磨きがかかり、エレクトロニックなサウンドの中にもオーガニックなグルーヴを感じさせるなど、新鮮な驚きに満ちた新章に相応しい仕上がり。昨年6月にシングル・リリースした「BROKEN MIRROR」をはじめ、初のカヴァーであるTHE BEATLESの「HELTER SKELTER」でのBBS流カオティック・ワールド、温度感や曲のストーリーをリアルに伝える「SNOW」。フィジカルに訴えるハード・チューン「FLUTTER」などを経て、ピアノのサウンドや清冽なサウンドスケープが印象的なタイトル・チューン「EMBRACE」や「NINE」へ至るエクスペリメンタルな全10曲。
-

-
V.A.
ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN COMPILATION 2011
アジカン企画&主催の夏フェス"NANO-MUGEN FES."も今回で9回目(ツアー形式だった「NANO-MUGEN CIRCUIT2010」を含めると10回目)。WEEZERやMANIC STREET PREACHERSをヘッドライナーに、BOOM BOOM SATELLITES、the HIATUS、若手注目バンドねごと、モーモールルギャバンなど、洋邦共に相変わらずの豪華ラインナップ。出演バンドの楽曲が1曲ずつ収録されているコンピレーション・アルバムは、今作で5作目。そして、今回収録されているアジカンの新曲は2曲。チャットモンチーの橋本絵莉子(Vo&Gt)を迎えた「All right part2」は、後藤と橋本の気だるい歌い方と熱が迸る歌詞のコントラストが鮮やかで、高揚感に溢れたギター・リフとメロディも力強く鳴り響く。ユーモラスなあいうえお作文、男性の言葉で歌う橋本の艶とレア感も思わずニヤついてしまう。東日本大震災時の東京を描いた「ひかり」は、人間の醜い部分や絶望感にも目を逸らさず、物語が淡々と綴られている。言葉をなぞる後藤の歌に込められた優しさと強さは、当時の東京を克明に呼び起こしてゆく。生きることが困難な時もあるだろう。だが"オーライ"と口ずさめば、ほんの少し救われる気がする。音楽の持つ力を信じたい――改めて強くそう思った。
-

-
BOOM BOOM SATELLITES
TO THE LOVELESS
BOOM BOOM SATELLITESから届いた衝撃の新作。徹底したブレのないスタイルから繰り出されるストイックなビートと姿勢はデビュー以来変わっていないが、今作もまた自由でエネルギシュ。誰もまだ到達出来ていない孤高とも言えるその世界感を完成させながら彼らはまた新たな一歩を踏み出している。どの曲も既存のポップ・ミュージックのフォーマットから外れていながらとてもドラマティック。そして彼らの持つダークなムードは維持しつつどこか暖かいフィーリングに包まれている。"聴いてくれた人の想像力と音楽が合体した時に本当の意味で完成する音楽"と語るように今作は私たちに訴えかけてくるような作品だ。
-

-
BOOM BOOM SATELLITES
19972007
昨年リリースされたシングル「Back On My Feet」は、最早説明不要の大衆性を獲得した後のBBSと、デビュー当時のエクスペリメンタルな要素が見事に調和した素晴らしい曲だった。そして、満を持しての2枚組究極ベスト盤が登場。これはもう、タイミングばっちりでしょう。選曲はメンバー自らが行い、リミックス&マスタリングも敢行。これまでにリリースした(「Back On My Feet」を除いての)8枚のシングルからは意外にも3曲しかセレクトされていないが、まるで2 枚のオリジナル・アルバムのような選曲の並びになっているので、単なるヒットコレクションとは違う聴き応えのある作品だ。「Well Kick Out The Fading Star」そう、彼らの快進撃は、またここから始まる。
-

-
BOOM BOOM SATELLITES
Back On My Feet
『Full Of Elevating Presures』『On』『Exposed』は、それぞれ違うアプローチではあるものの、どれも甲乙つけ難いほどの傑作だったことは言うまでもない。そして『Exposed』から約一年半、遂に彼らが始動した。このニュー・シングル『Back On My Feet』は、アニメ『亡国のザムド』のオープニング・テーマに決定している。トランシーながらも、どこか遠くから聴こえてくるかのような音作りで、ドラムの音だけが規則性を保ちながら波のように押し寄せてくる。とてもドラマチックでスケールの大きい曲で、思わず鳥肌が立ってしまった。BBS至上最高傑作といっても過言ではないだろう。また、『All In A Day』はRADIOHEADの『Pyramid Song』を彷彿とさせ、『Spellbound』から『Caught In The Sun』は、ひとつの曲として捉えるならば、14分にも及ぶ大曲だ。
-

-
bootleg verrolls
確信
愛媛県松山発の3ピース・バンド bootleg verrollsが、ライヴ会場および自身のオフィシャル・サイトで販売していた2nd EPをこのたび全国流通。Track.1「誰が為の人生か」冒頭、1分に及ぶギター・ソロで聴き手を"ひとり"に還してからはあっという間。以降、喧騒を筆圧高く塗りつぶすような轟音と腹の底から湧き上がらせたような歌声はひたすら"それでいいのか"、"いや、よくないだろ"と訴えかけ続ける。突き詰めていくとこのバンドが歌っているのは、俺は俺を生きる、お前はお前を生きろ、ということのみ。実にシンプルなのだが、だからこそエネルギーが尋常じゃないし音と言葉ひとつひとつの爪痕が深いのだ。デビュー作にして圧倒的存在感。今後にも期待したい。
-

-
THE BOXER REBELLION
The Cold Still
Drew Barrymore 主演映画『遠距離恋愛 彼女の決断』に楽曲を書き下ろし、その劇中にメンバーが重要な役どころで出演も果たすなど、最近は活動のフィールドを新たな分野へ広げているのが印象的なTHE BOXER REBELLION。その活動がきっかけとなって、今作であらためての彼らの作品に触れる人は多いかもしれない。そんな重要作は、幕開けからこのバンドならではの世界観に引き込まれる。ピアノと弦楽を背に、厳かなムードに包まれながら響いていく「No Harm」。重厚、かつ壮大な音色でアルバムの世界観にいきなり引き込まれ、「Step Out Of The Car」で一気に疾走を開始!スピード感豊かに疾走するかと思えば、繊細なファルセット・ヴォイスが心の琴線を揺らす……。バンドの持ち味を十二分に発揮しながら、新たな広がりも感じさせるアルバムだ。
-

-
BOYGENIUS
The Record
グラミー賞3部門を受賞したBOYGENIUSのデビュー・アルバム。それぞれソロでも活躍するJulien Baker、Phoebe Bridgers、Lucy Dacusという才能豊かな女性アーティストが集結し、見事な化学反応を起こした今作は、デビュー・アルバムながらある種の落ち着きや完成度を感じさせる、しなやかで強固な意志の集合体だ。親しみやすいソフトなインディ・ロックから、90年代初期エモのような内に秘めた激しさを感じる楽曲まで、多彩なアプローチでそれぞれの個性的な世界観を生かしつつ、楽曲ごとに浮いた感じもしないという絶妙な仕上がりを見せてくれている。メッセージ性の強いファッションを披露したかと思えば、少女のような素朴さも見せる不思議なこの3人組からまだしばらくは目が離せない。
-

-
THE BOY MEETS GIRLS
HITCH HIKE
保育大学出身バンド、THE BOY MEETS GIRLSによる待望のフル・アルバム。飽き性なソングライター 高島大輔(Vo/Gt/Key)の性格のせいか、曲ごとに違うカラーを見せるボーイミーツの音楽性だからこそ、全12曲という長編ボリュームが、実はベスト・サイズなのかもしれない。鳥のさえずりと共に"おはよう"のあいさつを交わす「朝食はみんなで」に始まり、中華系お遊びグルメ・ソング「卍ラーメンインザグルーヴ卍」、80sな雰囲気の甘いダンス・ナンバー「ふたり」、バンドの過去から未来へと想いを馳せる「グッドラック」まで、溢れ出す個性的な曲たちが聴き手の心を離さない。シークレット・トラックには、ヴォーカル高島から、ドラム かつくんへのバースデー・ソングも収録している。ついに、かつくんの本名が解禁......!?


























