DISC REVIEW
M
-

-
Martha Wainwright
Come Home To Mama
シンガー・ソングライター、Martha Wainwright。彼女は70年代にフォーク・シンガーとして活躍したLoudon Wainwright III とKate McGarrigleの娘であり、あのRufus Wainwrightの妹である。生粋の音楽サラブレットはこれまでもその才能を見事に表現してきたが、まだまだ底知れぬ存在と言いたい。通算4枚目となる今作。高低から強弱の巧みなヴォーカリゼーションで魅せるハスキー・ヴォイスは、やはり圧倒的で不変的な声の力。その魅力を支える豪華なゲスト陣も毎回話題となるが、本作はCIBO MATTOの本田ゆかプロデュース。加えてギタリストはWILCOのNels Cline、ベースは夫でありプロデューサーとしても活動するBrad Albetta。さらにドラムはDIRTY THREEのJim Whiteというから驚きだ。インディー・ファンは無視することなかれ。
-

-
THE MARY ONETTES
Islands
80'sニューウェイヴの影響を云々って、もう説明にならない気がする。今みたいに様々な角度からこの多様性を持った時代にスポットが当たると「80'sニューウェイヴのどの辺」という話が必要で、こういう言葉に対してもっと自覚が必要だと実感する。このスウェディッシュ・バンドTHE MARY ONETTESのレビューを書きながら、ふとそんなことを考えたので書き直し。デビュー・アルバムが本国のみならず、欧米でも高い注目を集めた彼等。THE CURE のようなナイーヴな歌心を、洗練されたクリアなセンスでまとめる完成度の高さは秀逸。WHITE LIESに通じるロマンティックな美意識を持つギター・ロックだが、THE MARY ONETTESの方が都会的な清々しさがあるのはスウェディッシュ・バンドならでは。
-

-
THE MARZIPAN MAN
Adventures
自国スペインではパフォーマンス等で話題のポップ・シンガー・ソング・ライター、Jordi Herreraのソロ・プロジェクト。2ndアルバムである今作にて、とうとう日本デビューを果たす。少年のような柔らかい歌声は、聴く者をおとぎの国に誘うような催眠効果がある。サウンドの基盤はフォークなのだが、アコースティック・ギター以外にも様々な楽器を駆使しており、一筋縄ではいかない独特のサイケデリックな空気感。こりゃ何だ? と動揺していても、彼の不安定ながらも人懐っこい歌声が、有無も言わさずリスナーを摩訶不思議な世界へとずるずる引きずりこみ離さない。Jordiの小粋な魔法が掛かった、ちょっぴり不思議な夢と優しさ溢れるサイケ・ワールド。既存の世界に飽き飽きしてる方々に、是非。
-

-
MASERATI
Pyramid Of The Sun
アメリカ発のインストゥルメンタル・バンド、MASERATI。イタリアのスポーツ・カーから取られたバンド名の通り、スタイリッシュで疾走感のあるサウンドを巻き起こす4 人組だ。サイケデリック、パンク、エレクトロをプログレ・テイストに昇華した新感覚の音楽性が凝縮。生楽器と電子音の融合は非常に繊細で、ストーリー性に溢れている。絶えず続くストイックな緊張感が逆に心地良い。 昨年事故で他界したドラマーであるJerry Fuchs の遺作ともなった今作。終曲「Bye M'Friend, Goodbye」は冒頭の透き通るコーラスが印象的で、非常に晴れやかなロックンロール・ナンバーだった。Jerry に捧げる曲なのだろうか。彼らの音には、言葉よりも確かな“思い” が詰まっている。
-

-
MASH
黄金の季節
10周年記念のベスト盤をひとつの大きな節目に、オリジナルとしては久々となる7枚目のアルバム。今作はMASHが年齢を重ねるなかで、輝かしかった少年時代にフォーカスした自伝的作風に仕上がっている。それは"昔は良かった"という懐古趣味ではなく、現在の自分と照らし合わせて、年齢に関係なく"青春はずっと謳歌できるんだ"と力強く宣言しているよう。内側から沸々と滲み出た生命力を感じさせる楽曲も最高だ。MASHの透き通った歌声を軸にラップ調のニュアンスを取り入れた曲調もあり、自由度の高いヴォーカルは彼ならではの魅力だろう。音楽的にはピアノ、アコギ、ホーンなどを導入し、バンド編成でフォーキー且つ壮大な曲世界を描き上げている。芯の強さと人肌の優しさに満ちたサウンドはどこまでもあたたかい。
-

-
MASH
MASH BEST 新しい星座 2006-2015
デビュー10周年を記念してリリースされる初のベスト・アルバム。ベスト盤と言えば過去にリリースした順番で収録するのがセオリーなのかもしれない。それはそれで素敵な1枚になると思うが、MASHのベストはひと味違う。これまでリリースした6枚のアルバムからチョイスした楽曲と最新曲を"新しい星座"を作るかのように並べて組み合わせる。そうすることで不思議と昔の曲が新曲かのように楽しめるベスト・アルバムに。さらにMASHの初期衝動を感じられるTrack.3「21世紀少年」から最新曲となるTrack.10「Lovers」の音楽性の変貌にも驚かされるが、何よりもブレずにあるのはシンプルに愛を叫び続けていること。きっと、光り輝く星のように、今と昔を繋ぐ歌に見惚れてしまうはず。
-

-
MASS OF THE FERMENTING DREGS
ゼロコンマ、色とりどりの世界
2007年EMI MUSIC JAPAN主催のオーディションにて最優秀アーティストに選ばれあのNUMBER GIRLのプロデュースでも知れれるDave Fridmannを迎え2曲をレコーディング。同年FUJI ROCKに出演するなど華々しい活動をしてきたマスドレことMASS OF THE FERMENTING DREGSがメジャー・デビュー後、初のフル・アルバムを完成させた。彼女達の持ち味である切れのある轟音ギター・サウンドと疾走感はもちろんの事、キラッと光るメロディ・ラインもまた健在で、バンドの力を十二分に発揮した力作。描き出す世界感は混沌としているもののそこから見える女性ならでは繊細な感性が聴くものをグッと惹き付けていくとても魅力的な作品だ。
-

-
MASTERLINK
SUPER SPEED E.P
各方面から話題を呼んだメジャー・デビュー作『Traveling』に続く、MASTERLINKの2ndシングル。最初聴いた時、一番に浮かんだのはやはりSUPERCAR。だが、メロディとサウンドと歌詞の3者が偶然出会い、互いに互いを尊重し高め合うような、その整合性すら信じたくなる黄金比を奏でていた彼らと比べてしまうと、このバンドは、あの高みにはまだ達していない。だが、3者のバランス自体はとても近い。メロディとサウンドという音の枠からはみ出ない言葉と、言葉が描く世界に彩りを与えながらも、やはりその世界からはみ出さないメロディとサウンド。3者全てが同じものを描こうとしているからこそ、「SUPER SPEED」は文字通り走り抜ける歌として完成しているし、そのサウンドスケープは水彩画で描く風のように爽やかで鮮やかだ。今はまだ少し保守的なこの均衡が破られた時、彼らはきっともっと輝く。
-

-
MASTERLINK
Traveling
2002年に結成され、様々なコンテストや音源配信サイトでも人気を獲得してきた3ピースMasterlinkのデビュー・シングル。柔らかくポップなエレクトロを軸にしたそのサウンド・スタイルは、一言で言えばSUPERCARチルドレンというところか。ほぼ英詞の耳馴染みのよいメロディと透明感のあるNARUの歌声も合わさり、キラキラとしたエレクトロ・ポップとなっている。トレンドのツボを押さえたプロダクションの完成度の高さはなかなかのもので、新人とは思えない。ただ、しっかりとした実力を感じさせると同時に、その的確なツボの押え方が少しお行儀良すぎるように感じてしまうところもある。これから登場するアルバムでこの良質なエレクトロ・ポップにどういう個性と遊び心が加えられていくのか。まずは注目してみたい。
-

-
MATCHBOX TWENTY
North
10年ぶりとなる通算4作目のフル・アルバム。1996年のデビュー作が1300万枚を売り上げた実績を持つアメリカを代表するロック・バンドから放たれるサウンドは、まるで彼ら自身が音楽の魅力を改めて楽しんでいるかのようにフレッシュでいて爽快な響きに満ちている。今作は真骨頂ともいえる深みのあるヴォーカルを堪能できる「Parade」からはじまる。そしてTrack.4の痛快なまでのダンス・チューン「Put Your Hands Up」から「Our Song」へと続く流れは、いまのバンドの充実ぶりと新たなスタート地点へ立つことに成功した清々しいまでの勢いを存分に感じとることができるだろう。もはやジャンルすら超越してみせた圧倒的な曲の力そのものに感動。
-

-
MATIAS TELLEZ
Clouds
瑞々しい天然色のポップ・ナンバーを鳴らすノルウェーの天才、MATIAS TELLEZのセカンド・アルバムが到着した。相変わらず素晴らしいメロディといい、ギター・ポップ、柔らかな光を放つソフト・ロック、そして、ディスコティックなナンバーも、澄み渡るような爽やかさを感じさせる天性のポップ・センス。若々しく跳ね回るポップ・ナンバーとともに、スキップでもジョギングでもサイクリングでもしたくなるね。しかも、海外ではSONY/BMGとサインしながら、日本ではファースト・アルバムと同じく、大阪のレーベルFLAKEからのリリースをMATIAS TELLEZが選択したという事実。天才の上に、何ていい奴なんだ。一曲目の「You」からラスト・トラック「Dreams」まで、颯爽と駆け抜けるピュアなポップ・アルバム。
-

-
Mat. McHugh
Love Come Save Me
オーストラリアを代表するオーガニック・ロック・バンドTHE BEAUTIFUL GIRLSのフロント・マンMat. McHughによるソロ・プロジェクト。シンプルで心に響くアコースティック・ギターやハーモニカの音色は、常に様々なジャンルを取り入れ新しいものを生み出してきた彼の、音楽の原点とも言える。余計なものを取り払い、等身大のMat. McHughを、惜しげもなく見せつけてくれる今作。軽快でありながらゆったりと流れるリズムは、晴天下の浜辺で海を見ながらのんびりと聴きたいものである。これからやってくる暑い夏をさわやかに乗り切るために、手に入れて間違いはない一枚。マリン・スポーツやドライブにも最適な曲が詰まっている。
-

-
MATT AND KIM
Grand
やはりこの男女デュオを紹介するにあたり、避けては通れないのが「Lessons Learned」の全裸PVだ。公開されるやたちまちネット上で火が付き、昨年のMTV AWARDSにて画期的な作品に贈られるBreakthrougt賞を獲得。最近ではERYKAH BADUもインスピレーションを受け同様のPVを発表し大きな議論を巻き起こしたが、シンプルながらインパクトの強い、そして端的に持ち味である無邪気なまでに音と戯れる姿勢が表現された素晴らしいものだ。キーボード&ドラムのミニマムなスタイルで、アルバムにはチープながらクセのあるフックを随所に散りばめたパーティ・ソングが詰まっているが、どこかメランコリー漂うメロディが印象的。楽しい時間は永遠に続かないことを理解しているのか?2人が紡いだのは、モラトリアムの夜明けなのかもしれない。
-

-
Matthew Herbert
One Pig
BjorkやREMなど、数多くのアーティストのプロデュースを手掛けるエレクトロニカ・サンプリング界の重鎮、Matthew Herbert。彼の三部作となる「One」シリーズの完結作が本作『One Pig』だ。第一部作『One One』では"ある男の一日"をコンセプトとし、第二部作『One Club』は"とあるクラブに集った人達"の音を、そして本作では、なんと豚の誕生から死まで...そして人に食される瞬間までをサンプリングして作られた!豚の一生をドキュメントしながら、生活音から音楽を再構築するのは、まさに鬼才(奇才)と呼ばれる彼の為せる技。本来逃避的とも言われるこうしたクラブ・ミュージックだが、ここで聴こえる豚の鳴き声は、どんな歌声よりも確かなメッセージを持っているように感じる。
-

-
MAXIMO PARK
Too Much Information
前作『The National Health』から2年ぶりの5thアルバムは、地元、英・ニューカッスルにてセルフ・プロデュースで制作。Gil Nortonを迎え制作されたソリッドでロック色が濃厚な前作とはまたちがった、繊細な陰影のあるギター・サウンドに仕上がっている。彼らならではの憂いあるメロディから色っぽさがにじみ出てきて、雰囲気のあるアルバム。前作でPIXIES的に鋭くタフに尖らせたポップ感を、今一度英国風に還元して、毒っぽくユーモラスなサウンドへと編み上げていて面白い。さりげなくも濃い印象を残すエレクトロや、細やかなギターのフレージングなど、空間をたっぷりと使ったアンサンブルになっているので、聴くほどに気づきのある作品だ。『The National Health』の邦盤化と4月には久々の来日公演も決定と、俄かに騒がしくなってきた。
-

-
MAXIMO PARK
The National Health
ダンス・アクトを中心に良質なギター・バンドも多く抱える老舗レーベルWARP RECORDSだが、想えばこのバンドが出発点だったのは懐かしい。イギリスはニューキャッスル出身のロック・バンド、MAXIMO PARKが4thアルバムをリリースする。プロデュースはPIXIESやFOO FIGHTERS、そしてMAXIMOでは2ndアルバムも手掛けたGil Nortonがカムバック。過去にバンドの表現の幅を拡げた重要人物だが、今作でもその手腕は遺憾なく発揮されている。UKのひねくれセンスを持ちながらもUSオルタナの憧憬を見つめるようなロックンロールは不変だが、4枚目でも瑞々しい勢いと潔さを保持しているのは素晴らしい。00年代デビューの現在中堅どころはセールス面の苦戦やメディアの露出低下などなにかと逆境に立たされるが、このパワフルなメロディは多くのリスナーを鼓舞するだろう。
-

-
Maxn
轟音
"感情爆発!!"をコンセプトに、台湾やアメリカでもライヴを行うなど、海外では"PIGAMAN"の名で活動する府中発3ピース・ガールズ・バンド、Maxn(読み:マクスン)が初の全国流通盤をリリース。攻撃的でダークなメロディに乗せて歌われるのは、誰しもが感じたことがあるであろう嫉妬や葛藤、夢。思春期の今しか出せないその感情を飾らずまっすぐにぶつけてくる彼女たちの音楽は、きっとどの年代の人の心にも刺さるはず。ラストを飾る「幸あれ」には彼女たちの思い描く未来への希望や"一緒に幸せになろう"という想いを感じる。"これからも進んでいくぞ(Go on)"という強い覚悟が込められたタイトルのとおり、素直な心を剥き出しにした彼女たちの"今"が表現された1枚。
-
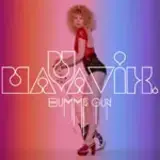
-
Maya Vik
Bummer Gun
ノルウェー出身のマルチ・アーティスト、MAYA VIKのソロ2ndアルバム。元々はノルウェーで国民的人気を誇るバンド、MONTEEにベーシストとして在籍し、そのルックスからモデルとしても活動するという才色兼備な彼女。前作から短いスパンでリリースされる本作は、とても煌びやかなシンセポップ・アルバムに仕上がっている。ディスコ、ファンク、ジャズやフュージョンも消化しながら、時に弾けるようなキュートネスを、時にしっとりと絡みつくようなメロウネスを醸し出すその楽曲は、全体的にキラキラしつつも、奥ゆかしさも感じさせて、実に味わい深い。スレンダーな身体つきとは裏腹に、表情には子供のようなあどけなさを残す本人のヴィジュアルがそのまま音になったような、魅力溢れる1枚だ。いい女はいいね。
-

-
Maya Vik
Chateau Faux-Coupe
70年代のジャズやフュージョンと80年代のディスコやファンクを混ぜ合わせて、その中に90年代のヒップホップを溶かし込んだようなサウンドはどこか懐かしい。しかしそこにMaya Vikの艶かしい歌声が絡みついていくと、近未来的とでも言えそうな、ちょっと浮世離れした雰囲気が広がり、全体のサウンドが新鮮に響きだす。ノルウェーのグラミー賞を受賞したロック・バンドMONTEEのベーシストであり、A-HAのメンバーであるPaul WaaktaarのバンドSAVOYでもプレイしていたという経歴を持つ彼女。このデビュー・アルバムではすべての楽器を自身で手がけ、グラミー賞を4度受賞した、プロデューサー/エンジニアのJimmy Douglassがミックスを行っている。
Warning: Undefined array key "$shopdata" in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/list/158877.php on line 27
-
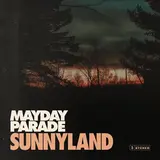
-
MAYDAY PARADE
Sunnyland
2000年代を代表するエモ・バンドのひとつ、MAYDAY PARADEのニュー・アルバムは、長年所属していたFearless Recordsを離れ、この春に契約が発表されたRise Recordsからのリリースとなる。これまでコンスタントに作品を発表してきた彼らの集大成とも言えるような今作は、王道エモの美しいメロディはもちろん、アップテンポなポップ・パンク、切ないアコースティック・バラードなど、バンドの持ち味が余すところなく発揮された充実の内容に仕上がった。また、Howard BensonやJohn Feldmann(GOLDFINGER/Vo/Gt)といった大物プロデューサーともタッグを組んでいるのも納得な重厚感のあるサウンドで、激しい曲としっとりした曲の振れ幅の広い作品を、ダイナミックにまとめ上げている。
-

-
the McFaddin
Rosy
京都の5人組ロック・バンド、the McFaddinの1stフル・アルバム。メンバー・チェンジを経て昨年1月より現体制として本格始動したようだが、そのサウンドはひと言で言えば"めっちゃ洗練されてる"。英語詞とか日本語詞とか関係なく、リズム感やメロディの作り方が洋楽的。洋楽っぽい=かっこいいではないが、多様な音楽がバックグラウンドにあるのが滲み出ている音楽は、やはり聴いていてワクワクする。エレクトロのキラキラしたエレメントも、インディー・ロックの泥臭さも、ブラック・ミュージックの色気もあり、80'sや90'sの味わいあるポップと今風のポップが交わった感覚も新鮮だ。難しいことを考えずに誰もが親しめる音楽性なので、気になったらとにかく聴いてみて!
-
-
MCFLY
Young Dumb Thrills
2016年のツアー以降バンドを休止し、ソロ活動などそれぞれのキャリアをスタートさせたUK発ポップ・ロック・バンドが再集結。オリジナル・アルバムとしては10年ぶりの作品が完成した。先行してリリースした、軽やかできらめきを詰め込んだポップ・チューン「Happiness」や、BLINK-182のMark Hoppus(Vo/Ba)をフィーチャリングした「Growing Up」など、全12曲が収録。ロック感の強いパワフルな曲が多かった印象だが、一呼吸置いて改めて4人のバンドで放つサウンドはアレンジの自由度が広がって、エバーグリーンなメロディを生かすような芳醇でマジカルなものとなっている。ボーイズ・バンドという荷を自然に下ろして、大人の佇まいや、ほど良く力が抜けた感じが音にも映る。
-

-
MEET ME @ THE ALTAR
Model Citizen
米フロリダを拠点に活動する若きポップ・パンク・トリオが、老舗名門レーベル Fueled By Ramenからメジャー・デビューEPをリリースした。"ポップ・パンク・バンドがもっと世に出るべき!"という想いで結成されたという彼女たち。先行公開された「Feel A Thing」、「Brighter Days (Are Before Us)」を筆頭に、威勢のいいアグレッシヴなサウンドに、Edith Johnsonの力強く瑞々しい歌声が輝くカラッとしたロックを響かせている。キャッチー且つオーソドックスな中に、活気に満ちたエネルギーが凝縮され、ユニークなフレーズが仕掛けられた楽曲は、3人と同世代の若者だけでなく、幅広い世代の心を捉え"明るい未来"を信じさせてくれそうだ。
-

-
MEG
KISS OR BITE/MEG ZOMBIES+SAVE/MEG
“MEG”“MEG ZOMBIES”の2つの名義でシングルを同時リリースするMEG。MEG ZOMBIES名義の「KISS OR BITE」は作曲・編曲にTeddyLoid、ギターにNARASAKI(COALTAR OF THE DEEPERS、特撮)を迎えたダークでロックなエレクトロ・ナンバー。鋭いビートとギターが交錯し、キュートなMEGのヴォーカルと息遣いも小悪魔的に響く。一方MEG名義の「SAVE」は8bitやゲーム・サウンドを大胆に取り入れ、MEGが手掛けたリリックもRPGゲームを彷彿させるワードが並ぶ。ZOMBIESとは相反的に彼女のヴォーカルもどことなく機械的だが、それがゲームの主人公である“凛とした女戦士”の存在感を醸している。白と黒のMEGのギャップを楽しんでみてはいかがだろうか。
-

-
Mega Shinnosuke
君にモテたいっ!!
UKロックを彷彿とさせる音選びや、中華料理店を舞台にあどけない恋模様を描いたMVが印象的な「愛とU」、思わず身体を揺らしたくなるようなダンサブルなビートと、フィーチャリングに迎えたchelmicoとMegaの歌声の掛け合いが心地よい「あの子とダンス(feat.chelmico)」等、収録される8曲全てが"ラヴ・ソング"だという本作。誰もが一度は経験したことがあるであろう出会いと別れ、好きな人を一途に想うことへのときめきやもどかしさを綴った歌詞は胸キュン必至だ。ロックやヒップホップといった様々なジャンルを軸に、彼の提示する新たなジャンル"MEGA POP"の懐かしさを感じつつもキャッチーなサウンドは、老若男女問わず幅広い層にモテること間違いなし。
-

-
Mega Shinnosuke
hello.wav
楽曲制作やアートワーク、映像製作をすべて自身で行う新世代のアーティスト、Mega Shinnosukeが約2年ぶりとなるEP『hello.wav』を配信リリースした。ヒップホップやハイパーポップ、シューゲイザーなど様々なジャンルが混在し、"メガシンノスケ節全開"になったという今作には、トラックの強さや等身大の愛をメロディアスに歌うハイトーン・ヴォイスが印象的な「hello shoegaze...」や、キャッチー且つダンサブルなサウンドと、情報過多な現代を軽やかに駆け抜けていくような歌詞が小気味よい「iPhone feat. Skaai」など全4曲を収録。彼の提示する新たなジャンル"MEGA POP"の魅力をこれまで以上に感じ、時代にとらわれず自由に生きていくパワーを貰えるような1枚だ。
-

-
Meg Baird
Seasons On Earth
フィラデルフィアのフォーク・グループESPERSのヴォーカルでもある歌姫Meg Bairdのセカンド・ソロアルバム。70年代にタイムスリップしたかのようなフォーク系の音で、ギター1本の弾き語りの曲が中心だが、どこか新鮮にも聞こえるのは彼女の歌声の存在感が大きいかもしれない。ソフトすぎずシャープすぎずで、歌声というよりは楽器の一部のように周りの音と驚くぐらい同調している。とにかくシンプルで心地の良いサウンドなので、幅広い層に受け入れられるんじゃないかと思う。しかしこの清涼感はなんだろう。高原の朝の空気とどっちが爽やかか競えるぐらい気持ちが良い。アルバム・タイトルがぴったりで、四季の変化を一枚のアルバムを通して聴いているような気分になり、とてもリラックスできる一枚。
-

-
mekakushe
heavenly
あどけなさや脆さの中にも静かな意志を感じる女性ヴォーカルが好きな人だけでなく、音楽という物理で穏やかな気持ちになれるこの作品はぜひ試してもらいたいところ。タイトル・チューンのTrack.1はピアノとアコースティック・ギターの素朴さやナマ感と、ぎこちなく動く機械音のコラージュ、クラシカルとエレクトロの融合がユニークな体感を生む。ギター・リフに和のイメージがある「I & you」で少し日常の世界を感じさせつつ、極端に展開のない淡々とした「オフライン」では、自ずと自分に向き合うことに。歌詞の内容は刺さるが、森に光が差してくるような弦とシンセが混ざり合ったサウンドなど、この曲で深呼吸できる人は多いはず。フランス音楽の影響が色濃いメロディや和声をじっくり味わうのもいい。
-

-
Melanie Martinez
K-12
タレント発掘番組"The Voice"への出演をきっかけに、前作『Cry Baby』(2015年)でデビューした、シンガー・ソングライターのMelanie Martinez。お人形のようなルックスと、おもちゃの楽器などを使用したアーティスティックなポップ・サウンドに加え、少し毒のある"本当は怖い童話"的なほの暗い世界観で、"グロかわ"などとも表現された彼女だが、2作目となる今作でもその方向性は貫いている。ヒップホップやR&B的表現も、ソウルフルというよりは夜空に浮遊する魂というようなフワフワした感触だ。ドリーミーなのにそれでいて描いているのは現実の暗闇なのだから、これはまた多くのティーンエイジャーを闇に突き落としそうな、甘い甘い毒入り綿菓子だ。
-

-
MELiSSA
GATHERWAY
アイドル・グループ アイドルカレッジから派生したロック・ユニット、MELiSSAが新体制で1stアルバムをリリースする。新体制での新録はBLUE盤に収録された「UTPA(God Seven Ver.)」と、形態共通の「レクイエム」の2曲。前者は、個性的な歌声を持つ新メンバー3人が加わったことで、よりカラフルなライヴ・アンセムに生まれ変わった印象だ。後者は、別れと旅立ちのニュアンスを孕んだ歌詞をエモーショナルに歌い上げる壮大なロック・バラードで、今後のグループの歴史を語るうえで重要な1曲になっていくことだろう。そのほか松隈ケンタ率いるSCRAMBLESによる曲が多数収められ、ライヴで威力を発揮しそうなナンバーが揃った。本作を携えた新生MELiSSAの活躍に期待が高まる。
-

-
Mellow Youth
Flash night
2017年結成の5人組、Mellow Youthによる1stアルバムは、これまでリリースしてきた4枚のシングルからの4曲も含む全9曲を収録。ホーンもフィーチャーした本格派のR&B/ファンクをバックボーンに歌謡曲、ディスコ、バラード、シティ・ポップス、ゴスペルも消化した曲作りは、現在のシーンを見据えたものと言えるが、彼らはツイン・ヴォーカルのインパクトに加え、ギター・サウンドのユニークさでもその個性を際立たせている。心地よく歪みをきかせた色と、泣きを含んだフレーズがハード・ロックやフュージョンの影響を感じさせるギター・サウンドは、彼らのバックボーンを考えると、武器のひとつと言ってもいい。アーバンなバンド・アンサンブルに滲むバンドらしい熱はライヴになると、よりいっそう発揮されそうだ。
-
-
MELODY'S ECHO CHAMBER
Melody's Echo Chamber
南フランス出身の女性アーティストMelody ProchetがMELODY’S ECHO CHAMBER名義でリリースするデビュー・アルバム。名義がそのままサウンドを示しているようなドリーミー・ポップがベースだが、サイケデリックやエレクトロニカ、そしてクラシックの要素まで感じられる幅広いサウンドに仕上がっている。そんなサウンドに乗る彼女の歌声は柔らかかったりけだるかったり、力強かったりととても魅力的。時折聴こえるフランス語も楽曲によく馴染んでおり、神秘的な雰囲気を演出している。全体的にとても聴きやすく、可愛らしい彼女のルックスも相まって、商業的な成功も見込めるのではないだろうか。一聴するとシンプルに聴こえる楽曲でもじっくり聴き込むと複雑な音作りになっており、何度もリピートしてしまう中毒性を生んでいる。
-
-
Beth Orton
Kidsticks
イギリスのシンガー・ソングライターによる4年ぶりの新作。夫であるSam Amidonの協力も得ながらアコースティックなセクションを突き詰め、現代のフォークロア・ミュージックとして仕上げた2012年の前作『Sugaring Season』から一転、本作ではAndrew Hung(FUCK BUTTONS)を共同プロデューサーに迎えたエレクトロ・アルバムに大展開。冒頭「Snow」のANIMAL COLLECTIVEを思わせるトライバルなグルーヴなど新鮮な響きに引き込まれる。しかし彼女のどこか所在無げでハスキーな声と紡ぐメロディにブレは1ミリもなし。どんなサウンドであってもエヴァーグリーンな輝きを持つ歌に感嘆。長いキャリアの中で肩の力を抜いて、新たな試みを楽しみながら作られたことのわかる風通しの良い作品。
-

-
MEMEMION
Cantaville
'21年4月に結成された5人組バンド、MEMEMIONによる愛と許しを謳った5thシングル。セクションごとに違う階層へワープするように転調を重ねるアッパー・チューンで、それを乗りこなす各メンバーのプレイも複雑で聴き応え抜群。しかし理論武装しすぎず、時には衝動に身を任せるなど、ある種の力技も共存しているバランスが面白くスリリングだ。また、こういった曲を小難しいものとして聴かせず、アンサンブルの疾走感やメロディの歌力でもって、キャッチーな音楽に落とし込んでいる点からバンドの手腕が見て取れた。エドガー・サリヴァンのギタリストで、このバンドでは曲を書いて歌を歌う坂本 遥が、音の人であると同時に言葉の人であったことを感じさせる歌詞表現も興味深い。
-

-
memento森
Tohu-Bohu
神戸発の4人組ミクスチャー・バンド、memento森による初の全国流通盤アルバム。バンド名の"memento森=死を想う"が表すとおり、このバンドが貫くシニカルな世界観は決して夢や希望に溢れたものではない。宮地 慧(Vo)がラップで切り込む詞世界は[すぐ言う"死にたい"](「UNO」)、[ご立派な悲観もシェアして拡散](「sick hack」)、"老いも若きも緩やかに自殺"(DabaDance)と、豊かさや平和と引き換えに、どこか諦念がはびこる現代社会の生々しいリアルだ。その混沌とした言葉とリンクするように、ヒップホップ、ロック、ファンク、レゲエと雑多な嗜好性を反映させたサウンドはカオス。わかりやすいキャッチコピーでカテゴライズすることのできない人間そのものを暴く怪作だ。
-
-
MEMORYHOUSE
The Years
カナダのトロント出身のドリーム・ポップ・デュオMEMORYHOUSE。本作は昨年リリースしたEP『The Years』を再録音し、新曲を2曲追加したもの。幻想的でどこか物悲しいシンセ・ポップに柔らかな女性ヴォーカルが自然に溶け合い、無限の海の中を漂っているような気持ちにさせてくれる。人工的な音の中に自然的な要素もあり、冷たい音の中に温かみもあって、相反する2つの要素が上手く融合されているように思う。眠る前に聴いたら絶対良い夢を見ることが出来そうだと思うけれど、個人的には全曲聞き終わると思わずまたリピートしてしまうほど中毒性があるので逆に眠れないかも。容姿も音楽もアートワークもとにかく優美で、来年リリース予定のフル・アルバムにもますます期待が高まる魅力的な一枚。
-
-
MEMORY TAPES
Grace/Confusion
デビュー以降、グローファイ/チルウェイヴの旗手として評価されてきたMEMORY TAPES。チルウェイヴがUSインディの一大潮流となった去年リリースされた『Player Piano』は、シーンの動きとも相まって、大きな話題になった。チルウェイヴというジャンル自体は今年に入り様々な形に細分化されていったが、このMEMORY TAPESも、本作で新たな顔を見せている。全6曲約40分と長尺曲が並んだ本作は、それぞれの楽曲で浮遊感漂うアンビエントや、ドラマチックなエレ・ポップ、躍動感のあるトライバル・ビートなど様々なエッセンスを盛り込み、音楽的に多彩な、実験性の高い仕上がり。しかし、そんな混沌としたサウンドを、流麗なメロディ・センスと構成力でむしろエンタメ性の高い作品へと昇華している点は、流石のひと言。
-

-
V.A.
KITSUNE MAISON COMPILATION 8
KITSUNE MAISON、この間7が出たばかりなのに、もう8がリリースですか。相変わらずのスピード感。それだけ、面白いインディ・バンドが多いということなのか、それとも流行のサイクルがさらに加速しているということなのか。今回も、TWO DOOR CINEMA CLUBやDELPHICといった今が旬のアーティストから、THE DRUMS、MEMORY TAPESを始めとした、これからのアーティストをコンパイルした充実の内容。ディスコ・ポップからエレクトロ、インディ・ロックまで、ヴァラエティの豊富さとコンピとしての統一感を両立させているところはさすがの仕事。今の潮流をしっかりと追い続けているからこそ・・・と、言うよりは先導しようとしているからこそと言うべきか。
-

-
THE MEN
New Moon
爆笑してしまった、最高の賛美として。ブルックリンのシーンにおいてMGMTやDIRTY PROJECTORSらとは違い、むき出しの熱量でガレージ・パンクやサイケを1つの鍋に放り込んできた彼らが、今回は山奥にガレージをおっ立てたようなアプローチを展開。特徴はラップ・スティール・ギターやピアノ、マンドリン、ハーモニカなどの素のサウンドが醸すアメリカン・ルーツ・ロックの匂い。が、そこは一筋縄でいかないこのバンド。Neil Young & Crazy Horseの曲が初期SONIC YOUTHのメンタリティを通したような「I Saw Her Face」とか、ホワイト・ブルースっぽいギター・ソロがありつつ、質感はガレージ・サイケな「Supermoon」とか。ローファイで生々しいサウンドでありつつ、ライヴじゃ体験できないスタジオ盤ならではのプロダクションも魅力。
-
-
THE MEN
Open Your Heart
NYブルックリン出身の4人組パンク・バンドの3枚目のフル・アルバム。ガレージ・ロックやハードコア・パンクをベースにした楽曲を中心にしているが、ただのパンク・バンドとカテゴライズ出来ないほどあらゆる要素を取り込んだ振り幅の大きい楽曲が特徴的だ。今作は冒頭2曲でストレートすぎるパンク・ロックを聴かせたかと思えば、次に一転してサイケデリックな浮遊感のあるインスト曲をもってくるあたりがとても面白い。そしてそこから繋がる「Please Don’t Go Away」、「Open Your Heart」、「Candy」といった完成度の高い楽曲が続くアルバム中盤の流れには思わず唸ってしまう。ノイジーだったりサイケデリックだったりアコースティックだったりするギター・サウンドが病みつきになり、一筋縄ではいかないバンドの魅力が詰まったアルバムだ。
LIVE INFO
- 2025.10.16
- 2025.10.17
- 2025.10.18
- 2025.10.19
- 2025.10.24
- 2025.10.25
- 2025.10.26
- 2025.10.27
- 2025.10.28
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号























