DISC REVIEW
M
-

-
mol-74
colors
心を真っ白にしてひとつずつ聴き進めていくと何もないキャンパスが色づいていく、そんな"色"がコンセプトの6thミニ・アルバム。繊細なピアノの音色で始まるTrack.1「hazel」。美しくも儚い武市和希(Vo/Gt/Key)のファルセットがまるで音の一環のように耳に入り、序盤からグッと惹き込まれる。Track.4は補色を意味するタイトルの「complementary colors」。徐々に音が重なる幻想的な音色は、まさにmol-74の世界観そのもの。ラストを飾るのは「tears」。"同じ涙を流せないんだ"というフレーズは、透明な涙にはいろんな感情がこもっていて、それは人と一緒にはできない。あなたにしかない"色"があると伝えてくれる。そんな今作『colors』も、あなた色に染めてみてほしい。
-

-
mol-74
kanki
これまで、季節に喩えるならば一貫して"冬"を鳴らしてきたmol-74。この全国流通盤3作目においても、「プラスチックワード」、「ゆらぎ」を筆頭に従来の冷たく繊細な音を研ぎ澄ませつつ、「アンチドート」では目に見えない温もりを歌い、"君の手をひいて連れ出すような歌を歌うよ"と宣言する。そしてその先に用意されていたのは、雪解け、芽吹きを知らせる「開花」。今作はあらゆる解釈ができる"kanki"と名づけられているが、この曲が見せる目がくらむほどの光が溢れるサウンドスケープ、歌詞のとおり"魔法の声"のような幸福に満ちたコーラスが告げる新しい季節の訪れは、"歓喜"と呼ぶほかなかった。小気味よいリズムと今までにない疾走感で駆け抜ける「%」も、新境地を開こうとする彼らの決意表明のように感じる。
-

-
mol-74
まるで幻の月をみていたような
"昨日見た夢を上手く思い出せないように、僕らは大切なことを忘れていく"というテーマを、水面に揺れる幻の月という情景描写に託した2作目の全国流通盤。音と音の隙間を大切にしたサウンド作りにも、多くは語らずに行間を読ませる歌詞にも、聴き手が想像力を膨らませるための余白がある。柔らかなハイトーン・ヴォイスはときに日の光を乱反射させながらあたたかみを放ち、ときにどこまでも澄み渡る世界を冷たく提示する。この"どちらにも受け取れる"感じ、mol-74を色に喩えると白だなあと思う。広がり続けるこの白さが、彼らの大きな特徴だ。人混みに何となく疲れたとき、私はmol-74と一緒に独りになる。お気に入りの本のページを開くみたいに、このアルバムの1曲目を再生する。
-
-
mol-74
越冬のマーチ
それは新雪のように真っ白。降り積もった雪にそっと触れて、手のひらの温度でじんわりと溶けていくあの瞬間のように儚い。3枚目のミニ・アルバムとなる今作でついに京都出身の3ピース、mol-74の音楽が全国流通される。硝子細工のように繊細で、ひんやりとした武市和希の歌声で歌われる甘美なメロディと、そこに重なる賛美歌のようなハーモニー。楽曲の持つ壮大なスケールとドラマティックな世界観は深く、どこまでも澄んでいる。"いつも言葉は足りないままだ"と歌う3人の気持ちが、ひとつひとつの音に刷り込まれているようだ。誰よりも冬を歌ってきた彼らが本当に見つめるその先は、春。冬の冷たさや息の白さを越えるためにこのマーチを持って、胸に宿った種を芽吹かせる。
-

-
MOLE HiLL
普通でいいこと?
ストレートなメロディに熱いメッセージを託したロック・サウンドでライヴハウスを席巻する京都発の4人組ロック・バンド MOLE HiLLがリリースする約1年ぶりの新作。まず今作はタイトルの"普通でいいこと?"で、バンドからリスナーに向けて"普通の幸せとは何なのか?"というクエスチョンを投げ掛ける。その答えが今作に収録される全6曲だ。"生きているという事は 続いてるって事なんだ"と確信を持って歌うミディアム・バラード「モノゴコロ」を始め、アコースティックな演奏に乗せたウェディング・ソング「shiny blue」など、様々な角度から幸せの在り処を描いている。新しい何かに挑戦することも(「始まりの音」)、失敗から立ち上がることも(「99+1」)、すべて幸せなことだと言い切る強さこそ、いまのMOLE HiLLのたくましさだと思う。
-

-
MOLE HiLL
Time
誰もが生きる今この一瞬一瞬を輝かせるための音楽を鳴らし続けたい。それが京都発の4人組バンド MOLE HiLLが1stフル・アルバムを作るうえで見いだしたバンドの確固たるテーマだった。今作にはこれまでにMOLE HiLLがライヴで披露してきた楽曲の中から9曲をリアレンジして収録。2曲の新曲も加えたことで、バンドの過去と今を総括する集大成の1枚となった。プロデューサーには阿久津健太郎を起用。サウンド面でもバンドの新たな可能性を切り拓いている。ドラマチックなストリングスのアレンジが疾走感を掻き立てる「変わりゆく世界と君」、ブラス・セッションがいっそうカオスを生んだ「Release」など、その丁寧な音作りにもバンドの今作にかける意気込みを感じた。
-

-
MOMA
MOMA EP
蓄音機で音楽を聴く時の、レコード盤上に針を置いたときの様な"ジーッ"という懐かしい音から始まる、東京発4人組インスト・バンドMOMAの1st EP。しばらく経って流れる「やわらかいことば」の繊細なピアノの旋律にうっとりとしてしまう。その後「SUN」、「Two Way Light Delight」と続き、ギターの叙情的なメロディにミニマルなドラム、ベースが織りなす表情豊かなサウンドが繰り広げられる。エモ〜ポスト・ロックを基盤としながらも、独自性と可能性を秘めている彼らの澄み渡った空気感は、シビアな現実から心身ともに解き放ってくれるような感覚を与えてくれる。身を切るように寒い冬の朝、ホット・コーヒーでも飲みながらこの作品をじっくりと味わいたいものだ。
-

-
MONGOL800×WANIMA
愛彌々
以前より親交があり、イベントなどでの共演もあったモンパチとWANIMA。昨年のラジオ番組でキヨサク(Ba/Vo)とKENTA(Vo/Ba)が対談した際の、"いつかコラボレーションしよう"が実現した。タイトル曲は両者のコラボ曲、その他互いが曲を提供し合った曲と、互いのカバー曲という全5曲で構成した濃密な1枚になった。言葉の向こう、音楽の向こうに誰かの顔が見える、フレンドリーな歌を届ける両者だけに「愛彌々」はポップで強力なサウンドで、またいつでもこの歌のもとに集まれるような明るく、おおらかなメロディが冴える曲となった。リスペクトとともに、こんな曲を歌ってほしい願望も込められたのだろう。提供をし合った曲では両者新しい面が垣間見える。発展的な1枚であるところにバンドの姿勢が窺える。
-

-
MONGREL
Better Than Heavy
THE REVEREND AND THE MAKERSのJon McClureが、ARCTIC MONKEYSのMatt Heldersらと結成したプロジェクト、MONGRELのファースト・アルバム。Damon AlbarnにとってのGORILLAZ的なプロジェクトと捉えればいいだろうか。全編に渡って、ソリッドなロッキン・ヒップホップを繰り広げている。もともとJon McClureがロックに留まらず、HIP HOP、REGGAE/DUBなどにも振り幅を持つ人だけに、納得の出来である。「Hit Rom The Morning Sun」などで胆の据わったラップを聞かせる女性ラッパー、Pariz -1も注目したい存在だ。また、本作は二枚組みとなっていて、『BETTER THAN DUB』と題されたディスク2では、Adrian Sharwood先生が原曲をさらにスモーキーなDUBアルバムへと仕立て上げている。
-

-
MONICA URANGLASS
YIPSLIPS
ドラムレスの3人組が満を持して作り上げた3rdアルバム。前シングルに引き続き、セルフ・プロデュースを行ったことで、バンドのやりたいことが明確に形にできたのだろう。ロックの衝動性、ダンス・ミュージックの躍動感、エレクトロのキラキラ感、異国情緒漂うメロディ、人を食ったような歌詞などを総動員して、彼らにしか鳴らせない音を確立させている。しかもどの曲も口ずさめるメロやキャッチーなフックが仕掛けられているので、散漫な印象も与えない。それも作り手が心から音楽と戯れ、面白がっているからできることだ。様々なジャンルが横溢しているようで、無駄を削いだシンプルなフレーズの数々もポップ度に拍車をかけている。ジャンルの垣根やシーンの壁が少なくなりつつある今、有効に響く音源だと思う。
-

-
MONICA URANGLASS
PUXA
80年代のニュー・ウェーヴやダンス・ミュージックに感化されたサウンドがいくつも存在する中で、MONICA URANGLASSは異色の存在感を獲得している。一目で目を引く程に徹底された奇抜さ。バンドのアイコンである68 (Vo , Syn , Pro)を筆頭に、電子音をバンド・サウンドに落とし込んだ強烈な音を彼らは作り出す。1stアルバム『THE TEMPTATION X』時の「Jill United」などバンド・サウンドに後押しされた勢いのある楽曲と比べ、本作ではギラギラと意欲的なビートが目立つ。異端的な楽曲は全体としてストイックにまとめ上げられ、その中で一音一音がネオンのようにカラフルで、ヴィヴィッドで、ポップな粒として大きく跳ねる。グルグルと目まぐるしく展開するサウンドは円を描くようにリスナーを取り巻き、躍動的なグルーヴを生みだすのだ。懐古的でありながら斬新に変貌を遂げるサウンドはどこまで突き進むのか目が離せない。
-

-
MONICA URANGLASS
CORELESS.BLAH!BLAH!BLAH!
ロック×トランス「ロッカトランス」という言葉で自分達の音楽を表現して来たMONICA URANGLASSのニュー・シングルが登場。ハイテンション且つエネルギー溢れるライヴ・パフォーマンスで人気を集め、日本のインディーズ・シーンの中核になりつつある彼らの新曲は持ち前のキャッチーな魅力はそのままに、中近東風のメロディを取り入れるなど新たなチャレンジが伺える。タイトル・トラックである「Coreless, Blah! Blah! Blah!」は一つのリリックを繰り返す挑戦的なナンバー。『Coreless, Blah! Blah! Blah!』リリースと幸先の良い2010年のスタートを切った彼らには今年のロック・シーンをどんどんかき回していって欲しい。
-

-
MONO
Requiem For Hell
年間150本以上のワールドワイドなツアーを行い、日本人バンドとして世界のオーディエンスを多く獲得しているインスト・バンド、MONO。近年、逆輸入的に新しいリスナーから支持を得ている印象も。本作では、昨年日本でダブル・ヘッドライナー・ツアーも行ったSHELLACのSteve Albini(Gt/Vo)がプロデュース、録音、ミックスを担当。前作がメンバーのみによるコアな印象だったことと比較すると、ストリングスやピアノも参加し、剛柔のバランスも良く聴きやすい。18分近い表題曲もそぼ降る雨のようなプロローグから、意外な8ビート、そして叙事詩的なストリングスがドラマチックに躍動する。黙示録的なダーク・サイドと、その中でも新たに生まれくる命の美しさ。研ぎ澄まされた轟音と繊細さに身を任せたい。
-

-
MONO
For My Parents
世界規模で評価されている日本の4人組インストゥルメンタル・ロック・バンド、MONO。約3年半ぶりのリリースとなる彼らのニュー・アルバム『For My Parents』は、タイトルから窺えるようにアメリカのホラー・コメディー映画から取られたものだと推測でき、アルバムを通してひとつのストーリー性を感じさせる。大胆にオーケストラをフィーチャーした楽曲群は神秘的で壮大なサウンドスケープがあり、なおかつひとつひとつの音の輪郭をくっきりと鳴らすことで静謐な音響美を生んでいる。初期の彼らにあったノイジーなギター・サウンドによる獰猛性は影を潜めたが、その分、音の全ては丁寧に配置されていて、昏睡を誘い、すっと聴き手を音世界に浸らせる。別の次元で鳴っているようなサウンドだ。
-

-
MONOEYES
Between the Black and Gray
約3年ぶりとなる3rdアルバム。ヘヴィすぎず、だからと言って、決して軽いわけではなく、作為なんてひとつもない爽やかなメロディに、ただただ心が洗われつつ、全体の印象がビター・スウィートなのは3作目ならではの成熟なのか、新型コロナウイルス以降の気分の反映なのか。とまれ、そんななかでTrack.1のグランジィなリフやTrack.7のメランコリックなギター・ソロ、日本語で歌うTrack.11の芯の強さが鮮烈な印象を残している。前作に続いてScott Murphy(Ba/Cho)もTrack.4、Track.6、Track.8の3曲のソングライティングとヴォーカルを担当。細美武士(Vo/Gt)が作る歌とはまたひと味違う清涼感を作品に加えている。
-

-
MONOEYES
Dim The Lights
細美武士(Vo/Gt)によるポップ・パンク回帰とファンを狂喜させた1stアルバム『A Mirage In The Sun』から2年。もちろん、ポップ・パンクなんてひと言には収まりきるわけがなかったその1stアルバムのサウンドを、さらに磨き上げた2ndアルバム『Dim The Lights』が完成した。アイリッシュ・パンク調のTrack.6「Borders & Walls」ほか、Scott Murphy(Ba/Cho)が作詞作曲のみならずリード・ヴォーカルを務める3曲が加わったことで、MONOEYESのバンド・サウンドはよりユニークなものに。もちろん、ファンが期待している疾走感は申し分ないが、ギター・フレーズが多彩なせいか、シンプルな構成を意識しながら、1曲1曲はそれぞれに広がりが感じられるものになっている。
-
-
MONSTER大陸
marry
2012 年の結成以来、FUJI ROCK FESTIVAL、SUMMER SONICなどの大型フェスに出演を果たし、すでに4枚のアルバムをリリースしている彼らの初のメジャー流通盤。メンバー自らがピックアップした10曲に未発表曲2曲を追加してリマスタリングしたベスト盤となっている。強烈なブギーがブルース・ハープと共に飛び出してくるオープニングの「The Grip」を筆頭に楽曲群はブルースの影響を受けた、というよりもブルース・ロックそのもの。各プレイヤーが聴かせる圧倒的な演奏力はメジャー・シーンではなかなか聴けない本格的なもので、血沸き肉躍るリスナーも多いはず。こうしたジャンルを日本人のオリジナルに昇華する難しさは感じるものの"ブルースを次世代に届ける"という使命感を帯びた彼らは貴重な存在だ。
-

-
Montecarlo Scrap Flamingo
Hollow
Montecarlo Scrap Flamingoの4年ぶりとなる2ndアルバム。バンド名からまったくどんな音楽をやっているのか想像ができなかったのだが、聴いてみるとますます自分の想像の範疇を超えていた。高校時代をアメリカで過ごしたというイノウエヒロミチ(Vo/Gt)の世界観が存分に発揮されている楽曲たちは、オルタナティヴ・ロックに影響されたギターを中心にアレンジされているが、ヴィブラートがかったロング・トーンを聴かせるヴォーカルがクラシックHR/HM調だったりIggy Popふうにも聴こえたり、なんとなく不安な気分を掻き立てられるのが不思議。そんな中カルフォルニアの空を想って書いたという「405 NORTH」が小唄的で楽しい。異端というわけではないがなんとも形容しがたいこのニュアンス、間違いなく今の日本の音楽シーンにはない存在だ。
-

-
moon drop
拝啓 悲劇のヒロイン
ラヴ・ソングだけを歌い続ける三重県発のバンド、moon dropによる3rdミニ・アルバムが到着した。すでにライヴでの人気曲となっている「シンデレラ」は、爽やかでポップなサウンドとは裏腹に、"前みたいに側で笑ってくれないか"と未練が残る様を歌い、「僕といた方がいいんじゃない」では、"僕と別れてほんとブサイクになったな"とディスりつつも、戻ってきてほしいと皮肉に嘆いている。"拝啓 悲劇のヒロイン"と題しているが、そんなヒロインに気持ちが残っているのは主人公のほうなのだ。彼らの楽曲は浜口飛雄也(Vo/Gt)自身や他者の恋愛体験がもとになっているぶん、等身大で聴き手の胸を打つ。心のどこかに引っかかっていた忘れられない恋愛を想起させる、moon drop渾身のラヴ・ソング集となった。
-

-
MOONRIDERS feat.小島麻由美
ゲゲゲの女房のうた A Ge Ge Version
映画版『ゲゲゲの女房』のエンディング・テーマである本作は、MOONRIDERS feat.小島麻由美=鈴木慶一と小島麻由美のデュエット・ソングとなっている。正直、一世を風靡した大ヒット・ドラマの映画版だとかは、どうでもよくなってしまいそうです。兎にも角にも、ヴォーカルが素晴らしく良いのですもの。デュエットは、交互に歌い、節目節目で一緒に歌うという、決まりきったスタイルで、極めてシンプルでありながらも、タンゴを踊っているように、軽快で楽しい。共に希有な存在感と活動スタイルを貫く両者の共演だもの、当然の結果だったのかもしれないが、胸躍らせる、この躍動感にはあっぱれとしか言いようがない。是非、ここで親交を深めてアルバムとか出しちゃって下さい。
-

-
MOP of HEAD
Aspiration
ダンス・ミュージックが多くの人に聴かれるようになる一方で、その定義が曖昧になってしまった現在のシーンに対するMOP of HEADからの回答と言えるミニ・アルバム。バンドの復活を印象づけた2015年の『Vitalize』の延長上にある躍動感に溢れた作品ではあるけれど、彼らが考えるダンス・ミュージックを提示するため、生楽器を一切使っていないテクノ・ナンバーのTrack.5「Acid Pilot」を始め、"人力"、"インスト・バンド"というもともとのバンド・コンセプトにこだわらない多彩な全6曲が揃い、さらに広がったバンドの可能性を印象づける作品に。それでも失われないメロディ・オリエンテッドな魅力は、やはり一番の聴きどころだ。UCARY & THE VALENTINE、向井太一をゲストに迎えたヴォーカル・ナンバーも2曲収録。
-

-
MOP of HEAD
and Touch You
インスト・バンドである彼らがヴォーカル・トラックにアプローチした前作『Vitalize』の挑戦が発展する形で完成したと言えるのでは。様々なダンス・ミュージックに対して、熱度満点のバンド・サウンドで挑む男女4人組の新作は、全5曲がヴォーカル・トラックとなっているが、全曲でゲスト・ヴォーカルを招いているところにバンドの志の高さが感じられる。前作同様、EDMを始め、流行に安易に与したくないというバンドの思いは、ファンキー且つR&Bの影響が色濃いトラックからも窺える。だが、SUPER BEAVERの渋谷龍太を始め、ロック畑を含む多彩なヴォーカリストの顔ぶれは、彼らが特定のジャンルだけに止まらない活動を目指していることを物語っている。そこに期待するリスナーは少なくないはずだ。
-

-
MOP of HEAD
Vitalize
約2年ぶりのフル・アルバム。Hitomi Kuramochi(Ba)やSatoshi Yamashita(Dr)がヴォーカルにチャレンジしている曲もあるが、そのことについて、"歌わない!というコンセプトもなかったので"と言及するのも好奇心旺盛な彼ららしくて好感が持てる。"活気づける、活性化する"という意のアルバム・タイトルの下、緻密な計算というよりも好きなものとやりたいことを全部盛りしたかのような、あらゆる音楽に敬意を払いながらもジャンルの壁をぶっ壊すような、歪且つ痛快なダンス・チューンが集まった。聴き手の身体を血液、いや、細胞単位から踊らせてしまうこの音楽は、狂気と呼ぶべきか、狂喜と呼ぶべきか。第六感までフル動員して確かめるべし。
-

-
MOP of HEAD
Breaking Out Basis
ヴォーカル・レスを感じさせない圧倒的なサウンドで今注目のロック・バンドMop of Headが、約2年振りとなる2ndフル・アルバムをリリース。どこか物悲しくメロディアスなTrack1.「Land」で幕を開けたかと思いきや、Track2.「Japanese Boring」から彼らお得意のアッパーなダンス・チューンが始まり、スピードを増していく。まるで真夜中の都会のクラブに迷い込んだような興奮が体を駆けめぐる。そしてこのバンドの実力はこれだけではない。クラブ・ミュージック、エレクトロに、ジャズ、ポップ、ロック……バラエティに富んだ彼らのセンスが続々と展開され、聴き手を惹き込んでいく。ジャンルの枠を飛び越えた1枚、そのめまぐるしさの中に快感を覚えること間違いなしだ。
-
-
Morestage
MATERIAL
2007年結成のギター×3、キーボード、ベース、ドラムス、VJによる7人編成のポスト・ロック・バンドが放つ2ndミニ・アルバム。Track.1「Intro」からTrack.7「Material」まで、各プレイヤーが楽曲の一部となって構築していく音楽は感動的な響きを持ってエンディングへと向かって行く。インスト曲でありながら各曲の世界観を表した詩と5人のグラフィック・アーティストが手掛けた絵画が封入されており、それらを見ながら展開していく曲を聴いていると新しいインスタレーションの手法を体験しているようにも感じる。ポスト・ロックやアンビエントという言葉では語り切れないスケールの大きな表現力を持った作品であるだけに、大きな会場での再現ライヴが観たくなった。
-
-
Morgan Page
Believe
アメリカ・バーモント出身のMorgan Pageは、2008年にリリースされた『Elevate』が2009年のグラミー賞にノミネートされるなど、実力を兼ね備えた話題のマルチ・アーティスト。リミキサーとしての手腕も高く、多くのアーティストが彼にリミックスを依頼。Madonna、Katy Perry、Stevie Nicks、B-52’s、COLD PLAY、オノ・ヨーコなどのリミックスも手がけている。そして日本デビュー盤となる『Believe』は全体的に包み込まれるような暖かみのあるサウンドとリズムで、じわじわとまったりとした高揚感が心地いい。ハウス・トランス初心者にオススメしたい1枚。夜一人でゆっくりしたい時に聴いてみるのもいいかも。
-

-
Mori Calliope
JIGOKU 6
VTuberのラッパー、Mori Calliopeのメジャー2nd EP。前作『SINDERELLA』で表現された"罪"を犯したあとに辿る"地獄"をテーマにした作品で、新曲6曲が収録されている。「虚像のCarousel」の作詞/歌はReol、「未来島 ~Future Island~」の作詞作曲はケンモチヒデフミ(水曜日のカンパネラ)、「Black Sheep」のプロデュース/作曲は蔦谷好位置、「six feet under」の作詞作曲はTK(凛として時雨/Vo/Gt)と、ジャンルを越えた幅広いアーティストが集結。彼らが参加した個性の強い楽曲を、Mori Calliopeはなんなく乗りこなし、特に「six feet under」では高速ラップを披露。その実力を遺憾なく発揮している。
-

-
Mori Calliope
Mori Calliope Major Debut Concert "New Underworld Order"
"死神ラッパー"として話題を集めているVTuber、Mori Calliope。昨年7月に豊洲PITで開催されたメジャー・デビュー記念ライヴであり、彼女にとって初の単独公演となった一夜が待望の映像化。TeddyLoidをDJに迎えたアグレッシヴな展開や、彼女が所属している"hololive English -Myth-"のメンバーたちがサプライズ登場した「The Grim Reaper is a Live-Streamer」をはじめ、豪華ゲストたちとの共演もあって見どころばかりだが、その中でもやはり強烈に残るのは、彼女のラップであり、歌だ。時に滑らかに、時にハードに、モードを巧みに切り替えながら言葉を捲し立てていく姿は、何よりも華がある。日本語と英語を交えたMCから伝わってくる真摯な想いにも胸を打たれる圧倒的な110分。
-

-
Mori Calliope
SINDERELLA
"ホロライブプロダクション"傘下の英語圏グループ"hololive English -Myth-"に所属しているVTuber、Mori Calliopeのメジャー1stフル・アルバム。"10個の大罪"をコンセプトに、THE ORAL CIGARETTESの山中拓也(Vo/Gt)、JP THE WAVYというロック・シーン/ヒップホップ・シーンの最前線を走るふたりや、Moriが多大な影響を受けた日本のネット・ラップ・シーンからはFAKE TYPE.を招聘しつつ、"死神ラッパー"の異名の通り、"魂ちょうだい"と叫ぶアッパーなダンス・ポップ「soul food」や、静謐でメランコリックな「glass slipper」など、自身がリリックを綴ったものも収録している。ラップ・ミュージックに軸足は置きながらも、様々なジャンルの架け橋にもなりうる強力な全10曲。
-

-
MoritaSaki in the pool
Love is Over!
2021年結成、京都を拠点に活動する4人組バンド MoritaSaki in the pool。風変わりなバンド名に気を惹かれたら最後、ドリーミーな音像とシューゲイザー・サウンドに一瞬で虜にさせられる。淡い高揚感が静かに凝縮された1曲目「Portraits」は、荒くれたギターで幕を開けるロック・チューン「MIRROR'S EDGE」への加速装置。物語の冒頭を想起させるような、煌めいた瞬間が詰め込まれた待望の1stフル・アルバム『Love is Over!』は"青春"という言葉がよく似合っており、透明感のある男女ツイン・ヴォーカルの掛け合いや要所のギター・リフ、サビで炸裂する轟音はどこかSUPERCARを彷彿とさせる。海外アーティストと共演する等、着実に歩を進める彼等の活躍から今後も目が離せない。
-

-
THE MORNING BENDERS
Big Echo
GIRLSのChristopher Owensを始め多くの地元ミュージシャンが出演した「Excuses」のビデオでも話題を集めたカリフォルニア出身の新人バンド。各メディアでも取り上げられ今旬のバンドの一つと言っても過言ではないだろう。THE BEACH BOYSを彷彿とさせるウォール・オブ・サウンドとグッド・メロディを聴かせてくれる。共同プロデューサーにGRIZZLY BEARのChris Taylorを迎えた事も多きのだろう、ストリングスの使い方も巧みでVAMPIRE WEEKEND と同様にロック・バンド然としたアプローチは薄く、クラシカルな雰囲気を持ちながらもとても刺激的なサウンド・スケープが広がっている。とても美しいアルバムだ。
-
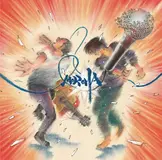
-
MOROHA
MOROHA Ⅳ
アコースティック・ギターのUKとMCのアフロ。ふたりによるふたつの音で紡ぐアンサンブルは、時にどんなバンドのサウンドよりも分厚く雄弁で、発明的な独自の形を進化させつつも、講談師の如く伝統芸能的な側面も見せる。昨年結成10周年を迎え、今や企業CM曲や公的機関のキャンペーン・ソング、映画主題歌にも採用される存在となったが、吐き出す言葉が緩むことも、忖度することもなく、赤裸々に鋭利に心から切り出して、まだ脈打つ熱さを持ったままの感情、言葉を手渡してくる。アフロ自身のパーソナルな視点、彼自身の歌であるが、その半径数十センチを極めるほどに、心揺さぶる歌となる。MOROHAの音楽が引っ張り出す自分の思わぬ気持ちに動揺することもあり、笑いが滲むこともあり、今作もまた厄介だ。
-

-
MOROHA
MOROHA BEST~十年再録~
TVドラマ"宮本から君へ"エンディング曲に起用された「革命」で幕を開ける再録ベスト。そう、今年結成10周年を迎えたMOROHAのメジャー第1弾作は、ライヴで磨き抜かれた楽曲を真空パックした内容となった。孤独や敗北をガソリンに時に感情をぶちまけ、時に優しく囁くアフロの情熱的なMCは聴く者の心臓をギュッと掴んで離さない。それに寄り添うUKのアコースティック・ギターは繊細だったり、パーカッシヴにリズムを刻んだりと、表現も実に多彩。最小ユニットにして無限の可能性を秘めた音楽は、全12曲という楽曲に収まり切れないエモーションに溢れている。彼らは"どこにも居場所がない"と口にしていたけれど、全ジャンルを対手に格闘する真のリアル・ミュージックがここにある。身も心も震える。
-

-
MOSHIMO
化かし愛
MOSHIMOがアルバム『化かし愛』でメジャー・デビュー! 今作は、これからの活動に勝負をかけるバンドの決意が窺える1枚であり、常に物事に対してまっすぐにぶつかっていくバンドの魅力がギュっと詰まった作品だ。キャッチーな言葉遊びも面白い「化かし愛のうた」、思わずバットを振る真似をしたくなる野球にまつわるフレーズ満載の「獅子奮迅フルスイング」、大切だった日々を回顧し切ない思いを吐露する「蜂蜜ピザ」、アグレッシヴなサウンドに乗せて未練に踏ん切りをつけようとする「断捨離 NIGHT」など全12曲。恋愛や日常の様々なことが描かれているが、葛藤しながらもいつだって全力な姿を見せてくれる岩淵紗貴が歌うからこそ、胸に響いてくるものがある。今作の曲たちがライヴでどう化けるのかも楽しみだ。
-

-
MOSHIMO
噛む
2020年1月に行われたツアー・ファイナル公演をもってメンバーが脱退し、新体制となったMOSHIMOによるニュー・アルバム。今作は、KEYTALKらを輩出した下北沢のインディー・レーベル、KOGA RECORDS内に設立した自身のプライベート・レーベル"Noisy"からの第1弾作品となる。サウンドには、バンドの強みであるライヴの熱量がギュッと閉じ込められており、底から這い上がるようなポジティヴなパワーが漲る楽曲が並んでいる。言葉では、自身の経験やリアルタイムの心情を偽りなく素直に伝え、聴き手と同じ目線に立ちながらも、その手を取って引っ張り上げてくれるような、頼もしさも感じる。学校や仕事、プライベートも一生懸命に頑張って生きている人々に届いてほしい作品だ。
-

-
MO'SOME TONEBENDER
Ride into HEAVEN
4月の"地獄盤"に続く"天国盤"はモーサム史上最強のハードコア・ファンタジーだ。その中で彼らはこれまでになく明確にそろそろ本気でヤバい地球についてや、ロックンロール・バンドを続けている根本的なモチベーションについて......を歌っている。もしかしたら順番が逆かもしれないが。藤田勇の現行のさまざまなインディー・ミュージックと呼応するセンスが溢れるのは冒頭の2曲。浮遊するシンセと谷底から鳴るような重低音の対比 が天国どころかバッド・トリップ気味の音像を描く「longlong long」、生命感を帯びた「nuts」。そしてフューチャリスティックなR&Rを経て武井靖典(Ba)渾身の叫び調ヴォーカルが涼しげな演奏と凄まじい対比を描くラストの「Kick Out ELVIS」に至るとき、本作が表現する切実さに気づくことだろう。
-

-
MO'SOME TONEBENDER
Rise from HELL
自由のために何だってやる、自分の責任において......それがパンクだと思っている自分にとって、モーサムは今や世界でも希少種のパンク・バンドだ。曲ができすぎたという理由で2回に分けてリリースする、今回は地獄盤。藤田勇がギターに転向して以降のタガの外れた、でもしっかりユーモアも含んだカオティック・ワールドが"HELL"の名のもとにより濃く集結した印象。ラウドで圧は高いがジャンク感はなく研ぎ澄まされた冒頭の3曲に続いて、武井靖典作曲のヒップホップとダブ要素の強い「カルチャー」、武井がヴォーカルをとる妖しげなエレクトロ・ディスコ「イミテイションシティ」、百々和宏が書く少年の日記のような痛みを伴う「ジャムパンちょうだい」など、時代に擦り寄ることの真反対を行きながら自ずと時代を映している。
-
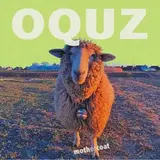
-
mothercoat
GOHUM
削ぎ落とした音圧の少ないサウンドスケープ、音のように言葉を扱いながらも、独特の高低差で言葉が残るヴォーカル。他のバンドにはない"数学"でエクスペリメンタルな楽曲を構築するmothercoatのセンスの塊のようなアルバム。前任ギタリストであるニノミヤソウと共に作った「fake a fake」「waltzheimer」「nipple cider」「u. n. o」に感じられるマス・ロック的な楽器の抜き差し、20代前半の若いギタリスト、アベフクノスケ加入後の「ten pura」のムーディなのにどこかインダストリアルな質感や、「poacher」のユーモアとダークさの共存も"音楽でこんな感情が発見できるのか?"という驚きとヒネリが満載。アナログ『OQUZ』と買うか? Tシャツと買うか? 全部入りで買うか? 配信で買うのか? 選べる(迷える)ことも表現のひとつだ。
-

-
Justin Courtney Pierre
In The Drink
2016年より無期限活動休止中のポップ・パンク・バンド MOTION CITY SOUNDTRACKのフロントマン、Justin Courtney Pierreが初のソロ・アルバムを古巣Epitaph Recordsからリリース。プロデューサーにバンド・メイトのJoshua Cain(Gt)を迎えた本作は、MCSの持ち味であったどこか懐かしく切ないメロディをしっかりと継承しながら、Justinの優しさと哀愁を帯びた歌声もさらに引き立った作品に仕上がっている。今回Justinはドラム以外の全パートを演奏しており、エモーショナルなギター・ワークのみならず、ベース・プレイも聴きどころ。MCSのファンはもちろん、まだ聴いたことがないという人にもおすすめだ。
-

-
MOTION CITY SOUNDTRACK
Panic Stations
今年3月に無期限活動休止を発表し、現在ワールド・ワイド・ツアーを行っているMOTION CITY SOUNDTRACK。9月には日本でのファイナル・ジャパン・ツアーを控えているが、その前にアメリカで昨年秋に発売された6thアルバムに、2曲のボーナス・トラックを加え日本でのリリースが決定。ポップでシュールなモーグ・サウンドと爆裂なバンド・アンサンブルとの2枚刃と、おセンチ節全開のメロディとで、パンク~パワー・ポップ・ファンの心をこれでもかと掴んで泣かせた必殺技は、1ミリもブレることなくここにある。アルバムとしては久々の作品でもあるので、その健在ぶりがまた切なくもあるが。こうして大人ぶったりかしこまったりすることもなく、エヴァーグリーンなままで突き抜けているのは嬉しいところでもある。普遍の青春サウンドトラックだ。


























