DISC REVIEW
H
-

-
HAPPY HANDS CLUB
EP+Parking Lot
スウェーデンから登場の7人組の大所帯バンド、HAPPY HANDS CLUBが日本編集盤をリリース。大所帯バンド特有の壮大なアンサンブルも魅力だが、元々ソロで活動していたRicky Sokhiのプロジェクトというのもあるのだろう、サウンドはとても統一感のある仕上がりになっている。ネオアコやサーフ・ポップとTEAM MEを彷彿とさせるような、疾走感のあるドリーミーなダンス・ロックがブレンドされたサウンドに、男女の掛け合うヴォーカルとハーモニー がと ても心地良い。北欧バンドらしい透明感あるメランコリックなメロディと電子音、そして荒削りなバンド感のバランスが絶妙で、インディ・ロッ ク・ファンからスウェディッシュ・ポップのファンまで幅広い層に響く素晴らしい作品。
-

-
HARD-FI
Killer Sounds
今年は海外の大物アーティストのリリースが絶えないが、HARD-FIの新作もそのうちのひとつだろう。3作目のオリジナル・アルバムは4年待った甲斐が充分ある、非常にポジティヴでエネルギッシュな快作だ。ロンドン郊外にあるステインズ出身の彼らだが、1stと2ndを生みだしたその地元だけに留まらず、ロサンゼルスなどでレコーディングを敢行。新たなプロデューサーを迎え、サウンド面での探究も目まぐるしい。ロックをベーシックに、パンク、ダブ、スカ、レゲエ、ファンクにディスコなどなどカラフルな音楽性と、ダイナミックなヴォーカルやコーラス。身体をスウィングせずにはいられない。彼らが4年掛けて導き出したバンドの在るべき姿と、殺傷能力抜群のミュージック。音を楽しむ、まさしくこれぞ“音楽”!
-

-
harue
Dear my hurt
円Doをフロント・ウーマンに据え、小学校の幼馴染/音楽仲間で結成した"青春ロック・バンド"の全国デビュー盤。冒頭「theme」でガツンと各楽器の切れ味鋭い演奏を聴かせるところから惹き込まれた。続く"コロナ"をもじった「call of now」では、最終審査まで残っていた"スパソニ"オーディションの中断など、思い通りにいかなかったもどかしさを、みんなを明るくしたいというポジティヴな想いに変換。また、ライヴをしたい素直な願いを込めた「宇宙からI LOVE YOU」はポップ・ロックに挑戦し、初ライヴから演奏している「僕なりの青春」、「pacific」などは再録でパッケージ。全曲とにかく親しみやすいメロディがいい。まっすぐだからこそ届くものを信じてみたくなった。
-

-
HARUHI
INSIDE OUT
「ひずみ」で彗星のごとくメジャー・シーンに躍り出た、 ロサンゼルス生まれ18歳のシンガー・ソングライター HARUHI。今回、満を持して1stフル・アルバム『INSIDE OUT』をリリースした。実に13曲中5曲がタイアップということで、彼女の名刺代わりとなる作品だ。その中でも惹きつけられたのは彼女の強く、儚く、澄んだ魅力的な声と重なる全英語詞のシンプルな曲の数々。メロウに表現した曲でありつつ、タブー視されがちな現実を歌う強さが音に乗るとじっと耳を傾けてしまう。一聴するだけならその旋律の美しさに気を取られるが、聴き進めると時折センセーショナルな言葉が散りばめられているところが秀逸。曲ひとつを取ってもまさに二面性が表現されている深みのある作品が世に放たれた。
-

-
HARUHI
ひずみ
1999年ロサンゼルス生まれ、現在17歳のHARUHIが、映画"世界から猫が消えたなら"の主題歌となる「ひずみ」を携えてメジャー・デビューを果たす。今作には小林武史が手掛けた2曲と、彼女自身が作詞作曲した2曲の全4曲を収録。17歳らしからぬ圧倒的な歌唱力をもって惹きつけられる唯一無二の歌声も素晴らしいのだが、HARUHIが手掛けた英語詞のTrack.3、Track.4の大人っぽさたるや尋常ではない。また、トラックを進めるごとに彼女のソングライターとしての才能が徐々に明らかになっていく曲順もよく考えられている。歌い上げるバラードからブルージーなロック・ナンバーまで幅広く表現する底力にも驚く。ある意味、彼女にとって"ひずみ"となるデビュー・シングルになるかもしれない。それにしても、一聴してすぐわかる小林武史節には本当に脱帽です。
-

-
HATE and TEARS
Make a Change REMIX
名古屋で結成されたエレクトロポップ・ユニット、HATE and TEARSによるメジャー初のパッケージ作。タイトル曲は、クールなサウンドの楽曲が多い彼女たちの中では珍しい、青い空が目に浮かぶ爽快感溢れる仕上がりに。また、センチメンタルな「Mirror」(TYPE-A 収録)や、キュートながらも影がある「invisible strawberry」(TYPE-B収録)、サマー・チューンの「Light up my luv」(TYPE-C収録)に、アンニュイな空気が漂いながらも力強いビートが身体を揺らす「AFTER SUMMER」など、トータル全5曲を収録。グループ結成初期に生まれたものもあり、ライヴでファンと育てて上げてきた楽曲を詰め込んだところからも、彼女たちのメッセージを感じ取れる1枚。
-

-
HATEM
Ultraviolet Catastrophe
スペイン発4人組ニュー・ウェーヴ・バンドHATEM(アテム)の2ndフル・アルバム。哀愁漂うメロディと懐かしいシンセの音色が独特の浮遊感を演出する今作には、夏の終わりのノスタルジックな気持ちを思い起こさせる珠玉のナンバーが詰まっている。それはリード・トラック「They Won't Let Me Grow」の美しいギターとキャッチーなコーラスからも存分に味わうことができる。80’sテイストが強い「You Know We Found New Words」のダンス・ビートは日本人の琴線に触れること間違いなしだろう。そして随所に垣間見えるシュー・ゲイザーのごとく壮大なサウンドの展開が、とても良い塩梅で作品への深みを与えているのも秀逸。
-

-
HB
Black Hole in LOVE
いやあ、こういうのは個人的にツボ過ぎるんですよね。ドラム、パーカッション、ベースによるインスト・ガールズ・トリオ。2004年から都内を中心に活動しているというこのHB。ファンクやダブを基盤に、徹底的にリズムに拘ったスリリングなベース・ミュージック。徹底的に無駄を削ぎ落とした剥き出しのグルーヴが腰を直撃してくる。ドラムとパーカッションが生み出すポリリズムとベースのうねりを増幅させるダブ、エレクトロニカ的要素。ツボを押さえたファンキーなアレンジで全く飽きることなくそのグルーヴに身を委ねることができる。タフな強度としなやかさを兼ね備えたこの黒さ。地面から立ち昇ってくるグルーヴに遥か彼方までトバされます。深夜3時のダンス・フロアのど真ん中とかでライヴをやったら、とてもいいんでしょうね。
-

-
HEADLAMP
タクトを振れ
"苦しい時こそ生まれる歌がワンダーソング"と、音楽が切り拓く未来を信じて歌い上げるリード曲「タクトを振れ」を収録した、HEADLAMP約1年ぶりの新作となるミニ・アルバム。昨年7月にフル・アルバム『ON THE GROUND』をリリースしてから、精力的にライヴを重ねてきた彼らが、改めて音楽と向き合うことで生まれた楽曲たちが収録されている。切ないメロディ・ラインにいつかまた会いたい人への想いを捧げた「Skyline」、スカを取り入れた穏やかなサウンドに両親に貰った大切な言葉をモチーフにした「アンビー」、"愛"についてのバラード曲「愛に生きて」。ソングライティングを手掛ける平井一雅(Vo/Gt)が、今この瞬間に動いた想いを切り取った歌たちは、何ひとつ嘘がなく、だからこそ心に響く。
-

-
HEADLAMP
ON THE GROUND
タイトル・トラック「ON THE GROUND」から夜明けを告げるような堂々としたサウンドスケープで幕開ける、HEADLAMP初の全国流通アルバム。7年前に大阪 高槻のライヴハウスから始まったバンドの集大成となる1枚が完成した。バンドの原点にあるメロディック・パンクの要素を随所に感じさせながらも、その枠を超えて瑞々しいメロディとビートが躍動するロック・アルバムは、朝から夜へと日常生活のサイクルに寄り添うように曲順を組み立てたという裏テーマもある。心に隠した反骨精神が漏れ出た「PUNKS!!」や、熱き青春の日々を綴る「アオハルロンド」を経て、特にアルバムのラストに収録された「帰せる列車に」、「旅の後書き」、「ウチュウイチ」で溢れ出るエモーションがいい。自分たちこそ"宇宙一のバンドマン"であると何のてらいもなく歌えるピュアさが眩しかった。
-

-
HEADLAMP
アオハルロンド
大阪高槻のライヴハウスから生まれた4人組ロック・バンド HEADLAMPの2枚目となる全国流通盤シングル。年間100本におよぶライヴを行いながら、前作から8ヶ月ぶりに完成させた今作は、起承転結の"承"としてバンドを大きく前進させる1枚になった。学生時代に大きな影響を受けたというメロディック・パンクを始め、バンドのルーツと再び向き合うと同時に、"青春"という大切なテーマを打ち出した今作。"青春という季節は/ただ一つだけ。"と歌うフレーズからは、かけがえのない一瞬に命を燃やせることの尊さを思い出させてくれる。カップリングには、10代のころバンドを続ける決意を固めるきっかけにもなった「空が落ちてくる日」を収録。ここにバンドの原点がすべて詰まっている。
-

-
HEADLAMP
NEW ORDER
"負けんなよ!"と聴き手を全力で鼓舞するようなバンドだ、HEADLAMPは。しかも誰ひとり置いていくことなく、1対1で向き合うような真摯さがある。ライヴで彼らと心をシンクロさせるかのようにシンガロングするオーディエンスが多いのは、その証だろう。初の全国リリースとなる今作は、平井一雅(Vo/Gt)が実際に体験した仲間とのエピソードをありのまま歌う1曲を表題に掲げ、光射す方へ駆け上がるような、瞬発力のある作品。仄かにR&Bの香りを持つ熱を帯びたヴォーカルを中心に、それを後押しするエッジの効いたサウンドを基盤としつつ、「晴々」では楽器隊も代わる代わる前に出てアピールし、全員の見せ場が活きていることもバンドの成長を窺わせる。何より、背中を押してくれる友人の手を思い出させる温度感があり、誰かにとっての大切な1枚になるはず。
-

-
HEARSCAPE
Transient
フランスの女性リード・ヴォーカル&キーボード Léa Berthouxが率いるプログレッシヴ・ロック・バンド HEARSCAPEのデビュー・アルバム。RADIOHEADやMUSEといったイギリスのバンドから影響を受けているとのことで、歌詞は英語、かき鳴らす感じのギター、そしてプログレッシヴな曲調と、そのあたりのバンドのファンならばニヤニヤが止まらないようなそれっぽい雰囲気を纏っている。だが、それだけにとどまらないような、ヨーロッパっぽい不思議なおしゃれ感もあり、それに拍車を掛ける女性ヴォーカルの少々クセのある歌唱が堪らない。ピアノを効果的に使った音作りも、楽曲のドラマ性を演出していて引き込まれる要素のひとつだろう。アルバム終盤まで出し惜しみして効果的に用いられるフランス語の歌唱もセクシーでいい。
-

-
THE HEARTBREAKS
We May Yet Stand A Chance
UKの4ピース・バンド、THE HEARTBREAKSの2ndアルバム。一昨年リリースの1st『Funtimes』は、THE SMITHSやORANGE JUICE直系の、清廉としてドラマティックなメロディと情熱的でアクの強いヴォーカルが冴え渡るギター・ポップの快作だった。しかし本作において、そんなギター・ポップ路線はあくまでも数ある音楽性の内のひとつに落ち着いている。むしろ本作で耳を引くのは、フォークやカントリー、果ては躍動感のあるストリングスを全面的にフィーチャーしたオーケストラ・ポップなど、アメリカン・ルーツ・ミュージックからの多大な影響を感じさせる楽曲群だ。そもそも1stの時点で一介のインディー・バンドに収まらないスケールのデカさは感じさせていたが、本作ではより饒舌になった楽曲とアレンジでもって、ネクスト・ステージへと歩を進めている。
-
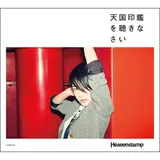
-
Heavenstamp
天国印鑑を聴きなさい
茶目っ気と自信が漲るタイトルは、"極度乾燥(しなさい)"などといった、直訳のようで違和感のある日本語を前面にプリントするイギリスのブランド"Superdry"を現地で見たことがキッカケになっているのだそう。洋楽から影響を受けた、サウンド重視のバンドといったイメージが強かった彼らだが、今作は、初っ端の「愛を込めて、ウェンディ」から、ファンタジーとリアル、ユーモアと毒といった、両面を含んだ秀逸な歌詞が続く。特にラストの「春の嵐」は、マイブラ直系の音像に叙情的な日本語詞が乗り、彼らならではのジャパニーズ・シューゲイズ・サウンドを確立させている。また、Tomoya.S(Gt/Cho)がヴォーカルを務める「Monday Morning」などの新機軸からは、今後の可能性も垣間見える。
-

-
THE HEAVY
Hurt & The Merciless
ブラック・ミュージックという音楽の背景を紐解くと、そこには虐げられてきた人々の血と汗と涙の――そんなもので簡単に語り尽くすことのできない魂の歴史がある。THE HEAVYはそんな歴史が積み上げてきたものに最大限のリスペクトを払い、今この時代にしか鳴らしえないモダンなロックンロールを紡ぎ上げる。ブルースやソウル、R&Bをサウンドの核として据えながら、ビートはコンテンポラリーでヒップホップ的。ゴスペルの素養もうかがえるKelvin Swabyのヴォーカルには人生の苦みが滲み、抜群の説得力が宿る。テレビCMのタイアップのおかげでお茶の間まで浸透した前作から4年ぶりとなる今作でも、変わらぬ彼らの音楽的精神が貫かれている。まあ何はともあれ、Little RichardからTHE BLACK KEYSまでまとめてぶっ飛ばすTrack.11で痺れていただきたい。
-

-
THE HEAVY
The Glorious Dead
英国南部出身、前作収録「How You Like Me Now?」が大ヒットを博した後の3作目。ロックとブルース、ファンクといった黒いグルーヴにサイケを注入!前作以上にスケールはデカく豪奢で、レコーディング・スタジオから自分たちでおっ建て、ヴィンテージ機材を買い込む程の気迫の入れよう。多種多様な音楽性をアピールしつつも、バンド・サウンド自体は非常に重厚である。基盤の強固さがブルージーでアグレッシヴな上モノを支えつつ、しかし、あくまでも中心にあるのはKelvin Swabyの力強くソウルフルな歌。今作のテーマは“B級ホラー”で、アメリカ南部を舞台とした視覚的でオーケストラ的な作品にしたかったという。スウィートでノスタルジックな「Blood Dirt Love Stop」を聴き終える頃にはお腹いっぱいです!
-

-
HEESEY
33
イエモンのベーシスト、HEESEYによる4年ぶり3枚目のソロ・アルバム。"33"とは制作期間中にハマったという数秘術にもとづいて計算されたHEESEYの個性を表すナンバー。"変人"の自分を全力で楽しむ気分で制作したことで、ジャンルも言葉遊びもリミッターを解除するような1枚になった。闇の中で高らかなシュプレヒコールを上げる「NEW DAYS」を皮切りに、生のホーン・セクションが新しい世界の幕開けを祝福する「ROCK'N'ROLL SURVIVOR」、孤独に濡れるジャズ・ナンバー「雨音のララバイ」、雷門がテーマの「THUNDER GATE SHUFFLE」から、エヴァーグリーンな名曲「INFINITY OF MY GROOVE」まで。どこを切ってもロックンロールへの愛情が溢れている。
-

-
HEIKE HAS THE GIGGLES
Crowd Surfing
イタリア出身3ピース・ガレージ・ロック・バンドHEIKE HAS THE GIGGLESの日本デビュー盤。今作には紅一点Emanuela(Vo&Gt)のキュートで弾けるメロディと無駄のないタイトなサウンドが荒々しいまでの初期衝動のまま収められている。冒頭曲「I Wish I Was Cool」の畳み掛けるような激しいビートと「Dear Fear」の豪快な疾走感は一気にロック好きのハートを掴むだろうし、なかでも野太いベース・ラインにのる四つ打ちリズムが踊らずにはいられない「Repetitive Parts」はキラー・チューンという言葉がふさわしい。既に海外では人気急上昇中ということもあり、ここ日本でも新たなロック・プリンセスになること間違いなし。
-

-
heliotrope
大丈夫、君なら。
レコーディング・エンジニアにtoeの美濃隆章、ドラム・テックにASPARAGUS/MONOEYESの一瀬正和を迎えたheliotropeの1stアルバム。ピアノ、ベース、ドラムの3人 編成と聞いて想像しうる音と彼らの音がまったくと言っていいほど違っているのは、なんといってもメンバー全員のルーツがハードコアにあるからだろう。太くうねるようなベースと、激しく力強いドラムの中に凛と立つ小林恵子のピアノと歌声。その絶妙なバランスが、いわゆる普遍的なピアノ・ロックとは一線を画した唯一無二のサウンドを生み出している。また小林の紡ぐ歌詞とメロディには人生の物悲しさと喜びが凝縮されており、Track.1「ツミキ」からラストを飾る「大きな文字が降ってきて」まで統一された世界観は、ひとつの大きな物語のようにも感じられる。ひと癖もふた癖もある今作は、一聴の価値あり。
-

-
Hello!!!
海辺のグッドバイ
この作品は、それまでアルバム用に作っていた曲をすべて捨て、その後まっさらな状態で作られた楽曲たちで構成されているという。その6曲に"新たな境地に辿り着いた"という手ごたえを感じた彼らは、バンド名を"ELECTRIC LUNCH"から"Hello!!!"と改め、再スタートを切った。まどろみのような幻想的なシューゲイズを取り入れたサウンドは、朝焼けの崇高な空気を思わせる高揚感があり、自らの目指す音楽を発見したバンドの夜明けがそのまま投影されているようだ。表題曲はサンバとジャズを昇華したダンサブルなドラムに、歌うようなギターとベースが交わり、海辺にそよ風が吹いている画が頭の中に自然と浮かんで来る。文学的な歌詞世界とともに、じっくり目を閉じて音の隅々を体感することをおすすめする。
-

-
Helloes
ビデオテープ
昨年10月にセルフ・タイトルを掲げた1stフル・アルバムでインディーズ・デビューを果たした4人組ロック・バンドHelloes。アルバムは様々なアーティストの影響が現れた楽曲や、内向的な印象を持つ楽曲が多かったが、今作に収録された4曲はどの曲も開放感に溢れている。前作の経験を踏まえて、とは言え5ヶ月足らずで一気にここまで跳ね上がれるのは若さゆえの吸収力だろうか。力強いストロークと堂々としたリード・ギターが印象的な表題曲「ビデオテープ」、米田圭一郎の高音とコーラス・ワークが冴え渡るキャッチーでポップな「エスケープ」、つんのめるようなスピード感の「空想ゲーム」、ドラマティックな展開を見せる「サテライト」。どの曲にも現在のHelloesが示したい方向が如実に出ている。
-

-
Helloes
Helloes
2011年に結成された、都内を拠点に活動する4ピース・バンド、Helloesの1stアルバム。基本となるのは、恐らくメンバーの原風景なのであろう00年代ギター・ロックを消化したサウンドで、そのメランコリックなメロディと孤独や倦怠感を滲ませる歌詞はSyrup16gやTHE NOVEMBERSに通じるものがあるし、時に差し込まれるダークなダンス・ロックからはThe MirrazやARCTIC MONKEYSなどを連想させる。総じて、まだまだ荒々しさを感じさせるし特別な目新しさはないのだが、その音の端々にキラリと光るものがあるのも確か。明らかに“やりたい音”よりも“出てきた音”を重視したようなアルバム後半楽曲が粒ぞろいなところを見ても、今後もっともっと歌とメロディを大事にしていって欲しいなと思ったりする。
-
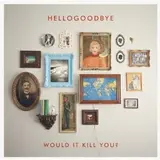
-
HELLOGOODBYE
Would It Kill You?
2001年カルフォルニアで結成されたパワー・ポップ・バンド。2004年にDRIVE-THRU RECORDSと契約し、2006年、1stアルバム『Zombiee! Aliens! Vampires! Dinosaurs!』は50万枚以上のセールスを記録。エモ、ポップパンク、ダンス・ロックなどを取り入れた初期と比較すると、今作は大人っぽいインディー・ロックを展開している。初期のTAHITI 80やBEN FOLDS FIVEなどを連想させる部分もある。Track.6「When We First Kissed」のキラリと光るギター・フレーズと心地よい疾走感はリピート必須。またForrest Kline(Vo)の伸びやかな歌声も絶好調のようだ。良質なインディー・ロックがまたここに一枚誕生した。
-

-
Hello Hello
blooms
ミュージシャンにとって"1stアルバム"とは名刺代わりのような作品と言えるが、奈良発3ピース・バンド Hello Helloがリリースする『blooms』は、まさにそんな作品に仕上がった。本作品には、バンド結成当初から現在に至るまでライヴで演奏され続けてきた、"これから始まる僕たちの音楽を/聞いてくれよ"と高らかに歌うギター・ロック・ナンバー「Hello!!!」、楽曲タイトルを体現するような疾走感で駆け抜ける「youth」、爽快感と哀愁が交差する「THINK」など、彼らのバンドとしての魅力が開花した全8曲が収められる。"ひとり一人に寄り添う音楽を"をコンセプトに活動するHello Helloが満を持して届ける楽曲の花束をぜひ受け取ってほしい。
-

-
Hello Hello
燦 / リリィ
"ひとり一人に寄り添う音楽を"を掲げる奈良の3ピース・バンド、Hello Hello。10月10日開催の"FM802 MINAMI WHEEL 2021"にも出演する彼らが、バンド初となる両A面シングルを完成させた。「燦」は感情や情景を鮮やかに描いたバラード。どこか懐かしさも感じられる叙情的なギター・ソロや、思わず感情移入してしまうようなヤナギの切ない歌声が印象的だ。一方「リリィ」は、明るい音像の応援歌的なナンバー。聴く者の心を一瞬で掴むようなサビでパッと開ける高音ヴォイス、推進力のあるリズム隊のノリ、ポジティヴな気持ちが乗っかった歌詞もいい。対照的な2曲だがどちらもキャッチーであり、多くのリスナーに届きそう。彼らのふたつの側面を堪能してほしい。
-

-
Hello Sleepwalkers
Planless Perfection
前作からは1年半が経過、その期間が空白ではなかったことを証明するような4thアルバム。複雑怪奇な展開をする自らの曲(ヴォーカルのシュンタロウだけでなく、タソコやマコトが曲を書けることも頼もしい)に、バンドの心と身体が追いついてきたのかもしれない。ロックとラウドとメタルをないまぜにしたその世界はもともと異彩を放っていたが、それはもはや単なる飛び道具ではなくハロスリのアイデンティティに変わったのだと、この11曲を聴けばわかる。だからこそ、"2XXX年の世界"をテーマにしたコンセプチュアルな作品にもかかわらず、隅から隅まで、バンドの血がしっかりと流れているのだ。凄まじい生命力に吹っ飛ばされるシーン多数。これはもう、怖いものなんてないんじゃないかな。
-

-
Hello Sleepwalkers
Liquid Soul and Solid Blood
アルバムを語る際に"今のモードを全部詰め込んだ"とはよく耳にも目にもする言葉だが、ハロスリの新作はそれを堂々と言い切るパワーを持った6曲が収録されている。前作に続き、HARD-FiのRichard Archerとの共同プロデュースを実現。歌詞世界を汲んだ妖しげなアッパー・ナンバー「百鬼夜行」、デジタル的な手法をサウンドに用いたスリリングでシニカルな「Worker Ant」、和メロ、鮮やかなツイン・ギターとテクニカルなアンサンブルのコントラストが眩しい「アキレスと亀」、優しいヴォーカルが印象的な「朝に二人は」、歌謡ジャズな「デジ・ボウイ」、ラストの重厚な高揚感が圧巻の英詞曲「Ray of Sunlight」、今作で彼らはバンドの可能性を果敢に試している。好奇心の賜物というべき作品だ。
-

-
Hello Sleepwalkers
Masked Monkey Awakening
デビュー・アルバム『マジルヨル:ネムラナイワクセイ』から13ヶ月ぶりとなる2ndフル・アルバムは、HARD-FiのRichard Archerとの共同プロデュース作。自身の持つ世界を深く広げていた前作に比べると直情的でアッパーな楽曲が多く、ライヴでの着火性も良さそうだ。こう書くとシンプルになったのか、と思われそうだがそんなことはなく、寧ろ先の読めない展開はより緻密に作りこまれている。随所にラウド的なアプローチやエレクトロ・テイストも取り入れ、よりロックを根幹にしたジャンルレスが加速。トリプル・ギターのなかで唯一ギターのみ担当のタソコのカラフルな音色は、楽曲の持つ空気感をより異次元的に彩る。彼が作詞作曲を担当した楽曲も2曲収録。バンドのキャパシティを目一杯広げた挑戦作だ。
-

-
HELSINKI
A Guide For The Perplexed
BABYSHAMBLESのベーシスト、Drew McConnellのサイド・バンド、HELSINKIの2ndアルバム。そもそも、THE LIBERTINESが00年代のUKロックにもたらした成果のひとつに、ロックンロール誕生以前のフォークやトラッドや大衆音楽までも昇華した音楽性が挙げられるわけだけど、やはりこのへんの人脈はその素養が強く出てくる。2日間のライヴ・レコーディングで仕上げられたという本作は、可愛らしいフォーク・ポップから幽玄なアシッド・フォーク、果てはサイケにレゲエも飛び出して、でもどの曲もグッド・メロディが心地よい小品集。THE STROKESのAlbert Hammond, Jr.も参加していて、でもやっぱり『Up The Bracket』原理主義者としては、Track.3でPete Dohertyの声が聴こえてきたときに、グイッと引き込まれた。
-

-
Helsinki Lambda Club
月刊エスケープ
漫画の月刊誌を買うときのような、稀にしか訪れないワクワクがパッケージされた本作は、アジア各国の音楽や土地の雰囲気に影響を受け制作された「キリコ」を筆頭に、海外ツアーの中で触れた"非日常"に焦点が当てられる。束の間のバカンスを思わせるタイトルにも納得だ。普段は得られない快楽が夢見心地なリズムに乗って次々とやってくる一方で、浮き彫りとなったエスケープの果てにある"現実"に聴き手それぞれが無事に帰還できるようにと、「THE FAKE ESCAPE」や「Yellow」のような、"自分らしさ"を見つめ直すきっかけを詰め込んだ楽曲も収録される。ワクワクの感触を引き延ばすような「My Alien」の残響音に身を委ねた今夜はもう少しだけ夜更かししていたい気分。
-

-
Helsinki Lambda Club
Tourist
CD、USB、LPなど、異なるリリース形態で"1st"にこだわり作品を発表し続けてきた彼らが、"2nd"と銘打った2ndミニ・アルバムを完成。フレッシュ感を脱ぎ捨てた3人は、ここからが本番と言いたげな、やりたい放題ながら完成度の高い7曲を揃えた。まずフィンランドのファッション・ブランド"marimekko"の意味を表すタイトルの「マリーのドレス」。ムーディな鍵盤の音が不穏に捻じ曲がり、突如口ずさむような歌声を聴かせたと思えば、今度は多層的なコーラスで彩る展開に"これヘルシンキ?"という驚きの連続。さらにホーン隊を携え華やかでグルーヴィな一面を見せる「PIZZASHAKE」、浮遊感たっぷりの「引っ越し」など、さながら"ツーリスト"のように様々な音世界を練り歩く楽しい1枚となった。
-

-
Helsinki Lambda Club
ME to ME
中学のときに英語の授業で習った"This is a pen."という例文で大人になることのバカらしさを感じた人は絶対に聴いた方がいい。Helsinki Lambda Clubがリリースする初のフル・アルバム『ME to ME』、その1曲目が「This is a pen.」だから。そこに意味なんてなくていい。ただなんとなく耳触りが良くて、だけどピリッと皮肉が効いた、そんなヘルシンキの歌の数々は人を食ったような遊び心がありながら、時々、真正面から涙腺を刺激するセンチメンタルも詰まってる。70年代パンク~90年代のオルタナティヴ・ロックまでをルーツに持ち、その片鱗をおそらく"あえて"隠そうともしないまま、ここまで奇妙にポップなオリジナティを確立するセンスは、この世代のバンドでは群を抜いていると思う。
-

-
Helsinki Lambda Club
友達にもどろう
"友達にもどろう"―― 数々の思い出を一緒に重ねてきた恋人に突然言われたら、きっと誰もが胸を刺されるだろう。その言葉が変えた、当たり前だった昨日までの景色と、後悔、妄想、哀愁......などなど、様々な感情が一気に押し寄せる今日。そんな痛恨のひと言をタイトルに冠し、言われたあとの心情をユーモアも交えながら描いた1stマキシ・シングル。地獄を舞台にした一風滑稽な「しゃれこうべ しゃれこうべ」、合いの手を入れながら踊れる1曲に仕上げた「TVHBD」、"こんな気持ちはいけないよな"とまだ断ち切れない思いとの葛藤を綴った「ぢきぢき」、ここまでの感情を爆発させるようなパンキッシュなショート・チューン「メリールウ」と濃厚な4曲を収録している。橋本薫(Vo/Gt)の、味わい深くもどこか甘酸っぱい歌がより胸を締めつける。
-

-
henrytennis
R.U.R
多分、何年経っても薄れることのない景色の記憶が、誰でも一つはあると思う。僕の場合、20代前半の頃に一人旅で訪れた山陰地方の無人駅から見た日本海。決して特別な景色ではないのに、一度だけしか訪れたことがないその景色だけは、いつまで経っても記憶の中で輝きを失うことがない。このアルバムを聴きながら、僕の頭の中にまたその眩しい日本海が浮かび上がっている。プログレッシヴな音響ポストロックをベースにしているのだが、AORのような穏やかさを湛えるこのポップ・ミュージックの完成度の高さは、henrytennis ならではの職人技。部屋でもcafeでも野外でも、あらゆる場所にフィットするであろう、開放感と風通しの良さも魅力。自分の記憶とは関係なく、海を連想させる音だと思うのは僕だけかな。
-

-
HERE WE GO MAGIC
A Different Ship
RADIOHEADのプロデューサーであり、時には6人目のメンバーとして称されるNigel Godrichがライヴを観て気に入りプロデュースを申し出制作されたという今作。ブルックリンを中心に活動を続ける彼らは今までに2枚のアルバムをリリース。フォーキーでサイケデリックなサウンドとヴォーカルLuke Templeが歌うどこかノスタルジックなメロディ・ライン。VAMPIRE WEEKEND以降を代表するUSインディー・シーンのバンドとして評価を受けて来たが今作で一皮剥けた印象。緊張感ある緻密なサウンドとARCADE FIREを彷彿とさせる壮大でメランコリックな世界感。6月にはHostess Club Weekenderでの来日も。これは見逃せないでしょう。
-

-
HERE WE GO MAGIC
Pigeons
アメリカ、ブルックリン発のサイケデリック・ポップ・バンドが待望の日本デビュー盤をリリース。飄々としたギターと、柔らかくあたたかいキーボード。その中に芯を通すようにリズムを刻むベースとドラム。その音にぽっかり浮かぶ、ちょっと風が吹けばどっかに飛んでいってしまいそうな頼りなさげなヴォーカル。思わずうたた寝をしてしまいそうな心地良さだ。『Pigeons』という物語を進めれば進めるほど、夢なのか現実なのか分からなくなってゆく。だがどんどん彼らの世界が曖昧になれば曖昧になるほどどんどん鮮やかになっていくから不思議である。それこそ彼らが巧みに操る“マジック” なのかもしれない。催眠効果を伴う圧倒的な浮遊感とノスタルジック。気だるい夏の暑さと共に、夢と現実の狭間へ落ちていくのも悪くない。
-

-
HERE
電撃
ウエスタン調の「電撃KISS」で幕を明ける本作は、"全曲リード曲のつもりで作った"と尾形回帰(Vo)が言うように、究極の祝祭チューン「BANG-BANG-ZAI」、王道ポップ・ソング「Sing!! Sing!! Sing!!」、ゴリゴリのハード・ロック・ナンバー「すべてぶつけて愛し合おうか、猛烈に。」と、かつてないほど粒揃いな曲が揃った。一方で、これまでとはまったく違うアプローチで生まれた「複雑な熱帯夜」では、HERE流AORをグルーヴィに決め、「今ここがポイントだ」や「ギリギリで鳴らす」では、現状からの脱却をポジティヴに歌う。限界を作らず、万歳するほど突き抜けたHEREの存在感を具現化した全12曲。これまでとはレコーディング方法を変えたことで、各パートの音が際立ち、立体感あるサウンドを手に入れたのも大きな武器だ。
-

-
HERE
詩になる
"うたになる"でも"歌になる"でもなく言葉に重きを置いた"詩になる"。人生において抗えない場面に直面したとき目の前にあったのは生も死も含めて"心"が通じ合えているかどうか。森羅万象の中で表現に向き合った尾形回帰(Vo)の本気作。前アルバムで強固となったサウンドも絶頂を極め、武田将幸と三橋隼人のギターの音色も華やかで艶が増している。Track.2はインビシブルマンズデスベッド時代の盟友、西井慶太をアレンジャーに迎えた軽快なロック・チューン。スカ調のビートが刻まれるところが興味深い。Track.3は壱(Support Ba)、角谷正史(Support Dr/→SCHOOL←)が転調を繰り返す複雑な曲を支えておりライヴでの重要曲になる予感。新境地と対峙したバンドの希望を感じる全4曲。
-

-
HERE
風に吹かれてる場合じゃない
前作『OH YEAH』が結成10周年の集大成だったとすると、6枚目の本作はHEREがこの先、何十年も活動していくエンジンを新たに積むことに成功した快作。「風に吹かれてる場合じゃない」で、現状は大変だけど前を向いて生きようと高らかに歌う尾形回帰に勇気づけられ、武田将幸&三橋隼人によるギター弾きまくりハード・ロック「最高ですから最強なんです」に胸を焦がし、イントロ・フレーズが印象的な「BOON BOON BOONでPON PON PON」でハッピーになり、HERE初のスカ・パンク・ナンバー「それではさようなら」で気分が軽くなる。壱(Ba)、ハジメタル(mezcolanza/Key)、#STDRUMS(Dr)、角谷正史(→SCHOOL←/Dr)ら、お馴染みのサポート陣との相性も完璧でライヴでの演奏が楽しみな全10曲。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























