DISC REVIEW
H
-

-
HERE
OH YEAH
年明けに発表したシングル『スーパーポジティブ』では、80sを彷彿とさせるニュー・ウェーヴ・テイストに挑戦。これまでのハード・ロック寄りなサウンドから大きく方向転換したかと思いきや、最新アルバム『OH YEAH』では、それが手始めだったとばかりに、ビート・パンクやラップなど、ロックを演奏するのが楽しくて楽しくて仕方がないという無双状態に。9mm Parabellum Bulletのサポートとしても名を馳せる武田将幸&三橋隼人のツイン・ギター面目躍如のHERE王道のロックンロール/メタル調の楽曲ももちろん健在。10年やり続けたからこそ歌えたという尾形回帰渾身のロック・バラード「OH YEAH」など、充実の全12曲を収録している。スケール感をアップしたHERE、ロックへの愛に溢れた5枚目。
-

-
HERE
I WANNA EAT YOUR CHAOS
昨年TOWER RECORDS限定で1stアルバムをリリースし、アルバムを引っ提げたツアーでは、アルカラ、9mm Parabellum Bulletとの3マンで盛大なファイナルを迎えたHERE。2作目の本作でいよいよ全国流通を果たす。上記バンドとガチンコ勝負するところからも濃さは伝わるが、そのサウンドはとにかくシアトリカル。喜怒哀楽も、笑いもハングリーに詰め込んだロック・オペラとなっている(不定期でロック+演劇のライヴ"PHOENIX"も開催しているという)。キャッチーで、大合唱や合いの手を呼ぶメロディに、ハード・ロック全開のギター・ソロで派手に煽り、かと思えば凛々しいビートでシリアスに攻める。毒を盛って、盛って、そして引き算によるタイトなロックンロールを聴かせる。これが中毒者を増やしているんだろう。
-

-
herpiano
ourseason
静岡を中心に活動するherpianoの実に5年ぶりのリリースとなった2ndアルバムがリリース。このアルバムは秋に差しかかり、風の冷たさを感じ始めるこの季節に聴くにはあまりに眩しくて儚く暖かい楽曲が詰まっている。優しくて淡いメロディはいつまでも色あせることのないエヴァー・グリーンな魅力に溢れているし、シンプルかつツボを抑えたバンド・サウンド、そして決して饒舌ではないヴォーカルやコーラスが所謂“琴線”をそっと撫でるからクセになってしょうがない。優しく紡がれたギターとヴォーカルのコントラストが鮮やかなTrack.1の「エイプリルフール」から始まる1枚のストーリーを是非味わっていただきたい。まるで遅れてきた夏休みのような光に満ちた作品。
-

-
the HIATUS
Hands Of Gravity
これを待っていた!というファンにとっては、ついに!ということになるのかもしれないけど、その間、細美武士(Vo/Gt)がMONOEYESとしても精力的に活動していたことを考えると、あっという間だったようにも感じられる前作から2年半ぶりの新作。とても清々しいアルバムだ。ピアノやシンセサイザーのフレーズが印象的に使われ、曲によってはストリングスも加えてはいるけれど、奇をてらわずに5人のメンバーが奏でる抜き身のバンド・サウンドを、もうそのままとらえたという印象だ。メンバーは歴戦のミュージシャンたち。レコーディングでは迷いもためらいもなく、いつも以上に確信を持って音を鳴らしたに違いない。そのひとつひとつがエモーショナルなロック・ナンバーの数々に結実。全10曲40分という尺も潔い。
-

-
the HIATUS
Keeper Of The Flame
聴く者の気持ちを鷲掴みにするアンセミックな歌と熱度満点のバンド・アンサンブルという意味では、the HIATUSらしさは変わらない。しかし、全編で鳴るシンセ・サウンドはバンドが辿りついた新たなサウンドスケープを印象づける。約2年4ヶ月ぶりとなる4作目のアルバム。新章の幕開けをアピールした『Horse Riding EP』で一気に高まった期待に応える、いや、期待を上回る作品を、彼らは完成させた。『A World Of Pandemonium』を聴いた時も驚かされたが、その時とはまた違う驚きが待っている。特徴的なシンセ・サウンドが1つの世界観を作り上げる中、ギター、ベース、ドラム、キーボードそれぞれが主張しあいながら多面的にアルバムの魅力を作り出している。焦燥感をはじめ、さまざまな感情を歌うメロディも多彩だ。個人的には温もりあるメロディから感じられる成熟に惹かれる。
-

-
V.A.
ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN COMPILATION 2011
アジカン企画&主催の夏フェス"NANO-MUGEN FES."も今回で9回目(ツアー形式だった「NANO-MUGEN CIRCUIT2010」を含めると10回目)。WEEZERやMANIC STREET PREACHERSをヘッドライナーに、BOOM BOOM SATELLITES、the HIATUS、若手注目バンドねごと、モーモールルギャバンなど、洋邦共に相変わらずの豪華ラインナップ。出演バンドの楽曲が1曲ずつ収録されているコンピレーション・アルバムは、今作で5作目。そして、今回収録されているアジカンの新曲は2曲。チャットモンチーの橋本絵莉子(Vo&Gt)を迎えた「All right part2」は、後藤と橋本の気だるい歌い方と熱が迸る歌詞のコントラストが鮮やかで、高揚感に溢れたギター・リフとメロディも力強く鳴り響く。ユーモラスなあいうえお作文、男性の言葉で歌う橋本の艶とレア感も思わずニヤついてしまう。東日本大震災時の東京を描いた「ひかり」は、人間の醜い部分や絶望感にも目を逸らさず、物語が淡々と綴られている。言葉をなぞる後藤の歌に込められた優しさと強さは、当時の東京を克明に呼び起こしてゆく。生きることが困難な時もあるだろう。だが"オーライ"と口ずさめば、ほんの少し救われる気がする。音楽の持つ力を信じたい――改めて強くそう思った。
-

-
HIGH FLUX
04
ザ・チャレンジのメンバーとしても活躍しているTaiju Wada(Composer/Manipulator)が率いるHIGH FLUXが、前作から約1年ぶりにリリースするミニ・アルバム。前作発表後、ツイン・ドラムの7人編成でライヴをやりつつ披露してきた曲を中心に収録していながら、バンド然とした作品にならなかったところは、変容的ダンス・ロック・バンドを掲げる彼らの面目躍如。バンド・サウンドをアピールした前作の延長で、ここでは四つ打ちを始め、様々なダンス・グルーヴにアプローチしながら、これまで以上に多彩な6曲に。それぞれに趣向を凝らしたサウンドに埋もれずに際立つ、熱いヴォーカルとアンセミックなメロディからは、自分たちが作る曲の核には、いい歌が常にあるという彼らの矜持が窺える。
-

-
HIGH FLUX
03
既存のバンド・フォーマットにこだわらないという意味で、"変容的ダンス・ロック・バンド"を掲げるHIGH FLUXが前作からわずか10ヶ月で2ndミニ・アルバムをリリース。エレクトロやダンス・ミュージックの要素を取り入れた踊れるロックはこれまでの延長と言えるものの、4人のヴォーカリストが歌っていた前作から一転、本作では前作にも参加していたKiyoharu Okabeをリード・ヴォーカルに据えたうえで、ギタリストを新たに加え、ツイン・ギター編成で力強いバンド・サウンドにアプローチ。曲調もアンセミックなものに変化したため、歌が主役の、いわゆる歌モノのロックという印象が強い作品になっている。ライヴを意識したという曲の数々はライヴを盛り上げると同時に、さらに多くのリスナーにもアピールしそうだ。
-

-
HIGH FLUX
02
ダンス・ロック・バンド、hare-brained unityのメイン・コンポーザーだった和田大樹率いるHIGH FLUXが結成から3年、ついに完成させた1stミニ・アルバム。5人編成のバンドながら、ふたりのゲスト・ヴォーカリストを迎えるなど、音源制作、ライヴともにひとつの形にとらわれない"変容的"ダンス・ロック・バンドというコンセプトを実践したという意味で、改めてバンドのスタートを印象づける作品だ。"ロック×ダンス・ミュージック"という方向性の延長上で、よりエレクトロ色濃いものに進化した音楽性はキャッチーな歌を聴かせる「Believe」という新境地を含め、多彩な全8曲に結実。曲ごとに趣向を凝らしたアレンジを試しながらスピーディー且つハードな印象に落とし込んだところに、このバンドで勝負しようという意気込みが窺える。
-

-
THE HILLS
ロストインザヤムヤムエクスペリエンス
メンバー全員の地元である新潟三条市で結成された4人組ロック・バンド、the hillsの1stミニ・アルバム。軽やかでポップなメロディと、少し掠れた脱力感のあるヴォーカルが気構えることなく耳に親しみやすい。夕焼けや陽だまりなど、日常の穏やかな自然の風景を描いた歌詞に、そよ風のような涼しげなサウンドが一味違うフレッシュさも与えてくれる気持ちの良いバンドだ。その中でどこかセンチメンタルさを醸し出す彼らの音楽は、泣いたり笑ったり不安定な日々を不器用ながらに生きる若者の姿によく似ている。先は見えないけれど、とにかく今この瞬間を思い切り楽しむ。そんな時間が何よりも大切だったりすることを教えてくれる。見えない重圧に息苦しくなったら、楽しさも悲しさも彼らと共鳴しよう。
-

-
THE HILLS
DROP
これは面白い。2004年結成の新潟出身4ピース・バンドの1stシングル。Track.1「コースのないレース」がわりとストレートなギター・ポップなので、この路線のバンドなのかと思ったが、Track.2「シロップ」はメロディとビートが絡まり合いながら摩訶不思議な魅力を醸し出す、ゆったりとしたダンス・ナンバー。Track.3「時を駆ける少女」は性急なポストパンク風ギター・ロックと、一筋縄ではいかない三者三様の楽曲が並んでいる。でも、どの曲にもキャッチーなフックがしっかりと備わっていて、アナログフィッシュやmooolsのようなセンスのよさを感じさせる。全体的な雰囲気がファニーで、尚且つ変態っぽいところもいい。このポップ・ポテンシャルと変態性を等しく高めていってもらいたい。期待大。
-

-
Hinano
CHANGEMAKER
劇場版"DEEMO サクラノオト~あなたの奏でた音が、今も響く~"の歌姫オーディションで、世界中の応募者の中から当時14歳でグランプリを獲得したシンガー、Hinanoの3rdシングル。これまではミディアム~スロー・ナンバーが多い彼女だったが、本作では初のアップテンポなロック・チューンに挑戦した。持ち前の美しいハイトーンを繰り出しながらも、要所で飛び出すがなり声が新鮮且つ楽曲に力強い熱を与えている。そんなパワフルな楽曲から一転、カップリングの「Never Ever」は、温かなサウンドながらも切なさを帯びたスロー・ナンバー。柔らかで包容力のある歌声が抜群に心地よく、その表現力の振り幅でシンガーとしての確かな実力を感じさせる1枚に仕上がった。
-

-
HINTO
LAST NIGHT
SPARTA LOCALSが復活し、HINTOも継続。ドラマーが違うだけの2組のバンドが並行して活動するという稀有な状況は、両バンドにいい刺激をもたらしているのではないだろうか。自主レーベル第1弾作品となるHINTOのニューEPは"夏の終わり"と"夜"にフォーカスし、個性を追求しつつ音楽性の幅を広げた作品だ。Track.1は、淡々としたトーンのなかに、他の曲とは情景を変えてひりついたリード・ギターが舞う。心地よさと鋭さや寂しさが交錯する、秋の空気を音と言葉で表現した楽曲になった。無感情のヴォーカルと音色のユーモア・センスが炸裂するHINTO流メタル曲、幻想的なギターの音色がロマンチックで感傷的なミディアム・ナンバーなど、繊細に揺れ動く感情を丁寧に描いた楽曲が揃う。
-

-
HINTO
WC
これまでのHINTOのバンド・アンサンブル、特に伊東真一のギターと思えないストレンジ感がまず耳に飛び込んできていたことを思うと、今作はユニークさはダントツでありながら鳴っている音の必然性が全然違う。夏の情景が浮かび、多幸感すらあるウワモノのサウンドとタフなファンクネスの絶妙なバランスが冴える「なつかしい人」、続く「ガラスのハート」の勘違い女子の純情とポスト・パンク的なプロダクトの不思議な同居。希望的なことを歌いながらサウンドは硬質な「star」、民話的なヴォーカルと少年性に溢れるヴォーカルが錯綜するギャップが楽しい「風鈴」。思いの正体は決して一色ではないことに腹落ち感満点な8曲を経て、珍しくストレートにバンドという魔法を讃える曲で幕を閉じるのも彼らの今を示唆している。
-

-
堕落モーションFOLK2
私音楽-2015帰郷-
"堕落モーションFOLK2"はHINTOの安部コウセイ(Vo/Gt)×伊東真一(Gt)によるアコースティック・ユニットである。彼らの2ndミニ・アルバム『私音楽-2015帰郷-』には、故郷・福岡県の出身中学校の体育館で録音され、安部コウセイの実家で歌録りされた楽曲も収録される。そういったことからもこの作品は、SPARTA LOCALSから数えると20年近いキャリアを歩んできた彼らが、改めて自身のルーツと人生に向き合った作品といえるのではないだろうか。HINTOにも見られるメロディの叙情性やノスタルジックな歌詞は、基本的にはアコースティック・ギターとヴォーカルのみというミニマムな形をとることで、より美しくフォーキーに、そしてメロウに昇華された。全5曲どれも心の奥底にすっと入り込む人間臭さに溢れた秀作。
-

-
HINTO
AT HOME DANCER
安部コウセイのソングライティングは、SPARTA LOCALS時代は外界に対するヒリヒリとした攻撃性、そしてそれを反転させた真っ直ぐなポジティビティを機軸に成り立っていたが、HINTO結成後、後者は受け継がれつつも、前者は鳴りを潜めている。その代わり、人間関係の機微、その裏にある社会性などを暗に示したストーリーテリング主体の曲が増えた。去年のアルバム『She See Sea』ではそんな安部の作家性とバンド・サウンドにどう折り合いをつけていくのか、その過渡期的な部分もあったが、この「アットホームダンサー」は完全に吹っ切れている。ダンサブルでキャッチーなサウンドと引き篭もりの心理を描いた歌詞。この対比が、ディスコミュニケーションこそがコミュニケーションであるという真理と狂気を鋭く光らせている。
-

-
HINTO
She see sea
元SPARTA LOCALSの安部コウセイ(Vo&Gt)率いるHINTOによる満を持しての1stフル・アルバム。過去のフリー・ダウンロード音源と今年1月に発表された『NUKIUCHI LIVE. EP』のスタジオ・テイクを中心に収録。2010年より公式な音源未発表のまま活動を開始し動向が注目され続けてきた彼らだが、そんな待ちに待ったファンの期待を超える胸熱なグッド・メロディが詰まった傑作を届けてくれた。あの鼻にかかった独特な歌声と言葉遊びのような歌詞、そして聴く者の心を芯から揺さぶるバンド・グルーヴは大健在。サイケデリックで捻くれたポップ・チューンで日本のロック・シーンに一石を投じたスパルタの魅力そのままに、現在進行形で進化するHINTOの今がここにある。
-

-
THE HIVES
Lex Hives
THE HIVES 5年振り5作目のスタジオ・アルバムは、構想1年半、レコーディングに3ヶ月という、じっくり練り込まれた濃厚な作品だ。“lex(法)”を掲げてセルフ・プロデュースされたサウンドは、バンド初期から貫かれているガレージ・ロックが炸裂。個性豊かなメンバー5人全員が“THE HIVESはこうあるべきだ”と大マジメにバンドと向き合い、衝突し合った末の結晶だ。ファッショナブルではないかもしれない。だが、自分たちが表現したいことを貫き通す彼らは、どこまでも勇敢だ。どれだけ時代が流れようと、THE HIVESはTHE HIVES。そう感じさせる彼らの芯の強さは聴く者にエネルギーを与え、笑顔を生む。真剣な熱いハートの衝突、これを青春と言わずして何と言おうか!
-

-
H MOUNTAINS
GOLD MEDAL PARTY
大森靖子のバック・バンド・メンバーとしても活躍する畠山健嗣を中心に、東京のインディー・シーンで活躍するメンバーが集い結成されたH MOUNTAINSの1stアルバムは、ニュー・ウェイヴ、サイケ、プログレまでをも飲み込んだ異色作。ゆるいヴォーカルとは裏腹に、しっかりと構成されたエキセントリックな楽曲たちが、気付けば頭の中をぐるぐると回り続け、思わず口ずさんでいる自分がいることに驚かされる。一聴するとなんだかよく分からない違和感を覚えるのだが、何故か再び聴きたくなるような衝動に駆られ、聴けば聴くほどに彼らのライヴに行きたくなってしまう。オルタナ界のくせ者たちが生み出した麻薬のような中毒性をお楽しみあれ。
-

-
HNC
Cult
CAPSULEの「Idol Fancy」へのフィーチャリングや、自身が参加するLOVE AND HATESでのAFRAとの共演でただ今注目を集めるYUPPA からHNC(HAZEL NUTS CHOCOLATTE) 名義での3rdアルバムが届けられた。軽やかでキュートな楽曲からは、海の向こうのシーンにも通じるベース・ミュージックを感じる事が出来る。女性は強しと言うべきか、世界中のインディ・ポップからダブ・ステップ、ボルティモア・ブレイクビーツまで飲み込んで彼女は自分のものにしてしまっている。最先端のビートを手作り感覚で、世界にカラフルに発信する。とにかく最高に楽しいYUPPAのマジカル・ポップ・ワールド。是非入り込んでみて下さい。
-

-
HOCKEY
Wyeth Is
ソリッドでダンサブルなサウンドを展開したデビュー・アルバム『Mind Chaos』で、THE STOROKESやTHE KOOKSと比較されるなど大注目のHOCKEYによる、4年ぶりのニュー・アルバム。2010年にメンバーが2人になったことでスケール・ダウンするかと思いきや、アルバムの冒頭「Wild Style」から、研ぎ澄まされたギター・ロック・サウンドが心地良く、むしろ自由度が増している。Track.4の「Dancer」は、ヴォーカルBenのソウルフルな歌声と遠くまで響き渡るようなドラムが印象的で、大ホールでのライヴにトリップしたような感覚に陥る。前作『Mind Chaos』同様さまざまなジャンルの音楽を駆使した多彩さはそのままに、落ち着いて丸くなり幅広い世代に聴きやすくなったのではないだろうか。
-
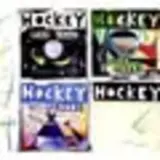
-
HOCKEY
Mind Chaos
耳の早いあなたならもう知っているかも。新たなインディ・ダンス・バンドとして注目を集めるHOCKEYが1月の来日公演に合わせいよいよ日本デビュー。最新のダンス・ミュージックを自分達のグルーヴに置き換え突き進む彼らだが、個人的に惹かれるのはKOOKSを彷彿とさせるヴォーカルBenのソウルフルな歌声とダンサブルで粘っこいリズム。乱暴に言うならばダンス・ビートに魅せられたMAROON 5と言った所か。それは先行シングルである「Lean To Lose」やファンキーな「3AM Spanish」でよく表れていて一筋縄には行かないポップ・センスと遊び心も忘れない彼らの魅力が溢れてる。
-

-
HOLIDAYS OF SEVENTEEN
HO17
既に全国的な知名度を誇る実力派4人組ポップ・ロック・バンドの3rdフル・アルバム。その内容は直球でキャッチーなロック・アンセムがこれでもかと詰め込めこまれた、勢いに満ちた出来となっている。冒頭を飾るリード・トラック「Is This Love?」の胸を締めつけるセンチメンタルなシンセ・サウンドと爽快なメロディで一気に彼らの世界へと引き込まれ、続く「Baby Baby」「MMM」では笑顔で埋め尽くされたライヴハウスのフロアが目に浮かぶようなポップ・チューンを堪能できる。様々なジャンルを飲み込みながらも、一貫して作品全体から溢れ出しているバンドの遊び心と聴く者を楽しませようとするサービス精神に心を奪われること間違いなし。
-
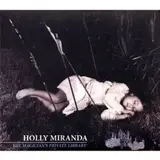
-
HOLLY MIRANDA
The Magician's Private Library
昨年末にシングル・デビューを果たしたばかりのブルックリン出身の大型新人。キュートなルックスと呟くようなハイトーン・ヴォイス。昨年末から各メディアに絶賛されて来た彼女がいよいよアルバム・デビュー。NYで出会ったという売れっ子プロデューサーであるTV ON THE RADIOのDavid Sitekを迎えて制作された今作はサイケデリックなFLORENCE & THE MACHINEとでも言いたくなる様なミステリアスで官能的な楽曲があったり、リズムミックなポップ・ソングがあったりと独創的ながらとても風通しのいい作品となっている。そして音の広がりや一つ一つの音のクオリティも素晴らしい。フォーク・シーンにとどまらない新たな才能の誕生だろう。
-

-
HOLY FUCK
Congrats
トロント出身の4人組インストゥルメンタル・ロック・バンドによる6年ぶり4作目となるアルバム。前作以降はそれぞれ別バンドやプロデュース・ワークなどのソロ活動期間となり、今作で再び集結。初めて本格的なスタジオでの録音となったのもそういった外部活動での経験を本体に還元できる体制になったゆえであろう。これまで直線的なビートを軸にクラウト・ロック、スカム、インダストリアル、エレクトロニカなローファイ・サウンドで高揚感を積み上げていく作りであったが、さらにパンキッシュ且つトライバルに極彩色を纏わせている。一方で、初めてヴォーカルを歌(≠ノイズ)として機能させることによりポップな面にも気を配っている。CAN、Sun Ra、BOREDOMS、SUICIDEが輪になって盆踊りを踊っているような光景。カオス!
-

-
HOLY FUCK
Latin
車を運転し、さらにはバンド活動を行う猫たち。そんなファニーな動画が話題を呼んでいるHOLY FUCK。『Latin』は、囁くように何かを語る声が不穏な予感を招くところから始まる。ほとんど沈黙に近い状況が、私たちの不安感を煽る。そして、激しいノイズの中、突然のスクラッチからトライバルなバンド・サウンドが姿を見せる。一気に引き込むように加速するノイズに、重ねられる予測不能な展開。4人ともが自由に音を鳴らし、神経を刺激するような不安定なサウンドを好き勝手に重ねていく。それは、怖いもの見たさの好奇心を痛いほどに刺激する。目隠しをされて嵐の中放り出されるような不安と異様な気分の高まりの中、息苦しいほどの恍惚感、倒錯感を覚える。
-

-
Homecomings
New Neighbors
Homecomingsが、2年ぶりとなるアルバム『New Neighbors』をリリース。本アルバムには、TVアニメ"君は放課後インソムニア"EDテーマ「ラプス」をはじめ、TVドラマ"失恋めし"主題歌「アルペジオ」、TVドラマ"ソロ活女子のススメ2"EDテーマ「i care」などのタイアップ・ソングを含む全12曲が収録されている。HomecomingsらしいUSインディーやギター・ポップに加えて、「光の庭と魚の夢」ではストリングスを導入。そのアレンジを同郷の岸田 繁(くるり/Vo/Gt)が手掛けるなど、音楽性の幅をさらに広げた作品に仕上がった。そして、フェミニズムやシスターフッドといったテーマに切り込んだ福富優樹(Gt)の歌詞も本作に重要な奥行きを与えている。
-

-
Homecomings
Moving Days
ネオアコ/ギター・ポップを起点にしたイメージから、レトロでシネマチックな世界観やフォークにもアプローチし、音楽性の幅を広げた前作『WHALE LIVING』の魅力をさらに拡張したような作品。中でもソウル/R&Bと切なさや儚さを孕んだ素朴なメロディ・センスが溶け合った味わい深い香りがたまらない。コロナ禍もあり、スタジオでのセッションからデモをやりとりする制作スタイルに。その結果、ストリングスや鍵盤、打ち込みなどメンバー4人が同時に奏でられる音以外にも前作以上に目を向けられるようになったことは大きかっただろう。優しく丁寧に紡がれた11曲は、社会的な問題に思うことをストレートに書いたというメッセージとともに、聴き手の心に想像力という名のあかりを灯す。
-

-
Homecomings
Somehow, Somewhere
ネオアコやアノラックって、厄介なジャンルだと思う。何故なら、ちょい下手なコーラスとか、お洒落な7インチとか、記号化されやすい要素が多い分、単なるファッション・アイテムになってしまう危険性が高いから。でもHomecomingsは違う。このバンドは自分たちの音を鳴らしている。待望の1stフル・アルバム、これは期待をはるかに上回る名盤だ。こだわったのはおそらくリズムの多様化だろう。畳野 彩加の、単調な、ゆえに乙女の溜息のような素晴らしい歌声を映えさせるには、実はメロディ以上にリズムが重要であると考え抜かれた楽曲たち。全10曲、名曲ぞろいだ。ひとつ今後への要望があるとすれば、日本語でも歌ってほしい。平賀さち枝とのコラボ曲は素晴らしかった。このバンドは、自分だけの言葉を紡げると思うのだ。
-

-
HOMESHAKE
Under The Weather
カナダのシンガー・ソングライター Peter Sagarによるソロ・プロジェクト、HOMESHAKE。Peterは、同じくカナダのシンガー・ソングライターであるMac DeMarcoのライヴ・バンドでギターを担当していたが、このHOMESHAKEに専念するため、そちらの活動からは離れている。そして、そんな彼の描く音楽世界は、ポップで温かみがありつつ、どこか毒っ気もあり、デジタルなサウンドの中に人間味が感じられる。特に、今作では鬱状態にあった2年前の心象風景を描いているということで、晴れやかな内容ではないが、鬱屈した心情を丸みのあるシンセ・ポップに仕立てることで、独特の心地よさを生み出している。深夜にひとりで何も考えず聴くと、疲れた心にほっと休息を与えてくれる作品だ。
-

-
HONEBONE
13
予備知識がないまま1曲目の「13」を聴くと、"漫談の口上か?"もしくは"この人は何をまくし立てているんだ?"と驚くかも。だが、この曲ではHONEBONEのプロフィールがほぼ理解できるのでまずは傾聴を。他人や世間、自分に対する鬱憤が大半を占める曲もあれば、日々の"せんべろライフ"を充実させてくれる愛すべきお店への感謝を歌った曲もある。それを役者顔負けの声と演技力で歌うEMILYと、ギター1本で支えるKAWAGUCHI。曲によってはリズム隊も入り、日常のブルースをタフに下支えしている。東横線沿線に住む人間を糾弾する、東京住みなら笑える「東横戦争」の荒涼としたサウンド、きれいごとに別れを告げる歌詞とドライな音像の「サラバ!」など、シンプルゆえに音と言葉が刺さる。
-

-
Honeydew
Time to Tell
90年代オルタナの最良の部分を受け継いだ男女3人組、Honeydew。彼らが約2年をかけて、じっくりと作り上げた2ndアルバムはバンドの進化が彼らの中にあるオルタナの定義の変化になって表れた。すなわち"ギターを轟音でかき鳴らすロック"から"何でもありな音楽"へという志向の変化は今回、シンセや打ち込みのビートも使いながら見事に多彩な楽曲へと結実した。従来の、どこかノスタルジックな轟音ポップ・ナンバーとサイケデリックなドリーム・ポップ、ハード・ロッキンなミクスチャー・ロック、エキゾチックなインストなどがひとつに溶け合い、架空の近未来ウエスタン映画を思わせるワイルドでロマンチックなひとつの世界観を作り上げている。丸ごと1枚トータルで楽しみたい懐の深さと器の大きさを持った作品だ。
-

-
HONNE
Ouch
UK出身のエレクトロ・ポップ・デュオ HONNEが3年ぶりのアルバムをリリース。自身の人生について歌われた本作は、彼等の持ち味であるハートフルな温かみがより色濃く反映された。パートナーとの結婚、親になることへの想い等、生活を取り巻く環境が変化したことに対して綴られた"本音"は、パーソナルでありながら我々リスナーの生活にも寄り添う、幸せな情景が描かれている。「Girl In The Orchestra」や「Imaginary」の柔らかなコーラスや跳ねるようなローズ・ピアノが、アルバム全体を明るく心地よいトーンに引き上げた、16曲49分と非常にタイトで聴きやすい1枚(※日本盤はボーナス・トラックあり)。愛らしいアニメーションや家族が出演するMVでも視覚的にハッピーな空気が感じ取れる。
-

-
HONNE
Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do?
ロンドン出身のエレクトロニック・アーバン・ソウルの名手の新作は長いタイトルが示す通り、ある仮定にもとづいたふたりの物語を軸に展開する。これまでマイナー・キーのメロウで洗練されたネオ・ソウル×エレクトロを持ち味にしてきた彼らが、グッと開かれたトーンのメロディやコードを多用。先行配信された88risingのNIKIをフィーチャーした「Coming Home」や、ブラスが印象的でアップリフティングなニュアンスすらある「Back On Top (Feat. GRIFF)」、デビュー作で2021年のブレイク・アーティストとなったArlo ParksとのTHE CARDIGANSを思わせるナンバー、Sam Smithらとの共作曲など、聴き心地の良さはそのままにポップスの強度を高めた名作。
-
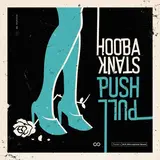
-
HOOBASTANK
Push Pull
何をHOOBASTANKらしさと考えるかで評価が変わりそうな8作目のアルバム。しかしもともと、いわゆるラウドロックの範疇に収まり切らない表現を追求してきたバンドだ。ファルセットを交えたDoug Robb(Vo)の歌唱も含め、今回のR&Bおよびファンク・サウンドの導入もその延長と考えれば、全然不思議なことではない。懐かしいTEARS FOR FEARSの「Head Over Heels」のカバーを含む前半は、80年代のファンク・サウンドがインスピレーションになっているんじゃないか。歪ませたギターの音が足りないというファンには後半がオススメ。R&Bの影響が色濃い楽曲にヘヴィなリフを巧みに組み合わせることで、哀愁のHOOBASTANK節は新境地と言えるアンサンブルをものにしている。
-

-
HOPE SANDOVAL & THE WARM INVENTIONS
Through The Devil Softly
MAZZY STARの歌姫Hope SandovalとMY BLOODY VALENTINEのColm O'Ciosoigによるユニットの8年ぶりの新作アルバム。ノスタルジックなアコースティック・サウンドに載せて、物憂げな歌声で物語るように歌うHope Sandoval。リヴァーヴがかかった、揺らぐようなリズムと悲しげに爪弾かれるアコースティック・ギターやストリングスの音色。全体を覆うような深淵なサウンド・スケープ。深い森の中を漂うような幻想的な闇夜の世界を築き上げる、ストーリー性の高いコンセプチャルなアルバムだ。それにしても、Hope Sandoval の妖艶でありながら少女性を失わない歌声を聴いていると、一体何歳なんだろうと余計なことまで考えてしまう。
-

-
THE HORMONAUTS
Spanish Omelette
イタリアのネオロカビリー・バンドTHE HORMONAUTS。このアルバムが日本でどれだけ出回るのかは正直未知数だけれど、とにかくこのアルバムは楽し過ぎる。スウィングするブレイクビーツ×ロックンロールがフロアを煽りに煽るパーティ・トラックが満載だ。ウッドベースにブレイクビーツを重ね合わせるスウィンギン・ビート。THE BPAとBECKとSTRAY CATSを足して3で割ってイタリアの太陽を浴びせまくったゴキゲンなロックンロールは、ロカビリーという枠で語ることなんてほとんど無意味。上昇を続けていく狂騒の夜を愛するならば、THE HORMONAUTSがその道程のどこかであなたを昇天させてくれることになるだろう。レーベルの皆様がこのアルバムを日本に持ち込んでくれることを切に願う。
-

-
THE HORRORS
V
THE HORRORSから3年ぶりの新作が到着。プロデューサーにAdeleやCOLDPLAYも手掛けるPaul Epworthを迎えたことで、独特な耽美的なメロウネスもNINE INCHNAILS的なインダストリアルなテイストも内にこもらず、大きなパースペクティヴで鳴っているのが新鮮。エレクトロニック且つ激しい先行トラック「Machine」もあれば、ギターのクリーン・トーンのカッティングがアーバン・ミュージックの要素も感じさせる「Press Enter To Exit」、スタジアムも似合いそうなドラマチックな「It's A Good Life」など、多彩だがメロディの良さとFaris Badwan(Vo)のクールな色気のある声ですべてに芯が通る。BOOMBOOM SATELLITESやD.A.N.、THE NOVEMBERS好きにもオススメしたい作品。
-

-
THE HORRORS
Luminous
THE NATIONALやARCTIC MONKEYSらを手掛けてきたCraig Silveyを共同プロデューサーに迎え、15ヶ月の期間を掛けて制作された、THE HORRORSの3年ぶりとなる待望の4thアルバム。今作はエレクトロニックな要素と、彼らの持ち味でもあるシューゲーズ・サウンドとを巧みに掛け合わせ、これまでの作品よりも明るくポジティヴなものに昇華させている。Track.1の冒頭ではどこかエスニックな雰囲気も醸し、静かに作品の始まりを告げる。ロンドンにてThurston Moore(SONIC YOUTH)をゲストに迎えてのライヴで初披露したことでも話題となった、7分半を超える大作「I See You」も収録されており、アルバムの中でも大きな存在感を示している。
-

-
THE HORRORS
Primary Colours
強烈なキャラクター性を持つガレージ・ロックで世界に衝撃を与えたデビュー・アルバムから早2年。前作の続編となるような作品への期待をいい意味であっさりと裏切る傑作。8分間の先行トラック「Sea Within Sea」でTHE HORRORSが次なるステップへ進んだことは明らかになっていたが、ここまでのアルバムを作ってくるとは思わなかった。プロデューサーに PORTISHEADのGeoff Barlowを起用し奥行きのある、まるで水中にいるかのようなシューゲーズ・サウンドが生み出す独特のグルーブ感。特にアルバムの後半は今までに無かったドリーミーな展開が繰り広げられる。呟くようなボーカルの中にも今回の変化が感じ取れるだろう。アルバム・ジャケットの様に手が届きそうで届かない蜃気楼のような作品。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























