DISC REVIEW
S
-
-
Su凸ko D凹koi
涙隠して尻隠さず
2010年に結成された3ピース・ガールズ・バンドSu凸ko D凹koi(読み:すっとこどっこい)の2ndミニ・アルバム。いきなりLED ZEPPELINのリフが聴こえてきたかと思いきや、一気に加速するオープニングから、Track.1「くず息子」、Track.2「店長、私バイト辞めます。」、Track.3「童貞応援歌」と続く楽曲は、女性ながら悪ガキ感満載のあるパンキッシュさ。Track.5「紅に染まる女子達」では身の周りのどころか生理について苛立ちと悲しみを歌っている。SNSからはみ出たようなリアルな日常を歌う言葉の数々を、共感して痛快と感じられるかどうかは聴く人を選ぶはず。音楽的表現力に長けた女性バンドが増えているだけに、音楽面で光る何かをしっかりと残して欲しい。
-

-
THE SUZAN
Golden Week For The Poco Poco Beat
"オフィスに届いた一本のデモテープ。「THE SUZAN」と書いてあり、プロフィールらしき紙には、英語で「世界中に自分たちの音楽をばらまきたい」と..."これは彼女たちの古巣、ROSE RECORDのHPに掲載されている曽我部恵一によるTHE SUZANの紹介文の一部。そして、本作が念願の世界デビュー作、コケティッシュな魅力がいっぱいの4人の女の子が、世界にばらまく最初の音だ。一歩先ゆくインディ・サウンドを鳴らすバンドがこの国にいたという奇跡が、下北沢の小さなハコにいたなんて嘘のように、今や彼女たちは世界の人気者になろうとしている。それ見たことか。もたもたしてるから、THE SUZANが海の向こうに持っていかれてしまったじゃないか。おいそれと日本発なんて言ってはいけませんよ。彼女たちは、初めから世界水準なのだから。
-

-
THE SUZUKIS
The Suzukis
2000年前半のロックンロール・リバイバル期にデビューしたTHE MOONEY SUZUKIというバンドがいたが、「SUZUKI」という名前は向こうにとってどれほどインパクトがあるのか聞いてみたい所だがそれはさておき。マンチェスター出身THE SUZUKISのデビュー・アルバムは伝統的なUKパンクの流れを受け継ぎながら、切なくもメロディアスで力強い楽曲が並ぶ渾身の一枚。ヴォーカルChris Veaseyの鬼気迫るパワフルな歌声ももちろん聴き所なのだが、アルバム全体を流れるイギリスのバンドらしい男臭さや、シンプルでストレートなビートにやられる。疾走感も合わせ持ちながらしっかりと聴かせる部分があるのが、彼らの魅力の一つでもあるだろう。
-

-
suzumoku
真面目な人
アコースティックなイメージを一新し、エレキ・ギターをかき鳴らしたロック・アルバム『Ni』でも驚かされたが、その勢いのまま発射されるニュー・シングルはピリッとスパイスの効いた応援歌。現実を見据えた自分自身への心の叫びでもありながら、他者にも向けられた救いなのかもしれない。イマイチ煮え切らない真面目な性分と衝動がいつだって自分の中に同居しているのだ。切迫感のあるカップリング曲「鴉が鳴くから」は挑発的で、今まで気づかなかった自分の本心を突いてくる歌詞に心打たれる。suzumokuというアーティストは地に根付くように力強い低音と、開いていく歌声がなんといってもクセになる。ギター1本でメッセージを投げ続ける姿はシンプルで何よりも力強い。
-

-
SVOY
Grow Up
ロシア生まれのソロ・アーティストSVOY(スヴォイ)の3rdアルバム。幼少時にクラシックとジャズ・ピアノのレッスンを受け、10代の頃にはトップ・ジャズ・ミュージシャンの手ほどきを受ける。その後、ボストンのバークリー音楽院へ進学し、さらなる音楽の探究を開始…。その半生からも分かる通り、音楽の英才教育によって育った音楽解釈とエレクトロ・ビートとのスマートなる融合が、このなだらかな景色と疾走感を生みだしたのだろう。まずはそのメロディ・センス。雨の日の憂鬱と静けさも、心地良い気だるさへと変わっていくような、淡く流麗で滑らか、そしてシンプルなメロディは秀逸の一言に尽きる。これが都会的なエレクトロ・ポップと出会った時、洗練された中に滲みだすのは透明で美しいサウンド・スケープだ。
-
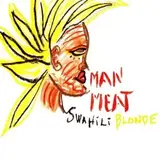
-
SWAHILI BLONDE
Man Meat
元WEAVEのドラマーであるNicole Turleyが中心となって始まったこのプロジェクト。今作の話題はなんと言ってもRED HOT CHILLI PEPPERSを脱退したばかりのギタリストのJohn Fruscianteが全面的に参加している事だろう。ヒリヒリとするようなノーウェイヴ/ニューウェーブ・サウンドが駆け巡る今作ではJohnのファンキーで切れ味のあるギターが炸裂している。もちろんNicole Turleyのエキセントリックで幻想的なヴォーカルも聴き所だが、今のブルックリン勢にはない攻撃的で異国情緒漂う独特なサイケ感がとても新鮮に響く。変則的なグルーヴも新たな体験を与えてくれる。豪華ゲスト陣と作り上げたフューチャー・サイケデリック・アルバムの完成だ。
-

-
SWANKY DOGS
ショートシーン
繊細にきらめくギター・アルペジオに乗せて、そこにいる誰かに"声を聞かせて"と語り掛けていく「hope」で始まるミニ・アルバムは、日々の何気ない瞬間や、沸き起こる感情のうねり、見上げた美しい景気や俯いた足元の不透明さ、あるいは遠くに思いを馳せる想像力など、様々なシーンを通した日常が綴られた。バンドの15周年を締めくくる作品にもなり、衝動的に叫ぶような初期作品「Raysman」の再録バージョンから、ソングライター 洞口隆志(Vo/Gt)の打ち込みのアレンジを生かした軽やかでノリのある「MTMY」など、新たなタッチの曲もパッケージされた。オーセンティックな3ピース・ロックの良さはもちろん、時を重ねた今の3人だからこその自由度の高さで、曲に息を吹き込んでいる。その呼吸の心地よさを感じる作品だ。(吉羽 さおり)
-

-
SWANKY DOGS
流転
時の流れは止められず、人の気持ちも移ろうもので、無情に思えるほどに変わらないものなどない。だからこそ、まったく同じ日は訪れないし刹那の美しさも実感する。そしてそれでも永遠というものに憧れてしまう。結成15周年を迎えるSWANKY DOGSによる3年ぶりのフル・アルバム『流転』には、タイトル通りそんな日々の中での心の機微を描いた曲が揃っている。グッド・メロディとめまぐるしい毎日を必死で生きようとする直球のメッセージがライヴでも映えそうな「がらんどう」、"声になって 傍にいられたら"と体温の感じられる歌唱で届ける「こえ」、かっこつかない生活に寄り添う「ルチル」などを経て、作品を締めくくる「gift」のラストの一節まで聴き終えたとき、なんだか昨日よりも優しくなれる気がした。
-

-
SWANKY DOGS
Light
岩手発の3ピース・バンド SWANKY DOGSが、前ミニ・アルバム『イデア』から2年ぶりにリリースするフル・アルバム。ロックな楽曲で攻めた前作から一転して、バラードやミドル・テンポの楽曲も多く収めた今作は、作詞作曲を手掛ける洞口隆志(Vo/Gt)が持つ温かい歌の魅力が強く浮き彫りになった。言い訳ばかりの日々に対する後悔も、理不尽に涙を流す日々も、"大丈夫さ うまくいくよ"(「ワンダーライフ」)と大きな心で受け止める、バンドの揺るぎない包容力はそのままに、「アポリア」や「花火」では、打ち込みを取り入れた新機軸となるサウンド・アプローチにも挑戦。バンドの地元岩手県盛岡市と東京でレコーディングしたという今作では、彼らの原点と現在地が美しく交錯する。
-
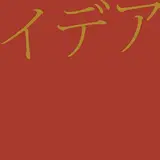
-
SWANKY DOGS
イデア
地元・盛岡のライヴハウス、CLUB CHANGEを拠点にライヴ・バンドとして精力的な活動をする3ピース、SWANKY DOGSが前作『In The City』から2年ぶりに完成させた初メジャー流通アルバム。バンドの原点回帰をテーマに掲げ、初めてメンバーがロック・バンドに出会ったときの衝撃や熱量を取り戻すべく完成させた今作は、全曲がソリッドなロック・ナンバーになった。同時にどの曲にも貫かれる瑞々しいメロディには、時に生々しく、時に語り掛けるように、それぞれの人生にある"イデア(真実)"とは何かを問いかけてくる。孤独ややけくそな自分を認めながら、ラスト・ナンバー「Hello」で、ようやく言えた"あなた今照らせたなら"というフレーズ。その言葉は控えめだが、あたたかかった。
-

-
SWANKY DOGS
何もない地平線の上から
盛岡発の3ピース・バンド、SWANKY DOGSの1stフル・アルバム。バンド6年目にして初の全国流通盤は、全曲新曲で臨んだ意欲作だ。盛岡でのライヴ活動で交流が生まれたex.No Regret Lifeの小田和奏がレコーディングに参加し、ライヴハウスの人々の意見も存分に反映されている。盛岡のライヴ・シーンが一丸となって作り上げたアルバムと言ってもいい。彼らがそれだけ多くの人々を巻き込むことができる要因は、健やかに音楽を続けてきたことが感じられる、力強くもとてもぬくもり溢れるサウンドと、日々の生活への葛藤から生まれる"決意"が綴られた歌詞。洞口隆志(Vo/Gt)は感情を明快な日本語に落とし込み、素朴なメロディに乗せてまっすぐ歌い上げる。粗削りながらも、強い芯が貫かれた11曲だ。
-

-
SWANS
Leaving Meaning.
NYエクスペリメンタル・ロックの重鎮による15thアルバム。2010年の再結成以降の活動スタイルであった6人編成を、前作『The Glowing Man』をもって解散させたSWANSだが、今作ではフロントマンのMichael Giraを中心に、エレクトロ・ノイズの鬼才 Ben Frostや、豪州の即興演奏バンド THE NECKS、さらには元メンバーなど、Giraが性格面まで考慮して選んだという30名以上のアーティストが参加している。近作に比べるとポスト・ロック的な轟音ノイズはやや控えられ、ネオ・フォーク/ゴシックのオーガニックな質感が増しているが、Giraの呪文のような歌唱と、反復しながら展開していく暗黒のグルーヴは実にSWANSらしい。美と混沌を湛えた、奥深い1枚。
-

-
SWANS
The Glowing Man
いわゆるオルタナティヴという概念がロック・シーンに定着する以前は、畏怖の念と共にジャンクと謳われたMichael Gira率いるニューヨークのエクスペリメンタル・ロック・バンド、SWANS。その起源は1982年にまで遡るが、13年の空白を経て、2010年に再結成してからは立て続けに大作を発表してきた。その彼らが再結成後4作目となるアルバムをリリース。本作は現在のラインナップで作る最後の作品。前々作、前作に引き続き、全8曲で2時間を超えるCD2枚組。Giraのうめき声のようなヴォーカルの印象が強烈すぎるせいか、鬼気迫る演奏は彼ら以外の何者でもない。アメリカーナの源流に迫りながら、ゴシック、ドローン、サイケ、スラッジなど、様々な要素が入り混じる底知れなさにこそSWANSの真骨頂がある。
-

-
SWANS
To Be Kind
Michael Gira率いるUSオルタナの真の帝王、SWANSはいま再びキャリアにおける絶頂を迎えたようだ。再結成第2弾アルバムだった前作『The Seer』は彼らの最高傑作と謳われたが、それから2年、彼らはそれを遥かに凌駕する新作を完成させてしまった。CD2枚組全9曲2時間超の大作。ツアー中のジャム・セッションを発展させ、スタジオで丹念に作り上げたという。その世界を表現する言葉はアート・パンク、アメリカーナ、ドゥーム・メタル~ドローン、ゴシックと枚挙に暇がないが、ここではアメリカに対する地下世界からの呪詛だと言ってみたい。圧巻はドローン効果を追求した34分のTrack.4「Bring The Sun」。とは言え、長尺だからすごいのではない。そこに渦巻くどす黒い情念の濃密さが重要なのだ。
-

-
シュリスペイロフ
遊園地は遠い
結成21年目を迎えた札幌発の4人組がさらなる新境地を打ち出した6thフル・アルバム。聴き手のマニア心をくすぐるアングラな魅力を絶妙に残しながら、ロック・バンドとしてパキッとした印象をアピールしたのは、バンドの成熟を汲み取ったプロデューサー、山中さわお(the pillows)のサジェスチョンによるところも大きいようだ。ともあれ、日本語のロックの系譜に位置する4人組のレパートリーに、例えば、NIRVANAやWEEZERを連想させる曲が加わったことは、今後ライヴにおけるインパクトしても効いてくるに違いない。わかるような、わからないような、わからないような、わかるような歌詞も大きな聴きどころだが、1組の男女の物語として想像を膨らませると面白い。それもひとつの聴き方だろう。
-

-
シュリスペイロフ
シュリスペイロフ LIVE+-
ある人は言っていた、彼らを“北の最終兵器”と。99年結成(初ライヴは04年)、北海道を拠点に活動を続けるシュリスペイロフのライヴ・ベスト・アルバム。公式サイトのプロフィール・ページでは、本文の頭に“今年はユルくも動くぞ、シュリスペイロフ!!”となんとも気の抜ける宣誓(?)をしているが、確かに全てがそんな感じ。全てなんてことないとでもいうように、明け透けな、あっけらかんした佇まいのヴォーカルとバンド・アンサンブル。“変わらず僕らは此処にいるよ”と言われているような安心感には、郷愁のようなものすらこみあげてくる。このバンドが持つのは、そんな暖かさと、良質な3ピース・バンドとはなんたるかという確立された世界観。つまるところ、“ゆるさ”だけを期待して聴いた日にゃあ、確実にえらい目にあうということだ。
-

-
Swimy
僕と魚の物語
Leo Lionni作の絵本"スイミー"からバンド名を付けたSwimyにとって、初の魚ソングが完成。NHK「みんなのうた」へ書き下ろした表題曲「僕と魚の物語」は、哀愁漂う歌謡的なメロディに"もしも僕が魚になったら"という架空のストーリーを描く。7月にドラマーが脱退したことで、生ドラムによる打ち込みを使用したドラムレスのレコーディングに挑戦したほか、カップリングの「天使と悪魔の歌」ではsyrup16gの中畑大樹(Dr)も参加。これまで抽象的な歌詞を好んだソングライターのTakumi(Vo/Gt)が自分自身を鼓舞するような歌詞をストレートに綴った「しゅるる」からは、メンバー脱退というバンド最大の危機を3人で乗り越えて新たなスタートを切る決意が込められているようにも感じた。
-

-
Swimy
絶絶ep
TVアニメ"NARUTO-ナルト- 疾風伝"エンディング・テーマ「絶絶」を収録したSwimyの新作。"ひとり"をテーマにした前作『おひとりさま』に続き、今作では"人との繋がり"がテーマ。パレードのような祝祭感が溢れる「僕の言葉で」、一筋縄ではいかない複雑な曲展開の「ナンカイ」や、聖歌隊のようなコーラスとバンド・サウンド+EDMの融合で昂揚感のある「どうして」など、自由でジャンルレスなポップ・サウンドが新鮮な音楽体験をもたらしてくれる。全体に賑やかなサウンドが持ち味だが、不意打ちのように置かれたピアノ・ロック「アナタキミ」のセンチメンタルは、実はSwimyはシンプルな曲の良さでも勝負できることを証明する佳曲。隠れた名曲と呼ばれそうな予感がした。
-

-
Swimy
おひとりさま
親しみやすいメロディとメルヘンチックな歌詞、男女トリプル・ヴォーカルが特徴的なSwimyが、今年3月にメジャー・デビュー。独特なフォーマットを持つバンドだけにどんな道を歩んでいくのか気になっていたが、このミニ・アルバム、大正解だと思う。今作のテーマは"孤独"と"愛"。命の重さにまで話が及ぶほどのシリアスな内容でもポップに鳴らせば受け入れられてしまう――というマジカルな力が発揮されている。先に挙げたバンドのキャラクターがそれを可能にしているのだ。"怖ければ目を背けてもいいよ/変わりに僕が君の目になる/君のための歌だ さぁ逃げよう"(Track.4「ナイトミュージック」)と歌うその優しさで何もかもひっくり返すための、痛快な宣誓がここに。
-

-
SWMRS
Berkeley's On Fire
Billie Joe Armstrong(GREEN DAY)の息子であるJoeyがドラマーを務める、カリフォルニア出身の4人組、SWMRS。名門"Fueled By Ramen"からもリリースされた前作『Drive North』で躍進を遂げ、"SUMMER SONIC 2017"にも出演を果たした彼らが、約3年ぶりとなる新作をリリースした。エネルギッシュなトラックに打ち込みも交え、現行シーンにも通じるラップ調のフロウを乗せたTrack.1やTrack.4が表すとおり、プリミティヴなパンクを土台としながらも、インディーからヒップホップまで様々なジャンルをセンス良く混ぜ合わせたサウンドは独自の存在感がある。"IKEA Date"などシュールなタイトルや歌詞にも注目だ。
-

-
SWMRS
Drive North
Billie Joe Armstrong(GREEN DAY)の息子 Joseph Armstrongがドラムを務めることでも知られるカリフォルニア、オークランド出身のパンク・ロック・バンド。といっても、単なるパンク・ロックなんて言葉だけでは表現しきれない魅力溢れる彼ら。ポップだけど気だるさたっぷりのサウンドとCole Becker(Vo/Gt)の叫びは、カリフォルニアのポップ×サーフ×パンクのイメージをアップデートしてくれた。エッジーなギター・サウンド、鳴り止まないドラムとベースのビート、そして"ポスト思春期"とでも言える主張たっぷりのリリック、どれも都会と田舎の良さを知る彼らだからこそ創り出せるものだろう。日常に窮屈さを感じている人におすすめしたいアルバム。
-

-
Symdolick
GATE
昨年10月に新体制となった"オシャレ高速チョイ横アイドルロック"を奏でるSymdolickの、初CD化となるミニ・アルバム。新体制第1弾となったシングル「Symdolicxxxxx」で始まり、前身グループからSymdolickでも歌い繋いできた曲をパワーアップさせ、新曲を加えた全6曲を収録した。ストレートなロックやダンス・ロックはパワフルで、また憂いや切なさを帯びて繊細にもダイナミックにも振れる複雑な心情をメロディ・ラインが描く。5人の声で歌い繋ぐことで、その歌が生き生きと呼吸を始めてフレンドリーになっていく感触だ。つんつく♀︎による作詞作曲に加えて、「ごめん」では小原ジャストビガンが作詞作曲、SCRAMBLESがプロデュースを手掛け、キャッチーさとキュートな5声が際立つ曲になっている。
-

-
SYML
Syml
シアトルのインディー・ロック・バンド BARCELONAのフロントマン、Brian Fennellによるソロ・プロジェクト SYMLが、初のフル・アルバムをリリースした。バンドとしてのアプローチや個人名義でのアプローチとも違う、SYML名義ならではのシンプル且つエレクトロニカをふんだんに用いた表現で、センスの良さが光る。アップテンポでちょっとレトロなインディー・ロック臭のするTrack.1「Clean Eyes」はキャッチーな掴みで、全体的には、ゆったりとしたテンポ感でアンニュイなサウンドが漂う。囁くようなBrianのヴォーカルも心地いい。シンガー・ソングライターで、マルチ・プレイヤーで、プロデューサーというBrianの才能が凝縮された1枚。
-

-
sympathy
泣きっ面に煙
今年メンバー全員が大学などを卒業して、これまでの遠距離から東京を拠点とする活動となったsympathy。学生時代や10代への郷愁感を滲ませながらも、社会に出て毎日を目一杯生きている女の子の姿を描いているのが、この4thミニ・アルバムだ。いろんな恋愛で味わった痛みで成長をしたり、相変わらずのところでつまずいたりもする。それを冷めた目で見ながらも、それでも夢を見ることは忘れない、ビター&スウィートな物語をポップなギター・ロックで聴かせる作品。ノイジーにギターをかきむしるオルタナ曲から、シティ・ポップ風のサウンドに気だるいヴォーカルがコントラストをつける曲、引き算のサウンドが歌心を呼ぶ曲など、サウンドそれぞれのこだわりも高くなった。でもやっぱり大人になるって難しい。
-

-
sympathy
トランス状態
絶妙に跳ねるビート。それなのに、甘いメロディと独白めいた言葉が粘着質を持って耳と心にこびりつく。"ギター弾けないの 弦が傷口に引っかかってね"――それでもギターを掻き鳴らす少女たちが痛みと共に滲ませる鮮血。sympathyの音楽は、"若さ"という名の永遠の病を、そこに潜むぬかるみを、抜け出そうとすればするほど濃淡を濃くしていく底のないサイケデリアを、狂おしいほどの瑞々しさで描き出す。歌詞の中で"あの日"という言葉が繰り返し歌われるのは、すべては失われてこそ永遠となり、喪失感こそが、私たちを常に魅了し続けるという悲しくも甘美な真理を、彼女たちが身をもって知ったからだろう。メロウなTrack.3「紅茶」、そして弾き語りのTrack.5「泣いちゃった」が刻む痛みの痕跡が、息をのむほどに美しい。
-

-
sympathy
カーテンコールの街
大人と子供の間で引き裂かれた"ティーンエイジャー"という価値観。それはロックンロール永遠の命題。高知出身の4ピース・ガールズ・バンド、sympathy。未だ平均年齢19歳の彼女たちがこの1stミニ・アルバム『カーテンコールの街』に刻み込んだものこそ、そんなティーンエイジャーという宙ぶらりんな季節に宿る哀しくも美しい煌きに他ならない。日本マドンナと相対性理論の狭間にあるような、初期衝動全開のグルーヴィなギター・ロックと柔らかく可愛らしいポップネスを横断するサウンドは、何者にもなれない苛立ちと、抱きしめようとするものすべてを傷つけてしまう哀しみを生々しく描き出す。もう2度と、彼女たちはこんな作品は作れないだろう。何故なら若さは失われるから。だからこそ、僕はこの作品が愛おしくてしょうがない。
-
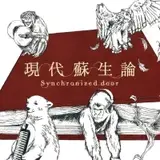
-
Synchronized door
現代蘇生論
"あの時こうしていたら"、"この1言を伝えていれば"、"もし、あの瞬間にもう1度戻れるのならば"。そんな"たら、れば、もし"の呪いは必ず誰しもが胸の中でふつふつと抱えているだろう。毒薬のようなその感情を、メンバーの脱退に伴い活動を休止していたSynchronized doorが2ndミニ・アルバムとなる今作で、爽やかなサウンドを持って表現している。ギラギラした野心を感じさせる乾いたギターに乗る、透明感のあるurio(Vo)の澄み切った歌声がとても印象的だ。Synchronized doorの新たな門出に相応しい、開放感溢れる作品。そして、日々葛藤に苛まれ、"たら、れば、もし"の呪いがいつまでも胸の中で色濃く残るあなたにも相応しい作品だ。
-

-
syrup16g
delaidback
名盤『COPY』から16年を迎えるにあたり、ツアー開催に加え、なんと未発表曲からなる新作が出る。五十嵐隆(Vo/Gt)個人や"犬が吠える"、さらに遡ってsyrup16gでもライヴでしか演奏されてこなかったデモを掘り起こし、今の3人で更新したアルバムだ。これまでの作品にも、派手さはないものの五十嵐の本質を突き詰めた言葉とアンサンブルに落とし込んだ楽曲を収めてきたが、今回もシューゲイザーやグランジの匂いをさせつつ、シンプルだからこそ不穏さも立つサウンドと平熱の視点が響く。喜怒哀楽からも遠く、絶望も通り過ぎた。だが、Track.12「変拍子」の"あきらめているのでもない/分かりあえた日々が 眩し過ぎて/見れないだけ"というハッとする一節にも耳を澄ませたい作品。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























