DISC REVIEW
P
-

-
POETASTER
The Gift of Sound e.p.
誰に、なんのために、この音楽を届けるのか。それが明確に浮かびあがる作品だ。八王子発のギター・ロック・バンド POETASTERが、ふたり体制で初めて完成させた1st EP。これまで恋愛の歌が多かった高橋大樹(Vo/Gt)のソングライティングが一転、君を泣かせる奴は許さない、とストレートに歌う「君に話があるんだ」に代表されるように、聴き手の人生に寄り添う全5曲が収録されている。バラエティ豊かな作風となった前作に比べると、シンプルにまとめ上げた今作は、歌と言葉が鋭く心に突き刺さる。彼らが届けるべき"誰に"とはリスナーであり、"なんのために"とはその人生を肯定してあげるために、だ。まさに"The Gift of Sound=音楽の贈り物"というタイトルがぴったりな、強くて優しい1枚。
-

-
POETASTER
Imagination World
今、こういう音楽を求めていた。オリジナル・メンバーの脱退を乗り越え、新メンバーを迎えたPOETASTER。彼らはこのニュー・ミニ・アルバムで、逆境を追い風に変えるという自信と、吹っ切れた強さを手に入れている。パワフルなクラップが響く1曲目「DANCE DANCE DANCE」の"いつか その傷に意味があること"、"僕が わからせてやる"という言葉、全身全霊のコーラスからその気概が滲み出ていて沁みる。情報が多すぎる現代を一緒に進む術を、説得力をもって高らかに歌い上げる表題曲「イマジネーションワールド」もいい。そんな自分たちの決意や信念と、音楽を聴いてくれる"君"のことだけを想った全7曲。音像も言葉も、ストレートだからこそ飛びっきりグッとくる。それが今一番味わえる1枚だ。
-

-
POETASTER
トロイメライ
八王子発の4人組日本語ロック・バンド POETASTERが、前作からおよそ7ヶ月で発表する全曲ラヴ・ソングのミニ・アルバム。オープニングの「キャラバンに乗って」は明るく軽快なサウンドだが、ファンタジーなワードと現実味溢れる描写との対比が共感と切なさを生む。続く「デイジー」はわがままだけどなんだか憎めない女の子が主人公のアッパー・チューンで、サビに向けてぐっと熱量を増す、ライヴでも映えそうな1曲だ。「あなたのことばかり」では、忘れたいけど忘れられない人への想いをひたすらに綴った歌詞が痛いほど胸に沁みる。彼氏目線だったり彼女目線だったり、はたまた失恋ソングだったり妄想の歌だったりと、カラーが異なる全6曲。今のあなたに寄り添ってくれる曲がきっと見つかるはず。
-

-
POETASTER
声命力
グッドモーニングアメリカ、NECOKICKSを擁するFIVE RAT RECORDSから初の全国流通盤を放つニューカマー、POETASTER。"生"を"声"に換えて"声命力"――それだけで、彼らがいかに声に想いを託して歌にしているかがわかるだろう。"詩人"を名乗るだけのことはある、ドラマ性が高く情景的な歌詞と、そこに込められたメッセージを運ぶ熱を帯びた歌声は相乗効果で強い武器に。"所詮"とか"どうせ"とか、若者がこぼしがちなネガティヴなワードをフックにしつつ、そこから光の当たる方へ引っ張っていくパワーは計り知れない。そして、ライヴ感のある熱いバンド・アンサンブルから始まる曲が多いあたり、さすがはライヴハウス・シーンが色褪せない八王子育ちのバンドだ。メロディックなギター・フレーズも、彼らのカラーを強く印象づける。
-

-
Poet-type.M
A Place, Dark & Dark -永遠の終わりまでYESを-
"A Place, Dark & Dark=夜しかない街"の4部作の最終章。自ずと自分や世界の本質を深く覗きこむことになるこの"街"を舞台にした連作は、同時に門田匡陽と仲間たちのバンド感、楽団感も有機的に育んでいったように思う。ニュー・ウェイヴ的なクールネスと気が遠くなるようなサイケデリアを基盤に持ちつつ、肉体性を兼ね備えた楽曲が大半を占めるようになったのだ。もとより強力なメロディ・メーカーである門田の歌が存在感を増し、潔癖なだけではない、他者に傷をつけられないメンタリティを印象づける。そして第1作で語られていた"小さなNoと大きなYesを言う"ことの実相が、ラストの「永遠の終わりまで、『YES』を(A Place, Dark & Dark)」に登場するこれまでの楽曲の断片も相まって聴く人それぞれの"扉"を開ける。
-

-
Poet-type.M
A Place, Dark & Dark -性器を無くしたアンドロイド-
秋らしい哀愁とかアンニュイという形容に収束しきれないカオティックな展開を見せるTrack.1「だが、ワインは赫(Deep Red Wine)」の、物語とともに呼吸するようなストリングス・アレンジにまず圧倒される。Good Dog Happy Menから綿々と続く世界観をさらに熟成したようなこの曲に門田匡陽の作家としての背骨を感じつつ、意外なほどキャッチーな歌メロを持つTrack2「あのキラキラした綺麗事を(AGAIN)」など、光を感じる楽曲を経て、門田と楢原英介のギターが織りなす空気感が森の中や、瞬く星空をイメージさせるTrack.5「プリンスとプリンセス(Nursery Rhymes ep4)」、穏やかな音像に乗せて厳しい言葉が並ぶタイトルチューンに至る6曲。世界に対する決然とした態度、表現の自由度を堪能できる。
-

-
Poet-type.M
A Place, Dark & Dark -ダイヤモンドは傷つかない-
夜しかない街、"Dark & Dark"も、さすがに夏は輝度の高い楽曲が居並ぶ。Track.1「バネのいかれたベッドの上で(I Don't Wanna Grow Up)」で聴けるGood Dog Happy Menでの楽隊的な生命感、打って変わって、8bit感たっぷりなゲーム・ミュージック的なイントロダクションから80年代ニュー・ウェイヴ的な「窮屈,退屈,卑屈(A-halo)」、ピアノとシンセのレイヤー、辛辣な言葉が涼し気なサウンドに乗るクールネスが、正義を振りかざすことの怖さを伝える「神の犬(Do Justice To?)」。しかし最終的には、"君の本当の自由は星の数以上さ"と、夜しかない街をうろつく私やあなた自身の物語を優しく、ある種冷静に見守ってくれているような心持ちになるのはなぜだろう。過去に思いを馳せ静かに過ごす夏もいい。
-

-
Poet-type.M
A Place, Dark & Dark -観た事のないものを好きなだけ-
Poet-type.Mの四季に渡る作品の序章は、キラキラしたきれいなメロディ、有機的なバンドサウンドとエレクトロニクスが融合した「唱えよ、春 静か(XIII)」のまっすぐな眼差しからスタートする。シューゲイズやニューウェイヴ・マナーに則った透明感と輝度の高いナンバーを軸に、寓話的な部分をちょっとタガが外れたギターや唐突なパーカッションがユニークな「泥棒猫かく語りき(Nursery Rhymes ep3)」、軽快なスウィングに乗せて、タイトルにもある"観た事のないものを好きなだけ"と、それぞれの冒険に誘うような「楽園の追放者(Somebody To Love)」など胸躍る6曲。楢原英介(Gt)、水野雅明(Dr/Syn)、Good Dog Happy Menからの盟友、伊藤大地(Dr)の3人が曲ごとに異なる組み合わせで参加している。
-

-
polly
Heavenly Heavenly
2022年にギタリストとベーシストが脱退し、志水美日(Key/Cho)を迎えて3ピースになったpollyの新体制初EP。前作同様"別れと再会"をテーマにしつつ、前作よりも"別れのあとの自分のリアルタイムな想い"にフォーカスしたという本作は、引き続きシューゲイズ・サウンドを基調にしつつ、「ごめんね」に顕著な、地声に近い歌声をあえて使うといったヴォーカリゼイションの変化があり、「Snow/Sunset」では女性コーラスの新規参入により物語性の奥行きも増していて、新たなpollyのシューゲイズが感じられる仕上がりになっている。特に「K」は越雲龍馬(Vo/Gt/Prog)が初めて母への気持ちを歌にした温かなナンバーで、歌心がこもった近作の彼らのひとつの到達点のように感じられる。
-

-
polly
Four For Fourteen
自主レーベル"14HOUSE."設立後初のアルバム。シューゲイザーなどの影響を色濃く映す、浮遊感あるサウンドのイメージが強いバンドだが、一歩深く踏み込めばそこにあるのは、優しいだけではない音の濁流だ。カオティックなサイケ・サウンドから、恐怖を感じるほどのアンビエント的な音の奔流まで――脳髄に直接作用するようにじわじわと胸がざわめくが、クライマックスの「言葉は風船 (hope)」や「点と線」の、唱歌的なメロディと絹のように滑らかな越雲龍馬のヴォーカルには、まるで鎮魂歌のような途方もない優しさと郷愁が満ちている。「狂おしい (corruption)」、「刹那 (canon)」など既発楽曲のリアレンジ4曲も収録された、pollyというバンドの奥行きを存分に感じられる1枚。
-

-
POLPO
peels off
ヴォーカル・ナンバーとインストをほぼ半々ずつ収録したPOLPOのデビュー・アルバム。曲の根底にあるのは、90'sエモやポスト・ロックだろうか。しかし、曲ごとにアンビエント、アヴァンジャズ、シューゲイザー、ハード・ロックと切り口を変え、オルタナ・ミュージック・グループを名乗るこのユニットのスケールのデカさを印象づけている。その正体はPay money To my Painのメンバー、PABLO(Gt)とZAX(Dr)。ふたりが出会って30周年を迎えたことを記念して、活動を始めたそうだ。各楽器が歌うTrack.2「in the mountain」ほか、英語で歌っているにもかかわらず、ヴォーカル・ナンバーが持つメロディからは、どこか日本情緒を感じられるところが極めてユニーク。
-

-
POLYSICS
走れ!with ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)
シングルとしては約9年ぶりになる今作は、TVアニメ"はたらく細胞BLACK"のOP/ED主題歌である2曲と、過去に同アニメに起用されたClariS「CheerS」のカバーを収録。タイトル曲はキュウソネコカミのヤマサキセイヤ(Vo/Gt)をゲストに迎えた。"明日へ振り絞って/奮い立たせ進め"、"決してその光 絶やさないで"というPOLYSICSでは歌わない直接的な表現や、まっすぐに疾走するサウンドも、アニメの内容やヤマサキの存在があるからこそだろうか。ハングリーなヤマサキの歌声を曲の動力にする感覚で、馬力あるバンド・サウンドに、いつにも増した人力のエネルギーを迸らせた曲で新鮮だ。ED主題歌ではCVを務める声優を迎え、ピコピコサウンドで遊びに遊んでいる。
-

-
POLYSICS
In The Sync
前作から約2年ぶりとなるアルバムは、ガレージ感のあるギター・リフとアグレッシヴなビートに乗せ"Broken Mac!!!"と叫ぶ「Broken Mac」でスタート。毎度アルバムのムードを伝える1曲目に、一発で録りあげたような生々しいアンサンブルを聴かせてくれるのが爽快だ。20年を経てエクストリームに加速するサウンドを聴かせ、また「Belong」ではファンク的なアプローチも健在。「Surprise me」や「Abrinbou」の言葉や語感で遊ぶリズミカルな歌詞とギターとの絡み、というか緩急のある掛け合い漫才のような心地で聴かせるニューウェーヴ感は、彼ららしくもあり、さらに進化している面白さがある。4人のバンドとしての呼吸が冴えている、生身のせめぎ合いが詰まった作品だ。
-
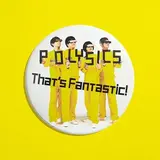
-
POLYSICS
That's Fantastic!
結成20周年にして、新メンバー ナカムラリョウ(Gt/Vo/Syn)加入! というウルトラCな展開を迎えたPOLYSICSの最新作。新たな血が入ったことは制作の刺激となったようで、1曲目のタイトル曲から、目をよく開け、耳をかっぽじってよく聴けと歌う攻めっぷり。挑戦的でありシニカルな歌をフルスロットルで飛ばし、ニュースクールなラップ風からファンク風のブラック・ミュージックに、トライバルなダンス・ビートに、オルタナ感溢れる奇想天外なEDM(?)に、ロックンロールに......と様々な音楽的な引き出しを躊躇なく開け放っている。何を調理しても、歪でファニー且つとびきりキャッチーでパンチ力のあるものになってしまうのだから、もう恐れることなくやってしまえという、オトナの余裕を感じる1枚。
-
-
POLYSICS
Replay!
今年、結成20周年を迎えるPOLYSICS。アニバーサリー・イヤーを飾る作品は、現メンバーで定番曲をリテイクしたトラックやライヴ音源、新曲を収録した、リアルタイムでオールタイムなベスト盤。2010年のカヨ(Syn/Vo)の脱退以降サウンドを再構築し、ライヴで洗練してきた曲だけに、爆発的なステージの熱をもパッケージした内容となっている。新曲「Tune Up!」は、縦ノリのソリッドなビートではなく、トライバルなアフリカン・ビートを採用。そのプリミティヴな胎動と、電子音楽、ポリならではの奇天烈なキャッチーさがぐるぐると大車輪で回る、ダイナミックな曲になっている。前のめりのビートでの爆発感やカオスともまた違ったグルーヴで、ライヴでのいいフックになりそうだ。20年、探求はまだまだ続く。
-

-
POLYSICS
What's This???
超高速のポップでデストロイなテクノ・サウンド「Introduction!」で幕を開け、怒涛の勢いでPOLYSICSの音の宇宙を旅させる全19曲。結成19周年だから、19曲という安易な、それでいて無謀なことをやってのけるのがこのバンドらしい。そしてタイトルの"What's This???=これはなんだ???"の通りに、リスナーは、次から次へと頭上のクエスチョンマークが消えぬうちに続く曲へとピンボールのように弾かれていく。このソリッドなスピード感と、瞬時に場面を切り替えていくようなダイナミックさがPOLYSICSだ。そんなすこぶるパワーのある最新鋭のエンジンを持ちながらも、実は人力で動かしているような、汗が迸っているのもまたこのバンド。人の手と感情と気まぐれと遊び心とのいびつさが生み出すポップネスが、聴き手を全方位から揺さぶってくる。
-

-
POLYSICS
HEN 愛 LET'S GO! 2 ~ウルトラ怪獣総進撃~
ハヤシの偏愛するものを曲にした『HEN 愛 LET'S GO!』第2弾は、円谷プロ全面協力によるウルトラ怪獣とのコラボ作。よく知られた怪獣ばかりでないチョイスは"らしい"ところだが、そのサウンドを聴いていると怪獣のフォルムやキャラも浮かび上がってくるのが面白い。好きゆえに暴走気味で、POLYSICSと言われて連想するエクストリームな音、凸凹の凸部分をこれでもかと詰めて構築したサウンドの振り切れぶりも最高だ。しかし、怪獣の偏愛でありつつ、サウンド的にもこのバンドの音楽の偏愛を改めて確認する内容でもある。食べ物や怪獣をテーマに作品を作るとなれば確実に三の線でネタっぽいものになりがちで、もちろんその笑いもありながらも、音楽的にはストイックに真正のパンク、ニュー・ウェイヴたる姿勢を見せる。それがPOLYSICSだ。
-

-
POLYSICS
HEN 愛 LET'S GO!
ハヤシが言った、"ドクターペッパー(炭酸飲料)の存在感がPOLYSICSに似てる"とはなるほどなと納得。毒やクセもたっぷりながら、その独特の味が秘薬のように身体をめぐって、いつしかロングセラーになっている。そんな特異性と中毒性というポリの魅力を、大音量で詰め込んだのがこのミニ・アルバム。テクノにストレンジなポップス、ハードロックからインダストリアル等々、好きな音をとことん詰め込んで、3人のアグレッシヴなアンサンブルで昇華していったサウンドは、破壊力満点だ。キャリアを重ねてきたアレンジやバランスの妙味はあるも、彼らが登場してきたときの"何じゃこれ?!"という衝撃が音の最前線にあるのが面白い。アートワークにも様々なオマージュがちりばめられているので、サウンドと共にその"偏愛"を楽しめる。
-
-
POLYSICS
ACTION!!!
10月にミニ・アルバム『MEGA OVER DRIVE』をリリースし、ツーマン・ツアーを大盛況で終わらせたばかりのPOLYSICSが『Weeeeeeeeee!!!』以来、約13ヶ月ぶりとなるフル・アルバムをリリース。ポップでシャープなシーケンス、ハードなバンド・サウンドで攻める『MEGA~』の勢いをスケール・アップさせ炸裂する楽曲群はとにかく痛快!テクノやニュー・ウェーブ・サウンドに絡むひりついたギターやハードコア的なアプローチのリズム隊は肉体的で、EDM要素もあれば80'sに特化したナンバーなど、止まない音楽的好奇心に翻弄される。収録曲は全て益子樹がエンジニアリングとマスタリングを手掛けているとのことで、よりクールで洗練されたサウンドに仕上がった。ぶれずに攻め続けるその姿勢に、毎度のこと感服である。
-

-
POLYSICS
MEGA OVER DRIVE
表題曲のTrack.1のイントロからヤラれました。さすがですPOLYSICS。シャープなシンセがポップに炸裂、ゴリゴリのベースとタイトなドラムが走り抜け、ハヤシの耳を突き刺す高音がスコーンと抜ける......ロックすぎるポップ・センス、切れ味鋭すぎです! ギターとベースがどちらも引かないTrack.2も肉感たっぷりで飛びかかり、Track.3はロックな展開とポップなアプローチが交錯するアイディア満載の楽曲。衝動的に攻めまくるその音像に、まだまだポリが落ち着くということはなさそうだなとニンマリしてしまう。2010年のカヨの卒業以来封印していた人気曲を3人体制で新録した「I My Me Mine 2013」と「Baby BIAS 2013」も収録。まさしく大爆発の全5曲。
-

-
POLYSICS
Weeeeeeeeee!!!
活動15周年を迎えたPOLYSICSの今年2枚目のフル・アルバム。「Sparkling Water」で一気に弾け、8月にリリースされた「Lucky Star」、「Distortion」という爽快なポップ・チューンで軽快に始まるが、あっという間に「Steam Pack」、「Ice, Tights, Mike」とロック・チューンに突入していく。そして、テクノ色の強い「Why」へと続き、アルバム後半は「Kitchen Ban Ban」、「Lightning Express」とコミカルな楽曲へ。そのサウンドは変幻自在。相変わらず1曲1曲はコンパクト。ぎゅっと濃縮された音の塊が次々と襲来する。息をつく間もないその展開は、まさにPOLYSICSの真骨頂と言えるだろう。
-
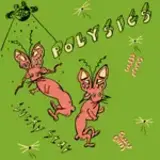
-
POLYSICS
Lucky Star
約3年ぶりとなるPOLYSICSのシングル。表題曲「Lucky Star」はフミがヴォーカルをとる瑞々しさと爽快感に溢れたポップ・チューン。今年3月には結成15周年を記念して、様々なゲストを招いた記念アルバム『15th P』をリリースし、さらにSHIBUYA-AXで通算1000本記念ワンマンを行うなど(この日のライヴ映像のダイジェストが、本作の初回限定盤特典DVDに収録)、メモリアルな活動が目立っていたPOLYSICSだが、この「Lucky Star」から感じられるのは、築き上げてきたキャリアに甘んじることなく最前線を突き進まんとする今のバンドの充実ぶりだ。"止まらない 遊んでる/不器用に 詰め込んで/忘れてる 忘れてる"――遊び続けることの重みと強みをこれでもかと感じさせる1曲である。
-

-
POLYSICS
Oh! No! It's Heavy Polysick!!!
POLYSICS、3人編成となってから初のフル・アルバムはその名もHeavy Polysick=重度のポリ病。今年1月に行われた彼らの新年一発目のライヴで初めてスリーピース版POLYSICSを観たのだが、兎に角"Heavy"だったのを覚えている。そう、タイトルにも使っている"Heavy"という言葉は、今の彼らを形容するにぴったりなのだ。ハヤシ、フミ、ヤノが不動の三点とでもいうように存在感を放っている。これが、本作がドPOPでありながら妙に骨太である由縁、全方位からけたたましい音が一気に溢れ返ってくるような賑やかさの中にも、一点突破してくるような猪突猛進感へと繋がっているのだろう。シンプルな編成となったからこそ、よりシンプルに、より力強く、より痛快に。全ての要素がより明快になったようだ。
-
-
POLYSICS
eee-P!!!
メンバーの卒業を経て3人編成となった新生・POLYSICSの待ちに待った新譜が到着。これがもう、テンションMAXで振り切っている。中でも、すでにフェス等でも披露されているファミコン・ピコピコ・サウンド炸裂の「Mach肝心」はスピード感ある展開に引っ張られていくように音の乱反射が止まらない、POLYSICSらしくもありながら今までになかった新たな一面を覗かせている。POLYSICS経由でニュー・ウェイヴというジャンルに触れたキッズも多いことだろう。こんなにもとっつきやすくコミカルに最上級のパフォーマンスをやってのけるバンドは他にはいないと再確認させられた。歌詞にも表れているが"じっとしていられない!"というウズウズ感が伝わって早くライヴでToisu!と叫びたくなるはず。
-

-
POLYSICS
BESTOISU!!!!
メジャー・デビュー10周年という節目を迎えたPOLYSICSにとって、2枚目となるベスト・アルバム。2004年、Drのヤノ加入以後の作品から選曲されているこの作品。シングル曲やライヴでの定番曲などを中心にまとめられたDisc-1と、未発表曲や海外でのリリースのみだった楽曲からライヴ・テイクまで、充実のレア・トラックをまとめたDisc-2(初回生産限定盤のみ)というPOLYSICSらしいヴォリューム感。POLYSICSのライヴを意識したというだけに、通して聴くとPOLYSICSが持つポップさを改めて感じることができる。POLYSICSの音楽にまだ触れたことがないという人にも、POLYSICSという唯一無二のニューウェーヴ・バンドの音楽性を楽しむきっかけになるはずだ。
-

-
POLYSICS
Young Oh! Oh!
POLYSICS通算13枚目のシングル。POLYSICS節全開のハイテンションで奇天烈なエレクトリック・ロックンロール。この人達のテンションは一体どこからくるんだろう?初めてPOLYSICSを耳にした時から、変わらぬこのテンション。音楽への偏愛と笑っちゃうくらいのハイテンションがかけ合わさって生み出される、POLYSICSというエネルギッシュなエンターテイメント。腹を抱えて爆笑するか、汗だくになりながら踊り狂うか。いや、爆笑しながら踊り狂うしかない。下世話に陥りかねないギリギリの一線。そこは、最高のエンターテイメントの居場所だ。そして、POLYSICSは今日もそこで汗だくになって暴れ回っている。
-
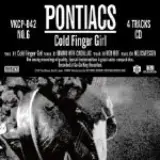
-
PONTIACS
Cold Finger Girl
元BLANKEY JET CITYの浅井健一と照井利幸を中心に、昨年結成されたPONTIACS。1stアルバム『GALAXY HEAD MEETING』以来約半年振りのリリースとなる今作のタイトル曲は、滲むように響くミステリアスなギターと、鋭く打ち付ける低音が轟くロックンロール・ナンバー。夜の都会を颯爽と走り抜けるようなスマートな空気感は、背筋をひたすらぞくぞくさせる。「RED BEE」のスリリングなリズムと不安定なマイナー・コードが織り成す緊張感も、百戦錬磨と言うべきスキルを誇る3人だからこそ作り上げられるものだろう。疾走感のあるインスト・ナンバー「DELICATESSEN」など、バラエティに飛んだ4曲入りシングル。同日発売のライヴDVDも併せてチェックだ。
-
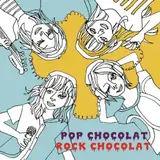
-
POP CHOCOLAT
ROCK CHOCOLAT
2000年に京都で結成され、現在では東京で活動を続ける4人組女性ロック・バンド、POP CHOCOLATのミニ・アルバム。豪快にドライヴするギターに乗っていながら、ふわふわしたコーラス・ワークが曲の中で虚無感を演出する「passing」をはじめ、4人のメンバー全員がヴォーカルを取るスタイルを活かしたコーラス・ワークが際立っている。所属のDELICIOUS LABEL代表を務める山中さわおのバンドthe pillowsがツアーで今作をSEとして使用したりと、インディ・ロック・ファンへも浸透してきており、会場限定リリースだった作品が、全国流通となり、さらにiTunesとレコチョクでの配信も開始することとなった。初期RADIOHEADの影響を仄かに感じさせる冒頭の「夕暮れ」からラストの「HAPPY END」まで、ディストーションの利いたギター・サウンドと強烈なスネアの音の上で歌われる世界はあくまでも"君と僕"の身の回りの日常。オルタナ・サウンドにキュートな声がイイ。
-

-
POP ETC
ハーフ
Bird Bear Hare and Fishの1stアルバムを共同プロデュース、尾崎雄貴(Vo/Gt)らとの親交も深いものになってきた、Christopher Chu(Vo)率いるPOP ETC。今回は日本のみ(というか日本のファンへのギフトという印象)のリリースだ。前半はまるで目の前の人に向けて歌うような、繊細で機微のあるChrisの歌とアコースティック主体のアンサンブルの曲、後半をニュー・ウェーヴ~ポスト・パンクや煌めくエレクトロニックな要素も光るバンド・サウンドの楽曲で構成。ラストは尾崎雄貴との共作で、アルバム中、最も高揚感とドラマチックな展開を見せる「We'll Be OK」。ボーナス・トラックには同曲の尾崎ヴォーカルVer.や、くるりの「ばらの花」などの英語詞カバーも。Chrisたちの音楽愛と温かな人間性が随所に溢れる。(石角 友香)
前作以降に配信リリースしてきた新曲の数々を、前半は弾き語りに必要最小限の音を加えたアコースティック・サウンド、後半には80sのダンサブルなエレポップ・サウンドとカラーを分けて並べることで、それぞれの魅力を際立たせたPOP ETC名義の3作目のアルバム。そこに日本のみのリリースということで、YEN TOWN BANDの「Swallowtail Butterfly~あいのうた~」、くるりの「ばらの花」の英語カバー、日本語で歌詞を書いたオリジナル曲「思い出していた (First Try)」、盟友である尾崎雄貴(Bird Bear Hare and Fish/Vo/Gt)と共作した「We'll Be OK」を加えながら、作品全体に不思議と統一感があるのは、作り手の人間性が滲み出ているからだ。絶妙に入り混じる温もり、切なさ、そして儚さは、POP ETCの真骨頂。
-

-
POP ETC
Souvenir
セルフ・タイトル作以来、約4年ぶりの新作。もともとUSインディーのスノビッシュな側面は薄い彼らだが、特にTrack.1「Please, Don't Forget Me」はバンド感溢れる広大なナンバーで、THE MORNING BENDERS名義時代の匂いも。その他の楽曲は80年代のUKニュー・ウェイヴのニュアンスが色濃く、シンセ・ドラムやシンセ・ベースの懐かしめなサウンド・プロダクションと、Christopher Chu(Vo)が書く哀愁味のあるメロディ・ラインが中毒性高め。しかし、アレンジがどうあれ、来日時にマイクすらないアコースティック・セットで堪能させてくれたChristopherの歌の力や表現力、美しいものやユーモアをこの3人ならではのセンスで着地させるバンドマジックこそが最大の魅力だ。日本盤にはTrack.1の尾崎雄貴(Galileo Galilei)版などを収録。
-

-
POP LEVI
Medicine
Jonathan James Mark LeviのプロジェクトPOP LEVI。Noel Gallagher、Jarvis Cocker、KASABIANらの錚々たる面子が彼の才能に賛辞を贈っているが、音を聴くとそれがなるほどと納得できる面白さが詰まっている。ロック、ブルース、サイケ、ファンク、ポップ等の全ての要素を飲み込み、彼流に吐き出したとでも言えるようなカラフルで魅力的な楽曲が満載。全曲シングル・カットできるクオリティで、キラー・リフが炸裂するロック・ナンバーから美しいバラードまで幅が広く、あっという間に1枚を聴き終えてしまうほどの取っ付き易さも素晴らしい。タイトな8ビートに畳み掛けるシャウトがかなりカッコいい先行シングル「Strawberry Shake」をまずは聴いてみて欲しい。
-

-
POP MARSHAL
Rejoice!
2022年、その活動にひと区切りをつけたHEADSPARKS。来日ツアーを行うなど、ここ日本でもUKメロディック・ファンの間で愛されていたそのバンドのメンバーが、POP MARSHALとして再始動。メンバーを変えると、長年愛されたバンドから印象を変えることを目指すバンドも多いが、彼らはあくまで自分たちが積み上げてきたものを上手く生かし、ファンの期待に応えるものを作り上げた。特に、中心メンバーのAndy Barnardは、90年代から様々なバンドでシーンを支えてきた実力派だけあって、安定したメロディメーカーとしての才能を存分に発揮している。耳に残るギター・フレーズ、口ずさみやすいメロディ、ワクワクするようなテンションのリズム、これぞ愛すべきメロディック・パンクだ。
-

-
popoq
00
popoq初のフル・アルバムは"00"(読み:リンリン)と名付けられた。コロナ禍によって気持ちや活動の面でもゼロになる、リセットさせることが繰り返されたこと、また強制的に止められた時間の中で、彼らが10代の多感な時期を過ごした00年代へのノスタルジーが湧き上がったこと。制作期間での体験や目まぐるしい情報の変化とディレイ状態の日常とが生む混沌のエネルギーが、曲作りや新たなアイディア、歌を研ぎ澄ませていくことに向けられた。シューゲイザーやポスト・パンク、エレクトロなどに根ざしたpopoqサウンド、そして上條 渉(Vo/Gt)のエアリーなハイトーンで描かれる繊細でドリーミーなメロディは、輝きを増して、心を研ぎほぐすような温もりと美しさを放つ。シビアな現実を、ファンタジックに灯すようなアルバムだ。
-

-
popoq
Crystallize
疾走感のある硬質のギター・サウンドと、プリズムが柔らかに跳ねるような上條 渉のヴォーカルとのコントラストが、清らかで美しい「holy」で始まる2ndミニ・アルバム。結晶化させる、具体化するというタイトルが示すように、今作は頭の中や心の内でおぼろげながらも確かに存在する音のきらめき、プリミティヴな叫びなど、形なきものたちを丁寧に拾い上げてコードやリズム、旋律に映した作品だ。前ミニ・アルバム『Essence』からさらに踏み込んで曲のあるべき形が追求されている。バンド・サウンドとのバランスを計ることなく、必要ならばエレクトロ要素も強めながら曲の持つ情景や温度が描かれたゆえ、リスナーは素直にこの音楽に飛び込んで五感を開放すればいい。甘美な時間をくれる作品だ。
-

-
popoq
Essence
フロントマン 上條 渉(Vo/Gt)の、憂いの陰影を持ったハイトーンで歌う浮遊感のあるメロディと、シューゲイザーやポスト・ロック、ポスト・パンクや、インダストリアル的な匂いまで、様々な音楽の片鱗を感じるサウンドが描くのは、夢うつつで、感情の波に揺られ、リアルさとシュールさが溶け合う世界に漂流してしまったような感覚だ。轟音が鳴っている間、メロディに包まれている間は、その不可思議な幻影に浸り、時間を奪われてしまう音楽となった。初の全国流通盤となる今作は、結成初期から大事にその世界観を育て色づけてきた「flower」のほか、これからの代表曲となっていきそうな最新曲「solaris」や「essence」など全6曲を収録している。これまでとこれからを繋ぐ1枚。
-

-
Pororoca
I Love You -EP-
今年7月にベーシストが脱退&加入したPororocaが、現体制初音源をリリース。新しく入った小熊雄大(Ba)がもともと親交のある人物だったこともあってか、本作ではロック・バンドとしての塊感、初期衝動を剥き出しにしたサウンドが鳴っている。歌詞もかなり赤裸々だ。そんななか、食ったリズムとアクセントで勢いをつける「S.B.C」、浮遊感のあるサウンドが新鮮な「彼女は言った」、明るくもどこか哀愁漂う「そのレコードは止まらずに」と1曲たりとも似た曲調のものが存在していないこと――言い換えると、これまでの5年間を背負ったうえでの原点回帰がなされていることも特筆しておきたい。全5曲は彼らがバンドに、そして音楽に向かい続ける理由を何よりも明確に語っている。
-
-
THE POSIES
Blood / Candy
90年代のUSギター・ポップ/パワー・ポップを牽引してきたTHE POSIESの5年振りのニュー・アルバム。88年にデビュー、しかし98年に活動休止、そして05年に再結成と長いキャリアを持つ彼らは、他アーティストの支持率も絶大であるとともに日本のファンからも人気が高い。それは、彼らが涙腺に訴えてくるような素晴らしいメロディ・センスを持っているからだろう。新作では、そのキャリアの初期のような瑞々しいサウンドが全開。TEENAGE FANCLUBを彷彿とさせるような暖かいメロディも魅力的なのだが、あのTHE BEATLESをも引き合いに出される曲の展開や引き出しの多さが彼らの真骨頂だろう。BROKEN SOCIAL SCENEのLisa Lobsingerなどゲスト陣も豪華。
-

-
Post Malone
Austin
ラッパーにしてシンガー・ソングライター、ジャンルにとらわれないコラボレーションで世界を席巻する、Post Malone。そんな彼の5作目となるアルバムは、彼の本名を冠したタイトル"Austin"が表す通り、彼自身の内面にフォーカスした作品となっている。破天荒なラッパーでありながら、耳に残りやすいメロディ性、ポップでスタイリッシュなアレンジなど、親しみやすさが人気のPost Maloneらしさはそのままに、新曲はさらにエモーショナルな方向に一歩踏み込んだ印象。アルバム全編にわたって自らギターを弾くというチャレンジもあり、ただただシンプルに演奏を楽しんでいる様子が伝わってくるようなワクワク感もある。規模の大きな野外会場で聴いたら、本当に最高な時間になるだろうな、という想像も含めて楽しめる作品。
-

-
Post Malone
Twelve Carat Toothache
"SUMMER SONIC 2022"でヘッドライナーを務めるPost Maloneの、3年ぶりとなる最新作。過去作よりもさらに彼の歌メロを引き立たせた作風に仕上がっていて、ピアノの伴奏とともに名声の代償を歌うTrack.1、アコギにスモーキーな歌声が合ったTrack.3などエモーショナルな楽曲に、DOJA CATを迎えたTrack.5のようなポップ・サウンドが交ざり合い、揺れ動く感情のように悲喜のグラデーションが生まれている。酒での失敗談をドラマチックに仕立てたTrack.8はFLEET FOXESがコーラスを奏で、クライマックスに配されたTrack.13はTHE WEEKNDとのデュエットと、ゲストも豪華。スーパー・スターでありながらどこか親しみの持てる、パーソナルな部分が発揮されたアルバムだ。
-

-
postman
Night bloomer
2018年春に全国デビューを果たした平均年齢20歳の名古屋発4ピース・バンドによる1年ぶりの新作。タイトルのとおり"夜"と概念を基盤に、ソングライター 寺本颯輝(Vo/Gt)が自らの経験から導き出した思想や哲学が色濃く反映された楽曲が揃った。スケール感のあるミドル・ナンバー、ダンサブルな楽曲、シューゲイザー的なギターの音色も効果的なポップ・ソングなど、アコースティックからハード・ロック、テクニカルなアプローチまでバンドのポテンシャルの高さが際立つ。歌詞の言葉数の多さはまさに想いが溢れて止まらないといった様子で、それを歌い上げるヴォーカルも切実で生々しい。デビューしてからの1年の充実性がダイレクトにソングライティングとサウンドスケープに反映された成長の1作。


























