DISC REVIEW
P
-

-
postman
干天の慈雨
名古屋発、平均年齢19歳の4ピース・バンドpostmanが、RX-RECORDS/UK.PROJECTより初の全国流通盤をリリース。寺本颯輝(Vo/Gt)の伸びやかで透明感のあるハイトーン・ヴォイス、情景を鮮やかに描き出すドラマチックな歌詞、そして、どこか切なさも感じるような洗練されたアンサンブル。これらが組み合わさることで、音の粒が煌めいているような美しく瑞々しい音世界を作り上げている。リフレインするフレーズが耳に残る「光を探している」、サビに向けて体温が高まっていくような疾走感に包まれるライヴでの定番曲「Moongaze」、いまの自分を優しく肯定してくれる「漂落」など、7曲すべてがリード・トラックばりの存在感と強度を誇り、これから長く聴き続けられていくであろう1枚に仕上がった。
-

-
POT
MISH MASH
関西ネクスト・ブレイクの呼び声も高い4人組、POTがメンバーの病気療養を経て、1stミニ・アルバムをリリース。療養中もサポート・メンバーを迎え、活動を休止したわけではないが、本来のメンバーが再び揃い完成させたこの作品で改めて完全復活をアピール。3人の掛け合いヴォーカルを軸にメロコア、レゲエ、スカの影響を巧みにブレンドしたライヴで盛り上がること必至の全8曲を収録。「COUNTDOWN」の四つ打ち、「Jolly summer」のサンバっぽいリズムを始め、はねるリズムを多用していることからもこの作品をどう楽しんで欲しいかメンバーたちの想いが窺える。ドラマチックなフレーズを奏でるギター、随所で歌うベース・ラインも聴きどころ。そんなところにもじっくり耳を傾けたい。
-

-
potekomuzin
check e.p.
ズキスズキ(Vo/Gt)の生み出すユーモアな歌詞世界と、圧倒的にシャープでグルーヴィな演奏で、急速にファンを増やしている日本語ロックの新星、potekomuzin。彼らが前作『問題児はつらいよ』からおよそ半年ぶりという短いスパンで1st EPをリリースする。今作もレコーディング・エンジニアに石川泰隆、マスタリングに中村宗一郎、アートワークにど藤田という、お馴染みの布陣で制作。中毒性抜群の楽曲が並ぶ今作は、聴けば聴くほどに、難しいとか簡単だとか、そういう次元を飛び越えた独特の世界観に引きずり込まれていく。五十嵐俊樹(ベルリンペンギンレコード)の手により、ゲーム・ミュージック風に仕上げられた「まてんろう」など、リミックス2曲をオリジナルと聴き比べてみるのも面白い。
-

-
Prague
明け方のメタファー
5月にミニ・アルバム『花束』をリリースし、7月には二度目となる人気アニメ「銀魂」のエンディング・テーマも務めたPragueの2ndアルバムが早くも完成。デビュー当初から高い演奏力と幅広い音楽性で評価を受けて来た彼らだが、今作ではさらにキーボードやパーカッションのゲストを迎え、サウンドはより奥行きが広がった印象だ。勢いだけではないタメを効かせたファンキーでグルーヴィーな楽曲や、彼らの持ち味でもある疾走感たっぷりなナンバーもあり聴き応え十分で、アルバム全体の完成度も高い。そしてヴォーカルの鈴木雄太の描く世界感はよりストレートに聴く者に訴えてくる生々しさを持っている。彼らの美学や進化が刻まれた充実作。
-

-
Prague
バランスドール
関東発のスリーピース・バンドのニュー・シングル。表題曲はアニメのエンディング・テーマ曲になっていることからも分かるように、大衆受けも狙えそうなキャッチーな楽曲。しかし決して安っぽくなっていないのは、彼らがもつ独特のグルーヴがあるからだろう。ベースとドラムの音が際立っていて、それだけでもずっと聴いていられるぐらい心地良い。音の印象よりも前向きに感じる歌詞も魅力的だ。そして、オルタナティヴ・ロックの要素がより強い楽曲「サイ」ではVo鈴木の存在感が増し、リズム隊との絶妙な化学反応を生み出すことに成功している。このバンドのグルーヴ感を直に体現できる表題曲のインストゥルメンタルも収録されているので、こちらもぜひ聴いてもらいたい。
-

-
Prague
花束
1stアルバム『Perspective』以来10ヶ月振りのリリースとなる、09年にメジャー・デビューした3ピース・バンドPrague(プラハ)の5曲入りミニ・アルバム。タイトルにもなっている“花束”の持つ魅力を5つの角度から切り出してゆく、美しく儚くもありながら非常にスタイリッシュでエネルギッシュな作品だ。 耳を劈くパワフルなサウンドと、包容感と切迫感を兼ね揃える鈴木雄太のヴォーカルが心臓を抉るように入り込んでくる。羽ばたく蝶のように悩ましげなメロディが頭の中をかき回し離れない。どの曲も3人が自らが奏でる音の可能性を強く信じ、それに向かって突き進んでゆくような勇敢な心意気に満ち溢れている。油断していると置いていかれそうなほどの疾走感。クールな情熱に焦がれる。
-

-
Prague
Distort
2009年9月9日にシングル『Slow Down』でデビューした関東出身スリーピースバンドPRAGUE。セカンドシングル『Light Infection』が大人気アニメのオープニングに起用され既にご存じの人もいると思うが、前作を初めて聴いたとき複雑に絡み合うメロディーとリズムに目新しいと感じたのを覚えている。今回のシングル曲「Distort」は切なさと爽快さが入混じったギターのディストーションに注目してほしい。そして2曲目の「願いfeat. Mummy-D」は彼らが雑食性に長けているバンドであることを証明している気がした。現在ファースト・アルバムを制作中の彼らだが、簡単に彼らをロックバンドというジャンルでは分類できない可能性を感じた。
-

-
Predawn
Calyx
昨夏は活動10周年ライヴに小山田壮平(AL/Vo/Gt)、ホリエアツシ(ストレイテナー/Vo/Gt/Pf)らをゲストに招くなど、Predawnの愛されぶりの一端を知れたが、今回は初の日本語詞のみからなるEPをリリース。お馴染みの神谷洵平(Dr)、ガリバー鈴木(Ba)に加え、コーラスで小山田壮平も参加。儚く脆そうでいて意志の強さを感じる声が、情景と心象がないまぜになった言葉に乗り、放たれる瞬間は、どの楽曲も奇跡を見るような美しさだ。オーセンティックで音数の少ないフォーク・ロック調のアンサンブルは、肩の力を入れずに楽しめる音像。生きていくなかで自然と堆積した思いにいいも悪いもない。ほんの少しのブルーを抱えながら人生という旅に出る――彼女らしい心強さがある1枚。
-

-
Predawn
Absence
ライヴではギターの弾き語りだから潔いまでの尺の短さなのだと思っていたら、バンド・アレンジを加えた音源でもその潔さに変わりはなかった。自分のイメージをどう着地させるかというシビアさと、曲が求める歌唱の必然と、音楽を作る自身への誠実さという意味で彼女はThom YorkeやJoni Mitchellに似ている。儚げでかわいい声で描かれる大人の女性の孤独というギャップには少々震えるものがあるし、虚無的になるギリギリ手前の感覚を切り取った歌声が聴ける楽曲があったりして、パッと聴くと穏やかな彼女の作風が、実は自身を削り出して立体化していることを知ったとき、深い感銘を受ける。聴き流すことも深くコミットすることもできる、聴き手にとっての多様性を残してあることもPredawnの懐の深さだ。
-

-
Predawn
手のなかの鳥
清水美和子のソロ・ユニットPredawn 初の全国流通音源。一見すると少女が花を摘むように可憐で無邪気に音楽と戯れているような作品。赤、青、黄...色鮮やかな沢山の糸を、思うまま紡いでいく。そんな風に言葉を紡ぎ、それを歌に乗せ飛ばしていく。手のひらに花びらを乗せてふっと息を吹きかければ、言葉は宙を舞いゆらゆらとたゆたう。どこまでも自由な彼女の歌はそこに留まってはくれないのだ。リード曲「Suddenly」では、まどろみの中で恋人を想い、相手への深い愛情を、寝ぼけ眼で囁くように歌っている。恋人が自分にもたらしてくれる幸福は"突然"やってくる、つまり貴方は私の世界を一瞬で塗り替えてしまうのだと言っている。そんな強い言葉すらも淡く瑞々しいものにしてしまう、彼女の言葉で想いを彩るセンスは素晴らしい。
-

-
PREFAB SPROUT
Let's Change the World with Music
PREFAB SPROUTほど、青春という言葉が似合う音楽を生み出したバンドがいるだろうか。甘酸っぱい想いにかられる青春映画のようなポップ・ミュージックを育み続けてきたPREFAB SPROUT。2001年以来(!)となる今作は、実際は名作「Jordan: The Comeback」の次の作品として準備されていたが、ずっとお蔵入りしていたものだという。打ち込みを主体としているが、Paddy McAloonの叙情性に溢れたメロディの魅力は相変わらず素晴らしい。Brian Wilsonの『Smile』に触発されて制作したというこのアルバム。PREFAB SPROUTのポップ・センスを堪能できる、青春時代から抜け出すことのできない大人のポップ・アルバム。
-

-
PRIMAL CURVE
OALL
圧倒的なライヴ・パフォーマンスで関西を中心に人気を誇る"理系ロック・バンド"、PRIMAL CURVEの3rdミニ・アルバム。ブルースの香り漂うリフからのダンス・ビート、そしてサビではKasai hiroyuki(Vo/Gt)の声が爽やかに響き渡るTrack.1や、激しいブギーを鳴らしたかと思うと爽快な疾走感で駆け抜けるTrack.4など、どの曲も一筋縄では終わらない。多様なジャンルの音楽とリズムを積極的に取り入れた挑戦的な1枚となっているが、ごちゃ混ぜ感がないのはそれぞれの音にそこで鳴ることが必然のように思わせる説得力があるからだろう。ピースをあるべき場所へ当てはめた計算され尽くされた今回のアルバムは、"理系ロック・バンド"を名乗るに相応しい作品となっている。
-

-
PRIMAL SCREAM
Come Ahead
2016年リリースの『Chaosmosis』以来8年ぶり、12枚目となるPRIMAL SCREAMのアルバム『Come Ahead』。今作も、ファンキーでサイケデリック、それでいて伝統的な様式美を感じるロックンロールと、フロントマン Bobby Gillespieのこだわりがふんだんに盛り込まれた作品となっている。ライヴにも帯同するHOUSE GOSPEL CHOIRのコーラス、ストリングスをはじめとした様々な楽器のプロフェッショナルを迎えたサウンドは、聴き応えがある。いくらでも合成音声やシンセ、打ち込み等を用いて少人数で重厚感のある音楽が作れてしまうこの現代において、ここまで大所帯で作り上げるリッチなサウンドはまさに贅沢の極み。
-

-
PRIMAL SCREAM
Give Out But Don't Give Up - The Original Memphis Recordings
1993年当時、自分がAlan McGee(バンドの所属レーベル"Creation Records"のボス)じゃなくても、この失われたメンフィスの名門スタジオ録音の音源にGOは出さなかっただろう。なんというか、手練れのアメリカン・ルーツ・ミュージシャンの演奏と、妙にお金がかかった印象のクリアな仕上がりは、アメリカ南部サウンドをテーマに据えた面白さや試行錯誤は垣間見えるが、音像に彼ららしさが窺えない。そこから四半世紀。オリジナルが存在し、歳月が過ぎたからこそ「Rocks」や「Jailbird」のアレンジやミックスを聴き比べる面白さがある。ただ、当時Bobby Gillespie(Vo)が心酔していたマッスル・ショールズのサウンドやゴスペルを、今聴くことは無意味じゃない。もちろん、アーカイヴとして貴重な2枚組だ。
-

-
PRIMAL SCREAM
Chaosmosis
ロックンロールは好きだが、ストーンズ命みたいなオヤジにはならねえぞと思っている人がいたら聴いた方がいい。もっとも、そう言ってしまった時点で、新しい刺激を求める人にはちょっと物足りないということが明らかになってしまうわけだが、ブルースの本質をモダンなサウンドで表現した美しいポップ・アルバムと本人が言っているんだから、3年ぶりとなる11作目のアルバムは、時代を先取りすることがテーマではなかったということだろう。だからって、「Where The Light Gets In」でSky Ferreiraとデュエットだなんてちょっと甘っちょろいんじゃない? いや、それを楽しむ余裕があるということだ。前々作、前作同様、集大成と言える多彩な曲とともに持ち前の歌心はさらに味わい深いものになってきた。
-

-
THE PRIVATES
Les beat
モノラル録音と言えば、60年代のブリティッシュ・ビートやガレージ、50年代のデルタ・ブルースなどが想起されるが、そうした音楽が持っていたパワーに匹敵する曲の良さ、サウンドとしてのかっこよさをTHE PRIVATES自身が持っているからこそのこの手法。ロックンロールにしか慣らせないロマンを存分に感じられる30年を経た現在地と呼べるアルバムだ。DISC 2には色褪せないとびきりのリズム・アンド・ブルースのカバーを全10曲収録。ゲストに花田裕之、甲本ヒロト、真島昌利、チバユウスケ、THE NEATBEATSのMr.PAN、オカモトショウ、オカモトレイジら、世代を越えたミュージシャンが参加しているが、どんな曲にどんな組み合わせで参加しているのか?その垣根のなさもぜひ堪能してほしい。
-

-
Maxim
Love More
THE PRODIGYのフロントマン、Maximが約14年半ぶり3作目となるソロ・アルバムを日本先行でリリースする。共にフロントマンとして活躍した盟友で、2019年3月に亡くなった"Keef"ことKeith Flintへと捧げられた今作は、反骨精神だけでなく、"今を懸命にハッピーに生きる"というポジティヴなメッセージも込められている。トラックはレゲエのヴァイブスが色濃く反映されており、女性VoをフィーチャーしたTrack.3、4や、過去作に通じる攻撃的ヒップホップのTrack.2、モダンなトラップ・チューンのTrack.8など、様々なジャンルのエッセンスを凝縮。THE PRODIGYのような派手さはないものの、Maximのパーソナリティが伝わってくるような作品だ。
-

-
THE PRODIGY
No Tourists
90年代初頭からビッグ・ビートのパイオニアとして後発バンドに多大な影響を与え続けるTHE PRODIGYが、約3年ぶり7枚目のアルバムをリリースする。一聴してそれとわかる"THE PRODIGY節"とでも言うべきサウンドは健在で、先行シングル「Light Up The Sky」や「We Live Forever」などミドル・テンポの"らしい"曲はもちろん、"Fuck You"のヴォイス・サンプルとともにマッシヴなシンセが殴り掛かる「Boom Boom Tap」のようなアッパーで攻撃的な曲も。トラックメーカーのLiam Howlett(Prog/Key/Syn)が"バンド・アルバム"と語るように、ライヴでの光景が目に浮かぶような、フロア対応型の力強いグルーヴに満ちた作品だ。
-

-
THE PRODIGY
The Day Is My Enemy
6年ぶりの来日を果たすTHE PRODIGYのニュー・アルバムが完成した。90年代からエレクトロ/ロック・シーンをボーダーレスに行き来してきた超硬質のデジタル・ハードコアはここでも健在。ビートとヴォーカルをメインに押し出したソリッドなサウンドで、ループによる覚醒感とブレイクダウンからの爆発感、ジェットコースターのように上り詰め急降下していく興奮ありという、極限のPRODIGY節たるスタイルを突き詰めた内容だ。一発でそれとわかる音のアイデンティティを提示しつつ、昨今のEDMをどやしつけんばかりの勢いとパワーをぶっ放しているのがいい。ダブステップの旗手Flux Pavilionやヒップホップ・パンクSleaford Modsといったひと癖あるUKアーティストをゲストで起用しているのも一興。
-
-
THE PRODIGY
Invaders Must Die
我らがPRODIGYが堂々帰還!しかも、前作「Always Outnumberd,NeverOutgunned」はLiamの一人舞台であったが、今作ではKeithとMaximがプロダクションに復帰を果たしている。肝心のサウンドはというと、はっきり言って大傑作!!!彼らのデビュー当時を思わせるレイヴサウンドへの回帰作とも言えなくはないが、NEW RAVE以降の若者に聴かれることを明らかに意識したモダンな音作りとなっている。FOO FIGHTERSのDave Grohlが2曲ドラムで参加しているのも大きな特徴。冒頭からフロア仕様のハイテンションな曲ばかりだが、PRODIGY版『Loaded』とも言える『Stand Up』で締めくくられているところに、彼らの懐の深さと年季の入りようが伺えて頼もしい。
-
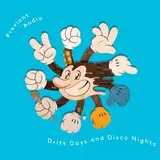
-
PROVIANT AUDIO
Drift Days & Disco Nights
LINDSTROMやPrins Thomasなどの天才を数多く排出してきたノルウェーのダンス・ミュージック・シーンに現れたニュー・スターPROVIANT AUDIO。プロデューサー/DJである21歳の天才マルチ・インストゥルメンタリストMathias Stubeを中心とした9人組ユニットがついに日本デビュー。煌びやかな80年代的ディスコ・ファンクのスタイルに、北欧ディスコ・エッセンスとフレッシュな次世代センス、さらにはジャズやヒップホップをもミックスした極上の最新型ディスコ・サウンドは目を見張るものがある。ファットでグルーヴィなビートとキャッチーでソウルフルなメロディのミックスが何ともクール。これまでディスコをあまり聴いてこなかった人も一聴の価値ありの傑作だ。
-

-
THE PSYCHIC PARAMOUNT
II
ライヴでのジャムやインプロヴィゼーションの熱量そのままブッ込んだ様なノイズの洪水。聴く前にまず音量に注意しないと、再生ボタンを押した瞬間から一気に呑み込まれてしまうことだろう。本作はカルト的な人気を誇るニューヨークのスリー・ピース・インスト・ロック・バンド、THE PSYCHIC PARAMOUNTの2作目。前作以上にエッジ―で音の粒が際立ち、実験的なノイズ垂れ流しでサイケ効果抜群、ともすれば聴く人を選ぶかもしれない程に混沌に満ちた作品だ。MOGWAIやLIGHTNING BOLT、GODSPEED YOU! BLACK EMPERORと共に挙げられることもあるが、より荒涼/殺伐としており、聴き通した後にはライヴ帰りの様な錯覚に陥ってしまう。もはや聴くアトラクション。
-

-
PTTRNS
Science Pinata
ドイツのアヴァンギャルドな実験性を受け継ぐパンキッシュなディスコ・パンク・バンド。時には3人同時にパーカッションを務めるなど、変則的なスタイルながら高い演奏力とグルーヴで多くの音楽ファンの心を掴む事必死のニューカマーの登場だ。このデビュー・アルバムは全体で約40分とコンパクトな作りで、勢いをそのまま詰め込んだようなとても熱量のある作品。パンキッシュでありながらとてもダンサブルで踊れる所も今作の魅力。3人それぞれのヴォーカルも聴き所で、またその3人が歌い上げるコーラス・ワークも美しい。ポスト・パンクやディスコの要素を吸収し、それを生演奏というスタイルにこだわりそのケミストリーを今作では爆発させている。
-

-
PULLED APART BY HORSES
Tough Love
のっけから勢いよく耳に飛び込んでくるのはギターと大音量の重低音ベースのユニゾン。ポイント・ポイントではバスドラまで重なってくる。しかも今時のお洒落なフレーズなんかではなく、ロック・リスナーであれば誰もが聴き馴染んできたベタベタのフレーズをガツガツ弾いてくれちゃうのだ。笑ってしまうくらいシンプルで馬鹿馬鹿しさすら覚えるのだけれど、それが清々しくて心地良い。「馬裂きの刑」なんていうおどろおどろしいバンド名だが、サウンドに感じるのは馬が駆け出す勢いだろう。ライヴでは間違いなくファンがピョンピョン跳びはねたくなるようなエネルギッシュなパフォーマンスを魅せてくれるにちがいない。パンクなのだろうかとかメタルなのだろうかとかいろいろ小難しく考える必要はない。頭をからっぽにして楽しんでみてほしい。
-

-
PULPS(ex-南蛮キャメロ)
the the the
大阪は八尾市発の幼馴染4人組バンドの初全国流通盤。古き良きUKロックや、フォーク・ソング、歌謡曲などを、2020年代を生きる彼らの感覚で採り入れた全5曲は、時代や世代を超えて多くの人に届くこと間違いなし。ニューミュージック調の「青い鳥」で幕を開け、吉田拓郎や原田知世を意識したという、ささやかながら温もりが染みわたる愛の歌「クチナシの部屋」、彼らの思うロック・バンドへのこだわりが見え隠れする「1989」、軽快に突っ走る「untitle crown」と畳み掛け、"どうしても届けたい/君だけへの歌がある"と飛びっきり美しいメロディと、叫ぶのではなくリスナーを包み込むように歌心を響かせる「Flower」が締めくくる。ライヴハウスで彼らの鳴らす生音をたまらなく聴きたくなった。
-

-
Pulse Factory
ULTRANOVA
大阪発のPulse Factoryの新作は、1stアルバムにして多くの挑戦をした作品だ。ライヴを重ね、自主制作の作品を全国流通し、サーキット・イベントを主催するというバンド発信の活動を真摯にし、それに恥じない熱くスケール感溢れるロック・サウンドや、ユーモアも交えたキャッチーなサウンドを奏でてきたが、今回はバンドという形態にとらわれず、自分たちが想像する音を自由に形にした。派手なエレクトロやEDM、ラップやポップなサウンドまで幅は広がり、また、アンセミックなロック・チューンは、その存在をさらに軽やかさと鮮やかさをもって伝える。臆せずに次なるステップに進んだことをリード曲「Sky's the Limit」で晴れやかに、図太くファンキーに表明しているのが気持ちいい。
-

-
PUP
This Place Sucks Ass
2019年のアルバム『Morbid Stuff』が数多の音楽メディアで年間ベストにリストアップされるなど高い評価を得た、トロントの4人組ポップ・パンク・バンド PUP。彼らが、同作のアウトテイクに新曲を加えたEPをリリースした。エネルギッシュなTrack.1、破天荒な展開をみせるTrack.2、疾走感溢れるショート・チューンのTrack.6など、内省的なムードが漂っていたアルバムに比べると、本作ではバンドの持つ狂騒的で豪快な部分を増幅させたようなサウンドを披露していて、アルバムと好対照をなす作品と言えるだろう。映画"28日後..."で使用されたGRANDADDYの「A.M. 180」を轟音でカバーしたTrack.3も、混迷の時代に寄り添うようで趣深い。
-

-
PURLING HISS
Water On Mars
フィラデルフィア出身のギタリストMike Polizzeを中心に活動するサイケデリック・ロック・バンドPURLING HISSのニュー・アルバムがリリース。ファズの強いブルージー且つ骨太のガレージ・マナーのギター・サウンドは男なら胸を熱くさせるものがある。ただラウドでヘヴィなだけじゃなくツボを押さえたフックと極上のメロディ。それがこのアルバムにとても聴きやすさとポップさを生んでいて、より特別なものにしている。ローファイ感ある独特なサウンドも彼の個性を際立たせる要因だ。彷彿とさせるのはやはり男臭さ全開の一時期のPRIMAL SCREAMか。男泣きのギターと爆発力あるガレージ・ロックンロールが炸裂する大注目の1枚。
-
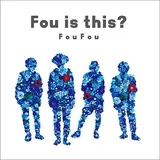
-
PURPLE HUMPTY(ex-FouFou)
Fou is this?
クラウドファンディングでの企画を経て今年8月に現バンド名に改名した4ピース・バンド、FouFouによる1stミニ・アルバム(いしわたり淳治プロデュース)。新名義での初音源ということもあってか、昂揚感、幸福感、期待、少しの不安など様々な感情が透明感のあるサウンドの中に落とし込まれている。飛び道具を用いることなく、ただただ丁寧に音を鳴らすのみ、という誠実さが感じられるのも良い。ブラスやストリングスなど、曲によってはメンバー以外のサウンドも鳴っているが、それらをナチュラルにバンドにとっての追い風に変えられるのも彼らの長所だろう。ゆえに、これから先はもっと幅広い表現に打って出る可能性もありそうだが、さて、そのあたりはどうなるだろうか。
-

-
PURPLE HUMPTY(ex-FouFou)
BABY BABY/Lotus
フォーキーで温もりのあるポップなサウンドと井田 健(Vo/Gt)の優しい歌声が心地よい大阪出身の4人組、PURPLE HUMPTY。『BABY BABY/Lotus』はTOWER RECORDSの一部の店舗とライヴ会場などで限定リリースされた、彼らにとって3枚目のシングルだ。そこにはかつて日本のポピュラー音楽が持ち合わせていた歌心が確かにある。'60sガールズ・ポップとドメスティックなポップスの融合という王道感のあるポップ・チューン「BABY BABY」。そして「Lotus」は、個人的に学校から帰ってきてランドセルを置くときのような安心感を思い起こさせるノスタルジックな楽曲だ。この楽曲の完成度と音の感触は、お茶の間でも静かに、そして暖かく迎え入れられるのではないだろうか。
-

-
PURSUIT GROOVES
Fox Trot Mannerisms
ルックリンに拠点を置く女性アーティスト Vanese SmithによるユニットPURSUIT GROOVESの音源が日本初上陸。海外でのリリースはあの超人気ダブステッパーPINCHが主宰するレーベルTECTONICからということで、この作品もダブステップのイメージを持って聴くと……ちょっとビックリするかも。断続的に打ち込まれるブレイクビートはダブステップとは一線を画すスタイルだが、そのハネッぷりはダブステップ・フリークも強烈にステップを踏みたくなること確実。さらに面白いのは、そのビートを包む多彩な音色。優雅な響きの女性ボーカル、パーカッション、ときに空間的に広がり、かと思えば可愛らしい響きで弾ける電子音……。あえて言うならテクノ・ダブとでも表現できそうな、新種のエレクトロニック・ダンス・ミュージックだ。
-
-
PVRIS
Use Me
ONE OK ROCKやcoldrainとも共演し、オルタナ・ロックというジャンルの垣根を越えてその知名度を増しているPVRIS。Warner Records移籍作となる3rdアルバムは、フロントウーマンのLynn Gunnが作詞作曲はもとより、演奏やプロデュースなどクリエイティヴ面の多くを担った、心機一転の作品になった。退廃的なエレクトロ・サウンドに気だるいLynnの歌声が絡むTrack.2、ハード・サウンドでEDM的な高揚感を生み出すTrack.5、アコギ・サウンドに美しいコーラスが染みわたるTrack.8など、持ち前のエモーショナルなオルタナ×エレクトロのスタイルを進化させながら、メインストリームにも接近。さらにサウンドの自由度を増したアルバムだ。


























