DISC REVIEW
K
-

-
KANA-BOON
TIME
怒涛のフィルが時間に追われながらも全力で走る決意をタフに表現するオープニングの「タイムアウト」から、時間をテーマにしたアルバムの大きな意志に巻き込まれる。90年代後半以降の"ザ・日本のギター・ロック"な「ターミナル」の孤独と自由。雨音のイメージを増幅するギター・フレーズが美しい「スコールスコール」や、谷口鮪がパーソナルな心象を都会のどこにでもありそうな情景に溶け込ませて歌う「愛にまみれて」のバンドにとっての新生面。特に「愛にまみれて」にうっすら漂うノスタルジーを表現するコーラスの美しさはレコーディング作品ならでは。攻めの前半からメロディや歌詞の新しさにはっとする後半への流れそのものが聴き手にとっても"生きている今"になるような強い作品。
-

-
KANA-BOON
シルエット
4カウントとギター・リフのおなじみのイントロの次に展開する開放的な8ビートが作る、KANA-BOONの新しいスタンダード、「シルエット」。思期から青春期を走りぬけ、覚えてないこともたくさんあるけれど、ずっと変わらないものを教えてくれた人たちのことを思うヴァースはライヴでも大きなシングアロングが起こりそうだ。カップリングはインディーズ時代から存在していた「ワカラズヤ」と、最新曲の「バカ」。すれ違う気持ちが一層ジリジリする恋心を浮かび上がらせる「ワカラズヤ」の愛らしさも、エッジーな16ビートに乗せて谷口のラップも交え、フラストレーションの吐き出し先のない自分のめんどくささを歌う「バカ」にも、いい意味で肩の力が抜け、曲作りに対してタフになった今の4人が見えてくる。
-

-
KANA-BOON
生きてゆく
清涼飲料水のタイアップがついてもおかしくないような、夏らしい眩しさの中で描かれるのは、バンドで生きていくことを決めた自分が、別の道を行くことになる"キミ"との距離を描きながら、最終的には自分の決意。事実から生まれながら、長くKANA-BOONが音楽や自分と向き合うときに思い出される大切な曲になりそうな予感もある名曲だ。毎回、表題ともアルバム収録曲とも違うチャレンジングな一面を見せるカップリング。今回もこれまでにない変則的なビートが印象的なダンス・ロック「日は落ち、また繰り返す」、ドライヴ感に加えてグラマラスな印象さえある「ロックンロールスター」の2曲は、無意識のうちにも彼らが洋楽のエッセンスを吸収していることを実感。ライヴの楽しみ方の幅も広がりそうなシングルだ。
-

-
KANA-BOON
フルドライブ
ソリッドなギター・リフ、四つ打ちのなかに部分部分でヒネリの効いたスネアが入り、谷口鮪のリリックは意味より破裂音や韻の快感を重視しているような「フルドライブ」。リスナー側がスリリングなチェイスに身をおいているような感覚が新しい。Track.2「レピドシレン」は魚ながら肺呼吸をしなければならない魚を比喩に用いたことで、焦燥と疾走を同時に焚き付けられるような仕上がりに。特に古賀のギターは全編、カオティックな曲のバックグラウンドを形成するサウンドスケープを担う出色のアレンジ。Track.3「夜のマーチ」は、まさに夜の色と空気感が立ち上がるような映像喚起力抜群の聴感。マーチングのリズムを主体に変化していくリズムが、歌詞での心の動きとシンクロするアレンジもいい。
-

-
KANA-BOON
結晶星
逞しささえ感じるリズムと澄んだ空気を感じさせるギターのフレーズが好対照を描くタイトル・チューン「結晶星」。やめたいことはやめればいいし、やりたいことをしっかり結晶させればその輝きで、これからを変えていけるというメッセージが、今の彼らの経験値やスキルで鳴らされていることに大きな意味がある。新しい季節を迎えるあらゆる人の心に穏やかだが確かな火をつけてくれる1曲。「ミミック」は前作『DOPPEL』収録の「ウォーリーヒーロー」にも似た、顔の見えないSNSのコミュニケーションに対する問題提起。「桜の詩」は「さくらのうた」から時間が経過し、女性目線で描かれたアプローチが新しい。まったく異なるニュアンスとテーマを持った、挑戦的な1枚。
-

-
KANA-BOON
DOPPEL
人懐こいサビにも、思わずステップを踏みたくなるビートにも、もちろん、想いを遠くに投げかけようとする谷口鮪の声にも、"音楽があったから今、僕はここにいる"、そんな切実さが横溢している。ライヴでもなじみのインディーズ時代からの「ワールド」「MUSiC」「東京」「目と目と目と目」はアップデートされたアレンジ、演奏と音像で収録。現在のライヴ・シーン、ひいてはSNSでのコミュニケーションについて谷口の思うところが、鋭いギター・リフや性急なビートとともに表現された「ウォーリーヒーロー」をはじめ、デビュー・シングル「盛者必衰の理、お断り」などの今年の楽曲から成る、1stフル・アルバムにしてKANA-BOONの存在証明的な1枚。10代に圧倒的な人気を誇る彼らだが、現状に息苦しさを感じるあらゆる人に響くはずだ。
-

-
KANA-BOON
盛者必衰の理、お断り
彗星の如く、という言葉が相応しい快進撃を続ける、大阪は堺から現れた4ピース・バンドKANA-BOON。初の全国流通盤『僕がCDを出したら』から約5ヶ月というインターバルでメジャー・デビューという異例のスピードも、現在の彼らの注目度と楽曲のクオリティやライヴ・パフォーマンスを考えれば当然のことだ。そしてデビュー曲である「盛者必衰の理、お断り」はKANA-BOONの持つ抜群のセンスが冴え渡る楽曲。抜けの良いヴォーカル、思わず口ずさみたくなる語感の良さと人懐こいメロディ、ヒーロー感のあるギター・リフ......非凡な展開でありながらもストレートさを感じさせるのは、彼らが素直に自分たちの気持ち良い音を鳴らしているからなのだろう。10月にリリースされるフル・アルバムにも期待が高まる。
-

-
KANA-BOON
僕がCDを出したら
ライヴで大合唱が起こる人気曲「ないものねだり」でアッパーにスタートし、大きなステージに立っているアーティストと入れ替わる感覚をアレンジでも表現したユニークな「クローン」、ギター・リフのソリッドさと、聴き手ひとりひとりにダイレクトに放たれるストレートなメッセージが痛快な「ストラテジー」「見たくないもの」、アルバム・タイトルのフレーズも含まれる「眠れぬ森の君のため」。そして、ヴォーカルの谷口鮪にとっての歌や思い出の重みや、それゆえの切なさが胸に迫るラストの「さくらのうた」の全6曲。歌詞カードなしでも飛び込んで来る言葉の鮮明さと歌に沿った演奏の音楽的な破壊力。"僕がCDを出したら"その先は......野心と不安のバランスに大いに共感。
-

-
KAQRIYOTERROR
Reaper feeder
今年4月に新メンバー RЯ(ありゃ)、そしてオリジナル・メンバーだったのなめらが再加入して、新体制となったKAQRIYOTERROR。表題曲「Reaper feeder」は、ダークでポップなエレクトロ・ダンス・チューンだ。どこかオリエンタルな香りがする響き、また4人の個性的なヴォーカルがリズミカルに織り成されることで、不可思議な桃源郷感があり、そんなふわふわ浮遊するような心地よさから、それでいいの? 今のままでいいの? と矢継ぎ早に問い掛けられていく。この疑問符がボディ・ブローのように効いてくる曲だ。c/wは2018年のミニ・アルバム収録曲の新バージョン「アイデンティティークライシス(FF Ver.)」を収録。「Reaper feeder」と共鳴し、こちらは痛烈な一撃を食らわす。
-

-
KAQRIYOTERROR
BWG
『lilithpride』に続くシングル。ジャンルレスでルール無用なKAQRIYOTERROR節は「BWG」でも加速していて、インダストリアル・ロックをベースに、エキゾチックなフレージングから詩情溢れるピアノの旋律も織り成され、着地点も不明なカオスなサウンドに乗って5人の声が跋扈する。惰性と日常を疑えとばかりの縦横無尽さで、拳を突き上げる曲はまさにKAQRIYOTERRORだ。また、レーベルメイトの少年がミルクと、そのバンド・メンバーであるハヤシタカヒロのタッグで、作詞作曲を手掛けた「なんちゃらバブルス」もまた、「BWG」に共振する内容をポップに描いたもの。禁忌がタブーというマイ・ルールで素っ頓狂なパワーがあるが、2曲共に確実に仕留めにいく鋭さを持つ本領発揮の新作だ。
-

-
KAQRIYOTERROR
lilithpride
幽世テロルArchitectから名前を変え、5人体制で始める第1弾シングル。幽世時から受け継がれている、不気味でいてかっこいいエクストリームなサウンドやヴァイブは変わらずに、アップデートしながら、1stシングルとしてグループの決意や不変のクセを全開にしたのが表題曲だ。デジタルでラウド&グルーヴィなサウンドに5人の声が跋扈し交わっていくこの曲で、感情のメーターを振り切ってKAQRIYOTERRORとして狂い咲くことを宣誓する。ポジティヴなタイトル・チューンに対して、c/w「SOS」はアンニュイなポップさが光る曲。低体温的だが、気持ちは迸っている歌は、空回りしている人生にピッタリと寄り添ってくれる。ここからまた"電磁的恐怖こうげき"がパワーアップしてスタートする。
-

-
KAQRIYOTERROR
The Forbidden Masturbating
不穏にして邪気たっぷりな音像と、殺伐とした剣呑な言葉たちが吹きすさぶなかで、彼女たちは今日も楽しげに躍り歌い続ける。ぜんぶ君のせいだ。などを世へ送り出してきたレーベル"コドモメンタルINC."の手掛けるアイドル、幽世テロルArchitectにとって、今作は新体制での初シングルだ。"禁忌がタブーの電磁的恐怖こうげき。なにひとつ思い通りになんてならない世の中だから、幽世からこうげきを開始しますけど"なるコピーを掲げながら小悪魔の所業さながらに少女たちが暴こうとしているのは、閉塞した現世にはびこる欺瞞なのかもしれない。圧倒的密度の中で音像と歌が炸裂する「The Forbidden Masturbating」のほか、代表曲「かごめかごめ」の"2019Ver."なども収録。
-

-
KAQRIYOTERROR
Cultural Mixing
2017年10月に1stシングル『かごめかごめ / Hybrid TABOO』、翌月に2ndシングル『ユビキリゲンマン』を発売し、早くもアルバムというハイペースなリリースと、音源ごとに新たなサウンドを切り出す撹乱ぶりに驚かされる。ぜんぶ君のせいだ。やゆくえしれずつれづれを擁するコドモメンタルのニューカマーは、ポップでキャッチーなふうでいて、一番厄介な存在だ。カラフルなシンセ・ポップがあり、ラップやシャウトが入ったラウドやダンス・チューン、メロウなメロディを響かせる曲もあり、また今作はGeorge(MOP of HEAD/Machine)による曲が2曲収録され、さらなる幅を生み出している。ファットなビートと重厚なサウンド、3人の個性溢れる歌声が織りなすめくるめく高揚感を味わいたい。
-

-
KAQRIYOTERROR
ユビキリゲンマン
10月にシングル『かごめかごめ / Hybrid TABOO』でデビューした3人組が、早くも2作目を完成。アグレッシヴなビートのシンセ・チューンや、儚げなポップ・ソング、ぶっ飛んだヴォーカルやラップが乗る曲など不思議な存在感を醸し出していた前作だが、今回もその掴めなさに拍車が掛かっている。バキバキのEDM「ユビキリゲンマン」に、カラフルなポップ・ナンバーに突如ラップが切り込む「いろはにコラージュ」、そして「Therefore?」はエキゾチックな雰囲気漂うダンス・チューン。ハイトーン・ヴォーカルと、パンチの効いたロックなヴォーカルという凸凹な組み合わせの3人だからこそ、クールな曲も歪な面白さで多面的に見せられる。3人の未知の可能性が、曲によって開かれていくのが楽しみだ。
-
-
KAQRIYOTERROR
かごめかごめ / Hybrid TABOO
ぜんぶ君のせいだ。、ゆくえしれずつれづれに続き、コドモメンタルが送り出す3ピース・アイドル・グループ、幽世テロルArchitect。他グループ同様、尖ったエクストリームなサウンドと歌で、素っ頓狂に暴れ回る1stシングルだ。ヘヴィなインダストリアル感と攻撃的な音響感で打ちつけるサウンドに、ラップやウィスパー・ヴォイス、メロディで畳み掛けるように織りなしていく「かごめかごめ」のスリリングさ、めまぐるしく展開していくEDMサウンドで何度も爆発や暴発を繰り返す「Hybrid TABOO」の奇天烈さなど、頭も身体も引っ掻き回していくこのグループのテーマは、"禁忌がタブー"。結成したばかりで3人のポテンシャルは未知数だが、ここからの展開への期待を存分に詰め込んだ、宣戦布告的な曲が揃った。
-

-
KAREN
Sunday Girl In Silence
ART SCHOOL、DOWNY(現在活動休止中)のメンバー、石橋英子とのデュオでも知られるアチコという個性的なメンバーが集結しているKARENのセカンド・アルバムが完成した。デビュー・アルバム『Maggot In Tears』以上に挑戦的で多彩なリズム隊がまず印象的だが、各メンバーがKARENとしてさらに自由な表現を見せている作品だ。緻密で美しいバンド・アンサンブルと、アチコの伸びやかな声によって歌われる詩世界が絶妙のバランスで絡み合う本作。一音一音がとてもクリアに響いてくる緻密な音作りも合わさって、音楽的挑戦が決して内向きになることなく、全編を通じて、どこまでも開放的な雰囲気に満ちている。多彩な光に満ちた音が心地よい、清々しいポップ・ミュージックだ。
-

-
KAREN O AND THE KIDS
Where The Wild Thing Are Original Sound Track
YEAH YEAH YEAHSのKaren Oが、多数のゲスト、そして子供達とコラボレーション!? Spike Jonez監督の映画『Where The Wild Thing Are』のサウンド・トラックとなる本作。YEAH YEAH YEAHS で見せるエッジーなフロントマンの表情とは全く異なる、とても優しく柔らかい歌声。ライオット・ガールでもセックス・シンボルでもない女性の一面が全面に出た、温かみのあるキュートなポップ・ミュージック。何だかんだ言っても、こういう音楽には抗えない。このサウンドトラックから、何も知らずにYEAH YEAH YEAHSに辿り着いて度肝を抜かれる小中学生が出てくるんだろうね。そういう意味では、罪作りな作品とも言える。
-

-
KASABIAN
Happenings
先行シングル「Call」は、攻撃性を内包したダークな世界観と中毒性のあるリフが耳に残る"これぞ、まさしく新時代のKASABIANビート!"という楽曲。2022年にリリースした前作『The Alchemist's Euphoria』では、Serge Pizzorno(Vo)にフロントマンが変わったことで、いい意味でも悪い意味でもどこかトゲが抜け落ちたような印象があったが、今作は本当に解放感のある自由なロック魂に満ちていて、ギラギラとしたアグレッションもある。もちろんヘヴィなビートに振り切った楽曲ばかりではなく、UKオルタナ、ギター・ロックの魅力を引き継いだメロディアスな楽曲もあり、これまでの彼らの百戦錬磨のライヴ猛者っぷりがわかる作品に仕上がった。
-

-
KASABIAN
The Alchemist's Euphoria
Tom Meighan(Vo)脱退後、初のフル・アルバムとなる本作。新たに外部からヴォーカルを招くことなく、メンバーのSerge Pizzorno(Gt/Vo)がリード・ヴォーカルも務めたことにより、KASABIANのKASABIANたる要素が欠けることなく、うまく前に進めた印象だ。サウンドにはまとまりがあるし、それでいて常に現状打破というかチャレンジングな姿勢を崩さないところはさすが。モダンなエレクトロ・サウンドを意識したアレンジもあって、パンチの効いた激し目の楽曲もトゲトゲしくなく、とても洗練されている。初期には初期の、これまでの彼らには作品ごとの魅力があるのはもちろんだが、いい方向に変化と前進を受け入れていく彼らのポジティヴな魅力が感じられる。
-
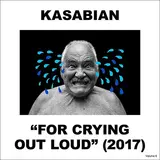
-
KASABIAN
For Crying Out Loud
ギター・ロックの復権どころか、70年代から現在に至るまでのあらゆるビート、グルーヴをロック・バンドの手法とガッツで昇華した作品。Ed Sheeranのモンスター・ヒット・アルバム『÷』の全英1位を9週でストップさせた理由もそれだろう。初期作品を想起させるポスト・パンク的なビートからファンクネス溢れるサビに解放される「Ill Ray (The King)」での幕開けから、BLONDIEとも符合するセクシーで美しいメロの「You're In Love With A Psycho」、ROXY MUSICやDavid BowieのグラマラスなR&Rを底に感じる「Good Fight」や「Comeback Kid」、ザ・UK的なメロディを持つ「All Through The Night」。淡く薄いトラック全盛だが、グランジ×ダンスの肉体性と完成が求められている証左が本作の高評価に顕在した感がある。
-

-
KASABIAN
Velociraptor!
まったく、彼らはリスナーを飽きさせることを知らない。約2年振りのリリースとなる4枚目のオリジナル・アルバムは、KASABIANの活動の集大成であり、新たな力が凝縮された作品だ。怪しく不穏な閉塞感、獲物を虎視眈々と狙うような危険度。ひたすらに不気味な空気を醸し出すストリングスは、おどろおどろしくも美しい。と思いきや、まどろむ様な優しさ溢れるミディアム・ナンバーや、軽快なヴォーカルが炸裂する人懐っこいキャッチーな側面も。次から次へと目まぐるしいその自由度にどんどん身体も思考も翻弄されて行く。ちなみに"Velociraptor(ヴェロキラプトル)"とは、ティラノサウルスを倒すことが出来た唯一の恐竜。挑戦を止めず、常に攻め続けた彼らが、とうとう最強の猛獣を生み出した。
-

-
KASABIAN
West Ryder Pauper Lunatic Asylum
前作『Empire』の時代錯誤的とも言える大仰なハード・ロックは、彼らが本来持つ不穏なグルーヴを半減させてしまっていた。しかし、Dan Nakamura(DJ SHADOW等)をプロディースに迎えた本作では、そのグルーヴがより強靭なものとなって戻っている。一音一音がしっかりと聴こえてくる立体的な空間処理が施された結果、驚くべき化学変化が生まれている。このコンセプチュアルなサイケデリック・アルバムで、KASABIANは彼らの築き上げた帝国へと聴く者を連行する。しかし、いびつで不可思議なその世界を受け入れるかどうかは僕達に委ねられている。EAGLESが歌ったあの一節が頭をよぎる。「You can checkout any time you like, but you can never leave」。
-

-
KASMS
Spayed
ARCTIC MONKEYS、FRANZ FERDINANDを擁するインディ・レーベルDOMINOよりデビューを果たし、NME誌をして「<NEW> THE BEATLES」とまで絶賛された伝説のバンド、TEST ICICLESのメイン・メンバーであったRory Attwellを中心に結成された4人組がこのKASMS。Crystal Castlesを手掛けていることで有名なTROBLE RECORDSよりリリースされた2000枚限定のデビュー・シングル『Taxidermy』がUKのシングルチャート12位を記録。そしてセカンド・シングルを経て今回のアルバム『Spayed』をリリース。混沌としたノイズ一歩手前のサウンドに、時に気だるいメロディを浮遊させ、時にエキセントリックにスクリームする女性ヴォーカル、Maryの存在感が抜群。
-

-
Kate Nash
Girl Talk
デビュー・アルバムが全英チャート1位でプラチナム・アルバムを獲得、FUJI ROCK FESTIVALで来日、続く2ndも好セールスを残す等、順調にキャリアを築いているシンガー・ソングライター、Kate Nashの3年振りの新作。イギリス国内の学校を回り自ら女の子の悩みや望みに耳を傾けた経験を元に制作されたという本作は、「Fri-End?」「Death Proof」、さらにSuzi Quatroばりのアバズレ・ロック・ヴォーカルを聴かせる「Sister」など、パンキッシュでローファイな楽曲の仕上がりが目立つ。それだけにけだるいサウンドの「Labyrinth」、アカペラから壮大なエンディングを迎える「Lullaby For An Lnsomniac」等、耳元で囁くようなメロウな曲の印象度も高い。まるで女の子の感情の振り幅を見せつけられているような、男性には勉強になる(笑)、傑作アルバム。
-

-
Katy Perry
143
"プリンセス・オブ・ポップ"Katy Perryの復帰作。母となり、より大きく深い愛を手にした彼女の4年ぶりのアルバムには、"I Love You"を表すスラング"143"が冠された。全ての女性たちを讃える自信に満ち満ちたアンセム「Woman's World」や"永遠の愛"という壮大なテーマを掲げた「Lifetimes」等、女性として、母として、愛とともに力強く生きる姿が、至極のダンス・ポップに乗せて煌めいている。ダンス・フロアにフォーカスした今作は、21 SAVAGE、Kim Petras、Doechii、J.I.DといったラッパーやSSWを迎えた豪華なコラボ曲も聴きどころ。「Wonder」に登場する娘 Daisyの天使のような愛らしい歌声にも注目だ。
-

-
katyusha
I Like Me
DADARAYのフロントマン、ゲスの極み乙女。/indigo la Endのサポートとしても活躍する"えつこ"のソロ・プロジェクト katyushaが始動から約10年を経て完成させた1stフル・アルバム。ピアノなどの鍵盤楽器、ベース、ドラム&パーカッション、コーラスを基盤にしたサウンドはジャンルにとらわれない自由度がある。それすなわち彼女が曲に込めた想いを最大限に生かすサウンドメイクに注力しているということだ。生活するなかで心の中に宿った感傷や、抱えたまま置き去りにしていた物悲しさを丁寧に描くヴォーカルは、聴き手やえつこ自身を肯定する優しさと強さがある。彼女と対話をしているようなささやかで濃密な空気感、そして零れた涙を優しく拭うようなぬくもりとユーモアがさらに涙腺を刺激する。
-

-
KEANE
The Best Of Keane
"心臓が止まるほど美しい"と評されたデビュー作『Hopes And Fears』から10年を経たUK発の4ピース、KEANE。作品は毎作UKチャート1位となり、日本でもこれぞUKロックたる叙情性の高い鍵盤サウンド、繊細で憂いがあり、かつ大らかでアンセム的なメロディ・ラインが人気の彼らの、初のベスト・アルバム。2枚組で、1枚はシングルや定番曲のベスト・セレクション、もう1枚は初CD化となる曲などをセレクトしている。泣きの琴線に触れるだけでなく、ブライトで高揚感のあるスケール感たっぷりのサウンドもこのバンドの真骨頂。ドラマ性の高い王道感を、正攻法で形にしてプレイするというアプローチがリスナーの裾野を広げている。この真っ直ぐな姿勢を磨いた、重厚な10年が詰まっている。
-

-
KEANE
Strangeland
イギリスのピアノ・ロック・バンドKEANEによる4枚目のオリジナル・アルバム。サポート・メンバーだったJesse Quin(Ba)が正式加入してから初の作品となり、全英チャートにおいて前作に続き初登場1位を獲得している。時間に囚われず制作されたこともあり、イギリスの伝統的なロック/ポップの精神を継承した正統派サウンドと、真摯に歌に取り組んだTom Chaplinのヴォーカルは、のびのびと響き渡る。彼の歌声の凛々しさやたくましさは、歌そのものの素晴らしさを伝えようという思いから生まれるものだろう。どこまでも伸びやかな歌が紡ぐメロディが耳に佇み、聴き手の視界を広げていく。きらびやかなピアノとふんわりとしたストリングスがその歌を包み込み、優しく温かい雰囲気を作り出している。
-

-
KEEP SHELLY IN ATHENS
In Love With Dusk / Our Own Dream
EPをリリースすれば即完売、インディー・ロック・シーンで注目を浴びているギリシャはアテネで活動する男女デュオ、KEEP SHELLY IN ATHENSの初のCD作品。2010年のデビューEP『In Love With Dusk』と2011年にリリースされたEP『Our Own Dream』がコンパイルされた今作。クールで重厚感のあるシンセ・ワークとダウンテンポのビートにメランコリックなメロディの女性ヴォーカルが絡みつきゴシックな雰囲気を醸し出しているが、カラフルな音色が要所に重ねられ、まるで暗闇の中を光の輪が躍っているようである。エレ・ポップの枠に留まらない多彩なサウンドはこれから更に進化していくだろうことが予想され、わくわくさせられる1枚である。
-

-
Keishi Tanaka
What's a Trunk?
Bruno Marsもいいけど日本にはKeishi Tanakaがいる! と歓喜したくなるほどポップに、そして現代版にアップデートされたソウル、ジャズ、スカなどがずらりと並ぶ好盤。Tokyo Recordings、LEARNERS(松田"CHABE"岳二&紗羅マリー)、そしてジャズ・ロック・バンド fox capture planとのシングル3部作をアルバムのフックにしつつ、新たにRopesと共演したアコースティックもエレクトロも呑み込んで独自のフォーキーな情景を完成させたTrack.8などもごくごく自然に並列されている。しかしなんといってもこれからの寒い季節をものともせずに外へ飛び出し、思わず仲間と踊りたくなるようなオープニングの「What A Happy Day」と、続く「Another Way(is so nice)」の清々しさったらない。粋でエモくて笑顔と涙が共存する傑作。
-

-
fox capture plan feat. Keishi Tanaka
透明色のクルージング
ジャズ・ロック・バンド fox capture planとシンガー・ソングライター Keishi Tanakaが互いをフィーチャリングした作品をそれぞれのレーベルから同時リリース。表題曲のTrack.1「透明色のクルージング」と同曲のインスト・バージョンを共通トラックとした内容違いの5曲入りとなっている。「透明色のクルージング」はfox capture planにとっては初めてのヴォーカル入り楽曲を収録したものとなっており、見事なマッチングで躍動感溢れる楽曲を聴かせている。その他、fox capture planサイドでは軽快なピアノをバック・ビートで聴かせ、まさに本領発揮といった爽快さのTrack.3「Silent Fourth」、Keishi TanakaサイドではTrack.4「After Rain」の"fox capture plan Remix"など、互いに異なる聴きどころを楽しめる。
-

-
KELE
The Boxer
BLOC PARTYのヴォーカル、Kele Okereke がKELEとしてソロ・デビュー。SPANK ROCKのトラック・メーカーXxxchangeをプロデューサーに、ダンスホールやグライムを下敷きにしたようなブレイクビーツ、女性Voをフィーチャーしたトラックから、80'sなエレクトロまで。肉体的であると同時に、彼が持つ知的でフェミニンな世界観がアルバムの基調となっている。BLOC PARTY『Intimacy』がそうした世界観をバンドとして構築してみせた作品だとしたら、このソロは、その源泉であるKele Okerekeという特異なキャラクターそのものにスポットライトを当てた作品と言える。それゆえに、肉体性と知性が艶やかに跳ねるこのアルバムは、とても生々しい。
-

-
Kendra Morris
Mockingbird
昨年、アルバム『Banshee』でデビューしたNYのシンガー・ソングライター、Kendra Morrisの新作は、David BowieやLou Reed、Isaac Hayes、PINK FLOYDやRADIOHEAD等のカヴァー・アルバム。音楽一家で育ち、ソウル・ミュージックのレコードを教科書にヴォーカルを磨き表現力を培ってきた彼女らしく、どんなアーティストの曲にも深くダイヴして、その精神を掴みとろうとする姿勢がうかがえる。真摯なアプローチでインプットした曲を、自身の感情で翻訳して解き放った歌声は、静かに熱を帯びながら心に広がって、胸を締め付ける。エアリーに響くヴォーカルだが、歌の終わりには痛みや切なさや、哀しみが、ふつふつと沸く爪痕を残していくようだ。ソウルフルなアレンジでデジャヴにも似た、記憶に心に響くカバー集。
-

-
Kent Kakitsubata
ELEKITEL
ヴォーカル、コーラス、ギター、作詞作曲を全てひとりでこなす21歳のシンガー・ソングライター、Kent Kakitsubataのデビュー・アルバムがリリース。ロックを基盤に、ファンク、ポップス、レゲエ、フォーク、ヒップホップの要素が取り入れられたサウンド・メイクと、青年と少年の両方の感性が融合した歌詞が次々と爆発し、聴き手の心を良い意味で休ませない。世の中や、同世代に対しての警鐘、生きてきた上で辿り着いた自分なりの哲学を、彼独特のウィットに富んだ表現で打ち鳴らす。不安定で混沌とする現在と向き合いながら未来への可能性を創造する――まさにこれから大きく羽ばたく世代だからこそ実現できるリアリティだ。マイナー・コードが効いたメランコリックなメロディ・ラインも軽やかに響く。
-

-
KETTLES
Here!
2008年8月に結成したコイケ(Vo&Gt)、オカヤス(Vo&Dr)による男女2人組みバンドのほぼ1年ぶりとなるニュー・アルバム。体制的にはTHE WHITE STRIPESのそれと同じではあるが、彼らは限りなく最小限の人数で灼熱のロックを展開していたが、KETTLESは非常に力の抜けた、ただ強靭な芯の強さを持ったロック・バンドだ。1曲目の「吹き飛ばしたら」からボーナス・トラックを除いた最後の曲「日が昇るまで」全曲において言えることなのだが、ポップさの中に確実に眼を光らせた何かが潜んでいる。それは日常を切り取った詞の端々にも、決して大げさなギミックを用いないアレンジの中からもギラギラと感じるのだ。ボーナス・トラックにはヤバイバイバイのリフレインが中毒性満点の「ヤバイバイバイ」のCHABEリミックスを収録、お洒落な化粧を施されたトラックにも注目。
-

-
key poor diary
keyword
福岡の4人組ギター・ロック・バンド key poor diaryが放つ初のミニ・アルバム『keyword』は、バンドのコンセプトである"振り返りながらもきちんと前に進むための曲を"という思いがそのまま落とし込まれた1枚。プロローグのようなTrack.1「九月の月」から、5ヶ月前を振り返るTrack.2「四月の彼女」への流れはまさに"あのときを振り返る"構成になっていて素晴らしい。また、プロデューサーに、YMOやくるりなど数多くのサポートを行っているゴンドウトモヒコ(METAFIVE/anonymass/蓮沼執太フィル)を迎え入れているのもチェックするべきポイント。そして、エッジの効いたギター・ロック・サウンドに乗せて心に語りかけてくる大島正太(Vo/Gt)の"あなたがどんな人でもいいから"という正直な言葉には安心させられる。何気ない日常を大切にしようと思った。
-

-
KEYTALK
DANCEJILLION
"ダンス"を追求し続けてきたKEYTALKが、改めて"ダンス"と向き合ったアルバム。1曲目の「ハコワレサマー」が八木優樹(Dr/Cho)の書いた曲であるように、誰がメインで誰がオルタナティヴではなく、ソングライターとしてもプレイヤーとしても4人揃ってド真ん中を狙う姿勢。そしてKEYTALKがKEYTALKであるために4人が身につけた"王道"は、外から見ると"異様"であり、とんでもないスゴ技であることが今作を聴くとよくわかる。山場だらけのメロディ。突然の転調。それを見事に乗りこなすツイン・ヴォーカル。不思議な軌道を描くギター。様々なリズム・パターンを繰り出すドラム。これだけいろいろやっているのにどこかケロッとしているのは、重ねた歳月によるところが大きいのだろう。
-

-
KEYTALK
ACTION!
思えばコロナ禍以前にリリースした「サンライズ」が、彼らには珍しいファストなポップ・パンクだったのも、バンドが初期衝動に満ちていた予兆だったのかも。何度も更新されてきたKEYTALK流カーニバル・ソングは、「宴はヨイヨイ恋しぐれ」でゴリゴリした感触さえ残すし、前作以降、冴えを見せる首藤義勝のファルセットは奇妙なメロの「大脱走」で映えているし、EDM路線でありつつドラムは生音がタフな「ラグエモーション」、16ビートの中にハード・ロック・テイストが否応なしに滲む「不死鳥」は、小野武正のギターあってこそ。終盤は首藤のソロ・ヴォーカル曲「あなたは十六夜」、「愛文」、寺中友将の「照れ隠し」が並ぶことで、自然体の歌詞の強さも伝わる。結成12年にしてこの飽くなき好奇心と振り幅が彼ららしい。
-
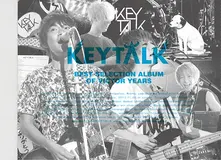
-
KEYTALK
Best Selection Album of Victor Years
2013年にメジャー・デビューしてからの、14枚のシングル表題曲+タイアップやライヴ人気曲からなる20曲に、怒濤の5年間の進化を感じるベスト・セレクション。首藤義勝、寺中友将のツイン・ヴォーカル、四つ打ち、目まぐるしい転調とどこかメランコリックなメロディは今でも独特だ。「MONSTER DANCE」、「桜花爛漫」など和テイストの振り切れっぷり、祭りというテーマを太いファンクに昇華した「MATSURI BAYASHI」あたりから、全体の屈強さもアップ。ストリングスとプリミティヴなビートと、EDM風味を融合させた「Summer Venus」に至っては、楽しいことを120パーセント体現するKEYTALKの真骨頂だ。完全生産盤にはライヴ映像も。フィジカルならではのお楽しみは見逃せない。
-
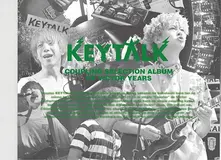
-
KEYTALK
Coupling Selection Album of Victor Years
ビクター時代のc/w集。人気曲「OSAKA SUNTAN」、寺中友将(Vo/Gt)の美メロ・メーカーぶりが発揮された「エンドロール」、ルーツであるthe band apart的なアレンジにニヤリとする「O型」、怒濤のブラストビートの「ナンバーブレイン」、小野武正(Gt/MC/Cho)、八木優樹(Dr/Cho)の共作で、めくるめく展開や早口のトーキングVoがユニークな「鏡花水月」、テクニックの高さを笑えるスクリーモ(!?)に昇華した「One side grilled meat」、レア・グルーヴ~ニュージャズ風の「wasted」、タフさが増した「SAMURAI REVOLUTION」、モンドなメロディが癖になる「誓い」など、高い作編曲能力と斜め上のセンスを満喫できる。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号


























