DISC REVIEW
K
-

-
KING BROTHERS
THE FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
ベースレスの獰猛なガレージ・ロックンロールを掻き鳴らし続け、国内外多くのバンドからリスペクトを集めるKING BROTHERS、ベースのシンノスケが加入してから初のアルバム。精力的なライヴ活動で全くそんな感じはしなかったのだが、何と6年ぶりのアルバム・リリースとなる。ガレージ・ロックンロールの破壊的、暴力的な部分は、実はとてもロマンティックなアイデンティティの上に成り立っているわけだけど、KING BROTHERSはこの新作でまさにそのロマンを詰め込んだ爆音を轟かせる。要所、要所に配置される繊細なポップな楽曲も美しい。愚直なまでにロックンロールの様式美と精神性に拘り続けてきたKING BROTHERSだから鳴らせる爆音ロックンロール。この説得力は、そんじょそこらのバンドに出せるわけがない。
-

-
King Gnu
一途/逆夢
初日で100万人以上動員した"劇場版 呪術廻戦 0"で、物語とともに「一途」と「逆夢」の意味を飲み込んだ人も多いことだろう。つまり、ここからさらにファン層を拡大していくことは間違いない。先行配信された「一途」はスピード感のあるガレージ・ロックを下地に持ちながら、"一途さ"をサウンドやアレンジに昇華したかのごとく、リフもドラム・パターンも圧に耐えながら突破していくような体感をリスナーにもたらす音像に、King Gnuでしか鳴らし得ないパースペクティヴがある。そしてエンディングで、"呪術廻戦"という複雑で矛盾を孕んだドラマに説得力を与えたのが「逆夢」だろう。鍵盤やストリングスを配し、バースやサビも細かにその中で変容。4サビでメジャー・キーに転調する構成はまさにエクスペリメント。
-

-
King Gnu
CEREMONY
King Gnuの強すぎる音楽的背景を伴ったポップ・シーンへの確信犯的なブレイク要素は、ヒップホップ並の言葉数を、楽器を弾くような難解で癖になるメロディに乗せる常田大希(Gt/Vo)の作曲/アレンジ能力と、それを歌いこなせる井口 理という恐るべきヴォーカリストが実在することだ。配信サービスで1億回再生を突破した「白日」、アンセミックな「Teenager Forever」、詩的な美しさを湛えた「傘」など馴染みの曲を収めた本作だが、見事なのは、"俺たちの東京ニーゼロニーゼロ"とでも言うべきテンションの上に成り立つ"儀式"がテーマである点。情報量の多さがデフォルトの彼らの作品の中でも歪み系ギターの「どろん」、常田のチェロがこの儀式の方向を示唆するフィナーレの「閉会式」に震えた。
-

-
King Gnu
Sympa
始動から1年強にもかかわらず急速に知名度を上げ、ワンマンをすべて即完するなど注目を集めるKing Gnuが、アルバム『Sympa』でメジャー・デビューを果たす。色気たっぷりの美しいサウンドだけでなく、歌詞のメッセージ性も全体的に強度を増した印象。壮大なリード曲「Slumberland」、ロック色が強い「Sorrows」、アニメ"BANANA FISH"EDテーマ「Prayer X」などキラー・チューンが多いなかで、悲しげなピアノがひと際意外性を放つバラード「The hole」は彼らなりの挑戦だったのでは。また、世界観を強調するインスト4曲がアルバム全体のバランスを保ち、ひとつの作品としての完成度を高めている。まだまだ進化の余地を感じさせる、可能性に満ちた1枚。
-

-
KINGONS
Pop Of The World
2008年に宇都宮で結成されたポップ・パンク・バンドKINGONS初のフル・アルバム。今年一月にリリースされたミニ・アルバムのツアーで全国30箇所を回り、台湾ツアーさらに6月にはSANCE PANKS主催のイベントへ出演とライヴ・バンドとして成長と注目を集めてきた彼ら。その勢いを象徴するように今作は一曲目「Happines」から疾走感溢れるパワフルなナンバーが並ぶ。ただ彼らの魅力はそこにドキドキ感やドタバタ感を盛り込んでいる所。「青春パンク」という言葉では片付けられない人間臭さが一曲一曲に感じられ、懐かしささえ感じるメロディ・ラインにもグッとくる。RAMONES風のルックスとスタイルから放たれるオリジナルなポップ・パンク・サウンド。
-

-
KINGS OF LEON
When You See Yourself
米ナッシュビル出身4人組の、約5年ぶり8枚目となるアルバム。初の全米アルバム・チャート1位を獲得した前作『Walls』から引き続き、プロデューサーにARCADE FIREやCOLDPLAYを手掛けたMarkus Dravsを迎えているが、きらびやかなディスコ・チューンや疾走感のあるギター・ロックなど華美な印象だった前作に比べると、静かに聴かせる曲も多く、アダルトで落ち着いた雰囲気に。そのぶん、いなたいグルーヴを聴かせる楽器陣と、クセのある歌声で紡がれるどこか切ないメロディが主張していて、じわじわと温かく心地よい音世界に包まれていくかのよう。飾らない、等身大で素朴な姿で聴き手に寄り添う本作は、依然として家で過ごすことの多い今にも合っている気がする。
-

-
KINGS OF LEON
Walls
ナッシュビル出身4人組ロック・バンドの約3年ぶり通算7作目となるニュー・アルバム。これまでのアルバムすべてを手掛けてきたプロデューサーに代わりCOLDPLAYやARCADE FIREなどを手掛けたMarkus Dravsを迎えて制作された今作は、1stシングルとなった「Waste A Moment」を始め、大きい音の広がりを感じさせる楽曲が並んでいる。そこには数々の大型フェスのヘッドライナーを務めてきた彼らならではの音楽で人々を巻き込んでいく力を感じさせる。あたたかくキラキラしたポップスで踊らせる「Around The World」、スリリングな「Find Me」など、表情豊かな曲たちは、"ファンとの壁がなくなる"という意味が含まれた歌詞"walls come down"を歌う表題曲「Walls」が象徴しているように多くの人に受け入れられそうだ。
-

-
THE KINKS
Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One
今年はデビュー50周年となり、1964年から1970年までの作品が復刻リリースされることとなったブリティッシュ・ロック・バンド、THE KINKS。今なお多くのバンドに影響を与え、世界中の音楽ファンのフェイヴァリット・バンドであり続ける、ポップでシニカルで、それでいて甘美なロックンロールの名盤たちの最初の復刻盤である今作は、1970年に発表されたコンセプト・アルバム。音楽業界のあれやこれやを批評的に、たっぷり毒もユーモアも盛って1枚のアルバムへと仕立てられていて、コンセプト・アルバムと言うと敷居の高い感じ?と思いきや、シンプルでキャッチーな曲のオンパレード。ガツンとワンパンチでKOする即効性の高さがあって、口ずさめるフレンドリーで中毒性の高いメロディやフレーズで酔わせ続けるアルバムだ。
-

-
KIRINJI
SUPER VIEW
来春のツアーをもって堀込泰行の脱退が発表されたキリンジの、約2年2ヵ月ぶりの新作。今年はインディーズ・デビューから15年という節目の年だっただけに脱退の報は衝撃だったが、本作は、そんな衝撃的な知らせもどこ吹く風と言わんばかりの素晴らしい仕上がり。室内楽的なストリングスとバンドによる、繊細かつダイナミックなアンサンブル。清涼感のあるコーラス。時に差し込まれるファニーな電子音。メロディ・オリエンテッドなサウンドにあって、自在に曲の表情を変えてみせる多彩なリズム。すべての完成度が高く、ユーモアとメッセージ性を絶妙に交えた歌詞も秀逸。だが、最後を飾る「竜の子」の幻想的かつ雄大な響きは、別離する兄弟の今後を祈っているかのようで、美しくもあり、切なくもある。
-

-
KIRINJI
BUOYANCY
爽やか、かつハイテンポにアルバムの幕を開ける「夏の光」から、なんていう気持ちよさ......(恍惚)。自身8作目のアルバムは、"キリンジ節" と言っても良いメロディの魅力を全面的に展開。かつ、キリンジ作品史上でも一、二を争いそうな音作りの多彩さにも注目だ。口笛、ギター、鍵盤のアンサンブルから、三拍子への一瞬の変化がリズムにアクセントをつけ......。さらに、エコーするスティールパンにハミングとバンド・サウンドが加わる7分45秒の大作、「セレーナのセレナーデ」。1曲の中にどれだけたくさんの要素を織り込むんだと、感心しきり(笑)。1曲だけでもこうなのだから、アルバム全体にもどれだけ多くの仕掛けが施されているかは言わずもがな。心地よくも奥深いキリンジ・ポップス、超充実の仕上がりです!
-

-
KISHI BASHI
151A
全米iTunesチャート急上昇中の注目株である日系アーティスト。“151A”と書いて“一期一会”と読むデビュー・アルバムには、まさしく出会えたことに感謝したくなるような独特でいて壮大な音の世界観が描かれていた。本人がヴァイオリン奏者だけあり作品全体からはクラシックにも通じる深みを感じることができるが、それらを形作る要素は雑多なほどバラバラである。冒頭の「Intro/Pathos,Pathos」からエレクトロの匂いがしたかと思えば、Track.3「Bright Whites」では賛美歌のような明るいリズムとメロディのなかに奇妙な日本語まで含まれている。まるで彼の頭の中を覗き見ているかのような感覚すら覚える楽曲たちから、新たな癒しや刺激を受けること請け合いである。
-

-
kittone
独白
2020年に結成し、昨年HANA(Vo)、ヤマザキユウキ(Ba/Composer)の体制となった音楽ユニット、kittone。ヤマザキが曲を手掛けるようになって初の配信限定アルバムは"独白"と名付けられた。このタイトルは、誰かに向けてというよりも、形にしたい美しい音楽にだけ純粋に向き合って、音や言葉を紡いだ作品を象徴する言葉だったとヤマザキは語っている。人生で初めて作詞/作曲するにあたってまずはひとつの小説、物語を書き、その様々なシーンが曲となった。必然的に自己とも向き合う作業だったという『独白』をキャッチーにしているのが、軽やかでどこか懐かしさも覚える瀟洒なアレンジが効いたJ-POPサウンドと、ほのかにメランコリーを帯びた優しいHANAの歌声。読み聞かせるような音楽のタッチが、心に響くアルバムだ。
-

-
KITTY, DAISY & LEWIS
Superscope
ソウル、ブルース、ロックンロールといったルーツ・ミュージックを卓越したセンスで現代のポップ・ロックへと昇華するロンドン出身3兄弟の2年ぶりの新作。冒頭の「You're So Fine」から気怠く"いなたい"サウンドに惹きつけられる。軽妙な「Black Van」や3拍子のバラード「Love Me So」、疾走するロックンロール「Down OnMy Knees」など、曲の構造は単純でオーセンティックだが、古びたものに感じないのは、彼らが自分の血となり肉となっているサウンドを流行り廃り関係なく生み出しているからだろう。曲ごとに男女交互で歌うヴォーカルも楽しい。ハモンド・オルガンの音色もクールなインスト・ファンク・チューン「Broccoli Tempura」で締める、最高のダンス・ミュージック・アルバム。
-

-
Klan Aileen
Astroride
今まで、まったく知らなかったバンドなのだが……最高すぎる!MUDHONEYとか、BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUBとか、そんな名前が頭を過ぎる、最高のサイケデリック・ガレージ・ロックンロール。ダーティーでネチっこくて、だけどメロディやハーモニーのセンスは抜群。故に、聴き触りはポップ。資料によると、07年に鹿児島で結成、現在は東京を拠点に活動する3ピースらしいが、このアルバム自体は、ヴォーカル&ギターの松山 亮が“リズム演奏からミキシング、マスタリングまでもを一人で手掛けた”らしい。確かに、4曲目や10曲目なんかは孤独をこじらせたアシッド・フォークといった感じで、こんなものがひとつのベッドルームで純粋培養されていたのかと思うと……興奮と共に、末恐ろしい。
-

-
Klang Ruler
Space Age
Z世代有数のトラックメイカー yonkey(Vo)率いるKlang Rulerが初のフル・アルバム『Space Age』をリリース。レトロフューチャーをモチーフに、SF感を纏った壮大な楽曲群で構成される本作は、「クリーチャー」や「飛行少女」を筆頭に、スペイシーなシンセ・リフと幾何学的リズムが印象的なテクノ・ポップに懐かしさを覚える。一方、ツイン・ヴォーカルによる響きが心地よい「ジェネリックラブ2.0」、憂いを帯びた現実への破壊や逃避を示唆する「Crush!」や「Set Me Free」など、現代特有の視点で紡がれる詞世界には人間らしさが根底にあり、メタバースにもノスタルジーを感じさせる斬新なアプローチが際立つ。ここではないどこかへ旅立つ切符代わりの本作は、ヒトに代わってAIが音楽を創る時代でも聴き継がれる現代的且つ未来的アルバムだ。
-

-
V.A.
Kitsuné Maison 16 Sweet Sixteen Issue
エレクトロ系中心の仏レーベル、Kitsunéの名物コンピ『Kitsuné Maison』の最新版。筆者にとってKitsunéといえばニューレイヴ。今から7年ほど前、KLAXONSやDIGITALISMらを中心としたニューレイヴ・ムーヴメントが巻き起こったとき、Kitsunéは世界で最も重要なレーベルだった。嗅覚の鋭い音楽好きはみんなこのコンピをチェックしていたものだ。今は時代の中心にいるわけではないけれど、着実にいいものを届けるレーベルとして確固たる地位を築いている。今作は収録アーティストが全体的にしっとりと静謐な世界観を持っていて、"アガる"だけじゃない豊潤な時間を堪能できる。個人的にはJAWSとNIMMO AND THE GAUNTLETTSという2組の英バンドがツボ。
-

-
KLAXONS
Love Frequency
ニュー・レイヴ=インディー・ロックとダンス・ミュージックの融合の先駆者による4年ぶりの新作。メタル/ハードコア畑のプロデューサーとして知られるRoss Robinsonと組み、ロック色濃いサウンドに挑んだ前作から一転、今回、彼らが目指したのはダンス・ミュージック回帰。それはJames Murphy、Tom Rowlands(THE CHEMICAL BROTHERS)に加え、今をときめくErol Alkan、GORGON CITYも起用したプロデューサー陣の顔ぶれからも明らかだが、ポップ・アルバムを作ることをテーマにエレクトロなサウンドやR&B/ディスコの影響を大胆に取り入れ、強烈に"今"を印象づける曲の数々は、ひょっとしたら前作以上に物議を醸すかもしれない。メロウな作風とは裏腹にバンドの野心が窺える問題作だ。
-
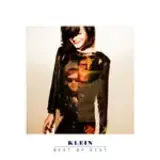
-
KLEIN
Beat By Beat
スペイン出身の3人組エレクトロ・ポップ・ユニット、KLEINのタワーレコード限定デビューEP。紅一点ヴォーカルであるMonica Vazquezのキュートな存在感もあってか、去年、日本でも話題になったNYのエレクトロ少女、COMPUTER MAGICと比較されることもあるようだが、KLEINはCOMPUTER MAGICに比べてよりダイナミックでストレート。3人組ということもあって、COMPTER MAGICのような宅録的メランコリーはないが、ロック・バンド的な爆発力は凄まじい。とにかく、アガる。Katy Perryなどの高性能アイドル・ポップのファンや、FOSTER THE PEOPLEやPASSION PITといったエレクトロ・ロック・バンドのファンにもアピールできる力を持っている。これはブレイクの可能性も大いにあると思う。
-

-
KNIFE PARTY
Abandon Ship
PENDULUMの中心メンバー、Rob SwireとGareth McGrillenが新たにスタートさせたユニット、KNIFE PARTY。これまでデジタル配信のみのリリースだった彼らがついにリリースしたデビュー・アルバム。テクノとダンス・ミュージックとロックを融合させ、ここ日本でも大歓迎されたPENDULUMの音楽性を受け継ぎながら、よりハウス/ダブステップに接近した印象。いわゆる歌もののTrack.10 「Superstar」他、EDMにもアプローチしながら、「EDM Trend Machine」なんて皮肉っぽいタイトルをつけてしまうところが彼ららしいというか何というか。そんなところも含め、持ち前のエッジィな感覚はまだまだ健在。無期限活動休止中のPENDULUMの不在を埋める存在として、彼らもまた歓迎されるに違いない。
-

-
KNIGHT SCHOOL
Revenger
いまや、“ブルックリン”という地名を聞いただけで、“おっ!”と反応する音楽ファンは相当数に昇るかも(笑)。そんな世界随一のミュージック・シティから、面白い素材がまたひとつ登場だ。今年のサマソニにも参戦するTHE DRUMS の「Let's Go Surfing」を、ローファイ感たっぷりにリミックスした2 人組、KNIGHT SCHOOL。Kevin AlvirとChris Ballaのデュオが鳴らすサウンドは、インディー・スピリットをビシビシ感じるザラついた質感。そして、ときにはシューゲイズな感覚もほのかに漂う轟音の中から響くメロディは、たまらなくスウィート!ユラユラと揺れるように響く声は、聴いているこっちの頭も自然とユラユラ揺れて、心地よく酩酊状態に……。夏の夕暮れに、ビール片手に聴いたら最高ですね(笑)。
-

-
KNOCK OUT MONKEY
HELIX
約2年半ぶりとなるノクモンのフル・アルバムは、彼らのライヴの楽しさが凝縮されたような作品となった。冒頭から、激しくも踊れるノリノリのラウドロック・ナンバーのTrack.1「Louder」で一気にテンションを上げ、さらに、夏フェスにぴったりのミクスチャーとなったTrack.2「Jump」、疾走感とメタリックなギターが冴え渡るTrack.3「1:48」と続く、かなり飛ばした内容だ。また、キック・ボクシングの森井洋介選手の入場テーマとなったTrack.4「Dog」は、格闘技のイメージにマッチした破壊力満点の楽曲。そして、激しい楽曲だけでなく、ポップに聴かせるTrack.6「cloud 9」や、ミドル・テンポでグルーヴ感のあるTrack.8「Wake Up」も交え、そのままライヴに使えそうなトラック・リストになっている。
-

-
kobore
HUG
切なさ混じる柔らかな春風のような、桜舞う季節にぴったりの爽やかなナンバーが並ぶ本作。ツー・ビートが爽快な「TONIGHT」で勢い良く駆け出すと、ストリングスがラストをドラマチックに彩る「もういちど生まれる」、ちとせみな(カネヨリマサル)とのツイン・ヴォーカルで魅せるkobore流シティ・ポップ「雨恋」では、アレンジャーを迎え新たな一面を見せる。そして「ひとりにしないでよね」で前作から続くキラキラとした瑞々しいサウンドを煌めかせると、最後は弾き語りとシンガロングが印象的な、ライヴハウスで聴きたい泥臭い青春ロック「この夜を抱きしめて」で締めくくった。暖かな季節の訪れに弾む心と、この曲たちをライヴで一緒に歌えることへのワクワク感がリンク。春のセンチメンタルな心も抱きしめたくなる温かさが心地いい。
-

-
kobore
Purple
これまで全面に打ち出してきた泥臭いバンド・サウンドから一転、koboreのメジャー2ndアルバムは多彩な楽器の音色を取り入れた、キャッチーでポップな1枚に仕上がった。クラップの打ち込みに乗せて、安藤太一の奏でるギターが、水面に乱反射する光のように美しく煌めく「ジェリーフィッシュ」をはじめ、そこにあるのは勢いや衝動ではなく、一曲一曲に細やかな情景を描く緻密なサウンド・プロダクションだ。"大事なものだけ盗まれて"とコロナ禍の物憂げな心情を吐露するような「微睡」、あっと言う間に過ぎていったふたりの時間に"ありがとう"を歌う「彗星」など、ミディアム・テンポの佳曲が目立つ。アルバムを締めくくる田中そら(Ba)作曲のバラード「きらきら」は、混沌の時代に託す希望か。
-

-
kobore
Orange
koboreの6曲入りEP『Orange』。これまでも楽曲やライヴを通して、自身の大事な想いを真摯に伝え続けてきた彼らだが、今作は特に日々を懸命に生きる人々の力になりそうな言葉が多い印象だ。先行公開された「夜空になりたくて」は、彼らの真骨頂と言える"夜"の匂いがするナンバーで、悩みや迷いを抱える聴き手に寄り添い、心の澱を流してくれるような温かさがある。そして、「灰になるまで」では"転びそうなら背中くらいは押したるわ"と、肩を組んで語り掛けてくれるような頼もしいワードに文字通り背中を押され、「SUNDAY」では"適当にやろうぜ"と、頑張りすぎな人の凝り固まった気持ちをほどくような優しさも見える。バンドの音楽に対する意志が窺える「OITEIKU」の疾走感も痛快だ。
-

-
kobore
風景になって
ギター・ロックの王道とも言える"koboreらしさ"を研ぎ澄まし、同時に新しい挑戦もはっきり見える意欲作。そして、4年前に出したデモ音源収録の「当たり前の日々に」をメジャー・デビューのタイミングで再録すると決めていたというのはとびきり粋なストーリーだし、何よりその曲が今作の中で一切の違和感なくハマっていることが、彼らのインディーズ5年間の歩みと心意気をすべて表している。新生koboreの楽曲群を楽しむのはもちろんだが、個人的にはやはり収録曲のうち最後に制作した「ボクタチノアシタ」からの「当たり前の日々に」の流れに注力して聴いてみてほしい。何年経ってもどこに立っても、koboreはなんにも変わらない。そのことが手に取るようにわかるから。
-

-
kobore
音楽の行方
精力的なツアーとライヴを重ねる府中発の4人組ギター・ロック・バンドの5曲入り1st EP。キャッチーな歌メロ、意志がまっすぐ伝わるストレートな歌詞、力いっぱいの演奏といった、彼らがもともと持っている旨味を生かした楽曲が揃った。表題曲は"自分らしさを失わず自分の音を鳴らそう"と少年少女へのエールを綴り、Track.2やTrack.3では何気ない平凡な日常の素晴らしさを歌う。ソングライターの佐藤 赳(Gt/Vo)の人生哲学が明確に前面に出た楽曲が多い中で、いい異彩を放つのがTrack.4。清涼感と憂いを併せ持つサウンドと、季節の移り変わりを背景にした感情の機微を昇華した歌詞が"躓いてもどこまでも行けるような気がした"と独り言のような一節を効果的に響かせている。
-

-
kobore
零になって
バンド初のフル・アルバムは、過去にリリースした"夜の3部作"から各1曲と、2018年初夏から秋にかけて開催したツアー中に制作した新曲の計10曲を収録。3年のバンドのキャリアだけでなく、未来に向けて成長をしていく過程をそのままパッケージしたアルバムになった。新曲はコード感が豊かなものが多く、佐藤 赳(Gt/Vo)が零す感傷的な心情をより繊細且つ鮮明に描き出している。特に「ナイトワンダー」はバンドにとっても新しいアプローチ。落ち着いたテンポとギミックが効いたギターのリフレインでグルーヴを作り出し、細部まで凝られたフレージングも楽曲の世界に深みをもたらした。アルバムの頭からラストまで、koboreを軸としたオムニバス映画のように楽曲がリンクしていくのも趣深い。
-

-
kobore
ヨル ヲ ムカエニ
1stミニ・アルバム『アケユク ヨル ニ』と1stシングル『アフレル』の流れを汲んで制作された2ndミニ・アルバム。夜明けを迎えたうえで夜に戻ってくるというタイトルのとおり、初期曲と新曲を収録したうえで、現段階でのkoboreの完成形を示す作品となった。着火力の高い約1分の楽曲で幕を開け、これまでのバンド人生を走馬灯のように見せる曲順もドラマチック。佐藤 赳(Gt/Vo)にとっての"音楽とは"が綴られている初期曲「テレキャスター」は、今の彼らがリアレンジしたことでさらに音も言葉もメッセージの威力を増したと言っていい。ラストを飾るタイトル・トラックは夜明けのイメージを与えるサウンドスケープが圧巻だ。衝動も余裕も併せ持つ彼らの音楽が世間を席巻するのは時間の問題かもしれない。
-

-
kobore
アフレル
府中発の4ピース・ギター・ロック・バンド、koboreにとって初のシングル。3分弱のショート・チューン「君にとって」、ミディアム・バラード「僕の全部」、初期曲「声」の再録バージョンを収録。三者三様の3曲はバンドのポテンシャルを十分にアピールしてくれるが、全曲に共通しているのは、"koboreはなぜ歌うのか"に迫るような内容であること、そのメッセージを強調するためにシンプルな曲構成が採用されていること、そして歌詞の起伏を体現するようにドラマチックなサウンドが鳴らされていること。脇目も振らず、このバンドの核にある"伝える"という点を研ぎ澄ましてみせた今回のシングルは、ファンはもちろん、これからkoboreを知っていく人にもおすすめしたい作品だ。
-

-
kobore
アケユク ヨル ニ
東京・府中発の4ピース・バンド、koboreにとって初の全国流通盤。"今を歌うバンド"としてのバンドの在り方をそのまま託した「幸せ」を1曲目に配置することによって、そのあとに続く曲で歌われるモヤモヤとした葛藤も、少しの意地や強がりも、拭えない情けなさも、全部ひっくるめて"幸せだ生きてる"と大きく肯定していく眩しさたるや。歌詞の内容は案外ポジティヴとは言いがたいが、爽快なほどに直球ストレートなギター・ロック・サウンドは後ろを振り返るためでなく、前に突き進むためだけに絶えず鳴らされている。平均年齢20歳の彼らが今しか鳴らせない音楽に真っ向から挑んでいる印象だが、このバンドはこれから、どのように歳を重ねていくのだろうか。キャンバスはまだ白い。
-
-
KODALINE
In A Perfect World
アイルランド出身の4人組、KODALINEのデビュー・アルバム。叙情的で壮大なメロディが何よりも特徴的なバラード・ロックで、音楽性的にCOLDPLAYと比較されることは避けられないだろう。だが、ここ数年、COLDPLAYが音楽的実験を推し進めながら重量感のある作品を作り続けているのに対し、このKODALINEのデビュー作にあるのは、とても瑞々しく、繊細なメロディの輝きである。ある意味、COLDPLAYが失ってしまったものがここにあると言ってもいい。タイトルの『In A Perfect World』とは皮肉か、願望かはわからないが、このどうしようもない日常にも輝くものはあるのだと、このバンドが描く美しいメロディは伝えているようだ。今、UKロックが再び日の目を浴びているが、こういうバンドの存在も必要なのだ。
-

-
Koji Nakamura
Masterpeace
3/25のBEADY EYEのゲスト・アクトとしてその全貌をファンの前に現したナカコー。そのレパートリーにスーパーカーがあったように、iLLよりLAMAより、スーパーカーでのナカコー好きとしては待ちに待った彼のフィロソフィが詰まった新プロジェクトだ。プログラミングやシンセ、ギター、ベースなど全てのインストゥルメントを彼が操るオケは有機的なサウンドスケープを描き、そこには最早、生音と打ち込みの区別はない。特筆すべきは、リリックをLEO今井や脚本家の永津愛子ら、6人の言葉の達人に任せていること。意味よりインスタレーションの如く配置された言葉が、あの低体温かつアンニュイな声で、感情と視覚が同時に起ち上がるニュアンスは無二だ。
-

-
THE KOOKS
10 Tracks To Echo In The Dark
独特のグルーヴ感とポップ・センスで、根強い人気を誇るTHE KOOKS。6枚目のアルバムとなる今作は、80年代インディー・バンドのテイストを取り込んだちょっぴりレトロな雰囲気も漂う、遊び心のあるアルバムとなった。全体的に、シンセ・サウンドを大胆に取り入れたポップ・サウンドを展開。前作『Let's Go Sunshine』で表現した王道感のあるギター・ロックを、ポップなメロディで中和しながら、4thアルバム『Listen』とはまた違ったアプローチで、THE KOOKS流のダンス・ナンバーを追求した意欲作だ。結成15年を超えてなお、まだまだこんなにも爽やかでフレッシュなサウンドを生み出せる、THE KOOKSというバンドのピュアな魅力に触れることができた気がする。
-

-
THE KOOKS
Let's Go Sunshine
R&Bやダンス・ミュージックにアプローチした前作『Listen』は賛否両論を巻き起こしたが、ファンには美メロとザ・ブリティッシュ・バンドな今作の方が好まれるのかもしれない。哀感が漂い日本人受けするメロディの「All The Time」や、ノーザン・ソウル風味のビッグ・ソングがどこかOASISも想起させる「Kids」、THE BEATLES中期的なサイケデリックな音像の「Tesco Disco」、ストリングスとギター・アンサンブルで編み上げていく壮大な「Swing Low」など、2018年において再びギター・バンドならではの響きや構築の奥深さを実感できる仕上がりだ。サブスクで「Naive」が上位に位置し続けているという本国イギリスでの状況を勘案すると、モダン・クラシックなブリティッシュ・アルバムが今なお必要とされているのかもしれない。
-

-
THE KOOKS
The Best Of...So Far
UKロック・バンド、THE KOOKSのデビュー10周年を記念してリリースされる初のベスト盤。たびたび来日を果たし、日本でも人気の彼らの代表曲「Naive」から始まり「Always Where I Need To Be」、「She Moves In Her Own Way」といった全英チャート上位に入った曲を中心に、彼らが10年間でリリースしてきた楽曲からのチョイスと新曲2曲を収録している。曲の良さはもちろんのこと、UKロックの歴史を継承したサウンドがたまらなくカッコいい。ロカビリー調の「Sofa Song」など、ディストーションやリヴァーブ頼みじゃない、生音に近い本物のロック・サウンドがここにある。新曲「Be Who You Are」、「Broken Vow」はライヴで人気になりそう。日本盤CDにはデモ音源2曲をボーナス・トラックとして収録しているところも長年のファンにとっては嬉しいプレゼントだ。
-

-
Kotone(天神子兎音)
Autonomy
昨年、『PUNISHMENT』でメジャー・デビューを果たした神様系VTuber、Kotone(天神子兎音)の2ndシングル。表題曲は鋭利なシンセが高速で駆け抜けるデジタル・ハードコアなトラックにのせて、Kotoneの凛としたヴォーカルが自身の存在証明を問い掛ける。c/wの「今回の騒動につきまして。」は、ネット上の過激行動が炎上したことによる謝罪をテーマにしたこのご時世らしいナンバー。リズム隊に堀江晶太(Ba/PENGUIN RESEARCH)とゆーまお(Dr/ヒトリエ)が参加し、テクニカルなプレイが炸裂するダンサブルなロック・ナンバーに、こぶしの効いた歌唱が映える。楽曲ごとに表情を変え、どんなジャンルも乗りこなすKotoneのロックでパワフルな一面がフィーチャーされた1枚。
-

-
kOTOnoha
明日から借りた言葉
その佇まいから、朴訥としたギター・ロック・バンドなのかと思いきや、今作『明日から借りた言葉』の出だし「漂う」から日本語ラップが放たれて、意表を突かれた。さらに、そのままいくのかと思ったら、90年代のエモを彷彿とさせるような激情も顔をのぞかせる。エモ、ヒップホップ、ギター・ロック、ハードコアなど、自分たちが熱くなれる音楽を取り入れて、"今"のものへと昇華した独自の楽曲の数々。昨今ありがちな、しょっぱなから"目的"が見える音楽ではなく、言葉と音そのものが剝き出しで見えてくる純血種の音楽だと思う。歌詞のひとつひとつも、正直に書かれたことが伝わってきて、心を掴まれる。ロック・バンドの明日までも信じられるような気持ちになる1枚だ。
-
-
THE KOXX
Access OK
韓国出身といえばK-POPが日本でも社会現象になっているが、バンド・シーンもハイ・レベル。韓国ではすでにチケットが入手困難となっており、日本でもNANO-MUGEN CIRCUITやSUMMER SONIC 2011に出演し注目を集めている5ピース・バンド、THE KOXX。エモーショナルなギターとシンセが絡み合う踊れるナンバーに歯切れの良い語感が新鮮。ほとばしる衝動と卓越したセンスの狭間に見え隠れする知性が光るサウンドの重なりも面白い。11月から来日ツアーがあるとの情報も。フロアで踊らない手はない! それにしても、台湾の透明雑誌や韓国のTHE KOXXが現すように、アジアの国々にはまだ見ぬ良質な音がたくさんあるに違いない。
-

-
KOZUMI
アンデルセン
長野出身の同級生で結成された、KOZUMI。伊東 潤(Vo/Gt)ときたはらさき(Vo/Dr)の男女ヴォーカルによる4ピース・バンドで、つんのめった感情と、ふたりの歌のハーモニーや、フーガ的に追いかけ合うメロディの疾走感をエンジンに、駆け抜けていく曲が揃う。霧を裂くように、涙を振り払うように、叫んでも叫んでも吐き出せないものを、身体の底から絞り出すようにビートを加速させる。今は、それが止められないんだと言わんばかりの勢いだ。溢れるのは悲しみなのか、喜びなのか。自分の心を測るリトマス紙的な歌でもある。今作は4人のデビュー・ミニ・アルバムで、プロデューサー兼アレンジャーを"それでも世界が続くなら"の篠塚将行が担当した。迸る熱量をパッケージするプロデューサーとしては適役だろう。
-

-
KREWELLA
Get Wet
「Alive」の大ヒットをきっかけに現在、EDMシーンで注目されているシカゴのトリオ、KREWELLA待望のデビュー・アルバム。ヴォーカルを担当するJahanとYasmineのYousaf姉妹とDJ/プロデューサー、Rain Manからなる彼らはEDM系のフェスでヘッドライナーを務める人気者。ポップにハジける楽曲をアピールしつつ、ブロステップのエグさを刺激的に効かせたサウンドももちろん、グループの顔としてちょっとワルッぽい姉妹をフロントに立てた打ち出し方も彼らが歓迎された理由のひとつだろう。USダンス・チャートNo.1に加え、全米チャートでも8位に食い込む大健闘。Track.6「Dancing With The Devil」にFALL OUT BOYのPatrick StumpとBLINK-182のTravis Barkerがゲスト参加している。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号


























