DISC REVIEW
A
-

-
Aqilla
shave off
"ロック"という言葉だけでは到底言い表せない緻密な構成とアレンジ、独特なニュアンスによって展開される12曲――それでもこれだけまっすぐなロックに聴こえてしまうのは、彼女の覚悟や想いがすべての曲に刻まれているからなのだろう。デビューから2年の軌跡をつめ込んだ1stアルバムは、彼女のスタートとも言える1枚となった。どの曲もリード曲になり得るほどのポテンシャルを持ち、"shave off"(削ぎ落とす)というタイトル通り、ブラッシュアップされた彼女がその曲たちを行き来する。極限まで振り切った歌声には嘘偽りがなく、だからこそとても愛おしい。自信と覚悟がみなぎる今作には、Aqillaの本質そのものが表れた。恐れなくただひたすらに楽しむ様子も印象的。ここからまた彼女のロック人生が始まる。
-

-
aquarifa
マーニの秘密
月の運行や満ち欠け司りながらも常に狼に追いかけられているというリスクを抱えている、兎の姿をした北欧神話の美しき月の神"マーニ"をタイトルに選んだ4ピース・バンド、aquarifaの3rdミニ・アルバム。バンドのキー・ヴィジュアルに"月"を掲げる彼女たちにぴったりだ。ONE OK ROCKやMAN WITH A MISSIONを手がけるakkin、堂島孝平や吉澤嘉代子を手がける石崎光というカラーの違うふたりをサウンド・プロデューサーに迎えた今作は、捕まえようとすると笑いながらするりと逃げてしまうような軽やかさを見せつける「崩壊リカバリー」やリリカルな演奏が胸を打つ「溶けない嘘」、ライヴではすでに定番曲となっている「321」など、どの曲も遠くまで届いていきそうな可能性が込められている。
-

-
aquarifa
月明かりのせいにして
昨年はSUMMER SONICやMINAMI WHEELへも出演し、ファンを増やしているバンド、aquarifa(アカリファ)の2作目のミニ・アルバム。紅一点Vo.岩田真知のチャイルディッシュで、メランコリーを帯びた不思議なトーンの歌声と、アグレッシヴで、重厚なギター・サウンドとの組み合わせは、デコボコでトゥー・マッチな感覚がある。どっと押し寄せてくる感情の荒波や、激しく複雑にせめぎ合った感情の渦にも、すっと身を委ねて、淡い夢のなかをふわりとたゆたうように歌う。歌に宿る、その静けさや凛とした佇まいが、深く心を揺さぶる。そしてリスナーの心をとらえた声に続くようにして、ノイジーで力強いサウンドが、余計な思いを洗い流していく。甘美な余韻と、いつ引っかかれたのか少しばかり痛みや切なさといった傷跡も残す、静謐で鋭いアルバムだ。
-

-
ARCA
Xen
プロデューサーとしてKanye WestやFKA TWIGSの曲を手掛け、自主リリースしたミックス・テープ『&&&&&』で何者!?とエレクトロ・ファンの心をざわめかせた、ARCA。ベネズエラ出身で現在はロンドンを拠点とする24歳、Alejandro GhersiによるARCAがMUTEよりデビュー・アルバム『Xen』をリリース。ベースには、『&&&&&』での抽象的で、インダストリアル風のひんやりとした感覚がある。一方で、眠っていた記憶を掘り返された後味もある。うっとりと触れたくなる美しさと、居心地の悪さが同時に襲ってくる、その得も言われない感覚は何かともう1度この音世界に分け入っていく。そんな"今の何?"という音の奇妙な影にとりつかれてしまう。どこか"見るなのタブー"にも似た、解き明かしたら2度と味わえない何かを持った音楽。
-

-
ARCADE FIRE
We
RADIOHEADとの長年のコラボレーションで知られるNigel Godrichを共同プロデューサーに迎えた、約5年ぶりのニュー・アルバム。"I"と"We"の2部構成からなり、前半ではソーシャル・メディアや政治的対立、パンデミックなどによって生じた孤立への恐れや寂しさを、内省的でどこか冷ややかなサウンドで表現する。後半では他者との繋がりによって広がる、希望に満ちた世界をドラマチックに奏でていて、強烈なカタルシスを生む「The Lightning I, II」は圧巻。「Unconditional II (Race And Religion)」での、バンドの影響元のひとつと言えるPeter Gabrielの客演も絶妙だ。彼らなりのロック・オペラで現代を描き出す傑作。
-

-
ARCADE FIRE
Everything Now
2ndトラック「Everything Now」がローンチされた際には、まさにDAFT PUNKのThomas Bangalterのプロデュース色が強いとか、まるでABBAみたいとか、いずれにせよポップで明るいイメージもなくはなかった。が、彼ら自身のSNSでフェイク・ニュースを流していたことは(それこそ)すべて連動していた。すべての物事に今すぐアクセスでき、手に入る状況だけど、もはやリアルかフェイクか判別できない――この世界的な現象をフロントマンのWin Butlerは郊外の閉塞した少年が鳴らした=かの『The Suburbs』でのインディー・ポップも、Thomasを迎えた全世界的にもはやベタなトレンドであるエレクトロ・ファンクも折衷して見せたように思える。啓蒙的なわけじゃなく、聴いて"今を生きている"とは何か? を経験させる、そんなアルバムだ。
-

-
ARCHAIC RAG STORE
EXPLODE
2013年3月に結成、2014年2月に現在のラインナップになった東京の4人組ロック・バンドが前作から9ヶ月ぶりにリリースする2ndミニ・アルバム。ギター2本とベース、ドラムというオーソドックスな編成で演奏した、いわゆる歌モノのロック・ナンバーは、その範疇からはみ出しはしないものの、ちょっと不思議な魅力がある。絶妙に転調を重ねるオープニングの「プライマル」を始め、ヒリヒリとしたロック・サウンドの中で、まるで隠し味のように"洗練"を利かせているところが面白い。その"洗練"も最近流行りのシティ・ポップ系とは一線を画するものというところがいいじゃないか。易々とトレンドに与するような連中じゃないらしい。王道と思わせ、そんな見方をするっとかわすしなやかさがいい。
-

-
Archaique Smile
On The Eternal Boundary
2010年の結成以来、東京都内を拠点に活動を続けるインストゥルメンタル・バンドの記念すべき1stアルバム。言葉のいらないインスト・バンドの強みを活かし、今年はカナダのバンドMILANKUとの共演ツアーも成功させている彼ら。Track.1「falling to the sky」からラストの「faint light」まで、リヴァーブのかかったトレモロ・ギターの美しい音色が印象的だ。ヘッドフォンをして聴いていると、まるで以前からずっと頭の中で鳴っていたかのように感じてくる音像は、幼少期の記憶を辿る旅のようでどこか懐かしい。静寂から轟音へと変化していく曲の後半で聴かせるノイズ・ギターも険がなく、何故か親しみ易く柔和だ。バンド名の語源"アルカイク・スマイル(無表情にも拘らず口元に笑みをたたえた様子)"がバンドの音楽性を見事に表している。
-

-
ARCTIC MONKEYS
The Car
月面のホテルをテーマにした前作『Tranquility Base Hotel & Casino』を経た、約4年ぶり7枚目のスタジオ・アルバム。きらびやかなストリングス、ファンキーなギターやコンガが踊るオーガニックなサウンドの上で、Alex Turnerがファルセットを多用した芳醇なヴォーカルを披露する、渋さと甘さ、レトロとモダンが調和した作品だ。余白を巧みに用いて緻密に計算された音像は豪華だが決して派手ではなく、工業製品のような、地に足のついた機能的な美しさを放っている。不穏なシンセ・ベースが響くTrack.3や、大々的なストリングスでクライマックスを飾るTrack.10といった楽曲の、いい意味での違和感も心地よい。上質な革靴のように、聴けば聴くほど身体になじんでくる作品だ。
-

-
ariel makes gloomy
oxymoron
前作『carbonium』から約8ヶ月ぶりとなるariel makes gloomyの2nd EP。自身の活動形態を"プロジェクト"と称して、ベールに包まれた部分も多い音楽集団だが、全国流通としては2枚目となる今作『oxymoron』を聴いても、やはりそのポップ・センスは抜群だと思った。もっと言えば、ポスト・ロック的で予測不能なサウンドの根底にあるポップ強度は明らかに前作よりワンランク・アップしている。自分を曝け出しながら、言いたいことはひとつもないと煙に巻く「focal point」、偶然と必然の間で揺れる日常に虚無感を抱く「gradation」など、胸にある消えない矛盾を滑らかな筆致で捉えた歌たちを総称して、"矛盾した表現"を意味する"oxymoron"と名付けたところまですべてが美しい。
-

-
ariel makes gloomy
carbonium
メンバー全員がメイン・コンポーザーやプレイヤーとしても活躍する4人組プロジェクト、ariel makes gloomyがリリースする初の全国流通盤。炭素(カーボン)を意味するタイトルは、これまでに制作してきた楽曲を元素記号として数えたときに6番目だから、という意味だという。疾走感溢れるバンド・サウンドにピコピコと鳴る電子音がループするリード曲「slowmotion」を始め、繰り返す日常に横たわる後悔が綴られた繊細なポップ・ソング「infinite refrain」、スペイシーなサウンドスケープが高揚感を生む「シンクロニシティ」など、色彩豊かな音たちが飛び交う全4曲を収録。過ぎゆく時間の儚さや消えない孤独が描かれた歌詞には、ヴォーカル イシタミのピュアな歌声がよく似合う。
-

-
Ariel Pink
Pom Pom
ARIEL PINK'S HAUNTED GRAFFITIiではなくAriel Pinkソロ名義としては初のアルバム。膨大な数のローファイ宅録音源を作り続けていたところをANIMAL COLLECTIVEに見出され、2009年の『Before Today』で一躍インディー・シーンの寵児となり、後のチル・ウェイヴ勢などに大きな影響を与える"2010年代の音"の礎を築いたAriel Pink。このタイミングでのソロ名義とは、やはり『Before Today』と『Mature Themes』の2作で確立したHAUNTED GRAFFITIの"存在意義"にAriel自身が重荷を感じていたのかもしれない。故に本作は全17曲2枚組、各曲の完成度は高いが、しかし全体的には初期を思わせるやりたい放題盤である。70年代ポップスにハード・ロックにポスト・パンクにニュー・ウェーヴ......すべてを繋ぎ合わせ、時代のゴミ箱を宝箱に変えてしまう、その錬金術はやはり圧倒的。
-

-
ARIEL PINK'S HAUNTED GRAFFITI
Before Today
USインディのカルト・アイドルと言われるARIEL PINK。かつては知る人ぞ知る存在であった彼がGIRLSやANIMAL COLLECTIVEに認められついに今作でUKの名門レーベル4AD と契約を結びデビュー。ローファイ・サウンドと基本としながらもARIEL PINKを中心に結成された彼らのサウンドは明らかにそのカテゴリーをはみ出していて、とにかく摩訶不思議。ディスコやAOR風の楽曲もあれば、普通にシンプルなポップナンバーもあったり。ただ曲の展開は読めず。「L'estat」という楽曲はポップながら捉え所のない空間を漂うような曲で初めて聴いた時は度肝抜かされた。ただこの散漫と捉えられてしまうかもしれないこの作品のドラマティックさにはとても惹き付けられる。
-

-
Arika
LENS
圧倒的な世界観を構築した初作品からたったの4ヶ月で早くも2nd EPが到着。悲痛さを帯びた夏吉ゆうこのハイトーン・ヴォイスに胸を締めつけられる「蝙蝠」のような、前作で印象的だったダウナーなエレクトロ・サウンドを中心に置きながらも、ドラムンベースが闇の中を疾駆するイメージをかき立てる、ハードな「アンリアル」や、まどろみと踊るシティ・ポップ的な雰囲気の「hypno blue」といった、自身たちの音楽性を拡張する全4曲を収録している。特にラストを飾る「遺愛」は、柔らかな光に包まれるような感覚を覚えるスロー・ナンバーで、これまでふたりが提示してきた楽曲群とは真逆と言っても過言ではない仕上がりに。だがしかし、その中にもひと匙分の不穏さを入れてくるのが、このユニットらしいポイントでもあるだろう。
-

-
Arika
1440
声優の夏吉ゆうこ(Vo)と、コンポーザー/ギタリストの大和による音楽ユニットの1st EP。朝、昼、夕方、夜と1日の流れを描いた全4曲はダウナーで、アンビエントで、アトモスフェリックなエレクトロ・サウンドが大半を占めていて、ポップなキャラソンやヘヴィでラウドなロック・ナンバーといった、これまでふたりが携わってきたものとは正反対と言っても過言ではないほど、異なる表情を持った楽曲たちが収録されている。中でも、声楽を幼い頃から学んできた夏吉が、「からたち」のラストで聴かせるハイトーンは圧巻のひと言。今はジャンルを定めずに楽曲を作っていきたいと話していることもあり、ここからさらなる広がりを見せていくと思われるが、その出発点として強烈な個性と圧倒的な存在感を提示した1枚になった。
-

-
ARIZONA
VOLCANO
wash?の河崎雅光をプロデューサーに迎え、2ndミニ・アルバム『VOLCANO』をリリースした4人組の骨太ガレージ・ロック・バンド ARIZONA。初めてメンバー以外の意見を取り入れたという今作は、タイトルどおり沸々と湧き上がってくる抑えきれない感情を大噴火させた1枚となっている。怒りや憤りをイシイマコト(Vo/Gt)のがなり声に乗せた攻撃的な楽曲が多いなか、Track.3「Hello&Goodbye」では、"人と人との繋がりを大切にしたい"という穏やかな気持ち表現した新しい一面を聴かせている。初めて自分と向き合って生み出したという今作は、前作よりも確実に進化しているはず。やんちゃなARIZONAがどんなふうに成長していくのか、今から楽しみでしかたがない。
-

-
arko lemming
S P A C E
"OUTER"と"INNER"の2枚に分けることによって、開かれたメロディや曲調と、どちらかといえば内にこもるエネルギーを持った曲調がわかりやすい印象のこのアルバム。ジャンルの振り幅と新鮮味では"OUTER"収録の「ニューニュー」でのポップスとしての強度のあるサビメロやアーバン・テイストなリズムのアプローチ、無機的なビートを持つ「Avéc」などに新生面が。"INNER"もエッジーでありながら、前作での4リズムのバンド感とは違い、クラウトロック的な反復が冷徹な「NO」、ダークな浮遊感がある「weather report」などいずれも新しいアプローチだ。また"OUTER"の「dual-O」と"INNER"の「dual-I」は別曲ながら、同時再生すると「dual-TRACK」("INNER"のTrack.1)になることも本作のテーマを象徴しているし、試みとして楽しい。
-

-
arko lemming
PLANKTON
ヴォーカル、ギター、ベース、ドラムス、すべて有島コレスケ、以上! 1人バンドによる1人グルーヴと彼が好む音像が、宙ぶらりんな状態にあった心情と相まって、バンド・サウンドでありつつパーソナルなニュアンスを放つのが最大の魅力になっている。ポップなメロディとアップテンポにも関わらず苛立ちが炙りだされるTrack.2「空けたもの(うつけたもの)」、ダルいようでいて物事の芯を突くような歌声の個性がわかるTrack.4「灯台」、更新された現代のグランジと言えそうなTrack.5「Pale Blue Dot」、単に息苦しいではすまされない状況にある今を映しつつ、淡々と現実を射るようなTrack.8「稀ないもの(すくないもの)」など全9曲。曖昧な不安を描くことでむしろ自分にとって大事なことが照射される、そんな作品。
-

-
ARLINGTON
A Walk Through Jackson County
南カリフォルニア・オルタナティヴ・ロックを掲げる3人組、ARLINGTONが奏でるのは、ポスト・ハードコアというRise Recordsのイメージを、いい意味で裏切るモダンなガレージ・ロックだ。メンバー自ら影響を認めるJack White、THE STROKES、KINGS OF LEONを思わせる演奏やフレーズが、曲によっては出すぎるきらいはあるものの、どの曲からも感じられる人懐っこいポップ感覚と、音数を削ぎ落としながら閃きに満ちた演奏は、なかなか魅力的。もちろん、このままでも十分に聴き応えはあるが、楽曲の根底にあるブルースやR&Bの影響がさらに滲み出てくれば、ハスキーなヴォーカルと相まって彼らならではと言えるユニークさも際立ちそうだ。この機会に名前を覚えておいてもきっと損はない。
-
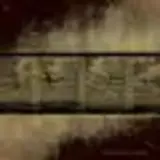
-
ARMS AND SLEEPERS
Matador
アメリカ本国では既に高い音楽的評価を獲得しているARMS AND SLEEPERSのセカンド・アルバム。柔らかいダウンビートとアンビエントな上音が織り成す緻密なサウンド・プロダクションと、多くのゲスト・ヴォーカルの切なくも美しい歌声が、深いストーリー性を生み出している。その幻想的な世界観は、トリップホップ勢やSigur Rosといったアーティストと同じ系譜にある。チェロやアコーディオン、さらにはオルゴールまで各楽曲に散りばめられた様々なアコースティック楽器が温もりを加える。この種の音楽には、正直もう新鮮味を感じない作品も多いのだが、このアルバムには自然と涙腺が緩んでしまう何かがある。押し付けがましさもなく、すっきりと聴きとおせる構成も素晴らしい。
-

-
arrival art
心海遊泳
たった4文字のタイトルで、ここまで見事に音楽性を表した作品もそうそうないだろう。渋谷を拠点に活動中の3ピース・バンド、arrival artの1年ぶりのミニ・アルバムはまさに"心海遊泳"。目を瞑ってじっと耳を傾けていると、楽曲たちがゆらゆらと泳ぎながら悠然と心の奥底へと入ってくる。胸にスッと沁み入る情感溢れるバラードから、エッジの利いたギター・ロック、ストレートなラヴ・ソングまで、色はそれぞれ異なるものの、坪本伸作(Vo/Gt)による甘く優しいヴォーカルが作品としての統一性を持たせている。各曲に詰め込まれたリアルな風景が印象深く、ついついリピートしてしまう。特にTrack.3「糸と意図」の突飛なサビにはなんとも言えない中毒性があり、耳をついて離れない。
-

-
ARTIFACT OF INSTANT
Recoil
当たり前だが、いくら音楽が好きだろうと四六時中、耳にイヤホンを挿しているわけにはいかないし、終演後にはライヴハウスを出なければならない。そのため瞬発的な快楽や上辺だけの一体感にはかえって虚しさを感じてしまうし、互いの何もかもを曝し合い、"この歌が終わったあと"も各自で闘っていくための勇気を得られるような音楽に強く惹かれる(というか、あなただってそうでしょ?)。このARTIFACT OF INSTANTはまさにそういうことをやってきたバンドだが、本作でいよいよその真価を発揮し始めたようだ。希望、憤り、やるせなさ、愛情。原色のままの感情は、あなたの胸に深く突き刺さることだろう。だから今、あなたの意志で彼らに出会ってほしいと心から思う。(蜂須賀 ちなみ)
宮崎を拠点に活動する男女混成4人組ギター・ロック・バンド、ARTIFACT OF INSTANTが1年ぶりにリリースする3枚目のミニ・アルバム。人間の闇を見据え、そこに溜まる膿をえぐるように楽曲を生み出す飯干達郎(Vo/Gt)の退廃的な世界観は、今作でさらに深みへと達した。殺伐としたコミュニケーション、生きることと同義の諦念。どこまでも広がる絶望の果てで光を見つけるまでの物語が『Recoil』というアルバムだ。虚無的な愛を綴るTrack.1「From Jacqueline」から、本当の意味で愛の尊さに気づくTrack.7「Dear Jacqueline」へ。人は人に傷つけられて、人の優しさに気づく、そんな矛盾に満ちた真理をアルバム・タイトルの"Recoil(=銃を撃つときに起こる"反動")"という言葉が端的に表している。奈良のMORGスタジオで6日間におよぶ合宿を行い完成させたという、研ぎ澄まされた音にも注目。
-

-
ARTIFACT OF INSTANT
モラトリアム
宮崎出身の4人組、ARTIFACT OF INSTANTの1stミニ・アルバム。静と動を行き来する構築的なバンド・アンサンブルの上をまっすぐに流れるエモーショナルなメロディと歌は、おそらく実体験をもとにしたであろう"別れ"や"喪失感"、"後悔"、そしてその先にある"再生"と"旅立ち"をモチーフに、どこまでもパーソナルな心象を、その音の中に描き出す。サウンドも詞も、すべてがあまりに赤裸々で、どこか痛々しく、でも切実。まるで赤の他人のフォト・アルバムでも見せられているかのような気分になる、そのぐらい剥き出しの作品である。しかしだからこそ、"音"にすることでしか昇華できない想いというものが、この世界にあることを教えてくれる音楽でもある。デビュー当初のLOST IN TIMEを思い出した。
-

-
ART-SCHOOL
Cemetery Gates
2000年のデビュー以来全キャリアの中からシングル表題以外の曲(アルバム曲含む)で、ファン投票を参考にメンバーの思い入れとともに選曲。いや、これはむしろART-SCHOOLの本質を表したベスト盤と言えるのではないだろうか。今改めて2001年の「ニーナの為に」のグランジーで青く研ぎ澄まされたテイクの鋭さに驚愕し、廃盤になった2枚組ミニ・アルバム『SWAN SONG』収録曲が今回、所収されたことの意義も大きい。それはその時代、RADIOHEADかART-SCHOOLか? と思うほど、感情任せではない透徹した絶望を表現していた曲群だからだ。他にもピアノが印象的で彼らの曲の中では素朴な美しさがある「LUCY」や、16ビートとファンク・テイストでセンシュアルな「その指で」など、改めて曲の良さと個性が味わえる。
-

-
ART-SCHOOL
Hello darkness, my dear friend
初期のギター・ポップやネオアコの匂い、純化されたグランジなどガラスのように繊細なART-SCHOOLが好きだった人にとって、現メンバーのスキルでそのセンスが表現された本作は、居心地のいい場所のように感じられるはずだ。アルペジオや空間系のギター・サウンドが織りなす透明な空気感をもった音像がいい。愛情に包まれていた幼い日の記憶と刹那的な感情が交差するリリックはいつもどおりなのだが、木下の丁寧なヴォーカルが、穏やかに見守る視点すら感じさせるのが新しい。「R.I.P」では"笑われた分だけ強くなるなんて嘘だ"という珍しく直截な表現をとっていることは快哉を上げたい。そして何より、音楽として美しく高い純度を誇るメロディ、それを活かすメンバーの音楽家としての誠意にも心が満たされる。
-

-
ART-SCHOOL
YOU
木下理樹は"このアルバムに今までの音楽キャリアの全てを詰め込んだ"と言う。それゆえだろうか、この11曲の新曲たちの随所で、ありとあらゆる時代のART-SCHOOLの姿や表情、熱量を思い起こさせた。オリジナル・メンバーは木下理樹だけだが、ART-SCHOOLというバンドは、バンドの歴史を全て背負い、今もこうして音を鳴らしている。その時その時でいちばん美しいと思うものを妥協することなく追求し、自分たちの鳴らす音を信じてきたバンドだからこそ、この歪で、清く柔らかなぬくもりのある音色を手に入れたのだ。サウンドで魅せた『BABY ACID BABY』『The Alchemist』と比較して、今作は歌を映えさせるアレンジやコーラス・ワークも特徴的。繊細なヴォーカルとシンプルで耽美なメロディを堪能する。
-

-
ART-SCHOOL
The Alchemist
中尾憲太郎(Ba)、藤田勇(Dr/MO'SOME TONRBENDER)という最強のサポートを得、Steve Albiniのスタジオで録音したCLOUD NOTHINGSへの日本からの回答(いや、それ以上だったかも)とも取れた前作『BABY ACID BABY』から約7ヶ月。今回は益子樹とのタッグで、轟音よりむしろ透明感のあるギター・アンサンブルや各楽器のクリアな粒立ちに耳を奪われる。特にTrack.1「Helpless」でのエロティックな16ビートのグルーヴは完全な新境地。が、木下理樹のもう1つのバンド、killing Boyで表現されるファンクネスともまた違う。加えて喉のトラブルを乗り越えた木下のタフで自由になったヴォーカリゼーション、THE SMITHSやTHE CUREの上澄みではなく深い部分での共通項など、さらなる進化を実感できるミニ・アルバム。
-
-
ART-SCHOOL
BABY ACID BABY
Ki/oon Musicへの移籍第1弾であり新体制後初のリリース、NIRVANAなどを手掛けたSteve Albini主宰のシカゴにあるスタジオでGreg Normanを迎えレコーディング、サポート・メンバーとして中尾憲太郎 (Ba)と藤田 勇 (Dr)が参加......と様々なトピックが目白押しの今作は、これまでのART-SCHOOLの作品の中でも抜群の鮮度と生々しさを孕んだ作品だ。4人が生み出す音はひとつひとつが立体的で、その透明感はガラス細工さながら。その音の良さがバンドの空気を更に大きく、強くする。特に木下理樹と戸高賢史の奏でるギターは鋭く美しく溶け合い、聴き手の心に飛び込み心地良く広がる。優しさと激しさ、緊張感と快楽。ART-SCHOOLが表現し続けてきた世界の究極と言っても過言ではない。
-

-
ART-SCHOOL
Anesthesia
<悲しいくらい抱き合って 朝が来たらまた僕ら一人になってしまったんだ――>。ラストナンバー「Loved」は、そんな一節でエンディングを迎える。抱き合う瞬間は甘美、それが過ぎればまた孤独に……。至福と絶望が交差するその場面は、ARTSCHOOLの音楽の真髄をまさに物語る。オープニングナンバー「ecole」は、ループするビートが陶酔感を誘うかと思えば、その空気を切り裂くように轟音ギターが切れ込む。「Anesthesia」は、その疾走感でライヴのオーディエンスを大揺れさせそう。かつ、“麻酔” や“無感覚” という意味を持つタイトルフレーズを始めとする歌詞は、一語一語がたまらなく切ない。音像の恍惚感と、歌詞の痛み――。二律背反な要素の共存が、聴き手の心をこれ以上ないほど激しく揺さぶる!
-

-
ArtTheaterGuild
NO MARBLE
前作『HAUGA』に続いて、the pillowsの山中さわお(Vo/Gt)がプロデュースを手掛けた2ndミニ・アルバム。本人たちも公言している通り、the pillowsをはじめとする国内外のオルタナティヴ・ロックからの影響を、良質なメロディとともにてらいなく届けるスタイルは健在だが、今作はタイトル"NO MARBLE"や1曲目の「Marbles」に用いた"マーブル"という言葉通り、その個性がより際立つ作品となった。リズム隊がどっしりと存在する不動の液体だとすれば、メロディや歌詞にある心象や、ギター・サウンドはそこに垂らされる絵の具。美しく絡み合いながらもそれぞれの色がはっきりと立った、極上のギター・ロックを、じっくりと堪能してもらいたい。
-

-
ArtTheaterGuild
HAUGA
2012年に栃木にて結成。しばらくして都内で本格的に動き出し、ジワジワと人気を高めてきた3人組 ArtTheaterGuildが、初の5曲入りミニ・アルバムをリリースする。the pillowsを知る人であれば、山中さわお(Vo/Gt)がプロデュースを手掛けていることに思わず頷くであろう、1990年代のオルタナティヴ・ロックやパワー・ポップからの影響を屈託なく前面に打ち出した、3ピースのバンド・サウンド。はっきり言って触りだけ聴けば"そのまんま"だ。しかし、少し聴き進めば見えてくる、さりげなくオリジナルな深みと味わいがニクい。どこかで聴いたことがあるようでなかった、今までずっとそこにあったにもかかわらず気づくことがなかった宝物を見つけたようなメロディが、心に沁みる。超良質なギター・ロックの世界へようこそ。
-

-
ART vs SCIENCE
The Experiment
ダンス・ロックの常識を覆す、激アツなエモーショナル! 完全生バンドで本国オーストラリアだけでなく、USやUKなど様々な国を踊り狂わしてきたスリー・ピース・バンドART VS. SCIENCEが堂々の日本デビューを果たす。パワフルでカラフルなJimとDanのツイン・ヴォーカルと、変幻自在に音色を変えるキーボード、フィジカルで激しく脈打つビート。思わず口ずさんでしまうメロディと掛け声に、自然と気分が高揚してくる。「常にライヴを意識している」というメンバーの言葉通り、非常にライヴ感が強く、非常に近距離で彼らの温度を感じられる作品だ。既存のスタイルに囚われず、自分達がやりたいように無邪気かつ自由に音を鳴らす。だから聴き手も安心して彼らの音の中に飛び込めるのだろう。
-

-
asayake no ato
Climbers aim high
年齢を重ねるごとに、純粋に夢を追うことは難しくなる。バンドなんてその代表格と言っていい。諦めさせようとする環境に勝てず辞めていく仲間もいる中で、自分はこのままでいいのだろうか? 今作の1曲目を飾る「クライマー」には、葛藤と戦いながら、それでも"次こそは"と高みを目指す、asayake no atoの本音が綴られている。息継ぎする間もなく重ねられていく言葉、気持ちに拍車をかける疾走感と横溢する眩しい音の粒――きっと、同じように夢を胸に抱いたままもがくすべての人の心を奮い立たせるはずだ。そんなメッセージ性もさることながら、このバンドの素晴らしいところは、歌詞の内容を抜きにしても情感溢れる歌、ポスト・ロック/エモの影響をいい塩梅の押し引きで散りばめながら描く美しいサウンドスケープ。そのアンサンブルの妙に感動する。
-

-
asayake no ato
Memories
cinema staffが2011年にリリースした1stフル・アルバムは、砂漠から"海"を目指す旅路を描いたものだった。asayake no atoは同じく2011年、京都で結成された4ピース。cinema staffやLOSTAGEなどからの影響を感じさせるエモさと、独自のセンスで多彩なサウンドを鳴らす彼らがいよいよ攻めに入る。1stミニ・アルバムのテーマは"海"。悲しみや弱さを抱えながらも、美しく強くあろうとした人たちの生き様を描いたドラマチックな7曲が展開される。スケール感のある音像も魅力的だが、なにより神社 宏行(Vo/Gt)のヴォーカルが素晴らしい。凛としたその歌声は、聴けば聴くほどにリスナーをひき込んでゆく。小説を1ページずつ捲っていくように、じっくりと味わいたい。
-

-
ASCA
CHAIN
これまたハネそうな予感しかしない。昨年リリースされたシングル『RESISTER』のヒットと、1stアルバム『百歌繚乱』の高完成度ぶりをもって、存在感を増してきたASCAがこのたび発表したのは、TVアニメ"ダーウィンズゲーム"のOP「CHAIN」を表題曲とした充実のシングル。看板曲のアタック感とキャッチーさがずば抜けているのはもちろんだが、いなためなロック・チューンにして、ASCAの歌にはソウルフルな色合いも漂う「いかれた世界だろ構わないぜ」や、DJ Massを制作に迎え、クラブ・テイストの漂う音像を背景に、ASCAが遊び心たっぷりなヴォーカリゼイションを繰り広げる「Don't disturb」も聴きどころ満載だ。全曲にてASCAが作詞に参加している点も要注目!
-

-
ASCA
百歌繚乱
液体、気体、個体、はたまたシャーベット状と温度や環境によって様々な形態となっていく水のように。歌う楽曲によって次々と表情を変えてゆくASCAというヴォーカリストの持つポテンシャルが、この1stアルバムではよりいっそうの鮮やかさをもって花開くこととなったようだ。超ビッグ・タイトル・アニメ"ソードアート・オンライン アリシゼーション"のOPとして名を馳せた「RESISTER」など、いわゆる代表曲たちが一挙集結しているという点でも今作はマストバイとなるが、一方ではアルバムならではと言える趣向が凝らされた新曲群が、実に興味深い仕上がりとなっている点にもぜひご注目をいただきたいところ。1stアルバムにして、もはやベスト盤かのようなこの充実ぶりはある意味で末恐ろしい。
-

-
ASCA
RUST / 雲雀 / 光芒
あたかも三種の神器のごとく、3曲の珠玉曲が揃った今回のシングルはASCAにとって今の充実した活躍ぶりをそのまま体現したものとなっているのではなかろうか。力強さとしなやかさをともに感じさせる「RUST」でのヴォーカリゼーションは彼女の持ち味を存分に映えさせる曲であるし、「雲雀」はかの梶浦由記氏が作詞作曲アレンジを手掛けたリリカル且つどこかオリエンタルな風情を漂わせた響きの中で、ASCAが繊細で温かな歌を聴かせるあたりが実に乙。なお、この楽曲は現在TVアニメ"ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-"EDとしてオンエア中とのこと。「光芒」は最もニュートラルなトーンでASCAが持つヴォーカリストとしてのポテンシャルを感じられる仕上がりだ。
-
-
ASCA
RESISTER
抗い難いものに抗うことで初めて生まれるアイデンティティがあるのだとしたら。この表題曲の中でASCAが歌い上げてみせるのは、ひとつの決心であり切なる願いでもあるのかもしれない。世界的な人気を誇るラノベ発祥のアニメ作品"SAO"シリーズ最新作"ソードアート・オンライン アリシゼーション"第2期OPテーマとして起用されているこの楽曲においてはASCA自身も作詞に参加。物語の中に漂う緊張感や渇望を言葉と歌の両面で表現することに成功している。なんでもアニメ・ファンの間では"神曲"であると評判も高いそうだが、いちアニソンの域を優に超えるドラマチックな展開はもはや痛快と言ってもいいほど。一方、初回盤に収録のc/w「ただいま。-Studio ver.-」で聴ける、素に近いASCAの歌声の赤裸々さもまたいい。
-

-
ASCA
凛
これまでのASCAは、比較的しっとりと聴かせることの多いシンガーであった。しかし、以前から彼女の声質にはパワー感のある楽曲も映えるのではないか、と個人的に感じていたのである。その意味でいけば、TVアニメ"グランクレスト戦記"後期OP曲となった表題曲「凛」はまさに彼女の持つポテンシャルをこれでもか! と抽出した仕上がりだと言えよう。c/wの「サルベージ with EMO Strings」は9人編成のストリングス・チームとの、スケール感たっぷりなコラボ曲。一方、「Don't leave me」はASCAがリスペクトしている阿部真央のカバー・チューンで、これまたASCAの新たな表情を垣間見ることができる秀逸な仕上がり。なお、購入するなら「凛」のMVを収録したDVD付き初回盤をぜひ!
-

-
ASCA
PLEDGE
ASCAは、年若い女性ヴォーカリストでありながら、すでに中学生時分、コンテストでファイナリストに選出されたことがあるという経歴の持ち主だ。故に、その歌唱力はもちろん折り紙つき。TVアニメ"グランクレスト戦記"のEDとして絶賛オンエア中の表題曲しかり、自らが過去に経験した遠距離恋愛をモチーフにして詞を綴り歌い上げたという「悠遠」しかり、聴き手の耳にまっすぐ届いてくるようなピュアな歌声は極めて瑞々しく尊いのだ。それでいて、「グラヴィティ with fox capture plan」で感じられるような躍動感を持ったタイプの楽曲も生き生きとパワフルに歌いこなすことができるヴォーカル力を持っているだけに、彼女の擁する可能性はとても大きいと言える。ここからが伸び盛り本番なのでは。


























