DISC REVIEW
カ
-

-
清 竜人
遥か
TVアニメ"Dr.STONE NEW WORLD"第2クールOPテーマとして反響を呼んでいる「遥か」。儚さを内包しながらも力強く歌い上げるヴォーカルに、爽快なギター、重厚感のあるストリングスが押し寄せるグルーヴはアニメの壮大な世界観とリンクする。アニメ主題歌書き下ろしは自身2作目とのことだが、これほど自然に物語との親和性を引き出せるのは、多彩なアプローチで磨かれたポップ・センスと比類なきキャリアによるものだろう。またDVDに収録のMVでは、神聖な世界でひたむきに生きる巫女の姿が描かれており、期待と失望のなかで前を向いて生きる等身大の詞世界が美しさとともに浸透している。遥か先でも歌い続けるという強い意志と素朴な優しさが紡がれた本楽曲は、アニメ・ファンのみならず多くの人に勇気を届けるポップ・ソングだ。
-

-
清 竜人
REIWA
一夫多妻制アイドル"清 竜人25"、観客と演者の垣根を取っ払ったプロジェクト"清 竜人TOWN"というキャリアを経て、竜人のニュー・アルバムがリリース。新元号への改元の日に発売する今作の収録曲は、シングル曲「平成の男」、シンガー・ソングライター、吉澤嘉代子とのデュエット、友達でも恋人でもない人との逃避行を、ピアノを基調としたサウンドに甘いエレキ・ギターを絡めて眩く描いたナンバーなど、時代性が感じられるものばかり。今自分が何をしたら面白いかを考え実行してきた彼の、メロウでエモーショナルな部分も、エンターテイナーっぷりを極めたミュージカル的魅力も満載だ。そんな彼がこれまでの活動で得たものが地続きとなって発揮された今作は、新時代に突入しても不朽の作品となるだろう。
-

-
清 竜人
WORK
頭のなかがどうなっているのか。今、最も覗いてみたい人だ。4thアルバム『MUSIC』でそのめくるめくポップ世界が覚醒し、続く限定発売の5thアルバム『KIYOSHI RYUJIN』では弾き語りで愛を綴った。毎作リスナーの想像を軽々と超えるアルバムを作る清 竜人。一瞬置いて行かれる感覚もあるけれど、いつの間にかその作品に囚われてしまうサウンド世界と、心に沁みこんでいろんな作用(いたずら)を引き起こす歌は麻薬的だ。ニュー・アルバム『WORK』もまさにそんな作品。ストリングス・アレンジも自ら手掛け、ときに三味線をも弾き、ファンタジー映画のように物語性の高い音楽を奏で、ジェリーフィッシュのやんちゃで知性も光るポップネスと特大のロック・アンセムも放つ。稀有な感性に、ポップ職人的ワザが加わったとなれば、無敵だ。
-
-
霧雨アンダーテイカー
ステレオとモノローグ
"片手で数えられるくらいの/譲れないものがここにあるから"――堂々と宣言するようなフレーズから幕を開ける「ステレオとモノローグ」。ポップとラウドの間を突く骨太な演奏と、音楽シーンの流れを汲み取ったようなシンセの音色がバッキングを固めつつ、際立っているのはクリアな歌声だ。アニメの物語へ力強くも滑らかに導いてくれる歌声が、実に心地いい。"会いたい自分になれるのがヒーロー"などと金言を連発しながら、パンキッシュに疾走していく「Don't Think Feel So Good!!!」。平熱の打ち込みサウンドと、切々とした歌詞が哀愁を誘う「Gunpowder Ballad」。三曲三様の表情からは、霧雨アンダーテイカーが只者ではないことが伝わってくる。
-

-
キングサリ
SURVIVE
"生きる、活きる、イキる、熱きる、射切る"という、5つの"いきる"をコンセプトに活動しているキングサリが、Noisy IDOLからアルバムをリリース。MOSHIMOの岩淵紗貴(Vo/Gt)と一瀬貴之(Gt)、岡田典之(空想委員会/Ba)、松永天馬(アーバンギャルド/Vo)といった、彼女たちにとってお馴染みの作家陣は本作でも手腕を振るっていて、立ちはだかるものをすべて蹴散らして突き進んでいく姿を彷彿とさせる「王様デスゲーム」、強烈なまでにエモーショナルな「一矢報いて」、血気盛んな祭囃子や口上が飛び出す「金愚上等」といったロック・ナンバーや、新規軸となるクールで清涼感のあるEDM「Cuteness Nemesis」など、全12曲を収録。また、デビュー作『I KILL』収録の4曲も再録され、これまでとこれからが凝縮された1枚に仕上がった。
-

-
禁断の多数決
エンタテインメント
音楽がエンタテインメントになれない時代だ。しかし、音楽がなんとなくの欲求を満たすチープな娯楽になるのは嫌だ。音楽は虚しいセックスじゃない。というわけで僕は禁断の多数決に1票。この新作のTrack.1「ちゅうとはんぱはやめて」で彼らは、ラッパーの泉まくらをフィーチャーし、これまでになく明確なメッセージを発している。"好きにも嫌いにも聞こえん言葉と/得体の知れん星の数で出来上がるレビュー""丁寧に練った愛の歌ハモって/禁断の多数決が好きなんて言えんで"。何故、禁断の多数決は数多の情報でその身を隠し、数多の情報をその音楽の中に詰め込むのか?――それは彼らがエンタテインメントだからである。エンタテインメントとは、かくも複雑に入り組んだエゴイスティックな駆け引きなのである。
-

-
禁断の多数決
アラビアの禁断の多数決
YouTubeにアップしたPVが話題を呼び、その謎が多い存在感も相まって注目を集める禁断の多数決の2ndアルバム。現時点で筆者の手元に届いているのは全14曲中7曲のみなので詳しく書き切ることはできないが、今聴ける楽曲――ストリングスとホーンをフィーチャーした壮大なOPトラック「魔法に呼ばれて」、ロマンティックでキャッチーなダンス・ポップ「トゥナイト、トゥナイト」、精錬としたシティ・ポップ風の「リング・ア・ベル」、トライバルな太鼓の上を幽玄なギターと尺八(?)のような音色が響く「踊れ踊れ」、様々な音楽要素が重なり合ったアイリッシュ風ダンス「アイヌランド」......などなど、ジャンルや地域性を飛び越え、かつ前作以上にポップ・ミュージックとしての強度を持った楽曲が並んでいる。傑作の予感しかない。
-

-
禁断の多数決
はじめにアイがあった
自作のミュージック・ビデオが一部の間では話題になっていたが、まだまだロック・シーンの中では無名の存在である“禁断の多数決”。楽曲もチル・アウトありエレクトロありポップスありヴォーカルも4人いたりとトピックだけをとると、かなりとっちらかっているように思えるが、その全てが実験的ではなく非常に高いクオリティを持っている。YouTubeでも話題になっていた変態的エレクトロ・ポップの「アナザーワールド」やアルバム用に装いを変えた今のこのバンドの代表曲と言える「透明感」の中毒性の高いリフレインするヴォーカル・ワークなど、1曲1曲を切り取っていくとキリがないのだが、まずは聴いていただきたい。その未知数のふり幅に、恐らく十人十色の感想を得れるだろう。
-

-
V.A.
THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION vs ギターウルフ
アリストテレスの言葉を引用する――友情とは2つの肉体に宿れる1つの魂である。THE JON SPENCER BLUES EXPLOSIONとギターウルフとは、まさにそんな関係に思える。ルーツに対する憧憬または純粋な愛情、そして先鋭性を持ってモダナイズしたロックンロールを描き続けてきた両者は、ブルースとガレージの相違はあっても根幹は同じなのだ。"それぞれに影響を受けたバンドのカヴァー曲とここぞの勝負曲"をテーマに選曲された4曲は、1つの魂を追求する上で最良のアイテムと言えるだろう。さらにボーナスDVDには昨年11月下北沢SHELTERで行われた対バンを完全収録。チケット即完でプレミア化しただけに泣く泣く見逃したファンは必見だ。あの伝説の夜が蘇る......。
-

-
ギャーギャーズ
elevatormusic
結成時はこねくり回した難解な曲を作っていたそうだが、心機一転このミニ・アルバムでは新たなフェーズに突入している。楽曲は蛭田マサヤ(Vo/Gt)のキャッチーな歌メロを主軸に、3分前後にコンパクトにまとめられ、シンプルにしてひと癖あるサウンドは妙に耳に引っ掛かる。ロック、パンク、ニュー・ウェーヴなど多彩な曲調が揃っているけれど、匂い立つような人間味と口ずさみやすいポップなメロディがどの曲にも息づいているので、散らかった印象も皆無。ノリのいいアッパー・チューンからしっとり聴かせるバラード風の曲調まで、ギャーギャーズを形成するメンバーの泥臭い人柄がきっちりと刻印されている。どこかにいそうでどこにもいない強烈なオリジナリティが、全6曲にびっしりと張り巡らされている。
-

-
ギャーギャーズ
ばんぱく
アルバムとしては2年ぶりとなる今作は、2007年の結成以来、同じメンバーで大阪を拠点に活動を続ける彼ららしいタイトルが付けられた。等身大の言葉で歌われるパンク、ロックンロールはライヴでその真価をより発揮しそうだが、延々とループするギターリフが頭にこびりつく「プーアル・チック・ラブ」、オリエンタルなイントロから導かれる「オシロメサマ」など、その楽曲アレンジには中毒性を感じさせ、聴きどころ満載。随所に人生の機微が描かれた歌詞も特徴的で、ミディアム・テンポのロッカ・バラード「銀色の観覧車」を始め、その情景に心を重ねることができる人もいるはず。とはいえMVも公開されている「チョップ」のユーモラスでタフな世界がバンド最大の必殺技なのかも。
-

-
ギャーギャーズ
先祖返り
東大阪発、何でもありのロックンロール・バンド"ギャーギャーズ"が、約2年半ぶりとなるフル・アルバムを2枚同時リリース。『先祖返り』と名づけられた2ndアルバムは、ライヴでも披露されているお馴染みの楽曲が並ぶ。今作では、ストレートなロックやパンクに、不器用でまっすぐ、でもどこか歪な歌詞がのるという、これまでの彼らのスタイルがひとつの形として実を結んでいるようだ。一聴したところ(いい意味での)アホっぽさが強烈に印象に残るのだが、フォーキーでどこか懐かしいメロディやシンプル且つタイトなギター・サウンドからは、彼らのロックンロール・バンドとしての品位を感じる。かっこつけずひたすらアホなことを追求するその生き様が、結果的に人間臭くもかっこいいという、ロックンロールのミラクルが炸裂した作品。
-

-
ギャーギャーズ
逆襲
個性派バンドがひしめく関西ロック・シーンにおいてすらも異彩を放つロックンロール・バンド"ギャーギャーズ"が、『先祖返り』とともにリリースする3rdアルバム。その名も『逆襲』。今作はほとんど新曲で構成された、これからのギャーギャーズを打ち出す内容となっており、全体的にNUMBER GIRLやeastern youth直系の90年代のエモ/オルタナティヴ・ロック色が増しているように感じられる。正直どこまで狙っているのかは不明だが、THE STROKES以降のソリッドなロックンロールをベースにしたサウンドに遊び心を通り越したユーモアを取り入れる、ある意味逸脱したアナーキーなスタイルは相変わらずである。これを自然とやってのける姿勢からは、ロックの可能性を追求した70年代後半の真のパンクスたちと同じ心意気を感じずにはいられない。
-

-
ギリシャラブ
悪夢へようこそ!
ヒップホップやエレクトロニック・ミュージックの現在と共鳴するような曲もあれば、かつてのインディー・ロック隆盛を思わせる曲、もはや古典扱いされてしまいそうな"THEロック"な曲まで、ここは時代の先端なのか、はたまた"昔は良かった"そのときなのか。我々は何を思いどこに向かうべきなのか。答えに答えを掛け合わせることが求められ、結果が出て安堵を覚えたころには疲れ果てている生活に対してなのかはわからないが、今作のタイトルが"悪夢へようこそ!"とはよく言ったもの。誰も見たくない出口のない夢の世界に、答えはなくとも、ポジティヴな感情を抱くことができる。曖昧であることが明快な夢の世界だからこその、新しい感覚を持ったポップ・アルバムだ。
-

-
銀杏BOYZ
恋は永遠
NHKの朝ドラ"ひよっこ"で名演技を披露し、世代を超えて名と顔を知らしめた峯田和伸。彼が率いる銀杏BOYZの最新シングルとなる今作で、彼は音楽においても老若男女を魅了する存在になり得るのではないだろうか。そう思えるほどポピュラリティを感じる名曲だ。『エンジェルベイビー』、『骨』に続く、"恋とロック"を軸とした3部作の締めくくりに位置づけられているが、"恋とロック"とは、彼の中で――遡ればGOING STEADY時代からあった軸と言えるわけで、その集大成にも感じられる壮大な甘さを味わえる。2曲目の「二十九、三十」は、クリープハイプのカバー。アレンジこそ違えど、クリープハイプと銀杏BOYZに通じるメンタリティのようなものが表れていて、ファミリー・ツリーを見ているような気持ちになる。
-

-
銀杏BOYZ
骨
峯田和伸がNHK連続テレビ小説"ひよっこ"の小祝宗男役で俳優として、ぐんと知名度を上げるなか、3ヶ月連続でリリースするシングルの第2弾。2016年に安藤裕子に提供した「骨」と『DOOR』(2005年)収録の「援助交際」を再録・改題した「円光」の2曲を収録。ともに歌メロそのものの人懐っこさや洗練なんて言葉さえ浮かぶ演奏とは裏腹にアクが強すぎる峯田のヴォーカル、歌詞の世界観が聴く者を選んでしまうであろうラヴ・ソングだ。ある意味、ショッキングと言ってもいい。しかし、愛とはそもそも、それくらいの強い想いに突き動かされた感情のはず。それを単に感情を迸らせるなんて安っぽいものにせず、冷静ささえ感じさせながら、ぐぐっと押し出したような表現にしたところに凄みを感じずにいられない。
-

-
銀杏BOYZ
エンジェルベイビー
ロックンロールに人生を変えられて、今や中年の域に足を踏み入れた者として峯田和伸は覚悟を決めて、再びまっさらなバンド・サウンドで世界中にいるひとりぼっちの脳天を揺さぶろうとしている。これまでも録音物としては尋常じゃないバランスの音源を残してきた彼だが、今回の表題ではエレクトリック・ギターやシンバルの金属的なサウンドがシューゲイザーとは違う目的で、光る洪水のように聴く者を溺れさせる。この音こそが意思だ。Track.2「二回戦」はライヴ映像作品『愛地獄』に弾き語りで収録された「イラマチオ」のタイトルを変更したバンド・アレンジ曲。シティ・ポップ的ですらある野崎泰弘のエレピも、UCARY VALENTINEが差し込むノイズも音としては逆方向なのに、曲の純度を上げている。何度目かの新章到来だ。
-

-
銀杏BOYZ
光のなかに立っていてね
自分の人生の中で、今まで出会ったすべての人に会いたい。そして愛する人にはキスをして、抱きしめて、嫌いな奴はぶん殴って、その後やっぱり無理やりにでも抱きしめてやりたい。そして警察に捕まって終身刑で牢屋に入れられて、その牢獄の中で抱きしめた人たちの匂いや感触を思い出しながら、死ぬまで生きたい。このアルバムを覆うインダストリアルやエレクトロも食い散らかした狂騒的なビートとノイズは人間という牢獄そのもので、その中にある美しいメロディと言葉は、牢獄の中で浮かべる笑顔と涙のようだ。9年間、ずっと待ってたわけじゃない。このアルバムを聴いて、何かを思い出したわけじゃない。ただ、"生きている"という事実だけが僕にも銀杏BOYZにもあった、それだけのこと。本当に、それだけのことなんだよ。
-

-
空想委員会
世渡り下手の愛し方
2年間の活動休止を経て、21年4月、活動を再開した空想委員会が『恋愛下手の作り方』で全国デビューしてから10周年という節目にリリースした、全12曲書き下ろしのフル・アルバム。日々の暮らしで感じる生きづらさと、そこに潜む希望の欠片を探す3人組ギター・ロック・バンドと自ら掲げる彼らがここで歌うのは、自分たちも含む"世渡り下手"への愛......ではなく、叱咤激励だ。彼らには不似合いかもしれない叱咤激励という言葉を使いたくなるほど力強くなったメッセージと、ファンクを含めダンサブルなリズムを強化したアレンジに、バンドの成長を感じずにいられない。かつて身上としていた恋愛下手をテーマにした曲は、Track.10「ラブソングゾンビ」のみ。そんなところからも再出発にかけるバンドの思いが窺える。
-

-
三浦隆一
空集合
空想委員会が活動休止をして2年、三浦隆一(Vo/Gt)のソロ・デビュー・アルバムが完成。もともとは昨年春の発売を予定していたが、コロナ禍や三浦の体調不良もあり、1年の時を経ての発売となる。Kenji Smith(Gt/ex-ウソツキ)、出口博之(Ba/モノブライト)、渡辺拓郎(Dr/藍坊主)といった盟友と作り上げたのは、三浦の心の内に触れる作品だ。ソロという新たな道を歩んでいく、そこでふと襲われる不安や正解を求める焦燥感は、自分の足元が不安になる出来事が多かった昨今の日常にも重なりそう。その音楽は、どうにもならない悩ましさを抱えながらも、一歩を踏み出す確かで軽やかな躍動がある。彼が自身に問い掛け、自分の声に耳を傾け続け聞こえてきたこの音楽は、誰かにとっての道しるべになりそうだ。
-

-
空想委員会
何色の何
1年3ヶ月ぶりの新作は、クラウドファンディングにより制作された、フロントマン 三浦隆一(Vo/Gt)が原作を手掛ける同名アニメと連動したEP。これまで三浦の実体験や心情に焦点を当てた楽曲制作を行ってきた彼らだが、今作では登場人物ふたりのそれぞれからの視点で綴られたもの、三浦から主人公に向けて宛てられたものと、歌詞表現の幅が広がった。リスナーからメッセージを募って制作されたという「エール」、アニメの主題歌であり歌を最大限に生かしたサウンドスケープの「マイヒーロー」など、着火性は高くないかもしれないが一過性ではない、バンドの核心となるエモーショナルな温度感をじっくりと伝える楽曲がひと際存在感を放つ。楽器隊のシンプルでありながら細やかな音使いも聴きどころだ。
-

-
空想委員会
デフォルメの青写真
"作った人間によってデフォルメされた音楽を、聴き手にも好きなようにデフォルメしてほしい"という意味のアルバム・タイトルを冠した約1年2ヶ月ぶりのフル・アルバム。これまでの人生経験を綴った三浦隆一(Vo/Gt)の歌詞も題材が多岐に渡り、岡田典之(Ba)も自らが作曲した楽曲はアレンジのイニシアチブを取るようになるなど、これまでで最もそれぞれのメンバーのカラーが出た作品になった。その結果3人の化学反応の生みだす調和によって、バンドとしての鋭さや楽曲のバリエーションが生まれている。佐々木直也(Gt)による全収録楽曲のフレーズを織り交ぜたインスト・ナンバーももちろん収録。3rdフル・アルバムが原点も成長も存分に含んだ作品になったことは、バンドにとっても大きな自信になったのでは。
-
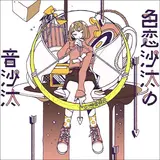
-
空想委員会
色恋沙汰の音沙汰
TVアニメEDテーマや映画の主題歌などを収録した両A面シングルから約8ヶ月ぶりのリリースとなるEPは、初期空想委員会の代名詞ともいえる恋愛ソングを主軸にした作品。とはいえリスナーに懐古の念を起こさせないのは、アレンジや歌詞に新しいアプローチがあるからだ。特にアレンジは目覚ましく、通常盤に収録されている「波動砲ガールフレンド」のアコースティック・バージョンは、アップ・テンポの原曲を落ち着いたタッチでリアレンジ。テンポ・チェンジを用いたTrack.1、曲名のとおりトランス要素を取り込んだTrack.2を筆頭に、らしさを残しつつ斬新な印象を与える。非常に理想的なアップデートでは。ラストに"その先"を匂わせる歌詞も、タイトでクールな音のなかで力強く響く。
-

-
空想委員会
ダウトの行進
世の中には嘘が多く存在する。それは自分自身を優位に立たせるものであったり、自己防衛のものであることも多く、穿った見方をしてしまうこともある。だが音楽を含めた芸術に関して嘘は天敵である。空想委員会は、そういった狡猾なことは一切せず、努力を欠かさず生身の自分自身で音楽を作り鳴らすバンドだ。フロントマンの三浦隆一の人間性はメジャー・デビュー以降さらに楽曲に明け透けになり、心境の変化が新たな色彩をもたらす。楽器隊もそこに突き動かされるように、楽曲の奥行きを作るため以前以上に細部まで音色を追求。これまでの持ち味をブラッシュアップさせながら、新たなチャレンジを要所要所で取り込んだ精度の高い楽曲が揃っている。彼らの音楽愛と好奇心はこれからも我々の心を刺激し続けるだろう。
-
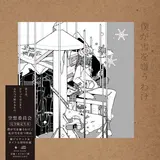
-
空想委員会
僕が雪を嫌うわけ/私が雪を待つ理由
男性目線と女性目線の2曲で、ひとつの冬の恋の終わりを描くことをコンセプトに制作された完全限定生産の両A面シングル。Track.1はシンプルで疾走感のあるギター・ロック。冬の冷たい空気の中を疾走していくような力強さもあれば、触れたらすぐに溶けてしまう雪のような繊細さや感傷性も持ち合わせた空想委員会らしい楽曲だ。Track.2は舞い落ちる可憐な雪を彷彿とさせる、ストリングスを用いた軽やかなナンバー。"終わった恋の続きを始められたら"と願う女性の切なくささやかな希望が綴られた歌詞とサウンドの親和性が、冬が終わると春が来ることを伝えてくれるようだ。2015年は制作面でも活動面でも彼らにとって大きな過渡期と言っていい。来年の活躍に期待を寄せざるを得ない完成度である。
-

-
空想委員会
GPS
初めて"自分"と"あなた"のことを歌いたくて曲を書いた――三浦隆一(Vo/Gt)に訪れた転機(※詳細はインタビュー記事にて)から生まれたこのミニ・アルバムは、間違いなくバンドの、そして三浦の新境地だ。元来、彼は自分の心情を嘘偽りなく歌詞にしているが、今作にはその心境の変化や新たな意志が克明に記されている。聴き手を誘うTrack.1、自分自身の変化とメッセージを投げかけるTrack.2、作曲者である岡田典之(Ba)を詞に投影したTrack.7など、これまでにはなかったカラフルな表現が揃った。歌の芯が強くなった分、佐々木直也(Gt)の作る遊び心のあるアレンジやギター・ソロもより際立ち、3人のプレイヤーとしての個性が見られるところも面白い。空想委員会、劇的革命の真っ最中だ。
-
-
空想委員会
空想片恋枕草子
精力的な活動を行い続ける空想委員会からわずか約3ヶ月で届けられた新作は、枕草子をモチーフに、四季折々の恋模様を描いた4曲入りEP。「春恋、覚醒」は5拍子の上に、6拍子のギター・リフが乗るイントロから、疾走感のあるセクションへと移る様が桜吹雪のように鮮やかで、バンドに新たなモードをもたらす攻勢的な楽曲。メジャー・デビュー以降、サウンドのギミックがさらに洗練されており、よりロック・バンドとしての腕を強化する意思表示と言ってもいい。男子からの共感性抜群であろう生々しい歌詞の描写とダンス・ビートのコントラストもクールな「作戦コード:夏祭り」、夕日に染まる教室が浮かぶ穏やかな「秋暮れタイムカプセル」、現在の空想委員会の原点である「マフラー少女」と、4曲それぞれ異なった趣を楽しめる。
-

-
空想委員会
純愛、故に性悪説
バンドの中心人物である三浦隆一は不思議な人だ。冷静で淡々としつつも人当たりは良いし、よく笑うしジョークも言う。だが心の奥底に何か大きなものを抱えているような、深い目をしている。そんな彼の内面が出た"THE三浦隆一"とも言えるのが今回のメジャー1stシングル。表題曲は自分を振った相手を恨む気持ちを歌ったもので、本人は"自分の鬱憤晴らしだ"と言っていた。だがその中でも自然とリスナーを導いたり夢やエンタテインメント性を与える楽曲に昇華されているところは、バンド・メンバーが元来持つ人間力が大きい。三浦が自分をさらけ出した楽曲に対して、ふたりは"歌を聴かせたい"と真摯に向き合い、楽曲制作を経て彼らはさらに絆を深めた。この先バンドの自由度がさらに広がることを予感させる。
-

-
空想委員会
種の起源
淡々としているのか、それとも情熱的なのか。突き飛ばしても倒れない、そんな強さを持つ声が紡ぐのは、恋愛にまつわる不平不満と恐怖に、憧れ――。インディーズ時代から学校と紐付けされたユーモア溢れる活動と、完成度の高い楽曲で10代のリスナーを中心に話題を集めていた空想委員会がメジャー・デビューを果たす。正統派ギター・ロックとひねくれた恋愛観、遠くから憧れの人を見つめる切なくひとりぼっちの音楽。そこに美しく華やかなギターの音色と安定感のあるベースが加わることで、委員長・三浦隆一ひとりだけの世界だったものがドラマティックに変貌し、空想委員会の世界となる。ひとつひとつの音があたたかいのは、このCDの向こうにいるリスナーへ宛てる想いだろう。そう、彼らの音楽は優しいのだ。
-
-
空想委員会
空の罠(下)
皆様は雨というものにどのようなイメージをお持ちだろうか。濡れる、髪が広がる、傘が邪魔、頭痛に悩まされる......ネガティヴなことがたくさん思い浮かぶが、本当にそれだけ?少し見方を変えるといろんな世界が広がっているのでは? ――そんなことを教えてくれるのが、春にメジャー・デビューが決定している空想委員会の『空の罠』だ。2013年11月にライヴ会場限定でリリースした2nd EPの後編となる3rd EP。雨をコンセプトにした作品を作ることになった発端は、ライヴの日は大抵雨、ワンマン・ツアー初日に台風直撃等、雨バンドと称されることが多くなったからとのこと。そんな自虐を巧妙にエンタテインする手腕がニクい。ちょっぴり切ないムードの漂う音色と文学的な言葉遊びの罠にかかってみては。
-
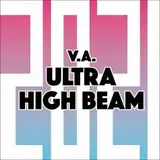
-
V.A. (HIGH BEAM RECORDS)
V.A.ULTRA HIGH BEAM 2021
どんな世の中でも前向きに進まなければいけない。そんな強いメッセージを感じられたHIGH BEAM RECORDSコンピレーション・アルバム第2弾。ライヴ規制をかけられた今、悶々とした思いを彼らなりにポジティヴに変換して吐き出した曲には、現代社会で日々もがき苦しんでいる人にもきっと刺さるものがあるはず。ふっと心を軽くしてくれるフラスコテーションの「そんな気がしている」、関西弁でパワフルなPICKLESらしいロック・ナンバー「シランケド」、もがき苦しむ様子をストレートに歌い上げるGAROADの「ハウル」など全15曲収録。今回は初の試みとなるライヴハウス推薦枠もあり、よりパワー・アップした内容となっている。この先も変わらず音楽を鳴らし続けることを決心した彼らのドラマがここにある。
-

-
空創ワルツ
Waltzer Waltz
福岡発3ピース・バンドの2ndミニ・アルバム。サイレンのようにギターが唸ってから4分間、息つく間もなく展開するTrack.1「近未来系宇宙少女」だけでもバンドの引き出しの多さがうかがえる。バンドのテーマである"シャル・ウィ・ダンス?"をそのままタイトルに持つ楽曲には"悲しいときには泣いて/嬉しいときには笑えばいいはずなんです/本当は"と彼らの表現の核であろうフレーズがある。飛び散る汗が目に見えそうなほど熱いバンド・サウンドと、それと同様の熱量を持ちながらもクリーンに飛んでくる歌だからこそ、喜怒哀楽を全肯定する姿勢の説得力が増すのだ。架空の物語が題材となる楽曲が多くてもそれらが単なるおとぎ話に終始しないカラクリは、紛れもなく3人自身に在る。
-

-
空創ワルツ
それより僕と踊りませんか?
2011年から活動を開始した福岡発の3ピース・バンドの1stミニ・アルバム。アルバム・タイトルが『それより僕と踊りませんか?』で福岡出身となるとやはり反射的に「夢の中へ」の井上陽水を連想する。直接的な影響は音楽面からは感じられないものの、次々と言葉を放つ饒舌さに共通点があるのかもしれない。ジャケットにもなっている象徴的な楽曲「ガラパゴス」に歌われているマイノリティ的な自覚が彼らのバンドとしてのアイデンティティになっているようだ。パンキッシュなガレージ・サウンドは歌詞の情報量とバランスを取るようなシンプルさながら、凄まじい音圧で迫ってくる。ライヴハウスの熱気がそのまま伝わってくるような硬派なロック・アルバム。
-

-
クウチュウ戦
超能力セレナーデ
前作から約7ヶ月ぶりとなる3枚目のミニ・アルバムが到着。2015年5月に1stミニ・アルバムを発表したクウチュウ戦が、この短いスパンに3枚もの作品を発表。楽曲を生み出すバイタリティはどこから湧き出るのかとその貪欲さに感心するばかり。そんな彼らが放つ今作は、ポップ・ミュージックへの愛が止まらない1枚となっている。プレイ・ボタンを押した瞬間、足をすくわれ音に呑み込まれるかのような「ぼくのことすき」から始まり、ジェットコースターのような展開の後、煌びやかなピアノの音色がまるで魔法を解く呪文を唱えてくれるような「魔法が解ける」で現実世界に舞い戻る。音だけを見つめさせられる引力がものすごく、時間が経つのが本当にあっという間だった。彼らが生み出すメロディの魔法にかかるとマジでヤバイ。
-

-
クウチュウ戦
Sukoshi Fushigi
あらゆる物事が理性の支配下に置かれ、画一化/効率化されているスクエアな世の中にクウチュウ戦はクエスチョンを投げかける。初の全国流通作となった前作『コンパクト』から約8ヶ月で届けられた『Sukoshi Fushigi』は、こういった大きなテーマを孕んでいる。とはいえ、収録される6つの楽曲が前作以上に洗練されたポップネスを打ち立てているという点から見るなら、今作を上質なポップ・ソング集と言ってしまうこともできる。はっぴいえんど的ソングライティングと井上陽水の歌心の邂逅とでも言うべき「雨模様です」や、リヨのキュート且つ狂気的なポップ・センスが爆発した「台風」、そしてゆらゆら帝国と同じ純度で"美しさ"を描き出す稀代の名曲「エンドレスサマー」などが収録された今作は、必ずやシーンを揺るがすはず。クウチュウ戦の真の快進撃はここから始まる。
-
-
クウチュウ戦
コンパクト
"バーニングSFプログレッシブバーチャルリアリティ神秘ロック"という長い肩書きや多展開の曲調、メンバーのヴィジュアルやライヴでの振る舞いなど、奇抜な要素が人目を引きやすいのはわかる。しかしこのバンドの本質は、歌謡曲から正統に引き継いだ哀しみの感情ではなかろうか。ねっとりとした唄い方のハスキー・ヴォイス、グラスの中の氷のようにきらめくキーボード、泣きのギター&ベース。それらの目線は常に過去、喪失、孤独へと向けられる。音楽ですくい上げた感情は誰かの心を震わせることができるのだと、そんな音楽の魔法があるのだと信じているからこその表現の形だということがよく伝わってくる。不特定多数の"君"へ均質的なメッセージをあてがうアンドロイド・ミュージックへの、麗しき反抗声明。
-

-
空中ループ
Walk across the universe EP
“Walk across the universe”とは、空中ループ×大谷友介(POLARIS / SPENCER)、益子樹(ROVO)によるコラボ・プロジェクトを指すものだ。この3者による最初の作品は、バンドに主軸を置いた3つの個性の融合は最高の形で実を結んだのだということを証明している。 空中ループは羽を得たのだ。彼らの持ち味である、フォーキーなギター・ポップが囁くように響くセンシティブな世界に、革新が起こった。これは確実に大友と益子という2人のクリエイターの手腕あってのことなのだろうが、それにしても驚きの変化である。演奏もヴォーカルもケタ違いの躍動感。そして、滴り、弾けるような瑞々しさ。まさに“空中”を“ループ”。浮き上がり、浮遊する。空中ループは、美しきオーケストレーションという新たな武器を手に入れ、此処から飛び立つ。
-

-
空白ごっこ
マイナスゼロ
何もないけど何かある"空(くう)"の世界観を"心"に例えて、その精神世界で遊ぶ(ごっこする)ことをコンセプトにした音楽プロジェクト、空白ごっこが1stフル・アルバム『マイナスゼロ』を発表。"どこまでいってもずっと満たされない感覚がある"という言葉から生まれたというタイトルの通り、貪欲な音楽的探求心が具現化した1枚になった。ポエトリー・リーディングを取り入れた「go around」から疾走感溢れる「ゴウスト」への展開、中毒性抜群の「乱」という冒頭3曲で一気に引き込まれる。葛藤を吐露した内省的な楽曲が多いが、決してダウナーな印象は受けない。それはセツコのエモーショナルな歌声、koyoriと針原 翼が手掛ける色彩豊かな楽曲たちが、アルバムという枠の中で最大限に"ごっこ"しているからなのだろう。
-

-
空白ごっこ
ラストストロウ
"ラストストロウ"とは最後の藁(わら)を意味する。重い荷物を運べるラクダもいつかは限界がくる。最後に乗せた1本の藁がラクダの背を折る、という英語の慣用句から着想を得た言葉だが、空白ごっこの最新シングルはそんなギリギリの緊張感で保たれる"生と死"の境界線がテーマだ。大場つぐみ×小畑 健が原作の人気アニメ"プラチナエンド"のエンディング曲に起用された今作の作曲はメンバー全員で担当。繊細なバラードに乗せて"息をするまでの全部を 抱えきれなくていいから"と歌うセツコのヴォーカルが切実だ。カップリングにはkoyoriとセツコがそれぞれ作詞作曲を手掛けた「カラス」(初回限定盤)と「ふたくち」(通常盤)を収録。人間の心の声を音に変える。今作でもそんな空白ごっこの真価は十二分に発揮されている。
-

-
空白ごっこ
開花
コンポーザーの針原翼とkoyoriが生み出すジャンルレスなサウンドに乗せて、女性ヴォーカル セツコが紡ぐ切実な歌唱が人間の心の深いところを表現する音楽ユニット、空白ごっこ。前作の1st EP『A little bit』から1年ぶりとなる2nd EP『開花』は、セツコ自身が"歯を食いしばりながら駆け抜ける少年が浮かぶ"とコメントを寄せる、疾走感に満ちた「運命開花」をはじめ、躍動感あふれる「ストロボ」、享楽的なダンス・ナンバー「ハウる」など、前作以上にライヴ映えするパワフルな楽曲が並んだ印象だ。不確かな日々のなかで懸命に何かを掴もうとする焦燥や黎明期の衝動が滲む今作は、今音楽シーンにその才能が"開花"しつつあるバンドのリアルとも重なる。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























