DISC REVIEW
D
-

-
Devendra Banhart
What Will We Be
フリー・フォーク界の貴公子として、音楽以外でも話題を提供しながら、圧倒的な存在感を放つDevendra Banhart。この憎らしいほどの美男子が鳴らす、自由な精神性を湛えた音世界は相変わらず素晴らしい。トラッド・フォーク、トロピカリズモ、サイケデリック、JAZZ、ポップス、ロック・ステディあらゆる音を吸収し、万華鏡のように変化するオーガニック・サウンド。レイドバックした音の波に揺られていると、どこか遠い国の喧騒が聴こえてきそうな、まさにサウンド・ジャーニーと呼ぶべきサイケデリア。プロデューサーとして参加しているTHE BEESのPaul Butlerの存在も、この柔らかくもスリリングな音世界に一役買っている。才色兼備ってのは、こういうことを言うんだな。
-

-
DIALOGUE+
イージー?ハード?しかして進めっ!
田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)が音楽プロデューサーを務める女性声優8人組のアーティスト・ユニット、DIALOGUE+の10thシングルは、アニメ"弱キャラ友崎くん 2nd STAGE"のOP&EDテーマをW収録。田淵が作詞作曲、編曲を伊藤 翼が手掛けたOPテーマ「イージー?ハード?しかして進めっ!」は、電子音を効果的に挟み込みつつ、圧倒的なポップさと瑞々しさを振り撒きながら賑やかに駆け抜けていくアップチューン。EDテーマの「誰かじゃないから」は、歌詞を大胡田なつき、作曲を成田ハネダと、パスピエのふたりが担当。ストリングスが流麗に鳴り響く、洒脱でダンサブルなポップ・ナンバーになっている。これまでも良曲を送り出し続けているグループなだけあって、音楽ファンも激しく唸らせる仕上がり。
-

-
DIALUCK
A First Aid Kit
グッドモーニングアメリカ企画のコンピレーション・アルバム『あっ、良い音楽ここにあります。その伍』に参加するなど注目度上昇中の、大阪発の3ピース・ガールズ・バンドが初の全国流通盤をリリース。気だるげなヴォーカルとループを活かした各パートの旋律、まどろむようなバンド・アンサンブルは、熱すぎることもなく冷たすぎることもなく、どこまでも平熱。そこには"作品全体をBGMとして聴いてほしい"というバンドの想いが込められているというが、そんな中で浮き彫りになる"何か捨てなきゃ/何か言わなきゃ/何か歌わなきゃ/何か 何か"(Track.3「憂日幻想列車」)というフレーズの切実さが気になる。"何となく"で聞き流せない魅力の欠片があちこちでキラリ。
-

-
DID
Bad Boys
デビュー・アルバム『Kumar Solarium』が日本でもスマッシュ・ヒットしたイタリアン・バンドDIDの約3年半ぶりとなる2ndアルバム。前作のようなエレクトロニカと融合した、ギターやドラムの輪郭がくっきりとしたバンド・サウンドは影を潜め、よりコマーシャルに深化されたEDMに仕上がっている。冒頭の「You Read Me」のトライヴァル・ビートや「Coin Slot」のダブステップ等、現代に呼応したアレンジ・センスがキラリと光り、飽きさせずにリピートしたくなる曲たちが並んでいる。今年大ヒットしたDAFT PUNKの『Random Access Memories』はバック・トゥ・80'Sなアルバムだったが、当初彼らに期待されていたのは実はこんなアルバムだったのでは?と思わず夢想してしまう程、メガヒットしてもおかしくないポテンシャルを秘めた秀作。
-

-
THE DIDITITS
REFUSE
キャリアを振り返ってみるとわかるが、HAYASHIは本当に正直なアーティストで、その時々で興味がある音楽性にトライし、私たちに新しい世界を見せてくれた。それはもちろん、THE DIDITITSに関しても同様だ。ただ、今まで以上にナチュラルな印象を受ける。それは、彼の血肉となっているオルタナ感がそのまま出ているからだろう。新作も、PENPALSの初期から彼を追い掛けているリスナーにとっては、グッとくるに違いない。とはいえ、あのころの青さは、年齢を重ねて深みがある色合いに変化している。さらに、常に新しい時代を見ているHAYASHIと、若いメンバーの相乗効果によって、きっちり今の音楽にも昇華されているのだ。ぜひ、歌詞も噛み締めて聴いてほしい。
-

-
DIGITALISM
Mirage
5年ぶりのニュー・アルバムだが、制作期間は5ヶ月という"インスピレーションで勝負!"な1枚。この間、すっかりEDM優勢になったダンス・ミュージック・シーンだが、"俺はエレクトロ・インディーが聴きたいんだ!"というリスナーをDIGITALISMは裏切らない。1曲1曲が"ミラージュ=蜃気楼"の構成要素であり、ただ機能的にフロアをブチ上げるようなトラックはない。あくまで"曲"なのだ。興味深いのは前半の耽美な「Utopia」や「Destination Breakdown」と、後半のタイトル曲のパート1、2を挟んで情景が変化する展開。ポップ・ソングとして成立する「Indigo Skies」や、彼らには珍しいヒップホップのゲットー感すらある「The Ism」を経て再び光のある場所へ。この新曲群が"SUMMER SONIC 2016"でどう構成されるのか興味深い。
-

-
V.A.
Kitsuné Maison 16 Sweet Sixteen Issue
エレクトロ系中心の仏レーベル、Kitsunéの名物コンピ『Kitsuné Maison』の最新版。筆者にとってKitsunéといえばニューレイヴ。今から7年ほど前、KLAXONSやDIGITALISMらを中心としたニューレイヴ・ムーヴメントが巻き起こったとき、Kitsunéは世界で最も重要なレーベルだった。嗅覚の鋭い音楽好きはみんなこのコンピをチェックしていたものだ。今は時代の中心にいるわけではないけれど、着実にいいものを届けるレーベルとして確固たる地位を築いている。今作は収録アーティストが全体的にしっとりと静謐な世界観を持っていて、"アガる"だけじゃない豊潤な時間を堪能できる。個人的にはJAWSとNIMMO AND THE GAUNTLETTSという2組の英バンドがツボ。
-

-
DIGITALISM
I Love You, Dude
インタヴューで発言していた「僕らはバンドだと思っている」という言葉が印象的だった。バンドとしての側面、エレクトロ・デュオとしての側面、どちらもDIGITALISMを構成する必要不可欠な要素だ。デビュー・アルバムから4年の歳月を経て作られた今作は"洗練"の一言に尽きる。もともと"Tourism"というタイトルになる予定だったアルバムだけあり、全編通して彼らと一緒に旅をしているような気分だ。その旅は、楽しいだけではなく苦しいこともある。だが、そんな喜怒哀楽の感情全てを含めた壮大な物語がこのアルバムには封じ込まれている。鋭いビートと幸福に満ちたメロディはひたすらに自然体。外界からの刺激を素直に受け入れた彼らの純粋さに胸が焦がれる。貪欲に成長を求める人間の生き様、此処に在り。
-

-
J Mascis
Tied To A Star
DINOSAUR JR.のJが2011年の初ソロ名義アルバム『Several Shades Of Why』以来となる2ndをリリースする。前作同様、ほぼ全編アコースティック・サウンドで構成された繊細なプロダクションが印象的だが、なんと言ってもこのアメリカならではの午前中の光の感じというか、だだっぴろい国道に誰もいない感じを醸し出せるのは、先達のNeil Youngか盟友James Ihaぐらいなんじゃないだろうか。しかし耳を澄ますとアコギのアルペジオの背景にお馴染みのファズ・ギターがうっすら鳴っているリード・トラックの「Every Morning」や「Come Down」の"J印"なこと!また、Track.1「Me Again」のナチュラルなアコギのフォーク感の中に配されたオルガンのゴスペル的な美しさ。どんな時も気持ちをフラットにしてくれる。
-

-
J Mascis
Several Shades Of Why
09年に9thアルバム『Farm』リリースでの華々しい復活が衝撃を呼んだDINOSAUR Jr.。THE ROLLING STONESを彷彿とさせるブルースを根底とした、ドラムとギターの昂ぶりがずしりと重なり合うへヴィなサウンドが印象的だ。そのフロントマンとしてバンドの核を成しているJ Mascisが、実に15年ぶりにソロ・アルバムをリリースする。バンドでの骨太なサウンドとは裏腹に、非常にしっとりと落ち着いたアコースティックなサウンドが展開されている。アルバムとしての起伏はしっかりと押さえながらも、全体的流れるようなゆったりとした大きなうねりを感じることができる。凛と響くメロディと、味わいと温かみの感じられるMascisの歌声が哀愁を漂わせているのだ。パンクやハード・コアを好んで聴いているという彼自身の姿は楽曲の根底に沈み込み、美しい音像を描き出すことに成功している。その情景は周囲の空気をゆっくりと色褪せさせていくにも関わらず、不思議と心地がよいのだ。
-
-
DINOSAUR JR.
Farm
これはもう、何も言うことないわ。どこを切っても、DINOSAUR Jr.だ。J Mascisの声とか余裕で裏返ったりするのに、何でこんなにかっこいいんだろう。USオルタナ・シーンの最重要バンドの一つ、DINOSAUR Jr.オリジナル・メンバーでの再結成後2作目となる新作『Farm』。轟音で掻き鳴らされるディストーション・ギターに対して、Low Barlwもこれでもかとブリブリベースを弾き、Murphも叩きまくっている。そして、これぞDINOSAUR Jr.なメロディ、ヘロヘロのヴォーカル。笑っちゃうくらい何も変わらない。だけど、もう圧倒的に説得力が違う。3人の充実ぶりが轟音にはっきりと現れている痛快作。いやあ、最高にかっこいいでしょ。
-

-
Dinosaur Pile-Up
ELEVEN ELEVEN(Japan Edition)
変な例えかもしれないけど、もしNIRVANAの面影を求め、FOO FIGHTERSを聴いているリスナーがいるなら、このバンドを聴くことをオススメしたい。すでに3度の来日を実現させているイギリスはリーズ出身のトリオ。ROYALBLOODを手掛けたTom Dalgetyプロデュースのもと、完成させたこの3rdアルバムでは、そんな魅力がさらに感じられるようになってきた。60年代を連想させるポップ・センスがその他のグランジ・リヴァイヴァルのバンドと彼らの大きな違いだが、ヘヴィな演奏とキャッチーなアピールがひとつになったTrack.7「Might As Well」は、そんな魅力がひとつ頂点を究めたことを印象づける本作のハイライト。もちろんMOTÖRHEADばりの暴走で畳み掛ける終盤の流れも聴き逃せない。
-
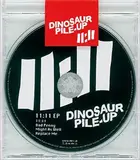
-
Dinosaur Pile-Up
11:11 EP
90'sオルタナ・ロックの醍醐味を現代に蘇らせる英リーズ出身の3人組。昨年に引き続き、今年も"SUMMER SONIC"に出演する彼らが4曲入りのEPをリリース。現在のライヴのラインナップでレコーディングしたことに加え、ROYAL BLOODを手がけたプロデューサー、Tom Dalgetyを迎え、轟音のロック・サウンドはさらにパワーアップ。ヘヴィなリフを畳みかける表題曲、MOTORHEADにオマージュを捧げた「Bad Penny」が新境地をアピールしながら、「Might As Well」では轟音のギター・サウンドとポップなメロディを組み合わせるというこのバンドの真骨頂を改めて印象づける。「Replace Me」は彼らのルーツを物語る正調グランジ・ロック。
-

-
Dinosaur Pile-Up
Nature Nurture (Japan Edition)
今年8月、知る人ぞ知る存在だったにも関わらず、爆音を轟かせたパワフルなパフォーマンスによって、SUMMER SONICを沸かせたイギリスの3人組。その彼らの日本デビュー盤となる2作目のアルバム。日本盤化にあたって、アルバム収録曲と比べても何ら遜色ない6曲が加えられている。バンドもその影響を認めているように、そのサウンドはNIRVANAを始めとする90年代グランジ直系。今時、珍しいと思えるぐらいシンプルな演奏が痛快というか、潔い。それはやはり曲のクオリティに加え、思いっきり歪ませたギターの爆音は何にも代えられないほどかっこいいという自信があるからだろう。時折WEEZERを連想させながら、そこまで泣いているわけではないメロディにもこのバンドらしさが感じられる。
-

-
Dios
CASTLE
かつて、ぼくのりりっくのぼうよみとして活動していたたなか(Vo)が、世界的ギタリストIchika Nito、ぼくりりを手掛けていたビートメイカー、ササノマリイ(Key)と組んだ新バンドの1stアルバム。R&Bを基調にした全12曲。ダイナミックなバンド・サウンドとエレクトロニックなトラックの融合、ノスタルジックなジャズを思わせる異色のダンス・ナンバーのTrack.2をはじめとする曲の振り幅、ヒリヒリとした歌詞――聴きどころはあまりにも多いが、一番はやはり、3人がそれぞれにフロントマンという自覚を持っているに違いないスリリングなアンサンブルだ。ヴォーカリストを楽器隊が支えるという固定観念は通用しない、言い換えるなら、強烈な個性が溶け合う奇跡のバランスという表現が相応しい。
-

-
DIRTY PROJECTORS
Lamp Lit Prose
メンバーとの別離で失意の色が濃かったセルフ・タイトルの前作から一転、Dave Longstreth(Vo/Gt)、および現在を生き抜く再生のパワーを実感させる新作。音数を少なく、印象的なサウンドで構築するサウンド・プロダクションはこれまでの手法を踏襲しつつ、今作の鍵はギター、ホーン、そしてDaveの優しくもアップリフティングな声だ。Syd Tha Kyd(THE INTERNET)の声も印象的な、ウォームなソウルがオーガニックに響く「Right Now」、FLEET FOXESのRobin Pecknold、元VAMPIRE WEEKENDのRostam Batmanglijが参加し、3声のテノールが醸し出すハーモニーが緊張を解く「You're The One」など、光に満ち溢れた仕上がりに。丁寧な音の構築がその明るさに真実味を添え、深い感銘を受ける。
-

-
DIRTY PROJECTORS+BJöRK
Mount Wittenberg Orca
特設サイトにてデジタル配信のみでリリースされていたアルバムが完全生産限定で待望のCD化。DIRTY PROJECTORSとしては2009年の『Bitte Orca』以来のリリースとなる。Björkを招いて制作された今作だが、楽曲は全てリーダーのDave Longstrethが手掛けたものだ。ドラムとギターが一切使用されていない楽曲群を彩るのは、圧倒的なヴォーカル・ハーモニー。感情を揺さぶるBjörkの歌声と甘く優しいDaveの歌声、妖精のように無邪気で煌びやかな女性メンバーのコーラス。肉声だからこそ出せるしなやかさとアンサンブルは、シンプルで力強く、一点の曇りも無い純粋さに溢れている。Daveのハーモニーへの探究心の結晶と言うべきだろう。前人未踏のファンタジーがここにある。
-
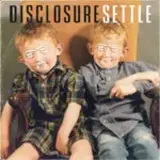
-
DISCLOSURE
Settle
noneイギリスは南ロンドン出身の兄弟エレクトロ・ダンス・デュオ、DISCLOSUREの1stアルバム。兄のGuyは21歳、弟のHowardは18歳とかなり若いユニットだが、実際、このふたりの作る音楽からは、若さゆえの瑞々しさとロマンティシズムが溢れている。90年代のクラブ・シーンからの影響を強く思わせる音作りながらも、昨今のR&Bに通じるしっとりとした甘さ、インディー・ロックとも通じる力強いポップネスも放出するこの音像は唯一無二。この無邪気さとキャッチーさは、イギリスにおけるtofubeatsのような存在と言えるかもしれない。ALUNAGEORGEやJessie Wareといった客演との相性のよさ、その華やかさも手伝って、本国のチャートでは初登場1位を獲得。9月に来日も決まっており、この夏をより熱くすること必至。
(天野 史彬)
ダンス・ミュージックとは即ち、絶え間のない変化の連環の中で、万物は微かな軋みと共にゆっくりと位相していく、という定理を分かり易く示す1つの行為である。それは"はじまり、やがて、おわる"というサイクルの中に生きる人間存在の縮図でもある。本来、Settle(定着)という言葉、概念は存在し得ない。このロンドン出身の兄弟デュオの作品はその理を見事に体現している。ステディなビートの中に入れ替わり立ち替わり現れる、昨年から今年にかけてポップ・ミュージックの地平を一変させたアーティストたち。門戸を多くの人々に開きながら、DISCLOSUREは1つの真理を教えてくれる。冒頭の牧師の説教にあるように"すべてはいつか変わってしまう"のだ。だから、僕らは今、踊る。
-
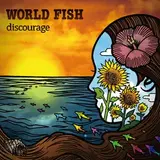
-
discourage
WORLD FISH
奄美大島出身のメンバーを中心に結成された4人組ロック・バンドの1stフル・アルバム。まずジャケットの無国籍ともとれるイメージのアートワークに惹かれてしまうのは都会での生活に疲れている証拠なのだろうか(笑)。その内容は日本の島特有の地元感満載の音楽かと思いきや、クリアな音質で迫ってくるエッヂの効いたロック・サウンド。榮広大(Vo/Gt)が描く魚や蝶、海をモチーフにした歌詞はその伸びやかなヴォーカルとマッチしており、鋭い演奏との絶妙のバランスでオリジナリティを成り立たせている。リゾート・ミュージックの緩い感じを連想して聴くとガツンと頭を殴られるインパクトがあり、「OLD FISH」「春をこえて」といったドラマチックな曲にはつい涙腺が緩んでしまう。大きな舞台で聴いてみたくなる、スケールを感じさせてくれるアルバムだ。
-

-
DISCOVERY
LP
柔らかな電子音と少し懐かしさ漂うメロウなメロディが調和するVAMPIRE WEEKENDとRA RA RIOTのメンバーが合体したDISCOVERYのデビュー・アルバム。大学時代からの友人という彼らが作り出す楽曲は何処か肩の力が入ってないというか、すんなりと体にしみ込んでくる。ただ、サイド・プロジェクトという枠の中で楽しもうという彼らの自由な雰囲気も伝わってくるのだけど、それだけで片付けてしまうには惜しい極上のメロディが並んでいて、決して片手間でやっているという感じはしないとても絶妙なさじ加減。エフェクトを加えたヴォーカルのエレ・ポップ・サウンドというと少しノスタルジックになってしまうんだけど、このアルバムからは前向きな新しい感覚を与えてもらえる。2009年を代表するサウンド・トラック。
-

-
DJ BAKU HYBRID DHARMA BAND
D.E.F
オリエンタルな空気の立ち込める中、スクラッチを合図に一瞬にして轟音と電子音の渦に放り込まれる。一発目「D.E.F」で、一気に勝負仕掛けたのだ。左右から迫る音と咆哮の洪水に飲み込まれる。神経が沸き立ち、覚醒させられるようなサイケデリックな音が一秒一秒と昂ぶりを見せる。バンド・サウンドでありながらも、DJを主体として打ち込みと生楽器による音の作りが強烈にハイブリッドな音を放っている。DJ BAKUによる16種のループを基本として構築された音は、様々な要素が絡み合っているにも関わらず、無駄が削ぎ落とされ完璧にソリッドだ。圧倒的な存在感が脳を直接揺さぶり、歪んだ音が重いビートに乗って鼓膜に突き刺さる。聴く者は自然と身体が揺れる。比喩的表現ではなく、本当に身体が揺さぶられるのだ。
-
-
DJ KYOKO
XXX“If You Came HERE”
DEX PISTOLS、80kidz、DJ KYOKO。いずれもここ1~2年の間に“エレクトロ” という言葉を、コアなリスナーから一般層にまで広めた功績は言うまでもない。それぞれに活動の幅やプレイの質は色々だけど、DJ KYOKOはあくまで一人のDJ、セレクターとして、その確かな実力とセンスに裏打ちされたプレイでフロアを沸かせてきたアーティスト。そんな彼女のMIX CD第2弾が、2010年のバレンタイン当日にリリースされる。全体を通して、快楽性が高くも、リズムと音階を自在に操りながら、非常に整理されているプレイは流石の一言。きっと音楽に対して、自由な感覚ではありつつも、もの凄く真面目な考え方をしている人なんだろうなと思う。
-
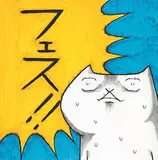
-
DJ和
フェス、その前に
2016年2月に発売された、レコード会社の垣根を越えてフェスで盛り上がる邦楽ロック40曲を集めたノンストップCDのロング・ヒットを記念して、芦沢ムネト描き下ろしの人気キャラクター"フテネコ"ジャケット仕様で新装発売。KEYTALK「MONSTER DANCE」に始まり、ラストのマキシマム ザ ホルモン「恋のメガラバ」まで、新旧の人気楽曲を絶妙な繋ぎ方で飽きさせることなく聴かせてくれる。中にはJUDY AND MARY、BEAT CRUSADERS、NIRGILISといった現在活動していないバンドの曲も入っており、最近音楽にどっぷりハマりだした世代にとっては現在進行形だけではない名曲との出会いになるはず。強烈なインパクトのジャケットはもちろん、スリーブ裏面のフテネコによる"フェスあるある"も最高に楽しい。聴いたり見たりしているうちに絶対フェスに行ってみたくなる1枚。
-

-
DJみそしるとMCごはん
ジャスタジスイ
待望のメジャー1stアルバムです。参加アーティストがすごいです。片想いにNORIKIYOに夢眠ねむ(でんぱ組.inc)に、果てはSHINCO(スチャダラパー)まで召喚。今最もヒップなバンドとラッパーとアイドルと、そしてレジェンド級のトラックメイカーまでもが、何故、この食べ物のことばかりラップしている女の子のアルバムに集まるのか? それは、美味しいものには垣根なんてないからです。食卓とは、みんなが集まれる日常の中の楽園だからです。そして僕らは、食べなきゃ生きてはいけないのです。"食"とは、僕らの過去と今と未来を繋ぐ生命活動で、だから彼女のラップは、懐かしくて最先端で、そして未来そのものなんです。人との繋がりも歴史の繋がりも分断されつつある今の僕らにとって、とても大事な音楽がここでは鳴っているのです。
-

-
DJみそしるとMCごはん
おりおりのおりょうり~X'mas~
ストリートから立ち上がった反抗の音楽であるヒップホップは、2013年の日本ではこうなる。今年7月にリリースされた『Mother's Food』が話題を呼んだラッパーDJみそしるとMCごはん(こんな名前だけどソロ・ユニット)のメジャー・デビュー作。料理を主なモチーフにしたリリック。アートワークやMV、ファッション性において徹底してDIYな手作り感を残した作風。この生活観漂う牧歌的な佇まいはしかし、新世代の反抗のアティチュードなのだと思う。知らない誰かが煽る目に見えない希望と、PC画面の向こう側からじわじわと襲い掛かってくるシニシズム。この不確かな現代社会において、生きるために食べること。食卓でそれを誰かと分かちあうことは、私たちに残された数少ない確かな実感の伴う幸福なのだ。切実でクレバーな女の子だと思う。
-

-
DMA’S
How Many Dreams?
幸福感溢れるシャイニーなギター&エレクトロの洪水の中で、"How many dreams"のリフレインが響くタイトル曲で始まる、豪州発バンド DMA'Sの4thアルバム。90年代UKロック、シューゲイザーなどをルーツにし、ブリットポップの再来と評されたそのサウンドが磨かれたのはもちろん、甘めのメロディ&歌や曲を印象づけるリフの存在感、キャッチーさが際立っている。その骨格が美しいからこそ、どんな装飾やアレンジも映える。Rich Costey(SIGUR RÓS/MUSE etc.)とKonstantin Kersting(TONES AND I etc.)がプロデュースしたシングル「I Don't Need To Hide」での、ミニマルで恍惚感のあるダンサブルなサウンドから、OASIS直系の「Forever」、ポップでサイケデリックな「De Carle」など、新しさとどこか懐かしさがある、いい香りがする作品。
-

-
DMA’S
For Now
"OASISの再来"と謳われたオーストラリアの3ピースが、デビュー・アルバムから約2年、成長を遂げて帰ってきた。ブリットポップを基礎とした方向性はそのままに、セルフ・プロデュースであった前作とは趣向を変えて、今作では、同郷のエレクトロニック・デュオ、THE PRESETSのKim Moyes(Dr/Key)を共同プロデューサーに迎えている。そのため、コンパクトで親密感のあるサウンドだった前作と比べると、シンセを取り入れるなどして音の厚みも増し、さらに打ち込みのリズムも取り入れたことで、音楽性の広がりを見せているのだ。それだけでなく、Tommy O'Dell(Vo)の哀愁漂うヴォーカルも表現力がアップし、それぞれの楽曲に自然に溶け込み、気持ち良く聴くことができる。
-

-
DMA’S
Hills End
2015年11月に初来日公演を行ったオーストラリアはシドニー出身の3ピース・バンドによるデビュー・アルバム。主にJohnny Took(Gt)の寝室でレコーディングされたというセルフ・プロデュース作で、前作EPにも収録されており、地元で大ヒットしたというTrack.3「Delete」を始め、Track.4「Too Soon」、Track.5「In The Moment」など、その楽曲には影響を受けたことを公言しているOASISやTHE STONE ROSESを彷彿とさせるウェットさと浮遊感があり耳馴染みが良い。ノイズの洪水に包まれて後半に向けて破壊的な展開をみせるTrack.8「Melbourne」やカオティックなTrack.12「Play It Out」では単なるブリット・ポップのリバイバルに終わらない気概を見せている。ダサかっこいいヴィジュアルも含めて日本で愛される要素満載のバンドだ。
-

-
DMA’S
DMA'S
オーストラリア・シドニー出身の3ピース・バンドのデビューEP。海外ではすでに2015年5月にリリースされたEPだが、11月に代官山UNITで行われる単独来日公演に合わせ、ボーナス・トラック2曲を追加収録した日本独自企画盤となっている。NMEではOASISの後継者として取り上げられるなど、新世代のギター・ロック・バンドとして期待されている彼ら。Track.1「Laced」とTrack.2「Your Low」の湿り気のないカラっとしたギター・サウンドだけを聴くとちょっとイメージが沸かないが、Liam Gallagherに似た雰囲気を持つTommy O'Dell(Vo)の声で歌われるTrack.3「Delete」の憂いを帯びたメロディを聴くと、確かにOASISの「I'm Outta Time」のようななんとも言えない余韻が心に残る。後半はやかましいサウンドも聴けるが、楽曲は全体的にフォーキーな印象。
-

-
DOES
道楽心情
活動再開したDOESの新曲は映画"銀魂 THE FINAL"の挿入歌である「道楽心情」、「ブレイクダウン」とカップリングの「斬り結び」という、前向きな戦いと友情がベースにある3曲。プリミティヴなビートでお祭り騒ぎに火をつける「道楽心情」は、シンセやピアノなど同期も効果的に配置され、映画の空間に身を投じるような感覚も。古典的な日本語も用いながら普遍的な生への渇望が描かれた歌詞も極まった印象。クランチなリフと8ビートの「ブレイクダウン」はキャラクターの哀愁や記憶を映したメロディの美しさにも注目。また、本音をぶつけ、殴り合うほどの魂のやりとりが表現された「斬り結び」は"銀魂"の世界観であると同時に、今、渇望している人間の本能を呼び起こす。
-

-
DOES
INNOCENCE
"ああ、この人、丸腰だなぁ"と思える人にはしっかり自分の軸や品性があるものだが、DOESのデビュー10周年となる今作にもそんな印象を持った。まず、メジャー・キーで「曇天」のアンサー・ソングだという「晴天」から始まり、"最高の今がある"と歌う「KNOW KNOW KNOW」が続く。コンパクトで必要な音がクリアに鳴っている「千の刃」では、新しいサウンドメイクに耳が行くし、エロティックな歌詞がどこか歌謡曲的な軽快ささえ漂わせる「熱情」。ブルージーなコードもクールに聴かせることに成功している。どの曲にもロックの粋が詰まっているのだが、極めつけはラストに置かれたシンプル極まりないパンク・ロックの「ロックンロールが死んで」だろう。意味深なタイトルの意味はアルバムを聴けば納得できるはず。
-

-
DOES
DOES
疾走感のあるビートとギター・リフ、憂いの滲む歌というDOES節を凝縮したシングル「紅蓮」を筆頭に、タイトな3ピース・サウンドを活かした前半。そして爆裂な高速ハードコア「殺伐とラブニア」や、レゲエ調の「問題」、能天気なサーフ・サウンドでありつつヒネくれた展開でサイケデリックな幻影すら見せる「アイスクリーム」など中盤では一気にサウンドスケープが広がり、何でもありの様相となる。「ブラック・チェリー」などはもともと、いわゆるLINKIN PARKのようなモダンなヘヴィ・ロックをやろうというところからスタートしたという。そんなふうに色とりどりでありつつも、どこまでもDOES節に落とし込まれているのが面白い。俺、俺、俺という押しじゃないし、むしろ肩の力が抜けているがしっかり己の色が出ているのが、今作の強さだ。
-

-
DOES
OTHERSIDE OF DOES
結成10周年を記念しアルバム完全再現ライヴなどを行い話題を集めるDOESからc/wベスト・アルバムがリリース。『SUBTERRANEAN ROMANCE』レコーディング時の未発表曲「ヒーロースター」、「ギンガムの街」の別ヴァージョン、今年の2月にZepp DiverCityで開催された10周年記念ライヴで初披露された新曲「遠くまで」を収録した全19曲を最新リマスタリングで収録している。カップリングだからこそ見せられるDOESやソングライターである氏原ワタル(Vo/Gt)の素の表情や音色が詰まった楽曲たちは、どの時代のものも鮮やかに響く。深層心理に入り込むサウンドスケープの「薄明」やライヴ感たっぷりの「S.O.S.O」など名曲も多く収録。DOESの歴史を違う側面(=OTHERSIDE)から楽しめるアイテムとなっている。
-
-
DOES
今を生きる
2012年DOESにとって初の作品となるシングルをリリース。メジャー・デビュー6年目となる今年、"3月11日の東日本大震災から1年、あの悲劇を忘れずに、これからの未来が輝かしい日々である為に今を精いっぱい生きよう"というメッセージが込められた今作は、新たなスタートを切った彼らを象徴する1曲だ。シンプルなコードとストレートな歌詞、決して派手な楽曲ではないかもしれないが、胸に突き刺さる力強さを内包している。彼らの真骨頂でもある日本語の歌詞がとてもしっくりと響き渡る。震災から1年というこのタイミングでリリースされたのも、 "忘れない"という彼らからのメッセージとして僕等はしっかり受け取るべきだろう。新たなアンセムの誕生だ。
-

-
DOES
FIVE STUFF
切れ味抜群のギター・リフとエイト・ビート――1曲目「イーグルマン」のイントロでいきなりノック・アウト。この生き生きとした躍動感、奮い上がるしかなかろう! 前作『MODERN AGE』から約7か月ぶりとなる本作は、DOES初となるミニ・アルバム。4人編成でのライヴを重ねてきたのが影響してか、カラフルなリフが特徴的なギター・アレンジが施され、前作以上に音の作りが立体的になっている。氏原ワタルのヴォーカルも非常に伸びやかで、この音に自分の声を乗せることを非常に楽しんでいるようだ。DOESは艶のあるクールなイメージが強いが、今作は最初から最後まで聴いても、どうしたって彼らがとびきりの笑顔で演奏している姿しか頭に浮かんで来ない。ポジティヴな空気がぎっしり詰まった全5曲。
-

-
DOES
MODERN AGE
モダン。現代的という意味を持つ言葉だが、日本においては少々古風な響きでもある。現代的なのに古風、それはDOESの音楽に通ずるものがあるのではないだろうか。歌謡曲の味を含む和風メロディと美しい日本語、そして洋楽的でスリー・ピースの枠に囚われないアレンジが施された、非常にカラフルなアルバムだ。氏原ワタルが「自分が好きなものの影響が出るのは当然」と言っていたが、その通りとはいえそれをサラッと言えてしまう彼にこれまでのDOESとは違う大きな余裕と度量を感じた。音にも詞にも“伝えたい”という意思と“伝えていく”という決意が迸っている。高らかに掲げられた新章宣言はどこまでも痛快で、心華やぐのも不可抗力だ。第二期DOESの充実した今と晴れやかな未来を感じられる、素晴らしいアルバムです、本当に。
-

-
DOES
ジャック・ナイフ
バンドの危機を乗り越え、再生した2009年。停止した遅れを取り戻すかの如く、精力的なリリースとライヴを重ねる2010年。この1年、止まる間も無くパワーを外へと発してきたDOESが、ライヴで育て上げた2曲を収めたシングルを叩き出す。足元から巻き上がる竜巻のような力強さと木枯らしのような哀愁が織り成す、膨らみのあるシンプルでストレートなバンド・サウンド。憂いと艶を帯びた和風メロディ。そこに乗る氏原ワタルの描く硬派なモノクロ映画のような詞世界。激情の先に踏み込んだ人間だけが手に入れられる冷静――これぞDOESの導いた研ぎ澄まされた刃さながらの輝きだ。小細工なしの真っ向勝負を挑む覚悟を決め、堂々と立ち向かう3人。一切迷いの無い音像に、ただただ痺れ、奮える。
-

-
DOES
SINGLES
日本語でロックンロールを歌える人って素直で尊敬してしまう。ロックは欧米から来た音楽文化。日本語をロックのメロディに乗せること自体、はじめから困難だった。しかしだからこそ、どこまで日本語で伝えられるのか?という困難な課題に立ち向かった日本のロック・バンドも沢山いた。DOES はその中でも存在感を放つロック・バンドだと思う。完全に日本語のはずなのにカッコイイ!いやカッコよすぎる氏原のソングライティングには毎回降参せざる得ない。最新シング ル『バクチ・ダンサー』が10万枚の大ヒット!ベストアルバムにはインディーズ時代の名曲から、ヒットシングル「修羅」「曇天」や新曲まで収録。DOES 入門編として是非聴いてもらいたい。
-

-
DOG MONSTER
PIMPA
ベース&ギターのツイン・スラップを打ち出し活動中の3ピース・ミクスチャー・バンド、DOG MONSTERの約3年半ぶりとなるニュー・アルバム。現代社会に生きる若者が感じる日頃の想いを、都市や商業施設などの名前も織り交ぜリアルに歌うのだが、それがエッジィなスラップ・サウンドに、chloe(Ba/Vo)の無機質な女性ヴォーカルで乗るのが特徴だ。さらに、EDMや、スクリームも取り入れたラウドなリード・トラック「smart born」をはじめ、曲によってシンセや変拍子を利かせたり、歌謡テイストさえ感じられるポップスになったりと、かなり広い振れ幅で聴かせる。また、「人魚姫」では歌詞を逆から読むと新たな物語が見えてくるなど、テクニカルな演奏面以外にも工夫が凝らされている。
-

-
Doit Science
information
“なんだ、これは!?” 聴き終わって真っ先に頭に浮かんだのは、物書きとしては情けないながらもそんな言葉だった。予想外のものに出くわした時、人間というものはなんてありきたりな言葉しか出てこないのだろう。奇想天外という四文字熟語を音で表したらこうなった、というような今作である。勿論、ただ奇天烈なだけではない。フレットレス・ベースを筆頭に弦楽器隊の波紋を描くような音の連なりは、非常にアーティスティックであり、異次元に迷い込んだような幻想感に溢れている。リスナーの脳を痺れさせていくその快感は“ドイ中毒者が多数発生した”という言葉も大げさではないことを思い知らされる。Doit Scienceの5年ぶりのニュー・アルバム、心して聴いていただきたい。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























