DISC REVIEW
D
-

-
DEAD POET SOCIETY
Fission
デビュー・アルバム『-!-』(2021年)が高く評価されたオルタナティヴ・ロック・バンドの2ndアルバム。名門バークリー音楽大学在学中に結成し、今はロサンゼルスを拠点に活躍している彼らは、"死せる詩人の会"というバンド名がしっくりくる、詩的でインテリジェントな魅力を持ったバンドだ。激しいサウンドを鳴らしながらも緻密で芸術性の高い音作りを感じる曲の数々。荒々しいギターと、高音のファルセットも用いた繊細なヴォーカルの対比も心地よい。本作はインダストリアル・ロックやガレージ・ロック・テイストのダークな響きを持った楽曲もあれば、COLDPLAYのようなスタジアム・ロックの爽やかなスケール感を持った楽曲もあり、才能豊かなバンドの有り余る表現欲を浴びるように楽しめるアルバム。
-

-
THE DEAD WEATHER
Dodge and Burn
Jack Whiteの70年代ブリティッシュ・ハード・ロック愛が3度炸裂! THE KILLSの女性シンガー、Alison Mosshartらと組んだ4人組が5年ぶりにリリースする3rdアルバムは、7インチ・シングルとしてリリースしてきた4曲のリミックスおよびリマスター・バージョンに新曲8曲を加えた全12曲を収録。ある意味、時代錯誤であることがテーマのひとつだったに違いないが、それを徹底的に追求したからこそ、ヒップホップの影響、エキゾチックなメロディ、レゲエのリズムが絶妙なアクセントとして効いてくるわけだ。ダイナミックなギター・プレイを披露しているDean Fertita(QUEENS OF THE STONE AGE)はもっと注目されてもいい。彼が加えるオルガンの古色蒼然たる音色も雰囲気ものだ。
-

-
THE DEAD WEATHER
Sea of Cowards
あまりにも唐突で、あまりにも衝撃的だったデビュー・アルバム『Horehound』から一年足らず。この4人の才能はどんどん加速していくようだ。凶暴なブルース・ブギは今回も留まることを知らない。図太くうねり、歪むリズムにViviとJack Whiteの鬼気迫るヴォーカリゼーション。うねりを上げるギター。そして、前作以上に際立つオルガンが妖しくも暴力的な輝きを放つ。この原始的なパッションに溢れていながら、とてつもない知性をも感じさせる全11曲、わずか35分。とてもそうは感じられないほどに濃厚で凶暴なロックンロールが全身を掻き乱すが、逆にそれはほとんど一瞬の出来事のようにも感じられる。ロックンロールが持つ刹那的な美しさを体感するのにこれほどピッタリなアルバムはそうそうない。
-

-
THE DEAD WEATHER
Horehound
WHITE STRIPESのJack WhiteとTHE KILLSのViviを中心とした新プロジェクト、THE DEAD WEATHER。この組み合わせでブルース/サイケ・ガレージをやるって、そんなの悪いわけがないけれど、それにしてもとんでもないことになっている。Jack Whiteという底なしの才能の箍が完全に外れている。音数最小、音量最大なリズム隊が生み出す凶暴な暗黒グルーヴとへヴィに歪み、軋みまくるギター。そして、Viviのダーティでドスの効いたヴォーカルが絡み合い、とぐろを巻く轟音サイケデリック・ガレージ。今が一体何年なのか分からなくなるが、そんなことはおかまいなしに、どこでもないどこかへぶっ飛ばされる異形の轟音ブギ。
-

-
Dear Chambers
Oh my BABY
昨年レーベル移籍し、サウンド・プロデューサーにKubotyを迎えて3作目となるシングル。3ピースながらひとひねりを加えた展開やコーラスなどのアレンジにより3曲3様、持ち前のグッド・メロディが全リスナーを包み込む心強い1枚が到着した。表題曲「Oh my BABY」は、愛しい人に笑っていてほしいと願うどストレートな歌詞がまっすぐなバンド・サウンドに乗せて響く。まるでモリヤマリョウタ(Vo/Gt)から直接語り掛けられているような、自分を全肯定してくれているような気持ちになる1曲だ。そして「まだ見ぬ君へ」を聴けば、音楽を通してバンドと繋がっていること、彼らの音楽が自分の味方でいてくれることを確信するだろう。最後は疾走感溢れる「ユートピア」が、ポジティヴな方向へと力強く背中を押してくれるはずだ。
-
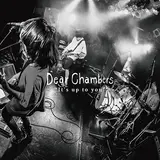
-
Dear Chambers
It's up to you
ゲリラ発表した自身主催のスタジオ・ライヴが手売りチケットのみで即日完売するなど、注目を集めるDear Chambersによる初のEP。1分未満のショート・チューン「Strikes Back」で勢いよく幕を開け、アップテンポでライヴ映え抜群な「ワンラスト・ラヴァー」、美しい夕焼けが脳裏に浮かぶ「青年時代」、夜を駆けていくようなスピード感の中に切なさが見え隠れする「幻に会えたなら」、至極のメロディに想いを凝縮したミディアム・バラード「本音」と、持ち味の疾走感溢れるサウンドと歌が引き立つグッド・メロディを詰め込んだ5曲が収録されている。そのままライヴのセットリストになりそうなラインナップでもあり、ライヴハウスの景色が自然と見えてくるのがいい。
-

-
Dear Chambers
Goodbye to you
それぞれに活動歴を持つ3人により2017年10月に結成されたDear Chambersの1stミニ・アルバム。彼らは銀杏BOYZ、Hi-STANDARD、ELLEGARDENを共通のバックボーンとして持っているそうだが、轟音で奏でる全6曲をユニークなものにしているのが、モリヤマリョウタ(Vo/Gt)が作る切ないメロディと昔の想いを綴った歌詞だ。そういうある意味女々しい歌を悲壮感たっぷりに歌うことに、自分たちの存在意義があると彼らは考えているという。曲はオルタナ調あり、青春パンク調あり、じっくり聴かせる曲あり、メロコア調ありとなかなか幅広い。歌を最大限に生かすシンプルなアレンジを追求しながら、バチバチと火花が散るような瞬間のある演奏も聴きどころだ。
-

-
DEATH CAB FOR CUTIE
Asphalt Meadows
アルバムとしては約4年ぶり10作目となる、デスキャブの最新作。近作は美メロを生かしたソフトで落ち着いた印象の作品が多かったが、本作ではいきなり強烈なパンチを食らわせる「I Don't Know How I Survive」を筆頭に、ザラついたラウド・サウンドが際立っている。ストレートなロック・ナンバーの「Roman Candles」や、スポークン・ワードとともに雄大なサウンドスケープを描く「Foxglove Through The Clearcut」、アッパー・チューンの「I Miss Strangers」から叙情的なメロディを奏でる「Wheat Like Waves」と、楽曲単体のみならずアルバム全体に静と動のコントラストを纏った、美しくも力強い楽曲が並ぶ。実験的でありながら往年のファンをも唸らせるであろう、結成25周年を迎えた彼らの革新性が光る。
-

-
DEATH CAB FOR CUTIE
The Blue EP
7月に行われた"フジロック"では豪雨の中でのパフォーマンスで観客を魅了したデスキャブが、新体制初のアルバムとなった前作『Thank You For Today』から約1年ぶりの音源となるEPをリリースした。前作で見せた生バンドとエレクトロニクスの融合を保ちつつ、より深い憂いを湛えた5曲を収録。ダイナミックなビートとフィードバック・サウンドが印象的なTrack.1、1999年に地元ワシントン州ベリンガムで起きた爆発事故で亡くなった少年たちを偲ぶ、ポップだが陰のあるTrack.2と、冒頭から癖のある楽曲が並び、バンドのプロデュースによるバラードのTrack.3、ドリーミーなクローザーのTrack.5と、約20分の中に魅力を凝縮。現体制での充実した創作意欲が垣間見える1枚だ。
-

-
DEATH CAB FOR CUTIE
Thank You For Today
グラミー賞にもノミネートされた前作『Kintsugi』から約3年ぶりとなる新作。ツアー・メンバーのギターとキーボードを正式に迎えたこともあってか、叙情的なBen Gibbard(Gt/Key/Vo)の歌メロや涙が出るような美しいアンサンブルはそのままに、シンセも含めた生バンドとしてタフ且つ研ぎ澄まされた仕上がりに。中にはアメリカン・ルーツ・ミュージックを思わせるギター・サウンドのプロダクションが印象的な「Gold Rush」や「Autumn Love」なども顔を出し、イノセントなまま大人になるこのバンドの静かで力強い意志を実感できる。現代アメリカにおいてデスキャブのインディー・ロック・サウンドは、30代以上のリスナーにとってはもはや、魂を癒す静謐なソウル・ミュージックなのかもしれない。心許せる親友のような作品。
-

-
THE DEATH SET
Michel Poiccard
メンバーの死を乗り越えて作り上げられた力強くとてもパーソナルなアルバムだ。THE DEATH SETの音楽をジャンル分けするならひとまずエレクトロ・パンク・バンドとなるだろうが、このアルバムはその枠を大きくはみ出したポップ・アルバムと言えるだろう。感情剥き出しのパンク・ナンバーやメランコリックなシューゲイズ・テイストのナンバーもありバラバラな印象も受ける。しかし全体を通して聴くとアルバムとしての完成度があるから不思議。それは今作のプロデューサーでありSPANK ROCKのトラック・メイカーであるXXXChangeの力が大きいだろう。彼らの持つポップ・ポテンシャルをグッと引き出し格段に聴きやすくなっている。困難に直面しながらも前を向く勇気をくれるそんなアルバムだ。
-

-
THE DEATH SET
Rad Warehouses To Bad Neighborhoods
オーストラリア出身、現在はボルチモアに棲息する奇天烈バンド、THE DEATHSETの来日記念編集盤。昨年発売され、一部の音好き(モノ好き?)の間で話題になったデビューアルバム『Worldwide』以前の初期EP2枚と、リミックスが収録されている。ハードコアを基盤に、エレクトロ、HIP HOP、PUNKをごった煮にした、ローファイで、ファニーな音楽が詰まっている。今作にリミックスも収録されているBONDE DO ROLEや、CSS、THE GO TEAMあたりを倍速再生させたような、陽性の破天荒サウンドは、まさに、極限まで振り切れたパーティミュージック。そのスピードについていくのに必死になりそうな、一筋縄ではいかない楽曲が並ぶが、その印象は驚くほどにPOPだ。
-

-
DEATH VESSEL
Island Intervals
2005年のデビュー作にはフィラデルフィアのフリーク・フォーク・バンド、ESPERSのメンバーらが参加していたので、そちらの文脈で語られることが多かった印象のDEATH VESSEL。しかし、久々に届けられた本作では、Alex Sommersの幻想的なアレンジによって、Joel自身の透明なヴォーカルの魅力がより一層強調され、時代を超越した不思議な"根無し草ルーツ・ミュージック"へと帰結している。近年ではJulianna Barwickが同じくAlexの下で録音し、ONEOHTRIX POINT NEVERらがミックスを同地でおこなうなど、USインディー勢とアイスランドとの距離が縮まっている印象だが、本作はまさにそうした動き(北米と北欧の美意識の融合)を象徴するものといえるだろう。
-
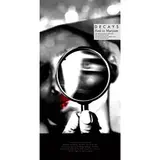
-
DECAYS
Red or Maryam
DIR EN GREYのDie(Gt)とMOON CHILDの樫山 圭(Dr)が中心となり2015年6月に始動したユニット"DECAYS"。DieがTHE NOVEMBERSの小林祐介(Vo/Gt)とともにツイン・ギター・ヴォーカルを務めていることも話題だが、特筆すべきはこのバンドのポップ・センスではなかろうか。シューゲイザーとダンスが融合し、そこにラップやデジタル・サウンド、ストリングスなどが入るという新感覚のミクスチャー。全曲が穏やかさと不穏さを併せ持つという統一性がありながら、シューゲイザーに寄せたTrack.3、ダークな側面を引き出したTrack.4、ポップ且つダークなTrack.6など1曲1曲が独立した確固たる個性を持っている。成熟の生む瑞々しい知的好奇心に舌を巻いた。
-

-
December
Alpha and Omega
2008年に結成されたポスト・ロック・バンド、Decemberの初の全国流通作品。本作は、新約聖書にある"全"、"永遠"もしくは"始まりと終わり"を意味する言葉をその名に掲げ、"1日の流れ"をテーマに制作。オープニングの哀しくも優雅なヴァイオリンの響きの裏にある、我々の生が背負う業や罪深さとそのすべてを許さんばかりの慈愛――それがそのまま今作の作品性を司っている。まさに贖罪のメロディと言わんばかりに美しさと瑞々しさを湛えるTrack.2、MOGWAIばりの吹き荒ぶシューゲイズ・サウンドを聴かせるTrack.3、ケルト的情緒を滲ませるシアトリカルなTrack.4と物語は続き、Track.7で無へと収束する世界にレクイエムを捧げ、Track.8で愛という名の浄化の光を以って幕を下ろす。我々は命の続く限り、夜を迎え、朝を待つ――ここにあるのはそんな生命の物語だ。
-

-
Declan McKenna
Zeros
デビューするや否や、矛盾と葛藤に満ちたこの世界を見据えた舌鋒鋭いプロテスト・ソングが歓迎され、社会派と謳われたイギリスのシンガー・ソングライター。デビューから3年。21歳になった彼がリリースした2ndアルバムは、楽曲の多彩さに可能性を見いだした前作から一転、ロックやライヴのエネルギーの影響を受け作り上げた。未来派というか、アートワークにも顕著な、宇宙派ガレージ/サイケなんて言えるサウンドは、巷間言われるDavid BowieやPINK FLOYDなど、かつてのブリット・ポップにも通じるUKロックの伝統が根っこにしっかりと息づき、マニアほど狂喜するに違いない。そういう作品が懐古調にならず、彼ならではと言えるユニークなものになっているところに大きな意味がある。
-

-
DEERHOOF
Deerhoof vs. Evil
OGRE YOU ASSHOLEとの東名阪ツアーや、ドラマーのグレッグがKIMONOSのアルバムにゲスト出演するなど、日本人アーティストとの交流も深く、世界各国で幅広く活動を続けるDEERHOOFの10枚目となるフル・アルバム。クリアになりすぎない音が刻む変拍子と、サトミ・マツザキの朴訥なヴォーカルの浮遊感が生み出す中毒性。何度も繰り返されるフレーズが脳内を支配し、その巧妙な罠に思考能力と体力を奪われていくようだ。飄々としているのに一切隙が無い。得体の知れないものに出会ってしまった気分だ。結成16年を迎えるが、"ベテラン"という完成形と言うよりは、まだまだ未知の可能性を秘めた若者のような空気感を帯びている。なんとも奇妙なバンドの、摩訶不思議なアルバムだ。
-

-
DEERHUNTER
Why Hasn't Everything Already Disappeared?
設立40周年を迎えた英国のインディー・レーベル、4ADを代表するDEERHUNTERが提示するバンドの新たな可能性。タイトル"Why Hasn't Everything Already Disappeared?(なぜすべてが消えていないのか?)"とアートワークを目にしたあと、本作を聴いて、まずその一文が頭に浮かんだ。カオティックな歌詞とテーマでありながら、華麗で儚いサウンドを調和させ、独自の世界観を形成してきた彼ら。今作の軸に据えるのはクラウト・ロックだが、ハープシコードやストリングス、ピアノが加わり、その音の鳴りはナチュラル且つクラシカルだ。このポスト・モダン的な手法により洗練された世界観はさらに深度を増し、美しさで空間を支配する。創意に満ちた1枚。
-

-
DEERHUNTER
Fading Frontier
ダークで不穏なガレージ・サウンドの中に甘美な側面を窺わせた前作『Monomania』とは一転、"いよいよBradford Coxは現世にいながらにして彼岸を見たのか?"と言いたくなるような、ドリーム・サイケなんて言葉では言い尽くせない世界観を提示してきた。すでにMVが公開されている、ミニマル・ファンクなビート感とサウンドが新鮮な――でもやっぱりどこか歪んでいるし揺らいでいる「Snakeskin」みたいな曲はこの曲だけ。彼らの名前を世界的に押し上げた『Halcyon Digest』を手掛けたBen Allenが今作もプロデューサーを務めているせいか、テクノ的なアンビエンスと生音のバランスは近いが、よりビートは後退。ぞっとするほど美しいメロが満載だ。
-

-
DEERHUNTER
Monomania
新しいアーティスト写真を見て驚いた人は、それ以上の衝撃をこの作品から受け取るだろう。フロントマン、BradfordがATLAS SOUNDの3rdアルバム制作後に陥ったパラノイアックでパーソナルな状況は混沌としたボーカリゼイションに、相反してバンド・サウンドは開放的で、思いつきをそのまま反映したようなノイジーかつノクターナル(夜の)ガレージで、むしろ無邪気なまでに開放的。これまでが半覚醒の睡眠導入音楽だったとしたら、今回は鬱屈し傷ついた魂を吐き出した生きるための音楽。ちなみにBradfordはLou Reedの『Metal Machine Music』が精神病を患う少年たちになぜか人気が高いことにインスピレーションを受けたのだとか。破綻寸前のアンサンブルも愉快で気高く聴こえるのもそのせいだろう。傑作。
-

-
DEERHUNTER
Halcyon Digest
08年リリースの前作『Microcastle』は各メディアで高い評価を集め、一躍USインディ・シーンの中心バンドの一つに上り詰めたDEERHUNTER。今思うと昨今のインディ・サイケポップ・ムーブメントの流れを作ったのはNO AGEとこのバンドである事は間違いないだろう。共同プロデューサーにANIMAL COLLECTIVEを手掛けたBen Allenを迎えた4作目は、水の中に吸い込まれるようなサイケデリアとATLAS SOUNDの流れを汲んだシンプルでポップなメロディ溢れる素晴らしい作品だ。緻密なサウンド・プロダクションはもちろん、圧倒的な美しさを放つ本作はサイケ・ポップというカテゴリーに収めるにはとても無理がある決定的な一枚。
-

-
DEERHUNTER
Microcastle
2008年、世界各地で大絶賛を浴び、ニューゲイザー・シーンの決定打となった『Microcastle』の日本盤がいよいよ発売される。ここまで日本盤が遅れたのは、本作が発売直前に急遽2枚組みに変更となり、日本のレーベルが対応できなかった為らしい。媚薬のように脳内に浸透してくる多彩で重層的な音と声を、一本の命綱のようなタイトなドラムが支える。DEERHUNTERにとって、ドラムがタイトでなければならない理由は、Bradford CoxのソロユニットATLAS SOUNDと比較するとよく分かる。Vo/GのBradford Coxが持つ表現衝動の危なっかしいまでの切実さが、フィードバックノイズの向こうから滲み出てくるが、その危うさをギリギリのところでポップに昇華しているところにDEERHUNTERの魔法がある。
-

-
THE DEER TRACKS
Eggegrund & Aurora
SIGUR ROS、MUMやMEWあたりを連想させるスウェーデンの男女デュオTHE DEER TRUCKS。本作は彼らのデビュー・アルバムと新作、さらに未発表曲も加えた2枚組となる。エレクトロニカやフォークトロニカからポストロックまでを内包した美しいサウンドスケープと女性Vo、Elinのウィスパー・ヴォイス。そして、巧みに強弱をつけた展開力が彼女の感情表現の幅広さを際立たせている。常に振り切れた感情を走らせるのではなく、感情をコントロールし、その頂に到達した瞬間のカタルシスを生み出す彼ら。その分彼らの美しいサウンドスケープやビートにははっきりとした輪郭があって、幽玄を彷徨うというよりは、幽玄の中でも目指す場所までしっかりとガイドしてくれているような安心感を与えてくれる。
-

-
DELOREAN
Subiza
昨年リリースされた『Ayrton Senna』EPに収録されていた昨年屈指のダンス・アンセム「Deli」が収録されていないのは少し残念な気もするけれど、待ちに待ったDELOREANのニュー・アルバムが完成。EPにあったキラキラとしたエレクトロとバレアリックなサウンドがより完成され、全体としてとても統一感ある仕上がり。ダンス・ミュージックとしての機能性も高いが、シリアスな所はなくそれでいてアゲアゲになり過ぎてない所もいい。彼らに向けられた期待感にバッチリ答えた作品と言えるだろう。女性ヴォーカルがループされる「Infinite Desert」のドリーミーでポップな展開も、「Stay Close」の加速してゆく爽快感もこれからの季節にぴったり。
-

-
V.A.
Trademarks01
最新で最旬の新世代インディ・アーティストを詰め込んだ好企画盤。NEON INDIAN、WASHED OUT、YES GIANTESS、DUCKTAILS、TORO Y MOIなど、これからが楽しみなアーティストばかり。エレクトロ、インディ・ロック、ポップまで実験的なメロディとリズムを満喫できる1枚。個人的には、NY出身4人組THE AMPLIFETESの「It's My Life」のベースとエレクトロの挑戦的なリズムサウンドがクセになりそう。そしてスペインはマドリードを拠点とする4人組DELOREANの爽快感溢れるポップ・ナンバー「Deli」はなんとも清々しい。全体的に様々な音が沢山詰まっていて、おもちゃ箱をひっくり返したような感じだ。
-

-
DELPHIC
Collections
デビュー作『Acolyte』で、既にエレクトロ・ロックの寵児というか、10年代ロックのど真ん中に躍り出た感のある彼ら。約3年ぶりの新作では、なんとも大人っぽく、さらにヴォーカル・オリエンテッドなバンドに変化した印象だ。ANIMAL COLLECTIVEやMASSIVE ATTACKを手がける複数のプロデューサーが関わっている遠因は、プリミティヴなビートやスケール感に伺えるが、彼らはもうダンス・ロックの狭義の枠にいないし、エレクトロは楽曲をさらにエモーショナルに届ける楽器のひとつでしかないんじゃないだろうか。どこかCOLDPLAYを想起させるピアノ・サウンドのTrack.3、ソウルフルといっても過言じゃないTrack.9や、RADIOHEADの不穏さとラップが遭遇したようなTrack.10など、独特でありつつキャッチーというある意味、現代の王道。これを大味ととるか成長ととるかは聽き手の嗜好次第。
-

-
DELPHIC
Acolyte
「何事も無く過ぎていく今日」とリフレインされる2009年屈指のアンセム「Counterpoint」1曲で全世界の注目を集めたDELPHIC.。SUMMER SONIC09ではトップバッターながら沢山の観客を集め、11月に行われた来日公演も大盛況のうち幕を閉じた。みんなが首を長くして待っていたアルバムというのはまさにこの一枚の事だろう。90年代のダンス・ミュージックにマンチェスターの伝統から受け継ぐメランコリックなメロディ。この二つを掛け合わせただけなのにどこまでも新しい。「Counterpoint」に並ぶキラー・トラックも兼ね備えながら、アルバムは川の流れの様に統一感があり且つ美しい。2010年の始まりを告げる傑作。
-

-
V.A.
KITSUNE MAISON COMPILATION 8
KITSUNE MAISON、この間7が出たばかりなのに、もう8がリリースですか。相変わらずのスピード感。それだけ、面白いインディ・バンドが多いということなのか、それとも流行のサイクルがさらに加速しているということなのか。今回も、TWO DOOR CINEMA CLUBやDELPHICといった今が旬のアーティストから、THE DRUMS、MEMORY TAPESを始めとした、これからのアーティストをコンパイルした充実の内容。ディスコ・ポップからエレクトロ、インディ・ロックまで、ヴァラエティの豊富さとコンピとしての統一感を両立させているところはさすがの仕事。今の潮流をしっかりと追い続けているからこそ・・・と、言うよりは先導しようとしているからこそと言うべきか。
-

-
DeNeel
導火 / ブラックアウト
今年1月に初ワンマンを終えたばかりの4人組バンド、DeNeelからシングルが到着。アニメ"キングダム"第5シリーズOPテーマとドラマ"彼女と彼氏の明るい未来"主題歌を収録、という情報からもバンドの勢いは伝わるだろう。オリエンタルなイントロからリスナーを一気に世界観へ引き込む「導火」は、メタルのような重厚感を湛えたバンド・サウンドで戦の厳しさと激しさを表現。クリアなヴォーカルが戦う人の強い意志を象徴しているようだ。対して、キャッチーなギター・リフから始まる「ブラックアウト」は踊れるロック。バンドの得意とする歌謡曲調のメロディに乗せて、恋に翻弄される心を歌いつつ、調や拍子、ダイナミクスの操作などによって、言葉の奥にあるものを描いている。
-

-
DeNeel
SYMBOL
約1年半ぶりのミニ・アルバムが到着した。オープニングは、リリック・ビデオの再生回数も38万回超えで好調の「百鬼夜行」。きらびやかな都会を"乾いたこの街"と表現し、きれいなものの裏側を描くクールなロック・チューンだ。続いて3拍子のテンポで、怪しげな音像から突如ロマンチックな香りを漂わせる不思議な1曲「円舞曲」、重めのイントロから新境地を感じさせるリード曲「煙」、歌謡曲的な要素をモダンにアップデートする、彼らの掲げる"OSAKA REVIVAL POP"が色濃く表れた「黒く、彗星」、アーバンなシティ・ポップ的チューン「サヨナラ」と、趣はそれぞれに違いながらも、ダークさと妖艶さを全7曲で貫き通す。バンドの向かうべき方向が固まり始めたという彼らのマイルストーン的作品。
-

-
DeNeel
MASK
大阪から昨年上京し、現在東京で活動中の4人組バンド、DeNeelから初の全国流通作品が到着。"OSAKA REVIVAL POP"を掲げる彼らの曲は、ダークなムードを纏ったずっしりした感覚のあるロックでありながら、各音が洗練された"踊れる"仕上がりになっている。そこにフロントマン 中野エイトの、艶がありつつも言葉を届ける意志のあるヴォーカルが乗り、一曲一曲の輪郭をよりくっきりと浮かび上がらせる。外から見える自分と、自らで思う自分とには差があり、見る人やタイミングによっても様々な人物像がある。そんな"MASK"=仮面について、リード曲「IF」を皮切りに気持ちを巡らせた全6曲。バンドの新境地的サウンドのラスト・チューン「Some day」まで聴き終えたとき、胸がすく思いがした。
-

-
DENIMS
RICORITA
すべてをDIYで取り組んできたDENIMSの4thフル・アルバム『RICORITA』。2本のギターが絡み合う「Journey To Begins」のチェンバーな音像に、自身のスタジオで制作する光景と旅の始まりを告げる空気感が重なり合う。爽快なカッティング・リフの虜になる「Sleep Well」、初のスカを軽やかに乗りこなした「春告」など、色とりどりな楽曲で構成された本作。ファンク、ソウル、時にロックと多様なジャンルを奏でる縦横無尽なグルーヴが心を弾ませ、踊らせる。様々な感情が詰まったジャケットからも垣間見える、緩さの中に秘められた覚悟や、"バンド"という旅を続ける彼らだからこそ見える情景は純度を保ちながら音に凝縮された。初期衝動はそのままに、新しい春の訪れに向かって熱が迸る本作は、DENIMSのさらなる飛躍を期待できる1枚だ。
-

-
DENIMS
makuake
前作以降、V6のメンバーによるユニット Coming Centuryへの楽曲提供もしてきたDENIMSの2ndアルバムは、そんな活動の影響もあるのか、R&Bを軸にしながらも、日本人のポピュラリティにも寄り添ったような印象を受ける。ファンキーながら暑苦しくはなく、ブラック・ミュージックのリズムではあるが、メロディが美しくエモーショナル。しかし2本のエレキ・ギターは相変わらずロック・バンドたる存在感を一際放っている。スタジオ・セッションの一幕のような短いインスト曲を境に、ジャンキーでサイケデリックなTrack.7、はっぴいえんどの香りもするTrack.8と表情をくるくる変え、リスナーを驚かせたままエンディングへ。2ndにして"幕開け"を掲げるバンドの進化と茶目っ気が窺える作品だ。
-

-
D'EON
LP
THE BIG PINKやPEAKING LIGHTSといったアーティストのリミックスを手掛け、GRIMESとスプリット・シングルを発表したことでも話題を集めた、新進気鋭のアーティストD’EON(ディオン)。今最も注目されているLAの最先端レーベルHippos in Tanksから待望のアルバムが遂にリリース。ソウルフルな歌声が男らしさを感じさせる一方、繊細で特徴的なリズムを奏でるシンセ音がなんとも切ない。スネアやクラップ、キックにハイハット、それに輪をかけてリムショットやトムトム、カウベルなどのエキゾチックなパーカッションを組み合わせた構成によって、革新的で創造的な音を可能にした唯一無二の1枚となっている。
-

-
depthqueuing
For My Adolescence
激しいドリルンベースや、クールなエレクトロニカなど、ストイックなインスト曲をネット上で発表してきた島根県在住のトラック・メイカー、depthqueuingの初となるフィジカル作品。本名も明かされておらず謎の多い彼だが、音楽センスは抜群で、エレクトロな要素を随所に交えつつも、ポップやオルタナティヴ、ポスト・ロックなどを通過したサウンドを主体に展開されていく。初期衝動溢れる詩的なヴォーカルも、電子音楽ならではのくぐもった質感とマッチしており、独特な世界観を生み出している。そんな中歌われているのは、危ういほどに透明な"Adolescence=思春期"の甘酸っぱさと、いつまでも心にぼんやりと残っている青々とした感情。不意に蘇る"あの日の思い出"のように、ふとしたときに聴きたくなる1枚。
-

-
Derailers
A.R.T
ラップとロックの融合という意味ではミクスチャーと言えるものの、いわゆるラウド系とは違うピースフルな魅力が彼らの個性を際立たせている。ラガマフィンDJとして活躍してきたRueed(Vo)と華々しい共演歴を持つAi Ishigaki(Gt/ex.THE MAD CAPSULE MARKETS)、Ju-ken(Ba)が結成したトリオによる1stアルバム。ホーンも使い、ファンキーに迫るTrack.1「Master Blaster」を始め、ラウドなギターが炸裂するロック・ナンバーとレゲエ・バラードのTrack.7「MARY JANE」他、メロウ・ナンバーの2本立て。Track.5「I'm Free」、Track.8「Coolin'」からはニュー・ソウルの影響も窺える。より成熟した音楽を求める志の高さ。そこに3人の矜持を感じずにいられない。いち音楽ファンとして大いに共鳴。
-

-
DESMOND & THE TUTUS
Mnusic
フランスのTIGERSUSHIからリリースされた『KISS YOU ON THE CHEEK』と日本のEVERY CONVERSATIONからリリースされたアナログが話題になり、FLAKE SOUNDSでリリースの『TUCK SHOP』が大ヒットしたDESMOND & THE TUTUSの2ndアルバムが遂にリリース!全編を通じてローファイでハッピーでピースフルな極上のインディー・ポップが詰まった前作を凌ぐ快作。track.1の「Tatoo」から、アレンジで特異なギミックは使わないで跳ねるリズムと丸くうねるベース・ライン、そして子気味よく刻まれたギターになにやら楽しげなヴォーカルと、緩さを持ちつつソリッドなグルーヴが超心地良い!個人的にはTrack.4の「The Future」のちょっと物憂げなヴォーカルと浮遊感のあるメロディと4つ打ちビート、track.6「More It」のちょっとバルカンっぽさも感じるギター・サウンドがツボです。
-

-
DETROITSEVEN
NUDE
今年1月にリリースされたミニ・アルバム『FRESH』では様々なゲスト・ミュージシャンを迎え入れ、新しいアプローチをした彼女達。フル・アルバムの今作では、『NUDE』というタイトル通り"ありのままの3人の姿"をはちきれんばかりに詰め込んでいる。菜花知美の切れ味抜群のディストーション・ギターと、攻撃的でいてふくらみを帯びたヴォーカル。それをがっしりと支える、スケール感のある重厚なベースとドラムのリズムが耳を劈く"ガレージ・ディスコ"。メンバー3人の本気が激突する尋常じゃない破壊力は非常にポジティブで、その爽快感に満ちたサウンドに自然と笑みがこぼれる。近年の精力的な海外でのライヴ活動で培ったタフネスの賜物だろう。結成10年目前、培ったスキルとキャリアは伊達じゃない。
-

-
DETROITSEVEN
FRESH
detroit7と様々なアーティストとのコラボレーション・アルバム。TOKYOエレクトロの新世代DJユニットMYSS、DUCK ROCKとのコラボレーションでは、00年代以降のエレクトロをdetroit7印の荒々しいガレージ・サウンドで仕立て上げた、縦ノリ・エレクトロ。元晴(SOIL & PIMP SESSION)のサックスが吹き荒れる「PEANUTS BUTTER BOMB」はノー・ウェーヴのようなパンク。金澤ダイスケ(フジファブリック)とはオルタナティヴ魂全開に疾走し、安部コウセイとは柔らかなバラードを披露する。しかし、新たなスパイスを与えられたdetroit7には全くぶれがなく、オルタナティヴなロック・バンドという根幹がより浮き彫りになっているところが面白い。
-

-
DETROIT SOCIAL CLUB
Existence
KASABIAN、PRIMAL SCREAMのグルーヴと土臭いブルースの薫りに、HAPPY MONDAYSのヘロヘロの恍惚も少し加える。UKロックの伝統とも言えるあのメロディとグルーヴを携えたDETROIT SOCIAL CLUBのデビュー・アルバム。「Northern Man」のような芯の太いロックもさることながら、煌くような美しさを放つダウン・テンポの「Universe」が特に秀逸。2010 年の「Loaded」となるか? これぞUKロックなメロディも、そのソング・ライティング力の高さを感じさせるし、OASIS、PRIMAL SCREAMの前座に抜擢されたという話も納得の実力派。ファーストとしてはTHE MUSIC やKASABIAN登場ほどのインパクトがあるわけではないが、しっかりと根付いていきそうなバンドだ。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























