DISC REVIEW
C
-

-
cinema staff
cinema staff
03年結成の4ピースバンドcinema staffの1stフル・アルバム。セルフ・タイトルを冠した本作は、まさにデビュー作というに相応しく、"海"という生命の源、始まりの場所を目指す希望に満ちた旅を描いている。そのジャケットの通り、冒頭曲「白い砂漠のマーチ」で夜の砂漠から旅は始まり、目指す"始まりの場所"は"海"。そう――これは、始まりへの旅路なのだ。未だ見ぬ生命の源、船出の場所へと近付くにつれて、光と潤いの色が徐々に加わっていく本作の流れ。と同時に、曲が進むにつれ、その足どりがより強くなっていくかのように、より強く、凛と響いていくヴォーカルもじつに勇ましい。そして、ラスト・ナンバー「海について」で約7分にわたり描かれる希望と歓びは、これ以上ない最高の"始まり"を描いている。
-

-
cinema staff
水平線は夜動く
ここ2年間の彼らの活躍には目を見張るものがある。リリースを重ねるごとに、音が一回りも二回りも膨らみを増し、洗練されていくのだ。前作から半年振りのリリースになる今作は"線"をテーマにした4曲入りのコンセプト・シングル。彼らが切り取る4つの情景はどれも一貫として、張り詰めた早朝の真冬の空気に零れる吐息のように柔らかであたたかく、闇の中で深々と降り注ぐ粉雪のように繊細で凛としている。白と黒のコントラストを感じさせる静寂と轟音で彩られた彼らの音は独特なリズムを刻み、どこまでも切なく、どこまでも美しく響き渡る。慢性的な不満を抱えた現実世界に"夢"という魔法を掛けるようなドラマティックな空気感に、完全に飲み込まれ抜け出せなくなった。目を閉じて聴き入りたい、そんな音。
-
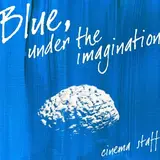
-
cinema staff
Blue,under the imagination
社会へと足を踏み出したcinema staffの溢れる衝動は、ひどい熱量を放ちつつも冷静さを内包している。彼らがいわゆる"激情系"を逸脱したのは、その凄然とした冷静さ故だと思う。『Blue, under the imagination』では、深層心理をを丸裸にし、非常に叙情的で完結された形で世界を切り取っている。3枚目にして、触れれば血が噴出しそうな鋭利さは磨きがかかり、より一層の純度が増した。内でうねる心の震えが激情へと高ぶりを見せ、石を投げ込まれた水面の波紋のように破壊力が広がりを見せるのだ。そこには衝動だけで語ることのできない、彼らのドラスティックなまでの確かな意思がある。彼らは知っているのだ。「想像力」こそが、未来へ向かう原動力であり、現実を作りだしていることを。そして、現実に対峙する唯一の手段であることを。"想像力"はやがて"創造力"へと変貌を遂げる。世界はまだ始まったばかりだ。
-

-
THE CINEMATIC ORCHESTRA
Late Night Tales
人気アーティストが監修を務めるコンピレーション・シリーズの最新作。ARCTIC MONKEYSのドラマーであるMatt HeldersにSNOW PATROLと人気ロック・バンドに続いての登場は即興ジャズと電子音楽を組み合わせ、映像化の高い音楽性で人気を集めるTHE CINEMATIC ORCHESTRA。"深い夜の物語"をテーマとするシリーズなだけに、彼らはまさにピッタリの人選だろう。共演した事もあるFLYING LOTUSのスローなナンバーから始まる今作は、ジャジーな前半からThom Yorke、Bjorkの代表曲を経てハウス・オリエンテッドな後半へと流れ、ラストは自身の新曲で幕を閉じる。まるで一つの美しい映画のように隙がなく、ため息が出るほどだ。ミックスもお見事。
-
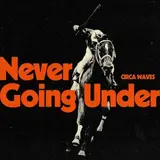
-
CIRCA WAVES
Never Going Under
2020年の前作『Sad Happy』がUKチャートの4位を記録し人気ギター・ロック・バンドの地位を確かなものにした、リヴァプールの4人組 CIRCA WAVES。彼らの5枚目となるアルバムは、"私たちが現在感じている恐怖と、それを乗り越えるために必要な回復力のスナップショットだ"とフロントマンのKieran Shudallが語るとおり、ポジティヴでエネルギーに満ちた快作だ。キャッチーに口火を切る表題曲から、アンセミックな歌メロが躍動するTrack.5、壮大なサウンドスケープを見せるTrack.6、ハネたピアノのリフが心地いいTrack.8、ドリーミーなリード・フレーズが光るTrack.9など、地に足をつけながら確実な前進を遂げていることが伝わってくる。
-

-
CIRCA WAVES
What's It Like Over There?
今年で4度目となる"SUMMER SONIC"への出演も発表されたCIRCA WAVESが、来日を前にニュー・アルバムをリリースする。前作『Different Creatures』で、それまでのやんちゃでポップなインディー・ロックの殻を脱ぎ捨て、よりゴリっとしたオルタナ・サウンドに変化し、ダークな一面も見せた彼ら。今作では、その内面の激しさは引継ぎつつも、効果的にシンセを取り入れ、ポップ感やダイナミクスが増した印象だ。ひとつひとつ大人の階段を上るように深みのあるサウンドに進化していく彼らの、無限のポテンシャルを感じる作品となった。ライヴハウスの似合う泥臭いインディー・サウンドもいいが、アリーナ級の伸び伸びとしたサウンドを奏でる彼らを生で観るのもいいだろう。
-

-
the circus
PARK
ライヴの定番曲と新たに書いた曲を収録した5人組ロック・バンドの2ndアルバム。自ら掲げる"気怠いダンスと焼き付くギター。唄うサイケデリック・ポップ。ロックンロールサーカス"は、まさに言い得て妙と思わせる一方で、ここに収められた全12曲を聴き込めば、R&Bからの影響が窺えるリズム・アプローチや、ガレージ・ロック由来の轟音の演奏等々、彼らの魅力はそれだけにとどまるものではないことがわかるはず。キーボード担当の女性メンバーが作詞作曲に加え、曲によりメイン・ヴォーカルも担当するなど、新たなことにも挑戦しながらバンドが持つポテンシャルがまんべんなく詰め込まれている。彼らのことを知りたければ、まずこれを聴けばいい。だからこその初の全国流通盤。
-

-
clammbon feat. THA BLUE HERB
あかり from HERE ~NO MUSIC, NO LIFE.~
clammbonとTHA BLUE HERBという異色のコラボレーション。この組み合わせに驚きと興奮を覚えた人も多いであろう、TOWER RECORDS日本上陸30周年を記念した限定シングル。BOSSの熱を帯びた言葉と原田郁子の伸びやかなヴォーカルが交錯しながら、一期一会の出会いと別れの繰り返しで過ぎていく人生を描き出していく。clammbonの柔らかい音とO.N.Oの硬質なビートが絡み合うトラックも、とりあえずの妥協点を見つけようとするようなものではなく、互いの個性をぶつけ合うような緊張感が漲っている。まさに、この一曲、一度きりの真剣勝負と言う凛とした美しい空気。何となくの企画盤など作るわけがないこの二組だからこその説得力。こういう音楽に、いつも救われる。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
Never Open Door For Strangers
ソングライターのコヤマヒデカズ(Vo/Gt)が、前向きな意味で作らなければ音楽家としての死は不可避だと感じていたというだけあって、彼の吐き出したかった思いや業が純度高く、且つ音楽的にも生々しい手触りで鳴っている苛烈なアルバムだ。そこに迷いはなく、1曲目の「わらけてくるわ」のイントロから意表を突く憎悪が音になったようなギター・リフが聴こえてくる。徹底的に軽蔑したり怒ったりすることで、このバンドの輪郭がむしろ明確に見え、後半に行くに従って、誰も信じられないけど誰かに愛されたいというアンビバレントな思いを書いた「光」や、自分にしか表現できない傷についての「僕だけの真相」、アルバムの発端になった「déclassé」、まるで海の底から世界を見ているような「遠征録」へと、微かな光が見えてくる構造も見事。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
灯命
前作『eve』から約4年ぶり。地球滅亡の絶望がやがて逃げ場のないコロナ禍の苦境へと重なるポエトリー・リーディング「遙か先の君へ」から幕を開ける2ndアルバム。誰も予想だにしなかった世界的情勢のなかでCIVILIANが投げ掛けるのは、命の残り時間を知ったとき、人は何を想うのか、という問い掛けだろう。人生の責任は自分にあると説く「ぜんぶあんたのせい」をはじめ、眠れぬ夜の苦悩を綴った「懲役85年」、いつか訪れる終わりが頭をよぎる「本当」や「残火」など、これまでも"命の使い道"を真面目すぎるほどに考え続けてきたコヤマヒデカズ(Vo/Gt)の歌詞は、こんな時代により強く心を揺さぶる。バンド史上最も自由に、貪欲に、多彩に振り切ったサウンド・アプローチも挑戦的。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
eve
Lyu:Lyuからバンド名をCIVILIANに改めた3人組によるメジャー1stアルバム。前作『君と僕と世界の心的ジスキネジア』から約4年8ヶ月ぶりのアルバムとなる。メランコリックなメロディを持ったオルタナティヴ・ロックという大枠こそ変わらないものの、壁にぶつかりながらバンドが求めてきた数々の変化が多彩な楽曲に結実。全14曲約68分はなかなかのボリュームだと思うが、過去を未来に繋げる挑戦の数々を表現するには、それだけの曲数が必要だったということだろう。"命の価値とは"という問いに、全曲を費やしてひとつの回答を導き出した思慮深さは彼らならではだ。そんなふうに歌詞のメッセージが評価されてきた彼らではあるが、今作では曲とともに広がったバンド・アンサンブルにも耳を傾けたい。(山口 智男)
CIVILIAN名義初のフル・アルバム。メジャー・デビュー後リリースされたすべてのシングルの表題曲、フロントマンのコヤマヒデカズ(Vo/Gt)がボカロP"ナノウ"として発表した楽曲のカバー、コヤマによるLyu:Lyu時代の楽曲の弾き語り、ライヴで育んできた新曲を収録し、これまでの歩みを見せながら"CIVILIANとはこういうものだ"を突きつける指針の作品となった。アレンジメントや詞世界の物語性が強化され、晴れやかなサウンドが高らかに舞う。かつてのコヤマにとって音楽は心の奥底を曝け出せる唯一の拠り所だったが、いまは様々な自分を表現できる場所であり、聴き手とコネクトする手段になっているのではないだろうか。"リセット"ではなく"転生"したバンドの姿が刻まれている。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
愛 / 憎
フロントマンであるコヤマヒデカズの"今までのバンドとして、ネット上の架空の表現者として、メンバー個人個人のすべての音楽をCIVILIANというひとつの大きなものにする"という言葉どおりのものになった。TVドラマ"黒い十人の女"書き下ろし主題歌Track.1は、歌謡曲風の耽美なメロディとエッジが効いたロック・ナンバー。Track.2はTrack.1のプロトタイプで、随所に共通のコードやワードなどが発見でき、1曲だけでは見えにくい核心も味わえるため非常に興味深い。制作過程を覗いているような感覚も貴重だ。Track.3は意外にも初の試みである、コヤマがナノウ名義で作った楽曲のバンド・カバー。CIVILIANを楽しむための様々な趣向が凝らされた、メジャー・デビューに相応しいシングルである。
-
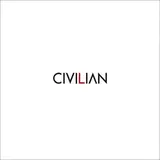
-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
Bake no kawa
Lyu:Lyu改めCIVILIAN、新機軸を掲げた快作だ。バンドにとって2年振りの新作は、最新モードを表題曲に、そこに辿り着くまでに生まれた2曲をカップリングとして収録している。「Bake no kawa」は化けの皮を被った人間に傷つけられる人間だけではなく、化けの皮を被った人間の心情も汲み取るという視野の広い歌詞ももちろんだが、様々な音色のギターと華やかなヴォーカル・エフェクト、躍動的なグルーヴを作り楽曲を引っ張っていくドラムと、サウンド的にも一皮むけた。自らに課していた制約を作らなくなったことで自分たちを解放し、さらに彼ららしい音楽ができる境地へと足を踏み入れたと言っていい。過去も今も未来も全部引き連れて活動していくという決意がどの音からも感じられる。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
Lyu:Lyu ONE MAN LIVE 2014「ディストーテッド・アガペーの世界」
まず、あの日あの場所で起こった出来事が、映像として残ることが心から嬉しい。そしてあの空間そのものが、ひとつの作品だったのだと改めて思う。2014年11月に渋谷TSUTAYA O-EASTにて行われたワンマン・ライヴ"ディストーテッド・アガペーの世界"を映像化したバンド初のライヴ映像作品。コヤマヒデカズ(Vo/Gt)が連載していた小説"ディストーテッド・アガペー"の世界観を映像や照明を駆使し表現したステージだ。バンドの想いが小説の世界に新たな輝きをもたらし、そこに観客の想いが重なり、さらに強く優しい光を放つ。"生まれて初めてあなたたちへ曲を書きました"――孤独の中で鳴り響いていた彼らの音楽を外へ向けたのは聴き手からの愛。彼らの姿を丁寧に切り取る画ひとつひとつからも、それが滲む。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
ディストーテッド・アガペー
心が傷だらけになった人がいて、自分はその人に何ができるだろうか、自分だったらなんと言ってもらえたら救われるだろうか。でも本当にその言葉が人を救うのだろうか? 相手も自分も傷つける可能性があるなら、何もしないままがいいのではないか? ......人間誰しも、傷つくことはできる限り避けたい。だが、他者を護り、救うために自分自身が傷つく覚悟をした人間の歌は深く、強かで優しい。「ディストーテッド・アガペー」はそういう曲だ。絶望の淵に落ちた人間を否定せず享受し、透明な声でまっすぐ"僕だって同じなんだよ"と語り掛ける。包容力のあるリズム隊の音色が寄り添い、ギターは人の息遣いや声のように歌い、囁き、泣き、叫ぶ。これは血の通った人間だからこそ作ることができる、愛という気魄だ。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
GLORIA QUALIA
"のたうち回る"――彼らの音楽に出会ったとき、そんな言葉が頭をよぎった。感情を吐き出すように歌い叫び、傷口を抉るようにギターをかき鳴らしていたコヤマヒデカズ。文学的な歌詞に常につきまとう"死"という概念に苦しみながらも、微かな希望を求め、もがく。そんな姿が痛烈だった。彼が歌っていることは今も昔も変わっていないかもしれない。だが全てを受け入れる覚悟をした彼は、信頼する仲間、聴き手の想いと共に新たな一歩を踏み出した。ざらついた攻撃的な音は研ぎ澄まされ、より鋭利に美しく、やわらかく響く。音の向こう側にいる我々に向かって全力で鳴らされる音色のひとつひとつに、血の通ったぬくもりが溢れているのだ。Lyu:Lyuは間違いなくこの作品で、新たなフェーズへと突入した。
-

-
CIVILIAN(ex-Lyu:Lyu)
君と僕と世界の心的ジスキネジア
動画再生サイトで人気を誇るボーカロイド・プロデューサーでもあるコヤマヒデカズを擁する3ピース・ロック・バンドの待望の1stフル・アルバム。いつも黙殺している冷たい日常のひとコマ、人から言われてちくりと心に刺さったひと言、どこかで常に感じている焦燥。悲劇ではない。絶望でもない。誰もが少なからず肌で感じている人間の、そして自分の心の弱さだ。普段は目を背けているその弱さと向き合って、親しみやすいエモーショナル・ロックに乗せて歌う。克服した先にある希望を歌うわけではない。そこにあるのは自分ではどうにもできない歯がゆさかもしれない。ただただひたむきに歌う。歌うことによって全て消化されていく。今作を聴き終えれば、そこには心が少し軽くなったような解放感と安堵が待っている。
-

-
CLAIRO
Charm
ベッドルーム・ポップ・シーンの新星が、3rdアルバムで満を持して日本デビュー。心地よいウィスパー・ヴォイス、シンプルなメロディ、お洒落なコード運び......派手さや強烈な個性はないが、聴く者を選ばない優等生な作風は好感度◎。今作はもはやローファイやベッドルーム・ポップとは言えない、作り込まれた精緻なサウンドメイクになっており、華やかな装飾も満載、シンガー・ソングライターとしてネクスト・ステージに進んだ印象だ。とはいえ管楽器やパーカッションを用いたジャジーなアレンジも、各楽器が主張しすぎず、マイルドに自然体で浸透しているなど、彼女の控えめで優しい世界観を壊さない工夫がされており、プロデューサーの手腕が見て取れる。
-

-
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
New Fragility
現在はフロントマン Alec Ounsworthの実質的なソロ・プロジェクトとして活動しているCYHSYの、約4年ぶり6作目となるアルバム。現代社会が抱える"新たな脆弱性"について歌った本作は、フォーキーなインディー・ロックを基調に、優しいドリーミーなポップ、そして叙情的なストリングスが同居した、どこか陰りのある作風だ。神秘的なコーラスとともに銃乱射事件の悲劇を歌い上げるTrack.2、1stアルバムのヒットで一変した生活を軽快なビートとどこか不安を煽る旋律で表現したTrack.7など、トレードマークであるヘロヘロとした歌声で紡がれる美しいメロディが、緻密なアレンジで引き立てられていて、CYHSYの作品群の中でもひと際切なく胸を打つアルバムと言えるだろう。
-

-
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
Only Run
セルフ・ネームのデビュー・アルバムで痛快なポジティヴティを発揮したCYHSYがなんと結成10周年!光陰矢のごとしとはこのことか......。今作は1st同様、リード・シンガー・ソングライターのAlec Ounsworthがレコーディング以前に大半の楽曲を完成。まさに彼の個のアイデアと脳みそを具体に落とし込んだような凄まじい自由度だ。人力ダブステップにAlecのあのヨレヨレなのにどこまでも伸びやかな声が乗るオープニング・ナンバーから既に、エレクトロ以降の時代のSSW、2014年のBob DylanやLou Reedのような替えの効かないSSWとしての存在感が際立っている。ミックスはDave Fridmann。細分化するUSインディーの中で特定のクラスタに収まりきれない個性と普遍性を備えた快作だ。
-

-
CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
Hysterical
いまやインディ・ロックの重要なアイコンとなりつつあるCLAP YOUR HANDS SAY YEAH(以下CYHSY)。07年リリースの『Some Loud Thunder』以降、作品としてはヴォーカルAlec Ounsworthのソロ作やメンバー個々の別プロジェクトなど課外活動が目立っていたが、ついにCYHSYとして待望の新作が完成した。実に4年振りの3rdアルバム『Hysterical』である。この間、スタジオ入り延期での解散説や来日公演中止など、なにかと負の話題が一人歩きしていたが、すべてを吹き飛ばす快作となっている。繊細であり親しみやすいメロディ、そして温もりあるAlecのヘロヘロ・ヴォイス、ここにしかない世界観はやはり胸を揺さ振るものだ。しかしトータルとしての構築美には本当に驚かされる。完全自主制作でリリースされたデビュー時を想うと、あのいなたさはどこへいったのか!?飛躍したCYHSYに拍手を送り、今後の活動も期待しよう。
-

-
CLARK
Death Peak
近年はドラマの劇伴や舞台音楽など、多方面で活躍するCLARKが自身の名をタイトルに冠した前作から3年。"死の山頂"と名づけられた今作は、彼がここ数年抱えていたテクノ・ミュージックにおける狂気が堰を切ったように溢れ出した力作と言えるだろう。先行公開されたTrack.3「Peak Magnetic」からも滲み出ていた、様々なリズムを取り込むカオティックな音像は、各楽曲にてそれぞれ拡張されており、アンビエント、レイヴ、IDMといった彼自身のバックグラウンドに対する経年変化がサウンドにも反映されている。今でこそARCAのような前衛的で、リズムすら遠くに置いてしまうビートがベーシックになりつつあるが、その礎の一角を築いたのは間違いなくCLARKである。今作を通して、改めてその事実を電子音楽史にしっかりと書き加えておきたい。
-

-
Joe Strummer
Joe Strummer 001
突然の死から16年、未発表音源収録の作品が世に出る。THE CLASH以前のオーセンティックなR&Rにパンク黎明期の勢いを感じるTHE 101'ERS時代。THE CLASH解散後、盟友 Mick Jonesと関係が修復されてから初めてレコーディングされた楽曲や、映画"Sid And Nancy"のサウンドトラックに収録した「Crying On 23rd」のアウト・テイク、THE MESCALEROSとの「London Is Burning」の初期の未発表Ver.、Johnny Cashとの共演によるBob Marleyの「Redemption Song」のカバーなど、膨大なアーカイヴ(全32曲)が2枚組に収録されている。パンクのオリジネーターのイメージが強いが、THE CLASHがそうであったようにカントリーやレゲエなど世界中の市井の人々の音楽に深部で共振していたことが再認識できる。
-

-
THE CLASH
The Clash Hits Back
究極のボックス・セット『Sound System』のリリースに合わせ、新たに編まれたTHE CLASHの2枚組のベスト盤。1982年7月10日のブリクストン・フェアディール公演のセットリストをレコーディング音源で再現した24曲に彼らを語るとき外せない8曲、さらに日本盤ボーナス・トラック2曲を加えた選曲が興味深い。代表曲をまとめて聴けるという意味では入門編にもぴったりだし、後期の傑作である『Combat Rock』発表後のツアーを追体験するという意味では、熱心なファンでも楽しめるものになっている。パンクの英雄であると同時に誰よりも早くレゲエやダブ、ヒップホップを自分たちの表現に取り入れたミクスチャー・ロックのパイオニアとしての彼らを印象づける、聴きごたえ満点のベスト盤だ。
-

-
CLEAN BANDIT
New Eyes
イギリスでNo.1ヒットになった「Rather Be」によって、一躍、世界中からの注目を集め始めた4人組、CLEAN BANDIT。クラシックをベースにしたエレクトロ・サウンドと話題になっているが、それが顕著に感じられるのはTrack.1「Mozart's House」ぐらいで、それ以外の曲はヴァイオリンとチェロの音色を味つけに使ったエレクトロニックなダンス・ミュージックという印象。クラシックと聞きビビッた人はご安心を。もちろん洗練された作風はクラシックの影響だが、期待しすぎるとちょっと物足りないかも。むしろ聴きどころは90年代、いや、80年代にまで遡って、多彩な表現を追求したサウンド・メイキングと、ほぼ曲ごとにフィーチャリング・シンガーを使いわけ、こだわった歌ものとしてのクオリティだ。
-

-
climbgrow
CROSS COUNTER
滋賀発の4ピース・バンド、climbgrowがリリースする『CROSS COUNTER』は、"逆境なんか跳ね返せ"という想いが込められたタイトルのとおり、苦しみや悩みを荒々しい歌詞とサウンドで吹き飛ばしてくれる全6曲を収録したミニ・アルバム。彼らなりの"革命"を予感させる50秒のショート・チューン「革命を待つ」から幕を開ける本作は、未来を夢見る「未来は俺らの手の中」、杉野泰誠(Vo/Gt)の咳込みも収められた冒頭の絶唱が印象的な「LILY」、照れ臭くなるほどストレートに愛を叫ぶ「BABY BABY BABY」とキラー・チューンが続く1枚だ。始まりから終わりまでclimbgrowのロックンロールを唸らせ、見えない未来や挫けそうな気持ちに彼らなりの光をくれる革命盤が完成した。
-

-
CLINIC
Bubblegum
RADIOHEADの来日公演のオープニング・アクトを務めたことで日本でも認知度の高いCLINIC。ARCADE FIREがファンと公言するなどアーティストからの評価も高い彼らだが、それから10年近く経った今、筆者を含め彼らへの関心が薄らいでしまったこともまた事実。しかし6作目の今作は彼らの持つフリーキーでサイケデリックな魅力が今の時代にマッチしたとても魅力的な作品だ。切れ味の鋭いリフで押し切るサウンドから弦楽器を全面にフィーチャーし、今のUSインディと共鳴するようなドリーミーな音色へ。不安定なアンサンブルに脱力系ヴォーカルと彼らの放つ独特な高揚感も健在。今のUSインディどっぷりという人に是非手に取ってもらいたい作品だ。
-

-
CLOCK OPERA
Ways To Forget
Kitsuneからシングルをリリースし注目を集めるロンドン出身のニュー・バンド。この春にはTHE TEMPER TRAPの前座にも抜擢され、このアルバムでさらに彼らがステップ・アップしていくのは間違いないだろう。COLDPLAYやSNOW PATROLを彷彿とさせる壮大で儚く美しいメロディとエレクトロとロックをまた新しい形で融合させた様なサウンドが魅力的である。オープニングを飾る「Once And For All」のMV(必見!)で描かれるストーリーのように楽曲もアルバムもとてもドラマティックだ。この楽曲はAndrew Weatherallがリミックスを手掛け、バンド自身もMETRONOMY等のリミックスを担当するなどダンス・フィールドでも活躍している。今後がとても楽しみなバンドだ。
-

-
CLOUD CONTROL
Dream Cave
FOO FIGHTERSやVAMPIRE WEEKENDらのオープニング・アクトに次々と抜擢されブレイクを果たした、オーストラリア出身のロック・バンドCLOUD CONTROLがリリースする3年ぶりの2ndアルバム。良い意味で気持ち悪いチャント風のコーラスが癖になる「Scream Rave」から始まり、引きずり気味のビートに乗ったAlister Wrightの気だるい歌声が印象的な「Dojo Rising」など、冒頭から個性溢れる楽曲が続く。ニュー・ウェーヴ色が強い「Ice Age Heatwave」のサビのコーラス部分はSPARKSの「Instant Weight Loss」を彷彿とさせる。多彩な楽曲の数々も、アルバムを通して聴くとまるで一貫した1冊の物語を読み終わったかのような感覚になる。タイトル通り"夢の洞窟"の世界に飲み込まれるような作品。
-

-
CLOUD CONTROL
Bliss Release
LOCAL NATIVESや、はたまたFLEET FOXESを彷彿とさせる、フォーク/サイケ・ロックを奏でる新人4ピース・バンドがオーストリアから登場。彼らは過去にVAMPIRE WEEKEND、 SUPERGRASS、 MAGIC NUMBERSなどのサポートを務めた経験もあるそうだ。近年のブルックリン周辺のバンド・サウンドを受け継ぐような男女が織りなす豊かなコーラス・ワークや多幸感たっぷりなメロディ・ラインが非常に特徴的。だが彼らはそれだけではなく、良い意味での雑多感が満載であり、とてもカラフルで、心地よさがある。新年のスタートには持ってこいのポジティヴな輝きに溢れたアルバムだ。
-

-
CLOUD NOTHINGS
Life Without Sound
Dylan Baldi(Vo/Gt)の宅録プロジェクトからバンドに発展したオハイオ州クリーブランドの4人組。オルタナ・リヴァイヴァルをリードする存在としてコンスタントにアルバムを作り続けている彼らがほぼ3年ぶりにリリースする4作目のアルバム。"高校生のときの自分がドライヴしながら聴いて、いいねって思えるような作品"とDylanは語っているから、作りたい作品はあらかじめはっきりとわかっていたに違いない。その意味では、ここに邪念はこれっぽっちも感じられない。持ち前のメロディに磨きを掛けつつNIRVANA、あるいはWEEZERフォロワーとしての真っ当な姿を追い求め、そのうえで疾走するだけに終始しない表現力を手に入れている。圧巻は終盤の盛り上がり。それまでの疾走感が混沌に変わる。
-

-
CLOUD NOTHINGS
Attack On Memory
どうしたCLOUD NOTHINGS! 驚異の飛躍というか、深化系変貌。90年代にシカゴ音響派周辺に浸っていたおっさん(俺もね)はとにかくオープニング・ナンバーで感涙だろう。ポスト・ロックやエモなんてカテゴライズもなかったあの時代、張り詰めた緊張感と“静と動”のエモーショナルな美をみせたSLINTによる名盤『Spiderland』の幻影が! こんな裏切りは想像できなかったが、レコーディング・エンジニアはノイズ御大Steve Albiniという納得の起用。昨年リリースされた泣きメロ満載のデビュー・アルバムはローファイ・リヴァイヴァルの追い風にも乗り注目を集めたが、ついに覚醒である。主要メンバーDylan Baldi曰く“前作のポップ・パンクとは対立するものとして、新作をロック・アルバムと呼びたい”と。逞しく成長した姿を見るにつけ、俄然来日を切望!
-

-
CLOUD NOTHINGS
Cloud Nothings
米オハイオ州クリーブランド出身のDylan Baldiのソロ・プロジェクトであるCLOUD NOTHINGSのデビュー・アルバムは、"等身大"という言葉が申し分なくしっくりくる作品に仕上がった。2009年、当時18歳の彼が自宅の地下室でレコーディングした楽曲がネットで話題を呼び、昨年はSXSWにも出演を果たした。軽やかなギターのカッティングが特徴的なローファイ・テイストのサウンドと、どこまでもキャッチーなメロディに隅々まで宿る躍動感。若者が内包する有り余るエネルギーが、全て音と歌にぶつけられたようなピュアネス。良い意味で軽いノリで始まったような、頑張りすぎないラフな空気が生々しくリアルだ。音楽を心の底から楽しんでいるポジティヴな意識と、甘酸っぱく瑞々しい青春がぎっしり詰まっている。
-

-
CLOW
DEAR FRAME
アコースティック・ギターを抱え、日常のドキュメンタリーを歌い綴るシンガー・ソングライター、CLOW。Track.1「スクロール」では、世界の紛争も、事件や事故、下世話な芸能情報から知人の近況まで、手の内で情報がスクロールされていくことを歌う。平熱のヴォーカルながらも、内側では、不穏な何かに押し潰されて、今にも叫び出しそうな衝動も抱えている。爆発寸前のヒリヒリとした感情が、静かで、可憐ですらあるメロディの薄い皮1枚の下で、尖っている。彼女自身はインタビューで、自分の歌はうまいこと言えてないと語っていたが、五感を研ぎ澄まし、見えるもの聞こえるもの感じるものを端的に切り取ったワードは、弾丸のようなスピードで突き刺さる。そういう歌の威力を持ったソングライターだ。
-

-
CNBLUE
人生賛歌
韓国と言えばダンス・ヴォーカル・グループのイメージが強いが、このCNBLUEはポップな曲調ながらも本格派のバンドだ。もともと、バンド文化が根付いている日本で活動したい、という思いがあって日本のマーケットを意識した活動をしていた彼等だが、今年UVERworldと日韓で対バン・イベントを行ったこともあり、より日本のファンに親しみやすい存在となった。今回のシングルでは初の日本語タイトルとなった表題曲、そして盟友 UVERworldとの共作含め、3曲とも日本語詞と英語詞の絶妙なバランスで歌が耳にスッと入ってくる。ソフトでノリやすいポップ・ロックは、EDMに慣れきったK-POP界隈よりも日本のシーンで受け入れられるはず。
-

-
Cocco
ニライカナイ
曲の幕開けを告げる、琉球音楽のメロディから強烈に心に突き刺さる。この人の声はやっぱり、一聴でCoccoだと認識させるインパクトを持っている。その唯一無味な個性を支えるのは、5thアルバム『ザンサイアン』以来4年ぶりとなる根岸孝旨との共同作業で作り上げたバンドサウンド。"生まり島 忘れんなよ 踊れ踊れ 輪になれー"。日々の喧騒の中で忘れがちになってしまう、自分の出自。家族、故郷、大切な人や心の在りかた・・・。あなたが生まれた原点は、どこにある?そんなメッセージも汲みとらせるスピリチュアルなリリックを、人間の本能に訴えかけるエネルギーに満ち満ちた強靭な音色が伝える。カップリング「やぎの散歩」は、若干14才の映画監督・中村颯悟作品『やぎの冒険』への書き下ろし楽曲。
-

-
Cocco
Coccoさんの台所CD
雑誌「パピルス」にて連載されていたエッセイに、書き下ろしエッセイなどを加えた最新エッセイ集『Coccoさんの台所』から生まれた4曲を収録した、1年10ヶ月ぶりの最新作。春夏秋冬、それぞれの季節への想いを歌った4 曲で四季を表現している。「絹ずれ」は、ダイナミックなロック・サウンド、「the end of Summer」は全英詞で夏の終わりの切なさを静かに歌う。「バイバイパンプキンパイ」では、オーガニックなアコースティック・サウンドに合わせ、前向きな歌詞を歌う。そして、美しいサウンド・スケープを見せる「愛について」でしめくくる。Coccoらしい深く自分を抉り出すような歌詞を散りばめながらも、柔らかく、ポジティヴなフィーリングが特徴的な楽曲集となっている。
-

-
CODE OF ZERO
Storage of Solutions
"渋谷最恐POP"を掲げるCODE OF ZEROの最新作は、"Storage of Solutions=解決策の倉庫"がテーマ。ガールズ・パワー全開のメッセージをラウドなサウンドに乗せた「S/O/G」や、挑発的な歌詞で焚きつけるヘヴィ且つダンサブルな「BAN=DA RANDOM」、弱音を吐く自分も受け入れ前に進むポジティヴなデジタル・ポップ「L.I.F.E. (SOS ver.)」、呪縛からの解放と新たなスタートを歌う爽快なナンバー「Periodicity」など、メッセージ性の強い6曲が収録された。ロックからEDMまでを独自のポップ・サウンドに落とし込み、ライヴで鍛え上げられた歌声はより表情豊かに。悩み多き時代に悲鳴を上げる心の"SOS"に応え、6曲それぞれのアプローチで解決へ導く1枚。
-

-
CODE OF ZERO
MAKE ME REAL
2016年の活動開始以来、精力的なライヴと会場/配信限定リリースを続けてきた女性ヴォーカリスト、0Cによるソロ・プロジェクト、CODE OF ZEROが満を持してリリースする初の全国流通盤。ラウドでありつつダンサブルな魅力も持つモダンなロックをバックボーンに、アンセミックでポップ、そしてエモーショナルな全5曲を収録した。ガール・ポップの王道と言えるパワフル且つキュートなヴォーカルもさることながら、熱度満点でライヴ映え必至のテクニカルなバンド・サウンドからは、0Cのバックグラウンドや、どんな表現を目指しているかが窺える。ライヴのサポート・メンバーに加え、印象に残るギター・プレイを披露したvivid undressのyu-ya、vistlipのYuhの客演も聴きどころ。
-

-
Cody・Lee(李)
心拍数とラヴレター、それと優しさ
高橋 響(Vo/Gt)が中学生の頃文集に綴った"僕はソニーからデビューします"という夢は現実となり、ついにメジャー・デビュー作がリリース。独特な表現のワードをポップに放つ「愛してますっ!」や、タイトルからは想像がつかないロマンチックで'80s感漂う「冷やしネギ蕎麦」、繊細なピアノと情熱的なギターが混ざりあう「honest」、アップテンポで駆け抜ける全肯定ソング「W.A.N.」、切なさが染みる冬のバラード「しろくならない」、街と日常を切り取った素朴さが心地よい「世田谷代田」など12曲が収録された。シティ・ポップからパンクまでを奏でるそのあまりの振り幅の広さに、まだまだ見せていない顔があるのではと期待してしまう。海外からも注目を集める彼らの、計り知れない可能性を感じる1枚。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























