DISC REVIEW
C
-

-
Charisma.com
ハッピーターン
MCいつかとDJゴンチの現役OLによるエレクトロ・ヒップホップ・ユニット、Charisma.comが2014 PARCO VALENTINEキャンペーン・ソングに起用された「チャンコイ」に続くiTunes限定配信シングルをリリース。今作は"幸運(ハッピー)は回ってる(ターン)"という想いを込めた、彼女たちらしいホワイトデー・ソング。本人たち曰く"こじらせ女子の日常の歌"だという今作は、日々の生活から嫌気がさしている女子の感情をありありと表現しており、現役OLの2人だからこそ産み落とせた作品と言える。1stミニ・アルバム『アイ アイ シンドローム』の楽曲と比べ軽やかにはなっているものの、独特な気だるさと刺々しいリリックは健在。iTunesエレクトロニック・チャート1位に輝いた「チャンコイ」同様、今回もヒット間違いなしの1曲。
-

-
Charisma.com
アイ アイ シンドローム
MCいつかとDJゴンチというふたりの現役OLから成るエレクトロ・ヒップホップ・ユニット、Charisma.comのデビュー・ミニ・アルバム。ヘヴィでアグレッシヴなトラックに乗せて歌われる、現役OLならではの生々しく社会の矛盾、暗部を暴き、告発するリリックの鋭さは、そのキュートな存在感と相まって、聴く者に大きな衝撃を与えるだろう。SNSに蔓延する肥大した承認欲求や、会社での理不尽な人間関係といった彼女たちの怒りの矛先は、今、誰もが無理やり隠し通そうとする現代社会の“弱さ”でもあるから。だが、だからこそ、Charisma.comの音楽には、この社会で悩み、傷つきながらも生きる者への慈愛にも似た優しさも孕んでいる。それは、メロウで感動的なラスト・トラック「OLHERO」に、何よりも顕著に表れている。
-

-
THE CHARLATANS
Different Days
2013年には結成以来のメンバーだったJon Brookes(Dr)を脳腫瘍で失いながらも、前作から2年4ヶ月でニュー・アルバム『Different Days』をリリース。その歩みを止めずに進み続けているTHE CHARLATANS。今作は、そんな彼らに愛とリスペクトを表するように、たくさんのゲストが集結した1枚となった。Johnny Marr、Paul Weller、Peter Salisbury(ex-THE VERVE)、Stephen Morris(NEW ORDER)など......UKロック・フェスのようなラインナップである。そして、収録されている13曲はというと、昔からのファンの期待にも応えてくれる彼ららしいメロディやビート感を生かしながらも、決して枯れてはいない鮮やかさと躍動感を誇っている。
-

-
THE CHARLATANS
Modern Nature
90年代初頭、THE STONE ROSES登場直後の英国ロック・シーンに現れ、そのダンサブルなグルーヴとアンセミックなメロディが見事に融合したサウンドで人気を博したTHE CHARLATANS。一昨年、結成時よりのドラマーを脳腫瘍で亡くすという悲劇に見舞われた彼らが、その苦境を乗り越え作り上げた通算12作目のアルバム。代わりのドラムには元THE VERVEのPeter Salisbury、NEW ORDERのStephen Morris、そしてFACTORY FLOORのGabriel Gurnseyが参加。アルバム全体に通底音として漂うのは、やはり喪失感、メランコリー。しかし本作には、それでも1歩を踏み出すために沸々と湧き上がる力強さがある。雪解けのあとに芽吹く新緑のような瑞々しい生命力がある。本編ラスト前の「Trouble Understanding」が何より感動的だ。
-

-
Charlie Puth
Charlie
US音楽シーンを代表するヒット・メーカーが、自身の名"Charlie"を冠したアルバムをリリース。タイトル通り過去最高にパーソナルな1枚となった本作では、彼が抱えた失恋の痛みも、そこから立ち直ろうともがく姿も、すべて正直に曝け出している。しかしそのサウンドは皮肉なほどに明るく軽やかだ。"Charlie Be Quiet!"と女性に対し前のめりな様を自嘲したり、照明のスイッチ音を曲に組み込んでみたりと、ユーモアを散りばめポップな仕上がりに。またJung Kook(BTS)とのコラボ曲を収録し、さらに収録曲の制作段階をTikTokで公開するなど話題性も抜群。今までの虚勢を脱ぎ捨てた彼は、ナイーヴな内面を映す歌詞とユニークなキャラクターで、飾らない新たなポップ・スター像を築き上げている。
-

-
Charlotte Gainsbourg
Irm
Serge GainsbourgとJane Birkinを両親に持つCharlotte Gainsbourg。80年代から女優として活躍しながら、これまで2枚のアルバムを発表してきた。そして、この3 年ぶりとなるアルバムはBECKが全面プロデュース、さらには全曲作曲も手がけ、作詞も共同で行っているが、二人の個性がうまく融合している。生音を多用した捻くれたサウンド・プロダクションとBECKらしいビート感が、Charlotteの持つアンニュイな雰囲気を醸し出す歌声とよくマッチしている。また、英語で歌われる曲ではBECKとのコラボレーションならではの色がよく出ているし、フランス語で歌う曲ではBECKが一歩引いて、妖しい色香を漂わせるChrlotteの個性がより際立っているところも面白い。
-
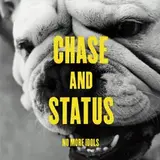
-
CHASE & STATUS
No More Idols
エッヂの効いたロックで、ヘヴィなビートが炸裂するエレクトロニカ。スリリングなHIPHOPで、哀愁のあるR&B。それでいてポップ! 近年ではJAY-Zのリミックスを手掛け、THE PRODIGYの復帰作やRIHANNAの『R指定』に共同プロデューサーとして関わり、注目度が高まるロンドン出身のドラムン・ベース / ダブ・ステップ・デュオCHASE & STATUS。2ndアルバムとなる今作ではPLAN B、TINIE TEMPAH、WHITE LIESなど多種多様なゲスト・ミュージシャンを招へい、彩り鮮やかな作品に仕上がった。起用アーティストによって楽曲アプローチを変え、そのアーティストの持つ個性は勿論、新たな魅力を引き出す。様々な音色を巧妙に操るその手腕は、マジシャンさながら。
-

-
CHASE & STATUS
More Than Alot
PENDULUM、THE QEMISTSなど、最近ロッキン・ドラムンベースが世間を賑わせているが、このCHASE & STATUSもその流れでオススメしたいアーティストだ。ただしCHASE& STATUSの場合は、もっとクラブ・ミュージック的なアプローチになっており、トラック・メイキングは前に挙げたアーティストより、もっと緻密で凝った内容のものになっている。ドラムンベースを基調にHIP HOP、FUNKなどの要素を取り込み、とても洗練されたモダンなサウンド。「SMASH TV」ではGUNS'N ROSESの「Welcome To The Jungle」がサンプリングされ、なかなかニクイ演出をしてくれている。PRODIGYやOUTKASTが好きな人にもオススメです。
-

-
CHASE ATLANTIC
Lost In Heaven
オーストラリア出身(現在はロサンゼルス在住)の3人組、CHASE ATLANTIC。同じくオーストラリア出身のTAME IMPALAからの影響を公言している通り、ロックとも密接したモダンなR&Bサウンドが特徴的だ。バンド・スタイルであるCHASE ATLANTICの持ち味が活きた、ライヴ・パフォーマンスが連想されるキャッチーなメロディ、洗練されたプロダクションも完成度が高い。今作制作時には、曲作りに使っていたラップトップの故障でデータがなくなってしまうトラブルがあったようだが、心折れずにここまでしっかりとアルバムを作り込めたというのもすごい。中性的な甘いヴォーカルと、メンバー全員のシュッとしたルックスも含め、K-POPファンにも響きそう。
-

-
CHATEAU MARMONT
The Maze
新世代パリ・シーンを代表するフランス出身の3人組。人気レーベルInstitubes、Kitsuneからのシングル・リリースを経て、自主レーベル“Chambre404”を立ち上げたバンドのデビュー・アルバムは、1作目にして大傑作に仕上がっている。70年代のシンセ・ポップ、プログレッシヴ・ロックなども感じられる洗練されたタイトなサウンドは、以前に、KENZOやCHANELといったラグジュアリー・ブランドのキャンペーン用のサウンドトラックを手がけたことも納得できる新感覚のエレクトロニック・ロック。モダン・フレンチ・ポップ的な「Wind Blows」を始め、キャッチーでメロディアスなサウンドが凝縮された本作は、多くの人々の心をくすぐるはずだ。
-

-
CHEEKY CHEEKY AND THE NOSEBLEEDS
Thespionage
メンバーが一心不乱に歯磨きする、人を食ったようなジャケット。冴えない主人公が周囲を斜めから観察する、ペーソスたっぷりのリリック。そしてXTC?BLUR経由の英国式ポップ・センスと、USインディーのローファイ・マナーを融合させ、パンキッシュにまとめたユーモア溢れるサウンド。 これまでポップの歴史を賑わせてきた、一癖も二癖もあるひねくれ者たちの系譜に名を連ねるバンドだろうと想像に難くないのだが、どうやら真相は異なるようだ。 初の来日公演でみせたパフォーマンスは、超直球ストレート。顔を真っ赤にしながら歌い、手拍子を煽り、ステージを所狭しと駆け回る。ギミックで肩透かしを食らわせるような要素なんて皆無。ひねくれ者の賛歌を真正面から歌い上げる、アツい奴らだったのだ。 この日本盤デビュー・アルバムは、メンバー全員が10代というCHEEKYの、実直とすら言える熱情をいち早く封じ込めたリポートである。
-

-
the chef cooks me
RGBとその真ん中
シモリョー(下村 亮介)は悲しいとか切ないとかで語りきれないモヤモヤした感情に名前をつけるのが恐ろしく上手い。前作『回転体』であれば「適当な闇」のように。作詞家として星野源や後藤正文と並び称されていいぐらい、彼は"音楽の言葉"を持っている。さて、今回は光の三原色(RGB)と、その交わる世界をコンセプトにしたという。冒頭、意表を突かれるぐらい疾走するコード・カッティングで幕を上げる「PAINT IT BLUE」には、ティーザー映像でも見られるが、昨年のライヴで350人のオーディエンスによるコーラス(みたいなもの?)を公開収録して、孤独なあなたと私たちが分かり難く関わっている心象を謳いあげる。青臭さと洗練を兼ね備えたインディー感と"にほんのうた"の絶妙な邂逅。今、あらゆる人に聴いて欲しい1枚。
-

-
the chef cooks me
回転体
the chef cooks meにとって、いやポップ・ミュージックにとっての名作が誕生した。『回転体』とはちょっとシュールなタイトルだが、作品を聴きすすめていくうちに、ここには日々や人生の機微、人とのつながりや小さなきっかけを辿ってマジカルな出会いをするような、ライフやライヴのずっしりとした重みや、魔法の種が詰まっているのがわかる。ホーンやコーラスで彩られたオーガニックで、高いパッションでのアンサンブルは、チアフルでいてかつじんわりと体に沁み込む柔らかさがある。そのあとに、メロディや言葉が静かに優しく流れ込んで、哀しみだったり、喜びだったりの琴線に触れ、さまざまなざわめきを起こす。入口と出口とでちがった体験をして、その道すがらたくさんのことを考えられる心地好い余白を持った音楽。変化を受け入れながら、バンドとして滋味を増した、ほんとうの成長作だ。
-

-
the chef cooks me
Love Transformation
都内のライブハウス、いや今やフェスでも引っ張りだこのTHE CHEF COOKS MEから新しいミニ・アルバムが届けられた。まず、人を食ったようなバンド名に惹かれてしまった。そして、良い具合に力の抜けたヴォーカルとポップなメロディ、踊るポイントをグッと押さえたグルーヴもバッチリ。ファンク、ハードコアからエレクトロまで、彼らはポップなアレンジでカラフルに料理してしまう。今回は2006年に発表された1stアルバム『アワークッキングアワー』の再発と併せてのリリース。この二枚は挨拶代りになるだろう。今回のミニ・アルバムでは、ダンサブルなナンバーよりも後半に収録されているセンチメンタルなバラードにこのバンドの底力を感じる。彼らが目指す<第二のクラムボン>へ期待が膨らむ傑作。
-

-
chelmico
Fishing
chelmicoのメジャー2作目となるアルバムには、ESME MORIや小袋成彬といった次世代を担うクリエイターから、お笑いトリオ トンツカタンの森本晋太郎などが参加。世間で長年親しまれているCMソングを、現代風のサウンドとリリックにアップデートした「爽健美茶のラップ」、VTuberドラマ"四月一日さん家の"のOPテーマで、ふと口ずさみたくなるキャッチーなメロディが特徴の「switch」、彼女たちがファンと公言するRIP SLYMEのフロウを彷彿とさせる「Summer day」など、どこを取ってもキラーチューン尽くしの全12曲が収録。アルバム・タイトル通り、彼女たちの魅力に"釣られて"手にとってほしい1枚。
-

-
chelovek.
Land(E)scape;
TRY TRY NIICHEのヲクヤマ(Pf/Vo)が所属するピアノ・プログレッシヴ・バンド、chelovek.(読み:チェラビェーク)による2ndミニ・アルバム。重々しいコードを一発鳴らして聴き手をグッと集中させる冒頭然り、メロも和音もリズムも奏でられるピアノという楽器の特性を活用した工夫が随所にある。それらの工夫は、この楽器が編成に組み込まれていなかったらありえなかったであろう展開だが、それに甘んじることなく、ギター/ベース/ドラムそれぞれもしっかりアプローチできている点がこのバンドの長所だ。特にラスト、「Nachtmusik」におけるドラマチックさは、このバンドの専売特許と言えるのではないだろうか。ライヴハウスの中だけでなく、その外にも十分響く予感のする音楽。
-

-
THE CHEMICAL BROTHERS
For That Beautiful Feeling
ダンス・ロックのパイオニア THE CHEMICAL BROTHERSがリリースした4年ぶり/10枚目となるスタジオ・アルバム『For That Beautiful Feeling』は、ノイズが点在するカオティックなトラックが描く幻覚的なサウンドスケープと、緻密なサウンドメイキングが光るドープな1枚に仕上がった。海岸に程近いスタジオで録音されたという本作には、フランスを拠点とするシンガー・ソングライター Halo Maudを招いた表題曲やシングル・カットされた「Live Again」に加え、フィーチャリングにBECKを迎えた「Skipping Like A Stone」など、色彩豊かでサイケな楽曲を多数収録。なお、日本盤CDにはボーナス・トラック2曲が収められている。
-

-
THE CHEMICAL BROTHERS
Hanna
FUJI ROCK FESTIVAL3日目のヘッドライナーを務める英テクノ・ミュージックの第一人者THE CHEMICAL BROTHERSから、約1年振りとなるフル・アルバムが日本先行発売される。今作は映画『ハンナ』のサウンド・トラック。殺すことだけを教えられ育てられた16歳の少女ハンナの哀しき運命を描いた映画だ。映画音楽のサントラ作成は初挑戦の彼らだが非常にストーリーに沿った内容になっている。巧みなケミカル・ビーツで織り成される16歳の少女のあどけなさや可愛らしさ、葛藤や苦悩、悲しみ。スクリーンの中の世界に生きる"ハンナ"という少女の生き様を通して奏でられた音楽は、これまでの彼らの音楽で感じることの出来なかった温度がある。派手さは無いが、心にずしりと響く全20曲。
-

-
CherryHearts
CherryHearts
昨年冬にデビューを果たした4ピース・ガールズ・バンド、CherryHeartsによるフル・アルバム。1stフルがセルフ・タイトルという超王道っぷりといい、デビュー・シングルの表題曲を収録していないというチャレンジ精神といい、華やかなルックスのメンバーといい、ここまで健全にギラギラ且つキラキラしたバンドはいそうでいなかった。快活な歌声とハイテンションなバンド・サウンド、そしてトキメキ&笑顔&希望至上主義の視点で描かれる全11曲はどれもとびきり陽性。普段なら恥ずかしくてためらうほどのポジティヴさも誰かの翼になりえる、という音楽のマジカルな力を目一杯謳歌する4人の姿が目に浮かぶ。バンドの自己紹介としては申し分のない作品。
-

-
CHERRY NADE 169
なまえ
メンバーの交代を経て2年ぶりのリリースとなった今作は、ただひたすら愚直に、"君と僕"の繋がりを描いている。とはいえ甘いラヴ・ソングではない。弱音も吐くし文句も言うけど、絶対負けたくない、君と生きたい、君もそうだよね? そんな少し情けない"僕"の感情を、透明感のある力強い歌声で、脇目も振らず直球で届けようとする曲の数々。本当は思っていても言えない苛立ちや嫉妬も吐露し、人間臭い部分まで表現しているのが彼らの魅力だろう。表題曲「なまえ」では大胆にも音楽シーンや若手バンドに中指を立てて苦言を呈し、抗う様子を見せる。楽曲はどれもキャッチーでありながら、今を闘いながら生きる者に、一緒に闘ってくれるような感覚を与え鼓舞する、優しさとロック精神を孕んでいる。
-

-
CHERUB
Year Of The Caprese
ディスコだ!ファンクだ!R&Bだ!......と叫んだところで、今、世界中のポップ・シーンはそれらに埋め尽くされているわけで、やはりBLOOD ORANGEやFKA twigsのように、ジャンルで語ることが野暮になるほど、サウンド自体を蹂躙してしまうアーティストの圧倒的な"自我"のようなものをリスナーとしては欲してしまう。その点で言うと、このナッシュビル出身のデュオ、CHERUBのメジャー・デビュー作にそれはない。でも、いいと思う。何故いいかと言えば、彼らはとっても"上手い"から。身を任せるのにちょうどいいゆったりとしたリズムも、心のひだをさらっと撫でるメロウなうわものも、全体的に凄くハイファイだけど、時折ちらりと覗くハンドメイドな耳触りも......全部、上手い。かなり優れたポップス職人だと思う。
-

-
The Cheserasera
幻
会場/通販限定盤『最後の恋 e.p.』から約1年2ヶ月ぶりの新作となる4thフル・アルバムは、バンドの表現方法が格段に増えた作品となった。それは変化というより、もともと持っていたマインドや感受性を、より繊細に音へ落とし込んだという言い方が正しい。手数の多いドラムとかき鳴らされるギター、洒落たベースで展開されるリード曲で幕を開け、まくしたてるヴォーカルと耳を劈くようなディストーションがスリリングなTrack.2、透明感のあるアルペジオがロマンチックなTrack.3――次々に異なる情景を描いていく様子は清々しい。楽器の練られたフレーズが音色を、音色がコード・ワークを、コード・ワークがメロディと歌詞を、メロディと歌詞がヴォーカルを生かすという美しい循環が絶えず鳴り響く。
-

-
The Cheserasera
WHATEVER WILL BE, WILL BE
アルバム・タイトルの意味は"なるようになるさ""なるようになれ"。すなわちこのThe Cheseraseraにとって初のフル・アルバムは、セルフ・タイトルと言える。2014年6月にメジャー・デビューし約7ヶ月。今作で彼らは感情のまま突っ走るのではなく、今まで培ってきたストレートなギター・ロックを軸に、聴き手の心に響かせるためにどうするべきか真摯に向き合い、音や言葉の細部まで表現を突き詰めた。その結果、サウンドのダイナミズムや音楽性も拡張し、これまで以上に歌がふくよかに響く。宍戸翼のヴォーカルにも、普段の生活でふとした瞬間に訪れるやるせなさや切なさを優しく吹き消すような余裕が生まれた。彼らは自身の音楽を最大限に生かすための方法を、この作品で掴んだのだ。
-
-
The Cheserasera
WHAT A WONDERFUL WORLD
2009年の前身バンド結成以来、堅実的な活動で着実にステップ・アップしてきた3ピース・バンド、The Cheseraseraがメジャーにフィールドを移す。ざらついたディストーション全開のギターが焦燥的に鳴り響く正統派ギター・ロックに、ブルースを感じさせるセンチメンタルな歌心――テクニカルな変化球だらけの日本のロック・シーンでは、彼らの音楽は至極シンプルだ。どんなバッターにも剛速球ストレートをぶち込むピッチャーのようでもある。だがそのど真ん中の球が、どんな人間でも打ち返せないほどの威力を持ったら、間違いなく無敵だ。The Cheseraseraはその球を投げるため、ひたすら身を削り、喉を枯らし、音を鳴らす。そんな挑戦と野心を感じさせる華々しいデビュー・アルバムが完成した。
-

-
The Cheserasera
The Cheserasera
昨年3月に開催した下北沢SHELTERでのワンマン・ライヴはソールド・アウト、10月にリリースしたタワレコ限定シングル『Drape』は新人ながらにしてインディーズ・デイリー・チャート1位を獲得するなど、次々と快挙を成し遂げた注目の3ピース・バンドThe Cheseraseraによる1stミニ・アルバム。宍戸 翼のエモーショナルな歌声と、日常から切り取られたシニカルで憂いのある歌詞がぐさりと心に刺さる。クールなようでいて実はセンチメンタルな楽曲の数々を、エッジの効いた突き抜けるようなギター・リフと、野性的でありながらバランスを計算し尽くしたベースとドラムが彩ってゆく。厳しい現実を生き抜いてきた人にこそ胸に沁みる作品ではないだろうか。
-

-
THE CHESS
太陽を追いかけて
空間的でエフェクティヴなギターで、シンプルなバンド・サウンドでいながらもシンフォニックな雰囲気を生み出しているTHE CHESS。そんなサウンドに対して、メロディは透明感がありながらも、まっすぐで力強く、あたたかな温度をまとっている。聴く人の支えになるような音楽をというメッセージを込めているが、それは面と向かって手を差し伸べるというよりも、横並びになって相手の話や呼吸に耳を傾ける感覚で、"見守る"に近い。その、ほどよい距離感が心地良さに繋がっているようだ。シリアスで、あたたかなラヴ・ソングが多く、本人たちは少しハズしがあってもよかったかもしれないと語ったが、「Rolling Stone」の疾走感の高いロックンロールや、哀しくも美しい物語と牧歌的なサウンドによる「ゴーストがやってくる」など、変化に富んだ内容。
-

-
Chicago Poodle
Fly~風が吹き抜けていく~
昨年3月のシングル「Odyssey」でのメジャー・デビューから着々と人気を集めて来た彼らから待望の4枚目のシングルが届いた。彼らの魅力はポップスとも形容される普遍的なものながらリスナーをハッとさせる意外性に富んだメロディと真っ直ぐで心地いい歌詞にあると思う。今回のシングルはそのポイントをグッと押さえた疾走感溢れるナンバー。まさにこれからの季節にピッタリの楽曲だ。本誌のインタビューでも答えてくれたようにCHICAGO POODLEは本当に四季を感じさせてくれるバンドだ。花沢耕太による流れるような変幻自在の伸びやかなヴォーカルは今作でも健在だ。メジャー初フル・アルバム以降の彼らの新たな一歩をしっかりと刻んだ充実のシングル。
-

-
Chicago Poodle
僕旅
デビュー作から3作連続でFMパワー・プレイ・ランキングTOP3入りの快挙を果たした、関西発名曲工房バンドCHICAGO POODLEから1stフル・アルバムが届けられた。名曲工房バンドの名に恥じない楽曲が並ぶ中、普段は作詞をしないボーカル花沢が作詞を担当し、ピアノ一つで歌い上げたしっとり聴かせる「空の青」や攻撃的な歌詞とダンサブルなグルーヴが気持ちいい「スーパースター」などがいいスパイスとなってアルバムをバラエティ豊かなものにしている。『僕旅』というタイトル通り様々な世界を僕等に見せてくれる名刺代わりの一枚。そしてこれからの季節にはピッタリの作品だ。年末からいよいよ全国ツアーもスタート。彼らの旅もまだ始まったばかり。
-

-
CHILDISH GAMBINO
Camp
俳優、ライター、コメディアン、そしてミュージシャンと様々な顔を持つDonald Glover。彼による新音楽プロジェクトがこのCHILDISH GAMBINO。過去にも同名義で数枚アルバムをリリースしているが、今年アメリカの名門レーベルGlassnote Recordsと契約し、本格的なCDデビューとなる。DJやプロデューサーとしての経歴を生かし、ヒップ・ホップをベースに様々なジャンルの音を融合させ、個性的な音楽を作り上げている。歌詞の題材は家族の問題、イジメ、男女関係、自殺願望やアルコール問題など、ありがちといえばそうだが、彼の声にはその歌詞がスッと心に入り込んでくるような力があり、時に激しく語り、時に繊細に歌い上げている。叙情的なUKバンドの楽曲を聴いているような哀愁も感じられ、多彩な楽曲が収録された宝箱のようなアルバムだ。
-

-
Chilli Beans.
blue night
今年2月には自身初の日本武道館ワンマンを成功裏に収めたほか、各地の音楽フェスにも多数出演、そんな充実の2024年を締めくくるChilli Beans.のミニ・アルバム。バンド初となる全編英詞で書かれたリード・トラック「escape」をはじめ、UKロックと接近した「Mum」、メロウなトラックがBillie EilishやCLAIROの最新作を彷彿とさせるベッドルーム・ポップ「fu uh」、ピアノと歌のみで構成された「look back」等、彼女たちの源流にあるインディー・ロックの影響を感じる1枚になっている。また、インタールードを挟んでラストに置かれた(いい意味で)ぶっ飛んだ規格外の「cyber」も必聴。抜群のセンスと柔軟な感性に感服させられる。
-

-
Chilli Beans.
Chilli Beans.
洋楽ポップスにルーツを持ち、3人ともヴォーカルを務める3ピース・バンド、Chilli Beans.の初フル・アルバム。彼女たちの名が知られるきっかけになった、Vaundyとの共作「lemonade」、「アンドロン」、そしてリード曲「School」をはじめ、抜け感があり肩ひじ張らない自然体な空気が漂うナンバーたち。だがRED HOT CHILI PEPPERSから取ったバンド名の"Chilli"のように、内面で燃えるソウルフルな想いが詞や演奏に滲む。14曲とたっぷり収録の本作では、低めの歌唱や"バカにされる筋合いもない"の言葉も印象的な「This Way」、危うげな繋がりをダークなムードで歌う「neck」など、より幅広い表情も見せ、セルフ・タイトルに相応しい聴き応え抜群の1枚に。
-

-
Chilly Gonzales
Solo Piano II
カナダ出身で現在はパリを拠点に活動しているChilly Gonzales。ピアニストやソングライターとしてだけではなくプロデューサーとしても有名で、Jane Birkinのアルバム『Rendez-Vous』をプロデュースして一躍注目を浴び、iPod nanoのCMソングにもなったFeistの「1234」をプロデュースしたことでも知られている。2004年にリリースしたピアノ作品集『Solo Piano』の続編と呼べる今作は、タイトル通り“ピアノだけ”の純粋で深みのあるアルバムに仕上がっている。カナダに居た頃に無声映画にピアノの伴奏をつける仕事をしていたことがあるからかもしれないが、1曲1曲に風景が思い浮かぶようにドラマティックで映画のサウンド・トラックを聴いているよう。壮大ではあるが仰々しい感じはなく、叙情的でどこか切なくなるのがピアノのみでも飽きずに聴ける理由かもしれない。
-

-
!!!
Certified Heavy Kats
2019年夏に8thアルバム『Wallop』をリリースしたばかりの!!!が、1年足らずの新作となるデジタルEPを発表した。今回は『Wallop』のチルな雰囲気を引き継ぎつつ、様々なクラブ・ミュージックをさらに大胆に取り入れた作風に。2ステップ/ガラージの影響が色濃いTrack.1や、ハイテンポでポップなジューク/フットワーク調のTrack.2、ウッド・ベースのリフにハウス・ビートが絶妙に絡みつくTrack.5と、あらゆるスタイルを飲み込みつつ、!!!らしい身も心も揺さぶるようなエネルギーに満ちたトラックを作り上げている。東京やデトロイトなど世界各地の都市名が歌詞に組み込まれた、約7分半の長尺曲で余韻を残しながら締めくくる構成も巧みで、ついリピートしたくなる。
-

-
!!!
Wallop
お馴染みニョーヨークが誇るディスコ・パンク・バンド、!!!が通算8枚目となるニュー・アルバムをドロップ。前作『Shake The Shudder』で推し進められたダンス・ミュージックへのアプローチは、今作ではさらに強化された印象だ。80年代ポップを思わせるキャッチーなTrack.5やファンクネスが光るTrack.9から、エレクトロ・ハウスのニュアンスが垣間見えるTrack.1、トラップを思わせるブラス使いが印象的なTrack.11まで、多様なスタイルを咀嚼した、これまで以上にバリエーションに富んだ作品に仕上がっている。エネルギッシュなフロアの熱量も、チルなムードも併せ持った本作がライヴでどう披露されるのか、10月から行われるジャパン・ツアーにも期待が持てそうだ。
-

-
!!!
Shake The Shudder
どんなジャンルと交差しても、どこか沸騰するようなエモーションとエッジ、そしてちょっとイカれた楽しさが溢れる、!!!。彼らが"恐れを振り払え"と題したニュー・アルバムは、従来のディスコ・パンク・バンドのスタンスはそのままに、ビートやサウンドメイキングでグッとハウスに寄った印象だ。MVも公開されているTrack.1のエレクトロニックでジャングリーなニュアンスは現行のR&Bにも通じるセンスだし、Track.5やTrack.7は、ミニマル・ファンク的で、PRINCEがポスト・パンクを演奏しているような隙間の多いスリリングで何が起こるかわからない、いい緊張感も孕んでいる。そして今夏の"SONICMANIA"で久々の来日となるステージでも盛り上がりそうなTrack.3は、どんなライヴ・アレンジになるのかも注視したいところ。
-

-
!!!
As If
猥雑でやぶれかぶれなディスコ・パンク・サウンドで世界中のミュージック・ジャンキーを熱狂させ続ける!!!による6枚目のアルバム。デビューより徐々に音楽性を深化させ、前作『Thr!!!er』では狂騒的なディスコ・パンクというパブリック・イメージから脱却、次なる一手を予感させた彼らが提示した今作『As If』は、端的に言うとダンス・レコードだ。ミニマル・ファンクなビートのTrack.1、ロマンティックなきらめきのあるロック・チューンのTrack.3、ディスコ・アンセム的なTrack.4、ハウスの刹那的高揚感を体現するTrack.7、ソウル/ゴスペルを取り入れるチルなTrack.10などをシームレスに繋ぐ完全クラブ仕様。かつての振り切った野卑さはなく、渦巻く禁欲的なエネルギーに限りない知性を感じさせる1枚。
-

-
!!!
Thr!!!er
ニョーヨークのディスコ・パンク・バンド、!!!が約3年ぶりにリリースした5作目のアルバム。これまでジャム・セッションで曲を作っていた彼らは今回、初めて組んだプロデューサー、Jim Enoのサジェスチョンによって、しっかりと曲を書き上げてからレコーディングに臨んだそうだ。最強・最凶と謳われてきたライヴ・バンドによるそんな挑戦は、ポップ・ソングとしてアピールできる曲を作るポテンシャルをとことん高め、このアルバムをきっかけに彼らが新たなファン層を開拓したことは想像に難くない。それが物足りないという昔からのファンもいるようだが、ライヴにおける彼らが何も変わっていないことは7月の来日公演が証明した。バラエティーに富んだ粒揃いの曲の数々とクールなトラック・メイキングがバンドの成熟を印象づける。
-

-
!!!
Strange Weather, Isn't It?
今度はどんなヤバイものを作ったんだという期待と興奮で、プレイ・ボタンを押す手にも力が入る。!!!って、そんなバンドの一つでしょ?その期待はあっさりと更新された。音数が整理され、研ぎ澄まされたビートに驚かされる冒頭の「AM/FM」から、もう堪らない。これ、現代版THE CLASH「This Is Radio Clash」。あ、タイトルまで繋がった。だが、この曲ですら序章でしかない。これまでと一線を画すスタジオ・ワークへのこだわりが生み出すファンキー・グルーヴの波が次々と押し寄せてくる。共同プロデューサーEric Broucekを介したDFAとのリンクが彼らの知的で凶暴な肉体性をさらにブラッシュ・アップさせている。全身からアドレナリンが溢れ出して止まらない。
-

-
Grand chocol8(ex-chocol8 syndrome)
天性のドロドロE.P.
今年4月、Grand chocol8として新たなスタートを切った新生ちょこはちの記念すべき1st EP。タイトルが秀逸だ。ちょっとアンニュイなトラックに、取り柄も才能もない存在をただただ肯定するかのような歌詞が印象的。とかく自己嫌悪や罪悪感に苛まれがちな人間にとっては、かなりの度合で救われるであろう1曲だ。カップリングの「宵の星」は懐かしさが漂うサウンドに過去の青春を絡め、「郷愁」では現在進行形の青春から少し先の未来を描いた。過去、現在、未来という流れの中に今現在のちょこはちがしっかり表れていることを感じる。まったく別モノのバンドになったという言葉通り3人の新たな挑戦と、そこから得られた自信が凝縮されたかのような1枚。ここからどう進んでいくのかが非常に楽しみでもある。
-

-
Grand chocol8(ex-chocol8 syndrome)
音楽はメジャーが全てじゃない!
シンセがガンガン鳴る曲もあれば、エレキ・ギターが前面に出た曲もあるし、レトロなメロと電子音を掛け合わせた不思議な雰囲気の曲もある。また、金が欲しいと連呼する身も蓋もない曲の直後にはドラマチックな展開のワルツを配置。そしてラストはまさかのラップ。前作の時点で予兆はあったが、なんでもありのモードに入りつつあるchocol8 syndrome。それに伴い各プレイヤーに求められることも当然増えてくるわけで、特にしゃおん(Vo)は、全編ファルセットの「冥王代で会ってる」から低音域で力強く歌う「ダイスロール」まで幅広いアプローチも見せている。ライヴでは演奏以外にもこだわりながらみんなで笑える空間作りを目指す彼らならではの、エンタメ精神に満ちた作品。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























