DISC REVIEW
ア
-

-
OKAMOTO'S
VXV
CDデビュー5周年を迎え、1月に5thアルバムをリリースしたばかりのOKAMOTO'Sによる"5.5th"アルバムは5組のアーティストとのコラボレーション作品。RIP SLYMEとはAEROSMITH & RUN-D.M.Cばりのオールド・スクールな王道ヒップホップとハード・ロック・サウンドの融合を聴かせ、スカパラとは大編成イケイケ音楽部隊と化し、Wilson PickettばりにシャウトするROYとはクロさ全開で渡り合う。タイトルと曲調から"民生愛"がビンビン感じられる「答えはMaybe」と、いずれもOKAMOTO'Sならではの、この企画を実現できる実力と各アーティストへの敬意を感じさせる内容。中でもラストの黒猫チェルシーとのデュエット「Family Song」が出色で、2組の友情を感じさせる感動的な楽曲となっている。
-

-
東京スカパラダイスオーケストラ
World Ska Symphony
スカという枠組みをさらに押し広げながら独自のスタイルを確立して20年間君臨するスカパラ。多彩なスタイルと方法論で、大衆性と独自の音楽性を両立する彼らの面目躍如とも言えるポップなアルバムだ。洗練されていながら、ダイナミズムに満ちたその音楽性はもちろんだが、スカパラほどメジャー・フィールドに対して戦略的なバンドはそういない。それはスカパラのようなバンドが未だに現れないという事実が物語っている。例えば多様なコラボ(今作では奥田民生、Crystal Key、斉藤和義が参加)をとっても、とてつもなく意識的で戦略的だからこそ、その高い音楽性をキープできるのだろう。「Won't You Fight For Happy People?」スカパラはファイティング・ポーズをとり続けている。
-

-
小谷美紗子
MONSTER
いくつも世の中に蔓延っている"薄っぺらなラブ・ソング"に飽きたという方にこそおすすめしたい、キャリア20周年を記念した弾き語りオールタイム・ベスト。好きだという感情を好きだと言わずして想いを伝える術を身につけてる彼女。愛情や哀情などの感情を生々しく表現している歌詞に要注目。特に、遠くにいるあなたのことを信じているという「手紙」、"コエガキキタイ アイタイアイタイ"とそれしか考えられなくなっている「Off you go」、元彼の新しい彼女に対して嫉妬心を曝け出す「こんな風にして終わるもの」など、ピアノで弾き語ることで感情の重さは2トン・トラック級。20年もの重みがここにしっかりと詰まっており、さすがのひと言。今作をもって歌詞世界に浸るのはもちろんだが、原曲をチェックしてさらに小谷ワールドの虜になってみてはいかがだろう。
-
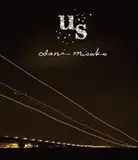
-
小谷美紗子
us
本作『us』は、震災以降最初の小谷美紗子の作品である。冒頭を飾る「enter」で打ち鳴らされる、殺伐としたブレイク・ビーツに宿った不安と苛立ち。しかしこれを出発点としながら、小谷はこのアルバム1枚かけて穏やかさと優しさを手に入れるための歌とメロディを目一杯の力で奏でていく。無論、不安や苛立ちは消え去っていない。Track.8「東へ」は震災直後に名古屋へライヴに行った時の車中での体験を元に書かれたというが、アルバム全編を通して小谷が今の社会、そして自分自身に向ける視線には鋭さが宿っている。だが、彼女は本作を聴く一人ひとりのリスナーに対して、慈愛にも似た無垢な優しさを与えようとする。あなたが穏やかでありますように――本作には、そんなことが書かれた手紙のような親密な祈りがある。
-

-
おとぎ話
CULTURE CLUB
"涙を拭きなよ男の子 下向いてる場合じゃないんだぜ"――かつておとぎ話は1stアルバム『SALE!』の中でこのように歌った。あれから7年以上の時が経ちリリースされる『CULTURE CLUB』は、これまでの愛と戦いの日々を音楽にした、おとぎ話の最重要作品だ。ここまでの道のりは、決して無難なものでも順風満帆なものでもなかった。だからこそ、もはやロックやオルタナやフォークの範疇では捉えきれない「光の涙」と「COSMOS」の懐かしさを掴まえたメロディと優しく力強い言葉は、泥まみれで光り輝き、胸を締め付ける。"おとぎ話"という言葉をそのまま音楽にしたような彼らの音楽には"音楽の魔法"が宿っている。それはこれまでずっと変わることのなかった、僕たちとおとぎ話の愛の魔法だ。
-

-
おとぎ話
FAIRYTALE
おとぎ話が、本気で覚醒したのではないだろうか。有馬のポップなメロディ・センスと歌詞世界を、しっかりとオルタナティヴ・ロックとして具現化している。一つ一つの楽曲の完成度の高さ、アイデアの豊富さ。そして、それを日本語でしっかりと「届ける」ことができる歌心。インタビューでは、「妖精」について「DINASOUR Jr. みたいにやろうとしたけど、出来なかった」と笑い「出来なかったが、まったく独自の音になった」と確信的に言う有馬。そう、ここでは一つ一つの音が、確信的に鳴っている。何となく、洋楽ロックのリスナーに避けられがちな位置にいる気もするが、そういう人にこそ聴いてもらいたい。くだらない物言いだけど、おとぎ話がUSインディから出てきていたら、もっと売れているはずだもの。
-

-
音沙汰
SUPER GOOD+
太陽は人を照らすが、では太陽を誰が照らしてくれるのだろうか。人は母なる海へと帰っていくが、では海はどこへ帰ればいいのか。星空は僕らの哀しみを癒すが、星々の涙は誰が拭うのか。大きいものはそれだけで優しくて、だからこそ孤独でもある。SEBASTIAN Xの永原真夏という人は、そんな大きなものの孤独と哀しみを知っているからこそ、ステージの上であれだけ強く美しく輝いていられるのかもしれないと、この工藤歩里とのユニット=音沙汰の初音源を聴いていると思う。ここには、歌とピアノというシンプルな編成によって紡がれた、まるで太陽や海や星空のように大きくて優しくて孤独な曲が並んでいる。帰る場所を持たない子供たちと、届くことのない"I love you"のための音楽。「ホームレス銀河」とSuiseiNoboAzの名曲「64」のカバーが特に素晴らしい。
-

-
音の旅crew
JOYSTEP
前身バンドを経て、2012年に活動開始した4人組がニュー・アルバムを完成させた。今作はこれまでのライヴ経験を活用し、ライヴで盛り上がれる曲調を増やした野心作。pepe(Gt/Vo)の爽快な歌メロを生かしたヴォーカルを主軸に、歌って踊って騒げるレゲエ・ロックを掻き鳴らしている。ライヴハウスを激しく揺らすダンス・チューン「my pace space my place」、フリースタイル風の歌を織り込んだミクスチャー・テイストの「Rebel soul dance」、いきなりドラムで始まる展開が面白い「MDNT EXPS」も勢いがあり、これも生で聴いたらアガること必至の曲調だ。全8曲の内容だが、1曲1曲が個性的で作品トータルで聴かせるクオリティの高さも備えている。これからが楽しみなバンドと言っていいだろう。
-

-
オトループ
反響定位
オトループの楽曲が聴き手の心に深くストレートに届くのは曲ごとのテーマがとてもはっきりとしているからだ。今作『反響定位』でも、毎週"サザエさん"の時間になると抱いてしまう月曜日の憂鬱「ブルーエストマンデー」や、バイトの飲み会が苦手な「Hit Me Silly」、就活がうまくいかずに現実逃避する「人間エントリーシート」など、そこで歌われる出来事がリアルに想像できるものばかり。そのテーマの奥にあるのは、この生きづらい世の中で何が正しいかを模索する人間のあがきであり、大切な人への想いであり、言葉にしづらい感情そのもの。それを訴求力のあるメロディと骨太且つバラエティに富んだバンド・サウンドに乗せて届けるオトループの音楽は、いつも誰かの日常を救うために鳴り続けている。
-

-
オトループ
カメレオンは何も言わない
2005年に纐纈悠輔(Vo/Gt)を中心に結成、今年10周年を迎えたオトループが完成させた4thミニ・アルバム『カメレオンは何も言わない』は彼らの勝負作。無駄な音を削ぎ落とした疾走感のあるストレートなサウンド、歌と歌詞をまっすぐ届けるために組み上げられた繊細且つアグレッシヴなバンド・アンサンブル――今作にはそんな聴く者の耳と心にストレートに訴えかける7曲が並ぶ。纐纈の紡ぐメロディはポップさとキャッチーさに一層磨きがかかり、綴られる歌詞は言葉として抜群の強度を誇る。素直になれない思いを抜けの良い四つ打ちのビートで描き上げる「アマノジャクの独白」、周りに合わせ器用に生きる現代人の病理を浮き上がらせる「無色透明カメレオン」、歌謡テイストのメロウなメロディで元恋人への思慕を綴る「モトカノループ」など、ギミックに頼らない高純度のポップ性に打ち抜かれる。
-

-
踊ってばかりの国
光の中に
踊ってばかりの国が立ち上げた新レーベル"FIVELATER"からリリースする第1弾作品。サイケデリックなサウンドと気だるそうな下津光史(Vo/Gt)の歌声は健在ながら、人として、バンドとして歳を重ねるごとに"今が一番カッコいい"を更新し続けている。本作に収録されているのは、下津だからこそ描ける美しさを持つバラードの表題曲「光の中に」など全13曲。中でも約2分間のイントロにガッチリ心を掴まれる「ghost」は、"乗っ取って 僕を乗っ取って 身体はいらないから"といういかにも下津らしい歌詞や、"幽霊"ではなく"生"の踊ってばかりの国の魅力がしっかりと存在しているところが素晴らしい。昨年の大みそかに渋谷のスクランブル交差点で撮影されたMVもぜひ併せて観てもらいたい。
-

-
踊ってばかりの国
踊ってばかりの国
2ndアルバムで「世界が見たい」と歌った下津光史には、きっと今、とてもはっきりと世界が見えている。『踊ってばかりの国』というアルバム・タイトルは、セルフ・タイトルである以上に、様々な事象で揺れ動くこの国の現状を暗に示しているようだ。これは今、最も美しく汚れたブルース・アルバム。若き歌唄いたちが作り上げた、本質的な愛と悲しみのアルバムだ。僕が最も好きな曲は「サイケデリアレディ」。このラインがいい。"この痛みが僕の糧さ 心じゃなく体が痛い"――自称"メンヘラ"ちゃんたちには理解できないだろう、生きているからこそ実感する、本当の痛みの歌。だからこそ、このアルバムには本当の喜びもある。滴り落ちるロマンティシズムもある。シンプルかつ美しいメロディによって紡がれた、今最も必要な音楽。
-

-
踊ってばかりの国
世界が見たい
我が子を抱いた悪魔は、一切の淀みのない生命体の存在を、無償の愛情というものを知ってしまった。――実生活で父親となった下津光史(Vo&Gt)。それが結果として彼独自の死生観のバランスを崩壊させたのかもしれない。これこそある種の境地というべきか。"死ありき"の世界を歌っていたこのバンドが辿り着いたのは、朽ちていくばかりの世界ではなく、"死ぬ"からこそ"生きている"のだという、痛々しいほどの"生"の美しさ。更にポップに、だが胸に詰まるメロディに乗せ、彼はこう歌う、"また笑って会いましょう 生きてたら""言葉も出ないだろう 死ぬんだから"。生の喜びと死の刹那とが共存し、生と死が同じだけ活き活きと輝く、生死すら曖昧な者にしか辿り着けなかったであろう、ぎりぎりの世界だ。踊ってばかりの国は、遂に此処まで辿りついてしまった。
-

-
踊ってばかりの国
SEBULBA
08年神戸にて結成された5人組、踊ってばかりの国の1stフル・アルバム。自主制作盤のミニ・アルバムからの曲も収録された本作は、ここまでのバンドの集大成的な選曲となっており、その素晴らしき成長ぶりがよくわかる。昔はやたらダウナーな奴らばかりの単なるサイケデリック・ポップ・バンドだったわけだが、4月で結成4年目を迎えるメンバー全員平成生まれのこの若いバンドは、ますますイカれちまって、ますます異質な存在となっていく。フィッシュマンズ、佐藤伸治のようなどんよりした夢見心地な下津(Vo)の声と少し懐かしいメロディ、ひとつひとつの音にファズがかかり、音像がクリアに捉えられないこのどろりとした心地よい音は、時に"死ぬこと"そのものを歌い、どす黒いサイケデリアという底なし沼を描き出す。
-

-
オモイメグラス
図解と消えたフィラメント
オモイメグラスの変革期なのだろう。その変革はシンセやストリングスを用いていることももちろんなのだが、どの曲もひたすら、目の前に広がる靄をどうにかして打ち消そうともがいている。それは彼女たちの現状なのかもしれないし、世間なのかもしれない。オモイメグラスというバンドは何ひとつとして満足をしていない。そんな反抗やエネルギーを、彼女たちの美意識で昇華しているのがこの『図解と消えたフィラメント』だ。ベーシストの脱退から"自分たちのやりたいこと"と向き合って完成させたサウンドは自由度が広がり、より外へと向かっている。インストの枠を飛び越えたTrack.4、シンプルなバンド・サウンドと鍵盤で突き進むTrack.5、優しいメロディで包み込むTrack.6など、むき出しの強い意志に息を飲む。
-

-
オモイメグラス
コラージュとして切り取られ、残された側
2012年結成、紅一点ヴォーカルを擁する4ピースの、インディーズ・デビュー盤から8ヶ月振りとなる2ndミニ・アルバム。バンド名やアルバム・タイトルなどからも読み取れるように、日本語を重んじた歌詞と情感たっぷりの歌声が作り出す波紋が、切り取られて残された側の想いを廻らすように無限に広がる。そんな切なる叫びの先にあるのは、つらいことも嬉しいことも全てを受け入れる覚悟。もがきつつも光を見据え、自らを貫く姿は実直だ。サカナクション、東京事変、フジファブリックなど、鍵盤楽器を巧みに用いたバンドから影響を受けているのもあってか、バンド・サウンドという枠に囚われない柔軟なアプローチ。8曲全てに自らの音楽が秘める可能性を貪欲に追い求めようとする姿勢を感じる。
-

-
オルターリードコード
gloomy box
近年、音楽的にひとつのジャンルに特化することなく、様々な音楽的要素を内包した楽曲を作るアーティストは決して珍しくないが、北海道札幌市を拠点に活動するバンド、オルターリードコードの1stフル・アルバム『gloomy box』は、まさにそんなジャンルレスな楽曲を詰め込んだ1枚だ。激情的でストレートな曲かと思いきや、間奏でラテン調に変化するところが面白い「PA・PA・RA・PA・PA」や、メタル、V系、アニソン調なイメージが浮かぶ「dummy system,fake core」、ミクスチャーっぽさ炸裂の爆音「サマーダンス」など、曲ごとに様々な表情を見せる。それらの曲が、大山亜理沙(Vo/Syn)のヴォーカルが乗ることで、ポップスになる化学反応がこのバンドの強みだろうか。特に、90's J-POPの懐かしさを纏ったタイトル曲「gloomy box」にそれを感じる。
-

-
オレンジスパイニクラブ
アンメジャラブル
オール新曲で挑むメジャー1stフル・アルバム『アンメジャラブル』。温かく素朴なサウンドの1曲目「ガマズミ」から、エッジの効いたUKロック調の2曲目「退屈かも知れない」と早速そのギャップに驚かされる。スズキユウスケ(Vo/Gt)、スズキナオト(Gt/Cho)兄弟が曲ごとに作詞作曲を担当し、アルバムを通しても12曲それぞれが異なる表情を見せているが、同時にどの曲もオレスパ色に染まっている。そこに一貫性を持たせているのは、日常を映す歌詞と哀愁漂うメロディ、そして曲全体を包み込む柔らかな歌声だろう。時折見せるパンク・ロックな一面もまた彼ららしい。まさに"計り知れない"(=アンメジャラブル)音楽性の幅広さを示すとともに、"オレスパらしさ"を確立させるアルバムとなった。
-

-
オワリカラ
PAVILION
結成10周年を迎え昨年末に初のベスト・アルバムを発表したオワリカラが、自主レーベル"PAVILION"を設立。その第1作目として会場限定シングルのアルバム・バージョンと新曲を詰め込んだ、約3年ぶりのオリジナル・アルバムをリリースする。オルタナ、ダンス・ミュージック、サイケ、プログレ、歌謡曲など様々な要素をブレンドさせ、それを高度なアンサンブルとピュアなエモーションで組み上げる手腕、スタイリッシュになりきらない絶妙ないびつさは今作も健在。そこからさらに既発曲含め、元来彼らが持ち合わせていたロマンチシズムが、よりディープでありながらユーモラスに響く楽曲が揃った。中でもタイトル曲はキャリアが生んだ洗練性、引き算の美学と豊かなコーラス・ワークが歌詞の重みを引き立てている。
-
-
オワリカラ
サイハテ・ソングス
オワリカラというバンドは、いつもちょっと人と違う場所にいる気がする。そんな4人が作り上げた極上の楽園――1st『ドアたち』はまさしくその結晶だった。そこから聴き手の心に突き刺さり踊らせる2nd、聴き手に問いかける3rdと徐々に楽園の入り口を広げ、今作4枚目は我々にまだ見ぬ新たな場所へと"行こう"と手を差し伸べる、いわば集大成であり新たな出発を感じさせる深い深いアルバムだ。1曲1曲に含まれる強いメッセージに、4人がこれまで歩んできた生きざまを落とし込んだ本能を刺激する直情的で耽美的な音色。強い気概を持ち、先陣切って歩き出す彼らに追いつくのは、もしかしたら容易いことではないかもしれない。だが追いかけるという行為やそのときに見える景色、感じた想いは間違いなく美しいはずだ。
-
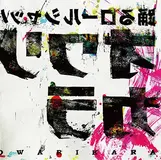
-
オワリカラ
踊るロールシャッハ
昨年5月にリリースされた3rdアルバム『Q&A』以来となる新作は、ライヴでおなじみの新曲にライヴ音源4曲を加えた全5曲ワンコインという太っ腹シングル。"ロールシャッハ"とは、インクを紙の上に垂らし、それを二つ折りにしてできた模様から何を想像するかをもとに性格などを判断する心理テストのこと。"ロールシャッ!ハッ!ハッ!"というサビなどの歯切れの良い語感を生かした歌、4人各々がインパクトのある音を鳴らす"点"を生かした構成で、音の隙間もリズムを作る重要な役割になっている。キャッチーでありながらも緊迫感のあるグルーヴは、推理小説のような謎めいたハラハラ感。楽しいだけではない空気を醸しながら踊れるナンバーを作る彼らのセンスと知性には相変わらず感服だ。
-

-
オワリカラ
Q&A
"オワリカラなのにオワリカラじゃない。そうか、これが今のオワリカラなんだ"と、前作『イギー・ポップと賛美歌』で思ったが、今回もそうだ。自分たちの新しい可能性を試したくて、それが面白くて仕方がないのだろう。瑞々しいサウンドに焦りの文字は無い。それは1stアルバム『ドアたち』から一貫しているから感服だ。"Q&A"というミニマルなコミュニケーションをテーマに掲げた今作は非常にストレートで、小難しいリズムも皆無。だが彼らが培った経験は、オワリカラ特有の謎めいたムードとして輪を描いてゆく。じっくり聴かせる楽曲、疾走感のあるギター・ナンバーから攻撃的なロックンロール、ファンク、やわらかいサウンドまで多彩な全11曲。皆さんもちょっぴり不思議なコミュニケーション、してみませんか?
-

-
オワリカラ
シルバーの世界
「swing」の振り子は、大きな弧を描きながら「シルバーの世界」へ――。2ndアルバム『イギー・ポップと讃美歌』で、バンドの現在進行形の衝動の全てを叩き込んでみせた、革新曲「swing」。タカハシヒョウリ(Vo&Gt)曰く、"マインドとフィジカルが拮抗している"と言うこの曲は "ハートに訴えかけたい、でも踊らせたい=心と体に訴えかけたい"という、内にも外にも突き刺さる "完全無欠の衝動"が波打つダンス・ナンバーであった。そして本作は、未だ止まらず進行していく衝動が、更にディープに作用する"怪作"である。タカハシの言葉を借りるならば "拮抗している"という、せめぎ合いによるストレス状態すらも超越した"超高揚状態"を味わえる。エンドルフィンもアドレナリンも過剰分泌されるシルバーの誘惑......オワリカラ、最早脳内麻薬の域っす。
-

-
オワリカラ
イギー・ポップと讃美歌
そのドアは、開けても開けても開けても開けても…きりがない。あれはなんだ?終わりなき欲望か?逃れようのない矛盾だったのか?サイケデリックかつディープなネヴァー・エンディング・ストーリーを描き出したデビュー作『ドアたち』はやはり本物だった。本作もまた、前作同様に演奏と言葉の説得力が凄まじく、歌詞はもちろん、音や曲の表情までもが一つのキーワードにリンクしている。今回のテーマは“つきささる”。この完成度の高さはコンセプト・アルバムの類いのものであり、より私的な言葉や表現を全面に押し出したDavid Bowieの『The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars』というような印象を受けた。音と言葉で完璧なビジュアル世界を作り上げたのがBowieならば、彼らは音でもって言葉の本質というビジュアルを明確にしていく。
-

-
オワリカラ
ドアたち
気が付けば、ノストラダムスの予言から11年が経過した訳で、私たちは変わりない毎日を生きている。けれど、恐怖に包まれた1999年以降、あけすけに幸せが充満した音楽に紛れ、シニカルな音楽が着実に育まれてきたように思う。そんな2010年に産み落とされたオワリカラの1stアルバム『ドアたち』。暴力的なまで引きずり込む熱気と、浮遊感あるノスタルジックな余韻が全身を圧倒する。中でも、「団地」は衝撃であった。人々の生活空間を“ハコ”という完結かつ閉鎖された空間となみす客観視の鋭さと、そこに存在する生活をいとおしいと感じる主観的な温もり。そして、最終的には逃れることの出来ない結末を受容する微妙な矛盾。衝動や焦燥感を伴った不安定な感覚は、限界まで掘り下げられ、吟味・咀嚼され、再構築された上で吐き出される。そこには、日常性を剥き出しにするタカハシヒョウリその人の人間性が、色濃く凝縮されているように思う。そして、練り上げた感情を実体として解放できるのは、強烈にストイックな4 つの音が存在しているからだ。誰もが全力で一点を目指す。“全員が4番”というサウンドが互いに音を磨ぎ合うからこそ、言葉が突き刺さるように弾けるのだろう。彼らをサイケデリック・ロックと言うジャンルで括ってしまうのは、どうも解せない。おそらくは、音楽性のカテゴライズというよりも、もっと深いそれ以上の世界を彼らは捉えているのだ。“オワリカラ”始まる“コレカラ”。まばたきする一瞬さえも惜しい。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























