DISC REVIEW
T
-

-
TEGAN AND SARA
Hey, I'm Just Like You
10代でデビューしたカナダのオルタナ・フォーク・ロックの双子デュオもキャリア20年余。本作は自伝"High School"の執筆のために資料を探していた際、発見したキャリア初期のカセットが制作の発端にあったのだとか。自伝と対になっている印象のある本作。現在ではアップデートした大人のエレポップを聴かせるふたりが、THE SMASHING PUMPKINSやPAVEMENTを想起させる、オルタナティヴなギター・ロックとエレクトロニックなアレンジをミックスしているのが楽しい。ただ、そこで歌われているのはティーンエイジャーならではの悩みや手に負えないほどの夢。アルバム・タイトルが示唆しているように、誰もが通ってきた青春期の思いを作品化することで肯定するような印象だ。
-

-
the telephones
Come on!!!
ライヴへの厳しい制限があった最中に会場限定CDを販売するなど、コロナ禍でも挑み続け"バカみたいに踊れる空間"を届けてきたテレフォンズの集大成的アルバムが完成。世の中のピリついたムードに反し、英語でのダラっとした会話から「Adventure Time」が始まると、次第に悩みや邪念は消え去り、ひたすら音楽に没頭しろと歌う「Feel bad」に後押しされ、気づけば何も考えずダンサブルなビートに身をゆだねている自分がいる。今までとはひと味違うサウンドがきらめく「Yellow Panda」やチャイナ感漂うクセの強い1曲「Whoa cha」など、中毒性抜群の楽曲が空っぽになった頭をぐるぐる回って離れない。息の詰まる日々から"Come on!!!"と誘い出し、非日常な世界へと導く渾身のダンス・ナンバー10曲。
-

-
the telephones
NEW!
2018年よりライヴを中心に活動を再開していたthe telephonesが、約5年ぶりにリリースするフル・アルバム。今やそれぞれ他にも活動の場を持っている4人。全体的に曲の自由度が上がっている(「New Phase」は特に実験的)のは各々の度量が大きくなったからと思われるが、そのうえで、バンドの根底にあるUKロックからの影響が滲み出てきている点が興味深い。歌詞でも、プリミティヴな気持ちを大切にしつつ、新たな世界へ挑む姿勢が綴られている。それにしてもダンス・チューンをずっと演奏してきたバンドだけに、どの曲も気持ち良すぎるし、リズムのメリハリのつけ方がそこらのバンドとは全然違う。お家芸を正面切って披露する頼もしさも5年で腹を括れたからか。
-
-
the telephones
Don't Stop The Move, Keep On Dancing!!!
9月にはPOLYSICSとヨーロッパ・ツアーを行ったthe telephones。彼らと言えば"DISCO!!""踊れるロック"というイメージが真っ先に浮かぶが、基盤にあるのは踊れるロックの奥にあるUKロックからの影響だ。"DISCOの向こう側"へ我々を連れていってくれた彼らが今回突きつけてくれたのはバンドの根幹とも言えるその部分。曲名だけ見るとゴキゲンなナンバーだが、シリアスに鳴り響くシンセ、若干の倦怠感を醸し物悲しく鳴り響くギターは時折牙を剥き、空間を繋ぐベースもクールに響く。なのに思わず踊り出したくなる、歌い出したくなる、という美しい矛盾の手ほどきはまさしくDISCOを凌駕するスケール感だ。キャリアを重ねるごとに前進し続けるthe telephonesの現在位置を見せつける。
-

-
the telephones
Laugh,Cry,Sing...And Dance!!!
音楽への感謝という切実な思いを"踊るロック"に昇華していたテレフォンズが、いよいよ"踊るロック"からも自由になったことで、よりロックの自由を手に入れた。シングル以上にブッといグルーヴで聴かせる「Keep Your DISCO!!!」、AIR JAMリスナー世代若手代表的なファストな8ビート「Pa Pa Pa La Pa」、和テイストと汎アジアっぽいメロディの「Odoru〜朝が来ても〜」の新ヴァーション、はやりのシンセ・ポップの1枚上をいく「90's Drama Life」、そしてドラムのセイジの歌の初出しも嬉しい「Four Guys From Saitama City」などなど、メンバー4人の笑顔、バンドの状態の良さがダイレクトに伝わる全12曲。これまでの石毛の美意識が"泣きながら踊る"なら、今は"笑い泣きしながら踊る"イメージだ。
-

-
石毛輝
My Melody (Diary Of Life)
the telephonesのフロント・マンにしてコンポーザーでもある石毛 輝の、前作から約1年半ぶりのセカンド・アルバムが完成した。ヴォーカル、ギター、ベース、ドラム、ピアノ、シンセ等全てを手掛ける才能にも脱帽するが、何よりもメロディ・センスが素晴らしい。歌声は味付け程度に抑えられていて、主役はとにかく音。電子音と生楽器とのバランスが絶妙で、とても耳触りが良い。自ら録音したという自然音も随所で聴こえてきて、神秘的で癒しの効果を生み出している。クラシック・ミュージックのメロディの一節が流れてくるのも印象に残るが、あくまで楽曲の一部として上手く融合されているのがとても効果的だ。もっと聴いていたいと思わせるほどに良い意味であっさりと聴き終われるので、the telephonesが苦手という人にもぜひ聴いてほしい作品。
-

-
石毛輝
from my bed room
石毛輝といえば、髪を振り乱してつんざく高音のシャウト!the telephonesでは、フロアをかき乱す底抜けにハッピーなサウンドとは裏腹に、諦めや嫌世感を含んだ言葉を吐き捨てる。対照的に個人としての"石毛輝"による本作は、より柔和で主観的な内面が滲み出ている。トライバルなサウンドが広がる「Machu Pichu」に始まり、まさにタイトル通りの内省的な感情世界が展開されていく。キラキラとチープでアッパーなサウンドと、シンプルでアンニュイな作りの音がふわふわと重なり合い、明け透けに率直な歌詞が独特な厚みを生む。攻撃的で圧倒的な立ち振る舞いを見せるthe telephonesと、その影で守られてきたナイーブな少年の姿。the telrphonesで見せる闇と石毛輝の光。この二つは相反するようで、密接に結びついている。圧倒的なカリスマがふとした瞬間に見せる素顔。そこに人は惹かれるのだ。
-
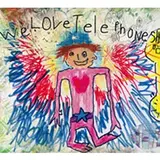
-
the telephones
We Love Telephones!!!
とにかく「現時点でのthe telephones の持ち球全部見せました!」な豪華盤。ここには彼らが過去作で掲げてきたデカイ言葉の全てが当てはまる。「LoveとDISCO」があるし、「DANCE FLOOR MONSTERS」にも成り得る。何よりも、ナカコーの手によって彼らのロマンティックが全開となった『A.B.C.D.e.p.』でみせた、the telephones的涙線刺激ポイントが冴えまくっている。ここでいう涙線が刺激されるとは、疼くことであり、徐々に高ぶっていくということ。もうここにあるのは「CLASHED MIRROR BALL」という破壊的狂喜乱舞ではない。パンクの破壊力と常にマックスのテンションで、フロアを盛り上げ倒すだけではないのだ(勿論、彼らにはそれは不可欠であるが)。彼らはようやくミラーボールを回しだした。叫ぶのでなくシンガロングを、モッシュでもダイブでなくダンスを、ということ。
-

-
the telephones
A.B.C.D.e.p.
快進撃を続けるthe telephonesから元SUPERCARそしてご存知iLLとしても活躍するナカコー初プロデュースによるニューEPが届いた。本来のthe telephonesが持つアグレッシヴさやポップな感性はそのままに、サウンドがグッと引き締まっており且つとてもロマンティックな仕上がりだ。また音の輪郭がはっきりとしておりダンス・ミュージックとし捉えても完成度が高い。ナカコー初プロデュースという事も驚きだったが、この組み合わせは面白いしとてもいい化学反応を生み出したことに違いない。2009年もツアー、リリースと駆け抜けた彼らだがまだまだ勢いは止まらない。来月にはセルフ・プロデュースによるEPもリリース。この次作EPは生楽器を多用したものになるとのこと。こちらも楽しみだ。
-

-
the telephones
Dance Floor Monsters
2008年、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、トップ・シーンまで駆け上がったTHE TELEPHONESがついにメジャー1stフルアルバムを発表。インディ時代の代表曲「Urban Disco」「HABANERO」を加えたこのアルバムは今年の日本のロック・シーンを代表する一枚になるだろう。ミラーボールとディスコをキーワードに、80'sシンセ・サウンドと切れのあるラウドなギターが暴れまわり、石毛輝のハイトーン・ヴォーカルは、シンプルだが、とても大切な言葉を僕たちに投げかける。凄まじい熱量が詰め込まれた、新たなポップ・スタンダード。Dance Floorを狂喜の笑顔で満たす「THE TELEPHONESの夏」がやってくる。
-

-
TELSTAR
We Love You!You Love Us!
キャッチーでゴキゲンなメロディに、さらに気分をときめかせるピコピコ・シンセをふりかけた「理解者」で幕を開けるTELSTER のニュー・アルバム。「フリフリ2010」ではTHE POLICEのようなレゲエ・テイストをとりいれ、「愛と政治のBGM」のような洒脱なロックンロールから「時代は変わらない」では穏やかな歌心をみせる。様々なスタイルを取り入れたひねくれたセンスを直球のポップ・ソングに変換するようなキラキラ感がTELSTARの持ち味だろう。エモーショナルな歌詞をスピードに乗って歌うポップ・ソングの裏側には、様々なロックの変遷がちりばめられている。そのアンバランス感が、他にはない独特のポップ・ソングを生み出している。間違いなく、自覚的にこのアンバランスさの狭間で闘っているのだろう。
-

-
Tempalay
((ika))
約3年ぶりのフル・アルバムは、テレビ東京ドラマ25"サ道2021"主題歌「あびばのんのん」、"真夜中ドラマ「地球の歩き方」"オープニング・テーマ「今世紀最大の夢」などのシングル曲に加え、Tempalayの得意とする浮遊感あるコーラス・ワークが絶妙な「預言者」、ヒップホップ風の緩いビートで揺れる「Aizou'」ほか全19曲が収録される。ジャンルレスなアレンジ、独創的リリックは今作でも神秘的な世界観を映し出すと共に、ひと筋縄ではいかないカオティックな表情を覗かせる。夢や宇宙が描かれる幻想的な詞には刹那的な救済を感じるが、そこには容易に理想郷へ辿り着けない現実も内包。明日が永遠に来ないループ感漂う夢見心地な本作だが、サイケデリックな残り香はあまりにも色濃く、リアルを生き抜くうえで強い信念を抱かせる。
-

-
Tempalay
Q / 憑依さん
椎名うみ原作のWOWOWオリジナル・ドラマ"青野くんに触りたいから死にたい"のOP、ED曲をTempalayが担当している意外性とともに、単にティーンエイジャーのホラーチックな恋愛なだけでなく、土着的な因習めいたエピソードも含まれるこの物語に、いわゆる青春ドラマ的な楽曲はハマらなかったのでは? とすら思える。メロウネスの中にあの世感を増幅させるシンセが漂う「Q」、ダブと日本の民話世界が出会ったようなモダンな"妖怪ソング"っぽい「憑依さん」。いずれもドラマの物語や主人公たちに重なりつつ、人を愛したときの感情、自分と他者の境界線の曖昧さを描き、思念が起こす不思議な事象を想像させる。浮遊感とグニグニしたグルーヴもその理由か。フィジカルを8cmシングル2枚組で出すユーモアも。
-
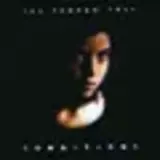
-
THE TEMPER TRAP
Condition
オーストラリアはメルボルン出身のTHE TEMPER TRAP。美しく壮大なメロディ・ラインとDougyの伸びのあるヴォーカル、そして強靭なビートに支えられた彼らの楽曲は、一度で耳に残る普遍性を備えている。シングル「Science Of Fear」や「Sweet Disposition」で聴けるように、スケールの大きさと楽曲の美しさを併せ持ち、U2やCOLDPLAYに引き合いに出される彼らだが、その特徴的なビートや緻密なアレンジには、普遍性だけに留まらない可能性を感じさせる。細分化が進む現在のシーンの中で、ど真ん中に芯を通すような存在として世界中から高い注目を集める彼ら。そこには受け手の過度の期待がある気もするが、それだけのポテンシャルを感じさせる壮大なデビュー・アルバムだ。
-
-
THE TEMPER TRAP
Science Of Fear
オーストラリアはメルボルンから登場した4人組、THE TEMPER TRAPの日本デビューとなる日本独自企画シングル。タイトル・トラック「Science Of Fear」は疾走感溢れるぶ厚いギターロック。このシングル収録の2曲だけでなく、シングル「Sweet Disposition」など、ドラマティックかつエモーショナルなサウンドが持ち味の彼ら。インドネシア出身のDougyの伸びやかで艶のある声とメロディといい、そのサウンド・プロダクションといい、U2のようなスケールの大きなバンドとなる可能性を持っている。それだけでなく、精力的に行ってきたというライヴで身に着けた強靭なグルーヴも魅力だ。SUMMER SONIC出演を間近に控え、秋にはデビュー・アルバムも発売される。要注目のニュー・カマーだ。
-

-
TEMPLES
Volcano
英国ミュージシャンから多数の賛辞を受け、2012年に華々しくデビューした4人組サイケ・ロック・バンドの2ndアルバムがついに到着。先行シングルであるTrack.1「Certainty」から幕を開ける今作は、彼らの根源でもある70~80年代を代表する英国サイケデリック・ロックの音像により接近したサウンドに。抑揚のあるメロディとドリーミーなヴォーカル・ワークは色彩感を増し、前作以上にシーケンスを多用した今作がセルフ・プロデュースというのも納得。TAME IMPALAと比較された過去も笑い飛ばすように、昨今の行儀の良いバンドたちを冷ややかに突き放すTrack.12「Strange Or Be Forgotten」など、ロック・バンドとして大きな責任感を背負う覚悟を決めた快作であることは間違いない。
-

-
TEMPLES
Sun Structures
ここ最近、活況を呈するUKギター・ミュージック・シーンの面白いところは、出てくるバンドそれぞれがまったく異なった音楽的アプローチをしている点にある。このTEMPLESはその最たる例で、なんでこんな60~70年代のサイケデリック・ロック直系の音楽性で、しかもMarc Bolanみたいな髪型した奴のいるバンドが突然現れるのか、一昔前なら意味不明だろう。しかし、今はこれが"あり"で、最先端で、実際、このアルバムは最高だ。どっしりと力強いビート。摩訶不思議で物憂げ、だけどポップなメロディとハーモニー。エレキ・ギターのダイレクトな質感と幽玄なフォーク・テイストの混ざり具合も絶妙な、スケールのデカいサイケ・ロック。これを懐古趣味と言う人がいれば、考えを改めたほうがいい。だってこれ、凄く"今"だから。
-
-
TEMPLES
Shelter Song e.p.
シングル「Shelter Song」でNMEの2013年の注目バンドに選出されたり、Noel GallagherやJohnny Marrが賞賛し、プログレやサイケの濃ゆい遺伝子を現代に開花させたMYSTERY JETSの前座に抜擢されと、こだわりのロック愛好家たちに愛されるUKのニューカマー、TEMPLESが、ここ日本でもデビュー!60年代バンドのマジカルなハーモニーが生む甘い白昼夢や、実験精神に満ちた音作りやレコーディングによる幽玄なサウンドの奥行きに、チルアウトしながらもエネルギッシュな体温があるヴォーカルなど、いにしえのバンドがタイム・トリップしてきたようなムードを湛えたサウンドにまずノック・ダウン。どんなバックボーンがあって、ここまで芳醇な音楽を生成できるのか。天性の勘や独自の審美眼があるのはまちがいない。
-

-
TENACIOUS D
Rize Of The Fenix
このアルバムの邦題は『鳳凰♂昇天』という。そして「ねらえ!お手頃ネエチャン」だとか「俺のナオンはアラフォー」だとかいう、何だか意味の分からん邦題の曲が並んでいる。アルバムのメイン・テーマは下半身だそうだ……。完全にふざけてやがる……。そう言いたくなるのだが、ちょっと違う。これは遊びではない。俳優として活躍しているJack BlackとKyle Gassの二人からなるTENACIOUS Dは真剣に、クソまじめにふざけている。彼らはここで70~80年代に輝いていたハード・ロックを細工せずに再現してみせる。70年代と80年代が俺の青春だと言わんばかりの勢いで、自分たちが憧れたロック・スターになりきっている。彼らのなりきりっぷりと、ふざけっぷりは中途半端ではない。
-

-
TENDOUJI
TENDOUJI
中学の同級生4人がほぼ素人ながら20代後半に意気揚々と結成したバンド、TENDOUJIが勢いそのままに今年10周年を迎えた。プロデューサーも入れず4人だけで作り上げたという最新作は、節目を飾る気合の入ったセルフタイトル・アルバムでありながら、肩肘張らず純粋に音楽を楽しむ大人たちのラフなムードが漂う。結成当初から変わらない"仲間と楽しいことをしていたい"というマインドが生み出す、純度の高いTENDOUJIサウンドが存分に詰め込まれた。そんななか「Just Because」では"ベッドルーム・オルタナ・テイスト"という新たな一面も。ネクスト・フェーズへの期待も高まる。ぜひライヴハウスに"遊びに"行って、喜怒哀楽を昇華する陽気で自由な"EASY PUNK"に身をゆだね、この名盤とともに踊りたい。
-

-
TENDOUJI
FABBY CLUB
モリタナオヒコ(Gt/Vo)が、映画"フットルース"に触発されて書いたという「Killing Heads」は、まさにアメリカのビッグなエンターテイメントにあるスケール感と、彼らのインディー・ロック魂が見事に融合。そしてモリタと双璧を成すフロントマン、アサノケンジ(Gt/Vo)作曲の「Something」は、伝統的なパワー・ポップの香り漂う、持ち前の甘いメロディ・センスがこれまで以上に輝く。この2曲に、初めて外部からプロデューサーとして片寄明人(GREAT3/Vo/Gt)を立てたことが、バンドを見事にネクスト・レベルに押し上げた。TENDOUJIのようなローファイ・サウンドの良し悪しは、"間"や"ニュアンス"で決まる。その空気みたいなものの中に含まれるポテンシャルを引き出す腕はさすがだ。
-

-
TENDRE
IMAGINE
通算3作目のアルバムにしてメジャー1stアルバムとなる本作はタイトルが示唆する通り、他者や時に見失いがちな自分の心も含めた想像力が、音にも言葉にも灯のように点在している。これまで以上にニュートラルな発声が、最早誰の価値観なのか分断が正当化されそうな潮流に静かにNOと言う。その背景にはこれまでより歌に向き合った事実や、トレンドではなく、人間の今を見つめたがゆえの、アップデートされた普遍的なサウンド・プロダクションが存在する。踊りやすいグルーヴより、意志を伝えるための重心の低い、ボトムの太いリズムや、特定のジャンルに収斂されないストリングスやホーンのアレンジにそれは明らかだ。心を調律してもくれるし、他者と共存する嬉しい気持ちを彩り温かくもしてくれる。まさに時代の灯。
-
-
Tequeolo Caliqueolo
Welcome
2015年9月にリリースした初の全国流通盤以来、約1年半ぶりにリリースするミニ・アルバム。Track.1「Sudden Death Game」、Track.2「Gossip Boys」と言葉数が多くスピード感のある曲が初っ端から続き、コミュニケーション欲求の高さを相変わらず感じるが、前作よりも"まずは自分のことから伝えよう"と自分の内側に踏み込み、同時に聴き手側に歩み寄るような姿勢が強くなったように思える。特に、バンド自身が抱える七転八起の精神を託したTrack.6「KUNG-FU!」にはグッときた。言葉は深く刺さるように、しかしサウンドはあくまで楽しく踊れるように。鮮やかな陰と陽のコントラストにはこの1年半での成長がよく表れている。
-

-
Tequeolo Caliqueolo
S.O.S
様々なイベントや夜の本気ダンスとの共同企画などで話題を集める京都の5人組がいよいよ初の全国流通盤をリリース。夜ダン同様にUKロック/ダンス・ロックをバックグラウンドに持ち、各楽器のリフなどの音作りからもその影響が窺える。彼らの個性は、そこに必ずJ-ROCKの要素を加えているところ。例えばTrack.1はその最たる例で、3分ちょっとでしっかりとA・B・サビ×2の間奏とラスサビにまとめるドラマティックな展開とメロディはこれぞと言わんばかりに日本的なのに、フレーズにUKの匂いがするというハイブリッド感。ラップの語感や譜割りの良さはルーツの賜物だろう。このバランス感覚は新鮮だ。the telephones、WHITE ASHに続く核弾頭かもしれない。今後の動向に注目である。
-

-
texas pandaa
Down In the Hole
男女混合4人組、texas pandaa。人を食ったようなバンド名といい、「そこそこ音楽を好み、ほど良く運に見放されたシャイでブルーな老若男女におすすめ。」なんて、本気か皮肉か分からないことをサイトに載せるところといい、不思議なバンドだ。女性ツイン・ヴォーカルによるポップな楽曲は、無駄のない空間的なバンド・アンサンブルとあいまって、柔らかさと浮遊感を持っている。エレクトロニカ、フォークトロニカを通過したSSWの作品にも通じそうな音楽性と、耳に馴染むメロディ・ラインが印象的。USインディからスウェディッシュ・ポップまで、幅広く音楽を消化しながら、日本人の琴線にも触れそうなポップ・ソング。可愛い顔をして裏では何か企んでいそうな小悪魔的な感じが、気になる存在だ。
-

-
the equal lights
LaLaLa-prima
10代のころから多くの新人オーディションで上位に食い込んできた実力を持つ大阪発の4人組バンド、the equal lightsの全国デビューとなるミニ・アルバム。再生ボタンを押した瞬間にリスナーを光の向こうへと導くような深遠で美しいサウンドスケープ、そのど真ん中にはミシマテツオ(Vo/Gt)のエモーショナルで澄んだ歌声がある。全7曲を収録したアルバムの中で何かひとつ貫かれているものがあるとしたら、それは君と一緒に生きる未来のための音楽が鳴らしたい、という意志だ。"笑っていたい泣いていたい 感じることをやめないでずっと"と、心を震わせながら生きる日々を肯定する「ファンファーレ」の優しい叫びには、今歌わずにはいられない、そんなミシマの熱い衝動が込められていた。
-
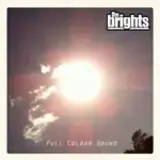
-
THE BRIGHTS
Full Colour Sound
日本でも熱く支持されている、UKインディー・ロック・バンドの2ndフル・アルバム。きらびやかで少し切ない旋律を奏でるギター・リフと甘く蒼いヴォーカルで聴く者の心を一気に掴んでしまう楽曲が今作には詰まっている。冒頭曲「Don’t Look Back」のポップなコーラスや弾けるサビを聴けば彼らの世界感へ引き込まれること間違いないだろうし、続く「Against The Tide」では真骨頂ともいえる独特な浮遊感の心地よさと力強いバンド・サウンドも楽しめる。古き良き時代のロック精神を今の時代に継承しつつ、決して懐古的なサウンド作りになり過ぎていないのも秀逸。何度でもリピートしたくなる聴きやすさと、その度に新しい魅力に気づかせてくれる珠玉のナンバーが揃った良作だ。
-

-
THE CORONAS
True Love Waits
2003年結成、母国アイルランドでは15,000人規模の動員を誇るロック・トリオの6thアルバム。バンド名と同じウイルスが猛威を振るう困難な状況にも負けず、"いま世界一不幸なバンド名だ"、"THE VACCINESと名前を交換したいよ"と明るくジョークを飛ばしていた彼らだが、今作にも前向きで希望に溢れたサウンドが詰まっている。ピアノやブラスも取り入れた生楽器と、染み渡るような優しい響きのヴォーカルが溶け合ったアンサンブルはぬくもりのある質感で、さりげなく挿入されるエレクトロニクスも絶妙に心地いい。これらを壮大な構築美でまとめあげた楽曲群は幻想的な世界を描いていて、特にラスト・トラックは圧巻。こんなご時世、そしてこの名前だからこそ聴いておきたい、心洗われる作品だ。
-

-
THE DARKNESS
Hot Cakes
7年ぶりのリリースとなる3rdフル・アルバム。一時の解散状態にまで陥った危機を乗り切りオリジナル・メンバーで再集結したバンドは、よりゴージャスでキャッチーなロック・アンセムを引き連れて世界の最前線へと帰ってきてくれた。それを象徴するような「Nothing's Gonna Stop Us」の痛快で疾走感溢れるサウンドは苦い過去なんて吹き飛ばし再び頂点へと迫る勢いに満ち溢れている。そして日本盤ボーナス・トラックとしてRADIOHEADの「Street Spirit (Fade Out)」のカヴァーが収録されているのも非常に興味深い。彼らのロック・アイコンとして支持されている魅力を存分に味わえる快心作。ぜひ頭を空っぽにして爆音で楽しんでもらいたい。
-

-
The Grateful a MogAAAz
BLUE WIND
地球防衛軍の6人組マスクド・アイドル"The Grateful a MogAAAz"のミニ・アルバム。表題曲は、グループのキャッチコピーにもなっている"昔見てた夢、今も忘れちゃいないぜ"という言葉を高らかに歌う、どこか懐かしいロック・ナンバーだ。哀愁が漂う、ディストピアな世界観は聴けば聴くほど癖になる。本作にはバリエーション豊かなカバー曲が収められ、SAMURAIの「インテリジェンスミキサー」カバー、BO GUMBOSの「ナイトトリッパー・イエー!!」カバー、チバユウスケ(The Birthday/ex-THEE MICHELLE GUN ELEPHANT)がPUFFYに提供した「君とオートバイ」のカバーも収録。音楽的にもテーマ的にも幅をグッと広げている。
-
-
THE HEAD AND THE HEART
Living Mirage
2016年リリースのメジャー・デビュー・アルバム『Signs Of Light』がUSビルボード・チャートでトップ5に入るという大ヒットを飛ばした、シアトルのフォーク・ロック・バンド、THE HEAD AND THE HEARTによる最新作。シンプルなピアノとギターで綴るメロディの美しさとキャッチーなコーラスが際立つ、フォーク・ロックらしい楽曲ももちろん素晴らしいが、重低音が響くグルーヴ感たっぷりの楽曲やシンセで装飾された楽曲には、ポップスとしても楽しめる大衆性がある。THE FRAYやTHE SCRIPTなどの美メロ系オルタナティヴ・ロック・バンドが好きな方、男女ツイン・ヴォーカル、ソフト・ロック好きな方など、幅広いリスナーに聴いてもらいたい。
-

-
THE LINDA LINDAS
No Obligation
"令和のRIOT GRRRL"THE LINDA LINDASが2ndアルバム『No Obligation』をリリースする。映画"モキシー ~私たちのムーブメント~"(2021年)でBIKINI KILLのカバーを演奏する彼女たちを見て、"小さな女子たちがこんなにしっかりとした演奏を!?"と驚いた方も多いだろう。それがあれよあれよという間に名門パンク・レーベル Epitaph Recordsと契約、"SUMMER SONIC"で来日と、着実にキャリアを築き、今作リリース時点では最年長のBelaがついに20歳に。1stの頃と比べると、確実に大人に近づいた印象だ。初期パンク/ガレージ好きには堪らない古き良きサウンドを勢いだけでない、しなやかなカッコ良さで表現する姿勢は、まさにファンの期待を裏切らない成長っぷり。
-

-
THE LITTLE BLACK
THE LITTLE BLACK
生身の3人がそこでプレイしている様子が手に取るようにわかるスリリングなサウンドをパッケージ。バンドの意思表示と宣戦布告を表現するようなリフが最高な「ドロミズ」や、前バンド解散の直後、すでに書かれていた「波紋」には、のび太(Vo/Gt)という人物の芯の太さ(柳に風みたいなしなやかさも強みだが)が自然と表出している。さらにヒップホップ~新世代ジャズ的なマットのドラム・センスが堪能できる「受け入れろ!」は、全体的な音数の少なさも相まって、この3ピースの感性の鋭さが最もわかる。さらにのび太のヴォーカリストとしての力や、メロディの良さが再認識できる「夕焼けはなぜ」、彩のベーシストとしての新たなアプローチが聴ける「渦へ」の全5曲。フレッシュなシーンの前線で戦える痛快な初作だ。
-
-
THENEWNO2
The Fear of Missing Out
George Harrisonの息子であるDhani Harrisonがフロントマンをつとめるオルタナティヴ・ロック・バンドの2ndアルバム。1stアルバム『You Are Here』をリリース後に出演した“Coachella Valley Music and Arts Festival”では“最も素晴らしいデビュー・パフォーマンス”と評される。生音とエレクトロ・サウンドを絶妙にブレンドさせた、非常に振り幅の広い作品に仕上がっている。1stシングルの「Make It Home」で垣間見せるサイケデリアは、Gergeの息子だからというわけではないが、THE BEATLESを髣髴とさせるような物憂げなミドル・チューン。偉大な父の名前を借りずとも、今後更なる飛躍を期待できる作品だ。
-

-
THESE NEW PURITANS
Field Of Reeds
前2作がミュージック・シーンに衝撃を与えたロンドンの新世代ポスト・パンク4人組、THESE NEW PURITANS、3年ぶりとなる新作だ。暗黒という言葉がふさわしいその世界は変わらないものの、彼らのサウンドを特徴づけていた執拗なまでのビートは影を潜め、今回、アンサンブルの主役となるのはピアノとホーン。そのせいか、これまでその影響が指摘されてきたクラシックよりもジャズに近い印象もあるが、同時にゴス色も一気に増した。うめくようなヴォーカルに混じる子供の声。オルガンの執拗なリフレイン。魂を抜かれたような女性ヴォーカル。教会音楽を連想させる荘厳なコーラス……。怖い。これは怖すぎる!!犯罪映画やサスペンス映画よりもむしろオカルト映画のサントラにぴったりだ。
-
-
THESE NEW PURITANS
Hidden
2008年、『Beat Pyramid』で衝撃のデビューを飾ったTHESE NEW PURITANSのニュー・アルバム。あのつんのめった性急なビート感は、このコンセプチュアルな新作にはない。様々なスタイルを呑み込んだビート・ミュージックを基盤としているという出発地点は変わらないが、このアルバムでは『Beat Pyramid』とは全く異なるベクトルを描いている。徹底的に研ぎ澄まされたサウンド・プロダクションは、前作のある種の乱雑さ故に生まれたあの高揚感を生み出すのではなく、脳内に浸透するように響いてくる。驚くほど高性能な脳内トリップの為のビート・ミュージック。正直、いきなりこんなところへ辿り着くとは思ってもみなかったが、彼らの才能の奥深さを見せ付けられる快心作。
-
-
THINK ABOUT LIFE
Family
カナダはモントリオールのTHINK ABOUT LIFE のセカンド・アルバム。ファーストの音楽性とは異なり、本作は腰と胸を同時に打ち抜くディスコ・ポップなのだが、これが凄いことになっている。PRINCE とTV ON THE RADIO とBASEMENT JAXXが融合したような・・・と似たような喩えも既に多く見られるが、特徴的なのは本作の説明には最低3つのアーティストが必要なこと。いや、3 つじゃ足りない位に多角的で挑戦的。完成度の高いアレンジと多彩なビートで、普通は繋がらないようなところもヒップに繋げてしまう。エンターテイメント性もグルーヴも満点。世界中のダンスフロアが彼等に夢中になってもおかしくない。個人的に、2009 年のベスト5に余裕で入りますね。大推薦。
-

-
THIRD COAST KINGS
Third Coast Kings
70年代アメリカの埃っぽく、煙草くさい匂い――、本来の意味でのファンキーな質感を現代に再現したような作品である。2000年代以降、音楽シーンの様々な界隈で"リヴァイヴァル"というムーブメントが起こり、その潮流は現代まで続いているように思う。しかし、そうした作品はときにある種の後ろ向きなどん臭さを持ってしまうものだが、THIRD COAST KINGSのこのデビューアルバムは70年代のファンク・サウンドを現代に瑞々しいまま響かせることに成功している。メンバー全員のファンクのノリをしっかりおさえた演奏のテクニックと、彼らの誠実な過去の音楽への理解が、場所、時代を問わない軽快なファンク・ビートを奏で、まさに時間、場所を問わずタイムレスに楽しめる作品になっている。
-
-
THIRTY SECONDS TO MARS
America
近年、バンドの顔のJared Leto(Vo/Gt)が映画"ブレードランナー2049"など、俳優として知名度をさらに上げているなか、バンドとして約5年ぶりのニュー・アルバム。「Walk On Water」のOPから、力強く打ち鳴らされるリズムと民衆の声の如きコーラスが聴き手を鼓舞する。現行のUSシーンの常道となっている他ジャンルのクリエイターとのコラボも、R&Bとロックの融合ではなく、EDM人気の中心人物 ZEDDと共作したエレクトロニックでセンシュアルな「Dangerous Night Produced By ZEDD」、ラッパーのA$AP ROCKYをフィーチャーした「One Track Mind Feat. A$AP ROCKY」、新世代SSWのHALSEYを迎えた「Love Is Madness Feat. HALSEY」など、今のアメリカを実直に表現していて芯がある。
-

-
THIS IS JAPAN
トワイライト・ファズ
かすかな光やたそがれを意味する"トワイライト"と、最も原始的なギター・エフェクトとも言われる"ファズ"。その名の通り、衝動的な轟音の中で、切なさと共に胸が熱くなる美しいナンバーが届いた。ディスジャパ曲の中でもひと際ポップなメロディに、あえてこれまで以上に骨太な演奏を掛け合わせ、杉森ジャック(Vo/Gt)の無鉄砲なキャラクター剥き出しの詞を乗せた1曲は、アニメ"BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS"EDとしても支持を集めている。c/wには、セントチヒロ・チッチ(BiSH)のピュアでヒロイックな歌声と、杉森の荒々しいしゃがれ声の対照的なツインVoで化学反応を起こす「KARAGARA」も収録。新たな試みを経てひと回り大きくなったバンドを感じられる。


























