DISC REVIEW
T
-

-
THIS IS JAPAN
new world
ディスジャパのメジャー進出後初となるCDシングルは、アニメ"ノー・ガンズ・ライフ"第2期EDテーマ「new world」だ。アニメのハードボイルドな世界観を意識しつつ、バンドの意志も乗せ、全員で構築していったというこの曲。ガツンと士気が上がるパワフルなナンバーだが、存在感のある水元太郎のベースで幕開けし、かわむらのグルーヴィなドラミング、ツイン・ヴォーカルを存分に生かした杉森ジャックと小山祐樹の掛け合いや、ラップ・パートなど、聴けば聴くほど楽しめる仕上がりに。c/wの「RRRIOT」は曲調的には対照的とも言えるじわりと温かく響く曲だが、共通して、聴いたあとに"やるしかないな"と今を受け入れたうえで前を向ける感覚があり、それこそがディスジャパらしさだと再認識できる。
-

-
THIS IS JAPAN
WEEKENDER
前作『FROM ALTERNATIVE』でタイトルに掲げた"オルタナティヴ"なロックの系譜に連なるスタイルではあるが、今作『WEEKENDER』は、そのクリエイティヴィティが大きく飛躍した作品となっている。ギターを主体にラウドに走るロックンロール然としたワイルドな魅力だけでなく、そのギターを置いてリズムにフォーカスし、ベースやドラムの音色にも遊び心を加えたり、ダンス・ミュージックのミニマルな要素を採り入れたりと、メリハリやダイナミクスに特化したアレンジにシフトすることで、フロントマン 杉森ジャックの放つ歌と言葉もさらに躍動。これを聴いてライヴに行けば、あなたの"WEEKENDER"ライフはより豊かになること間違いなし。
-

-
This is LAST
HOME
約3年ぶりのアルバムとなった今作は、原点のバンド・サウンドに立ち返った前作『別に、どうでもいい、知らない』から一転、格段に華やかなブラス・アレンジの「カスミソウ」でスタート。リアルな恋愛模様を歌ってきたThis is LASTの真骨頂を見せたTVドラマや恋愛リアリティ・ショーのタイアップ曲をはじめ、レゲエ調のリズムが心地よい「Any」から爽やかな王道ポップ・ロック「ラブソングにも時代がある」、ストリングスを効かせたバラード「言葉にして」など、完成度の高い多彩な楽曲群がこの3年間の充実度を物語っている。リテイク曲も多数収録され、全16曲とボリューム満点。菊池竜静(Ba)の脱退を経ながらも、勢い衰えることなく進んでいく彼らの今を刻むと同時に、さらなる飛躍を期待させる1枚。
-

-
This is LAST
いつか君が大人になった時に
1stシングル『ポニーテールに揺らされて』に引き続き、表題曲に珠玉のバラード・ナンバーを置いたThis is LASTの2022年の第1弾シングル。ピアノとストリングスの旋律を取り入れたドラマチックな表題曲「いつか君が大人になった時に」は、"君"との幸せな未来を想像するようなハートウォーミングなナンバーだ。カップリングには浮気する彼女のワガママな主張を綴った軽快なポップ・ソング「勘弁してくれ」と、恋愛のドス黒い一面を官能的に描いたマイナー調のロック・ナンバー「黒く踊る」を収録。それぞれ単曲でも成立するが、3曲を通して聴くことで報われない恋を歌い続けるソングライター、菊池陽報(Vo/Gt)の悲しい性(さが)がくっきりと浮かび上がる。精緻なアレンジにバンドの進化を感じさせる1枚。
-

-
This is LAST
ポニーテールに揺らされて
昨年11月にリリースした1stフル・アルバム『別に、どうでもいい、知らない』をひとつの区切りとしたThis is LASTが、バンドの新章を告げる1stシングル。あえてアルバムでは封印していたシンセ・サウンドを効果的に取り入れた、懐かしくも切ない表題曲「ポニーテールに揺らされて」をはじめ、よりポップ・ミュージックとしての精度が高まった3曲を収録。カップリングには、LASTの永遠のテーマ"浮気"を自虐気味に描いた「君が言うには」、恋人との思い出の食べ物をモチーフにした「オムライス」と、これまでどおり恋愛のワンシーンを描いた楽曲が並ぶが、悲壮感よりも、可笑しみが強いのが今作の魅力。結成から3年、菊池陽報(Vo/Gt)が作るメロディ・センスもますます研ぎ澄まされている。
-

-
This is LAST
別に、どうでもいい、知らない
菊池陽報(Vo/Gt)による実体験をもとにした赤裸々な失恋ソングが、若い世代の支持を集めるThis is LAST。結成から2年で完成させた初となるフル・アルバムは、ストリングスやピアノを多彩に織り交ぜた前作までとは一転して、3ピース編成の音に徹底的にこだわった。ダンサブルなグルーヴとは裏腹に、憂いを帯びたメロディが切ないリード曲「ひどい癖」をはじめ、ループする負の思考を疾走感溢れるビートが加速させる「囘想列車」など、ギター、ベース、ドラムというシンプルな構成に盛り込んだ鋭いフックの数々が、聴き手の耳を素通りさせない。10曲中9曲がラヴ・ソング。唯一ネガティヴな自分の情けなさを曝け出した、ラスト・ソング「病んでるくらいがちょうどいいね」が人間臭くて痛快。
-

-
This is LAST
koroshimonku
前作から約4ヶ月で早くも発売される2ndミニ・アルバム。身を切り裂くような悲しみとやり切れなさを、性急なビートが強烈なまでに高めていく「プルメリア」や、クラップやシンガロング系のコーラス、さらにはリフレインする歌詞とキャッチーな要素が盛りだくさんながら、歌詞は怒りに震えまくっている、ギャップの凄まじい「恋愛凡人は踊らない」など、ライヴでも強力な威力を発揮しそうな全5曲を収録した。また、かねてよりSNSなどで注目を集め、彼らの名前が世に広まるきっかけとなった「殺文句」が待望の音源化! "あなたが1番よ"という言葉に湧き上がる猜疑心と、それでも捨てきれない愛情が入り混じった胸の内を、繊細且つ激情的なバンド・アンサンブルで描いた同曲は、また多くの人の心を揺さぶるだろう。
-

-
This is LAST
aizou
何度も浮気をされた実体験をもとに書いた「殺文句」や「愛憎」が、SNSを中心に注目を集める千葉県柏発の3ピース・バンド、初の全国流通盤。"誰かの代わりなんて知ってるから"と拭いきれない未練が滲む「愛憎」や、"両思いのはずなのに/片思いをしてるみたいね"と悲しい恋愛を描いた「バランス」など、痛ましい恋愛経験と向き合うことで生み出されるキラー・フレーズの数々が胸に刺さる。赤裸々なまでに等身大な失恋を綴るギター・ロック・バンド。というのが、現在のインディーズ・シーンのトレンドではあるが、その枠だけに収まらないのがこのバンドの面白いところ。青春時代に想いを馳せ、前向きに日々を乗り越えるサラリーマンの歌「帰り道、放課後と残業」など、新機軸となる楽曲に無限の可能性を感じる。
-

-
THIS IS PANIC
ちゅどーん
11月には赤坂BLITZでの初ワンマンを控えた、今最も勢いに乗る最新型エレクトロ・ヒップホップ・バンドTHIS IS PANICの待望の最新アルバム。SUMMER SONICやCOUNTDOWN JAPANにも出演しライヴでのインパクトも絶大の彼ら。最新のダンス・ビートにお笑いスレスレのリリックを繰り出し、時にはグッとくるフレーズを挟み込み聴く者を夢中にさせる魅力を持っている。新作でも変わらず独特な語感と口ずさみたくなるフレーズが溢れ期待を裏切らない。パーティー前に聴くには持ってこいの1枚だろう。日本語ヒップホップともJ-POPともつかない彼らのポジションはとても魅力的だし、このまま突っ走ってほしい。衝撃と笑いが詰まったライヴも必見だ。
-

-
THIS IS PANIC
ちゅどーん
11月には赤坂BLITZでの初ワンマンを控えた、今最も勢いに乗る最新型エレクトロ・ヒップホップ・バンドTHIS IS PANICの待望の最新アルバム。SUMMER SONICやCOUNTDOWN JAPANにも出演しライヴでのインパクトも絶大の彼ら。最新のダンス・ビートにお笑いスレスレのリリックを繰り出し、時にはグッとくるフレーズを挟み込み聴く者を夢中にさせる魅力を持っている。新作でも変わらず独特な語感と口ずさみたくなるフレーズが溢れ期待を裏切らない。パーティー前に聴くには持ってこいの1枚だろう。日本語ヒップホップともJ-POPともつかない彼らのポジションはとても魅力的だし、このまま突っ走ってほしい。衝撃と笑いが詰まったライヴも必見だ。
-
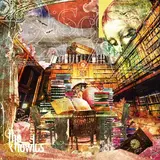
-
the knowlus
Discovery Age
ガレージ、ポスト・ロック、時にプログレなどを3ピースのストイックなアンサンブルで構築するスタイルにしか成し得ない引き締まった音像。混沌や危機感が迫る時代と個人の普遍的な内面を行き来する世界観。それらが高い地点で融合したthe knowlus、約7年ぶりのアルバム。ここから歩みを進めていく宣誓にも似たギター・フレーズから始まる1曲目の「僕らが深淵を見つめる時」、豪雨を思わせるざらついたギターと性急な8ビートがこのバンドのガレージの解釈を窺わせる「アルキメデスの螺旋」、今作の方向性を決定した「クロノス」のアルバム・バージョン、ピアノを取り入れることでドラマ性が押し上げられた「方舟の揺れかた」など、どれもこのバンドの誠実さを感じずにいられない完成度だ。
-

-
the knowlus
theory of everything
2015年に初のフル・アルバム『不確定の原理』をリリースした3ピース・バンド、the knowlusが約2年ぶりにリリースするミニ・アルバム。タイトルの意味は"万物の理論"。これまでバンドが築いてきたものと、これからバンドが鳴らしていきたい音を統合するアルバムという意味合いがある。高い演奏力を持つ3人が鳴らすプログレッシヴ且つエッジの効いた美しい音像に乗せて描かれるのは、現実と非現実を行き来するような不思議な世界。藤子・F・不二雄や宮沢賢治、ミヒャエル・エンデなどのSFファンタジーに影響を受けたという川野奏太(Vo/Gt)が綴る、一見難解にも見える抽象的な歌詞には、ここから自分たちの手で新たな未来を切り拓いていこうとするバンドの意志が刻まれている。
-

-
threedays film
woodland
八王子を中心に活動しているthreedays filmは4人組のインディ・ギター・ロック・バンドである。いろんな音楽を聴いていると、このバンド生で聴いたらどんな感じなんだろう?と思うことがあるけど、まさにライヴハウスで生の音を聴いてみたくなるそんなバンドだ。切ないけれど透明感溢れるサウンドに程良いギターの響きと、儚げで繊細なヴォーカルの歌声には、まるで深い海にそっと潜ってゆっくりと水面を目指し、浮き上がってくるような浮遊感にとらわれた。オルタナティヴとポストロックなどを融合し自分達のメロディとして確立できている類い稀なクオリティの高さに、八王子を飛び越えていろんな場面で活躍できる日もそう遠くないと確信した。
-

-
THREE LIGHTS DOWN KINGS
FiVE XTENDER
傾斜のきつい坂道で、巡航時と同等の速度をキープするには当然それなりのパワーが必要となってくる。サンエルの新体制音源第2弾にして1st EPとなる今作は、まさに彼らが次の高みへと向け走り出したことが感じられる、パワーの漲る1枚だと言えよう。『FiVE XTENDER』の名のとおり、収録されている5曲は方向性こそ個々に違うものの、いずれもが訴求力の強いサウンドメイクで仕上げられている点が実に興味深い。また、歌詞の面で随所に飽くなき上昇志向を持つが故の焦燥感を感じさせる表現が散見されるのも、今現在のサンエルを如実に投影したところだと解釈できそうだ。なだらかな道を行くのではなく、あえて急な登り道を疾走しようとしている彼らの確かな馬力が、この音からは感じられるはずだ。
-

-
THREE LIGHTS DOWN KINGS
始まりは終わりじゃないと確かめる為だけに僕らは・・・
新ヴォーカル、Hiromuが加入した新体制となって初のアルバムには、長い日本語のタイトルがつけられた。少しばかりエモーショナルなタイトルだが、アルバムの内容は新たなサウンドへの挑戦、今バンドとして打ち出したいモードをまっすぐに形にしている。カラフルなエレクトロの音響は控えめで、バンドでの馬力や躍動感を立体的にレコーディング。高揚感のあるシンガロングやコーラスも多く、大きなスケール感を持った、"響きわたる"というイメージを具体化した。新しいこと=最新鋭のもの、ジャンルでなく、スタンダードなロック・ミュージックとしてのデカさ、破壊力を、彼ら4人で派手に打ち鳴らしているアルバムだ。もともとのフレンドリーなメロディはそのままに、さらに前のめりで突き進んでいく今の音だ。
-

-
THREE LIGHTS DOWN KINGS
ROCK TO THE FUTURE
シングル『NEVER SAY NEVER』から、前作のアルバム『ENERGIZER』へという流れでは、キャッチーなメロディとバンド・サウンド meets EDMの破壊力のある音塊で、ハイボルテージなまま駆け抜けていったパワーがあったけれど、今回のアルバム『ROCK TO THE FUTURE』は、エモーショナル且つバンドの人力感を活かしたボリュームのある作品になっている。ツアーを経た実感、ライヴでのダイレクトなやりとりや昂揚感を、言葉とサウンドにした。もちろんエレクトロ要素はこのバンドの武器で、今回はより効果的で、エッジーに曲のパワーを引き立てている。音を選り抜いて、全体のサウンドをソリッドにした分、よりリズミカルで獰猛な音にもなった。その勢いのある音が、歌とメッセージを強力に後押ししている。
-
-
THREE LIGHTS DOWN KINGS
グロリアスデイズ
ラウドなバンド・サウンドにキャッチーで昂揚感のあるシンセを注入し、爆発的な勢いのあるサウンドを生み出している、名古屋発のTHREE LIGHTS DOWN KINGS。これまでのアルバムでは、ヴォーカルにオートチューンをかけたつるりとした流線型の歌が、射抜くような鋭さで乗っていたが、今回の「グロリアスデイズ」では声 を加工せずに、より生の躍動感とバンド・サウンドとの一体感が協調されている。フックのあるダンス・ミュージック的なノリも活かしたメロディックな曲で、華やかでエモーショナルな歌やフレーズが肝。地元名古屋では04 Limited Sazabysとも仲が良く、活動を共にしてきたというサンエル。ジャンルは違えども互いにしのぎを削ってきた名古屋のロック・シーンゆえに、磨かれた個性もあるだろう。その自分の音をフル・ボリュームで響かせるシングルだ。
-
-
THREEOUT
TALETELLER
期待のニュー・フェイスによる1stフル・アルバム。紅一点の女性ドラマー なおを含む4人組というバンド編成もちょっと珍しいが、音楽的にもかなり異色と言っていい。日本語詞をメインに爽やかなギター・ロックを響かせたかと思えば、いきなりブレイクダウンや舌鋒鋭いラップをアクセント的に取り入れ、ハッと驚く要素が曲調に仕掛けられている。エモーショナルなメロディ・ラインだけでも十分に魅力的なのだが、メタルコア/ハードコアの重厚なテイストを躊躇なくねじ込むセンスに、新世代の到来を感じずにはいられない。後半には美メロ振り撒くミドル・テンポの曲調を収録し、これがまた完成度高し。結成から約4年という歳月が作風にも大きな影響を与えているのだろう。このバンドの音楽的変遷を凝縮した1枚だ。
-

-
THRICE
Palms
1998年に結成し、2000年代前半のエモ/ポスト・ハードコア・シーンを牽引したカリフォルニア出身の4人組、THRICE。2012年に一度解散するも2015年に復活したバンドが、約2年ぶり10枚目のアルバム『Palms』を名門"Epitaph Records"よりリリースした。メタルの影響を色濃く残した初期のハードコア・サウンドから壮大なオルタナ・サウンドへと音楽性を変化させてきた彼らだが、今作ではさらにアダルトな雰囲気に。うねるギター・リフにTHRICEらしいパワフルでキャッチーなメロディのヴォーカルを乗せた「The Grey」、女性ヴォーカルとハーモニーを奏でる「Just Breathe」、ピアノをフィーチャーしたエモーショナルな「Everything Belongs」と、独創性を存分に発揮した多彩な楽曲が並ぶ、20周年を迎えたバンドの成熟を感じさせる1枚だ。
-

-
THROW ME THE STATUE
Creaturesque
本作がセカンド・アルバムとなるUSインディ・バンドTHROW ME STATUE。メランコリックなメロディと歌声、リズミカルなビートにローファイなアレンジを施した、最新型のネオアコ・バンドとでも言おうか。その抜群の歌心はどこかBELLE AND SEBASTIAN を思わせるのだが、彼等のように完璧主義的ではなく、いい意味でもっとラフで肩の力の抜けたリラックス感がいいVIBEを放っている。USローファイ・ポップらしい雑食性も随所に見られる、笑い泣き必至のミラクルなポップ・ソングが満載。あえて、BELLE AND SEBASTIANのアルバムを一枚並べるなら『The Boy With The Arab Strap』。USインディの底の深さを実感させられる一枚。
-

-
THURSDAY’S YOUTH
6 Bagatelles
THURSDAY'S YOUTHが5年ぶりの流通盤となるEPをリリース。"6 Bagatelles(=つまらないもの、些細な事柄)"というタイトルが印象的だが、"つまらないものですが"なんて言いながら至高の6曲が並べられた。篠山浩生(Vo/Gt)の人生観や喪失感を色濃く映す歌詞は、時に鋭く強い言葉を綴りながらも、琴線に触れる繊細な歌声、軽やかに韻を踏んでいく心地よさ、温かく包み込むコーラスによって柔らかに響く。その言葉たちを粒立たせるように、無駄のない洗練されたサウンドは緻密に構築され、要所要所で楽曲をドラマチックに盛り上げている。差別、多様性などにも触れ世の中の空気感を反映しつつ、独自の視点で人生を諦観する本作。正解を突きつけるのではなく気づきをもたらす、そんな心揺さぶる歌に救われる。
-

-
THURSDAY’S YOUTH
東京、這う廊
活動休止期間を経て、改名後初のリリースとなった1stアルバム。生きる意味を強く歌った「さよなら」と「はなやぐロックスター」を始め、彼らの再出発として相応しい全15曲を収録。そのすべての楽曲に生きることへの想いが散りばめられ、それに対応する日常が刻み込まれている。今作のタイトルでもある「東京」ではせわしない都会の中で"生きる"日常が切り取られ、リズミカルな曲調に言葉のリフレインがクセになる「這う廊」では、最初のドアを開ける生活音と最後の"今日もゴミに出す 僕の明日を"というフレーズがリンクし、生きなければならない毎日を歌い上げている。1枚を通して穏やかな曲調であるが、"生きること=日常"に視点を置き、心が揺さぶられるような衝動も感じられる作品となった。
-

-
THURSDAY’S YOUTH
さよなら、はなやぐロックスター
昨年12月から活動休止をしていたSuck a Stew Dryが脱退したフセタツアキを除いたメンバー4人のまま改名してバンドを再スタート。サック時代の曲名から受け継いだTHURSDAY'S YOUTH(読み:サーズデイズユース)として、再始動のEP『さよなら、はなやぐロックスター』をリリースする。これまでのカラフルなサウンドは影を潜め、篠山浩生(Vo/Gt)が胸に抱えるやるせない感情を飾らない音像で届ける全4曲。過去の自分にけじめをつけて前へ進んでゆくための決意を感じる「さよなら」や「ぼくの失敗」、どう転んでも自分以外の自分にはなれないということを嘆きながらも受け入れる「はなやぐロックスター」や「タイムシグナル」は、どの曲もいまのバンドの心情とリンクしているように感じるのは、決して深読みではないと思う。
-

-
THURSDAY’S YOUTH
世界に一人ぼっち
人の弱さ、愚かさを暴くかのような強い歌と演奏に注目が集まっているSuck a Stew Dry。今年3月に新ベーシストが加入し、より活発な活動を展開する彼らの初EP。タイトル・トラック「世界に一人ぼっち」を含めたスタジオ・レコーディングの4曲が収録された今作も、シノヤマコウセイらしいシニカルな歌詞が光る。それとは裏腹に、爽やかで軽快なメロディが、全体的に明るくポップな印象を与える。特に「カラフル」や「ヒーロー」は優しく透明感のある歌声が心地よく、音源化の要望が高かったのも頷ける。また、自殺者へ語りかけるように歌われる「七階」は対比的にシノヤマの生への執着が伺える。この他に2曲のライヴ音源が収録されるとのことで、この1枚だけでも十分にSuckの世界観を楽しめるだろう。
-

-
THURSDAY’S YOUTH
ラブレスレター
話題の若手5人組ロック・バンドSuck a Stew Dryの2ndミニ・アルバム。どこか熱い気持ちを内に秘めたような鼻にかかるシノヤマコウヘイ(Vo/Gt)のヴォーカルと、一聴しただけで心に染み渡っていくメロディが非常に秀逸な作品である。特に「ないものねだり」での跳ねたリズムに絡む哀愁のあるメロディにはグッと胸を締めつけられたし、続く「傘」での衝撃すら受けた生々しい歌詞からは純粋なまでの不器用な愛を感じとることができるだろう。そのメロディを最大限に活かしているバンド・サウンドは決して聴く者を圧倒するものではなく、むしろ必死に気持ちを伝えるために辿りついた轟音。そんなメンバーの人間性から紡がれたリアルな感情に触れてほしい。
-
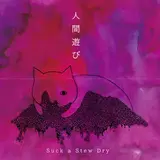
-
THURSDAY’S YOUTH
人間遊び
久しぶりに脱力してしまった。一言一言の痛々しさに胸が締め付けられ、気が付けば楽曲に同調し、立ちすくんでいた。漫然と日々を過ごしていたシノヤマコウセイ (Vo&Gt) の紡ぐ言葉は、世界とのつながり方がそのまま"生"を思わせる。 その派生としての"自己"に対する想い。何者でもない自分への憤り。深く枯渇した感情が溢れ出す。シノヤマの歌詞にノイズのようなサウンドを被せるSuck a Stew Dry は、2009年に結成し、翌年から活動を開始した非常に若い5ピースのバンドだ。息苦しいほどの気だるさの中 "誰でもない自分"を求めるが故の苦しさを歌う。壁を作って心を押し殺しながら、一方では心を追い求める。太宰 治が描くような不完全な歪さが、インクのような感染力を持つのだ。彼らが"帰ろう"とする場所は、過去かまだ見ぬ未来か。すべてはこれからだ。
-

-
Thurston Moore
Demolished Thoughts
SONIC YOUTHのフロント・マンであるThurston Mooreの3枚目のスタジオ・ソロ・アルバムが到着。なんと今作は、あのBECKがプロデュース。BECKのプロデュースといえば09年のCharlotte Gainsbourgの『Irm』やJamie Lidellの作品などが思い浮かぶが、今作はその2作にある先鋭的でクールな音像とは違い、Thurston Mooreが紡ぎ出す歌をシンプルに暖かく描き出す様なプロダクション。前作同様に、SONIC YOUTHの轟音サウンドとは違い、パーソナルで、とても繊細な歌声とメロディが心地よく響く。大胆に取り入れられたストリングスも、あのBECKの傑作『Sea Change』を彷彿とさせるようだ。
-

-
T-iD
New Attitude
俳優、声優、ラッパー、作詞家など様々なフィールドで活動し、2021年にはAcademic BANANAとのコラボ曲を発表した井出卓也(Takuya IDE)が、"T-iD"名義でリリースする初のEP。ヒップホップ/ラップとの出会いと信念を綴った「歌の神様」に始まり、日々の葛藤をポジティヴに昇華する「快晴」、アグレッシヴなビートでさらなる高みへ昇る決意を歌う「STAGE2 feat.KiDD」、荒々しく社会を斬る「Whatever」など、自身のスタイルを生々しくも等身大のリリックで表明した6曲を収録。固いライミングと鮮やかなフロウも手伝って、飾らないリアルな生き様をリスナーへとダイレクトに伝えている。名刺代わりに相応しく、この先にも期待の持てる1枚だ。
-

-
Tielle
Light in the Dark
ドラマや映画の主題歌などタイアップ曲が6曲中4曲を占めているものの、タイトルの"Light in the Dark"が示唆するように、現代の暗闇の中にあっても自らの意思で光を見ようとする主人公によって一貫性が保たれたミニ・アルバム。ピアノ・インストの「Noir.」のダークさから続く「In the Dark」に繋がるドラマ性。アルト・ヴォイスの魅力が際立つ。さらに海外シーンとシンクロするようなエレクトロニックなトラックが彼女の個性を際立たせる「CRY」、叫びたいような狂おしい状態を高低差のあるヴォーカルで見事に表現したハード・チューン「BLESSLESS」など、デビュー時からタッグを組むYosh(Survive Said The Prophet)とDAIKIによるプロデュース・チーム"The Hideout Studios"とのコラボもハマっている。ジャンルを超えるポップ・ヴォーカルの可能性が満載。
-

-
TIGERS JAW
Spin
アメリカ・ペンシルベニア州スクラントン出身の男女2人組インディー・ロック・バンド、TIGERS JAWの通算5枚目となるニュー・アルバム。数々のインディー・バンドを手掛けてきたプロデューサー、Will Yipが立ち上げた新レーベル"Black Cement Records"からの第1弾リリースとなる作品。1曲目の「Follows」からギターを中心とした演奏と淀んだところのないまっすぐな歌声による楽曲が続く。アコースティック・ギターの音色が美しい「Escape Plan」、物憂げな歌唱が耳に残るフォーキーな「Bullet」、女性ヴォーカル曲「Brass Ring」など、ひたすら歌を聴かせるためのシンプルな演奏は、正直派手なところはまったくないため特別なフックはない。そのぶん、噛めば噛むほど味がする、歌声の魅力がじわじわと胸に残るアルバム。
-

-
TILIAN
The Skeptic
DANCE GAVIN DANCEのヴォーカリスト、Tilian Pearsonによる3作目のソロ・アルバム。EMAROSA、SAOSINの作品にも参加するなど、ポスト・ハードコア・シーンに足跡を残してきた彼が、ここではバンドというフォーマットから解放され、存分にハイトーン&パワフルな歌声をアピール。エレポップ、R&B、ハウス・ミュージックのエッセンスを取り入れたサウンドメイキングからは、彼なりに現代のポップ・ミュージックに挑戦するというテーマがあったことが窺える。そんな試みとギター・ロック・サウンドが見事溶け合った「Handsome Garbage」、「Hold On」はそのうち日本のバンドが真似し始めるのでは(笑)。前者で聴かせる力強いシャウトにゾクゾクさせられる。
-

-
TIM & JEAN
Like What
PASSION PIT、そして最近国内盤が出たばかりのTHE NAKED AND FAMOUSを彷彿とさせる様なエレクトロ・ポップ・ユニットがオーストラリアから登場。それぞれ別バンドをやっていた二人が意気投合し、ベッドルームのキーボードを叩きながら作り出したという楽曲群は、昨今のシンセ・ポップの良い所をそのまま吸収した様なキャッチーで多幸感溢れるナンバーばかり。上記の2バンドが好きなら必ず気に入るであろうキラキラしたポップ・ソングが満載の一枚だ。ハイトーン・ヴォーカルにカラフルなシンセ・サウンドというスタイル自体には新しさは感じないが、それ故に彼らの作り出すメロディの良さが際立っている。二人ともまだ10代。これからが楽しみなバンドだ。
-

-
TIMES NEW VIKING
Dancer Equired
アメリカ、オハイオ州のローファイ・シューゲイザー・3ピース・バンド、TIMES NEW VIKINGの通産5枚目となるオリジナル・アルバム。これまでカセット・テープやVHSのビデオ・テープを使い録音しリリースしていた彼らだが、今作では遂にスタジオ・レコーディングを敢行したとのこと。メロディや不協和音はクリアに際立ち、極上のローファイ・サウンドはより一層深みを増し、新たな可能性へと導かれている。デジタルが溢れるこの時代に、ここまで人の汗と太陽のぬくもりを感じさせる音楽はなかなか存在しないのではないだろうか。気だるいポエム・リーディングのような男女ツイン・ヴォーカルを聴いていると幽体離脱しそうな感覚に陥って来る。非常に自由度の高い、これぞ自然体と呼ぶべきアルバム。
-

-
THE TING TINGS
Super Critical
200万枚を超える1stアルバム『We Started Nothing』の大ヒットを足がかりにマンチェスターのパーティー・シーンから世界に飛び出してきた男女デュオが前作から2年ぶりにリリースした3作目のアルバム。前作は1stアルバムのポスト・パンク/ニュー・ウェイヴ路線から一気に幅を広げた挑戦が印象的だったが、今回はそこから再び方向性を絞って、昔懐かしいディスコ・サウンドにアプローチ。なんでもアルバムを作っていたイビザ島のクラブでEDMばかり耳にした反動だそうだ。「Wrong Club」のPVからは70年代のディスコへの憧れが窺えるが、元DURAN DURANのギタリスト、Andy Taylorが曲作りとプロデュースで参加しているせいか、どこか80年代風にも聴こえ、そんなところがTHE TING TINGSらしいと思わせる。
-

-
THE TING TINGS
Sounds From Nowheresville
デビュー作『We Started Nothing』から約4年、SUMMER SONIC 11の出演も記憶に新しいTHE TING TINGSから待望のセカンド・オリジナル・アルバムがリリースされる。ベルリンで見つけたバーをスタジオに改造し、そこに拠点を移し制作された今作は、本人たちがインタヴューでも語っている通り、異なる音楽性を持つバラエティに富んだ楽曲が揃っている。Katieのヴォーカルやラップも曲によってキュートであったりクールであったり、時に穏やかで時に激しくと様々な表情を見せる。だがどの曲も共通して自然体のポップ・ソング。過剰な無理をせず、世間にも媚びず、自分たちが好きだと思ったことをのびのび行なっている。脱力系でありながらも、一本しっかり筋の通った彼らのライフ・スタイルが具現化された作品と言って良いだろう。
-

-
TINY TELEPHONES
The Heavenly Child
Patrick HeaneyとAaron Blombergの2人によって結成されたポスト・ロック・バンド。レコーディングにTHE ALBUM LEAFのJimmy Lavalleが参加していることから、彼らがエクスペリメンタルな音を奏でることは想像が容易であろう。Track.1「A Dream In Death」は冷たいドローンなイントロから徐々に神秘的なポスト・ロック・サウンドに展開していき、Track.2「Unfortunately We're Here」はミニマルなドラムと緻密に敷き詰められた音色が実に気持ちよく、Track.3「February 29, 1996」では淡いヴォーカルがSIGUR ROSを彷彿とさせる。冷たさと暖かさが同居したこの季節にハマる優しい作品。
-

-
TK from 凛として時雨
誰我為
日本のロック・バンドやアーティストが数多く手掛けてきたTVアニメ"僕のヒーローアカデミア"という努力や友情の物語のオープニングに、TKというある種エキセントリックな才能が書き下ろす意外性。すでに現在の代表曲になった印象すらあるが、やはりこれまでより格段に明快な歌詞とそれが乗るサビメロや歌唱には新鮮な驚きが。自分の限界を超えていく切実な想いと闘いを擬似体験させるエクストリームなアンサンブル、空間を切り裂くギターと滑空するストリングスなどすべてがTKらしさで溢れていると同時に、異形のひと言で括れないレベルに達したメルクマールだ。なお通常盤CDにはNHK「みんなのうた」に初提供した「クジャクジャノマアムアイア -TV edit-」も。言葉遊びとブラス・アレンジに驚きの新境地を見る。
-

-
TK from 凛として時雨
P.S. RED I
映画"スパイダーマン:スパイダーバース"日本語吹替版の主題歌として書き下ろされた「P.S. RED I」。まだスパイダーマンとしての能力をコントロールできず、異なる次元に存在する仲間とともに闘う主人公の像に歌詞で寄り添うだけでなく、メタリックなギターやローが強烈なシンセ・ベースなど、生身と無機物が軋轢を起こしながら融合するスパイダーマン自身の肉体感覚を想像させるようなエクストリームな仕上がりだ。カップリングの「moving on」はゲスト・ヴォーカルにSalyuを迎えたことで、TKの歌詞世界の普遍性がぐっと上昇した印象。映像が浮かぶような豊かな演奏も素晴らしい。初回盤にはこれまでの代表曲のスタジオ・セッションとドキュメント映像のDVDも同梱。貴重な映像だ。
-

-
TK from 凛として時雨
katharsis
TKのソロ作品9作目は、「unravel」以来となるTVアニメ"東京喰種トーキョーグール"シリーズでの再タッグだ。ピアノや弦楽器を加えた編成だからこそ際立つ、静謐と崩壊をギリギリのバランスで成立させるTKソロの醍醐味。アニメ・シリーズとTKの作品性の共通点であるアンビヴァレンツが高度に結晶し、歌モノとしての完成度も高い。また、c/wの「memento」で聴ける、TKにしては平易な歌詞も本質的で胸に迫る。なお初回盤のDisc 2には、Billboard Live TOKYOでの"Acoustique Electrick Session"から9曲を収録。単純にアコースティック、エレクトリックと分けられないヴィヴィッドな音の響きに、時に音源を超える臨場感に浸ることができる。
-

-
TK from 凛として時雨
Fantastic Magic
偏見や先入観の型に嵌められることは拒絶するが、自分でも測りかねない自分というものをわかってもらいたい、人間誰しも思うことではないだろうか。そういう意味でこれまでになく"人間・TK"が曝け出された作品。日向秀和、BOBOとヴァイオリン、ピアノとの五重奏は、タイトル・チューンや「kalei de scope」で破壊的までに高速回転しながらも、シンプルなアンサンブルの頂点に到達。一方、TKのピアノと歌のみの「tokio」やCharaがゲスト・ヴォーカルで参加した「Shinkiro」では、TKのジャンルや性別、年齢といった属性の希薄な声が、むしろそれこそ蜃気楼のような今、現在の不確実性を浮かび上がらせる。シンセ・ポップ的なサウンドでロックの衝動を示唆する「Spiral Parade」の発想も一歩踏み込んだ印象で痛快。
Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号

























