DISC REVIEW
W
-

-
WHITE ASH
THE DARK BLACK GROOVE
ハードでソリッドなナンバーから、ピアノが印象的な素直なラヴ・ソングまで、普遍的なロックの骨組みを持ちつつ、サウンドはWHITE ASHの2015年バージョン。UKやUSのR&Rリヴァイバル時のシンプルさも、現行のインディーR&Bが持つ削ぎ落とした洗練が持つシンプルさも想起させるあたりに、のび太のアレンジ・センスにバンドの音楽的筋力の進化も合わさって邦楽ロック・シーンではより突出した存在感を強めそうな1枚に。王道感と新鮮さの同居という意味ではヴォーカルの重ね方と80年代的なエレクトリックなビートの「King With The Bass」や、儚さや切なさを表現しつつ大仰さを微塵も感じさせないバラード「Gifted」が特に出色。王道とは、実は不変とアップデートの両輪があってこそ走ることができるのだ。
-

-
WHITE ASH
Hopes Bright
タイトル・チューンの「Hopes Bright」は、重い扉を自らの力でこじ開けざるを得ないようなヘヴィなコード感から始まり、孤独の中で自分自身の意志を確認するようなAメロの深さ、そこからダイナミックに上昇するサビ。ドラマティックなマイナー・チューンでポジティヴィティを湧き起こさせる、WHITE ASHならではのアプローチ。全編日本語詞であることも後で気づくぐらいの自然さだ。カップリングの「Killing Time」はイントロの不穏なピアノ、淡々と進む重心低めなリズムが印象的。もう1曲の「Faster」はのび太のヴォーカルとドラムのみのオープニングが、走り出しそうな勢い。相変わらず自由自在に伸びやかな声からシャウトまで、エモーショナルなヴォーカルの強さが痛快。
-

-
WHITE ASH
Ciao, Fake Kings
Track.1「Casablanca」の哀感とドラマ性たっぷりなイントロから変化を楽しむ姿勢が伺える2ndフル・アルバム。不穏なベースが牽引する「Zodiac Syndrome」、ラテン的なビート感や艶っぽさを増したのび太のヴォーカルが印象的な「Bacardi Avenue」、ダーク・サイケデリアがド--プな「Under The Lightless」など、いずれもグッとBPMを落とすことで冴えるリフやグルーヴで思わず曲の世界観に引きずりこまれてしまう。同時に従来の十八番的な構成の「Number Ninety Nine」や、全編日本語詞のクリスマス・ラヴ・ソング「Xmas Present For My Sweetheart」では蔦谷好位置のアレンジを有機的に導入。コーラス・ワークの素晴らしさも快感ポイントだ。
-
-
WHITE ASH
Would You Be My Valentine?
昨年夏にリリースされた1stフル・アルバム『Quit or Quier』はオリコン・インディーズ・チャートで見事1位を獲得し、初となるワンマン・ツアーも成功させたWHITE ASHからヴァレンタイン・デイにニュー・シングルが届いた。タイトル・トラックである「Would You Be My Valentine?」はいつものソリッドな彼らではなくドキドキするよな軽快で小気味良いロックンロール。メロディの良さはもちろんだが、ヴォーカルのび太の表現力豊かな歌声がとても気持ちいい楽曲だ。そしてカップリングの「I Wanna Be Your Valentine」は力強いハードなナンバー。DISC2には昨年行われたツアー・ファイナルの全14曲が収録。今のWHITE ASHの魅力がぎゅっと詰め込まれたシングルだろう。
-
-
WHITE ASH
Quit or Quiet
自らのヴィジュアルを揶揄するように意図的に“のび太”という強烈な記号を名乗るフロントマンを擁しながらも、所謂WEEZER的な泣き虫メンタリティとは無縁の場所でふてぶてしい表情を浮かべ、虎視眈々と変革を狙うWHITE ASHは、言わば日本のロック・シーンのジョーカーだ。ARCTIC MONKEYS譲りのグルーヴィなリフが印象的なダンス・ロック・サウンドに、日本人的な艶のあるメロディ、そして抽象的でありながらも、常に行間からは無垢なロマンと成功への野心が零れ落ちる歌詞。シリアスであることが美徳とされるシーンの潮流に迎合することなく、どこかユーモラスでヒラヒラとした佇まいを一貫しながら、しかしその実、誰よりも貪欲に自分たちだけの物語を描こうとしていることが、その音楽からもヒシヒシと伝わってくる。現時点の集大成と言うべき、未完の大器による堂々のファースト。
-

-
WHITE ASH
Kiddie
1 stシングル『Paranoia』に続き、ワン・コイン・シングルとしてリリースされた『Kiddie』。再生後1秒で緊張感に満ちたサウンドが展開される。「Stranger」で体を貫いた衝撃が蘇った。いや、「Stranger」で見せた圧倒的な歪みを越えていた。これまでは、独特な言葉の連なりで、ある種ファンタジックな世界を確立してきたWHITE ASH。どこか言葉を知らない子どものようで、狙い定めた言葉よりもストレートに核心を突いてきた。だが「Kiddie」は独自の世界を推し進め、確かな言葉を織り交ぜながら、終わりの先にある次のステップを描き出している。ハイトーン・ヴォイスで中性的なのび太のヴォーカルは、幾多のフェス、ライヴのステージを経て、不思議な色気を獲得。ギターのキリキリとした圧迫感のなか、心地良く響く。"WHITE ASH"が、"WHITE ASH"という枠から羽ばたいたのだ。
-

-
WHITE ASH
Paranoia
"日本のロック・シーンいただきにきました。"byのび太。――のび太の野郎、でかいこと言いやがる。しかしながら、このビック・マウスのひ弱な青年は、風車に戦いを挑む、現実と空想の識別不能な愚か者のドン・キホーテでもなければ、勿論ドラえもんと仲良しの少年でもない。暗闇から突如飛び出す鋭き刃のように、瞬間を切り裂いていくギター・ロックの新鋭WHITE ASH。彼らが初のシングルとして勝負を挑むのは、バンドの持ち味を凝縮した1曲。リズム隊が轟かせる不穏な空気、その鋭利な切れ味でもって最高のスリルを演出するギターと、冷温硬質でこちらも切れ味抜群のヴォーカルが切り込んでくる。彼らは「Paranoia」という剣でもって、勝算あり気でロック・シーンに切りかからんとしているのだ。
-

-
WHITE LIES
As I Try Not To Fall Apart
UKのポスト・パンク/インディー・ポップ・バンドによる6thアルバム。全英チャートで1位を獲得したデビュー作『To Lose My Life ...』などに関わったEd Bullerや、WEEZERなどを手掛けるClaudius Mittendorferをプロデュースに迎えた本作は、キャリアを総括したような作品に。ファンキーなカッティングが踊るTrack.1や、80sの質感を持ったシンセがきらびやかに彩るTrack.2、ドラマチックなサビを奏でるTrack.4、壮大なサウンドスケープのTrack.9、抑制されたハンマー・ビートからエモーションを爆発させるTrack.10など、時にノイジーに時にソフトに感情を揺さぶる楽曲はまさに粒揃い。着実な深化を感じる1枚だ。
-

-
WHITE LIES
Friends
デビュー盤からハズレなしにヒットを飛ばしてきたロンドンの3ピース・バンドによる4作目。シンセを主体としたJOY DIVISIONに通ずるポスト・パンク・サウンドに加えて、ニュー・ウェーヴやニュー・ロマンティックの香りを漂わせる本作は、10代でのデビュー時と比べるとスタジアム級のサウンドへと進化していることを感じさせる。冒頭「Take It Out On Me」のループするフレーズをドラマチックに盛り上げる構成や、「Don't Want To Feel It All」のスティールパンの音色を思わせるポップなエキゾチカなど、その多様性は全盛期のU2に通じる勢いを思わせ、急勾配なフェードアウトや散りばめられた80's要素にもニヤついてしまう。現代にコミットしたシンガロング・ナンバーが満載の1枚だ。
-

-
WHITE LIES
To Lose My Life
高速道路でトンネルを走っている時の感覚が好きだ(助手席だけど)。延々とループしているような錯覚と、暗闇から出口に向かっている実感が同時に味わえる、奇妙な一時だ。UKはウエストロンドン出身、本作でデビューを果たしたWHITE LIESの音楽性は、そんなトンネルを走っている時の感覚に似ている。暗闇を恐れるわけでも、暗闇を崇拝するわけでもなく、暗闇の中を光に向かって駆け抜ける感覚。人生の暗い部分から目を逸らさず、それでも希望をしっかりと持っていること。ロックが教えてくれることの一つは、きっとそういうことだ。一見、暗く、冷めているギターロックの先にある高揚感こそ、彼らの本質だ。JOY DIVISIONではなく、NEW ORDERになってほしい。
-

-
WHITE LIGHT PARADE
House Of Commons
とにかく、5曲目「Wait For The Weekend」だろう。イントロのドラムからTHE KILLERSやBLOCK PARTYを髣髴させるメロディまで、まさにアンセムと呼べる一曲だ。瑞々しいポップさを持つDanny、マッチョなTHE CLASHチルドレンという感じのJonoと、バンドの中心であるYates兄弟のヴォーカル&ソング・ライティングの個性がはっきりと異なるところも面白い。これぞワーキング・クラス・ヒーローという歌詞、疾走感と高揚感に満ちたシンプルなギター・ロック。週末を待ち望む退屈な日常へのフラストレーションをロックンロールに変換する。これまでも何度も繰り返されてきた図式そのものだが、それでも僕はまたもやこのアルバムに胸躍らせている。
-

-
WHITE REAPER
You Deserve Love
アメリカ ケンタッキー州ルイビルを拠点に活動しているガレージ・パンク・バンド、WHITE REAPERの3枚目のフル・アルバム。もともとは3ピースだったが、『White Reaper Does It Again』(2015年)はキーボードを迎えた4人編成でリリースし、今作ではさらに5人になってパワーアップした姿でのリリースとなる。今作では、よりキーボードの存在感も増し、パワー・ポップ的な軽やかさが加わっている。ロックンロール・リヴァイヴァル系のバンドの裾野あたりから、さらに踏み込んだアプローチで広いリスナー層に受け入れられるサウンドに進化したが、決して日和見なわけではなく、シンプルな音作りと粗削りな部分を残した彼ららしいスタイルには好感が持てる。
-

-
THE WHITEST BOY ALIVE
Rules
ドイツ、ベルリンにて結成されたKINGS OF CONVENIENCEのErlend Oye率いるエレクトロ・ユニット。KINGS OF CONVENIENCEのフォーキーなサウンドとは違いTHE WHITEST BOY ALIVE は大胆にダンス・ミュージックのフォーマットを用いて、とても都会的なサウンドを奏でる。今回の2ndアルバムは無駄なもの一切排除して、LIVEを意識したと語る様にシンプルかつとても完成度の高い仕上がり。Erlend Oyeのヘロヘロながら憎めないボーカルも健在で、独特のポップ・ワールドが広がっている。夜の街が似合うそんなアルバムです。
-

-
THE WHITE STRIPES
The White Stripes Greatest Hits
"なぜ今、THE WHITE STRIPES?"と思った方も多いだろう。"再結成でもするの?"と。残念ながら今のところその予定はないようだが、なんと初となるベスト・アルバムがリリースされた。改めて彼らの楽曲を聴いて驚かされるのは、色褪せることのないそのド直球なロック魂だ。純粋に、ただただひたすらカッコいい。クセのあるJack Whiteのギターはもちろんのこと、情熱と音楽への欲だけで叩いているようなシンプルなMeg Whiteのドラムも、唯一無二の彼らだけの世界観だ。ふたりだけの世界だからこその、衝突するような危うさや絶妙なバランス感覚。このベスト盤で、ロックンロール・リバイバル・ブームを知らない世代にも彼らの存在が広く再認識されれば嬉しいし、再結成されたらもっと最高だ。
-

-
THE WHITE STRIPES
Under Great White Northern Lights
THE WHITE STRIPES本体の活動は止まったままで、Jack Whiteだけがやたらと精力的に動き続けているが、やはりこういう音源を聴くとTHE WHITE STRIPESの新譜を聴きたくなる。カナダ・ツアー・ファイナルの模様を収録したライヴ音源とドキュメンタリー映像がセットとなった本作。目玉となるのはツアーのドキュメンタリーを収録したDVDだろうが、一音だけの演奏からオフ・ショットまで、その内容はここでは書ききれないほど濃密。そして、ライヴ音源ももちろん、荒々しいエネルギーに満ちた彼らのライヴが堪能できる。JackとMeg二人だけというのは、今さらながら信じられない。それにしても、2007年って『Icky Thump』からもうすぐ3年も経つんだな。早く動き出してください。
-

-
white white sisters
SOMETHING WONDROUS
yuya matsumura(Gt/Prog/Vo)、kitaro hiranuma(Dr)、そしてkouta tajima(VJ/Art Work)というなかなか珍しい編成の3ピース・エレクトロ・ロック・バンド、white white sistersの1stフル・アルバム。中性的なヴォーカル、感情的なギター、アグレッシヴなドラム――それらが煌びやかで近未来的な電子音に肉感を生み出す。細やかなエレクトロ、大胆なノイズ、随所にマニアックなこだわりを見せつつ、踊りだしたくなるようなキャッチーさも兼ね備えたセンスの高さに、サカナクションやavengers in sci-fiがシーンへ現れた時の高揚感を思い出した。サウンドに加え、ハイクオリティなVJのもとライヴを繰り広げる彼らなだけに、4曲入りの付属DVDにも期待が高まる。
-

-
white white sisters
spectrachroma
名古屋在住のエレクトロ・バンドwhite white sistersの2ndミニ・アルバム。電子音の波間をぬって流れ来るメロディは幾度も体を通りぬけ、その度に恍惚の波が押し寄せる。その広大なサウンド・スケープは神秘的だが暗く、重く、そして閉鎖的。まるで、人気のない孤独な宇宙空間のような世界だ。そんな中、ラスト・ナンバー「laddershaped seven horizons」で見せた展開には目を見張るものがあった。閉ざされた空間の中で渦巻いていた音波とメロディを、濁流のごとく一気に外へ解き放つ、それまでとはうってかわったパワフルで活き活きとした音に、宇宙とは全ての生命の源なのだというイメージが喚起された。動き出したマシンは止まらない。スピードと電子音の支配する、無重力空間へと放り込まれたら最後、あとはもうエレクトロニカの魔法にかかるだけだ。
-

-
The Whoops
Time Machine
2枚のミニ・アルバムを経て、The Whoopsが3年ぶり2枚目のフル・アルバムをリリース。自己紹介的な意味合いの強い作品だった1stアルバム『FILM!!!』(2016年)に対し、本作はより振れ幅の大きい内容。THE STROKESやSUPERCAR、Enjoy Music Clubといった彼らのルーツ、今興味のある音楽のエッセンスがジャンルを問わず色濃く反映されているようだ。3年の間に演奏も洗練され、特に「行方」のアンサンブルには大きなスケールを感じる。宮田と森のツイン・ヴォーカル曲「Soda」、全編打ち込みの「踊れない僕ら」といった新しい試みも。曲同士の繋がりを彷彿とさせる言葉選びにも工夫が詰まっていて、想像力を掻き立てられる。
-

-
The Whoops
FILM!!!
埼玉県北浦和発の3ピース、The Whoopsの1stフル・アルバム。"過去"と"遠く"へ目を向け、"今"、"ここ"のことについて歌わない歌、あえて余白を残した演奏、それから些細な日常の風景と微細な心象を重ね合わせることにより、誰もが密かに内にしまっているセンチメンタルな気持ちを呼び起こしていく。"FILM!!!"というタイトルが表しているとおり、最後に残るのはまるで映画を鑑賞したあとのような後味。そんなロマンチックな風景の中に佇む、どこか報われない主人公の存在とそれゆえの切なさ(メンバーの言葉を借りると"2軍感")もこのバンドの大きな特徴だろう。肩肘張りすぎないテンションや音楽的ルーツを感じさせられるフレーズからも、3人の体温が伝わってきた。
-

-
Who the Bitch
Unlimited
ehi(Vo/Gt)とNao★(Vo/Ba)からなる女性ふたり組がおよそ4年ぶりにリリースする4thミニ・アルバム。伸びやかな歌と、歪みがかなりエグいグランジ調のガツンとくるバンド・サウンドの組み合わせが聴きどころには違いない。しかし、リスナーの感情に訴え掛けるという作品の本質を言うなら、一番の聴きどころは聴き終わったときに得られるカタルシスとその結果の清々しい感覚だ。このミニ・アルバムがそういう作品になった理由はぜひインタビューを読んでいただきたいが、音楽の嗜好を超えたところで、日々、何かもやもやとした感情を抱えているすべての人に薦めたい1枚。根本的な解決にはならないかもしれない。しかし、何かが変わるきっかけになる。そういうエネルギーがここにはある。
Warning: Undefined array key "$shopdata" in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/list/189310.php on line 27
-

-
Who-ya Extended
Q-vism
純然たるバンドではないアーティストにここまでやられてしまうと、もう並のロック・バンドでは太刀打ちできる余地があまりない。今作でメジャー・デビューを果たしたWho-ya Extendedは、弱冠20歳のヴォーカリスト Who-yaを中心としたクリエイターズ・ユニット。TVアニメ"PSYCHO-PASS サイコパス 3"のOPに起用されている表題曲「Q-vism」の持つ鋭利さと中毒性フルゲージ加減は、憎らしいほどにカッコ良さが満載で一切の隙なし。かと思えば、c/w「S-cape 2 the abs」で聴ける爽快さを漂わせたギター・ロック然とした音像とWho-yaの伸びやかな歌声は、聴き手を癒したりもする。公式サイトにはまだ情報らしいものがほぼ見当たらない。いったい何者だ!?
-

-
WHY DON'T WE
The Good Times And The Bad Ones
2016年の結成以降、高い表現力と端正なルックスで人気を博し、新世代のボーイズ・グループとして確固たる地位を築いたWHY DON'T WE。約9ヶ月に及ぶ休止期間を経て、自ら演奏する"バンド"として表舞台に戻ってきた彼らが、待望の2ndアルバムを発表した。新章の開幕を告げる力強いビートのTrack.1を皮切りに、スマパン「1979」をサンプリングした爽快なTrack.2(BLINK-182のTravis Barkerもドラムで参加)、SKRILLEXが手掛けたチルなトラックのTrack.7などのポップなサウンドから、抜群の歌唱力が際立つ壮大なバラードのTrack.6まで、メンバーがプロデュース/作詞作曲を手掛けた楽曲は実にバリエーション豊か。確かな成長を感じる1枚だ。
-

-
Wienners
みずいろときいろ
昨年9月にオリジナル・メンバーの脱退、今年5月よりアサミサエ(Vo/Key/Sampler)、KOZO(Dr)を迎えた新体制として再始動を果たしたWiennersのカムバック作。表題曲の「みずいろときいろ」は瑞々しいシンセ・サウンドで幕を開け、玉屋2060%(Vo/Gt)の切なく疾走し突き抜けるエモーショナルな歌声にヤラれる。しがらみを振り解くようなまっすぐさが熱く胸を締めつける。そして、でんぱ組.incへの楽曲提供を通して世界中のナードたちの心をキャッチした玉屋節が炸裂するジャパニーズ・ヘンテコ・ポップ・チューン「姫君バンケット」では、アサミサエがリード・ヴォーカルを務め新体制を一層印象づける。キュートさの滲むヴォーカル・ワークや散りばめられたシンセやアッパーなお祭りビートと痛快なあっぱれ具合。復活の狼煙には十分すぎる必殺の2曲とそのリミックスが収録される。
-

-
Wienners
UTOPIA
2010年にリリースされたファースト・アルバム『CULT POP JAPAN』以来2年ぶりとなる、Wiennersのセカンド・アルバム。『CULT POP~』はAIR JAM世代に影響を受けたハードコア・パンク・バンドが村の夏祭りで演奏しているかのような、実に奇妙かつハイ・ボルテージな快作だった。そして『CULT POP~』以降にリリースされたミニ・アルバム『W』、シングル『十五夜サテライト』で、自分たちの中にある“歌心”を探り、楽曲の幅とスケール感を増してきた彼らは、本作において、ハードコア魂と祝祭感に溢れた唯一無二の音像を構築することに成功している。『UTOPIA』というタイトルが指し示すように、ここには音楽にしか生み出すことのできない、とてもロマンチックで、そして現実的な理想郷が描かれている。
-

-
Wienners
W
しばしの沈黙ののち、唐突に挿入される“タスケテ”という囁き。呪文を合図に、危うい狂気のポップ・ワールドが幕を開ける。1年3カ月ぶりの新作『W』は、幼いころの落書きのような無邪気さが溢れ、カラフルで、実に大胆だ。音楽のジャンルといった一切の枷を断ち切り、自由気ままに音が連なっていく。昔のアニメのように、率直で欲求がきちんと明確だった時代を思い起こさせる。だからこそ、臆することなく発せられた“I need you” “ウォーアイニー”という言葉に力が宿るのだ。華やかで賑やかで雑多な夢のように、無条件に明るく、物語は入り乱れる。様々な音がぶつかり合う洪水の中、サウンドは魔法の呪文となり、Wiennersという存在そのものを救済、そしてその先にある理想郷へと変えてしまう。
-
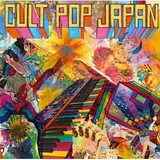
-
Wienners
CULT POP JAPAN
2007年結成、都内を中心に活動するバンドWiennersの1stアルバム。できること全て、思いつくこと全て、バンドが持っているパーツを全て詰め込んだこのアルバムは、全力全速力な中で、フレッシュなエネルギーが弾けている。勢いまかせにWiennersに身をまかせれば痛快このうえない。あなたの連想する“CULT”“POP”“JAPAN”とはなんですか?そう言われても、明確に言葉にすることはできないだろう。なぜなら、あくまでもこの言葉はニュアンスでしかないのだから。それはPOP を土台に、あとはなんもかんもサンプリングしてしまう、目についたものを次々に貼っていく子供の貼り絵のようにハチャメチャな画。常識無視で規格外。しかし、結果として連想されるニュアンスそのままの音が鳴っている。全てが過剰故に、感覚や感性を直接刺激する、これこそがWiennersの破壊力だ。
-

-
WILCO
Cousin
来年3月に来日公演が決定しているアメリカン・ロックを代表するバンド、WILCOから通算13作目となるスタジオ・アルバム『Cousin』が届いた。本アルバムは英ウェールズのミュージシャン Cate Le Bonをプロデューサーに迎えて制作。彼らが外部プロデューサーと組むのは6thアルバム『Sky Blue Sky』(2007年)以来とのこと。キャリアを通じて一貫された実験的な姿勢は今作でも健在で、オルタナ・カントリー・テイストのリード曲「Evicted」で見せるシンプルな音像ながらも繊細で奥深い表現力には舌を巻くばかり。Le Bonが"WILCOのすごいところは、彼らが何にでもなれること"と語っているように、WILCOというバンドの柔軟性と懐の深さを再認識させられてしまう1枚。
-

-
WILCO
Ode To Joy
"俺が作る最高の曲を、お前ら、どれだけぶっ壊せるんだ!?"というフロントマン、Jeff Tweedyの挑戦に経験豊富な名うてのミュージシャンたちが応え、バチバチと火花を散らしていたWILCOも今は昔。Tweedyのソロ活動を挟んで、3年ぶりにリリースするこの11作目のアルバムは、作品を重ねるたびごとに強まっていった歌志向がついに頂点に達したことを思わせる。まるでTweedyのソロを、WILCOのメンバーと作ったみたいだ。最初に聴いたときは、ボソボソと歌うTweedyのヴォーカルの印象のせいか、あんまり地味でびっくりしたが、聴いているうちに味がしみるいわゆるスルメ盤。Tweedyが屈指のメロディメーカーであることを改めて実感。バンドの演奏はちょっとTELEVISIONを思わせるところも。
-
-
WILCO
Star Wars
ベスト盤、レア・トラック集を挟んで、現代のUSロックを代表するバンド、WILCOが4年ぶりにリリースした9作目のオリジナル・アルバム。その印象を端的に言うなら、THE BEATLES(の影響)とアヴァンギャルドなサウンド。前2作の流れからさらにルーツ・ロック色濃い作品になるかと思いきや、こういう作品を作ってしまうところが現代屈指のソングライターが率いる最強のポスト・ロック~ジャム・バンドであるWILCOの面白さ。変拍子やノイズも交え、00年代前半に追求していたプログレッシヴなバンド・アンサンブルにアプローチしながら、それをポップ・ソングとしても楽しませることができるのが今の彼らだ。全11曲30分強という長さも心地いい。つまりここにはムダなものは一切ないということだ。
-
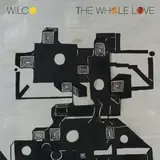
-
WILCO
The Whole Love
オルタナ・カントリーという音楽基盤を持ちながらも実験的な試みを繰り返し、知性溢れる良質な楽曲を生み続けるアメリカ、ポスト・ロック界の至宝WILCO。ベスト・アクトとの呼び声高いFUJI ROCKでのライヴが記憶に新しい彼らだが、その時、披露された「I Might」や「Dawned On Me」といった歌心溢れるライヴ・ナンバーも収録された今作は、新たに設立された彼らのレーベルdBpm Recordsからの初作品。メンバー個々の確かな技能によるバンド・アンサンブルが美しい構成を成し、随所に配された音楽IQの高さが伺えるアイデアに二ヤリとさせられる。豊潤な音の実りを感じさせる今作は、全音楽ファン必聴の内容だ。国内盤には、秋よりツアーを共にするあのNick Loweのカヴァーが収録(涙)!
-

-
WILCO
Wilco(The Album)
WILCOの最高傑作と言われる4枚目『Yankee Hotel Foxtrot』から7年。当時夢中になって『Yankee Hotel Foxtrot』を聴いた憶えがある。その後主要メンバーの脱退を経ながらも2 枚のアルバムをリリース。音楽的冒険心はあるものの、やはり『Yankee Hotel Foxtrot』を越える作品にはなっていなかった。そして今回の通算7枚目のオリジナル・アルバム。タイトルは初のセルフ・タイトル。60年代のサウンドを意識したと語る様に、とても耳障りのいい作品。「Wilco(This Song)」を筆頭にシンプルで前2作には無かったとても明るく風通しいい楽曲が並ぶ。Feistとのデュエット・ナンバーも収録。こんなWILCOを待ってました。充実の力作。
-

-
WILD BEASTS
Present Tense
2009年『Two Dancers』はマーキュリー・プライズにノミネートされ、前作『Smother』も全英17位と好セールスを記録した英国の4人組による4作目のアルバム。今作ではBjorkやBrian Enoを手掛けたプロデューサーを迎えており、独特の音像が広がりと深みを増し、メロディがぐっと際立つ仕上がりとなっている。3拍子のリズムがループされ、ポストパンク/ニューウエーブ的なアプローチのシングル「Wonderlust」、単音のシンセのメロディが印象に残る「Sweet Spot」はアルバムの中でもポップな部類で、全体のトーンはひたすら暗いのだが、美しさと恐ろしさを孕み、ファルセットで歌い上げられるソウルフルなヴォーカルに惹き込まれる。
-

-
WILD HONEY
Big Flash
マドリード発、Guillermo Farreのソロ・プロジェクト、WILD HONEYの2ndアルバム。STEREOLABのTim Ganeをプロデューサーに迎えた今作は、ソフト・ロック、60’Sポップへの憧憬やリスペクトを高い純度のまま譜に落とし込んで、そのサウンドを慈しむように甘いメロディやコーラスでリボンをかけた。白昼夢的でとろりと濃密な西海岸サウンドも、爽やかさにモンドな香りを忍ばせた北欧ポップの面白さも併せ持っていて、心地好くも刺激的。フォーキーなサウンドながら、広々とした音空間を漂う感覚で、スペイシーな音響やフィルや遊びのアクセントなどカラクリたっぷりで楽しませてくれたりと、Timとの作業でポップないたずら心も増した模様だ。マジカルなポップ世界はTAHITI 80ファンにも薦めたい。
-

-
Will Samson
Hello Friends, Goodbye Friends
イギリス生まれの23歳、Will Samson。彼は幼少期からオーストラリア、イギリス、ドイツなどに移り住み、ジャケット写真からも見てとれるように、19歳の頃ヒマラヤ山脈を経る放浪の旅を続けていたそうで、そこからインスパイアされた楽曲は、そびえ立つ山脈のように力強くも時間がゆったりと流れる。アルバム・タイトルの『Hello Friends,Goodbye Friends』はたくさんの地を旅して一期一会を繰り返した彼ならではのタイトルだろう。心臓の鼓動のようなリズムは安心感を生み出し、サウンドに溶け込んだ歌声と心地よい繊細な音に身を委ねたい決定的な睡眠導入盤。個人的に、彼はものすごいポテンシャルの持ち主だと感じるので、アートやデザインなど音楽以外の表現作品でも才能を発揮しそうな気がする。
-

-
The Winking Owl
Thanksラブレター
ラウド/エモの側面であるダイナミックな音像や演奏スキルは残しつつ、世界的な潮流であるEDM以降のポップスもJ-POPのキャッチーな要素もThe Winking Owlのフィルターを通して表現した2ndフル・アルバム。仲間やリスナーへの感謝や愛を感じる表題曲で清々しくスタートし、新たなモードを代表するポップな「Try」や、ドラマ"歌舞伎町弁護人 凛花"主題歌としても話題の「NEW」、切なさを表現するLuizaの歌唱が映える「片想い」、イントロでR&B的なトラックメイキングのセンスが窺える「Confession」や、遅めのBPMで横ノリできそうな「君のままで」、EDM以降のポップス手法であるエレクトロやプリミティヴなビート感が新鮮な「Flame Of Life」まで曲の良さが光る。
-

-
The Winking Owl
Try
前作『Into Another World』で変化を求めていたThe Winking Owlだが、今作『Try』は不意に感じる弱さや寂しさに人間らしさが滲むものの、全体的に明るくポジティヴな印象。この1年半の間に、彼女たちの中に眠っていた"野心"や"どう変わりたいか"が明確に見えてきたのだろう。挑戦することに迷いがなく爽快で、新しいウィンキンの音楽性が窺える作品に仕上がっている。前に進むためには"やってみること"が大切だというどストレートなメッセージも、英語詞と日本語詞をうまく使い分けることでまっすぐ心に響いてくる。温かみのある歌詞に寄り添う、優しいドラムも新鮮だ。9月の初ワンマンを経てさらなる高みを目指すバンドの決意表明のような、希望に満ち溢れた1枚。
-

-
The Winking Owl
Into Another World
The Winking Owlはポジティヴな意味で"宇多田ヒカルがONE OK ROCKで歌っている"ような破壊力とポピュラリティを持っていると思う。1stフル・アルバム『BLOOMING』以降、そのツアーや、各地の夏フェス、イベントであらゆるカラーのバンドと勝負してきた彼らの新作は、Yoma(Gt)のスケールの大きな曲の魅力と、切な苦しいLuiza(Vo)の声の表現力、そして踊るようにしなやかなKenT(Dr)のテクニカルなドラミングがバンドのスタンダードとして確かな背骨を形成した印象。堂々とコードワークやリズムの巧みさを構築するTrack.1、"次のステージに向かえ"と歌い、すでにデビュー時の話題性を自ら過去のものにするようなTrack.2、ラウド版ロック・バラードのTrack.5。地に足のついた楽曲が並ぶ本作で、冒頭の"掛け算"イメージもありつつ、己の道を進んでいきそう。
-

-
The Winking Owl
BLOOMING
そもそもエモ/ラウド要素をもったスタジアム・バンドは世界に数多く存在するけれど、これがスタンダードだと言い切れる洗練をThe Winking Owlもこの1stフル・アルバムで形にしてきた。デビュー・シングルの表題曲でもある「Open Up My Heart」、ブライトな「This Is How We Riot」、ストレートで美しいメロディを持つ「Bloom」と、頭3曲でグッと惹きつけ、Luizaもファンだという宇多田ヒカルを想起させる描写力の高いヴォーカルが印象的な「Lust」、シンプルながらコードの響きなどで、明るいイメージのアルバムの中でフックになっている「Walk」、ライヴを盛り上げる場面で聴いてみたいラフな「Your World」など全12曲を収録。パワフルだがあくまで女性ヴォーカルの良さを活かしたバンド像がより明快に届く。
-

-
The Winking Owl
Open Up My Heart
弱冠18歳のドラマー、KenTが加入して初の音源且つ、The Winking Owlのデビュー・シングル。エモ/ラウド系のサウンドやビート、プロダクションでありつつ、Luizaの切な苦しいヴォーカル表現が、彼女のバックボーンである宇多田ヒカルと共鳴する部分も。そんなバンドの特徴を端的に表現したTrack.1「Open Up My Heart」、光を感じさせるサウンド・メイクが、努力を表に出さず頑張ってきた覚えのある様々な人の肩を優しく叩いてあげるようなリリックにもハマっているTrack.2「Here For You」、楽器隊のスキルの高さや曲の構成力に唸るTrack.3「Fallen Angel」と、The Winking Owlを知るには最適なバリエーションが凝縮されたシングル。グッド・メロディとギミックを排した王道の展開が爽快だ。
-

-
winnie
Greatful 15years Dead
これまでにリリースしてきた6枚のアルバム、1枚のシングルから14曲を厳選。そのうち「ruby tube tail」、「sweep」、「suddenly」、「first class speed of light」は新録し、さらにPS4サバイバル・アクション・ゲーム"LET IT DIE"の挿入歌「let it die」をベスト・アルバム・バージョンとしてCD初収録。これで1,500円というのは破格だ。曲順はリリース時期と関係なく並んでいるので、まるでライヴで聴いているような感覚を味わえる。ioriのクールでキュートな歌声と、okujiのエモーショナルで男っぽい歌声が絡み合い、且つ様々なジャンルをフットワーク軽く取り入れた彼らの"代表曲"が続くので、とても濃い。総括でありながら、入り口にもなる1枚なので、これを機に多くの人に彼らと出会ってほしい。


























