DISC REVIEW
L
-
-
LiSA
LiTTLE DEViL PARADE
デビュー5周年を終えたタイミングでリリースされたフル・アルバム。ドラムロールをバックにして始まる表題曲「LiTTLE DEViL PARADE」からして新章の訪れを感じさせてくれる本作を聴き進めていると、音楽越しにLiSAと未来の話を交わしているような感覚に陥るが、その中心にあるのは、彼女がたびたびライヴで口にしていた"自分の好きなことは自分で守る"という部分。東京スカパラダイスオーケストラ編曲の「そしてパレードは続く」などこれまでにない挑戦も垣間見えるが、同時に原点回帰感もあるのは、おそらくその本質がブレていないからだろう。過去と未来をひとつなぎにする本作は、彼女のバイオグラフィにおけるマイルストーン的な役割を担うこととなるだろう。
-
-
LiSA
Catch the Moment
デビュー以降アニメ・タイアップ曲を多く歌い続けている彼女が、自分自身が持っている色を出せるようになって久しいが、ここまでディープに彼女個人の精神性が表れながらもアニメの世界観にも準じた楽曲はなかったかもしれない。UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が作る力強くキャッチーながらも一抹の感傷性を感じさせるメロディ・ラインは、LiSAの人間性そのもののよう。純粋で切実な願いを訴える彼女の歌詞と歌声含め、彼女から"ソードアート・オンライン"とリスナーへの感謝と愛を綴った、まさしく彼女の言うとおり"ラヴ・レター"だ。「みんなのうた」に起用されたTrack.2、八重歯を覗かせて目を細める彼女の笑顔をそのまま音楽にしたようなTrack.3と、全曲に経験と年齢を重ねた彼女の魅力が凝縮されている。
-

-
LiSA
Brave Freak Out
今年4月にソロ・デビュー5周年を迎えたばかりの彼女が、約1年ぶりとなるアニメ・タイアップを表題曲にシングル・リリース。この5年でロックとポップ、音楽シーンとアニメなどのポップ・カルチャーを繋ぐ女性シンガーという、新たな道を切り拓きその勢力を拡大させ続けている彼女だが、その成功の裏には何度も転びながら様々な壁を越えてきたというひたむきな姿があった。Track.1はLiSAの現在とタイアップ作品"クオリディア・コード"が持つ陰の中にある強さや勇敢な心をシンクロさせた、無敵感や力強さに加えて清涼感のある楽曲に仕上がっている。成熟した人間像が全面に表れたヴォーカルも説得力抜群だ。彼女は着実に自身だけでなく、楽曲も最大限に生かし魅せるアーティストへと成長している。
-

-
LiSA
LUCKY Hi FiVE!
ソロ・デビュー5周年記念盤として制作された、デビュー作『Letters to U』以来となるミニ・アルバム。今作もお馴染みから初タッグまで幅広いクリエイターが参加している。UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が携わったTrack.2は彼女の歴史を凝縮させたような爽快なロック・ナンバー。感覚ピエロの横山直弘が作曲を手掛けたTrack.3は、彼特有の妖艶なメロディがLiSAの様々な色気を引きずり出している。PABLOが作曲したTrack.4は、ヘヴィな楽曲を巧みにドライヴするLiSAの、パワフルでありながらも可憐な歌声が心地いい。個性的な楽曲をこれだけ自分の表現として成立させることができるのは、彼女がリスペクトと好奇心と探求心を持っている証。こんな歌姫、なかなかいない。
-

-
LiSA
Empty MERMAiD
今年1月に行った武道館2DAYS公演から休む間もなくリリースを重ね、活発なライヴ活動展開、さらに夏フェスや地上波生放送音楽番組に出演するなどフィールドを広げた活動を続けるLiSAが、最新作で掲げたテーマは"女性"。収録される3曲は女性ヴォーカリストを擁するUPLIFT SPICE、小南泰葉、カヨコがそれぞれ作曲を担当し、歌詞で恋愛を描くことからもその徹底ぶりがうかがえる。表題曲は報われない恋をする女性を人魚姫に例えた楽曲で、強く切なく歌い上げる彼女の声が女性の満たされなさや寂しさをかき立てる。ヘヴィなギターとスピード感も印象的な楽曲だ。ヴォーカルの表情も豊かになり、女性の多面性が歌だけでも大きく表現されている。彼女の脂の乗ったモードがそのまま音楽に投影された、非常にエネルギッシュで挑戦的なシングルだ。
-

-
LiSA
BRiGHT FLiGHT / L.Miranic
今年の1月には自身初の日本武道館単独公演を行い、来年の1月には武道館公演2daysが決定しているLiSAがリリースするノン・タイアップ両A面シングル。"PiNK"で"POP"な「BRiGHT FLiGHT」と、SiMのMAHが作曲を務め、編曲をakkinが担当した"BLACK"で"ROCK"な「L.Miranic」と、LiSAの持つ二面性がテーマになっている。キュートでありつつ人を巻き込むパワフルさを持つ前者と、醜い本音をぶちまけながらも自分の非を認めるという感情の揺らぎをラウドに昇華した後者。どちらにも彼女の積み上げてきたものや元来持つ表情がふんだんに詰まっている。自身が作詞作曲を務める等身大で素朴なアコースティック・ナンバー「東京ラヴソング」も含め"LiSA"という人間を克明に記す、リアルで体当たりな3曲。
-

-
Lisa Hannigan
Passenger
08年にリリースされた1stアルバム『Sea Sew』がマーキュリー・プライズとアイルランドのチョイス・ミュージック・プライズにダブル・ノミネートされるなど注目を集めたアイルランド出身の女性SSW、Lisa Hanniganの2ndアルバム。音楽的には大らかでどこか生々しさの残ったバンド・サウンドが主体で、ピアノやストリングスが時に華を添えながらも、常にそれぞれの楽器が主張し過ぎることなく自然と融和しながら、穏やかなメロディとLisaのハスキーな歌声に寄り添うように鳴っている。特別な派手さや奇抜さはないが、しっとりと、聴き手の耳と心に絡みつく音楽だ。たとえばEMMY THE GREATやSHARON VAN ETTENの作品ように、長く深く愛せそうな魅力に溢れた1枚である。
-

-
LISSY TRULLIE
Lissy Trullie
米ワシントンDC出身のLissy Trullie率いる4人組バンド。2009年にEPをリリースし好評価を得て、本作がデビュー・アルバムとなる。名前がそのままバンド名となっており、今作もセルフ・タイトルとなっている事実からもわかるようにLissyの存在感が突出しているが、今作にはソロではなくあくまでバンドとしての魅力が詰まっている。基本的に楽曲はポップでシンプルだが、ダーティーでロックな楽曲からナチュラルでポップな楽曲まで歌いこなす彼女の少しクセのある歌声はとても魅力的で、楽曲ごとの多彩なアレンジと相まって、独特で芸術性のあるものに仕上がっている。モデルとしても活躍しており、ファッション・アイコンとしても注目されている彼女のヴィジュアル面も話題で、今後の飛躍に大いに期待ができる。
-
-
LISSY TRULLIE
Self-Taught Learner
NYから登場した新たなガールズ・アイコン。モデルも務めるというスタイリッシュな佇まいの彼女から放たれる歌声は、エモーショナルとはほど遠いクールなものだけど、それでも僕らの胸をかき乱す。インディ・ロックという枠には収まり切らない確かなポップ・ポテンシャル、そしてたまらなくキュート。今ではあまり聴かれなくなった初期のTHE STOROKESを思い出すソリッドなギター・サウンドをよりキャッチーしたポップ・ソングがずらり。そして注目なのが、最後に収録されているHOT CHIPの「Ready For The Floor」の疾走感あふれるロック・カヴァー。原曲の良さと彼女の魅力を引き出した新たなキラー・チューン。
-
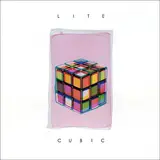
-
LITE
Cubic
インスト、マスロックと聞いて眉間にシワが寄るイメージを百万光年先にブン投げるほど痛快な、LITEの3年5ヶ月ぶりのアルバム。タイトルやアートワークにもあるように難解なルービック・キューブを笑いながら即座にクリアする少年性みたいな、突き抜けた楽しさやユーモアすら感じる。PCでできる創作も人間の脳や身体性には到底、敵わないのだ。唸るしかない音そのもののタフさ、生っぽいのに一切のノイズのなさがキャッチーなオープニング・ナンバー「Else」から、自然と楽しくなってしまう。まさに音が細胞を活性化させる。SOIL&"PIMP"SESSIONSのタブゾンビ(Tp)が参加した哀愁漂うLITE流スカあり、根本 潤が"音的"なヴォーカルで参加した「Zero」も楽しい。BATTLESのプロデューサーによるミックスも好相性。
-

-
LITE
Installation
絵画におけるインスタレーション、つまりどの絵を選びどんな配置でどんな空間で見せるか、と同じ意志で音をまとめられた4枚目のフル・アルバム。『For all the inoccence』「Past, Present, Future」で導入され始めたシンセなどのエレクトロな要素は、今のLITEにとっては生楽器と変わらぬ扱いだ。変な言い方だが自然(Nature)がナチュラルに複雑な要素から成立しているのと同様に。高速ギター・アルペジオが生き物のようにチェイスするキラー・チューン「Bond」、五臓六腑を揺るがすベース・ライン+ローズ+生ピアノのブロックがユニークな「Fog Up」、LITE流ファンク解体全書的な「Hunger」など多彩な10曲。でも出自はマスロックという端正さも魅力。「Between Us」などはJames Blake好きにもオススメしたい。
-

-
LITE
past, present, future
海外でも活動を行う、日本の4人組インスト・ロック・バンド、LITEのミニ・アルバム。ギター、ベース、ドラム、シンセサイザーがスクラムを組んで突進していくかのごとき、アグレッシヴなバンド・アンサンブルが聴ける。寄らば斬られそうな鋭さで刻まれるキメのフレーズが耳に残る。そして何よりも注目すべきはニューヨークのポスト・ロック・バンドMICE PARADEのCarolineを迎えたバンド初のヴォーカル・トラックである「time machine」と「arch」だろう。アグレッシヴな演奏とは違うスピードでゆったりとたゆたうように流れていくCarolineの透明感のある歌声が、この作品に収められたインスト曲にはないやわらかい空間を生み出している。
-

-
LITE
For All The Innocense
「人間と動物の関係性」――なんとも壮大なコンセプトのもとに形となったLITEの3rdアルバム『For All The Innocense』。次第に音の増えていく「Another World」は、音の積み重なりを越えた広義な意味での広がりとパターンを変えながらの反復が、重みのある緊張感を構築している。基軸にロックが据えられているが、随所にオリエンタルなサウンドやアフリカンな要素が散りばめられ、一方でジャズや70年代プログレが被さり、トライバルで無国籍な厚みが目立つ。非常に有機的に融合された音はいきいきと蠢き、螺旋を描くように立体的な音像を結ぶ。生物同士がしのぎを削りながらも、対峙しあう姿そのものだ。私たちもこの音の中に含まれていることを思う。
-

-
LITE
ILLUMINATE
東京を中心に活動しているインスト・ポストロック・バンド、L ITE がまた一皮むけた!プロデュースにJohn McEntireを迎えて、シカゴのSOMA STUDIOでレコーディングされたミニ・アルバムが到着。シンセなどを取り入れた前作の『Turns Red EP』から感じていたが、あらゆる音楽を取り込んで新たな世界観を形成していっている。従来のゴリゴリに尖ったサウンドにパーカッションやコーラスが融合し、深みのある音と音の結合力についつい酔いしれてしまう仕上がりだ。全体を通して、静かな幕開けから意外な結末を迎える、言葉のない物語のような音世界に圧倒。ちなみにジャケットのマラカスは実際にレコーディングで使用されたもの、とのこと。
-

-
littleAndy
サブカル
KANA-BOONやコンテンポラリーな生活らを輩出する大阪のロック・シーンで今、注目を集めている4ピース・バンド、littleAndyの2ndミニ・アルバム。一途に"君"を想うキュートな歌詞にほっこりする表題曲「サブカル」は変則的かつキャッチーなロック・チューン。実はこの曲、アイドルに片思いをした気持ちを歌っているという。やはりサブカル色の強いアルバムかと思ったが、田舎を思い出すような懐かしさ漂う「青春サイダー」や、"何回笑ってきたのかな あと何回笑えるんだろ 誰にも分からないから 君に会いに行くよ"と力強く歌い上げるラヴ・ソング「晴れのち雨でも」など多彩な6曲が並ぶ。"中毒性がある"と噂のライヴにもぜひ足を運んでみたい。
-
-
LITTLE BARRIE
Shadow
PRIMAL SCREAMのメンバーとしても知られるBarrie Cadogan(Vo/Gt)率いるLITTLE BARRIEのニュー・アルバム。3年ぶり4作目となる今作は、前作『King Of The Waves』と比べると、『Shadow』の名のとおり、全体的にやや落ち着いたダークなサウンドが印象的だ。ポップさが絶妙にそぎ落とされたぶん、1960年代のブルースに影響を受けてきた彼らの人間味すら感じ取れそうな独特なグルーヴが生まれている。これからの寒い季節によく合う、体の芯から温めてくれるようなじっくりと味わいながら聴きたい1枚である。今年6月に来日してくれた彼らだが、本作を引っ提げての来日公演も期待したいところだ。
-
-
LITTLE BARRIE
King Of The Waves
待ってました、LITTELE BARRIE!"帰ってきたロックンロール"などと有触れた言葉を吐きたくはないが、穏やかながらも確かなサウンドで彼らが再びそのエンジンに点火したことは一目瞭然だ。疾走感あふれるドラムに、曲を牽引するギターと土台を支えるベース。そして、シンセやオルガンの音が彩りを添える。ブルージーでUKロック全開なサウンドを全面に感じさせながらも、都会的な表情も失ってはいない。無論、この4年間の間にライヴを重ねてきた彼らにとってもはやジャンルなど無意味だ。古くはTHE BEATLESからTHE DOORS、さらにはBLACK REBEL MOTORCYCLE CLUBなどが入り乱れたようなサウンドが方々から押し寄せる。そして、あらゆるサウンドを"ロック"という熱い思いに回帰させ、生々しい熱さを閉じ込めることに成功している。『King Of The Waves』--サウンドの中、満ち溢れた熱に溺れてしまってもいい。
-

-
LITTLE BOOTS
Hands
昨年はADELEが一位を獲得した、BBC SOUND of 2009に選ばれた超大型新人LITTLE BOOTSことVictria Hasketh。ブラックプール出身の彼女は、5歳の頃からピアノに親しみ、後々シンセオタクとなっていくほど、鍵盤に愛情を注いでいる人だ。ネクストMADONNA、KYLIE MINOGUEなどと噂されているが、LITTLE BOOTSの音作りにはもっと手作り感があり、人間らしい温かみを帯びている。それこそがLITTLE BOOTSの大きな魅力なのだ。透き通った歌声と、キラキラとしたスペーシーなエレクトロ・ポップ・ソングの数々は、玄人から大衆までの心をがっちりと掴むだろう。LILY ALLENを手がけたGreg Kurstinがプロデュースに名を連ねているのも納得。尚、彼女の愛器は「メイド・イン・ジャパン」ヤマハのテノリオン。今年のSUMMER SONICは、LADY GAGAとセットでチェックすべし!
-

-
LITTLE DRAGON
Ritual Union
日系スウェーデン人のYukimi Naganoは、SBTRKTやGORILLAZの楽曲に参加する売れっ子アーティストだ。そんな彼女のけだるいヴォーカルで幻想的な世界を描いてきた、Nagano率いるプロジェクト、LITTLE DRAGON。3rdアルバム『Ritual Union』では、非常に意欲的な境地に足を踏み入れ、80年代を彷彿とさせるチープなエレクトロ・サウンドを基軸に、さまざまな毛色の音を入れ込み、より実験的に仕上げた。北欧のドリーミー・サウンドを奏でるバンドと言うとMUMが真っ先に思い浮かぶのだが、LITTLE DRAGONはこれまでの"ドリーミー"とは一線を画している。不思議な中毒性を持ったNaganoのヴォーカルは、前2作と比較して艶が増し、非常にソウルフルで生き生きとした呼吸を感じさせる。既成概念にとらわれない夢のようでいながら"生きた音"として音像を再現するのだ。内から湧き出る感情が鮮やかに迸る。"結婚式"なんてタイトルも実に小粋だよね。
-
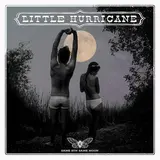
-
LITTLE HURRICANE
Same Sun Same Moon
スパニッシュなものからハードコアまで、アメリカを代表するリゾート地 サンディエゴ産の音楽は多様性を極める。そんな土地から最小人数で最大のロックンロールを爆発させているのが男女デュオ LITTLE HURRICANEだ。しゃがれたヴォーカルとファズの効いたギターを操るAnthony"Tone"Catalano、フォトジェニックな容姿とラウドなドラミングが最高にキュートなCeleste"CC"Spinaの組み合わせはヴィジュアルからして強烈なインパクトを残すはず。60年代のアメリカン・ブルースの現代版と比喩されそうな今作は、ハードとソフトなサウンドを使い分けることで、曲それぞれにドラマチックな要素を付加させている。巷ではTHE WHITE STRIPESの再来と言われてるらしいが、そんなクリシェ、このアルバムで塗り潰してしまえばいい。
-

-
LITTLE JOY
Little Joy
海岸沿いにあるバー、いや、お洒落にバールとでも言ってみようか。夕焼けも薄くなって、ほとんど夜の闇に覆われかけた夕暮れ時に、そのバールのテラスに並んで海を見つめるカップル。テーブルには、フルーティなオリジナルカクテル。実際にそんな場面を目撃したら、アホか、と突っ込みたくなるようなシチュエーションだが、そんな感じが似合いそうなアルバムである。THE STOROKESのドラマー、Fabrizio Morettiによる新ユニット、LITTLE JOY。メンバー3人で楽器を持ち替えながら、鳴らされるのは、トロピカルなフォークミュージック。THE STOROKESとしての重責から一時離れ、リラックスして、音楽を楽しんでいることが伝わってくる、心地よいレイドバックミュージック。サイドプロジェクトらしい作品だ。
-
-
Little Parade
感情特急
約1年ぶりとなるミニ・アルバムには全5曲を収録。軽快で賑やかな「最後の友人」では創作する日々の葛藤が滲み出ていたり、躍動感とまどろみ感たっぷりに繰り広げられる「煩悩グラインド」では、便利になっているのにどこか心が満たされないある種の現代病を描いていたりと、太志の視点を通しながらも、今を生きる多くの人たちの毎日の生活の中でふとした瞬間に湧き起こる感情や感覚に寄り添う言葉たちが、柔らかく、丁寧に紡がれている。物憂げなピアノから始まりながらも、徐々に視界が開けていくかのように景色が鮮やかに色づき、ドラマチックに広がっていく「感情ターミナル」で始まり、喪失感を抱えながらも、前に進んでいく姿を美しい歌声で紡いだ「晩秋のトロイメライ」で締めくくる流れも見事。
-

-
Little Parade
藍染めの週末
元Aqua Timezのヴォーカル、太志が立ち上げたプロジェクト Little Parade。今年1月に発表した初のCD作品から約10ヶ月で早くも2ndミニ・アルバムが到着。楽器隊が放つグルーヴや、アコギの音を押し出したアンサンブル、そして太志が響かせる伸びやかなロング・トーンが瑞々しい景色を描いていく「風の斬り方」や、シリアスでありながらも美しさを伴った「置き去りの鉛筆」、ジャズ・テイストで渋みのある「501 with oneself」など、様々なサウンドを繰り広げているが、耳心地のいいメロディと、日常の些細な場面やモヤモヤを掬い取り、気づきや彩りを与えていく言葉たちが、彼の音楽の核にあることを改めて知る全6曲。初の自伝エッセイ"ほんとうのこと"も同封。
-

-
LITTLE RED
Midnight Remember
まず息を潜めて最初の4曲を聴いて欲しい。すると感じるはず、今作には体も心も、大人でも子供でもない15 歳ぐらいのあの時に感じていた恋愛や不安や喜びなどの甘酸っぱいヴァイヴがはちきれんばかりに充満していることが。オーストラリア出身の五人組、LITTLE RED のデビュー作は、COLDPLAY のような透明感&浮遊感のあるポップと、THE VIRGINSなどを髣髴とさせる緩いノリのディスコ・ロック、MAROON5 のような甘いR&Bなどを参照点として、心擽るメロディを奏でる耳に優しいポップ・アルバムになっている。ただその参照点を未成熟な少年の視座から解釈したような、垢抜けた音楽を垢抜けない思春期の子供達が背伸びして演奏しているような、そんな雰囲気が出ていて最高にキュート。このバンド、愛さずにはいられないです。
-

-
LOCAL CONNECT
NEW STEP
フィジカル盤としては『未完成』から約2年ぶりとなる初のアルバム・リリース。バンド主導の再スタートを切った心機一転のムードを象徴するように、今まで以上に自由なアプローチで完成させた全9曲だ。エレクトロなサウンドを大胆に取り入れた「Hands (Album Mix) 」や、「ANSWER」をはじめ、跳ねるグルーヴにゴスペル風のコーラスを乗せた「2DK」など、"泣けるロック"なイメージを刷新する楽曲も含まれる今作だが、相変わらずローコネらしいと思えるのは、人間臭い感情がまっすぐに歌われているから。寄り添うのではなく、聴く人が新しい一歩を踏み出すための力になれたら。そんな覚悟を持って紡がれる歌詞からは、愛の中で生きるというバンドの揺るぎないメッセージが浮かび上がる。
-

-
LOCAL CONNECT
未完成
ミニ・アルバムとしては約1年8ヶ月ぶりとなる本作。曲の数だけ表情を変えていた前2作に対し、今回はタイトルにある"未完成"にテーマを統一。そのワード自体が"まだまだこれから"と意気込む彼らの象徴でもあるため、全体的に歌詞はドキュメンタリー色が強く、音作りも"歌を遠く広く届ける"という方向性に。その結果、ISATOとDaikiのツイン・ヴォーカルを始めとした、バンドが元来持っていた個性が大いに生きていたり、"大阪城ホールでワンマン開催"という当初から掲げていた目標に接近するような音像になっていたりと、いよいよ手段と目的が一致してきたような印象だ。メンバー自ら本作を"第一歩"と称しているのはおそらくそのためだろう。地面をグッと踏みしめたなら、あとは高く翔ぶのみだ。
-

-
LOCAL CONNECT
スターライト
京都府出身&在住の5人組の約1年ぶりとなるリリースは3曲入りシングル。2ndミニ・アルバム『7RAILS』は歌を主軸に様々な音楽性を取り入れていたが、今作はシンプルなギター・ロック・アレンジが際立つ。Track.1はISATO(Vo)が作詞、Daiki(Vo/Gt)が作曲を担当。ソフトなツイン・ヴォーカルを、夜空の下を駆け抜けるような清涼感と切なさのあるサウンドが、"僕らの光を受け、あなた自身も誰かを照らす光になってほしい"という気持ちを混じり気なく伝えている。Track.2は鼓舞するようなパワフルなロック・サウンド、Track.3はあたたかい音色が優しく包み込むミディアム・ナンバー。どの楽曲もまっすぐ聴き手の心に向けて届けられている。
-

-
LOCAL CONNECT
7RAILS
昨年6月にメジャー・デビューを果たした京都府長岡京発の5ピースの2ndミニ・アルバム。前作が誠実で爽やかな好青年のイメージならば、今作は男気が溢れる筋肉質な男子のような印象だ。その理由のひとつはISATOとDaikiという2名のヴォーカリストのアプローチの変化。両者ともルーツがブラック・ミュージックゆえにヴォーカリゼーションに共通する部分は多かれど、今作はそれぞれの個性が前作よりも濃く出ているため、ふたりがぶつかり合うようなインパクトも多く見られる。楽器隊も前作以上にフレージングにギミックが加わり、アンサンブルにも強固な安定感が生まれた。アッパーな骨太ロックやダンス・ナンバー、繊細なミディアム・テンポ、ファンク・ナンバーなど、バンドの伸びしろを感じる。
-
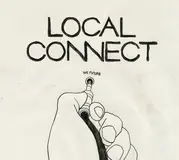
-
LOCAL CONNECT
過去ツナグ未来
前身バンドのメンバー・チェンジを経て2015年に始動した、京都は長岡出身のツイン・ヴォーカルを擁する5人組、LOCAL CONNECTがメジャー・デビュー。今作は前身バンド時代の楽曲から最新のものまで、すべてを現在のメンバーで録音している。サウンドの真ん中にあるのはISATOとDaikiのツイン・ヴォーカルだが、単純な歌モノで終わらない楽器隊のアンサンブルがダイナミックに響いてくる。すべての楽器が歌をより引き立てる緩急のあるサウンドを恐れることなくまっすぐ鳴らすのは、バンド内の熱い信頼関係の証だろう。アッパーで強固なバンド・サウンドの中に遊び心のきいたアレンジを投入するTrack.2、心あたたまるバラードのTrack.6など、可能性を感じさせる7曲が揃った。
-

-
LOCAL NATIVES
Sunlit Youth
前々作『Gorilla Manor』が全米160位だったことを考えれば、前作『Hummingbird』の全米12位がいかに大きな飛躍だったかがわかるだろう。だがその反面、それが大きなプレッシャーにもなったようで、3年ぶりとなる新作は、周囲の期待を一旦忘れて、自分たちが聴きたい曲を作ったという。2010年代前半のUSインディー・シーンの空気を決定づけたバンドのひとつに数えられるロサンゼルスの5人組。彼らの存在を特徴づけていたトライバルなリズムやエスニックなフレーズには頼らず、ここでは曲そのものの魅力で勝負しようとしているようだ。それがUSシーンを代表するバンドに相応しいスケール・アップに繋がった。演奏のテンポを抑えながら、最後まで持続する緊迫感も大きな聴きどころだ。
-

-
LOCAL NATIVES
Hummingbird
ロサンゼルスのシルヴァー・レイクを拠点に活動する5人組インディー・バンドLOCAL NATIVESの2ndアルバム。THE NATIONALのAaron Dessnerをプロデューサーに迎え、彼のスタジオでレコーディングされたという今作は、DIY精神をそのままに作り上げたデビュー作である前作『Gorilla Manor』よりも格段にその楽曲の持つ空気を研ぎ澄ましている。音に対して自由に何でもトライしたということもあり、サウンドの開放感と深みは増し、繊細なヴォーカルはよりその淡いラインを美しく映し出す。カラフルな印象が強かった前作に比べるとひとつひとつの色味は弱いかもしれないが、引き算により浮き彫りになった音像には大きな豊かさを感じることが出来る。まさしく"洗練"の1枚。
-

-
LOCAL NATIVES
Gorilla Manor
LA出身のニューカマー。FUJI ROCK FESTIVALにも出演が決定し、某レコードショップでも猛プッシュされていたのでご存知の方も多いかも。海外では今年2月にリリースされ、全米ビルボードでニューアーティスト・チャート3位にランクインするなど海外メディアでも大注目の彼ら。スウィート・アコースティック・サウンドと呼ばれる様にフォーキーな音色と美しいコーラス・ワークが彼らの魅力。ヴォーカルが3人もいてライヴでは4人で迫力ある歌声を響かせる。今作はアフロ・ビートも取り入れ軽快で爽快感溢れるナンバーもあり、しっかりとトレンドを押さえた内容。透明感あるメロディもさることながら、切れのあるドラムも聴き所だ。
-

-
LONE×ジラフポット
Black's ONE
白熱のパフォーマンスで関西のライヴ・シーンを沸かす2バンドのスプリット作。収録曲は、衝動と美しさが絶妙に入り混じるジラフポットの「Back Stab」と、歌を聴かせつつライヴ映えするLONEの「スプリットシングル」、そして共作となる「Black's ONE」。ジラフポット中野大輔(Gt/Vo)がベースとなる曲を作り、LONE山本浩之(Dr)が編曲、LONE牛首(Ba)が歌詞を作り、中野とLONE毛利翔太郎(Vo/Gt)がメロディを持ち寄って完成させた「Black's ONE」は、耳馴染みの良さと疾走感とスケール感が見事に共存し、アンセミックなコーラスを背負ったシャウトは爽快感も抜群だ。また、毛利には山本が、中野は自身でペイントとしたというジャケ写のふたりにも注目を!
-

-
LONE
ラウンドエンドランドリー
大阪を拠点に活動する4人組ロック・バンドがTOUGH&GUY RECORDSからリリースする1stミニ・アルバム。中学時代に結成された初期メンバーに戻って初めての音源、初の全国流通盤CDということもあり、新曲と既発曲の7曲で構成された自己紹介的な作品となっている。ドラマチックな展開で物語のように聴かせる「マリッジグルー」、毛利翔太郎(Vo/Gt)のハイトーンな歌唱が胸に迫る「エンドロール」など、歌メロの良さと文学的な歌詞、各プレイヤーの演奏と、三位一体となって感情を揺さぶる曲が並び、ライヴでもラストに演奏されることが多いという「幸福の奴隷」の余韻が長く心に残る。竹家千十郎(Gt)が謎のカスタム・ギターから繰り出す縦横無尽なフレーズにも注目。
-

-
THE OLD CEREMONY
Sprinter
Django Haskins率いるアメリカ・ノースカロライナ州出身の5人組ポップ・ロック・バンドの6枚目となるアルバム。軽快な弦楽器の音で始まりながらも緊張感のある表題曲「The Sprinter」から、「Magic Hour」「MissionBells」といった曲や物語が終わっていくようなエンディングの「Go Dark」まで、各楽器が醸し出す妖しげなムードと耳触りの良いヴォーカル、徐々に熱を帯びていく演奏は秀逸。若干曲の展開にワン・パターンさは感じるものの、いろいろな楽器のアンサンブルを楽しみつつライヴ感のある音楽を聴きたい方、BELLE AND SEBASTIANなどがお好みの音楽ファンにはおすすめしたい。R.E.M.のベーシストとして知られるMike Millsがヴォーカルとベースでゲスト参加している。
-

-
Long Tall Sally
Beg
2006年に地元・鳥取で結成され、地元で仲間とレーベルを設立、クラブを開業するなど独自の活動を行うLong Tall Sallyの、前作にあたる2ndフル・アルバム『Believe』から約10ヶ月振りとなる7曲入りミニ・アルバム。THE BEATLES直系のシンプルかつコンパクトで奥行きのあるサウンドは、音楽が鳴る空間をすべてパッケージしている。ゆえにどの音も瑞々しい音色で、どの曲もふかふかのベッドのように心地よい。メランコリックでもありながら優しさやあたたかさを含み、ひとつひとつのフレーズに余韻が残る。聴き手の精神状態で印象が変わる、聴き手の心や生活に寄り添うアルバムである。人と向き合う気持ちから生まれる、等身大の人間の想いそのものの音に、忘れていた大事なことを思い出す心地だ。
-

-
LOS CAMPESINOS!
Sick Scenes
前作から約3年、デビュー以来、バンド史上最も長い制作期間を経てリリースされる通算6枚目のアルバムは、昨年開催された欧州サッカー選手権"UEFA EURO 2016"開催中にレコーディングされたという。バンドの地元カーディフがある初出場のウェールズ代表が好成績を残すなか、どこか重々しい雰囲気を纏った楽曲が並ぶ理由は彼らを取り巻く政治情勢のせいかもしれない。それでも、英国産インディー・ロック特有のパンキッシュさが弾けたTrack.2や、ムーディなコーラス・ワークを堪能できるTrack.5など、活気と色気に満ちたバンド・アンサンブルは今なお健在。10年以上バンドを続けているからこそ訪れる心境の変化を結晶化した、ネクスト・ステージへ向けた渾身の1枚。
-

-
V.A.
Arts & Crafts 2003-2013
"役に立たないもの、美しいと思わないものを家に置いてはならない"民芸運動(アーツ&クラフツ)の父、William Morrisが生活と芸術の密接な関係を提示し、アート の未来を一変させた様に、2000年トロントの小さなベッドルームで誕生したインディー・レーベルArts & Craftsもまた、音楽の風景を変えてしまった。BROKEN SOCIAL SCENEや、LOS CAMPESINOS!、数え歌ソングで有名なFEISTなど、アコースティック・サウンドを基調とした、生活に馴染む人肌のポップ・ミュージックを提供してきた彼 らの歩みはそっくりそのまま、昨今の全世界的なネオ・フォークの流行に繋がっている。今、我々が求めて止まない温かな響きの1つの源泉がここにある。
-

-
LOS CAMPESINOS!
Romance Is Boring
前2作でおもちゃ箱をひっくり返しながら遊ぶ子供のような無邪気なポップ・ソングを鳴らしたウェールズの男女7人組LOS CAMPESINOS!。彼等の持ち味であるポップネスをしっかりと保ちながらも、前2作とは異質の鬱屈を吐き出しながら転がっていく今作。胸をかきむしられるようなオルタナティヴ・サウンドには、瑞々しい若さから一歩進み、焦燥感と「生と死」といった重たくのしかかってくる哲学的命題に向き合う若き知性が噴出している。時にポップに駆け回り、時にヘヴィなサイケデリアに溺れる幅広さと奥行きからは、分裂症気味に躁鬱を繰り返すある種の混乱すら感じられる。しかし、それでも彼等はポップであろうとする。そのせめぎ合いが、聴く者の胸をざわつかせるダイナミズムを生み出している。
-
-
LOS LOBOS
Tin Can Trust
ルーツであるヒスパニックからラテン、ファンクを咀嚼した骨太なロックで、36年というキャリアを築き上げるLOS LOBOS。この人達を「La Bamba」の陽気なおじさんってだけで終らせちゃ勿体ないんですよ。どっしりと腰の据わったグルーヴと、酸いも甘いも噛み締めた年輪の太さを感じさせる歌心。「Yo Cant」のラテン・ロック、「Mujer Ingrata」のトラッドが持つ陽気なノリは、この人達にしか出せないでしょう。時代に左右されず、我が道を進み続けたがゆえの間違いないグルーヴ。泣きのギターも胸にしみ込んできます。もはや伝統芸と呼べる豊潤な音楽でありながら、新鮮に楽しめるその音楽性の高さにただただ感服。


























