DISC REVIEW
E
-

-
ELIZABETH.EIGHT
ASK YOU!!
昨年、ヴォーカルのミワユータが病気からの復帰を遂げたELIZABETH.EIGHTの通算6枚目となるアルバム。脳炎で緊急入院して一時は後遺症に悩まされ音楽への復帰は絶望的だったというのが信じられないほど、力強いヴォーカルを聴かせている。サウンド面ではキーボードが加わったことで直情的なガレージ・サウンドにサイケ、グラム・ロック的な色っぽさが加わっており、ロカビリーチックな展開にピアノが艶を与える「ヘブンズ・イン・ザ・バッグ」にはその変化が如実に表れている。同曲に急性骨髄性白血病により療養中の深見之春(Gt)が参加しているのはファンにとっては嬉しいトピックだ。バンドが過ごしてきた月日への思いが凝縮されたようなラストの「冒険の書」は、強い意志で前を向いてきたバンドだからこそ歌える感動的な曲。
-

-
ELLIOT.C
the sun leading to my futures
08年に大阪にて結成された、尾上旭と岩井善崇による二人組ユニット、ELLIOT.Cの1stミニ・アルバム。90年代初頭のオルタナティブ・ロックへの愛を感じる、重厚でノイジーなサウンドと、繊細なメロディが詰まっている。ツイン・ギターであることをフルに活かしており、ところどころに面白いコードの重ね方をしているのが印象的。岩井の歌は力強く逞しいが、個人的には美しいバラード「儚光」で見せてくれている情感豊かな表現に一番魅力を感じた。DINOSAUR JR.とDEEP PURPLEがキーとなっている作品ということであるが、くるりやアジカン好きの邦楽ロック世代から、今後大きな人気を獲得することだろう。11月には、ELLIIOT.C企画の<ELLIFEST>が開催される。
-

-
ELLIOTT SMITH
An Introduction to Elliott Smith
昔はBob Dylan だったと思うが、現在20歳代の僕達の世代にとって、体に染み渡るアコースティック・サウンド&か細く美しい声とメロディでアコースティック・ギターが1本あれば何だって出来るということに初めて気付かせてくれたのはこのElliott Smith だった。彼の死後、7 年ぶりに発表されるこのベスト・アルバムには、生前に発表された5 枚のアルバムと死後に編集された2 枚のアルバム、計7 枚からの選曲になっていて、初めて彼の音楽に接する人にとっては絶好の入門盤であり、ファンにとっては様々な時期の彼を対比して聞ける楽しみ方もできるだろう。フォークを更新したと言われるTHE NATIONAL やSfjan Stevens などが評価されている今、黙々とフォーク・ミュージックを更新し続けた彼の功績はその大きな礎となっているだろう。
-

-
EL PERRO DEL MAR
Love Is Not Pop
ベリー・ショートにばっちりアイラインの入った大きな目、ボーダーのシャツ…これはもうフレンチ・ポップ炸裂かと思いきや、スウェディッシュ直系の独自の浮遊感を帯びた音がスローモーションのように流れ込んできた――。スウェーデン発の女性シンガー・ソング・ライターSarah Assbringによるソロ・プロジェクトEL PERRO DEL MARの最新作。Kate Bushを彷彿とされることが多いアーティストのようだが、それも納得。水面下で囁くような、妖艶なヴォーカルは、愛らしい色香を放ち、しなやかな曲線美と少女のあどけなさの両面を兼ね備える。捉えどころのない魔性の魅力を、彼女もまた持っているのだ。そんなヴォーカルと、いくつもの音が重なり合う耽美的なサウンドが混ざり合い、優雅に鳴り響くのもまたフェミニン。
-

-
EMERALDS
Does It Look Like I'm Here?
06年に結成されたアメリカのオハイオ発スリー・ピース・バンドの通産3枚目のアルバム。メンバーは全員20代前半。だがその作り込まれた音の構成は非常に成熟しており、研究に研究を重ねたベテラン科学者の発明品さながらの緻密さを誇る。煌びやかな70年代風アナログ・シンセ・サウンドと一癖あるギターが絡み合って作られる抒情的なメロディとノイズ、そのスケール感に拍車をかける重厚なベース音。洗練された電子音がひたすら頭の中を旋回し、どんどん思考能力は奪われてゆく。計算し尽くされた巧妙な精密機械の中を覗いていくとどんどんその中へ迷い込んでしまうような、はたまた宇宙の奥の奥に広がる未知なる世界に侵されてしまうような――異次元に連れ去られること必至の1枚。
-

-
Emiliana Torrini
Tookah
映画『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』のエンディング・テーマに起用されるのみならず、現代のディーヴァ、Kylie Minogueに提供した曲がグラミーにノミネートされるなど、じわじわと注目度がアップしているアイスランドの女性シンガー・ソングライター。日本ではクラムボンが彼女の曲を取り上げたことで、彼女のことを知っている人もいるのでは。その彼女が5年ぶりにリリースしたアルバム。ソングライターという意味ではトラディショナルな資質の持ち主と言えるが、オーガニックとエレクトロニックの幸福な出会いを思わせるサウンドは神秘的という言葉さえ連想させる。そんなサウンドと平熱が低そうなコケティッシュな歌声が漂わせるひんやりとした空気と、その中にほのかに感じる温もりがなんとも心地いい。
-

-
エミ・マイヤーと永井聖一
エミ・マイヤーと永井聖一
日米で活躍するシンガー・ソングライター、エミ・マイヤーと、相対性理論のギタリストであり、それ以外にも様々な幅広い活動を行う永井聖一がユニットを結成。全編日本語詞のアルバムを完成させた。制作期間は約2年。作詞と作曲はそれぞれが書いたものもあれば2人の共作もあり、Track.6はたむらぱんが作詞で参加していたりと、シンガーとしてのエミをよりじっくりと解き放ったポップ・ミュージック集だ。肩肘張らないリラックスしたバンド・サウンドに、英語と日本語両方の感触を与えるエミのヴォーカル。永井のギターは曲の雰囲気にあわせて変幻自在にアプローチをするも、どの曲でも音の魅力を存分に引き出すシンプル且つ印象強いフレーズを奏でる。エミの新たな表情を見られる楽しみと同時に、永井のギタリストの才能に恐れ入った。
-

-
EMMY THE GREAT
Virtue
驚くべきことに、冒頭曲「Dinosaur Sex」は原子力発電所から漏れ出した放射能の影響で荒れ果てた未来を描いている。当然、時期的にこの楽曲が福島の原発事故をモチーフにしたものではないが、このリアリティはあまりにも重く響くだろう。UK新世代フォーク・シーンの歌姫、EMMY THE GREATの2ndアルバム。やはり今作も純粋に作りたいものを作るという彼女ならではDIY精神があり、アルバム制作はファンから制作費を募るファンド形式で行われた。サウンドはシンプルに、前作のままフォーキーなトーンで構築し、神話やおとぎ話を現代に織り交ぜた詩世界が歌われているというが、上記のエピソードが物語るように、これはぜひとも対訳を読みながら反芻するように味わってほしい。そして、あなたの“virtue(美徳)”を考えてほしい。
-
-
EMMY THE GREAT
First Love
香港生まれで、ロンドン育ちの日系ハーフEmma-Lee Mossのソロ・ユニットであるEMMY THE GREAT。素朴なフォーク・サウンドによるぬくもりのある楽曲と、キュートなルックスで、急速に人気を獲得していく。そのエヴァーグリーンな歌声はLightspeedChampion「Galaxy Of The Lost」、THE BPA「Seattle」などでデビュー前からフィーチャーされるなど、ミュージシャンからの支持も厚い彼女。その確かなソング・ライティング能力は、「Dylan」のようなアップ・テンポの楽曲だけでなく、シンプルな弾き語りであっても、聴き手の耳を捉えて離さない魅力を備えている。そのセンスの良さが発揮された、日々のサウンドトラックとも呼べそうなキュートなフォーク・アルバム。
-
-
THE ENEMY
Streets In The Sky
正直、THE ENEMYの新作にここまで心動かされるとは、我ながら驚きである。ファーストの時点では、その社会派ラッド気質には惹かれるものがあったものの、ソングライティング自体は凡庸に思えたし、セカンドでも、その強い政治的問題意識には敬意を払ったが、そのスケール感を増したサウンドにはあまり馴染めなかった。だが、サードとなる本作には、聴くたびに涙腺を刺激されまくっている。シンガロングなメロディを備えたロック・サウンドに、日々の生活の喜怒哀楽をロマンティックに描いた歌詞を乗せた全12曲。そんな、なんてことないシンプルなアルバムなのだが、こんなにも普遍的な喜びと悲しみを説得力と共に歌い上げることのできるバンド、今やそう簡単にいるわけではないのだ。
-

-
ENO・HYDE
High Life
Brian EnoとKarl Hyde(UNDERWORLD)による2作目の共演アルバムがリリース。これが前作『Someday World』から、わずか2カ月でのリリースとなる。『Someday~』でやり残したアイディアを更新しながら、新しい形にしていった今作は、準備に約2週間、録りに5日間というスピードで行なわれた。実験を重ね構築したサウンドは緻密でいて、かつシンプル。必要最低限の音で、鮮やかで奥行きのある空間を生みだしている。エクスペリメンタル・サウンドでありつつ機能美という言葉もはまるような感覚。両者ともに長いキャリアがあるけれど、次から次へと湧くアイディアを、互いに触発し合い面白さを何倍にも増幅させて、"コラボレーション"の高いテンションを大事にしている。その熱量を瞬時にパッケージしたアルバム。
-
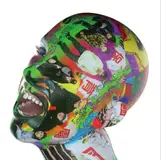
-
ENTH × SPARK!!SOUND!!SHOW!!
#ワイタイスカッ
鳴らす音楽は違うものの、その"ヤバさ"と"イマ感"は大いに共通するところがあるENTHとSPARK!!SOUND!!SHOW!!がタッグを組んだ5曲入りのスプリット・アルバム。2バンドの共作曲「#ワイタイスカッ」は、いつもはそれぞれのベクトルに向かっているエッジとユーモアが交差し、(歌詞も含めて)ぶっ飛んだ仕上がりになっている。他にも、お互いのメンバーをフィーチャーした楽曲あり、それぞれの新曲もあり。バチバチ戦うだけではない、楽しく慣れ合うだけでもない、危険物質の配合を変えながら次々と化学実験をやっちゃって、めくるめく新しい世界を差し出してくる、みたいな、昨今のロック・シーンでは貴重とも言えるスプリットならではの醍醐味が炸裂した1枚になっている。
-

-
ENTHRALLS
TEXTURE,MOISTURE
2013年から1年に1枚、計3枚のミニ・アルバムを制作し、3部作を完成させた彼女たちのネクスト・フェーズとなる1stフル・アルバム。作品のテーマは"質感"と"潤い"で、これまでの作品と比較してもポジティヴィティに溢れ、ピアノ・ロックの概念に縛られないゆとりのある伸びやかなサウンドになった。太さのあるファルセットによるハイトーン・ヴォーカルは今作のサウンドスケープとの相性も抜群で、以前よりさらに歌、歌詞、メロディの輪郭が鮮やかに。J-POPとしても成立するものになっている半面、ピアノの音色を残しながら各楽器が楽曲ごとに異なる音色を作るところや、奔放なリズム・セクションで構成されたTrack.7など、コアな手法をあくまでさりげなく用いてくるところも小粋だ。
-
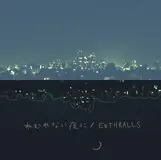
-
ENTHRALLS
ねむれない夜に
夜は孤独で苦しい時間。だが、夜ほどやさしい時間というのも存在しないのではないだろうか。劇場型ピアノ・ロックを掲げて活動するENTHRALLSが"ねむれない夜"をテーマに制作した3枚目のミニ・アルバムでは、無駄を削ぎ落とし洗練されたダイナミックなサウンドが打ち出される。ある種のシンプルさを志向しているものの、その音に自然と惹きつけられるのは、確かな技量に裏打ちされた演奏にそれぞれの強い思いが込められているからであろう。今作の核を成すのは、魂を奮い立たせるドラマチックでスケール感のあるTrack.4。COLDPLAYの楽曲にも通じる力強さを感じさせ、聴く者を包み込み肯定するこの楽曲は、今の彼らのすべてが詰め込まれた新たなスタンダードとなるはずだ。ここまで様々な音を吸収し表現してきた彼らが、進むべき道を見定めた今、次の作品こそが本当の勝負作となるであろう。
-

-
THE ENTRANCE BAND
The Entrance Band
グルーヴィで力強いロック・サウンドとサイケデリックで魅惑的なサウンドを持ち合わせたロック・バンドTHE ENTRANCE BANDが日本デビュー。元々フリー・フォークを作っていたバンドのリーダーGuy Blakesleeのソロ・ユニットであったENTRANCEに強力なリズム隊が加わりトリオへ変身。それによってブルージーなバンド・サウンドへシフト。最近のサイケデリック・ブ-ムの音というよりはLED ZEPPELINにも通ずるようなハードなブルース。変態的なギター・プレイとタイトなドラムがこのバンドの魅力の一つだろう。振り切れたようなヴォーカルもまたいい。SONIC YOUTHのThouston Mooreもお気に入り。ちなみに今年のFUJI ROCKにも出演が決定してます。
-

-
Equal
SCAPE
人気歌い手の"りょーくん"ことRYOTAが、VOCALOIDクリエイターの"164"と結成したロック・ユニット&バンドの初作品。ラウド寄りの力強いエモーショナルなギター・サウンドを基調に、シングルでありながら様々な音楽性を魅せる。Track.1はEqualとしての第一歩だという気持ちが明確に出た楽曲。力強くも焦燥感のあるギターがまっすぐ疾走し、"この手で大きく掴むんだ"という言葉により説得性が生まれている。Track.2はピアノの入ったマイナー・キーが効いたミディアム・ナンバーで、164の持つ繊細な側面が滲む。RYOTAのクリーン・ヴォーカルはメロディの良さを引き立てることに長けており、オケとの親和性も高い。バンドとしての第一球らしい、エネルギッシュなシングルだ。
-

-
ERASURE
The Neon
80年代から活動を続ける、Andy Bell(Vo)と元DEPECHE MODEのVince Clarke(Key)によるエレクトロ・ポップ・デュオが、実に18枚目となるアルバムをリリースする。想像上に存在する、光り輝く場所をイメージして制作されたという今作は、そのタイトルの通りに明るく温もりのある作風に仕上がった。軽快なリズムに乗せてピースフルなヴォーカルが響くTrack.1、ホーリーなメロディが印象的なTrack.7と、フロアの光景が脳裏に浮かぶダンサブルできらびやかなシンセ・ポップが収められている。ピアノ伴奏でソフトに歌い上げるバラードのTrack.8も絶妙。コロナ禍を受け、世界や人々の心からもネオンの灯りが消えつつある昨今だからこそ聴きたい1枚だ。
-

-
erie
トロイメライ
前作『erie』から半年で届けられた2ndミニ・アルバム『トロイメライ』。今作は制作が前作とほぼ同時進行で進めていたということもあり、正直バンドの明確な革命や進化を提示する作品ではない。しかし彼らの持ち味である叙情的でエモーショナルなサウンド、繊細な世界観は更に深く表現されており、人間という強く弱い生き物をerieとしてしっかりと描いた生々しさに満ちたミニ・アルバムになっている。結成当初に作られたという「枯花」は、結成時の衝動とバンドの成長が合致したまさに今のerieの名刺代わりになる楽曲。そして「最初の喪失」の狂気すら感じるサウンドはこのバンドの類稀なるポテンシャルを滲ませる。形骸化した“エモ”に警鐘を鳴らすフィジカルな作品だ。
-

-
erie
erie
2009年より活動を開始した5人組エモ・ロック・バンドerieのデビュー・ミニ・アルバム。まるで人間の喜怒哀楽のごとく激しく変化するサウンドと歌で貫かれた世界観はRADWIMPS meets envyと称されている。それは2010年にRO69JACK(ロッキン・オン主催オーディション)にて入賞を果たすキッカケとなった「hope」を聴けば納得して頂けるだろう。静寂と轟音の見事な使い分けと壮大な音像を表現する演奏力は、もはやエモ系という言葉だけでは説明できないほどのオリジナリティに満ちている。そしてバラード曲である「e.」からはバンドとしての音楽性の幅広さと深みも垣間見える。音楽に対する熱い思いと真摯な姿勢がストイックなまでに詰め込まれた力作。
-

-
ERRORS
Have Some Faith In Magic
MOGWAIの主催するレーベルRock Actionに所属する、グラスゴーの3ピース・バンドERRORS、3枚目となるオリジナル・アルバム。これまでインストを主体に音楽製作をしてきた彼らだが、今作では積極的にヴォーカルを取り入れている。とは言え、いい意味で一般的な歌モノとして落ち着いていないところはさすがインスト・バンド。生楽器の音の中にたゆたうヴォーカルとコーラスの、吐息を感じさせる温度が心地良い。ポスト・ロックに括られることも多い彼らだが、何重にも重なる繊細で軽快なシンセ・サウンドが浮遊感を生み、ロックよりはポップの要素が強いところも特徴だ。決して派手な音作りではないがその堅実な歩みには大きな安心感がある。ちょっぴり怪しい、だけど優しい。不思議な森に迷い込むようなアルバム。
-

-
ESBEN AND THE WITCH
Violet Cries
ひっそりと、真夜中に繰り広げられる魔女たちの舞踏会。その優美な舞いに魅せられたら最後、深く、冷たく、艶やかな闇に包まれ、どこまでも沈んでいく……そんなスリルが堪らない。“聴く”というより、“浸る”という表現がピッタリのナイトメア・ポップだ。英ブライトン出身、BBC Sound Of 2011にも選出された期待の3ピース、ESBEN & THE WITCHのデビュー・アルバム。ネーミングはデンマークの昔話から取ったそうだが、ミステリアスでダークな世界観には納得の由来だ。まるでBEACH HOUSEの官能的な歌声とTHE XXの呪術的なビートの邂逅、あるいはメランコリックなWARPAINTとTHESE NEW PURITANSのディープな交配なんて想像してしまうが、かつての4ADが醸したゴシック・ロマンな美意識、そのモダンな解釈とも呼べそうだ。いやはや、末恐ろしい新鋭が現れた。
-

-
Esme Patterson
Woman To Woman
USインディー・フォーク・グループ、PAPER BIRDのフロント・ウーマンの2ndアルバム。"ポピュラーなラヴ・ソングに女性のキャラクターの立場から返答する"という、なかなか面白いアイディアをコンセプトとして制作されたとのことで、Elvis Costello「Alison」、Michael Jackson「Billie Jean」、THE BEATLESの「Eleanor Rigby」他、全10曲のアンサー・ソングが収録されている。古いレコードを流しているような「Valentine」、カリプソ調の「Oh Let's Dance」など、多彩なアレンジと柔らかい音でまとめられた心地の良い作品だが、こういうコンセプト・アルバムを聴くうえで英語が理解できたらもっと楽しめるのにな~と思ってしまうのは筆者だけではないはず。もしかして女性の立場からとてつもない毒舌を吐いているのかもしれないかも?と想像しつつ聴いてみて!
-

-
ESP
ESP
Aska、Seiya、Bobbyから成る、LAで結成された3ピース・バンド、ESPの日本デビュー盤。AskaとSeiyaは日本人の兄弟だという。日本での知名度はまだほとんどないが、アメリカではレッチリのFleaに絶賛されたり、MAROON 5にラヴ・コールを送られて、彼らの武道館公演のオープニング・アクトに抜擢されたりと、かなりバズが起こっている。しかし音を聴けばそれも納得の、実にミステリアスでチャーミングなサイケデリック・ポップ。全体的にリヴァーヴがかった音のヴェールの中を、Askaの少し舌足らずなヴォーカルとエキゾチックなメロディが揺らめいていくのを聴いていると、まるで白昼夢の中にいるような気持ちよさに覆われる。陰鬱として恍惚とした文学性が、モダン・サイケデリアとなって花開いている。
-

-
ES-TRUS
Dear
初の全国流通となった1stミニ・アルバム『True or False』から約2年半。2ndミニ・アルバムではライヴ仕様のラウドなサウンドを封印し、"この間に何があったの!?"と思わせるような、歌を重要視したサウンド作りに変貌した。しかし表現方法は変われど、kyoka(Vo)の圧倒的な歌唱力や独創的な歌詞の世界観は凄みを増すばかりで、よりバンドの個性や存在感を増した感のある今作。バラード曲「華向」で始まる5曲は、日々の生活に寄り添うような身近さと、"僕と君"の物語を1枚を通じて綴るような物語性があり、聴き手を選ばないポピュラリティと、"これは私の歌だ"と思わせる共感性を併せ持っている。ここから大きく飛躍していくであろう、ES-TRUSのターニング・ポイントとなる重要な1枚だと思う。
-

-
ES-TRUS
True or False
本物志向のリスナーを唸らせるラウドロック・サウンドという枠組みの中に様々な音楽のエッセンスを凝縮するという意味で、このバンドの魅力を物語るのは、間奏がジャズになるリアレンジ版の「NOT HATCH」、仮タイトルが"激しいバラード"だったという「媚愛」、ヒップホップとラテンのテイストも含む「暁-akatsuki-」の3曲か。紅一点シンガーを擁する名古屋の5人組が結成から4年。満を持してリリースする初の全国流通盤は、ライヴの定番曲に新曲も加えた、これまでとこれからを繋げる全7曲を収録。マイナスの感情を歌うことが多かった彼らが爽やかさとシンプルさという新境地を打ち出したバラード「君がいて」をリード曲に選んだのは、彼らがすでに、ここから始まる新たなキャリアを見据えているからだ。
-

-
été
Apathy
ミニ・アルバム『Burden』からわずか3ヶ月でのリリースとなる初のフル・アルバム。変拍子に攻撃的なブラストビートまでもが織り込まれた、幾何学的なバンド・アンサンブルに、ポエトリー・リーディングとメロディが乗る「crawl」で本作は始まる。予定調和的なサビや良しとされるような展開は無視して、感情のカオスと静寂との無秩序なうねりがあるようだが、その曲は耳にスムーズに流れ込んできて心や身体を刺激していく。「ruminator」では世の中のムードや空気に順応できない自分を"ぼくらは劣等"と言いながらも、常にruminator=熟考し、考えや感情を発する人間でありたいと個性を突きつける。エレクトロ要素も交えるなどétéのポテンシャルを意識的に広げていくアルバムとなった。
-

-
été
Burden
コドモメンタルやCINRA.NETらが手を組んで開催した"404〈ヨンマルヨン〉AUDITION"の優勝バンド、étéの初となる全国流通盤ミニ・アルバム『Burden』。3ピースの演奏が複雑に絡み合うサウンドに乗せて、中性的......と言うよりも、むしろ女性的とすら言えるようなヴォーカル オキタユウキのポエトリー・リーディングが鋭利な言葉を紡ぐ「DAWN」から幕を開ける。オルタナティヴなギター・ロック、激情のハードコアからトラップ・ミュージックまで、様々な音像を行き来する全7曲には、人間の感情という不可解なものと真正面から向き合い、言葉(あるいは音楽)でそれを妥協なく捉えようとする想いが熱く滲む。その圧倒的な情報量の奥にあるかすかな希望の光がとても美しい。
-

-
Evan Voytas
I Took A Trip On A Plane
Flying LotusやGONJASUFIのキーボーディストを務める、超実力派アーティストEvan Voytasが遂に日本デビュー。数々の芸術家を輩出したアートの街、ペンシルベニア州のカッズタウンで生まれ育ったEvanは、幼い頃から色彩豊かな環境で個性を磨いていた。その環境もあってか、今作に収録されている楽曲は様々な色が混ざりあい、類を見ない独自の色を形成している。また、MGMT meets PASSION PITと称され、ミニマル・ポップとディスコ・サウンドの理想的な巡り合わせとも言える曲調は、エレクトロでありながら“ダンス”ではなく“昼寝”という言葉がよく似合うほど、ゆるくメランコリックである。
-

-
Eve
Under Blue
大ヒット曲「廻廻奇譚」も収録した前作『廻人』から約2年8ヶ月ぶりとなるアルバムは、その勢い衰えることなく、豪華タイアップ曲が目白押しの全19曲。「ティーンエイジブルー」や「スイートメモリー」では澄んだ空やきらめく水面を染める青春の青、「lazy cat」や「逃避行」では夜明けを待つ空を染める深い憂鬱のブルーと、爽やかなポップ・ロックもクールなダンス・ナンバーも色彩豊かに様々な"Blue"を描く。「さよならエンドロール」が象徴するように、ダークな感情を吐き出しながらも希望を見いだしていく姿は、地の底から青空を覗かせるジャケットにも通ずる。神秘的な「Under Blue」から、青の持つ冷たさを包み込むような「夢に逢えたら」が締めくくるラストも美しい。
-

-
Eve
廻廻奇譚/蒼のワルツ
リリースごとに名を広めてきたアーティストではあるが、本作はTVアニメ"呪術廻戦"のOP主題歌に、アニメ映画"ジョゼと虎と魚たち"の主題歌&挿入歌を収録......と、さらに遠くまで届きそうな予感。それでいて、「廻廻奇譚」から感じる筆の乗りの良さにも、「蒼のワルツ」の3拍子が生む大きなスケールにも、「心海」の開放感にも、タイアップもとに負けない熱量が詰まっている。他4曲は、エレクトロ・ポップからピアノやストリングスの鳴るバラードに移行するまでの流れが美しく、中には、曲の運び方に新鮮味を感じさせる曲や、コロナ以降だからこそ出てきたのであろう言葉が歌われた曲も。7曲入りEPという形式を採った点も含め、全体的にクリエイティヴの充実が読み取れる。
-

-
Eve
Smile
荘厳なストリングスと軽いビートが不思議と溶け合う「LEO」、心躍るイントロから息急き切るように歌い出す「レーゾンデートル」(直訳すれば"存在意義")、爽やかさに胸を撫で下ろしながら曲名を見てみるとハッとする「虚の記憶」、めくるめく音色とメッセージが押し寄せてくる「いのちの食べ方」......Eveという人は言葉を紡がずには、音を鳴らさずには、生きていけない人なのではないか。そんなことを思うほど、ズシリと響くフル・アルバム。ライヴでハンド・クラップが巻き起こる光景が見える「心予報」、澄んだファルセット・ヴォイスが聴ける「白銀」など、開放的な一面も見られるが、アーティスティックに捻じれたような「胡乱な食卓」がラスト・ナンバーというところに、なぜかホッとする。
-

-
Eve
おとぎ
『文化』に続く2枚目の全自作曲アルバム。トータル・デザイン力に秀でたアーティストらしく、アルバム1枚を通して物語を描く姿勢は健在で、その物語は前作よりも鮮やか且つ精巧なものになった印象だ。ここ最近ネット発アーティストの台頭が目立つが、やはり先陣を切っていくのはこの人だと改めて思った。ただ、個人的に最も気になったのはそこではない。本作では、MVやライヴなどですでに披露されている新曲と、完全未発表曲が共存していて、真ん中に通る軸こそは同じだが、両者の間にわずかな変化を読み取ることができるのだ。この1年での大きな出来事と言えば初のワンマン・ツアーの開催。生身のコミュニケーションが彼の創作に何か影響を与えたのだとすれば、それは非常に興味深いことだ。
-

-
EVERLONG
シグナルE.P
名古屋のライヴ・シーンで頭角を現してきた3人組、EVERLONG。メロコアからスタートしながらそれだけに収まらない幅広い曲を作ってきた彼らは、ファンタジックな歌詞によってもユニークさをアピールしてきた。その彼らがさらなる飛躍を目指してリリースする1stシングル。キャッチー且つアンセミックな魅力を持った4曲はメンバーが言う通り、今後、ライヴで武器になるに違いない。そう言ってしまうと、シンプルでストレートな曲ばかりと思われそうだが、「明日から本気出す!」はロックンロール風に始まったあと、予想外の展開をする風変わりな1曲。彼らは単にポップな曲だけを求めているわけでも、飛躍を目指しているからって単純にわかりやすくなったわけでもない。そんなところにバンドの矜持が窺える。
-

-
EVERYONE EVERYWHERE
Everyone Everywhere
フィラデルフィアを中心に活動する23歳の4人組 Everyone Everywhereのデビュー・アルバム。この音楽がみせてくれたのは、“憧れの時代”への時間旅行。私は彼らとほぼ同い年なのだが、90年代ロックというのは当時小学生だった私たちには、手が届きそうで届かなかった距離感であるからこその特別な想いがある。それは、当時は知り得ないはずの音楽へのノスタルジーという妙な感覚。例えば、彼らもフェイバリットに挙げたバンド、DINOSAUR JR の『GREEN MIND』を初めて聴いた時、そのスカスカの手ごたえとノイズと共に溢れるエモーショナルにかき立てられ涙した。この瞬間というのは、リリース当時にタイムスリップしている。もちろん当時はDINOSAUR JRなんて聴いたこともないのに…。ここには00年代に青春期を過ごした世代の、“間に合わなかった時代” への憧れがめいっぱい詰まっているのだ。
-

-
EVERYTHING EVERYTHING
A Fever Dream
日本でも"SUMMER SONIC 2010"に出演するなどして人気を博している、UKマンチェスターのエレクトロ・ポップ・バンド。結成10周年を迎えた彼らが3年ぶりにリリースする4作目のアルバム。制作にはSIMIAN MOBILE DISCOのメンバー、James Fordが参加している。1stシングル曲「Can't Do」を始め、ダンサブルなエレクトロ・ロック色のある楽曲が収録されている一方、「Good Shot, Good Soldier」、「Put Me Together」といったメロウな楽曲では、憂いのあるJonathan Higgsのヴォーカルを聴くことができる。その両方を兼ね備えているのが、一聴すると北欧のポスト・ロックを思わせる深淵な世界観を持つ表題曲。静かな立ち上がりからの、中盤以降のEDM的な展開は聴きどころ。やたらテンションが高いデジタル・サウンドを苦手に感じる人でも聴けるはず。
-

-
EXiNA
XiX
"激情放つ革命"とは、すでにリリック・ビデオが先行公開されている今作のリード・チューン「EQ」の最後で力強く高らかに歌い上げられる一節になる。今夏ここに起動したEXiNAは、2015年にTVアニメ"艦隊これくしょん -艦これ-"のED「吹雪」でデビューした西沢幸奏(にしざわしえな)であるのだが、おそらく当時のイメージをそのまま重ねることは、このEXiNAの音に触れるにあたってはあまり意味をなさない。なぜなら、EXiNAが体現するのは先鋭的でいて激情にかられた音像たちであり、衝動的且つ鮮烈な彼女自身の綴る歌詞たちがその主軸を成しているものだからだ。あの頃17歳だった彼女は時を経てメタモルフォーゼを果たし、今ここからEXiNAとして志す革命を始めていくのだろう。
-

-
EXLOVERS
Moth
日本でも限定生産のデビューEPが即完したほど話題となったロンドン出身の5人組EXLOVERSが待望のデビュー・アルバムを完成させた。FLORENCE & THE MACHINEやTHE BIG PINK等のプロデュースで知られる話題のプロデューサー・デュオDemian Castellanos & Jimmy Robertsonが手掛け、全編を通して奥行と広がりのある洗練されたサウンドに仕上がった。ドリーム・ポップ・サウンドを軸に、序盤は疾走感のある楽曲で惹き付けられるが、中盤以降のしっとりとした楽曲も魅力的だ。ソフトで浮遊感のあるPeterとLaurelの男女ツイン・ヴォーカルが特徴的で、特に中盤「Unlovable」で聴ける綺麗なハーモニーは永遠に聴いていたいぐらい美しい。楽曲の幅が広いので今後どういった方向に向かうのかにもとても興味が持てる魅力的な一枚。
-
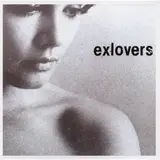
-
EXLOVERS
Exlovers
イギリスから現れたギター・ポップの新星EXLOVERS、日本初上陸となるミニ・アルバム。5月には出ていたようですが、あまりにひっそりすぎて、見過ごしてました。これまでに7インチ2枚、EP1枚を発表してますが、もうそのエヴァーグリーンなメロディを持つネオアコが密かに注目を集めていた彼ら(各ジャケットの淡く甘酸っぱいセンスもバッチリ)。ロンドンをベースに活動し、GOLDEN SILVERSなどからも支持を得ていることからも、その音楽的センスが分かるだろう。そして、まずは美しいギター・アルペジオから始まる「Just A Silhouette」を聴いてもらいたい。あまりに完璧で切な過ぎる青春の一頁。いよいよ、この素晴らしき歌心が多くの人のもとに届けられる。どうか、聴いて下さい。
-

-
EXPE.NISHI
INVISIBLE DUO
室内楽的グルーヴを追求するユニットPARAのメンバーである、スペースギターのYOSHITAKE EXPEとシンセサイザーの西 滝太のプロジェクト。美しいスペースギターと様々な音色を奏でるシンセサイザーがどんどん絡まり、溶け合い、ひとつになっていく。ここが未来なのか、宇宙なのか、よく分からない。不思議な世界の奥の奥へ入り込んでいくような感覚だ。繊細な二重奏が、やわらかい風に乗って宙を舞う蛍のように、きらめきながら吹き抜けていく。だが耳を凝らして聴いてみると、一筋縄ではいかないテクニックが効いたマニアックな音があちこちに散りばめられている。心地良さと緊迫感が入り乱れる非常に知的で数学的な音の構成は、この二人だからこそ成し得るものだろう。約73分にも及ぶ超大作が誕生した。
-
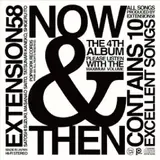
-
EXTENSION58
NOW AND THEN
1994年結成、新潟パワー・ポップ・シーンの最重要バンドとも謳われる、EXTENSION58の4thフル・アルバム。60'sマージービート、ガレージから70年代のロック、90年代のギター・ポップや渋谷系テイストを入れたバンド・サウンドは、どことない気だるい雰囲気も手伝って、甘くとろけるように耳をくすぐり夢見心地へ誘う。GRAPEVINEやサニーデイ・サービスを手掛ける高野勲をゲスト・キーボーディストに迎えたことで、バンドの持つ煌びやかな部分がより美しく輝いた。ここまでポップなのにしっかりロック。今年結成20周年を迎えるというキャリアもあり、ひとつひとつの音には余裕にも近い包容力がある。リアルに触れ過ぎていた人間には赤面ものかも?だがこんな夢を見せてくれるのは音楽の特権では。


























