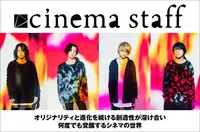LIVE REPORT
Japanese
cinema staff
Skream! マガジン 2015年08月号掲載

2015.06.26 @Zepp DiverCity
Writer 沖 さやこ
ここまで感情を揺さぶられた――いや、かき乱されて、ど真ん中から掴まれた感覚になるライヴは今まで観たことがなかったかもしれない。演者と心が通うというよりは、演者の心がそのまま自分の中に宿るような、こちらを飲み込んで同化するような切実さ。バンドの生き様が身体に刻みこまれ、突き動かされるようだった。音を通じて想いを共有し重ねることで、自分ひとりでは生まれない力が生まれていくことに興奮すると同時に、それをcinema staffというバンドが成し遂げている事実が眩しくて仕方がなかった。彼らの重ねた12年という歴史と、これから何十年と続くであろう未来が、ステージから溢れ出していたのだ。
 『blueprint』の1曲目である「陸にある海」がSEとして流れると同時に、ステージが青く光り始める。ゆっくりとバックドロップの"cinema staff"の文字が緑に染まり、少しずつ黄色が射し始めたころ、メンバーが登場。SEが止まるや否や、飯田瑞規(Vo/Gt)と辻 友貴(Gt)の2本のギターが「drama」のイントロを奏で出す。飯田と三島想平(Ba)のハーモニーも美しく、久野洋平(Dr)は安定感のあるリズムでバンドの音をしっかりとまとめる。「竹下通りクラウドサーフ」は辻が音源とは違うフレーズを奏でることで楽曲に新たな勢いを生み、「地下室の花」「theme of us」と三島がタイトルコールやアクセントとなるMCを挟むことで、1曲1曲に意味と重みのあるストーリーを生んでいた。三島は大きく手招きしてフロアを煽り、飯田は持ち前の美声と歌唱力を存分に発揮させ、流麗なメロディを鮮やかに乗りこなす。自信に満ちた音に心が華やぐ――だが今のcinema staffならこれを成し遂げることくらい、言ってしまえば至極当然。それは2014年の功績と傑作『blueprint』で立証済みなのだ。
『blueprint』の1曲目である「陸にある海」がSEとして流れると同時に、ステージが青く光り始める。ゆっくりとバックドロップの"cinema staff"の文字が緑に染まり、少しずつ黄色が射し始めたころ、メンバーが登場。SEが止まるや否や、飯田瑞規(Vo/Gt)と辻 友貴(Gt)の2本のギターが「drama」のイントロを奏で出す。飯田と三島想平(Ba)のハーモニーも美しく、久野洋平(Dr)は安定感のあるリズムでバンドの音をしっかりとまとめる。「竹下通りクラウドサーフ」は辻が音源とは違うフレーズを奏でることで楽曲に新たな勢いを生み、「地下室の花」「theme of us」と三島がタイトルコールやアクセントとなるMCを挟むことで、1曲1曲に意味と重みのあるストーリーを生んでいた。三島は大きく手招きしてフロアを煽り、飯田は持ち前の美声と歌唱力を存分に発揮させ、流麗なメロディを鮮やかに乗りこなす。自信に満ちた音に心が華やぐ――だが今のcinema staffならこれを成し遂げることくらい、言ってしまえば至極当然。それは2014年の功績と傑作『blueprint』で立証済みなのだ。
続いて「想像力」は辻の焦燥的なギターとプレイに釘付けに。ギミックの効いた飯田の歌からも彼の表現力がどんどん磨かれていることを感じる。今年3月にcinema staffを観たときは三島が飯田よりも前に出ることも多く、それがダイナミックで面白いとも思っていたが、この日は飯田と三島のふたりがしっかりと地に足をつけてフロントを張り、そこに彩りを添える辻のギターと、すべてを大きく突き上げる久野のドラミングがあるというバランスが、楽曲をより良い状態で輝かせているように見えた。がむしゃらにぶち当たることで生まれる美しさではなく、それぞれの確固たる個が目的やヴィジョンをはっきり持ち、ぶつかり合いながら高め合う。柔らかさと激しさを併せ持つ「borka」はそれを大きく物語っていた。
「borka」のアウトロのノイズからドラム・カウントで「ハトガヤ・ゲットー」。地響きのようなベースを筆頭にひりついた音像で魅了し、黒で統一した4人の衣装もより際立つ。インディーズ時代の楽曲である「skeleton」はひとつひとつの音が印象的に響き、三島のファルセットによる高音コーラスも楽曲を高める。過去曲を進化させていくところも、ひとつずつたしかに歴史を積み上げている彼らだからこそだ。「compass」は飯田と三島のハーモニーの中で、衝動的にギターを弾く辻の姿も印象的だった。
 続いては飯田と三島が共にアコースティック・ギターを抱え、弾き語りを披露するという。準備を整えた三島がフロアを見渡し"相変わらずZeppはでかいですねえ"とつぶやく。そのときフロアの男子から"おかえり"という言葉が漏れた。奇しくも丁度1年前のこの日、cinema staffは前作『Drums,Bass,2(to) Guitars』のリリース・ツアー・ファイナルをこのZepp DiverCityで行った。加えて、岐阜から上京してから様々な想いを感じ、考え、苦しみながらも一歩ずつ進んできた彼らが、這いつくばってでも東京で音楽をしていくという決意を固め、形にしたのが『blueprint』というアルバムだ。その東京で"おかえり"という言葉が聞けることは、彼ら(特に三島)にとって大きな感慨だろう。"ただいま......ただいま!"と言った三島は"17歳のときに作ったこの曲をここでやれることを幸せに思う"と言い、「daybreak syndrome」のイントロをアコギで爪弾いた。その音色は喜怒哀楽すべてを飲み込んだ、痛いくらいに純粋で優しく、透き通った海のように大きく深かった。ふたりの歌声も支え合うように強く遠くに伸び、曲が吸収してきた10年間の重みを感じる。
続いては飯田と三島が共にアコースティック・ギターを抱え、弾き語りを披露するという。準備を整えた三島がフロアを見渡し"相変わらずZeppはでかいですねえ"とつぶやく。そのときフロアの男子から"おかえり"という言葉が漏れた。奇しくも丁度1年前のこの日、cinema staffは前作『Drums,Bass,2(to) Guitars』のリリース・ツアー・ファイナルをこのZepp DiverCityで行った。加えて、岐阜から上京してから様々な想いを感じ、考え、苦しみながらも一歩ずつ進んできた彼らが、這いつくばってでも東京で音楽をしていくという決意を固め、形にしたのが『blueprint』というアルバムだ。その東京で"おかえり"という言葉が聞けることは、彼ら(特に三島)にとって大きな感慨だろう。"ただいま......ただいま!"と言った三島は"17歳のときに作ったこの曲をここでやれることを幸せに思う"と言い、「daybreak syndrome」のイントロをアコギで爪弾いた。その音色は喜怒哀楽すべてを飲み込んだ、痛いくらいに純粋で優しく、透き通った海のように大きく深かった。ふたりの歌声も支え合うように強く遠くに伸び、曲が吸収してきた10年間の重みを感じる。
ステージに戻ってきた久野が"(三島と飯田のふたりの弾き語りの)立ち姿がゆずみたい......いや、プロミスかな"と笑わせ、"17歳でこれ作れるって天才じゃない?"などと飯田とともに三島を褒めちぎり、三島が照れて顔を隠すという微笑ましい場面に会場が和む。3人による小気味よいトークは"ライヴハウスには霊が集まりやすい"という話題に。飯田が"音が鳴るところには出るみたいなんですよ"と言うと、BGMとともに死装束&白い三角布という幽霊ルックに赤ぶちサングラスで登場した辻......いや、フリースタイル・ラッパーの"MCウラミッシェル"さんがハンドマイクで登場(※ちなみに"ウラミッシェル"という名前は"うらめしや"とかけられているらしい)。ウラミッシェルさんに対してテンポよく容赦ない3人のツッコミ、ウラミッシェルさんのフリーすぎるラップに場内大爆笑。生前できなかったバンドがやりたいというウラミッシェルさんを交えて演奏されたのは「the ghost」、MCで盛大にふざけても演奏が始まれば空気が引き締まるところはさすがだ。
 目的を達成したウラミッシェルさんは成仏なさったようで、辻がステージに帰還。飯田の"DiverCityのみなさんいけますか? いけるか! 混ざっていけ!"とお馴染みの台詞から三島の"いくぞDiverCity!"で「exp」へ行くと、その音の懐のでかさに圧倒された。cinema staffは技術のあるバンドでありつつも、心が先走って演奏が走るときもある。だが彼らは絶対転ばない。つんのめりそうになりながらもしっかりと大地を蹴って疾走していく、そんな演奏がスリリングで心地いいのだ。間奏では三島が"オーバーグラウンドもアンダーグラウンドも、歌っちゃえばみんな一緒! 楽しんじゃえよ!"とコール&レスポンスを盛り込み、その情景も壮観だった。曲の繋ぎもドラマティックで、どんどん我々を力強く牽引していく。彼らのライヴは派手な舞台装飾があるわけではない。だがメンバーひとりひとりの気魄はどんなに華やかなセットよりも煌びやかで、「tokyo surf」も「青写真」も、その笑顔が溢れる真剣な本気の音の説得力に圧倒された。
目的を達成したウラミッシェルさんは成仏なさったようで、辻がステージに帰還。飯田の"DiverCityのみなさんいけますか? いけるか! 混ざっていけ!"とお馴染みの台詞から三島の"いくぞDiverCity!"で「exp」へ行くと、その音の懐のでかさに圧倒された。cinema staffは技術のあるバンドでありつつも、心が先走って演奏が走るときもある。だが彼らは絶対転ばない。つんのめりそうになりながらもしっかりと大地を蹴って疾走していく、そんな演奏がスリリングで心地いいのだ。間奏では三島が"オーバーグラウンドもアンダーグラウンドも、歌っちゃえばみんな一緒! 楽しんじゃえよ!"とコール&レスポンスを盛り込み、その情景も壮観だった。曲の繋ぎもドラマティックで、どんどん我々を力強く牽引していく。彼らのライヴは派手な舞台装飾があるわけではない。だがメンバーひとりひとりの気魄はどんなに華やかなセットよりも煌びやかで、「tokyo surf」も「青写真」も、その笑顔が溢れる真剣な本気の音の説得力に圧倒された。
本編ラスト「シャドウ」の前、三島が長めのMCで"land=ocean"というツアー・タイトルに込めた想いを語った。彼の作る曲には昔から"海"という言葉が多く出てくる。私もインタビューでそこに言及したことがあるが、岐阜出身の彼にとって身近な存在ではなかった海は、彼の頭の中で憧れや自由の象徴になっていた。だけどこれからはイメージの世界ではなく、目の前にあることと向き合い、地面をちゃんと踏んでやるべきことをやっていこう――彼のその想いが結実したのがこのツアーだった。彼は去年から嫉妬と後悔を繰り返す自分と向き合い、それを歌った「シャドウ」を作る。"自分を含め、誰かの背中を押せればと思った"と言う彼は、"背中を押してくれるメンバーやお客さんとエネルギーの循環ができればいいと思って音楽をやっている"と続けた。"弱いバンドなのかもしれないです。でも正直にずっと音楽をやり続けるので、ついてきてください"――そう彼が言って演奏された「シャドウ」は、三島が"汚い歌"だというこの歌を、飯田が強く美しく大切に歌う姿にとても胸を打たれた。彼が歌うことで三島の想いが浄化されるようで、三島が歌うよりも三島らしさや、三島の素直さが出ているような気もした。それはエモーショナルな辻のギターも、楽曲に大きなうねりを作る久野のドラムも同じで、粲然たる勇敢な音の中に、私はただただ零れ続ける涙とともに立ち尽くすしかなかった。
 アンコールでは飯田が"音楽は楽しいんですけど、楽しいだけじゃなくて......誰かのために音楽をやっていきたい"と語りながら、感極まり言葉を詰まらせる。そんな彼の姿を見たことがなかった観客は驚きながらも、からかいもせず、明るく"頑張れ!"と声を掛けることもせず、ただ静かに見守っていた。そして飯田が"あなたひとりひとりの力になれればと思うようになって、音楽をやっています"と続けると、大きなあたたかい拍手と"ありがとう!"の声が飛んだ。ハイスイノナサの森谷一貴(Key)と三島のアコギと飯田で「孤独のルール」、森谷とcinema staffで「望郷」を披露。感傷だけではない、未来を見据えた音像に、cinema staffがどんどん逞しく大きく、しなやかになっていることを感じる。昔の内向きな時代を知っているぶん、追い続けていたバンドがここまで進化していくことは代え難い喜びであり、誇りだ。自分も彼らに負けていられないと奮い立った。
アンコールでは飯田が"音楽は楽しいんですけど、楽しいだけじゃなくて......誰かのために音楽をやっていきたい"と語りながら、感極まり言葉を詰まらせる。そんな彼の姿を見たことがなかった観客は驚きながらも、からかいもせず、明るく"頑張れ!"と声を掛けることもせず、ただ静かに見守っていた。そして飯田が"あなたひとりひとりの力になれればと思うようになって、音楽をやっています"と続けると、大きなあたたかい拍手と"ありがとう!"の声が飛んだ。ハイスイノナサの森谷一貴(Key)と三島のアコギと飯田で「孤独のルール」、森谷とcinema staffで「望郷」を披露。感傷だけではない、未来を見据えた音像に、cinema staffがどんどん逞しく大きく、しなやかになっていることを感じる。昔の内向きな時代を知っているぶん、追い続けていたバンドがここまで進化していくことは代え難い喜びであり、誇りだ。自分も彼らに負けていられないと奮い立った。
客電がついてもダブル・アンコールを求める拍手が収まらず、急遽メンバーがステージに再登場。久野が"まだ言えないけどこの先決まってる予定がいっぱいあって。今年後半も攻めていきますので。ここに入りきらないくらいの人を集めてみせるよ!"と言い、「Poltergeist」へ。辻は上半身裸でギターを抱え暴れまわり、曲の終盤では三島がベースを手放しハンドマイクでフロアに飛び込みシャウトを続け、飯田は歯弾きをするなど、最後の最後でこれでもかというくらいタガが外れたようにひっかき回す。ギターのノイズの中で響いた三島の"岐阜県から来ました、cinema staffです"。ライヴで必ず聞くこの台詞も、これまでにないほどに堂々としていた。いつまでも彼らが掴んでいく景色を見続けたい――改めてそう強く思ったのであった。
- 1
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/livereport/2015/07/cinema_staff.php on line 417
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/livereport/2015/07/cinema_staff.php on line 417
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号