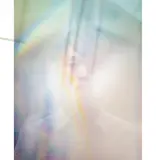LIVE REPORT
Japanese
戸渡陽太
Skream! マガジン 2016年07月号掲載

2016.06.18 @渋谷STAR LOUNGE
Writer 石角 友香
完成した作品を生で更新するというより、"歌詞"という限りない心象を見事な手さばきで切り取り、その瞬間を再び今の気持ちの移ろいで瞬時に歌声に変換していく――"戸渡陽太"というシンガー・ソングライターの得難い特徴に出会ったライヴだった。しかも、終演後は笑顔。何かを突きつけられて立ちすくむという体感ではなかったのだ。それは"音楽の力"、だったのだろう。
 メジャー・デビュー・アルバム『I wanna be 戸渡陽太』リリース後の初ワンマンであり、彼がシリーズで続けているライヴ"10番勝負"の7手目でもある。今回はアルバムにプロデューサーや演奏家として参加した深沼元昭(PLAGUES/Mellowhead/GHEEE)、高桑圭(Curly Giraffe)、白根賢一(GREAT3)とのバンド編成。90年代末から日本のオルタナティヴ・ロックを深化させてきた面々である。彼らのファンというか、戸渡が彼らとバンド編成でライヴすることを楽しみに足を運んだオーディエンスも多いようだ。
メジャー・デビュー・アルバム『I wanna be 戸渡陽太』リリース後の初ワンマンであり、彼がシリーズで続けているライヴ"10番勝負"の7手目でもある。今回はアルバムにプロデューサーや演奏家として参加した深沼元昭(PLAGUES/Mellowhead/GHEEE)、高桑圭(Curly Giraffe)、白根賢一(GREAT3)とのバンド編成。90年代末から日本のオルタナティヴ・ロックを深化させてきた面々である。彼らのファンというか、戸渡が彼らとバンド編成でライヴすることを楽しみに足を運んだオーディエンスも多いようだ。
1曲目、戸渡はエレピの前に座り、いきなり歌い出す。アルバム同様、「Beautiful Day」でのスタート。音源で語尾がフラットする感じも捨てがたいが、ライヴではもっとストレートに歌っている。続けてJ-POP的なサビへの歌詞の当て方がキャッチーな「すべては風の中に」と、ポップな2曲を続けて披露。次はアコギを持ち、インディーズ時代のミニ・アルバム『孤独な原色たち』からサビのぶっきらぼうなほどのヴォーカルに彼の少年性を見る「Y」。深沼のごくさりげないギター・リフが曲のパースペクティヴを広げる。このメンバーがある種、素朴なロックを演奏しているのがなんとも贅沢というか、必要最低限しか弾かない/叩かない演奏が戸渡の歌に似合う。バック・バンドじゃなく、4人組のバンドだなと思う。グルーヴが醸成されるにつれ、戸渡も深沼も自然に笑顔になるのもいい。本当にごく自然に生まれる笑顔だからだ。間髪いれず、このメンバーお得意のロー感のある16ビートが小気味いい"いぶし銀のグルーヴ"を生むうえで戸渡のトーキング風のヴォーカルが跳ねる「SOS」。我流の譜割というか、自在にフロウとメロディを行き来する戸渡の歌をどこまでも自由に泳がせるような演奏だが、歌が牽引しているようにも思える。楽しさの中に"いい勝負だな"と思わせるスリルがある。それこそがまさに今、戸渡がやっているライヴの性質なのだと思った。
軽くメンバー紹介をして、高桑と白根が秘密にしているエピソードをバラしそうになるところを高桑に制止されたところで、フロアから笑いが起こる。そして"ギター、深沼元昭さん"と紹介しようとしたところ、次の曲ではマンドリンという場面も。音源よりロック・バンド寄りのアレンジだが、熱さが加わった「青い人達」、ライヴでは、より"愛してるよ、君の事好きじゃないけど"など矛盾しているようで、確信なんてないよなという気持ちがよりダイレクトに刺さった「Nobody Cares」。オルタナ・カントリー風のアレンジはライヴでも空間の色を変えたが、それ以上に歌詞を再認識する演奏だった。
 その後、3人が一旦ステージからはけ、戸渡による弾き語りが始まる。"10番勝負と言いながらバンド・メンバーとやってるので、ここからひとりで勝負します"と、ディレイのかかったアコギをアコギの表現とは思えないほどある種、シューゲイザーやラテン音楽のように自在に鳴らしまくる。その「ハロー・グッバイ」で、冒頭の印象を深めたのだが、息苦しそうだけれど自在にも聴こえるし、自在に歌えるけれどそれが目的でもないという、歌いながらもその瞬間の最適値を叩き出すような戸渡の歌と言葉に対する直感力の鋭さを見た。苦しいのに身体を突き破って自然と出ているような凄まじい歌だった。いい緊張感を携えたまま、音源未収録の「長い長い夜を抜けるまで」では、途中から効果音のような白根のエレピも加わり、静かに迫るものがあった。
その後、3人が一旦ステージからはけ、戸渡による弾き語りが始まる。"10番勝負と言いながらバンド・メンバーとやってるので、ここからひとりで勝負します"と、ディレイのかかったアコギをアコギの表現とは思えないほどある種、シューゲイザーやラテン音楽のように自在に鳴らしまくる。その「ハロー・グッバイ」で、冒頭の印象を深めたのだが、息苦しそうだけれど自在にも聴こえるし、自在に歌えるけれどそれが目的でもないという、歌いながらもその瞬間の最適値を叩き出すような戸渡の歌と言葉に対する直感力の鋭さを見た。苦しいのに身体を突き破って自然と出ているような凄まじい歌だった。いい緊張感を携えたまま、音源未収録の「長い長い夜を抜けるまで」では、途中から効果音のような白根のエレピも加わり、静かに迫るものがあった。
再びバンド編成で、戸渡のアコギに深沼のエレキがユニゾンする形でシンプルに演奏された「SHIKISAI」、戸渡のアコギのカッティングが"タタタタタッ"と、ちょっと意外なビートを刻んでいることに気づいて、アコギの弾き方にさらに注目した「さよならサッドネス」は、彼がワールド・ミュージックや広く世界のフォークロアの影響下にあることを"目で見た"思いだ。そのグルーヴを16に変えた「ギシンアンキ」。コントロールできなさそうなサビの高音に自分自身がぶん回されるような、予測不能な歌。焦燥とそれが粉々になる瞬間を高速で見ているような歌だった。そんなのカタルシス以外になんて言えばいいのだろう。
下降するコード展開がユニークな「木と森」、そしてアルバムの中でも最も開かれたポップ・ロック・ナンバー「Sydney」がラストにセットされた。"愛"というものの存在を今は信じているとインタビューでも話してくれた彼が、"言葉をも飛び越えたその先にある物を/僕は求めている"と歌うこの曲は、今の彼が歌う姿勢でもあると感じた。自分の感情を解明するために曲を書いてきた彼は、今、音楽そのもので聴く者を揺さぶっている。
ここまで本編は正味1時間。正直もっと見たいし聴きたいのだが、とても濃い時間でもあった。アンコールに応えて再登場した彼は、アルバムのワンマン・ツアー"I wanna be 戸渡陽太 Tour 2016"を11月に開催することを告知し、再びバンドで「世界は時々美しい」を演奏。すでに何十年も生き残ってきたような普遍的な輝きを辣腕のメンバーが奏でていたことはもちろん、それはなぜなのかという疑問への回答は"戸渡の曲が愛されているから"だと、演奏する姿から感じ取れたことは大きかった。パーソナルな表現をバンドで鳴らす貴重な機会でもあり、これがもっと当たり前のことになれば、シンガー・ソングライターの面白さにもっと出会えることだろう。
- 1
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/livereport/2016/07/towatariyota.php on line 418
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/livereport/2016/07/towatariyota.php on line 418
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号