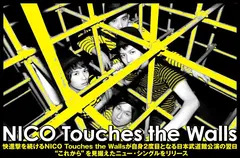Japanese
NICO Touches the Walls
2018年07月号掲載
Member:光村 龍哉(Vo/Gt) 古村 大介(Gt) 坂倉 心悟(Ba) 対馬 祥太郎(Dr)
Interviewer:山口 智男
-いっぱいある曲の中から、しゃぶしゃぶで言うところのアクをまとめてぽーんと出されると、やっぱり、どうしちゃったんですか!? ってなりますよ。
光村:いろいろな曲を、バランス良く松花堂弁当みたいに詰め込むっていう今までの理想に飽きたって言ったら違うんですけど、音楽なんだから、やっぱり楽しんだ者勝ちじゃないですか。楽しんでいるバンドを、お客さんだって見たいだろうし、聴きたいだろうから、「VIBRIO VULNIFICUS」や「SHOW」のような曲がスタジオでやっていて楽しいんだったら、その部分だけを特化する潔さが今必要なんじゃないかな。どうかしちゃったというよりは、バンドとして自然の流れだったのかなって思いますけど、続けてきたからこそ、ここまで振り切れたというか。そういう曲はこれまでのアルバムにも1曲は入ってたし。
古村:もとを辿れば、そういうところから始まったバンドではあったんで。
光村:そうだね。「アボガド」(2006年リリースの2ndミニ・アルバム『runova×handover』収録曲)とか、「そのTAXI,160km/h」(2007年リリースのメジャー1stミニ・アルバム『How are you ?』収録曲)とかね。
古村:1、2周して、武器を増やしたうえでもう1回それをやっている感じもあります。
-いや、どうかしちゃった!? っていうのはもうひとつ、今回、歌詞が結構トゲトゲしているというか、胸の中に溜まっていたものがドバっと出たというか。
対馬:アクが(笑)!?
-(笑)そういう感情をストレートに出しながら、言葉の選び方には遊び心があるというか、聴き手を煙に巻くようなところもあって。
光村:自分のマッドな部分というか、クセの強い部分が結果的に集まっちゃったんですけど、これも前作の手応えからの変化というか。「mujina」で、普段思っていることをちょっと面白おかしくボカしながらギリギリのラインまで行っちゃえ、でも下手したらコンプライアンス的にどうなんだろう......っていうことも、どれだけ自分なりのユーモアで歌えるか、みたいなことをやってみたんですけど、もっと自分の核心に近いところで書かないといけないと思ったんですよ。そういう意味では、『OYSTER -EP-』は自分から見た社会とか、自分を取り巻く環境とかをイメージしながら書いていたんですけど、それを歌っているうちに自分内ドーナツ化現象っていうか(笑)、何か書くべきものを書いていないって思えてきて、とにかく今回は自分の中にあるものをどんどん言葉にしていったんです。「SHOW」なんて、"ここまで書いたら、悲しがる人いるんじゃないかな?"って思いながら書いていたんですよ。"誰も俺の歌で泣かない"なんて、まさにそうですけど、そういうこともできるだけオブラートに包まないで書きたかった。それはどの曲でも意識しました。
-"誰も俺の歌で泣かない"なんて思うことがあるんですか!?
光村:毎日思ってますね。曲を書けば書くほど、ライヴで歌えば歌うほど、聴いている人と僕が書いていたときのイメージが一瞬繋がるようで、一生繋がらないみたいな感覚に陥ることは少なからずあるし、"この人は僕の何を見ているんだろう?"とか、"僕たちの音楽の何を聴いているんだろう?"とか、日々不安になります。
-そんなふうに言われると、質問できなくなる(笑)。
光村:いやいやいや(笑)。でもほんとにそこで、自分が楽しいからやっているんだって、自分自身を鼓舞することもあるし、夜な夜な、なんでこんなことをやっているんだろうって思うこともあるし。そういうことを、なんのストーリーもつけずに書いたっていう。ツアーをやっていてもそうですけど、ステージに立って何千人の人の前で歌っているときと、そのあとホテルの部屋に帰って、ひとりぼっちになったときのギャップというか、それを1日の中で経験すると、いろいろな気持ちの紆余曲折があるんですね。それを、まんま見せてやろうと。ただ、そこに特に答えはないし、言いたいこともないんです。ありのままっていうだけで。
-3人はそういう歌詞をどう受け止めたんですか?
坂倉:歌詞についても、さっき古君(古村)が言っていたバンド結成当初のイメージがあるんですけど、今回、みっちゃん(光村)のすごいパーソナルな部分が出たなって思います。そのころの曲たちの歌詞ができたときの感覚に近いっていうのはありますね。読んでいると、心が締めつけられる。結成当初はモノレールに乗ってレコーディングに通っていたんですけど、その帰りにモノレールの中で、その日歌入れした曲を聴いていたときの感覚を思い出しました。
古村:みっちゃんの奥にあるものをね。
坂倉:普段出さないけど、抱えているものを感じました。
-それは作品を作るうえで、何かしらの刺激にはなりましたか?
対馬:みっちゃんの書く言葉は、やっぱりみっちゃんなので、そのトゲがつらいときはつらいかもしれないですけど、それも一部なんだから、それを武器にするにはどうしたらいいか。そういうことを考えることが、昔と比べると増えていったかなって思います。
古村:前と違うのは、今回、そういう曲もアコースティック・バージョンでやるところ。アレンジが変われば、曲の雰囲気も全然違うものになるし、ライヴも全然違うし。同じ曲でも、これだけ違う気持ちでやれるんだってところで、バンドとして、また新しい楽しみ方ができたなっていうのはあります。
-自分の気持ちをありのままに書いた曲を、今現在ライヴで歌っているわけですが。
光村:演奏したりとか、曲を作ったりとかってことは、ほんとに楽しくやってるし、それ以外にいらないと思っているんですけど、言葉みたいなところはどうしても楽しいだけじゃ......。楽しいだけでいいんだったら、"ラララ"でいいと思うんですけど、そこに自分がいる意味みたいなものを残していくんだったら、やっぱり自分にしか書けない言葉で書かないといけないし、自分にしかできない歌い方を意識しないといけないし。自分がこの曲たちを一番理解して、表現しなきゃっていうのはあるから、ほんとに擦り減りますね(笑)、精神的に。今回の曲たちっていうのは。歌詞を書いたときの気持ちを思い返しながら歌っているところもあるんで、ライヴでやっていると、1曲ごとに息が上がる感じはあります。でも、「VIBRIO VULNIFICUS」でも"死ぬまで揺れていたいや"って歌ってますけど、きっと一生、音楽の中に自分が居続けたいという想いはあるので。そのなかで自分がどう生きていくかだし、それをどう人に見てもらうかだと思っているんで、その意味では、どんどんNICO(NICO Touches the Walls)印が濃密になっているという手応えがありますね。
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2018/07/nico_touches_the_walls_2.php on line 409
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2018/07/nico_touches_the_walls_2.php on line 409
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号