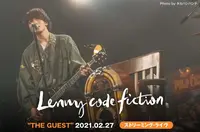Japanese
ASH DA HERO
昨年9月に開催されたZepp Tokyo公演でソロ・プロジェクトの完結と、今後はASH、Narukaze、Sato、WANI、Dhalsimの5人によるバンドとして活動していくことを同時に発表したASH DA HERO。今年に入ってからは単独公演のほかにも、a flood of circle、The BONEZ、ROTTENGRAFFTYを迎えたツーマン・シリーズの開催など、精力的に活動を展開。そしてこのたび、1stフル・アルバム『Genesis』を完成させた。ロック、パンク、ヒップホップを軸にしたミクスチャー・サウンドは、バンド ASH DA HEROの初期衝動であり、現在地点を刻みつけた会心作に仕上がっている。今回のインタビューでは最新作はもちろん、5人がバンドとして歩み始めた経緯も含めて、話を訊いた。
メンバー(写真L→R):WANI(Dr) Sato(Ba) ASH(Vo) Narukaze(Gt) Dhalsim(DJ)
インタビュアー:山口 哲生
-まず、改めてバンドとして動き出そうと思った経緯からお聞きできればと思います。
ASH:そもそもソロで始めたキッカケというのが、それまでいろいろとバンド活動をしていくなかで、なかなか思うようにうまく進まなくて。ある種、バンドをやってきた自分の人生に対しての反逆というのが、ソロを始めた動機のひとつとしてあったんですけど。そこから活動していくなかで、初めはたったふたつだけだった自分の足跡の横に、ひとつふたつと、気づいたらいろんな足跡が並んでいて。自分の人生に対してのアンチテーゼ的なもので始めたソロだったけれども、こういうメンバーだったら、こういう人とだったらバンドをもう一度やれるんじゃないか、もう一度バンドをやってみたいという気持ちがどんどん芽生えてきたんですよね。
-なるほど。
ASH:ロック・バンドというものに対してのロマンや憧れがものすごく強かった反面、ロック・バンドというものの理想と現実に敗れて、そこに対してものすごく大きなヘイトが生まれていたんですけれども、大きなヘイトが生まれるということは、裏を返せば大きなラヴだったりするので。そのことを感じながら、だんだんバンドにしたいという意欲が湧いてきたなかで、コロナ禍を迎えて。自分の仲間とか、エンターテイメント業界全体が停滞して行くなかで、もうここしかないな、と。このまま続けていたら、おそらく俺もこの濁流に飲み込まれて、すべてが終わる。そうなってしまうときに、"すべてを失う覚悟があるのであれば、お前はどうしたいんだ? "って、もう一度自分の人生と真剣に向き合ったんですよね。"お前は何をするために歌ってんだ? お前はロック・バンドをやりたかったんじゃねえのか? じゃあやればいいじゃん"っていう。そこからみんなに声を掛けさせてもらったというのが、始まった経緯です。
-メンバーのみなさんは、ソロ時代にサポートをされていた方々が多いのもあって、声を掛けやすかったですか?
ASH:逆に掛けづらかったですよ。"新しいバンドを作るんで、メンバー募集します"のほうが、全然声を掛けやすくて。自分が漕いできた人生に、新たに彩りを与えてくれる人をと考えたときに、もうこのメンバーだなっていうのはあったんですけど、やっぱりすごく考えましたよね。旧知の仲というか、サポートをしてもらっていたからこそ、プレッシャーはすごくありましたし、緊張感もありました。これが仲良しこよしで、なあなあな関係性でやっていたら声は掛けやすかったかもしれないですけれども、我々はそれぞれの人生を懸けて、プロとして音を奏でて、それを生業にしているので。だからこそ、生半可な覚悟では声を掛けられないし、生半可な覚悟でみんな解答しないとは思ったので、すごく慎重にはなってました。
-たしかに、酸いも甘いも経験したうえでバンドを組むというのは、かなり大きな決断ですよね。NarukazeさんはASHさんからバンドに誘われたときにどう思われました?
Narukaze:誘われたときは"来た!"って思いました。さっきASHも言っていたように、コロナのことが始まってから、俺も自分のことを考える機会があって。今までバンドをやってきたけど、自分の弾きたいギターを100パーセント弾いていたかと言ったら、どこかで"これならみんな好きだろう"とか"時代がこうだから"とか、そうやって考えていたこともあったし、サポート・ミュージシャンとしてやっていたときも、自分のギターを好きなように弾いているつもりでも、結局は自分の曲でもないし、そのアーティストのためだったりもするわけで。そういうのが好きな人は好きなんでしょうし、それもいいと思うんですけど、自分はギターが弾ければなんでもいいっていうタイプではなかったんですよ。やっぱりどこかしらで、自分の弾きたいギターをずっと弾きたいっていうのがあって。
-であれば、バンドをやろうと。
Narukaze:最初は自分でバンドを作ろうと思ってたんですよ。そう考えていたときに、ちょうどASHとあるライヴを観に行って。やっぱりバンドっていいなって思っていたときに声を掛けてもらったんですけど、自分が作ろうと思っていたバンドのヴォーカリストって、実は俺の中でASHしかいなかったんですよ。でも、ASHはソロでやってるから(笑)、それなら自分がギター・ヴォーカルで何かを作ろうかなと思ってたんで、話を貰ったときは単純に嬉しかったですね。
-すごいですね。かなり相思相愛な。
Narukaze:だから"来た!"ですね(笑)。
-それはたしかに"来た!"です(笑)。サポートで関わっていたときと、メンバーになってからとでまた距離感が変わったと思うんですが。
Narukaze:そこはもちろん。サポートって、人にもよりますけど、俺の場合はライヴのセットリストとか曲の構成とか、俺だったらこうするけどっていうことは特に言わずに、そのアーティストがやりたいことを支えるタイプで。でもやっぱりメンバーとなるとそうじゃなくて、なぜそうしたいのかっていうのをみんなで共有するというか。プラス自分はこうやりたいっていう気持ちもちゃんと伝えられるし、そこはやっぱり違いますね。
-何かを決めるときは、みなさんでディスカッションしていく感じなんですか?
Narukaze:わりかしそうですね。基本はASHが話を持ってくることがもちろん多いんですけど、そこにみんなからのいろんなアイディアをプラスして、みたいな。
ASH:主導権とかイニシアチヴは、場面によって切り替わる部分が大きくて。自分としては、"こうしようぜ"という提案をするというよりは、"こういうことを考えているんだけど、どう思う?"っていうのをテーブルに出す感じですね。
Narukaze:うん。そういう感じだね。
ASH:で、そこに対して"いいと思うよ"って追従してくれるパターンもあるし、"それだったらこんなんどう?"とか。その"こんなんどう?"に対して、"だったらこういうのはどう?"みたいな感じで、いろんなカードが出てきて、じゃあ整理するねって。そういうフローができているかなって感じですね。だから、僕がぐんぐん引っ張って感じじゃなくて。むしろ、僕はそういうリーダー像って嫌いなんですよ。俺が全体のリーダーで俺についてこいみたいな、すっごい古い昭和のイズムってあるじゃないですか。すごい時代遅れだと思ってて。全然カッコいいと思わないんですよ。
-そうなんですね。
ASH:だってカッコ悪くないですか(笑)?
-まぁ(笑)、いろんな人がいて、いろんなリーダー像があると思いますけど、ASHさん的にはそのタイプではないという。
ASH:そう。全然憧れなくて。なぜかと言うと、可能性が100と決まっていたら、100以上にならないじゃないですか。絶対的なリーダーが"俺が正解だ"、"俺がこう導いていく"みたいなのって。だから、そういうのってまったく興味がない。むしろ、このメンバーであり、スタッフも含めたこのチームには、それぞれいろんな個性とアビリティを持っている人がいて。この場面ではこの人の個性が絶対に生きるよねっていうのを考えて、各々がその場面で攻撃力を超発揮するみたいなことが起こったほうが、チームとしてめちゃめちゃ面白いんで。だから物事を決める際も"俺こうするから、これやって!"とかは、1回も言ったことがない気がする(笑)。
-なるほど。Satoさんとしては、ASHさんからバンドでやろうと思う、メンバーになってほしいという話が来たときにどう思われました?
Sato:"来た!"って(笑)。
-(笑)Narukazeさんと同じく。
Sato:僕は今後どうしようかなっていろいろ考えていたんですけど、サポート・ミュージシャンみたいな活動をしながらも、これはもう新しい生き方を模索しないといけないかもな......っていうぐらいのところまでいってたんですよね。それがちょうど1年前ぐらいだったんですけど。でも僕もずっと心の奥底に、バンドへの思いっていうものを閉じ込めていて。それをASHに開けてもらって、みんなと出会って、バンドになって。今はひとつひとつのことを、"そうそう、こうしたかった"って思いながらやっている感じですね。
-"バンドってこれだよな"というのを噛み締めながら活動していると。
Sato:みんながピュアにそこに向かって、一歩一歩やってるんですよ、バンドマンとして。そのなかで"そうそう、これをやりたかったんだよな"っていうのが、日々いろんな場面であって。言ってもまだ手探りなところもあるし、意識も日々アップデート中だとは思うんですけど、自分の好きなもの、自分のやりたいものはやっぱりこれだったなっていうのを感じています。
-バンドを始めた当時のピュアな衝動みたいなものって、キャリアを重ねるとどうしても薄れてしまうところがあるのかもしれないけど、それがまた掻き立てられて。
Sato:そうですね。むしろそこをピュアにやらないと意味がなくて。だから嫌な自分にもここに来ていっぱい会うんですよ。いろんな壁を作ってしまうというか、誰かのバックで弾くときはうまくそつなくこなして、みたいな。それが良いいい/悪いという話ではなくて、それが自分が本当にしたいことかどうかっていうところで、どんどん裸になっていったというか。まぁ、今は打ち上げで裸になって、みんなに迷惑かけてるんですけど。
-脱ぎ癖があるんですね(笑)。
ASH:ほぼ着てないよね? 数えると着てないことのほうが多い。
WANI:今日(服を着ているの)は、たまたまです。
Sato:(笑)まぁそういった心持ちというか、気持ちの面で影響を貰えているし、自分もそうしたいし。バンドってやっぱりそういうものだと思うので。
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2022/08/ash_da_hero.php on line 443
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2022/08/ash_da_hero.php on line 443
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号