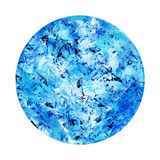Japanese
PELICAN FANCLUB
2019年07月号掲載
Member:エンドウアンリ(Vo/Gt)
Interviewer:TAISHI IWAMI
-ここまでの話で出てきたエンドウさんが好むUKのインディー・ロックは、サビに向かって上がっていかない、泣きにいかない展開やメロディの名曲が多いじゃないですか。サビで転調すると、仰々しくなってしまう怖さはないんですか?
だからサビで転調することには、もともと抵抗があったんです。特に、この曲みたいに日本語の響きが強い曲で転調するとクサくなりがち。でもそうやってサビを立たせたい気持ちもある。だからあまり大げさにしないために、サビのコードの流れをあまり感じさせないようにしてます。ベースはルートが取りづらいくらいに動かして、上で鳴ってる僕のギターだけで若干のコード感を出すことで、"ザ 転調"みたいにはならないんです。
-メロディやサウンドスケープのイメージについてはどうですか?
メロディや音の雰囲気については、そのまま真似たわけではないんですけど、THE PRIMITIVESがイメージのモデルにありました。パンク感はあるけど、すごくキャッチーでキラキラしたあの感じ。そこでメロディができたときに、"アレンジを加えたらすごく強い曲になるぞ"って、根拠のない自信が湧いてきました。
-100年前は、国内では"ネオアコ"と言われる、どこか懐かしく瑞々しいインディー・ポップの流れを汲む曲です。
これはたしかに懐かしさがテーマにあるんですけど、最初に思い浮かんだのはネオアコではなく、古い日本のフォークや歌謡曲。それこそ父が聴いていた海援隊とかです。とはいえ、単に今から見た昔の話ではなく、100年後から見た今。食べ物が良くなって、医学も発達して平均寿命も延びている昨今。となれば、本当に100年後に僕自身がこの曲を振り返って聴くこともあるかもしれない。そういうタイムカプセル的なイメージで作っていきました。だからこの曲も、具体的な設定はあって、それは僕の思い出話ではあるんですけど、それに対してどうこうではなく、人間の存在について考えたときのアプローチのひとつなんです。
-「7071」は、音楽性もプロダクション的にも、最も現代的な曲だと思いました。
そうですね。新しく買ったOP-Zというシンセで作った低音をかすかに入れたり、Alesisのシンセを使ってハイハットの音を作ったり、今までしてこなかったことが結構入ってます。
-今作はベースのカミヤマ(リョウタツ)さんとドラムのシミズ(ヒロフミ)さん、リズム隊の音色においても、曲ごとへのこだわりが強く感じられます。そのことについても、この曲を軸に話を聞いてみたいと思いました。
今回は音源とライヴは別だと考えて、ベースにも結構手を加えたんです。ベースはしっかり鳴ってるんですけど、それよりも下の帯域、ギター・リフの3オクターブ下に同じフレーズを刻むシンセを入れました。近い位置にいるベースとシンセのフレーズがぶつかって、変なことになるかもしれないという懸念もあったんですけど、結果シンセがあるとないとではまったく違ううねりが出ましたし、ドラムの迫力も際立ちましたね。
-ローの刺激やドラムのダイナミズムが凄まじかったです。
それと同時に、無機質な雰囲気も出したくてシンセのハットを入れたんです。ギターとベースとドラム、3人の肉体的なバンドらしさはありつつも、ニュー・ウェーヴ感のある、新しいタイプの曲になったと思います。
-ICEAGE以降や、今のUKにある、パンク/ポスト・パンクの流れを汲んでいるようにも思いました。それについてはどうでしょう。
ICEAGEはすごく好きなんですけど、そのへんのサウンドは意識してなかったです。冷たい狂気みたいなものを表現したくて、サウンドは極めてゴリゴリにして、歌い出しはかなり優しくささやくように歌ったんですけど、それは日本語の響きが美しく立つようにするためのアプローチでした。だから、何かを参考にしたわけではないんです。でも、制作時期にすごく好きでよく聴いていたLIVING HOURの『Softer Faces』とRobin Guthrieの『Carousel』は、多少関係しているかもしれないですね。この2作を聴いていると、気持ちがフワフワしてくると同時に、その心持ちを壊したい衝動にも駆られる。メンタルが揺さぶられるんです。そこで、安心の外にあるものを表現に変えていきたくなりました。
-"安心の外"とは?
使い慣れたギターとかではなく、使い慣れてない新しい機材を採り入れたり、これまでになかった音作りを試してみたり、そういう冒険心が最も熱く表れているのは、この「7071」だと思います。
-なるほど。それで今回は全体的にサウンドの豊かさやグルーヴの強度が増したわけですね。
前作はギターとベースとドラム、プレイヤーとしての3人の個性がしっかり際立つ作品にしたかったんですけど、今作は特に目立つソロ・パートもないですし、まさにグルーヴを徹底的に意識しました。そうなると、例えば、僕がもともと頭の中で描いていたギター単体の音だと、実際の演奏ではうまく機能しないことも起こってくるんです。だからといって、そこを目的のために寄せて変えることも極力しなかった。どの角度においても妥協せずに折り合いをつけていったので、表現として純度がとても高くて、かなりパワーアップしたサウンドになったと自負しています。
-PELICAN FANCLUBの可能性をこじ開けた4曲だと思いました。
こだわることが楽しいんです。ちょっとした音の変化で曲の表情はずいぶん変わる。そういうことをとことん追求しました。「Girlfriend In A Coma」は、ただシンセを入れただけだとのっぺりしちゃうんですけど、レゾナンスのかけ具合にこだわることで、バンドの音と相まって跳ねているように聴こえるところが一瞬あって、そこを見つけるためにちょっとずつ音を触っていきましたし。ギターとベースとドラムの3人であることにはとらわれず、でも明らかに人数が増えたようなサウンドでもない。そのバランスのなかで、どんどん高めていける可能性を感じました。
-では、ライヴはどうなっていくのでしょう。
ライヴを重ねていくうちに、来てくださる方々それぞれに想い入れのある曲があることを実感するようになりました。だから、ざっくり言えば音源以上のことをしたいんです。メンバーが4人いた頃の曲もそう。だから"グルーヴ"なんです。ロック・バンドの持つグルーヴをとことん追求して、誰かにとっての大切な1曲をライヴで更新したいと思います。
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2019/06/pelican_fanclub_2.php on line 402
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2019/06/pelican_fanclub_2.php on line 402
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号