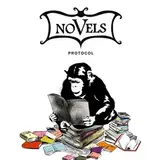Japanese
NOVELS
2015年06月号掲載
Member:竹内 真央 (Vo/Gt) 楠本 正明 (Gt)
Interviewer:奥村 小雪
-この曲だけでなく、アルバム全体を通して今までのNOVELSにはないサウンドが増えて、振れ幅がグッと広がったなと感じました。曲の自由度が増した理由として、やはりふたり体制になったことが大きいのでしょうか?
楠本:ふたり体制になってからは"今までやれなかったことをどんどんやって行こう"という考えがメンバーふたりにあって。具体的には、今まで頭の中では鳴っていたけれど再現しきれなかったサウンドや、効果音などを音源に取り入れることによって表現したい音がより理想に近づき、結果サウンドの幅が広がりました。
-Track.2「東京メランコリック」は、スケール感のあるサウンドが印象的でした。"東京"を題材にした楽曲は数多くありますが、竹内さんにとっての東京のイメージは"メランコリック"なのでしょうか? また、そう感じさせるような実体験があったのですか?
竹内:すべてがメランコリックというわけではなく、メランコリックな部分もあるということなんですけど、この曲のことで言えば、歌詞の冒頭部分"駅のホームで酔いつぶれた人が線路上に倒れたそれをヘッドフォンした若い女が見てその小さな口をへの字に曲げた"が最初にできて、そこから世界観を広げたんですが、まさにその冒頭部分は東京某所の駅で僕が見た実体験です。これが自分的には結構衝撃的な出来事で、でも案外周りの方は普通に対応されていて、その感覚のギャップというか、わけわかんなくなっちゃって。でも歌詞中にもある通り、その女性を単純に非難したいわけじゃないし、よくよく考えてみればその権利も自分にはないような気がして、そのとき生まれた"憤り"というのは言いすぎかもしれないようなもやもやした思いをそのまま楽曲で昇華させました。
-Track.3「坂道をこえていけば」はとてもハッピーで、ライヴで手拍子したくなる曲ですね。
楠本:この曲は去年のクリスマスに行ったアコースティック・ワンマンで初披露した曲です。そのときも自然と手拍子をいただいて、とても嬉しかったです!
-Track.6「彼と彼女の幸福」には、"いつか僕は君を追い越すけど 悲しいことなんてさ ひとつもないんだ"、"足の下をうろつくなって怒るくせに 突然抱き上げるその癖は直らなかったね"というフレーズが出てきますが、この曲に出てくる"僕"はペットということなのでしょうか?
竹内:正解です、拍手! そうですテーマはペットです。この曲は前に僕のボイトレの先生が、"飼っているペットが亡くなったら自分はどうなってしまうんだろう、生きていけないかもしれない"という話をされていて、僕もそうだなぁという思いから創作しました。ペットというのはほぼおそらく自分より先に亡くなってしまうものなのだと思うのですが、もし、もしもこの歌詞みたいなことを彼らが思っていたとしたら、その日が来たときに僕らは少しでも救われるんじゃないかなという思いから書いた内容です。
-今作のダーク・サイドともいえる「サーカス団に涙はいらない」、「死神ダンス」の2曲を最後にもってきたのには、何か意図があったのでしょうか?
楠本:実は曲順に関してはメンバーが意見を言ったのはTrack.1「バタフライエフェクト」だけです(笑)。それ以外の曲順は僕らが絶対的な信頼を置いているディレクターの方に決めてもらいました。決めてもらった曲順を何度か通して聴いてメンバーで最終決定を出しています。メンバーだけで決めようとすると迷いすぎていつまでもリリースができなくなってしまいますからね(笑)。なので意図はディレクターのみが知っています(笑)。
-7月から東名阪と韓国 ソウルでリリース・ツアーが開催されますね。昨年7月にも、初の海外公演として韓国ソウルでライヴを行われていましたが、日本でのライヴと異なる部分はありましたか?
楠本:やはり韓国に行ってすぐに言葉の壁を感じました。コンビニで物を買うのも電車に乗るのも大変で、ライヴも僕らの気持ちが伝わるか不安でした。しかしNOVELSのことを待っていてくれていた韓国ファンの方々。わざわざ日本から駆けつけてくれたファンの方々。NOVELSの音が鳴ったら言葉など関係なく盛り上がるんだという実感が持てたのが忘れられません!
-最後に読者へのメッセージをお願いします。
竹内:ぜひ『KICK BOOK』を手にとって聴いてみてください、今の僕たちの思いがすべて詰まっていると同時に内容もストーリー展開が多いのでわかりやすく、まさに"聴く本"としてあなたのそばに寄り添ってくれるような作品になっていると思います! そしてその聴く本を持ってツアーに遊びに来てください! 僕たちはあなたたちを心の底から待っています。
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2015/06/novels_2.php on line 385
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2015/06/novels_2.php on line 385
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号