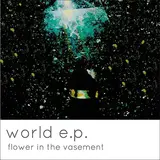Japanese
flower in the vasement
2016年05月号掲載
Member:渡邉 望(Vo/Syn/Manipulator) 齋藤 準基(Ba/Syn) 新垣 拓朗(Gt/Syn) 吉川 卓(Dr)
Interviewer:吉羽 さおり
-最初はどういうふうに始まったバンドなんですか?
齋藤:高校時代からバンドはやっていたんですけど、本気でバンドをやろうと思って、同じく高校時代からバンドをやっていた彼(新垣)を誘って、新しいバンドを立ち上げたのが最初だったんです。当時はヴォーカルが女の子で、メンバー編成も今と全然違って。バンド歴としては長いんですけど、メンバー・チェンジを経て、今の体制になってからは3年くらいですね。
-ドラムの吉川さん以外はシンセのクレジットが入っていますよね。それは、サウンド上で必要だから始めたのか、それとももともとみなさんが弾けたから入れたんですか?
新垣:どちらかというと前者ですね。ステージの見栄え的なところもありますし。新しいことに挑戦していくスタンスは必要かなと思っていて。だから、ドラムにもパットが付いているんですよね。
齋藤:電子音や打ち込み音に対するこだわりがすごく強くて、1音1音練り込んで作っているんですけど。あまり同期が全面に出てしまうと、バンドでやっている感じがなくなってしまうので、自分たちも演奏する割合を増やしていってます。だからバンドでやってる意味を出すために、鍵盤を置いたということもあるんです。今回の「deep deep april」で僕はほとんどシンセを弾いてるんですけど、やっぱり選択肢が多い方がいろんなアレンジができますしね。演奏や楽曲の幅が広がるというのが大きいですね。
新垣:同期を使用しているバンドってどうしても、同期とバンド・サウンドとが分離しがちじゃないですか。そういうバンドをたくさん観てきて、嫌だったんですよね。自分たちが電子音にちゃんとコミットしてる部分を出していきたくて、"これがまとめてうちらの音だ"という感じで聴いてほしかったんです。でもそれは、同期ではなく自分たちがキーボードで音を出すことで解消できるかもしれないと思うんですよね。
渡邉:ここまで同期が組み込まれているバンドってあまりいないんですよね。部分的に入れているのはよくあると思うんでけど、がっつり入れている人たちはあまりいないので。なんでみんながっつり入れないんだろうなっていうのはある。
-齋藤さんが最初にスタートさせた段階では、いわゆる3ピースや4ピースのバンド形態だったんですね? そこで何か変化が欲しかったというところですか。
齋藤:そうですね、他のバンドとは違う、自分たちにしか出せない音や、自分たちにしかできない楽曲、ステージングをずっと探し求めていて。その結果、楽曲やステージの配置、楽器もどんどん形を変えていって。今も機材が増えたり減ったりしているんですけど、常に、自分たちらしさを模索して実験しているという感じですね。
-そもそも渡邉さん、吉川さんとはどうやって出会っていったんですか。
渡邉:もともと彼(齋藤)とは中学の同級生で。新垣とは高校から友達だったんですけど。で、大学のときにバンドに誘われたのかな?
新垣:そうだね。そのとき卓は別のバンドでドラムを叩いていて、もともと仲良かったんで、いろいろ話して、"ぜひうちでやってくれ"と。
吉川:前のバンドをやっていたときから、flower in the vasementにいつか入りたいなと、ずっと思っていたんですよ。それでたまたまそういう機会があって、うまいこと入れたという感じだったんです。
渡邉:そのとき卓が組んでたバンドの解散ライヴに遊びに行って、"うち今ドラムいないから叩いてよ"って。
吉川:いいよ、って二つ返事で。
渡邉:"じゃあ、連絡するよ"って(笑)。スタートはそんな感じでしたね。
新垣:最初にスタジオで合わせたときに、すでにflower in the vasementの曲を完コピしていたんですよ。すごい熱意というか、愛を感じたので、ぜひっていうね(笑)。
-吉川さんはもともとflower in the vasementを外から見ていて、どういうバンドだと思っていたんでしょう。
吉川:楽曲のクオリティが周りにいた他のバンドよりも一枚上手というか、全然違ったんですよね。僕は当時、ヘヴィ・ロックやミクスチャー系のバンドでずっとやっていたんですけど、このバンドを観てから、エレクトロっぽいサウンドに惹かれるようになってきて。ファンみたいな感じだったんです。だから、いつかこのバンドに入れたら最高だなと思っていたら、2~3年後くらいにその夢が叶って(笑)。
渡邉:今は、卓(吉川)が言っていたような当時の音楽性とは少し違うんですけど。エレクトロを使いつつ、僕ら自身はエレクトロ・バンドではないと思っているんです。ライヴを初めて観た人に、"エレクトロは苦手だったけど、このバンドは好き"みたいなことを最近よく言ってもらえるようになって。つまりそれが"新しい音楽"としてできているということなんだろうなっていうのは感じていますね。
-その"新しい音楽"を作り出すのに最適なドラマーとして、音楽的なバックボーンが違ったり、いろんな引き出しを持っているような人がよかったと。
新垣:引き出しは多いからね。
齋藤:彼はクリックを聴きながら叩いてくれているんですけど、同期を聴きながら生感やバンドらしさを出してくれるので、ありがたいし、適任だなと初めてスタジオ入ったときに思ったんですよね。当時、キーボードとドラムがほぼ同時期に抜けて、3人になって。バンドとしてはどうしようかと迷うような時期だったんです。それでも誰も"解散しよう"とは言いださずに、新しいドラマーを探すしかないとなって。探し始めて半年も経たないうちに、彼が入ってくれたんですよね。すごくラッキーだったんですよ。
-ドラマーが抜けてしまったときに、それを機に同期でやっていくことに振り切っていくのではなくて、あくまでドラマーを探して生の音でという、バンドとしての在り方を貫いてますね。
渡邉:そうですね、たしかに。たぶんバンドの音楽が好きなんですよね。だから自分たちでやりたいのは、こういうバンド形態で奏でる音楽なんです。
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2016/05/flower_in_the_vasement_2.php on line 415
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2016/05/flower_in_the_vasement_2.php on line 415
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号