Japanese
BIN
2021年04月号掲載
Writer 石角 友香
未発表曲のアルバム収録で、絶望や拒否感の一歩先を示唆。既発曲とトータルで聴くことで見えてくる世界
アーティストのヴィジュアルや発言など属人性を前面に出さず(むしろ秘匿している)、音楽性や世界観を前景化するためにアニメーションによるミュージック・ビデオで自らの存在を世の中との最初の接点とするポップ・ミュージックのクリエーターが支持を集める今。ヴォーカリストとイラストレーター、そして演奏とトラックを手掛ける3人から成り立つ音楽ユニットである彼らBINも、まさに2020年代の日本のポップ・シーンの先頭を走りうる存在だ。しかも彼らの場合、アーティスト写真もイラストレーターであるトマトによる、少し病んだ印象のある猟奇的なまでに美しい少年の絵がそれにあたる。この絵や、絵のスチール画像にリリックが乗ったミュージック・ビデオでファースト・コンタクトを果たしたリスナーも多いだろう。初投稿曲の「チルドレン」を含め、これまでにYouTubeにアップロードされた全8曲の総再生回数は2,000万回を超えるという。大きなタイアップやプロモーションではなく、主にSNSの口コミで獲得したこの数字はBINのトータルアートに対する純粋なリアクションだ。
これまでデジタル・リリースしてきた9曲は、曲調は様々でありつつ、少年と青年の狭間にある存在の大人に対する猜疑心や、それゆえに外界をシャットダウンして内面に籠る様子や、あてもなく放蕩する様子だ。圧倒的なネガティヴィティを放ちながらも、未熟さゆえの弱さだと決めつけられないのは、そのネガティヴィティの中に純粋なものや、自己耽溺ギリギリであろうとも、真実を垣間見るからではないだろうか。もちろん、アートワークという名のキャラクターが徹底的に耽美的であることもBINの世界観を補完どころか、リアルなものにしている。漫画やイラストにしか表現できない暴力的で美しい存在。生身の人間が渇望してやまないそれはBINの楽曲の主人公として、音楽を牽引すらしているのだ。主人公のヴィジュアルは存在しているが、その主人公に自身を重ね合わせる余白があるという意味では、小説世界に耽溺する体験に近いかも知れない。
新しい表現手法とこの世界での存在の仕方を示してきた彼らが、1stアルバム『COLONY』をリリースした。前述の「チルドレン」や「籠の鳥」、「悪食」など初期の投稿曲をはじめ、昨年11月リリースのTOWER RECORDS限定CD(『灰』)に収録された「灰燼」に加え、未発表曲を含む全10曲。初回生産限定盤にはトマトが描いたイラスト画集が付帯し、そちらの人気が高いのもBINというユニットを物語っている。
では実際に聴いていこう。1曲目は彼らを世に知らしめた「チルドレン」。Tによる生音ヒップホップ調のビートに乗るフュージョン~歪なエフェクトがかけられたヒステリックなギターが、山上が歌う大人への嫌悪感を端的に押し上げる。だが、食えない青い果実である自分は、いずれ腐ることを知っている。そこに少しの不安も覗くあたりがリアルだ。他者からの好意も悪意も興味もシャットアウトしてしまう「籠の鳥」。不気味な生き物の声のようなベース・ラインや鍵盤のリフが作り出す3拍子もまるで終わりのない円環のようで、淡々とした楽曲でありつつ無限ループ的な怖さを演出している。グルーヴィな横ノリに思わず心地よく身を任せそうになるが、歌われている内容や、そのグルーヴの熱のなさに血の気が引くのが「悪食」。身体や健康に悪そうなモノを食べることを指す悪食という言葉をタイトルに持つこの曲も、主には若い主人公の希望や夢や愛や才能を"大人たちが貪る"と糾弾するのだが、餓鬼にも権力にも世界にも食い潰されると歌う。徹頭徹尾、被害者や犠牲者の目線のように感じられるが、若い才能は消費もされるし、消費を促すこともできる。単に大人に悪態をつく以上の恐怖と抵抗のニュアンスが、曲が進むにつれて濃くなっていく。この曲の冒頭のジョーカーのような笑い声と女の子の笑い声は自分が世界に向けて放つものと、自分に向けられる冷笑のようにも取れるし、はかなくも真実である誰かの笑顔かも知れない。BINの描く世界には他者にとっての真実も潜ませているように思えるのだ。
ジャジーでミニマルな音使いの「インスタント」では命さえ飯の種的に消費することへの嫌悪がうたわれるのだが、山上の歌声が怒りの感情を含んだ高音になる部分に、普段は声を上げられない存在だからこその切実さを思う。テクニカルに歌うより、主人公がどこにでもいる少年~青年であることがより伝わってくる歌唱だ。徹底して大人を糾弾してきた4曲に続き、「NEON」は比較的、街の情景も浮かぶし、メロディは切ないながらも軽快。日常的な聴感を持ちながら、逃避を夢見る心情が描かれる。都会のネオンが奪った星の輝きを思わせる単音ギターの音色。色褪せていく未来を迎えずに逃げてしまいたい――それが壮大でファンタジックなサウンドではなく、MVでのイントロとアウトロの雑踏のSEとも自然と接続するアレンジに帰着していることが臨場感を生んでいる。まさに今この時も"彼ら"は街にいる。
タイトなビートと腰のあるベース・ライン、琴のようなシンセ・サウンドがフックになっている「シニカル」。大方のことが金で解決できる世界において、勘違いした神のごとく独善的な存在が語る善は善なのか? という意味合いにも聞こえるし、影響力を持つ人間に少なくとも主人公は救われていない印象を持つ。ここまでの楽曲も一方的に他者を責めているわけではないが、次第に歌詞の世界に哲学的な色合いが浮かび上がってくる。そして山上のジェンダーレスな声の魅力がまず耳に飛び込んでくる「因果」。この曲のテーマはタイトル通りだろう。因果応報、人に投げた石は自分に戻ってくる。その事実を"群青"、"楽園"、"煽情"といった他の楽曲にも通じるワードで組み上げていく。マイナー・キーの洗練された16ビートのループは聴き心地がいいが、これもまた円環、因果が巡る感覚を増幅する。
人間関係、そして愛情とは何かをも聴き手に考えさせるのが「灰燼」。ビートこそ明快だが、ダウナーなサウンドが取り囲む音像の中、自己犠牲の果てに自分も相手も壊してしまう感情。コントロール不可能なそれを、高低差を行き来するヴォーカルが映し出す。
今回、初収録となる「遭難信号」は生々しいバンド・サウンド。いわゆる敷かれたレールに乗れなかった、主人公なりの生きる力が窺える。社会で遭難しても"僕は僕だよオーバー"と、誰かと交信している。前半の厭世的で生きながら死んでいるような態度で挑発する主人公の素直さや、実は持っている生命力をうっすら感じる流れだ。そして手探りで生きる彼がただ世界のありようをフラットに捉えたうえで、それでもこの日々を繰り返していくと歌う出口のあるロック・ナンバーがアルバムのタイトル・チューンでもある「colony」だ。単曲で発表していた段階でどこまで意識されていたのかはわからないが、この曲の歌詞で、なぜヴィジュアライズされた彼らはよく血を流していたのか、ピースがハマるような感覚に陥った。もちろん傷ついているし、比喩として血の涙を流すほど悔しかったり絶望したりすることもあるだろう。だが、血を流しながら彼らは生きている。それがアルバムとして纏められたとき、意味を持ってくるように感じた。
現実世界には存在しないが、どこまでも自分に重ね合わせたくなる二次元の彼らが、生身のアーティストが表現しえない部分まで強い言葉やユニークな音像を触発し、形にできる。この可能性はすでに出会ったリスナーが体験済みではあるが、アルバムで、さらに一歩先の感情の置き所を示して見せた今、BINの存在にあらゆる人が気づいてほしい。
▼リリース情報
BIN
1stアルバム
『COLONY』
NOW ON SALE
[PONY CANYON]
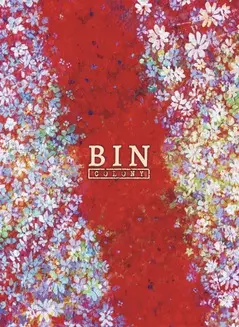
【初回生産限定盤】
PCCA-06003/¥3,520(税込)
※トマトが描くイラスト画集仕様
amazon
TOWER RECORDS
HMV

【通常盤】
PCCA-06025/¥2,530(税込)
amazon
TOWER RECORDS
HMV
1. チルドレン
2. 籠の鳥
3. 悪食
4. インスタント
5. 灰塵
6. シニカル
7. 因果
8. NEON
9. 遭難信号
10. colony
配信はこちら
- 1
Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/feature/2021/03/bin.php on line 431
Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/feature/2021/03/bin.php on line 431
FREE MAGAZINE

-
Cover Artists
ASP
Skream! 2024年09月号
































